3-2. 事業の変遷3
1965年(昭和40年)、青年海外協力隊が「日本青年海外協力隊」の呼称をもって、技術・技能を活かした青年の海外ボランティア活動として創設され、活動を開始した。当時我が国は、既に第2次世界大戦の戦禍から復興・再建を果たし、国際社会にも復帰して、輸出の増進、戦後賠償とも連関しつつ、アジア地域の新興諸国への経済協力・援助に乗り出していた。
発足に至るまで、協力隊事業創設にあたって、その実施母体をどうするかについて激しい議論があったが、発足前年の1964年(昭和39年)12月に自民党臨時特別委員会が「海外技術協力事業団(OCTA)」に業務委託するという大局的判断を下し、同事業団は1965年(昭和40年)1月20日に「日本青年海外協力隊準備事務局」を設置、事業開始に向け準備を進めた。同年4月20日、「日本青年海外協力隊事務局」が設置され、協力隊事業は7,287万円の予算をもってスタートした。初年度の昭和40年度派遣定員は50名であったが、それに対して応募者数は十数倍に上った。
既に非公式の派遣要請国もあったが、最初の派遣となる40年度1次隊は、フィリピン、マレイシア、カンボディア、ラオスの4ヶ国に決定された。同年2次隊にはこれらの国に加えて、アフリカ最初の派遣国となるケニアから新たな要請があり、派遣することとなった。
東南アジアが最初の派遣地域になったことは、日本との歴史的、経済的な結び付きや協力隊創設に先立つ調査団派遣がアジア地域中心であったなどの経緯から当然であると受け止められるが、創設当初からすでに、アフリカへの派遣が予定され、1966年(昭和41年)3月にはケニア、翌1967年(昭和42年)にタンザニアの東アフリカ2ヶ国に、また、同年には中近東圏である北アフリカのモロッコにも派遣が実現した。フランス語圏への派遣の始まりでもある。
中米地域への初派遣となったのは、エル・サルバドルに隊員派遣が始まった1968年(昭和43年)である。親日・知日家であった同国高官の協力隊への関心が契機であったが、創設後の早い時期に米州スペイン語圏への派遣が緒につき、同国周辺の中米諸国への派遣へと広がっていく基盤をつくった。
1971~72年(昭和46~47年)には、サモア、トンガ両国への派遣が決まり、それぞれ1972年、1973年に隊員が赴任して、オセアニアでの協力隊活動が始まった。
このような派遣地域の広がりの結果、協力隊が発足して10年目の1975年(昭和50年)には、中米、アフリカ、中近東への派遣がそれぞれ3ヶ国以上になり、同年末の累計派遣国は20ヶ国、年間派遣数200名以上、常時活動中400名以上の規模に拡大した。
1977年(昭和52年)にボリヴィア、翌1978年(昭和53年)にはパラグアイの南米2ヶ国に派遣が始まった。当時、移住事業のイメージがなおも濃かった南米地域に協力隊派遣が実現し、1979年(昭和54年)にはペルーにも派遣が始まり、これら3ヶ国の協力活動とその成果が、その後の南米各国への派遣の広がりに大きく影響を与えていく。
1980年代は、派遣規模の計画的拡大、3年倍増期に入り、年間1ヶ国増のペースで派遣国が広がって、その中には、ODA主要対象国であるスリ・ランカ、タイも含まれている。発足20周年の1985年(昭和60年)末には、累計派遣国35ヶ国となり、年間の派遣隊員数は、1983年に500名、1985年には800名の3年倍増目標に達した。
昭和60年代(1985年~)は、派遣国拡大のペースが加速する。大国である中国への派遣が1986年(昭和61年)に始まったのを皮切りに、アジアのもうひとつの大国であるインドネシアにも、1988年(昭和63年)に初派遣が実現した。またカリブ地域で初のドミニカ共和国、ジャマイカ両国、あるいは南部アフリカのジンバブエにも派遣が始まり、他の地域も、いずれも2ヶ国以上の派遣国増加があって、1990年(平成2年)末には、派遣国数48ヶ国に到達した。年間派遣数も800名規模が続いた。
平成に入って、新たな派遣開始のペースがさらに早まった。日本のODAは米国や西欧諸国をしのぎ、世界一の援助国・トップドナーとなり、東西冷戦の終結が大きな要因となって、ハンガリー、ポーランドなど東欧地域への派遣が始まった。これは、単に、派遣国の拡大にとどまらず、東欧地域をはじめとする旧ソ連圏・旧社会主義圏への協力開始であり、文化・スポーツ交流の側面もあって、協力隊にとって新しい「挑戦」の機会を開いたことにもなる。
中央アジア地域への派遣開始はユーラシア外交が叫ばれる中、最近の最も特徴的なことといえる。ウズベキスタン、キルギス両国に、それぞれ2000年2月、11月に初めて赴任することになった。これにより、派遣取極締結国77カ国中65カ国に対して2002年1月末現在2,446名(うち女性54%)の派遣が実施されている。隊員の平均年齢は27歳。
地域別では、アジア、中南米、アフリカはそれぞれ約25%となっており、アジアの中では中国、インドネシア、フィリピン、中南米の中ではホンジュラス、グアテマラ、ニカラグア、アフリカでは、タンザニア、ケニア、マラウィが隊員数の多い国である。
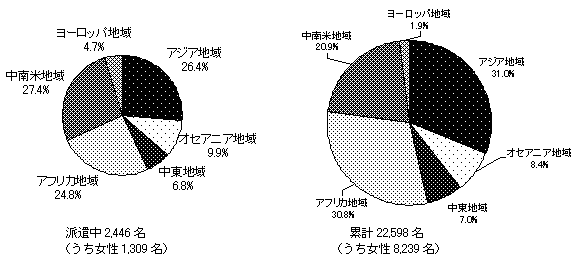
図3-1 平成13年度 協力隊派遣状況 地域別割合(2000年6月現在)
発足当初から、協力隊は、技術・技能を持った青年の海外ボランティア活動であることを掲げ、派遣要請はそれを期待し、要請の背景と内容に求められる技術・技能のレベルや幅や資格要件などが示されるのが通例である。要請を取りまとめる協力隊事務局は、隊員の活動分野を農林水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛生、教育文化、体育スポーツの7分野に分けて整理し、地方自治体や民間諸団体と連携して募集活動を展開し、選考をすすめ、派遣前訓練を実施してきた。
分野別の区分自体はこれまで変わりないが、派遣要請の多寡、応募者の傾向、適格者の選考などには時代の変遷があり、発足当初から現在まで、分野別の隊員の増減にもかなりの変化がある。
例えば、発足初期は派遣要請のかなりの部分が、途上諸国の産業構成を反映して農業をはじめ第1次産業が占め、それに応えるべく、農林水産部門の隊員派遣が多数を占めたけれども、日本の経済構造の変化から、この部門の応募者はそもそも少ない上に、求められる技術・技能に適合する適格者がなかなか見出せない現状が今日まで続いている。
2000年6月末現在の分野別派遣実績は表3-1のとおりである。
| 表3-1 分野別派遣実績(2000年6月現在) | |||||||||||||||||||||||||||
|
要請数を基本に、適格応募者数の推移などをかみ合わせて、職種の派遣傾向を概観すれば、
| 1) | 教育文化分野の「理数科教師」「日本語教師」、農林水産分野の「野菜」、保健衛生分野の「看護婦」の職種での派遣が伝統的に多い。 |
| 2) | 近年は、「村落開発普及員」、「システムエンジニア」等の派遣が増加傾向にある。 |
| 3) | 全職種の要請に対する平均充足率は約70%であるが、職種によってバラつきが大きく、一般に教育文化、保健衛生分野が高く、保守操作や加工の分野の充足率は低い。 |
また、相手国の派遣要請内容に応じて、多数の職種が新たに募集・選考に加えられ、また細かく分化されてきた。これは、相手国のニーズと応募者の専門性を合致させることで派遣効果を高めることが目的であった。例えば、1970年代初期のエティオピア派遣「公衆衛生=天然痘監視員」隊員は、文科系応募者の活動の場として活かされた先例でもある。同様に、1980年代に初派遣され文科系の応募者が多い「青少年活動」は、レクリエーション活動の振興・向上や青少年の育成、特殊教育など広範囲なニーズに対応し、近年盛んになりつつある環境保護活動を中心とする要請に応え、「環境教育」が枝分かれして新設された。やはり初期の派遣職種にはなく、近年派遣増加傾向にある前述の「村落開発普及員」は、農村部の地域開発を進める上でニーズが高く、「システムエンジニア」もコンピュータの導入に伴って、各地域で要請が増えてきたものである。
スポーツ分野では、「野球」は既に久しいが、最近は「テニス」「シンクロナイズド・スイミング」「相撲」など、途上諸国の社会変化もあって、新職種が生まれている。
派遣職種は、一時は7分野で300職種を抱えるようになったが、常時派遣されている職種は約160職種であり、職種の中には、時代の変化・進展に合わなくなっているもの、産業構造の変化に対応していない職種も見られたため、職種内容をできるだけ明確にして適格者の確保を確実にすることはもとより、応募者にとって分かりやすい職種名を明示するなど、それまでの職種を整理・統合して簡素化することが必要となった。一方、在外事務所からも、職種の整理統合について積極的に検討してほしいとの要望があり、大幅な見直しを行い、現行の職種分類表が作成された。これにより、整理統合前の7部門(分野)284職種から、7分野198職種にしぼられるに至った。
3 青年海外協力隊20世紀の軌跡 第1部より要約

