第2章 評価の体系
(1)青年海外協力隊事業の目的
青年海外協力隊は、国が国際協力事業団(JICA)の前身である「海外技術協力事業団(OTCA)」に委託して行う政府事業として1965年にスタートした。主管である外務省は関係省庁と協議を重ね「日本青年海外協力隊要綱(以降、協力隊要綱)」を決定し、国際協力事業団の設立(1974年)までの間、協力隊事業はこの協力隊要綱に基づき運営が行われた。以下は本協力隊要綱に記載されている協力隊の「目的及び性格」を示す部分であるが、ここには「相手国の社会・経済発展への協力」と同列で、「国際親善」および「青年育成」が併記されている。
| 【日本青年海外協力隊要綱 昭和40年5月12日経協技第40号】
開発途上にある諸国の要請にもとづき、技術を身につけた心身ともに健全な青年を派遣し、相手国の社会的、経済的開発発展に協力し、これら諸国との親善と相互理解を深めるとともに、日本青年の広い国際的視野の涵養にも資さんとするものである。 協力隊事業は、相手国政府との間にもとづいて実施される新しい国家的計画である。 |
しかしながら、国際協力事業団の設立(1974年)に伴い国際協力事業団法が制定され、上記の協力隊要綱の「目的及び性格」に相当する部分は以下のようにまとめられることになった。
| 【国際協力事業団法 第1章「総則」第1条「目的」より】
国際協力事業団は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び青年の海外協力活動の促進に必要な業務を行い、(中略)~もってこれらの地域の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とする。 |
| 【国際協力事業団法 第4章「業務」第21条「業務の範囲」の第1項第2号より】
開発途上地域住民と一体となって当該地域の経済及び社会の発展に協力することを目的とする海外での青年の活動(以下、この号において「海外協力活動」という)を促進し、及び助長するため、次の業務を行うこと。
|
協力隊要綱から国際協力事業団法への変遷、およびその解釈は、2001年1月に発行された「青年海外協力隊 20世紀の軌跡」に明確に記述されている。ここには、「協力隊は、“青年の海外協力活動”を事業内容としている。“活動”の目的は、途上地域の経済・社会の発展への協力、である。かつての「要綱」にうたわれた国際親善、青年育成は、いずれも協力隊事業にとって重要な要素にほかならないが、事業の目的ではない。それらは、国際協力・開発協力を目的とする海外協力活動を進めてゆく過程で、あるいはその結果として得られる貴重な成果、と考えられている。」、と記載されている。
つまり、国際協力事業団法上では、青年海外協力隊事業の目的は、「相手国の経済・社会の発展に協力」することである。
(2)青年海外協力隊事業のプログラム(施策)目標
前項で述べたとおり、国際協力事業団法上では協力隊事業の目的は「相手国(派遣国)の社会・経済発展への寄与」のみである。しかしながら、現時点において協力隊事業の貴重な成果(結果)として挙げられている「国際交流」、「日本社会への還元」および「青年育成」についても、単なる副次的な効果というより、むしろ期待されている成果として重要な役割を果たしている。この背景には、派遣人数の大幅な増加、要請・応募職種の細分化・多様化、相手国や日本の社会構造の変化、要請側・応募側双方の協力隊に対するニーズの変化など、相手国と日本の双方の変化が関係していると考えられるが、世界の国際協力分野の潮流や日本の国際協力に対する位置付けにも大きく影響を受けている。このため、ある時期は「技術協力」中心の事業展開、またある時期は「青年育成」や「日本社会への還元」を強く打ち出した事業展開と、時代ごとに「協力隊事業の期待される成果」が変化してきた、とも言える。しかしながら、時代の流れにより変化する事業の目標や方針は、参加する協力隊員や相手国に対し明確に伝わっておらず、また彼らのニーズとも合致しないことが懸念される。
このため、今回評価調査では以下の3つを協力隊事業の実施により出される成果=プログラム(施策)目標と仮定し、「相手国の社会・経済への寄与」という側面だけでなく、「国際交流」および「日本社会への還元」などについても具体的な成果を提示しながら検証を行っていく。
今回評価調査における協力隊事業の3つのプログラム(施策)目標:
|
今回評価調査では、下図のように、協力隊事業の範囲を大きく「プログラム(施策)」と「プロジェクト(事業)」の二つに分類し評価を行っていくが、プロジェクト(事業)レベルから出された各評価結果はプログラム(施策)レベルの評価を行う上での指標もしくは成果を裏づける根拠として扱っていく。
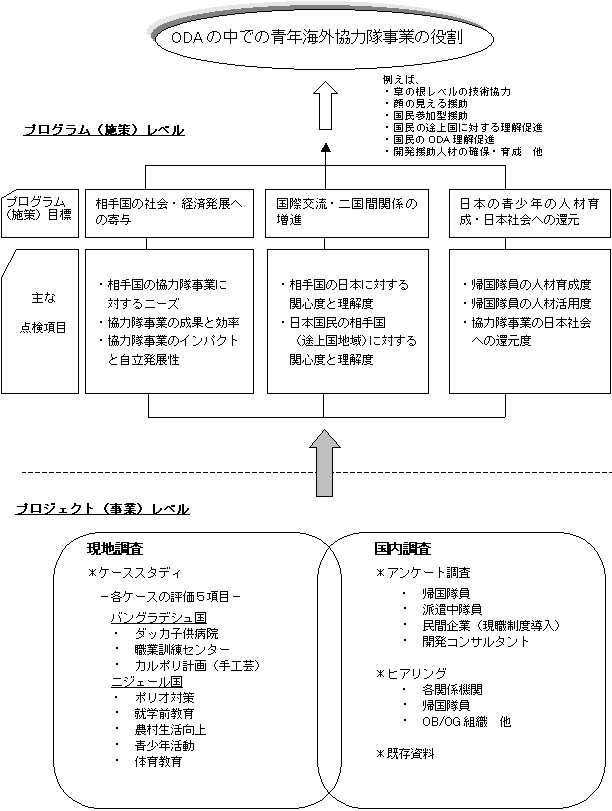
図2-1 評価の体系図
本評価調査は、プログラム(施策)レベルの評価を行うことを目的としているため、先の図2-1『評価の体系図」に従い、プログラム(施策)レベルとプロジェクト(事業)レベルに対し以下に示す点検項目と指標を設け評価調査を行うが、プロジェクト(事業)レベルで行われる国内・現地の各種調査の結果はプログラム(施策)レベルの評価分析を行う上での評価材料(指標)として用いられる。このためプログラム(施策)レベルで“指標”とされている項目は、プロジェクト(事業)レベルにおける調査結果に相当する。
プログラム(施策)レベルとプロジェクト(事業)レベルの評価手法は以下のとおり。
(1)プログラム(施策)レベル
3つのプログラム(施策)目標別に点検項目と指標を設定し評価分析を行い、その結果から提言を導き出す。また、3つのプログラム(施策)目標が、ODA事業のプログラム(施策)目標として妥当か否かについても検討し、特にODAを取り巻く環境の変化、NGOの台頭、国民へのアカウンタビリティ、日本の社会経済構造の変化、国民のODA理解の促進という観点に注目していく。
協力隊事業の実施プロセス(実施体制、支援体制や制度)については、各プログラム(施策)目標の目標達成を促進する要因および阻害する要因を整理し、提言を行っていく。
| 点検項目 | 指 標 | 調査方法 |
| プログラム(施策)目標1:相手国の社会・経済発展への寄与 | ||
| 相手国の青年海外協力隊に対するニーズと受入環境 | ・ プロジェクト(事業)レベルの妥当性で確認 | ・ 相手国の青年海外協力隊受入機関ヒアリング
・ 所管省庁、カウンターパート機関、カウンターパートヒアリング 注目するケーススタディ ・ 幼稚園 ・手工芸(カルポリ) ・ ダッカ子供病院 ・職業訓練センター |
| 青年海外協力隊事業の成果・効率の測定 | ・ プロジェクト(事業)レベルの5項目評価で確認 | ・ ケーススタディの全ケース
・ 手工芸の変遷 |
| ・ プロジェクト(事業)レベルの、プロセス評価で確認 | ・派遣中隊員へのアンケート調査 | |
| 青年海外協力隊事業のインパクトと自立発展性 | ・ ケーススタディの5項目評価
・ 協力隊員の活動状況 |
・ ケーススタディの全ケース ・ アンケート調査 |
| 点検項目 | 指 標 | 調査方法 |
| プログラム(施策)目標2:国際交流・二国間関係の増進 | ||
| 相手国の日本の理解度 | ・ 配属先、活動地域における日本の知名度
・ 協力隊枠での日本における研修参加人数 |
・ 青年海外協力隊の受入れ機関ヒアリング
・ カウンターパートヒアリング、最終裨益者に対するフォーカス・グループ・インタビュー |
| 日本国民の相手国の理解度 | ・ 隊員の家族・親戚・友人等の相手国理解の向上度合い
・ 途上国地域に対する関心度 |
・ 隊員OB/OG家族・親戚に対するヒアリング
・ 協力隊を育てる会ヒアリング |
| 点検項目 | 指 標 | 調査方法 |
| プログラム(施策)目標3:日本の青少年の育成・日本社会への還元 | ||
| 帰国隊員の人材育成度 | ・ 協力活動に起因する隊員の成長度(自己評価)
・ 協力隊経験が帰国後のキャリアパスに役立っている度合 ・ 協力活動に起因する隊員の成長度(自己評価) ・ 帰国隊員の国際協力分野に対する関心度 ・ 協力活動に起因する隊員の成長度(自己評価) ・ 民間企業における協力隊経験者の評価 |
・ 隊員OB/OGへのアンケート |
| 帰国隊員の人材活用度 | ・ 国際協力分野へ就職状況
・ 公共機関や民間企業への就職状況 ・ NGOやNPOの設立・運営に関わる状況 |
・ 隊員OB/OGへのアンケート
・ 協力隊を育てる会ヒアリング ・ OB/OG会ヒアリング |
| 協力隊事業の社会還元度 | ・ 協力隊事業の認知度と理解度
・ サーモンキャンペーン1の開催率、受講者数 ・ 現職教員の参加状況と活躍 ・ 地方の国際化への貢献度 |
・ 協力隊を育てる会ヒアリング
・ OB/OG会ヒアリング ・ 帰国隊員アンケート ・ JOCA実施の地方自治体向けアンケート |
| ・ 現職参加を送り出している、公的機関へのアンケートまたはヒアリング
・ 企業へのアンケートまたはヒアリング |
||
(2)プロジェクト(事業)レベル
1)国内調査
アンケート調査、ヒアリング調査及び既存資料から得られた情報を整理し、プログラム(施策)評価の指標として提示していく。
また、協力隊員の活動がなぜうまくいったのか、あるいはなぜうまくいかなかったのかを把握・分析するために、協力隊隊員の活動状況を中心としたプロセス評価を実施する。プロセス評価のための主な点検項目は以下のとおり。
| 調査項目 | 点 検 内 容 |
| 実施体制 | 募集、応募、選考、訓練の実施状況 |
| 要請開拓・背景調査の精度と隊員活動への影響 | |
| 協力隊事業に対する相手国(配属先)の理解度と期待度 | |
| 青年海外協力隊事業の最近年の取組み課題 | |
| 相手国の要請に対する充足度 | |
| 応募職種と要請職種の充足度 | |
| 国民へのアカウンタビリティ | |
| 隊員報告書の活用状況 |
| 調査項目 | 点 検 内 容 |
| 支援体制 | 現地事務所の支援状況 |
| 調整員の役割と業務量の適正 | |
| 配属先と隊員とのトラブルや活動阻害に対する支援状況 | |
| 技術顧問に対する任期中隊員の期待度 | |
| 活動期間中の隊員の健康管理や安全に対する対策 | |
| 隊員の活動支援現地活動において、“目標設定“に悩む隊員の増加 | |
| 留守家族に対する支援状況 | |
| 帰国隊員に対する支援状況 |
2)現地調査
バングラデシュ国から3案件、ニジェール国から5案件選定しケーススタディを行い、各案件ごとに評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性)を用いて評価分析を行う。
評価5項目に対する調査項目は以下のとおり。
| 評価項目 | 調 査 項 目 | |
主な視点: 活動目標や上位目標が相手国のニーズに合致しているか |
1.相手国のニーズとの整合性 | ・ 相手国に青年海外協力隊事業の制度、目的、特質等が正しく理解されているか。(他のボランティアや専門家との区分の有無)
・ 相手国の開発政策方針および要請数・要請職種に応じた派遣計画が策定されているか。 ・ 相手国のニーズに適した技術・知識を有する人材が募集・選考されているか。 ・ 相手国において日本の援助政策と整合した青年海外協力隊事業が展開されているか。 |
| 2.日本の援助事業としての妥当性 | ||
| 3.計画デザインの妥当性 | ||
主な視点: 活動目標が期待通りに達成され、それが活動成果の結果か |
1.プロジェクト(活動)目標の達成度 | ・ 活動目標が達成されているか。
・ 活動成果が達成されているか。 ・ 派遣された隊員の協力活動が十分にバックアップ(助長・促進)されているか |
| 2.成果の達成度 | ||
| 3.成果がプロジェクト目標の達成に貢献した度合い | ||
| 4.有効性に影響を与えた促進/阻害要因 | ||
主な視点: 投入が活動成果や活動目標の達成度に見合っているか |
1.投入の規模 | ・ 隊員派遣(含む資機材・資金)のタイミングの適正度
・ 隊員間(前任者と後任者)の引継ぎ(マニュアル、継続性等)の適正度 ・ 隊員(含む資機材・資金)の活用度 ・ カウンターパート、受益者の協力活動に対する定着度 ・ 相手国受入機関、カウンターパート、受益者の協力度 ・ NGOや他ドナーによるボランティア事業の類似ケースとの比較 |
| 2.投入の質 | ||
| 3.投入のタイミング | ||
| 4.他のスキーム、ドナーとの連携の実績や成果 | ||
主な視点: 上位目標が期待通りに達成されているか、それが活動目標が達成された結果としてもたらされたものであるか |
1.上位目標の達成度 | ・ 隊員の協力活動が地域住民や地域社会・文化に予期しない好 ・悪影響(プラス・マイナスのインパクト)を与えたか。
・ 隊員の協力活動に対する地域住民の満足度 ・ 隊員の協力活動により与えられた地域住民の意識の変化 ・ 隊員の協力活動により女性の地位や発言権の向上などのジェンダー配慮にかかる影響を与えたか ・ 隊員が地域住民(最終受益者)に直接技術・知識を普及する度合い ・ 配属先、地域住民が日本に親しみを感じているか。 ・ 帰国後においても配属先や地域住民との交流を維持しているか ・ 帰国隊員が派遣国に親しみを感じているか ・ 配属先、地域住民に日本語や日本文化が紹介されているか。 ・ 配属先、地域住民に日本人の考え方、仕事への取り組み方・姿勢が受入れられているか。 ・ 派遣国の情報(生活、文化、言語、慣習等)が日本で紹介されているか。 |
| 2.予期しなかった正・負の波及効果 | ||
| 2-1社会・文化への影響 | ||
| 2-2技術面での影響 | ||
| 2-3他機関への影響 | ||
| 1.政策的視点 | ・ 地域住民や地域社会・文化に隊員の技術・知識が受入れられているか。
・ 隊員の技術・知識を普及する人材や組織が育成されているか。 ・ 地域住民や地域社会において日本に対する理解・興味が高まったか。 ・ 地域住民により隊員の技術・知識が周辺に波及しているか。 |
|
| 2.組織的視点 | ||
| 3.技術的視点 | ||
| 4.財政的視点 | ||
また、現地調査で得られた情報のうち、上記の5項目評価の調査項目に入らない項目についても、出来る限りきめ細かく協力隊員の活動状況を把握し、分析を行う。5項目評価以外の調査項目は以下のとおり。
| 調査項目 | 点 検 内 容 |
| 受益者との関わり方 | 他スキームよりも草の根レベルへの影響が大きい協力隊事業の特性 |
| カウンターパートとの関わり方 | カウンターパートとのコミュニケーションや配属先のトラブルに悩む隊員に対する支援 |
| 他隊員との関わり方 | 他分野の隊員との連携や意見・情報交換によるプラス効果の特徴 |
| 他の日本のODAとの関係 | ODAにおける重要課題・中心課題以外の分野をフォローする援助スキームの役割 |
| 他ドナーやNGOとの関係 | 協力活動における他ドナーやNGOとの何らかの関わりや情報交換 |
| 相手国実施機関との関係性 | 受入機関責任者の青年海外協力隊事業に対する理解度と期待度の国別格差 |
1 JICAの実施する、開発教育に関連して小、中、高、大学等を中心に講師を派遣する制度。平成12年度実績で1,059回(うち帰国隊員は645回)の講師派遣を実施している。

