要 約
第1章 評価の背景・目的
青年海外協力隊事業は、技術を有する我が国の青年が、開発途上地域の住民と生活・労働をともにしつつ、当該地域の「社会経済の発展に協力」することを目的とした事業である。1965年の発足以来、36年目を迎え、協力隊派遣取極め締結国は総計77ヶ国(平成13年7月末現在)、事業発足時からの累計では22,000名を超える隊員を派遣している。
しかしながら、本事業は、必ずしも一義的に技術移転のみを目的としたものではなく、青年のボランティア精神に基づく草の根レベルでの相互理解、国際交流活動、さらには日本青年の育成としての意義をも併せ持つものである。このため事業効果として、大きく以下の3項目があげられる。
|
これまで青年海外協力隊事業は、要請国の受入機関や地方自治体より高い評価を得てきた。また国内においては、協力隊事業の「顔の見える援助」「国民参加型事業」としての重要性が浸透しつつあり、同時に本事業が青年の自発性に基づく「ボランティア事業」という点からも、国民の期待と評価が高まっている。しかしながら、ODAの一環である以上、より効果的な事業の実施が求められており、事業の成果を重視する傾向及びその評価に対する関心も高まっている。
本事業評価調査は、青年海外協力隊事業の変遷、および本事業を取り巻く国内外の環境の変化に注目しつつ、本事業の実施により出される成果を明示し、それらに対する評価を行うことを目的としている。また、今後より効果的に事業を実施するべく事業の課題を抽出するとともに、21世紀に求められる、より戦略的な青年海外協力隊事業としての提言を導き出していく。
第2章 評価の体系
2-1.評価のフレームワーク
2-1-1.評価の視点
(1)青年海外協力隊事業の目的
青年海外協力隊は、国が国際協力事業団(JICA)の前身である「海外技術協力事業団(OTCA)」に委託して行う政府事業として1965年にスタートした。主管である外務省は関係省庁と協議を重ね「日本青年海外協力隊要綱(以降、協力隊要綱)」を決定し、国際協力事業団の設立(1974年)までの間、協力隊事業はこの協力隊要綱に基づき運営が行われた。その後、国際協力事業団の設立(1974年)に伴い国際協力事業団法が制定されることになった。
協力隊要綱から国際協力事業団法への変遷、およびその解釈は、2001年1月に発行された「青年海外協力隊 20世紀の軌跡」に明確に記述されている。ここには、「協力隊は、“青年の海外協力活動”を事業内容としている。“活動”の目的は、途上地域の経済・社会の発展への協力、である。かつての「要綱」にうたわれた国際親善、青年育成は、いずれも協力隊事業にとって重要な要素にほかならないが、事業の目的ではない。それらは、国際協力・開発協力を目的とする海外協力活動を進めてゆく過程で、あるいはその結果として得られる貴重な成果、と考えられている。」、と記載されている。
つまり、国際協力事業団法上では、青年海外協力隊事業の目的は、「相手国の経済・社会の発展に協力」することである。
(2)青年海外協力隊事業のプログラム(施策)目標
前項で述べたとおり、国際協力事業団法上では協力隊事業の目的は「相手国(派遣国)の社会・経済発展への寄与」のみである。しかしながら、現時点において協力隊事業の貴重な成果(結果)として挙げられている「国際交流」、「日本社会への還元」および「青年育成」についても、単なる副次的な効果というより、むしろ期待されている成果として重要な役割を果たしている。
このため、今回評価調査では以下の3つを協力隊事業の実施により出される成果=プログラム(施策)目標と仮定し、「相手国の社会・経済への寄与」という側面だけでなく、「国際交流」および「日本社会への還元」などについても具体的な成果を提示しながら検証を行っていく。
今回評価調査における協力隊事業の3つのプログラム(施策)目標:
|
2-1-2.評価の体系図
今回評価調査では、図-1のように、協力隊事業の範囲を大きく「プログラム(施策)レベル」と「プロジェクト(事業)レベル」の二つに分類し評価を行っていくが、プロジェクト(事業)レベルから出された各評価結果はプログラム(施策)レベルの評価を行う上での指標もしくは成果を裏づける根拠として扱っていく。
(1)プログラム(施策)レベル
3つのプログラム(施策)目標別に点検項目と指標を設定し評価分析を行い、その結果から提言を導き出す。また、3つのプログラム(施策)目標が、ODA事業のプログラム(施策)目標として妥当か否かについても検討していく。
協力隊事業の実施プロセス(実施体制、支援体制や制度)については、各プログラム(施策)目標の目標達成を促進する要因および阻害する要因を整理し、提言を行っていく。
(2)プロジェクト(事業)レベル
アンケート調査、ヒアリング調査及び既存資料から得られた情報を整理し、プログラム(施策)評価の指標として提示していく。また、協力隊隊員の活動に係る実施体制や支援体制についても注目する。
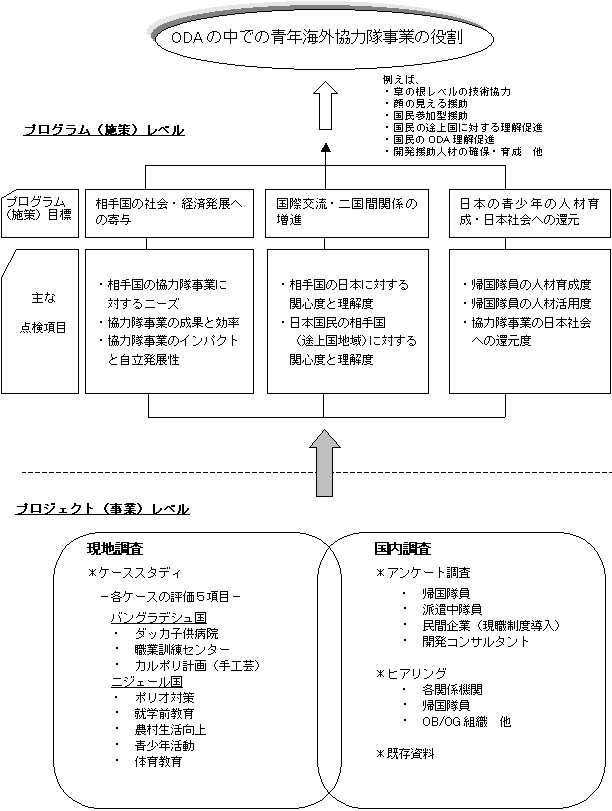
図-1 評価の体系図
第3章 青年海外協力隊事業の概要
3-1.事業の仕組み
3-1-1.派遣に関する取極
青年海外協力隊は、日本政府と相手国政府との間で締結される「青年海外協力隊の派遣に関する取極」に基づいて派遣される。この取極に基づき相手国政府から日本政府に対して協力隊員の公式要請がなされ、この要請に基づいて協力隊員の募集が行われる。募集は年2回、春と秋に行われ、一次選考と二次選考に合格すると、「隊員候補生」として79日間の派遣前訓練を受け、これを修了すると初めて正式な協力隊員となる。協力隊員たちは派遣国の省庁など関係機関やNGOに配属され、要請に従って原則2年間の協力活動を展開する。多くの協力隊員は、単独で派遣国政府機関に配属されるが、より幅広い協力効果を求められる要請については、協力隊員をチームやグループとして一括して派遣するプロジェクト形式の形態をとっている。
3-2.事業の変遷1
1965年(昭和40年)、青年海外協力隊が「日本青年海外協力隊」の呼称をもって、技術・技能を活かした青年の海外ボランティア活動として創設され、活動を開始した。当時我が国は、既に第2次世界大戦の戦禍から復興・再建を果たし、国際社会にも復帰して、輸出の増進、戦後賠償とも連関しつつ、アジア地域の新興諸国への経済協力・援助に乗り出していた。
発足に至るまで、協力隊事業創設にあたって、その実施母体をどうするかについて激しい議論があったが、発足前年の1964年(昭和39年)12月に自民党臨時特別委員会が「海外技術協力事業団(OCTA)」に業務委託するという大局的判断を下し、同事業団は1965年(昭和40年)1月20日に「日本青年海外協力隊準備事務局」を設置、事業開始に向け準備を進めた。同年4月20日、「日本青年海外協力隊事務局」が設置され、協力隊事業は7,287万円の予算をもってスタートした。初年度の昭和40年度派遣定員は50名であったが、それに対して応募者数は十数倍に上った。
東南アジアが最初の派遣地域になったことは、日本との歴史的、経済的な結び付きや協力隊創設に先立つ調査団派遣がアジア地域中心であったなどの経緯から当然であると受け止められるが、創設当初からすでに、アフリカへの派遣が予定され、1966年(昭和41年)3月にはケニア、翌1967年(昭和42年)にタンザニアの東アフリカ2ヶ国に、また、同年には中近東圏である北アフリカのモロッコにも派遣が実現した。フランス語圏への派遣の始まりでもある。
平成に入って、日本のODAは米国や西欧諸国をしのぎ、世界一の援助国・トップドナーとなり、派遣国が大幅に拡大した。2002年1月末現在、派遣取極締結国77カ国中65カ国に対して2,446名(うち女性54%)の派遣が実施されている。隊員の平均年齢は27歳である。
3-3.青年海外協力隊事務局の取組み
3-3-1.新規派遣
平成13年度当初実施計画では1,250名の派遣予定が、実績では1,050名であり、応募者が年々増えているにもかかわらず、新規派遣人数はここ数年横這い(平成10年1,093名、平成11年1,248名、平成12年1,135名)状況である。この背景には応募と要請のアンバランス、つまり国内ニーズと相手国側のニーズのマッチングが必ずしもうまくいっていないという問題点や健康診断での不合格者の増加(全体で約28%)の問題などがある。
3-3-2.隊員に対する帰国支援体制
専門家や協力隊員をバックアップする目的でJICA本部に「派遣支援部」が平成12年度新設された。その結果、福利厚生・健康管理体制の拡充や協力隊OB・OGといった若手人材の活用・育成等を一元的に支援する体制が強化されている。また、青年海外協力隊事務局内には帰国隊員の進路開拓および社会活動の支援などを目的として平成12年度から「帰国隊員支援室」が設置されている。支援室では、国際協力分野における人材育成を図るため、帰国隊員の総合的なキャリアパスの仕組み作りのための関係機関との調整・協議も実施している。
第4章 プログラム(施策)評価
青年海外協力隊事業の3つのプログラム(施策)目標「相手国の社会・経済発展への寄与」、「国際交流・二国間関係の増進」、「日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」に対する評価を行った。以下に評価分析結果の概略を述べていく。
4-1.相手国の社会・経済発展への寄与
ここでは、下記のA~Cの点検項目に基づき「相手国の社会・経済発展への寄与」に対する評価分析を行った。
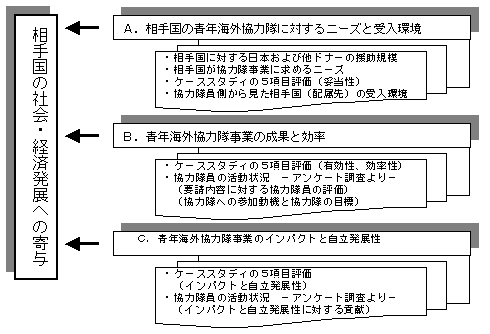
4-1-1.相手国の青年海外協力隊に対するニーズと受入環境
相手国の援助規模や受入環境の相違が、相手国の協力隊に対するニーズの質に何らかの影響を 与える一要因となっていることが明らかとなった。例えば、バングラデシュ国では、配属先によ っては高度な知識・技術を有する協力隊員の派遣を望む傾向にあり、また他ドナーの援助方針の 潮流を受け、“成果”や“評価”を意識した受入環境となってきている。
アンケート調査からは約3割の帰国隊員が配属先の協力隊員の活動に対するニーズは高くなかったとしており、その場合の隊員自身の目標達成度は低くなる傾向にある。しかしながら、相手国側からは、日本の青年が持つ技術・知識を移転してほしい、というニーズが非常に高く、加えて、現地の言葉や文化・慣習を理解し、地域社会に溶け込みながら地道に協力活動を行う隊員達の姿勢は、カウンターパート、同僚、および地域住民に非常に好印象・好影響を与えている。
また、ケーススタディに対する妥当性の検証から、協力隊事業の特徴として「最終受益者のニーズの高さ」が明確になっている。このことは、日本の援助スキームの中で協力隊事業が“最終受益者のニーズとの整合性”という点に対し重要な役割を果たしてきたものと評価できる。しかしながら、中長期的な派遣目標や上位目標が明確に策定されていないために、結果として隊員が自らの活動に対するニーズを実感できず、目標達成度が低くなるケースが今回見受けられた。いずれも当初計画のデザインに対する改善がなされれば、最終受益者のニーズを十分に反映し、かつ相手国の開発課題への取り組みに合致した派遣が可能であると考える。
4-1-2.青年海外協力隊事業の成果と効率
要請段階で明確な目標が出されている派遣については、妥当性も高く、また目標達成度も高くなっている。その一方、要請段階での計画デザインが不明確なものについては、多く隊員が派遣されてもそれに見合っただけの成果が得られ難い。在外事務所や調整員への不満の多くも要請背景調査や要請開拓に起因するものであり、要請段階の改善がなされれば協力隊員の在外事務所や調整員への不満は大きく解消されていく。調整員に対するヒアリングから、要請段階の改善点はある程度明確になっていることがわかった。また過去の調整員議事録からも、ある程度問題点の蓄積がされており、それがうまく現場でフィードバックされていないように見受けられる。協力隊事業全体を見渡し、相手国の協力隊に対する理解度の促進、相手国の現状のニーズに即した派遣計画、在外事務所と事務局の温度差のない円滑な連携体制、隊員の活動の目標達成度の向上、配属先でのカウンターパートと協力隊員とのコミュニケーションの向上、調整員の業務環境の向上などに対する改善点がなされれば、より質の高い要請背景調査や要請開拓につながり、「相手国の社会経済への寄与」のみならず、「国際交流、二国間関係の増進」に対しても効果を及ぼしていくと考える。
4-1-3.青年海外協力隊事業のインパクトと自立発展性
「協力隊の派遣は自己完結型で良い」「個別派遣に自立発展性を望むのは厳しい」という考え方もあるが、インパクトや自立発展性は、相手国の社会経済発展への寄与を考えた場合必要不可欠な要素である。今回の調査では、協力隊の活動が正のインパクトや自立発展性をもたらす可能性があるにもかかわらず、それらが十分に活かされていないことが明らかとなった。
また、インパクトや自立発展性が低くなる傾向は、協力隊員の派遣形態のうちマンパワー提供型2 に特に顕著にあらわれている。マンパワー提供型活動に対するアンケートとケーススタディの結果を総合的に分析すると、マンパワー提供型の活動は指導型3 、共同活動型4 よりも高い目標達成(活動に対する成果)を得ることができ、配属先のニーズも高く、安定した職場環境を得られる一方で、隊員が期待する上位目標への達成(インパクト)や自立発展性に対して成果を出していくことが難しく、隊員が活動に不満を抱きやすい。これは、協力隊員と受入側の間で、協力隊事業に関する考え方に相違があることも一因となる。また、協力隊員の派遣形態別の分類は明示的には存在しない。このことも協力隊に対する双方の考え方の相違を生じさせる要因になっていると考えられる。
マンパワー提供型の活動は、相手国のニーズの高さから今後も横這い、あるいは増加傾向にあると推定できる。このため、一つの活動形態として肯定的に見直していく一方で、組織やシステムの中でマンパワー的に活動する隊員の活動成果のインパクトを高め、持続させていく対策を、これまでの実績を踏まえ検討していく時期にある。
4-2.国際交流・二国間関係の増進
ここでは、下記のA~Bの点検項目に基づき「国際交流・二国間関係の増進」対する評価分析を行った。
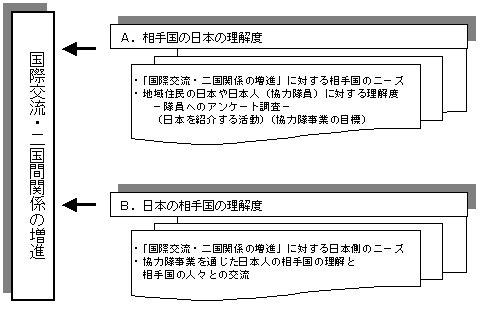
協力隊事業における国際交流は、相手国の人々と協力隊員との接触を持った時点から始まっている。そして協力隊員達は日本に関する生きた情報を相手国の人々、特に草の根レベルの人々に直接発信していく重要な役割を担っている。本調査では、国際交流に対する潜在的なニーズが確認されたが、さらに派遣国の状況によっては協力隊事業が主に日本人との人的交流を行える手段となっている国もあり、協力隊事業が、相手国と日本との相互理解を深め、二国間関係の増進に少ながらず貢献してきたことが確認された。相手国と日本との相互理解が深まっていけば、相手国の住民が有する潜在的なニーズを見出すことができ、日本側は相手国の協力に効率的かつ効果的に貢献していくことができるはずである。さらに、相手国の人々が協力隊員の活動を通じて日本人に対する理解を何らかの形で深めてもらうことは、経済大国という部分だけが前面に出がちな日本の援助に対するイメージを“日本国民が協力している援助”つまり“顔の見える援助”へと変えていくことも可能である。しかしながら、現在行われている協力隊員の国際交流活動は個人ベースでの自主的な活動が主体となり、協力隊事業として明確な目標と方針をもって推進されていない。このため、協力隊員を取り巻く人々に限らず相手国の人々全体を視野において、日本人の文化や思考などを理解してもらえるような事業展開を検討していくべきである。特に協力隊員が得意とする草の根レベルの人たちと持続的に交流していくことは大切である。
相手国の地域住民と協力隊員とはこれまで多くの友好関係を築いてきた。また、活動期間中に協力隊員自身が相手国の地域住民を理解しようとすることで、相手国の文化、芸術、スポーツや言語などを学び相互理解を深めてきたといえる。このため協力隊員達が草の根レベルの人々との相互理解を深めることで、協力隊事業としても日本が相手国の理解を深め、また人的交流を図ってきたことに大きく貢献してきたと評価できる。しかしながら、国際交流・相互理解の範囲は協力隊員自身に限られ、協力隊事業として協力隊員以外の人々が相手国の人々と直接人的交流を図ることにはあまり貢献していない。
世界の中の日本として、諸外国との友好的な関係を発展させていくには、今まで以上に日本に関する情報の発信と相手国の情報を受信していくことが求められている。協力隊事業は、相手国にとっても日本にとってもテレビや書籍などでは得られない生きた情報を発信、また受信することができる存在である。協力隊事業として明確に位置付けられていないが、「国際交流・二国間関係の増進」に対する効果はすでに国内外で認められたものである。しかしながら、現在の個人レベルでの交流活動を国と国との国際交流のレベルへと発展させていくためには、協力隊事業としての「国際交流・二国間関係の増進」の方針、目的、目標を設定し、今後の事業展開を図っていく必要がある。
4-3.日本の青少年の人材育成・日本社会への還元
ここでは、下記のA~Cの点検項目に基づき「日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」対する評価分析を行った。
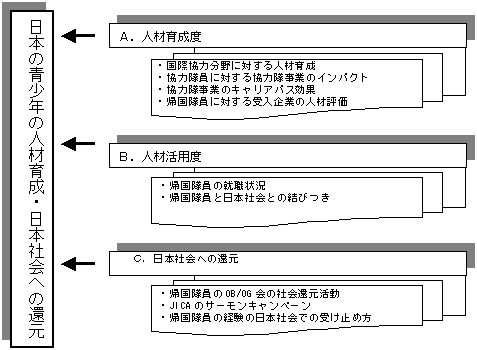
協力隊事業において帰国隊員達は、開発途上国での2年間に渡る協力活動を通じて成長し、日本社会にとって貴重な人材であると位置付けられている。そして帰国隊員達がスムーズに社会復帰を果たし、様々な分野で活躍することによりその経験が社会に還元されることを期待し、帰国隊員への支援事業、特に帰国後の進路問題を中心に取り組んできた。また、国民に対する開発教育や国際理解教育への貢献を日本社会への還元の一貫と考え、サーモンキャンペーン5を実施している。このように「日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」に関しては、目標として明示されていないものの協力隊事業として帰国隊員への支援事業を中心に取り組んでいるといえる。
その一方で、帰国隊員達は自身の経験を日本社会に還元しようと試みながらも、うまく実施できない状況に陥る場合がある。帰国隊員達が進路決定に困窮していることもこの一例である。また協力隊員が体得してきた相手国の異文化や多様な価値観を日本社会に還元しようとする際におこる摩擦も、日本社会に帰国隊員の経験を十分に受け入れる状況が十分に整備されていないことを示している。帰国隊員に対する帰国支援事業を促進するとともに、日本社会が隊員の経験を適切に評価し、できるだけ多くのものを受け入れることが可能となるよう、協力隊事業の理解度の向上や国際理解教育の推進などに積極的に取り組んでいく必要がある。
第5章 提 言
今回評価調査の結果、導かれる提言は以下に示す通り。
5-1.青年海外協力隊事業のプログラム(施策)目標の明示
| 青年海外協力隊事業の事業目標として、「A.相手国の社会・経済発展への寄与」、「B.国際交流・二国間関係の増進」および「C.日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」の3つを明確に国内外に提示していくと同時に、政府事業としての基本理念やODA事業としての位置付けについても国民に対し具体的に示していく必要がある。 |
国際協力事業団法において青年海外協力隊事業の目的は、技術協力を中心とした「A.相手国の社会・経済発展への寄与」とされているが、「B.国際交流・二国間関係の増進」および「C.日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」についても相手国側と日本側の双方のニーズを考慮すると、すでに成果を出すことが期待された事業目標として成立し得る。また、この3つは一つ一つが独立した目標というより、それぞれが密接に結びつき、「A.相手国の社会・経済発展への寄与」に対する何らかの改善が図られれば、「B.国際交流・二国間関係の増進」および「C.日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」に対してもプラスの相乗効果が与えられる。このため、A~Cの3つを事業目標として明確に提示し、協力隊事業の内容に反映させていく必要がある。
(1)正確なニーズの把握のための要請背景調査
| 協力隊員の協力活動にかかる問題点の多くが、要請段階に起因している。このため、特に要請背景調査の実施方法について広く議論し、国内外の多様なニーズに応えることができるシステムを模索していく必要がある。 |
「相手国の社会・経済の発展への寄与」に効率的かつ効果的に貢献していくためには、まずは現場で活動する隊員達の目標達成度を高めていく必要がある。隊員へのアンケート調査結果からは、配属先のニーズが高く、また隊員の活動計画や役割分担に対する明確な考え・認識が高い場合には、隊員の目標達成度が高くなる傾向となった。相手国のニーズを正確に把握していくためには、ローカルスタッフの育成・活用、要請背景調査に専念できる人員の登用、専門家との連携など要請背景調査を充実させる基盤整備から早急に対応していく必要がある。また在外大使館、JICA事務所および相手国側の受入機関や配属先と常時連携し、要請にかかる十分な協議を行うなど、相手国側および日本側の関係者を巻き込んだ参加型の要請背景調査を意識する必要がある。
(2)ニーズに正確に応えるための参加形態の体系化・弾力化
| 同じ職種の協力隊員であっても、協力隊への参加形態や配属先での位置付けなどの違いによって協力隊員の活動の特質に傾向が見られる。これまでの派遣実績を分析することで、隊員の活動の特質を体系化し、より効率的かつ効果的な派遣計画に反映させていく必要がある。 |
協力隊事業の35年間という実績を踏まえ、協力隊員の参加形態・活動形態を明確にし、例えば指導型、マンパワー提供型、共同活動型により異なる隊員活動の特質を見極めた派遣実施を行っていくべきである。
今後もますます多様化していく要請に対応していくためにも、隊員の活動の特質を体系化し、効果的な派遣計画の立案に反映させていく必要がある。
(3)より効果的な派遣計画
| "協力隊事業"に対する相手国のニーズや重要度は、国や地域により異なる。協力隊員の技術・知識レベルを見据えた上で、相手国の開発戦略や援助動向などに適合した国別派遣計画の策定を行っていく必要がある。 |
上の(1)、(2)で述べた通り、協力隊事業の目的、形態を明確化し、より効果的な派遣計画を策定していけば、協力隊事業は相手国側および日本側のニーズに応えた事業展開が可能となる。また、その派遣計画は相手国の開発戦略や重要課題に合致した内容であることが望ましい。しかしながら、協力隊員達が派遣計画のみにとらわれることなく自由に相手国のニーズを開拓していく余地を設けることも必要である。相手国の重要課題に対する協力なのか、協力隊員達の活動の特性を活かした協力なのかなど、相手国の社会経済背景、日本側の援助方針および協力隊活動の利点などを計画段階から十分に考慮していくことが大切である。
5-2.評価方針と評価手法の確立
| 協力隊事業に参加した多くの隊員が「評価を実施して、その結果を国民に知らせるべきだ」と考えている。今後、“評価”を協力隊事業の中に取り込んでいき、一般国民に評価結果を広く伝えていくと同時に、評価手法を改善し、より効果的な協力隊事業のために評価結果を的確にフィードバックしていくことが重要である。 |
アンケート結果から、約8割近い隊員が「評価を実施して、その結果を国民に知らせるべきだ」と考えていることが明らかとなった。評価は(1)アカウンタビリティの確保、(2)援助の質の向上という大きな二つの目的を持つ。ODAの透明性や効率性に対する国内の要請はますます大きくなっており、評価の重要性は高まっている。この中で協力隊事業についても評価を行うことは有意義である。
評価を行うことによって協力隊事業の活動を国民に対して広く知らせることができ、学んだ教訓を実施者にフィードバックすることでより効果的な協力隊事業の実施に資することができる。協力隊事業の評価は今回が初めてであるが、今後も引き続き評価を行っていき、評価手法の更なる改善に努める必要がある。
5-3.協力隊事業の日本社会への還元
| 「教えるものよりも教えられるもののほうが多かった」と感じている隊員は多い。この相手国の草の根レベルの情報や隊員が協力活動通じて体得した経験を、国民の国際理解教育や地方自治体の国際化に活用していくために、隊員の情報を蓄積し、広く公開できるシステム作りが必要である。また、日本の他の援助スキームへの積極的な活用も検討していくべきである。 |
帰国隊員の経験を社会に還元するための取り組みとして、地方自治体の職員としての採用、教育現場での教員としての採用、またサーモンキャンペーンなどの国際理解教育・開発教育分野での活躍が挙げられている。しかしながら、帰国隊員達が2年間現地で生活しながら得たものは経験だけでなく情報もある。現時点では、この情報はほとんど有効活用されていない。隊員の情報は報告書に集約されているともいえるが、隊員報告書は事務局・在外事務所や後任者などに向けての報告の形式をとっており、情報としては活用し難い。このため、派遣国別や職種別に隊員達が有する現地の情報をタイムリーに蓄積・提供していくことが可能なシステム(インターネットなどを利用)を構築し、積極的に国民に公開、利用されていくべきである。同時に、隊員達が蓄積した情報が要請背景調査やその他スキームの調査にも活かしていくことが望ましい。
また、例えば現職参加教員であれば、国際理解教育や開発教育の指導要領や教材の作成、資料提供など帰国後も積極的に情報提供に役立ってもらう体制作りも必要である。
5-4.協力隊員の人材育成および人材活用の促進
(1)人材育成
| 国際協力分野の仕事を希望する帰国隊員が多いにも関わらず、関連職につくことは容易ではない。現在の雇用状況を変えることは難しいことから、隊員の質の向上が必要である。すでに帰国後の支援については充実していく方向にあるため、活動期間中に援助手法に関する高い専門性や語学力の向上が目指せるような体制が必要である。 |
国際協力分野への就職を希望するものが多いにも関わらず、なかなか関連職につくことができない状況がアンケート結果からも明らかになった。また、協力隊に参加したことによって、国際協力分野に興味を持ち、仕事として携わりたい意向を持つものも少なくない。しかしながら、国際協力関連の団体や民間企業の数は限られており、近年はODA削減等により雇用市場も他業界同様にかなり厳しいのが現実である。このため、隊員の質の向上を目指していく必要がある。
帰国隊員に対しては、すでに帰国後研修やセミナーが充実していく方向にある。しかしながら、活動期間中にはあまり目が向けられていない。協力隊事業の経験を生かした援助手法の開発に取り組み、隊員の質の向上に反映させていくことも必要である。
(2)人材活用
| 協力隊事業のODAとしての役割や協力隊事業の基本方針などを国民にわかりやすく提示しながら、帰国隊員達の現地での活動だけでなく、帰国後の人材活用についても国民に広報し、帰国隊員に対する適切な人材活用について広く議論されることが必要である。また帰国隊員に対する適切な社会からの評価は、帰国隊員達の受け皿の整備にもつながる。最終的には、国民に親しまれる国民参加型の青年海外協力隊事業として確立されていくことが望ましい。 |
青年海外協力隊事業の認知度をあげていくためには、協力隊事業の基本理念、方針、目標およびODAの中で期待される役割などをわかり易く国民に提示し、広く賛同を得ていくことが必要である。この基盤が十分に浸透してから、個々の隊員の活躍などを継続して紹介していくことも大切である。最終的には、国民に親しまれる青年海外協力隊事業となっていくことが望ましい。具体的には、協力隊経験者が地方の国際化に積極的に貢献することをある程度義務付け、その体制を強化していくべきである。
協力隊事業は、隊員の活動が地域住民、つまり相手国の一般国民と直接接点を持ちながら協力活動を行っているため日本の他の援助スキームと比較した場合、もっとも一般国民が理解し易いODA事業であるといえる。協力隊事業のODAとしての役割や協力隊事業の基本方針などを国民にわかりやすく提示しながら、帰国隊員達が自身の活動を広く国民に伝えていければ、国際協力活動が国民に身近な存在として理解されていくと考えられる。また、協力隊事業について広く国民が理解し、帰国隊員が適切に社会から評価されていくことは、帰国隊員達の受け皿の整備にもつながる。
1 青年海外協力隊20世紀の軌跡 第1部より要約
2 マンパワー提供型:配属先の人材では補えない役務を担うために、協力隊員の投入を求める活動形態
3 指導型:配属先のカウンターパートや同僚に隊員が有する技術・知識を指導していく立場にある活動形態
4 共同活動型:配属先のカウンターパートや同僚と共同で協力活動を行い、その活動を通じて隊員が有する技術・知識が共有されていく活動形態
5 JICAの実施する、開発教育に関連して小、中、高、大学等を中心に講師を派遣する制度。平成12年度実績で1,059回(うち帰国隊員は645回)の講師派遣を実施している。

