参考情報 1 NGO事業補助金事業の事例
事例1-1:(社)銀鈴会の事例
1.プロジェクトの概要
 |
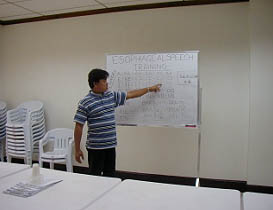 |
| <発声トレーニング> | |
(団体の概要)
社団法人銀鈴会は、喉頭摘出手術を受けた者の発声練習及び福祉啓発を図ることを目的に、1954年に創立された。1981年の国連障害者年を経て、1984年には、銀鈴会が中心となって、「アジア圏における各国・地域の喉頭摘出者の再教育の機会を作り、喉頭摘出者の最大多数がリハビリテーションの実現を期すること」を目的に、「喉頭摘出者団体アジア連盟(Asian Federation of Laryngectomees' Association (AFLA) )」を創設した1。AFLAは1997年には国連経済社会理事会との特別協議資格を有するNGOとして認定されている。
銀鈴会は、毎年、アジアの喉頭摘出者を日本に招き、食道発声法の研修を行っている。数カ国からの研修生を毎年受け入れてきたが、近年は一カ国からの研修生に絞って受入を行っている。2002年4月までに日本招致研修生の卒業生は総計226名に達している。1990以降は更に多数の喉頭摘出者の社会福祉増進を目指して、海外への指導員派遣を行ってきた。1998年にはバンコクに「AFLA食道発声研修センター」が発足した。現在までに派遣人員も148名に達し、研修事業の受講者は累計1,616名に上る。しかし、アジアの指導員の数は日本に比べ2まだ少ないのが現状である。
本事業は、銀鈴会の行うアジア12カ国への支援活動とお互いに補完するものとして実施されている。
2.2000年度 補助金事業内容
銀鈴会は、2000年8月27日から8月31日の5日間の日程で、フィリピン喉頭摘出者クラブ(AFLA加盟)のリハビリ活動の支援と、インストラクターの支援を目的に、日本から専門家を2名派遣した。当事業の要請は、2000年4月のAFLA常任理事会3において常任委員のフィリピン総合病院の耳鼻咽喉科リハビリ主任のDr.ルネ、トゥアゾンより行われた。
| プロジェクト名 | :医療事業、障害者復帰対策事業(2000年度) |
| 補助金事業実施期間 | :平成12年8月27日から8月31日 |
| ターゲットグループ | :喉頭ガンまたは咽頭ガンによる口頭全摘出者 |
| 対象地域 | :マニラ市 |
| 活動の内容 | :食道発声研修会の開催(対象:全く声が出ない25名の摘出者)と指導員の養成 |
| 補助金対象経費 | :501,000円(資機材設備費:人口喉頭、発声補助装置、テキスト) |
| 自己資金使用実績 | :562,080円(医師等派遣旅費、指導員費、通訳費、事業管理費) |
| 現地カウンターパート | :フィリピン喉頭摘出者クラブ(ケソン市内)、マニラ市ゼネラル病院医師(AFLA常任委員) |
3.訪問内容
2002年8月14日、喉頭摘出者クラブの診療所のある、退役軍人記念医療センター4(Veterans Memorial Medical Center)の耳鼻咽喉科を訪問した。面談相手:耳鼻咽喉科長のDr. Ureta、フィリピン喉頭摘出者クラブの代表者のDr. Tuazon(フィリピン総合病院勤務)
(事業の背景)
フィリピンの喉頭ガン5患者の数は1万人以上、マニラ周辺には約2,000人がいると推定されており、フィリピン総合病院ともうひとつの病院において、喉頭摘出者のリハビリを行っているものの、技術者不足のため食道発声は全く行われず、機械による発声に依存していた。このような状況に鑑み、銀鈴会は1996年にマニラ市内で食道発声法に関するシンポジウムを行った。参加した医師を中心に、1997年喉頭摘出者を組織化し、教育やリハビリを通じで社会的地位の向上を支援するために、フィリピン喉頭摘出者クラブが設立された。設立者のUreta 医師によると、「当時我々も食道発声への需要を感じていたが、自分達だけでは実現出来る自信がなかったが、シンポジウムで体験し我々もできる自信が持て、クラブの設立に至った」という。また、同年には、クラブを財政面支援、リハビリセンター設立、喉頭科学の研究促進、等の面で支援するために、フィリピン喉頭摘出者基金(Philippine Laryngectomee Foundation Incorporated: PLFI)が同病院スタッフにより設立された。設立当初のクラブのメンバーは8人であったが、調査時点では120人、家族を含めると約360人になるという。2000年3月には人気ドキュメンタリー番組 'Magandang Gabi Bayan' で当クラブのメンバーや活動が紹介され、喉頭ガン患者のための支援組織としてフィリピン国内で紹介された。
本リハビリセンターは、全国の喉頭摘出者を対象にリハビリを行う、国内唯一の病院である。通常彼らは、週に1回訓練に参加し、約1年ほどのトレーニングを続け発声を取り戻している。従って、病気のため職を失い収入のない者にとり、継続的にリハビリセンターに通うことは経済的に難しい状況であった。様々な発声方法があるが6、食道発声法は、いつ如何なるときでもすぐ話ができ、体力のある患者にとっては適しているといわれ、銀鈴会の支援を受けて行っている。
(成果)
補助金対象事業の効果は、訓練参加者全員の25名全員が声を取り戻したことである。訓練者(インストラクター)の数は既存の2名のまま増加しなかった。また、声を取り戻し社会復帰した者はいなかったが、声を取り戻すことによって笑顔を取り戻した効果は大きかった。
(自立発展性)
補助金事業実施後の、クラブ独自の自立発展性は高かった。第1に、AFLAの一連の活動である日本国内研修(JICAの研修員受入制度「喉頭摘出者のための食道発声指導員養成(フィリピン)」7を利用(2001年の8月~10月)し、5名の研修生が来日し、食道発声法を勉強した。現在そのうちの2名が指導員として働いている。第2に、2002年の2月からは、病院の耳鼻科の建物に付属して、敷設診療所およびトレーニングルームが一応完成し(機材設備が充分に揃ってない)、食道発声のトレーニングが金曜日の午後に行われるようになった。15名の患者が訓練を受けている。現在抱える当クラブの課題は、トレーニングコース実施や病院のネットワーキングのための資金不足であるが、そのために新たなドナーを見つける努力を続けていた。
以上のように、クラブ自体が積極的に事業継続の努力を行っていた。また、病院に付属してクラブが創設されており、手術、治療、リハビリという一環とした活動が行うことが出来、他病院との連携もあるため、持続性が高いと考えられる。
持続発展性の阻害要因としては、彼らが声を取り戻し社会復帰することで、指導者が去ることである。ただし、フィリピン社会の現状として、声を取り戻しても雇用が無く、社会復帰できていないという現状がある。そのため、クラブ自体の資金不足を解消し、指導者に給料を払い、一時的雇用に結びつける必要性もある。
(現地カウンターパートの体力)
将来は、現在マニラでの活動に留まっているために、国内全土での展開を考えているという。また、低い費用で活動を継続するためには、マレーシアでの研修を行う等の他のアジアのAFLA加盟国との協力を進めていこうとしている。将来への課題として、指導員の育成があり、現在の訓練受講生が、継続して訓練を受けられる体制を経済的にも支援して行く必要性を認識している。また、育成された指導者は現在、無給で指導をしているため、彼らの給料を手当てする必要がある。
1 当初はアジアの11カ国が参加したが、2002年4月現在は、マレーシア、日本、中国、香港、インド、インドネシア、大韓民国、パキスタン、フィリピン、台湾、タイ、シンガポール、ネパールの13カ国の国・地域が参加し、アジア圏に推定される患者33万人の発声リハビリ活動を継続している。
2 日本は8,000人の喉頭摘出者に対して800名の指導員がいる割合である。
3 毎年1回加盟国の持ち回りで開いている。その場で、各国の状況について年次報告とレポートの提出を受けている。
4 当センターは、国家防衛省(Department of National Defense) フィリピン退役軍人関連事務局(Philippines Veterans Affairs Office) の下に置かれているヘルスケア組織である。当耳鼻科には、耳科、鼻科アレルギー科、口腔・喉頭学、顎顔面整形外科等の5つの科に別れているが、喉頭及び耳に関するケースの担当数は、フィリピン国内で最大である。また、当耳鼻科は、外科診療所を持っており、毎日約20人の患者を見ている。また、手術の必要な患者用に30床の入院設備を有する。
5 Ureta医師によると喉頭ガンはフィリピンにおいて10番目の死亡原因の病気だという。
6 神奈川銀鈴会ホームページ(http://babu.com/~xxx/kanagawa/index.htm)参照。
7 2000年度よりJICA研修制度を利用し第一回目はタイからの研修生6名を対象に行われ、2002年度は第3回目としてインドネシアからの研修生6名を対象にして行われている。

