4-3 NGO事業補助金の効果の評価
第3章でみたように、本制度は、「外務省とNGOとの連携」という上位目標の下、2つの目的、(1)「被援助国に対して、国家レベルの協力では対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする」、(2)「本邦NGOの組織能力を強化する」を有していた。NGO事業補助金制度の効果を確認するために、具体的交付先の事業をケーススタディーとして、目的(1)(2)が達成されたのか検討する。目的(1)の達成度については質問票1と現地調査により検討する。目的(2)の達成度については、質問票2と、現地事業において日本のNGOの組織能力の強化が具現されているのかという点に基づき検討を行った。これら目的(1)(2)の達成度をもって、効果を計ることとした。
4-3-1 目的(1)「被援助国に対して、ODAでは対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする」の達成度
ここでは、補助金の交付先の4団体の事業を事例9に、目的(1)が達成されたかを検討する、検証に際しての、評価の項目は、募集要領の審査方法の「基本的考え方」で掲げられるきめ細かい援助を可能にするための4つの項目に分けて考察した。すなわち、(A)政府レベルでは対応が困難な草の根レベルの事業であり、途上国住民に対する人道的配慮及び環境保全の観点から配慮がなされており、かつ経済・社会・地域開発、民生の安定につながること、(B)地域社会のニーズが十分把握されていること、(C)地域住民の自助努力による自立を促し、地域住民の参加があること、(D)援助効果が対象地域の女性にも裨益するように配慮されていること、という4項目について、検証を行った。その際、(A)については、「草の根レベルの成果が出ているか」、(B)については「地域住民のニーズにかなった事業であったか」(C)は、「地域住民の参加が得られ、自立発展性があったか」(D)は、「女性の裨益効果があったか」という基準で、それぞれ評価を行った(事業の概要は参考情報1(NGO事業補助金事業の事例)を参照。また上記4項目に基づく評価は、本文第4章P4-21~22の表4-1にもまとめた)。
(1) 草の根レベルの成果がでているか?
第一に、「草の根レベルの成果が出ているか」についての評価方法は、利益が直接的に指導者や意思決定者でなく地域の一般住民レベルに結びついているかという視点で評価を行った。その結果、評価を行った4事業とも、国家レベルの協力では支援が行われにくい事業であったり、地域住民に直接支援を行うものであり、草の根レベルで事業の成果が達成されていた。具体的には、次のような事例が見られた。
(銀鈴会)
銀鈴会は、本補助金事業として2000年8月27日から8月31日の間に、日本から専門家2名を派遣して、喉頭ガン等によって喉頭を摘出した人たちを対象にして、発声を取り戻す訓練を行った。25人の患者を直接の対象とし事業を実施し25人が声を取り戻すという成果を出している。従って、草の根レベルの事業として評価される。ちなみに、受益者は、結核改善等の緊急課題を抱える国家にとり必ずしも支援対象としては優先順位の高くない人々であった。
(地球ボランティア協会)
地球ボランティア協会は、1998年から2001年度の間、事業を行ってきた。活動地域は、1998年は8地域、1999年、2000年は12地域、2001年度は20地域と活動地域を広げてきた。2001年度は、ルソン島のほか、セブ島、パナイ島、ネグロス島でも事業を行っている。活動内容は、(1)活動の担い手となるボランティアと対象地区の共同体リーダーの育成、(2)保健医療及び教育サービスの提供、具体的には対象地域20箇所に対して定期的に医師団を派遣しての住民に対して保健・医療サービスの実施、(3)所得向上を目的とした女性を対象としたマイクロファイナンス事業の実施、である。 保健事業については、保健所への薬の支援や、無料医療診療活動を行っており、受益者は、低所得地区の住民、子供たちである。一般住民を直接の受益者としており、草の根レベルでの成果を出しているといえよう。
(金光教平和活動センター)
金光教平和活動センターは、1997年~2001年の間、マニラ市(2ヶ所)、マラボン市、セブ島マンダウエ市で、保健衛生事業を行っている。具体的には、保育所の運営と給食サービスによる栄養改善事業と、教育を行っている。それぞれの受益者の数は、児童80人、200人、200人であり、直接受益者に対して、草の根レベルで事業を行っている。調査団はマラボン市の現地調査を行ったが、栄養改善に関する具体的調査結果は出ていないものの、母親や子供が便益を受け、草の根レベルの効果が見られた。
(日本フィリピンボランティア協会)
日本フィリピンボランティア協会は、1996年より2001年の間、補助金の交付を受け、ミンダナオ島ダバオで活動している。活動内容としては、フィリピン日系人会の活動支援を通じて、次の活動をしている。(1)ダバオ市トリル地域での地域医療福祉総合センター(CMU)の活動支援:貧困集落における無料巡回医療活動、給食の提供、野菜栽培指導活動、母親学級、授産活動の支援。(2)移動児童館の活動、貧困集落の児童を対象にした教育・福祉活動の推進:学校に行けない児童を対象に紙芝居や本の読み聞かせ、絵・歌・踊りなどの出前教育の実施。(3)山の小学校の保健室整備:40校の学校に対して薬の提供を年3回実施。その際、CMUの医師・看護婦が保護者に対して、子どもの健康や衛生について講義、健康問題や生活改善に関心を持った地域のリーダー育成の実施。(4)指導者養成講座の開催(日本向けヘルパーの講座を含む):上記の地域リーダーの育成をするとともに、日比の福祉交流・教育交流を行なうフィリピン側のスタッフの人材育成。フィリピンでは子どもの福祉、日本では高齢者の福祉と両国の福祉に関する課題の解決を担う人材育成の推進。
活動に際し、事業対象地を日系移民の多いコミュニティーを対象にし、実際に住民が活動より便益を受けており、草の根レベルの成果が達成されていた。
以上のように、4事業とも一般の地域住民を対象として、草の根レベルで成果が見られた。
(2) 地域住民のニーズにかなった事業であったか?
第二に、「地域住民のニーズが十分把握されていたのか」という点については、プロジェクトが住民のニーズを反映するものであったか、現在もニーズがあるか、という点で、評価を行った。 その結果、計画当初地域住民のニーズが把握されていたといえるが、継続事業の場合、現在のニーズについての検討が不十分である事例が見られた。具体的事例は次の通り。
(銀鈴会)
銀鈴会のAFLA(喉頭摘出者団体アジア連盟)の理事会において、フィリピンの喉頭者摘出者クラブの申請を受けて、日本人食道発声の専門家の派遣という本NGO事業補助金事業が計画・実施されており、現地のニーズが十分把握された事業であったといえよう。そして、現在も患者達の間で、食道発声習得のための要望は高く、ニーズがある。
(地球ボランティア協会)
地球ボランティア協会はカウンターパートのDAWV(Development Advocacy of Women Volunteerism Foundation, Inc.)(スタッフ5名)と共に、ボランティアの派遣と、無料の医療診療活動等を行い、2001年度は20地域で活動を行っている。事業地の選定は、個別地域からの要請を受け、それを審査し、事業を選定しているとのことであり、ニーズに基づいた対象事業の選定が行われているといえよう。ただし、現在も、各サイト毎の活動報告のレポートはあるが、地域毎の現在のニーズや、成果についてのデータの蓄積が不十分であった。
(金光教平和活動センター)
金光教平和活動センターの場合、現地調査で訪問したマラボン市のケースは既に住民組織があり、その住民組織の要請に対応して、本事業が行われたため、計画時にニーズが反映されていたといえよう。現在も本住民組織は活動しており、金光教の活動へのニーズはある。
(日本フィリピンボランティア協会)
日本フィリピンボランティア協会の場合は、ダバオで日系人会が貧困に置かれた日系人のために給食活動や無償医療活動や学校の保健室への薬の配布等の活動を行っていたが、その日系人会の活動を支援してきた。従って、ニーズのあるところへの支援を行ってきたといえる。しかしながら、調査団の訪問した地区は、マニラ付近の低所得者居住地区に比べ、劣悪な環境とは言えず、現在の事業のニーズの説得力が弱かった。
以上のようにプロジェクト開始時のニーズの確認はどの事業でも行われていた。しかし、懸念事項としては、継続事業を行うに当たり、現在のニーズの確認や他の地域に比較しての当地域のニーズの確認が十分行われていない様子であった。従って、外務省は審査に当たり、この点を十分に確認する必要があると思われた。そのために、NGOが地域計画とNGO事業との関連性も把握することが必要であろう。また、より効果的な開発協力事業の実施のためには、地域における連携またはNGO事業間の連携等の重要さも認識してく必要があろう。
| (参考) AusAIDでは地域行政とNGO事業との関係を重視しており、NGO事業申請書の中で申請事業と地区の計画との整合性を書くようにしていた。 |
(3) 地域住民の参加が得られ、自立発展性があったか?
第三に「地域住民の自助努力による自立を促し、地域住民の参加があること」については、住民が事業に参加し、我が国のNGOや、現地カウンターパートが住民の自立を促す事業を行っているか、検討した。その結果、住民の参加がいずれの事業においても見られたが、住民の主体的な自立発展的な活動につながったかという点においては、団体により差異が見られた。具体的には次の通り。
(銀鈴会)
喉頭摘出者に対する発声トレーニングを行う銀鈴会は、受益者を今後、日本人指導員に代わって指導者として養成することを活動のひとつとしており、地域住民の自立を促し、参加があったといえる。
(地球ボランティア協会)
地球ボランティア協会の場合は、カウンターパートの、DAWVは、主な活動として、ボランティアを発掘・派遣し、地域でのボランティア活動を促進している。その結果、地域住民はボランティアの行う講習会へ参加し、意識向上が行われたが、地域住民が自ら自発的に事業を行っていく試みは見られなかった。付言すると、DAWVは、同地区で既に他のNGO活動が存在しているところにボランティアを派遣しており、住民の自立、組織化への働きかけは積極的に行っていなかった。
(金光教平和活動センター)
カウンターパートの金光教の現地法人がマラボンの住民組織を支援する形で中心となって、活動を行っている。受益者は子供であるが、母親達がプロジェクトに参加し、主体性をもって、保育所運営の改善や、様々な問題に対応して活動している。従って、地域住民の参加が在り、地域住民の自立を促している。
(日本フィリピンボランティア協会)
日本フィリピンボランティア協会の場合は、現地事務所を持ち、日本人が2名駐在し、NGO事業補助金事業の他にも多様な活動を行っている。NGO事業補助金事業としては、日系人会と共に、給食活動、薬の配布、無料医療診療活動を主に行っている。これらは、慈善活動的要素が強く、地域住民の参加や自立を促すような事業にまでは繋がっていなかった。
以上のように、住民参加については、いずれの事業においても、住民の参加は見られたが、自立促進という意味では、促進の度合いに差異が見られた。これには、日本のNGOと、現地のカウンターパートの住民参加や地域開発への考え方が現れているといえよう。
参考までに、今回の調査においては、4事業中3事業の場合に、カウンターパートが中心になって事業を行っていた。概略を示すと、銀例会のように自らが技術支援を行うものと、その他の3事業のように、カウンターパートに対して、活動内容に関する支援や、財政支援を行うものがあった。後者の場合は特に、カウンターパートのNGOの能力や、活動理念が事業における住民参加や自立促進への動きへの影響をもたらしていることが見受けられた。
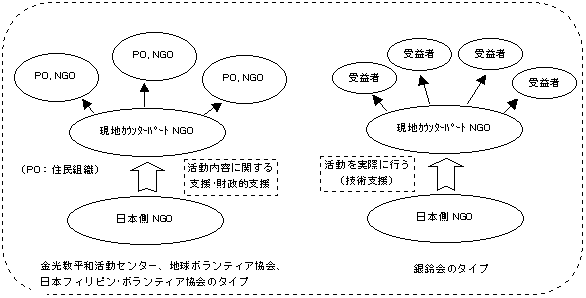
また、カウンターパートの能力については、今次現地調査を受け入れてくれた団体は、調査団に対して協力する能力があり、カウンターパートの能力の高い団体であったといえよう。一方で、今次調査の困難であったプロジェクトの中には、終了後カウンターパートがなくなり、また担当者も異動し、受益者との連絡も困難である団体もあった。この場合、カウンターパートの能力が低く、自立発展性の低いことが思料された。(実際にあるNGOはスタッフとの関係が上手くいっていなかったというような情報も得た。)従って、住民参加や自立発展性を考えた場合、カウンターパートの能力は重要な要素であるので、モニタリング等の事業進捗の中で外務省側が情報収集して行くことが必要であろう。
(4)女性の裨益効果があったか?
第四に、「援助の効果が対象地域の女性にも裨益するように配慮されていること」については、女性がプロジェクトの便益を受けているかという点で評価を行った。その結果、女性が事業へ参加し、便益を享受していたといえるが、具体的には次の通り。
(銀鈴会)
銀鈴会は訓練対象の患者の25名中に女性が1名含まれていた。また、受益者の妻達が活動資金の捻出のためにキャンドル作りと販売の活動を始めた。このように女性への裨益があったと考えられる。
(地球ボランティア協会)
地球ボランティア協会は、カウンターパートのDAWVが女性のボランティア育成を目的としており、実際に女性のボランティアが育成され、女性への裨益があった。
(金光教平和活動センター)
金光教平和活動センターでは母親である女性達が子供への給食活動や学習指導に参加して、自らが保育所運営等のための自信をつけ、間接的であるが便益を得ていた。
(日本フィリピンボランティア協会)
母親学級や母親の給食活動への参加を通じて、女性の意識の向上といった便益を受けていた。
従って、いずれのプロジェクトにおいても女性の裨益があったといえる。これは今次調査対象が保健医療事業であったこととも関連し、このような結果に繋がったと思われる。
以上のように、NGO事業補助金制度の開発事業に関しての「基本的考え方」の4つの基準が4事業において確実に達成されていた。すなわち、一般の住民が直接の対象となり、便益を受けており、地域のニーズのあるところで活動し、住民の参加や自立発展性が見られ、女性も裨益していた。従って、目的(1)「被援助国に対して、国家レベルの協力では対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする」は達成されていたといえる。
しかし、「地域住民のニーズにかなった事業であったか」「地域住民の参加が得られ、自立発展性があったか」の達成度については、NGOの事業により差異が見られた。従って、事業の審査に当たり、事業の成果を高めるために、この2項目について重点を置くことが重要であろう。
表4-1:NGO事業補助金の目的(1)の達成度(4事業の例)(PDF)
4-3-2 目的(2)「本邦NGOの組織能力の強化」の達成度
ここでは、目的(2)が達成されたかについて、補助金交付先の9団体10(対象9団体については別添6を参照)に対して、アンケート調査(9団体のうち7団体から回答有り)及びインタビュー等を通じて、実際にNGO事業補助金がNGOの組織強化に役立っているかを検討することとした。ちなみに、NGOの組織能力の強化は、NGO事業補助金のみにより達成されるわけはなく、組織能力の強化をNGO事業補助金のみの成果として判断することは難しいが、「NGO事業補助金の交付を受けている間に組織能力の強化につながったか」というレベルで評価を行った。最後に、ケーススタディとしてそのNGOの行う具体的な現地の開発事業4事業11の組織能力、財政能力についても検証した。
(1) 9事業におけるNGOの組織能力の強化の達成度についてのNGOの認識
具体的に、NGO 9団体への質問票による調査(別添10参照)を中心に行った。実際に組織能力・財政能力が強化されたかとの問いに対して、NGO事業補助金を受け取った結果として、約半数のNGOが達成されたと評価しているが具体的には次の通り。
| 財政基盤の強化 | 組織能力の強化 | 補助金額(円)※ (1997~2001年度) |
|
| 金光教平和活動センター | ○ | ○ | 20,452,943 |
| 銀鈴会 | × | ○ | 501,000 |
| 国際ボランティアセンター山形 | ○ | ○ | 8,603,000 |
| ICA文化事業協会 | × (管理費が出ないので) |
× | 9,340,075 |
| 地球ボランティア協会 | ○ | ○ | 35,636,224 |
| 日本フィリピンボランティア協会 | × | × | 15,410,999 |
| AMDA | ○ (自己資金の強化を図ったため) |
× (今後の課題) |
6,628,455 |
財政基盤の強化
財政基盤の強化については、7団体中4団体が財政基盤の強化に繋がったと応えており、一定のNGOに対しては、財政基盤の強化に貢献したといえる。例えば、AMDAは、「NGO事業補助金は開発事業の2分の1以下しか交付されないので、自己資金を集める必要があり、それを通じて自らの資金獲得能力が向上し、財政基盤が整備された。」と回答している。つまり、NGO事業補助金を通じて、補助金の補助率が2分の1であるというプロセスを経ることによって、自らの組織能力を向上することができたと評価している。従って、目的(2)は、4団体においては、達成されていた。ちなみに、補助金を利用した理由について、3団体が財政面、活動面の資金12充当が目的であったと回答している。
しかし一方で、財政基盤の強化に繋がらなかったと回答する団体も3団体あった。銀鈴会は、NGO事業補助金の交付金額が50万円と少額であり、このような回答に繋がったのであろう。また、日本フィリピンボランティア協会については、NGOの支援層が厚く、資金が潤沢に在るので、このような回答に繋がったと思われる。また、ICAは、NGOは「開発協力事業に対する管理費が出ないので、団体としての財政能力の強化に繋がっていない」と回答している。
組織能力の強化
また、組織能力の強化についても、7団体中、4団体が強化されたと回答している。一方、2団体が無し、1団体が「今後の課題:中長期的視点で組織能力の強化を図っていきたい」と回答している。
以上のことから、NGO事業補助金の目的(2)「本邦NGOの組織能力を強化する」は一定NGOにおいて達成されていた。
(2) ケーススタディ: NGO事業補助金交付4事業における組織能力・財政能力の強化の事例研究
ケーススタディとして、NGO事業補助金交付4事業を取り上げ、当該4事業のプロジェクト現場の現地調査、及び事業実施NGO、現地カウンターパート、受益者等のプロジェクト関係者へのインタビュー等を実施し、現地での開発協力事業に組織能力及び財政能力の強化がどのように具現化されているのかを検証した。検証に当たっては、開発協力事業を行うことで、NGOの中に「人、資金、情報をより上手くマネージする能力」を蓄積することが出来たかという点につき、以下の4つの視点に基づいて見極めを行った。
| (1) | 良い効果を生むプロジェクトを実施するプロジェクト運営能力の強化、スタッフの育成・経験の蓄積を積む。また、それらを「組織体制の強化」として体現する。 |
| (2) | 資金調達力、社会に活動をアピールする力をみがくことができたか?→会員・支援者の獲得。相手側の視点から日本社会のあり方・協力の仕方を考えてもらう。社会にNGOを国際協力の必須のアクターとして認知させる→ODA、国際機関、あらゆる助成団体と対等で双方向の関係作り。 |
| (3) | 現地との草の根レベルのネットワークの強化をはかり、現地の本当のニーズや問題点、問題解決能力を持った主体を把握し、国際協力・連携の中味を深めることができたか。 |
| (4) | 活動を通じて得た経験、教訓、情報を通じて、ODAなど他の援助活動や国際協力のあり方への提言活動をより豊富にさせることができたか。 |
(銀鈴会)
| (1) | 現地の喉頭摘出者クラブのメンバーは、1997年の設立時8名から現在の120名に増大し、また、2000年には活動内容がテレビ放送でも取り上げられ、フィリピン国内での知名度を上げる等、確実に活動は拡大している。また、クラブの財政支援を行うための基金も1997年に設立され、組織の財政面での支援体制が整備されてきた。 |
| (2) | 資金調達力については、資金収集に積極的である。現在も、クラブのトレーニングセンターに隣接する診療所の機材の整備のためのプロポーザルを作成中である。また、JICAの日本国内研修を利用し、患者10名を日本に送り、発声訓練研修を受講している。従って、資金調達力、プロジェクト運営力が高いといえよう。 |
| (3) | 現在、喉頭摘出者クラブはマニラにあるが、全国の患者にも呼びかけを行っており、ネットワークつくりに積極的である。 |
| (4) | 特に国際協力に関する提言活動は行っていない。 |
(地球ボランティア協会)
| (1) | ローカルカウンターパートのDAWVのスタッフは、栄養士、看護婦等の資格を持っているが、年齢的には20~30歳代が中心で若く、地域開発の経験が浅い。団体としてもボランティアの派遣や、ボランティアの育成を目的としており、地域に根ざした開発を目的としたNGOではないが、過去にもAusAIDの資金を利用する等、財政基盤の整備や組織能力を向上させているようであった。 |
| (2) | DAWVは企業家の支援者を理事に抱え、資金的サポートが厚い。また、アジアのボランティア育成のための国際会議に参加する等、PR力は高い。積極的なPR活動を行っている。 |
| (3) | ボランティアの育成とネットワークつくりに積極的である。 |
| (4) | ボランティアの育成のための提言を国内外を問わず、積極的に行っている。 |
(金光教平和活動センター)
| (1) | 現地調査の結果、金光教平和活動センターの現地法人は、地域に根ざした開発協力活動の経験の長いスタッフを採用し事業を行ってきた。プロジェクトの資金管理はスタッフが銀行送金する等して確実に行っているとのことであった。また、事業の運営方針についても明確で、例えば、「事業補助金の対象である3つの地域では、全面的な事業支援を行い、残りの地域では、資金援助程度の支援を行い、情報収集の手段とする」というものであった。 |
| (2) | イギリスのボランティア派遣制度を利用する等、他の援助スキームの利用に積極的であり、資金調達力等はあると判断される。現地事務所では、英語と日本語のニュースレターを用意しており、社会へのPRにも積極的な様子がうかがわれた。 |
| (3) | 対象事業地域における他の住民組織、NGOや保健所の行う医療活動に、金光教の受益住民が参加できるように取り計らう等、地域の中での連携や協力に積極的である。 |
| (4) | 在比日本大使館のNGOとの意見交換会にも参加しており、国際協力に関する提言活動に積極的である。 |
(日本フィリピンボランティア協会)
| (1) | 現地法人があるが、日本人の専門家は着任して1年以内であり、どれだけ開発専門家としての経験が蓄積されているかは定かでない。しかし、ローカルスタッフは数年に亘り活動しており、プロジェクト運営力は蓄積されている。 |
| (2) | 資金調達力は日本フィリピンボランティア協会の潤沢な資金力に依存しており、特に現地法人自らが資金調達力の向上のための努力をしてないようであった。しかし、日本フィリピンボランティア協会はNGO事業補助金以外の活動も行っており、2002年6月に、国際大学を開設したばかりであり、現地での知名度は高い様子が伺われた。 |
| (3) | 日系人会の支援を通じて地域社会とのつながりを進めており、直接的な地域とのかかわりを積極的に行ってはいない。 |
| (4) | 日本とフィリピンの交流中で活動を行っていくことを目的としており、開発協力事業のための提言は特にしていない。 |
以上の4つの事例では、補助金の交付を受けたNGOは、現地開発協力事業のカウンターパートの組織能力・財務能力も向上させ、事業の改善が行われていることが判明した。従って、目的(2)「本邦NGOの組織能力を強化する」は、現地の事業において現地のカウンターパートの能力や事業が向上する形で具現している。
4-3-3 まとめ
4-3-1で、補助金交付先の事業を事例に、目的(1)「被援助国に対して国家レベルでは対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする」の達成度については、4つの項目に分けて検証した。その結果、4つの項目、すなわち、「草の根レベルでの成果が出ているか?」「地域住民のニーズにかなった事業であったか?」「地域住民の参加が得られ、自立発展性があったか」「女性の裨益効果があったか?」について、達成されていることが確認された。
ただし、「地域住民のニーズにかなった事業であったか」と、「地域住民の参加が得られ、自立発展性があったか」については、達成の度合いについて、NGOの事業により差異が見られた。従って、事業の審査に当たり、事業の成果を高めるために、この2項目について審査で重点を置くことが重要であろう。
4-3-2では、目的(2)「本邦NGOの組織能力を強化する」も、調査対象NGOの約半数がNGO事業補助金の利用にあたり達成されたと認識しており、さらに、フィリピンの具体的事業においてもカウンターパートの能力やNGO事業の強化が行われており、本邦NGOの組織能力の強化が達成されていたことが確認された。
9 対象4団体は、(1)(特非)金光教平和活動センター、(2)(社)銀鈴会、(3)(特非)地球ボランティア協会(GVS)、(4)(特非)日本フィリピンボランティア協会。4団体中、銀鈴会を除く3団体は、1997年から継続して事業を行っていたため、評価の際は複数年にまたがる事業についても1事業として取り扱った。
10 対象範囲をフィリピン保健分野における開発協力事業(1997~2001年度)とし、その条件をもとに絞込みを行った結果、次ぎの9団体が調査対象として候補に上った。その9団体は、(1)(特非)金光教平和活動センター、(2)(社)銀鈴会、(3)(特非)国際ボランティアセンター山形(IVY)、(4)(特非)ICA文化事業協会、(5)(特非)地球ボランティア協会(GVS)、(6)(特非)日本フィリピンボランティア協会、(7)(特非)AMDA(アジア医師連絡協議会)、(8)神奈川海外ボランティア歯科医療団(KADVO)、(9)南太平洋に歯科医療を育てる会、であった。
11 4事業とは前述の(特非)金光教平和活動センター、(社)銀鈴会、(特非)地球ボランティア協会(GVS)、(特非)日本フィリピンボランティア協会によるプロジェクトである
12 NGO事業補助金制度は、2003年度を以って終了予定であるが、その後の資金源としては、アンケート調査によると、5団体が日本NGO支援無償資金協力の利用を検討していた。また、補助金等が受けられない場合は、事業縮小や、自己資金での継続といった選択に迫られているのが実情である。

