4-2 NGO事業補助金のプロセスの評価
NGO事業補助金制度のプロセスの概要は第3章で述べたように、(1)申請手続き、(2)書類審査と採択の通知、(3)完了報告書、補助金の支払い、(4)プロセス全体を通じての関連する情報公開から成り、それぞれの手続きの概要は以下の通りであるが、ここではこれらのプロセスについて評価を行う。
| (1) | 申請手続きに関連して、募集要領にA.応募要件、B.補助金交付の条件、C.申請書類、が定められている。
主なA.応募要件は、「我が国のNGOで自ら人員を派遣して、ODA対象国である途上国で開発協力事業を行っている団体であること」、「対象事業の種類は11種類に分かれており、農漁村開発、人材育成、女性自立、保健衛生、医療、地域産業向上、生活環境改善、地域総合振興など」、「対象事業の要件として、単年度事業であること」、「常時連絡可能な責任者がいること」等である。 主なB.補助金交付の条件は、「同一事業への支援は原則3年まで、合理的理由があるときは5年まで」、「補助金の補助率及び交付上限額は2分の1以下、1事業1,000万円まで、1団体としては5,000万円まで」、「補助対象経費の費用項目も多様で、特に、人件費、渡航費、事業管理費を認めている」である。 主な、C. 申請書類は、所定の申請書、事業計画明細書、見積書、案件概要などの事業に関する書類と、団体概要、団体設立趣意書、定款、寄付行為、規則等、過去2年間の事業及び収支報告書、役員名簿等の団体に関する書類である。 |
| (2) | 書類審査と採択通知が行われる。審査に当たり、開発協力事業の適性と団体の適性が考慮される。 |
| (3) | 事業実施後は完了報告を提出し、補助金金額の確定後、支払いが行われる。 |
| (4) | 申請・採択状況の情報公開、事業完了報告書の公開。 |
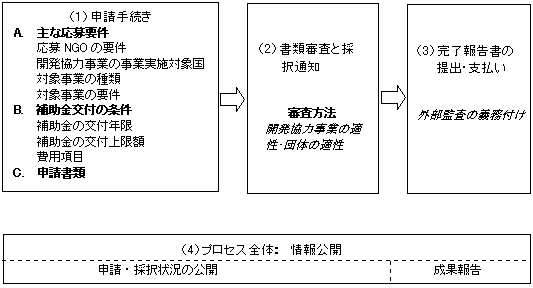
4-2-1 プロセスの適切性
(1)申請手続き、(2)書類審査と採択の通知、(3)完了報告書、補助金の支払い、(4)プロセス全体を通じての関連する情報公開、の各手続きの適切性について、本制度の各手続きと本制度の目的、我が国の上位概念(ODA大綱、ODA中期政策)、我が国の法・規則との整合性という評価基準に基づき、評価を行った。
(1)申請手続き
A. 主な応募要件
(A-1 応募NGOの要件)
|
第一に、応募要件(1)では、「本邦内に実態的に住所を有する」を挙げ、応募要件(2)で「自ら人員を現地に派遣して供与対象事業を実施すること」を掲げている。これは、本制度が我が国のNGOを対象として、我が国の人員が事業を実施することを挙げており、これは、目的(2)の「本邦NGOの組織能力の強化」と関連性があり適切である。
第二に、応募要件(3)(4)は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の適用に基づき団体の開発協力事業の実施能力を問うものであり、過去に開発協力事業として「100万円以上で過去2ヵ年以上に亘り自ら人員を派遣して」の開発協力事業の業務経験を課している。100万円の金額設定については、NGO事業補助金が、NGOの開発協力事業を支援するもので、開発協力事業への補助金額は50万円以上で、その補助金の総事業費に占める割合は2分の1以下であることに鑑み妥当であろう。
(A-2 開発事業の事業実施対象国)
| 原則として、(1)世銀ガイドラインによるIDA(国際開発協会)適格の所得水準の開発途上国であること(平成14年度においては、2000年の国民一人当たりのGNPが、1,445ドル以下の国)、(2)本補助金事業を実施した場合に援助効果が期待される開発途上国であること。 |
(A-3 対象事業の種類)
補助金の交付対象となる事業は以下のとおりです(詳細は別紙「事業区分及び対象経費一覧」(P11~P12)を参照して下さい)。なお、事業区分1~11までを総称して「開発協力事業」と呼びます。
|
開発協力事業として、事業区分1~11までの幅広い種類が用意されており、多様な開発事業を可能にしており現地側のきめ細かなニーズに対応することができると考えられ、目的(1)「きめこまかな援助を可能にする」と関連性があり、妥当な設定であろう。
(A-4 対象事業の要件)
|
「自ら人員を現地に派遣して実施・遂行する事業」であることとし、現地住民・団体に対し資金助成、物資輸送のみを行う事業は対象とならないことを規定している。さらに、現地体制につき、「少なくとも、現地に常時連絡可能な責任者がいること(現地カウンターパートでも可)。」「経験あるスタッフ・専門家が現地に赴き、事業目的に照らし合理的な期間滞在し本補助金の交付対象事業区分に該当する事業活動を行うこと。」ということを挙げている。これらは、自ら活動を行う団体を対象とすることを示しており、目的(2)「本邦NGOの組織能力を強化する」に関連性がある。
「単年度事業であること」は、補助金制度が国の補助金であり財政法等の制限、つまり、「国の補助金、負担金等は、当該年度に実施される事業をその対象事業として、その年度において交付決定をし、またその支出も年度で行われるのが原則である。」2を受けるので、現在の枠組みの中では、妥当であろう。
以上のように、これらの応募要件は、ODAの上位概念、法・規則に整合し、あるいは、本事業の目的に関連しており、適切であるといえよう。
B. 補助金交付の条件
(B-1 補助金の交付年限)
| 同一事業への支援は原則3年までとし、合理的理由が認められる場合に限り最大5年までとします。ただし4年目以降も支援する場合には、前年の補助金交付実績を下回る場合もあります。 |
「同一事業への支援は原則3年までとし、合理的理由が認められる場合に限り最大5年まで」としている。これは、NGO事業は通常3~5年のプロジェクトとして、立案を行っていることから、NGOプロジェクトの実態に合わせ多様なケースに対応するための設定であり、目的(1)「きめ細かい援助を行う」に整合しているといえ、妥当な設定であろう。また、本規定は、本補助金が基本的に単年度事業への支援を行っているが、事実上、継続して交付を受けられる可能性を残している意味で、NGO事業の多様性・柔軟性に対応でき、目的(1)を達成させるため整合していると言え、妥当であろう。
(B-2 補助金の交付上限額と補助率)
| 本補助金の1件当たりの供与額は、総事業費の原則2分の1以下かつ事業区分ごとに補助金交付要綱において定める補助対象経費の範囲内で外務省が決定する金額であり、平成14年度は原則として50万円以上1,000万円以下(但し、(11)事業促進支援制度は500万円以下)とします。 なお、1団体が複数の事業について申請を行う場合、1団体が交付を受けることができる補助金総額の上限は5,000万円であるのでご注意願います。 |
補助金総額の1事業に対する上限を1,000万円としていることは、小規模の事業に対する援助を規定するものであり、目的(1)「被援助国に対して国家レベルの協力では困難なきめ細かな援助を可能にする」に整合しており、妥当である。また、現在の日本のNGOの財政規模が40%の団体が2,000万円以下と言われている3こと、および補助金は総事業費の2分の1までを供与できることを鑑みると、NGOの財政規模を圧迫しない程度の補助額と考えられ妥当であろう。また、一団体が受けられる上限を5,000万円に制限していることに関しては、別添4のとおり2000年度の実績では、3千万以上交付を受けた団体は3団体、1千万円以上は14団体であり、現在大きな制約要因となってはいないが、特定のNGOへの偏りを少なくするように配慮されていると言え妥当であろう。
本補助金の1件当たりの「補助率」は、「補助金交付額の総事業費に対する割合を2分の1以下と、上限を設けている。一般的に、国の補助金の場合、補助率を数値で規定する法律はないが、その対象となる事務、事業に関する経費の全額が支給されることは、補助金の性質上考えられていない4。本規定は、事業補助金交付先NGOに対して補助金額に関わらず、事業費全部をNGO事業補助金に依存するのでなく、一律に財政力があることを義務付けているものであり、目的(2)に整合しており妥当な設定であろう。
(B-3 費用項目)
| 補助金の交付対象となる経費は各事業区分につき別紙(P11~P12)のとおりです。 |
「補助対象経費の費用項目」は様々な費用項目が用意されている。草の根無償資金協力は、資機材、設備及び役務(技術及び輸送など)を調達するために必要な経費を出しているが、これに加えて、NGO事業補助金は、人件費、渡航費、事業管理費等のソフト関連経費を補助している。具体的には、草の根無償では支払わないが、栄養改善を試みる団体には給食費を、保健事業の場合には薬の購入費を、医師派遣事業を行うNGOには、渡航費や宿泊費を交付する等、柔軟に対応している。これは、目的(1)に整合し、妥当といえよう。
以上のように、補助金交付の条件は、目的(1)「きめ細かな援助を可能にする」、目的(2)「本邦NGOの組織能力を強化する」に整合しており、適切であろう。
C. 申請書類
|
申請に当っては、事業の概要説明のために、所定の申請書、事業計画明細書、見積書、案件概要が義務付けられている。これは、事業計画が目的(1)に合致しているかどうか確認するものと考えられ、妥当であろう。特に見積書については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」でも、補助金等の交付の申請の項で、「補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え…(略)」とあるように、法律でも経費の申請が義務付けられており妥当である。
また、団体の説明のために、団体概要などの書類に加えて、添付書類として団体設立趣意書、定款、寄付行為、規則等、過去2年間の事業及び収支報告書、役員名簿等の書類の提出が義務付けられている。これらは、補助金交付対象としての団体の適性、そして開発事業の実施能力を見るための書類であり妥当なものと思料される。
以上のように、申請書書類は、目的(1)「きめ細かな援助を可能にする」や関連する法律に合致しており、妥当であろう。
しかしながら、申請書のフォーマットは、基本的考え方を反映したフォーマットには必ずしもなっていなかった。例えば、案件概要(2)では、「住民、現地政府・自治体、その他関係機関等からの要望状況・内容」、「今回の申請事業の継続予定年数、現地住民・団体等への引継ぎ予定」「事業の年間スケジュール」を記載が定められている。しかし、目的(1)の4つの審査基準、例えば、「草の根レベルの事業としての特徴」や、「計画、実施における住民参加」、「女性の裨益」等を記載する項目が無く、必ずしも審査の考え方を反映するようなフォーマットになっていなかった。この点、妥当性は低いと考えられる。
また、案件概要(1)では、「目的」「内容」を記載する様式になっているが、プロジェクトの「成果」に関する説明を求めていない。そもそも、補助金事業は補助金金額の確定に当たり、「成果の報告を受け、その成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を決定し、5」とあり、成果の確認は補助金額の決定に当たり、重要なものである。しかしながら、現在の案件概要(1)の様式の中には「期待する成果」を記載するフォーマットとはなっていない。プロジェクト計画時に「期待する成果」がきちんと把握され認識されていなければ、当然のことながら事業完了時において、計画時と比べて「期待される成果」がどれだけ達成されたのかをはかることは困難となろう。従って、同法に照らし合わせた場合、案件概要(1)は様式についての妥当性が低いと思われる。
参考までに、実際に提出された申請書は、各団体の担当者によって記載内容の充実度に相違が見られ、案件概要(2)については、審査の基準をどの記載により判断したのか不明である申請書や、案件概要(1)についても「目的」「内容」の記述が数行であり、また事業の「目標とする成果」が明確でない申請書が多く見られた。
第二に、団体の審査基準としては、以下の項目を総合的に審査し交付対象事業を決定する。「(1)団体として事業遂行・組織管理能力(団体の実績、財政規模、職員数等を含む)、(2)事業内容、(3)経費積算、(4)従事する要員、(5)総合的評価、とある。前年度の完了実績報告書や事業の内容等、本補助金を受けて実施した過去の事業内容や事務処理状況等も、翌年度以降の補助金審査の参考とする」、としている。これは、補助金の適正支出を確保するためのものであり、妥当であろう。
以上のことより、申請に際し事業と団体に関する審査基準は、妥当なものであったといえるが、申請書の様式については、4つの基準を反映するのに十分でなく、また、補助金事業としての「成果」の確認を報告時に行うのに適した申請書のフォーマットになっておらず、様式の妥当性が低いという結果になった。
(2)書類審査と採択の通知
(審査方法)
| 補助金交付の審査は以下のような基本的な考え方、方法等により行われます。
|
まず外務省民間援助支援室が、NGOから提出される申請書を審査した後、在外公館の担当者に、対象地域のニーズ、計画の妥当性、NGOの現場での評判などを照会し、総合的に判断している。審査に当っては開発事業の適性と団体の適性の2つを基に審査しており、それぞれ以下のような審査基準を設けている。
第一に、開発協力事業の審査に際しての、基本的な考え方として4点を挙げているが、一つ一つ妥当性を検討する。
(A)「 政府レベルでは対応が困難な草の根レベルの事業であり、」については、目的(1)「国家レベルでは対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする。」に整合しており、妥当である。後半部については、ODA大綱の基本理念と整合しており、妥当である。
(B)「地域社会のニーズ」の把握については、ODAがNGOとの連携を行うに当ってのNGOの利点として、ODA白書(2001年度)「NGO等市民社会による援助活動は、多様化する途上国の開発ニーズにきめ細かく応えることができ」とあるように(第4章参考参照)、NGOが地域ニーズを把握した上で計画していることを確認するもので、目的(1)を達成するために妥当である。
(C)「地域住民の自助努力」「住民参加」は、ODA大綱の基本理念の中で、政府開発援助の目的として、「開発途上国の離陸へ向けての自助努力を支援することを基本とし」とあり、それに整合し、妥当である。
(D)「女性にも裨益」することは、ODA大綱の「政府開発援助の効果的実施のための方策」の中でも「開発への女性の積極的参加及び開発からの女性の受益の確保について十分配慮する」とあり、これに整合し妥当である。
以上のように、これら4つの基準は、補助金の目的(1)「被援助国に対して国家レベルの協力では困難なきめ細かな援助を可能にする」や、ODA大綱に合致し適切である。
(3)完了報告書、補助金の支払い
(完了報告書と補助金交付)
| 当補助金は精算払いであり、事業終了後、完了報告書の提出を受け、その内容・金額等が適正であると認められる場合に限り交付されます。 |
本手続きは、事業完了後に事業完了報告書の提出を義務付けているものである。完了報告書の様式は、次の報告を行うとしている。「1.補助事業の名称、2.補助金の交付決定額およびその精算額(別紙のとおり)、3.補助事業の実施機関、4.補助事業の成果(「備考」として、「必要に応じ図面等を添付してその将来を明らかにすること」)」。現状では会計報告についての様式は別添として細かく定められているが、その他は自由記述となっている。
この評価であるが、完了報告書の様式で、会計報告を重視している点に関しては、会計報告は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づいて補助金額の確定のために行われる手続きであり、また、これに基づき支払いが行われるため妥当であろう。一方、同法律では、補助金事業の成果が外務省によって承認された事業内容や計画、補助金事業の条件や目的等と照らし合わせて、適合するものであるかどうかを確認した上で、補助金額の確定を行うことと定められている 6。しかしながら、補助金事業の成果について、現在は各NGO団体の任意な様式による報告になっており、具体的な事業成果の報告を行うための形式を詳しく定めていない。補助金の成果を明確にする報告書を求めていない点、妥当性が低いと考えられる。
参考までに、実際に提出される報告書は、団体によって内容の深さに違いが見られる。全体的な活動報告のみで個別事業の成果が明らかでないもの、今後の活動の見通し等について書かれていないもの、当初期待された成果に対してどの程度の達成度があったのか等の明確な記述が無いもの、つまり目的(1)、(2)の達成度を報告する内容となっていないものが、大半であった。このため、より成果の記入を容易にするために、現在の様式では、応募要領の中でも、「活動報告」と「成果」の言葉の定義が明らかでないが、これを明確にする必要がある。さらに、成果の記述に当っては、NGO事業の性質として、「ハード中心の政府開発援助(ODA)事業の場合は、執行や実施機関が当初の計画通りだったかという‘定量的’な評価が中心であるのに対して、NGOが行う事業の場合は、どちらかというと人づくりや意識化といったソフト中心であることから、それを適正に評価するには独自の‘定性的’な評価基準を作る必要がある」7といわれるように、定量的・定性的な両面からの報告も行うのが望ましい。
以上のように、報告書の様式として、会計面では、法律に整合し詳細であり適切性がある。しかし、成果の報告という面では、様式面が不十分と判断された。
さらに、事業の成果を測るためにも、モニタリング・評価は重要な役割を果たしていると考えられるが、現在の手続きの中には盛り込まれていない。
現在は、外務省の民間援助支援室より1名と外部有識者1~2名により、年に2回対象各1カ国、プロジェクト数で言うと各3~4件を視察している。また、その視察調査報告書は外部有識者が執筆し、受入団体には渡しているが内部報告書の扱いである。また、現地大使館でも、モニタリング・評価の責務を負っておらず、草の根無償資金協力等のNGO担当者によって任意に行われているだけである。しかし、プロジェクトの申請で掲げた成果や目標や達成度合を確認し、成果を確保するためにモニタリング・評価を行うことは必要と考えられる。なぜなら、国の補助金であり会計検査院制法の適用も受け適正に使われる義務があり、さらに報告書だけでは判らない経費や実際の事業実施実情を外務省が確認するよい機会となる。ODA中期政策の中でも「実施・運用上の留意点」の中で、モニタリングの項を設け、「事業進捗のモニタリングを充実し、事業実施中に起こる問題に対して各援助形態を活用しその連携を計りつつ所期の成果が上がるように対処する。」とあるように、モニタリングの導入は、上位概念にも整合しており、より妥当性が高まるであろう。また、事後評価も、近年ODA改革の一環として評価の比重が高まっており、プロジェクトの効果的・効率的運営を進めるためにも、評価の需要は高まっているといえよう。「ODA改革・15の具体策」の中では評価対象等については明確に規定されていないものの、第三者評価を盛り込む等の評価方法の充実が提言されており、より上位概念との妥当性が高まるであろう。
| (参考) AusAIDのPACAPの場合は、3ヶ月に一度、担当者がプロジェクトを視察し、NGOとの密なコミュニケーションを図り、事業の柔軟な実施を可能にしていた。 |
| (参考) 郵政事業庁の国際ボランティア貯金は、NGO活動推進センター(JANIC)に委託して、評価調査を行っている8。評価調査委託に当たり、郵政事業庁は、対象地域、分野、規模などのバランスに考慮しつつ、全体の15%-20%にあたる数のプロジェクト(91年度は28件、94年度は38件)を評価対象としてピックアップしている。 |
(外部監査の実施)
| 補助金事業の適正な会計処理を確保するため、補助対象事業(開発協力事業部分)の全案件に、原則として現地の監査法人等による外部(会計)監査を義務付けます。 |
「外部監査の実施」についても、平成13年度までは1千万円以上の案件であったが、平成14年から全案件の「原則として現地の監査法人等による外部(会計)監査」が募集要領で義務付けられたが、外部監査については、「第二次ODA改革懇談会報告書(2000年3月)でも、透明性の確保のために、「入札手続については抜き打ち監査を含む第3者による徹底した監査システムを導入する」とあり、外部監査について述べられている。また、最近では、平成14年7月9日に「ODA改革・15の具体策について」との外務大臣の発表の中でも、「経済協力の各スキーム(有償資金協力、無償資金協力、技術協力)の全てについて、外部監査を拡充」するとされているように重視されてきており、本規定はそれに対応するもので、妥当であろう。また、現状は、外部監査に関する費用は総事業の5~10%までとして、補助対象費項目として、認められている。
(4)プロセス全般
(情報公開)
| 従来より補助金を交付した案件については、翌年度において団体名、事業区分及び交付金額を外務省ホームページ及びパンフレットに掲載しておりますが、平成14年度からは、より透明性を高めるために、以下のとおり、更なる情報公開を推進します。
|
平成14年度からのNGO事業補助金の募集では、より透明性を高めるために、例えば、申請締め切り時における申請状況の公開、補助金交付決定段階における案件概要の公開等の申請時、採択時の情報公開をすすめ、また、事業完了報告書のNGOのホームページによる公開を推進している。これは、ODA中期政策の「実施・運用上の留意点」の中で、「プロジェクトの入札プロセスに関する情報、個々の案件に関する関連情報の一層の公開に努める」に対応しており妥当であろう。
しかし、事業結果の報告について、完了報告書をNGOがホームページで公開することを義務付けているが、これは外務省の情報公開とは言えず、不十分であろう。外務省側にも情報を電子データで蓄積していく必要性は大きい。関連して、電子データで情報を蓄積することにより、事業担当者以外の者が、事業毎の年度を亘る情報閲覧を行うことが可能となり、事務の効率化・透明性の向上にも繋がるであろう。
| (参考) 国際ボランティア貯金では、ホームページでの広報に加え、助成金配分先のNGOによるNGO活動報告会を実施したり、ボランティア情報誌(With Your Love)を郵便局で配布し、NGO活動の紹介をしたり、助成金配分先NGOを公表したりしている。 |
4-2-2 プロセスの効率性について
ここでは、時間的、コスト的に無駄がなかったかという点で効率性を検討する。
第一に、NGO側のコストを見てみる。申請書類の作成に要する作業量については、所用日数は団体によりばらつきが見られ、4~5日(金光教平和活動センター)から、1ヶ月くらい(AMDA)であったが、概ね妥当な作業であるとの意見を得ている。完了報告書の作成日数についてもばらつきが見られ、1週間から1ヶ月と様々であった。調査対象となった9団体のうち殆んどのNGOは補助金の交付を受けるに当たり、ふさわしい手続き面での作業を行っていると感じているようであった。
ただし、一点要望があったのは、毎年申請している団体は、毎年申請書類を作成することになり、省略を検討して欲しいとのことであった。これについては、もし3年等の継続案件として補助金事業を交付しているのであれば、省略も可能だが、NGO事業補助金は単年度事業に対する交付であり、同一事業として次年度も交付されることもあるが、次年度の交付を保証するものではなく、提出書類の省略は難しいであろう。
第二に外務省側のコストである。NGOから提出される申請書について、NGOの担当者によって質的にばらつきがあると見ている。外務省側へのインタビューによると、申請書の審査にかける労力については、補助金の対象費目等に関しての書き直しや、不備があることが多く、両者にとって手続きが一度で完了しないという意味で、作業に無駄が在ると思われる。外務省の要望として、領収書等について、細かくきちんと整理して提出して欲しいとのことであった。作業費目の分かりやすい説明、NGO担当者の学習が必要であろう。しかし、プロセス自体は、歴史的には申請書に見積書をつける等、複雑化してきた経緯があるが、一方で、外部監査を実施している団体は、現地の領収書はオリジナルでなくコピーでよしとする等の、簡略化の動きも同時に行われており、制度の変化に伴い柔軟に対応してきている点は評価できよう。
総じて、国の補助金事業という枠組みと募集要領で定めたスケジュールの下で、時間的にも、コスト的にも効率的に行われていた。しかし、書類の不備、書き直しという点で多少の無駄も見られたので、より効率的な実施のためには、NGO側の事務能力の強化が必要であろう。
4-2-3 プロセス評価のまとめ
以上のように、一連のプロセスすなわち、(1)申請手続き、(2)書類審査と採択の通知、(3)完了報告書、補助金の支払い、(4)プロセス全体を通じての関連する情報の公開は、我が国の補助金制度という枠組みに従い、目的(1)「国家レベルの協力では対応が難しいきめこまかな援助を行う」、目的(2)「我が国のNGOの組織能力を強化する」に整合しており、適切であった。しかし一方で、手続き的にも形式的にも補助金金額の確定に重点が置かれ、活動の成果については申請書においても、報告書においても、不十分な様式であると判断された。成果の面についても申請から報告に当たり、一貫して確認するための様式設定が必要であろう。
効率性に関しては、国の補助金事業の枠組みと募集要領で定めたスケジュールの下で、時間的にも、コスト的にも効率的に行われていた。しかし、書類の不備、書き直しという点で多少の無駄も見られたので、より効率的な実施のためには、NGO側の事務能力の強化が必要であろう。
2 加藤剛一他(1996年)
3 JANIC(2002年)
4 加藤剛一他(1996年)
5 補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律。
6 補助金等に係わる予算の執行の適正化に関する法律第十五条(補助金等の額の確定)によれば、「各省各庁の長は、補助金事業等の完了又は廃止に係る補助金事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助金事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助金事業者等に通知しなければならない。」とある。
7 アーユス(1995年)
8 アーユス (1995年)

