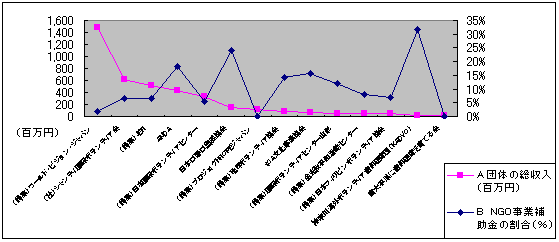| 第3章 参考 NGO事業補助金制度の特徴 |
(参考-1)NGO事業補助金の我が国の他の類似ODA制度との比較
目的(1)「きめ細かな援助」を目的に掲げている制度との比較
目的(1)「被援助国に対して、国家レベルの協力では対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする。」について他の類似ODAスキームの目的の比較を行うこととする。
前提として、NGO事業補助金制度の政府開発援助における位置づけを確認する。ODA白書によると、政府開発援助は、大きくは「贈与」及び「借款等(開発投融資、円借款及び海外投融資)」の2つに分類され、「贈与」はさらに「二国間贈与」及び「国際機関への拠出金」へと分けられる。NGO事業補助金は「二国間贈与」の中の、「技術協力」の一つとして位置づけられている。
|
||||||||||||||
我が国ODAの中でNGOへの支援や連携・協力を謳っているスキームのうち、NGO事業補助金制度以外の主要なものは以下が挙げられる。
| □ | 草の根無償資金協力(草の根無償):
草の根無償の基本理念は、「開発における現地住民の自発的、自立的活動を支援することを目的とした無償資金協力の一形態」である。一般プロジェクト無償の供与額が一件数億円以上といわれるのに対して、一件当たりの供与額が原則上限1,000万円(最大供与限度額5,000万円)であり、少額である。また、一般プロジェクト無償は援助先が中央政府であるが、草の根無償はNGO、地方政府、教育・医療機関である。(NGO事業補助金との比較、別添2参照) |
| □ | JICAの草の根技術協力事業及び開発福祉支援事業:
草の根技術協力事業とは、JICAによる従来の小規模開発パートナー事業及び開発パートナー事業を引き継いだかたちで2002年より創設された制度である(同年9月より応募開始)。草の根技術協力事業及び開発福祉支援事業は技術協力の中でも、きめ細かな援助を狙ったものである。以下の表3-2は小規模開発パートナー事業、開発パートナー事業、開発福祉支援事業の概要を示したものである。 |
| 事業名 | 特徴 |
| 小規模開発パートナー事業 | (1) 日本のNGO、大学、地方自治体等からのアイディア募集→多彩且つ草の根レベルに届く国際協力の実施。
(2) JICAと団体間での委託契約に基づくプロジェクトの実施。(互いのノウハウと経験の融合) 事業規模:団体の経験に照らして適正な事業予算規模 |
| 開発パートナー事業 | (1) 同上⇒一層多くの団体からの参加を求めている。
(2) 同上 事業規模:100万円以上、数百万円(1,000万円未満) |
| 開発福祉支援事業 | 途上国のローカルNGOにプロジェクトの実施を委託するもの。「我が国の社会開発福祉分野での経験を踏まえつつ、福祉向上を中心に草の根レベルで貧困問題に対処すること」を目的としている。そして、当該事業では「住民が直接益するようなプロジェクトを、住民の参加を得て実施」し、「資機材や施設の供与よりも、社会的弱者や貧困層住民が自立いて生活していくために必要な技能の訓練や組織化の支援に重点」を置いている。 |
| □ | 郵政事業庁の国際ボランティア貯金によるNGOへの助成金配分制度10:
預金者からの郵便貯金の通常利子の数十%11の寄付金を我が国のNGOに配分し、開発途上国の地域の住民の福祉向上に役立てるための制度である12。目的は、「住民の福祉向上」である。具体的な助成対象事業は、「開発途上国地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助事業」と緊急援助事業「海外において、天災その他非常の災害が発生した際に、その災害を受けた地域の住民の緊急を満たすための援助」の2つを支援しており、前者についてはNGO事業補助金制度と類似性がある。助成事業の数の多さからも、NGOの側からも、政府補助金としては利用し易い制度として、NGO事業補助金制度と並んで、利用されている。 |
| □ | 円借款:
「開発途上国政府等に対して、低利で長期の緩やかな条件で開発資金を貸付けるものであり、それぞれの国が発展していくためには、その土台としての経済・社会基盤の整備が欠かせないため、必要な資金を援助し、これらの国々が経済的に自立するための自助努力を支援すること」13を目的としている。従って、きめ細かな援助を第一義的に掲げた制度ではない。ただし、最近では、国際協力銀行(JBIC)はNGOと連携した小規模インフラ事業や、マイクロファイナンスを行い、草の根レベルへ直接支援が行き渡るような取り組みを行っている。 |
上記の各スキームを比較すると、日本のNGOを対象にしたものは、小規模開発パートナー事業、開発パートナー事業であるが、これらは、委託契約に基づくプロジェクトを実施するもので、NGO事業補助金制度とは性格的に違いがあることがわかる。
目的(2)「NGOの組織基盤を強化する」を有する制度について
上記制度の中で、日本のNGOを対象とする制度は、草の根無償資金協力と、開発パートナー事業、小規模開発パートナー事業であったが、これらにつき、目的(2)を有しているかどうか検討する。
| □ | 草の根無償資金協力は「開発途上国での多様な開発援助活動を支援対象としていて、直接的に我が国の国内NGO支援を目的とした制度ではありません。」14とある。 |
| □ | 開発パートナー事業、小規模開発パートナー事業については、NGOへの委託事業であり、直接にNGOの強化育成、支援を目指したものではない。 |
従って、きめ細かい援助を可能にすることに加え、NGOの財政基盤・組織基盤の育成を第一義的に意図している制度は他には存在しなかった。NGO事業補助金制度は、政府開発援助において独自の役割を果たしていた。
(参考-2) NGO事業補助金のNGOの利用度
(1)NGO事業補助金のNGOの財政基盤に占めるシェア
NGOの財源としては、自己財源(寄附金、会費、事業収入)と民間財団からの助成金、政府からの補助金や委託金等がある。平成12年度の平均では、自己財源は59%、政府からの補助金や委託金は10.1%(うち、国際ボランティア貯金の配分金151.7%)、民間財団の助成金5.4 %、国連委託金3.2%、その他22.3%(うち前年度からの繰越金16.6%)となっている16。NGO事業補助金の交付先団体の財政規模に対する割合については、NGO事業補助金受け取りの多い7団体と今回の調査対象NGO9団体については下図の通り(詳細は別添7)で、平成12年度では、2%から24%まで様々であった。一つの特徴として、海外で無料歯科医療診療を行う団体がNGO事業補助金への依存度が24%、30%と高いことがうかがえる。これは、NGO事業補助金が、人件費、渡航費等を補助対象としていることと関連があろう。
| NGO事業 補助金 受け取り 金額の 順位 |
団体名 | (A) 団体の総収入 (百万円) |
(B) NGO事業補助金 の割合(%) |
| 4 | (特非)ワールド・ビジョン・ジャパン | 1,488 | 2% |
| 1 | (社)シャンティ国際ボランティア会 | 621 | 6% |
| 6 | (特非)JEN | 517 | 6% |
| 3 | AMDA | 442 | 18% |
| 7 | (特非)日本国際ボランティアセンター | 336 | 6% |
| 2 | 日本口唇口蓋裂協会 | 146 | 24% |
| 5 | (特非)プロジェクトHOPEジャパン | 110 | 政府補助金 15.8% |
| 10 | (特非)地球ボランティア協会 | 90 | 14% |
| 13 | ICA文化事業協会 | 67 | 16% |
| 43 | (特非)国際ボランティアセンター山形 | 58 | 12% |
| 41 | (特非)金光教平和活動センター | 48 | 8% |
| 58 | (特非)日本フィリピンボランティア協会 | 43 | 7% |
| 11 | 神奈川海外ボランティア歯科医療団(KADVO) | 24 | 32% |
| 37 | 南太平洋に歯科医療を育てる会 | 14 | n.a. |
| 76 | (社)銀鈴会 | - | - |
(注)上記はNGO事業補助金受け取り金額の多い団体のうち上位7団体と、フィリピン保健事業の9団体(今回の調査対象の9団体)。
| 図3-6:平成12年度における団体の総収入とNGO事業補助金交付額の割合
|
| (出所)JANIC「国際協力NGOダイレクトリー2002」をもとに作成。 |
(2)NGOにとってのNGO事業補助金制度の利点と制度への要望
現地調査(4団体)やアンケート調査(質問票2)(送付9団体、7団体から回答有り)をする中で、NGOの捉えるNGO事業補助金制度の特徴が明らかになったので、参考として付す。また、今回の調査では、他ドナーの現地事務所を訪問し、現地事務所の行うローカルNGO支援策によるNGO事業を訪問し、NGO支援策について考察を得た。本国のNGOを対象とするNGO事業補助金とは異なり、単純に比較は行うことが出来なかったが、NGO支援の今後の方向性を検討する上で参考とした。
(本制度の利点)
| □ | 対象事業の事業区分が多様であり、利用しやすい。特に、事業区分10地域総合振興事業は、NGOのきめ細かいニーズに対応するための柔軟な事業を行うことが出来NGOから評価が高い。また、事業区分11事業促進支援事業(プロジェクト企画調査支援、プロジェクト評価支援)が、2001年度から設定されたことからも、NGO事業補助金の手続きの設定が極めて柔軟にNGO側のニーズに対応している。 |
| □ | NPO法人格が応募要件でなく、また、50万円という小規模の資金から利用可能である。 |
| (参考) Aus AIDの応募NGOの要件:
PACAP(Philippines-Australia Community Assistant Program: ローカルNGO支援プログラム) はNGOやPOの登録制度は採用していない。対象NGOの要件として、フィリピン政府機関、例えば、証券取引委員会、労働雇用省、農業省、社会福祉省、協同組合開発庁に登録を行っていること、団体名での銀行口座を持っていること、プロジェクトを効率的効果的に実施する能力を持っていること、正確な財務諸表および補足レポートを提出することができることが、要求されている。 (注)PACAPとはフィリピンの貧困層や社会的弱者の生活水準向上のためのNGOプロジェクトを支援するプログラムである。1999年からPACAPでは保健分野のプロジェクトを支援開始した。スキームの概要であるが、グラントの資金供与を行い、技術支援やモニタリングのアドバイスを、行うものである。 |
(本制度への要望)
| □ | 補助対象費用項目として、日本のNGO本部の管理費、運営費は現在補助対象ではないが、補助対象として欲しい。これに対して、外務省は、本部経費をまかなえない程、財政基盤の脆弱なNGOには補助をしないとの方針である。参考として、草の根無償資金協力、郵政事業庁の国際ボランティア貯金でも本部経費を見ていない。しかし、日本NGO無償資金協力では、本部プロジェクト実施経費等のプロジェクト実施期間に限定した一部ソフト経費も供与可能としている。 |
| □ | 単年度事業であるが、複数年にして欲しいとの要望もある。 |
| (参考) AusAID
PACAP(Philippines-Australia Community Assistant Program)は、1~3年のプロジェクトに対して支援を行う。具体的には、1年目で成果を出すことができれば、2年3年目も資金を提供するという対応をとっている。(コラム2参照)。この背景には組織の未だしっかりしていないNGOでも、育てながら財政的支援・連携を行っていく姿勢が見られた。 |
| (参考) 2002年6月に創設された、日本NGO支援無償資金協力のセクター連携事業においては、数年度に亘る案件で、次年度以降も継続していくことが望ましいと思われる時は、次年度も優先してその案件を採択することとなっている。 |
| □ | 他国に比べて補助の比率の低さ、額の少なさを改善して欲しいというNGOの要望や意見もある。 |
| (参考) USAIDは、いずれのNGO支援スキームでも、25%の自己資金を有していることを義務付けている。金額は、Matching Grant の場合は、1件当たりの、平均供与額が50万5千ドルと多額である。また、子供と母親の健康状態の改善に直接的な効果が期待できる開発事業を支援するChild Survival Grant は、平均供与額は約68万ドルである。また、CIDAは、プロジェクトファシリティーというNGO支援スキームの中で、5万カナダドルから、35万カナダドルの支援を行っている。AusAIDのANCPというNGO支援スキームでは、2000~2001年実績、一件当たり平均1万7千ドルであった(2000年~2001年)。 |
| (参考) 2002年度に創設された日本NGO支援無償資金協力では、原則1,000万円以下だが、最大5,000万円まで可能である。また、2,000万円までは全額供与することになっており、この背景には今後は日本政府は、一定の条件を満たしたNGOに対してより多い額の支援をする方向にあるといえよう。 |
| (参考) 郵政事業庁の国際ボランティア貯金は、申請案内によると、上限金額は設けていない。参考までに、平成13年度の実績の最高額は、団体としてはJEN(3件、2,511.9万円)、事業としてはオイスカ(1,985.4万円)であった。高額が出ているのは、緊急・復興関連が多いようである。 |
| (参考) 郵政事業庁の国際ボランティア貯金の事業への配分率は、継続案件の場合は、前年度配分額の多寡、または、新規申請の場合は団体の経験や規模に応じて、事業における自己資金負担の割合が変わる。まず、継続案件で前年度配分金が200万円未満、また、新規申請でNGO団体が設立後10年未満または会員数が500名未満の場合は、自己資金の助成対象事業に対する割合は10%以上必要、言い換えると助成金は90%まで支払われる。
次に、継続案件でも前年度配分金が200万円以上と大きくなると、または、新規の場合でも団体が設立10年以上を経ており、会員数が500名以上の場合は、自己資金の割合は20%以上必要、言い換えれば助成金は80%まで支払われる、としている。このように、国際ボランティア貯金事業の場合は、NGO団体の規模が大きく、実績が在ればあるほど、自己負担の比率を高めようという試みが見られる。さらに、法人設立の目的が開発途上地域での援助活動の実施になっていないもの、あるいは、募金などによる寄付収入がきわめて高額で、資金調達能力が顕著な団体は、自己資金の割合が助成対象事業に対して30%以上必要、というように、体力のある団体、純粋な開発事業を行う団体でないと見なされる場合は、自己資金の割合を30%にするとしている。 また、国際ボランティア貯金の場合は、NGO事業補助金に比べて事業への助成率は、70%から90%と高く、NGOにとっては、プロジェクトの多くの資金配分を受けられる制度となっている。 |
| □ | 精算払いは、財政的に体力のないNGOは一定の期間資金負担をせざるを得ず、利用しにくい。 |
| □ | 採択通知が8月中というのは、NGO側にとっては、その年の事業計画が立てづらい。 |
| (参考) 郵政事業庁のボランティア貯金は、事業の年度は6月~翌年7月までであり、3月に申請を受け付け、6月に交付団体の決定、7月に配分金の交付となっている。配分金は活動計画に基づいて、年に2回、または3回配分される。事業報告書は、8月末提出である。また、報告書に基づき、配分金額の確定作業を行い、返却請求の確定が行われるが、完了報告書提出から1年程度後に確定が行われ、資金の返却の可能性もかなり高いという。 |
10 郵政事業庁の国際ボランティア貯金事業の実績額は、平成13年度は、6億6,646万4千円、全国172のNGO 193事業に対して助成金が配分された。平成14年度は、3億4,102万8千円。全国137のNGOが実施する150事業を対象に配分されたといい、平成13年度については、NGO事業補助金制度と同規模であった。
11 100%~20%の間で貯金者が自由に選択する。
12 貯金者の利子によるので税金による政府開発援助とは性質を異にするが、郵政事業庁が管轄する。配分金の配分先の決定については、各団体からの申請を受けて、外務省を始めとする各関係省庁の意見を基に原案を作成し、郵政審議会で決定する。(対外経済協力審議会 第13期第8回 議事次第:平成9年12月18日)
13 JBICホームページ
14 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/seisaku_4/shien/kusanone.html
15 同年、郵政事業庁の国際ボランティア貯金の配分を受けた団体は84団体に上る。
16 JANIC「国際協力NGOダイレクトリー」2002年