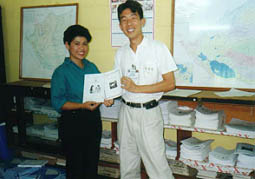6.1 社会開発・貧困対策
第3章で述べたように、我が国の対「ニ」国援助は無償資金協力を中心に行われてきた。無償資金協力において社会開発・貧困対策分野は重要な位置付けにあり、援助実績額全体の19.5%を占める。ここでは教育、保健医療、貧困対策の3重点セクターに分けて評価を行うこととする。
(1) 現状と課題
「ニ」国教育制度は、初等教育(6年間)と中等教育(5年間)が教育省の管轄下に、これ以外の高等教育は大学と技術系学校に分かれ、それぞれ自治委員会、国立技術機関(INATEC)の管理下にある。教育省によれば、2001年の教育施設は就学前教育施設5,306校、初等学校6,506校、中等学校891校、教員養成学校8校、技術系学校313校、大学31校、技術研究機関2機関、特殊教育校28校がある。全学生数は、1997年には約124.5万人で、その人数構成は、就学前教育10.7%、初等教育62.5%、中等教育20.6%、教員養成0.5%、技術教育0.9%、高等教育4.6%、特殊教育0.2%であった。これ以外に約6万人が成人教育を受けた。
教育省の予算は1997年から1999年の3年間において常に国家全体予算の10%を占めており、1999年度予算は82.5億円相当である。教育省予算に占める初等教育予算の割合は60%前後であり、1999年度予算は49億円である。かかる予算の中で初等教育人件費は4割以上を占めているが、教員の給与は極めて安く、教員の質を保持できないことが問題となっている。また教育省以外に、緊急社会投資基金(FISE)1及び社会補足基金(FSS)2が教育セクターで活動している。FISEは大統領府直属で、貧困層を対象として教育、医療分野に重点を置き、学校建設などを実施している。SSFは各援助国や国際機関による融資を財源とし、国家予算で賄い切れない部分を補充している。
識字率はサンディニスタ時代に推進された運動により88%に達していたが、内戦時代に一時悪化した。民主政権になって初等教育の拡充が図られた結果、全国レベルの識字率は上昇傾向に転向した(表6.1.1-1)。他方、教育省によれば地方レベルでの非識字率は1993年には39%、1998年には30%、さらに非識字率は40%にのぼるとの報告があり、地域格差が問題とされている。
| 表6.1.1-1 識字率の推移 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| (出典)El Desarrollo Humano en Nicaragua 2000(UNDP) |
純就学率は3歳から6歳の児童では40.4%、7歳から12歳では85%、13歳から16歳では46.7%であるが、中途退学率は初等学校で29%、中等学校で48%、高等教育で37%といずれも高い。特に初等教育の純就学率は、全国平均で73.1%(1998年)、85%(2000年)と改善されているが、貧困及び極貧層の平均就学年数はそれぞれ貧困層では3.1年(男子学生3年、女子学生3.2年)、極貧層では2.3年(男子生徒2.2年、女子生徒2.3年)と短く、教育セクターにおける重要な課題とされる。
高い中途退学率の原因として、施設の老朽化とハリケーン・ミッチの影響から、学校施設以外で授業をする学校があるほか、机や椅子などの基礎備品が不足して、適切に整備された教育施設が不足していることを教育省は挙げている。また、教材不足、不適切なカリキュラム内容、教員の質の低さ等ソフト面での問題も原因と考えられている。しかしながら、学校に行かない児童10人のうち4人は経済的理由によるものであるとの報告もあり3、今後は貧困層への教育へのアクセスの改善に取り組むことが政府としての重要な課題となっている。
(2)教育セクター政策
民主化以降、政府は社会・経済の再建を目的とした経済調整政策においてインフラの再建、教育・社会福祉の拡充を主要課題とし、その具体的目標に教育制度の改革、農業の振興、生産基盤の再建、小規模工業の振興、元軍人・国外からの帰還者の社会生活への復帰を掲げた。これを受けて、教育省は1994年に1994年から2000年の計画を策定し、以下の主要目標に設定している。
| 1) | 初等教育の第1学年から第4学年を中心に就学率、進級率を向上させる |
| 2) | カリキュラム内容および教育活動を通して、モラル、社会、民主主義、文化、市民生活、環境保護についての価値観を育成する |
| 3) | 教育の地方分権化を進める |
| 4) | 制度的能力と効率を向上させる |
| 5) | 国際機関から供与される資金、人的資源、資材を教育システムのために確保する |
| 6) | 教育事業の範囲を維持し、全教育プログラムの質を改善すること |
教育省は、2001年に2001~2015年の教育国家計画を新たに策定し、1)教育機会の拡大と教育機会の均等化、2)教育の質の改善と地域社会に適合した教育内容の強化、3)発明、科学、技術の強化、4)教員の労働条件の改善、5)教育の地方分権化などを、教育分野の政策における中心的課題として掲げている。
(3)我が国支援の評価
我が国の援助方針においては、社会開発・貧困対策分野が重点分野に据えられているが、具体的なセクター、サブ・セクター、目標値などは設定されていない。一般的に社会開発・貧困対策分野において初等教育の果たす役割は特に大きいと考えられ、我が国の援助も初等教育中心に実施されてきている。
1990年から2000年までの援助実績額によると、社会開発・貧困対策分野の援助実績額74.22億円の28.4%(21.11億円4)が教育・文化センターに投入された。その援助の内容は、一般無償資金協力により行われた第1次及び2次初等学校建設計画、文部省に対する印刷機材供与のほか、草の根無償資金協力による学校建設、図書館建設・整備などのプロジェクト支援である。
なかでも初等教育整備は当セクター援助供与額の大部分をしめる。初等学校建設計画は第1次、第2次にわたって実施されており、第1次では9.24億円、第2次では30.14億円の供与が予定され、第1次で37校を建設し、第2次では74校が建設される(このうち、2002年1月現在91校の建設が終了している)。また、一般プロジェクト無償以外にも、草の根無償資金協力で小学校のインフラ整備に関わる案件21件(US0.66百万ドル)を支援しており、無償資金協力による小学校インフラ整備総額は40億円近い。
| 表6.1.1-2 草の根無償案件数の内訳(1994~2000年) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| (出典)在ニカラグァ日本大使館 |
また、インフラ整備以外にも教育プログラム支援、国語副読本作成などの草の根無償援助が実施されているほか、2000年から2001年の実績では海外青年協力隊65名中9名が教育分野(うち3名が初等教育)に派遣されている。
しかしながら、他セクターと比較すると当セクターへの技術協力は協力隊員24人(全派遣の11.0%)、専門家は教育省には一切派遣されておらず、その実績は少ない。
前述のとおり、教育省では初等教育の重要性、特に初等学校の1年から4年の就学率及び進学率を上げることが中心的課題と見なしており、また国家の財政不足から教育省への予算が十分ではないため、教育省予算の大半は教員給与を含む人件費に割かれ、施設維持管理費及び新たな施設に投資することが難しい状況にあった。よって、教育セクターの現状と政策及び我が国の援助方針から判断すると、我が国援助が初等教育援助を重視して実施されてきたことは妥当であったと判断される。
我が国の教育セクターにおける援助効果としては、第一に初等教育建設計画による対象地域の教育普及が挙げられる。第1次初等教育建設計画はグラナダ県、カラソ県、マサヤ県において、校舎の老朽化、教室の不足などにより充分な教育が行われていない既存初等学校を対象に、1996年から1998年にかけて37校、177教室、32管理室、32便所等の施設整備(総面積14,240平方メートル)を整備したものである。本計画は目標として1)初等教育の普及範囲の拡大、2)退学、留年者の減少、3)教育の質的向上、4)生徒の学習能力向上、5)識字率の向上を掲げていた。
対象となった学校では1教室当たりの平均生徒数は60人弱と多く、同国の基準生徒数40人を大幅に上回り、多くの学校で2部授業が行われている現状にあることが確認された。視察した3校の校長によれば、退学者数の減少、進学率の向上も認められるという。
また、生徒数増加率は全国平均9.7%であるのに対し、37校中22校では14.6%の増加率を示す。人口増加率2.6%5を考慮しても14.6%の児童数増加は、純就学率の増加もしくは学区以外からの生徒の受入れによるものと考えられる。実際、視察した3校では校区以外の生徒も受入れていた。
一方、37校中11校では生徒が減少している。この原因として、粗就学率の低下(学齢期外の生徒数の減少)、過疎化もしくは少子化による児童の絶対数の減少等が考えられるが、各学校の事情を確認することはできなかった。
学校関係者(教師陣)及び教育省関係者によれば、きれいな学校、机とイスのある学校は親が「子どもを学校に行かせる」動機に繋がっているとのコメントがあった。以前は、雨漏りしコケが生えている教室で、机とイスが足りず床に座って勉強をするような学校があったことが受益者インタビュー6でも明らかにされており、こういった学校では特に生徒の集中力の低下が顕著だった他、親が「学校に行っても勉強できる環境にない」といった理由で、子どもを通学させないケースもあったとされる。
中途退学者数と留年者数においては27校のデータのみでの分析となった。生徒数は1995年から2000年に7%増加しているのに対し、中途退学者数は37%、留年者数は87%に減少している。27校の生徒数増加に対し、中途退学者数・留年者数が大幅に減少したことは、施設建設以外にも要因はあろうが、我が国初等学校建設の総合的な効果と考えられる。
さらに、建設された37校のうち8校では校名が日本に関わる名前に変更され、地域住民から感謝されている。また、各施設はハリケーン時や地震の時に避難場所として利用され、高い評価を受けている。また、教員研修が行われたり、地域住民の集会、大統領選挙の投票所などに利用され、地域住民の公的活動の場として活用されている。
かかる状況から、教育セクターにおける我が国の援助効果は、教育へのアクセスの改善に留まらず、教育の質の向上、教員・生徒・保護者の教育に対する意識向上、学校を中心とする地域住民の活動を可能とし、自助努力への契機となったと評価される。
事例(1):初等学校建設計画
教育省の予算が少ないため、上記学校では各家庭から2~5コルドバ 程度を集め、ガラス破損などに対する修繕費などの費用等を当てていた他、1校では教師の管理下でジュース等を販売し、費用を捻出していた。視察した3校では生徒に対し施設の使い方の指導がされており、校舎は清掃され良好な状態にあった。受益者インタビューでは、学校建設後の全体的な成績向上、生徒・教師・保護者などが一体となったよりよい学校造りへの努力等が明らかになった。同様に96%の受益者より「学校建設が満足のいくものであった」との回答を得ており、教師陣の再訓練が行われ教育の質が向上したこと、ハード面で適切な教育環境が整備されたこと、衛生的な配慮が日常的に行われるようになったこと、教育教材の新規利用等がその理由であった。 |
事例(2):草の根無償資金協力「商業職業訓練学校コンピューター機材整備計画」
同学校では機材供与以前、パソコン不足の他、そのリース費用が予算を圧迫していた。教育インフラ不足は教育水準の低下、生徒数の減少、学校経営の悪化等をもたらした。機材供与後、援助資産に対する減価償却手続の採用により、次期購入資金を内部留保でき循環的援助効果が発現された。プログラムを更新、コンピューター・コピー機等も新規購入された。また、同校情報学科では1994年に比し2001年には49%生徒数が増加した。特記すべき点は、経済及びシステム・エンジニアの隊員により技術協力が行われている点であり、マニュアル本の作成・販売を通じて学校運営が改善されている。本案件は資金協力と技術協力の相乗効果が見られ、特に成功を収めている。 |
(4)教訓と提言
教育分野では、初等教育施設整備中心に援助が実施されてきた。これは内戦での施設破壊に続いて自然災害による影響もあり、施設整備への必要性も要望も強かったことが背景にある。この状況は現在も続いており、教育省の財源不足と教育への需要の拡大などから、今後も教育施設整備は重要な課題であり、援助の必要性が認められる。現在FISEなどを通じて多くのドナーが初等教育施設整備への資金協力を続けており、SGPRS実現の為にも、我が国からの更なる支援が望まれるところであろう。他ドナーとの連携などを考慮して、具体的な戦略や目標値を打ち立て、支援を継続することが望まれる。
また、いくつかの援助スキーム(例えば技術協力と資金協力)を組み合わせて援助の有機的連携を図り相乗的な援助効果をあげ、教育の質的向上へ貢献することも望まれる。例えば、第1次、2次初等学校建設で対象となった6県の教育省地方事務所などに人材を派遣し、教員研修計画の策定、実施などを行えば、援助の相乗効果が期待できるほか、教育省が推進中の地方分権化にも貢献することになる。さらに、校長の能力によって教育の質の向上のみならず学校経営にも違いが確認されたことから、校長や教員を対象に学校経営のノウハウに関わる研修を行うことも、開発の持続性を高める効果が期待できる。有機的連携の実施にあたっては、技術協力の拡大を検討すべきであろう(現状では、個別に派遣される青年海外協力隊が中心であり、それ以外の技術協力はほとんど行われていない)。
今後の技術協力の可能性としては、開発調査のスキームを利用して他ドナーとの協調関係を構築しながら我が国の初等教育分野の協力案件を形成・実施することが考えられる。初等教育における開発調査の例は少ないが、現在ヴィエトナム国で実施されているセクタープログラム開発調査のように、研修事業を通し教育行政の計画・実施能力を高めることも一案である。あるいは、専門家を中央に配置し、地方事務所に協力隊員を派遣することにより、中央と地方の連携を図ることも一案と考えられる。教育の地方分権化が促進される中では、中央と教育現場の双方へ連携した支援が行われることがより効果的であろう。
(1) 現状と課題
「ニ」国はかつてプライマリー・ヘルス・ケアを推進し、住民の基礎保健指標を改善させWHO保健機構から賞賛された経験を持つ。その後内戦を経験し、健康水準は著しく低下した。現在、人口構成は年少人口の割合が高い開発途上国型を示している(表6.1.2-1)。また、その疾病構造は先進国型に変わり始めたばかりである(表6.1.2-2)。健康水準は中米7カ国と比較して最悪の値を示してはいないが(表6.1.2-3)、地域格差と貧困が深刻化する中で、国民の健康問題は懸念事項であり、健康水準の向上は今後も継続的に取り組むべき課題とされる。
| 表6.1.2-1 「二」国年齢別人口比(1998年) | ||||||
|
||||||
| 注)計算の都合上、100%にならない
(出典)Encuesta Nicaraguense de Demografia y Salud 1998 |
| 表6.1.2-2 疾病による死亡原因(1998年) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| (出典)保健省 |
| 表6.1.2-3 中米7カ国における一般的保健指標の比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *WHO、1997年データ
(出典)UNICEF(2001)The State of the World’s Children |
保健医療分野における中心的課題は、脆弱な保健行政にある。財政面での不足と組織・制度的な脆弱さである。国家予算における保健省への配分はわずか5.3%(1999年)を占めるに過ぎず、その主な財源は一般税収と援助機関からの資金であり、その割合は3:2となっている。
1995年以降、当分野においても地方分権化が推進され、地方保健行政は県区分と同じ行政地区の地域総合保健サービス(Sistemas Locales de Atencion Integral a la Salud:SILAIS)が担当することになった。しかし、地方分権化はまだまだ部分的なものであり、特に予算面でSILAISは中央政府に依存している。
SILAIS管轄下の医療機関としては、一次レベルの保健センター(Centro de Salud)及び保健センター支所(Puesto de Salud)、二次レベルの病院がある(表6.1.2-4 地域別公共保健医療施設数の内訳)。理論的には、一次医療機関は基礎的な診療と予防サービスを提供し、二次医療は一次医療施設から紹介された患者の診療にあたる。実際には、末端の一次医療機関に当る保健センター支所では医療従事者と医薬品の不足から十分な医療サービスが提供されておらず、地域住民の末端医療施設に対する信頼度は低い。よって、保健センター支所を介さずに直接保健センターあるいは二次医療機関である病院へ診察を受けに行く患者が多く、基礎的な診療しか必要としていないにも係らず患者が高次医療施設を利用するという事態をもたらしている。結果として、高次医療施設の本来の業務に支障をきたし、さらに公的医療機関における診療費が無料であることから、高次医療施設の財政逼迫の一因にも繋がっている。
| 表6.1.2-4 地区別保健医療施設数の内訳 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| (出典)保健省(2000) Memoria de la Cooperacion Externa en Salud 1997-1999 |
上記の問題に加えて、一次医療機関と二次医療機関はSILAIS管理下であるにも拘らず、双方の連携は弱く、協力・協調体制は確立されていない。地域医療の向上のためには、一次・二次レベル間で管理者及び実務レベルのコミュニケーションを図り、地域特有の問題とその背景を両レベルの視点で分析し、それを医療の現場で活用していくことが重要と考えられる。
(2)保健医療セクター政策
10年にわたる内戦中に充分な公共投資を行うことができず、社会基盤の多くは老朽化が進み、国民の生活水準は悪化していた。民主政権に代わり、医療サービスの向上・強化による国民生活の向上を目標に、1993年に保健医療セクターの政策が策定された。その内容は以下の8項目であり、保健省は国際機関・各国ドナーからの援助に頼って実施してきている。
1) 医療サービスの質の向上
2) 地方分権化の推進
3) プライマリー・ヘルス・ケア(PHC)の展開・発展
4) 第二次医療施設の強化
5) 保健省の能力向上
6) 法律による責任の明確化
7) 管理方式の近代化
8) 財務体質の改善、社会参加への推進
その後、1997年に保健省は「国家保健政策1997-2002」を新たに策定し、各ドナーからの援助を積極的に受け入れている。主な政策内容は以下のとおりである。
- 1) 保健セクターの近代化
- 保健省、民間セクターの役割の明確化をするとともに、法的枠組みを完成させる
- 2) 保健省の強化
- 各レベルの役割と機能の明確化、地方分権化の促進、財政の見直しと確保、適正な人材配置と再訓練、医薬品確保、情報システムの確立、計画立案や運営管理の改善、住民参加などを重要事項として掲げる
- 3) 病院機能の強化
- 自治病院(独立採算性)の促進、サービスの質の向上、施設設備の改善、一次医療機関との連携強化、病院運営強化、情報公開、救急医療ステムの確立を目指す
- 4) 公衆衛生の新戦略
- 予防医療強化、予防医療と治療の統合化、一次医療サービス強化、感染症のコントロールなどにより、社会的弱者への医療サービスの拡充を目指す
- 5) 社会保障の改革
- 社会保険制度の拡大、医療従事者のリスクの保障、年金制度を検討し、社会保障制度の拡充と住民への普及を目標とする
さらに1998年には、より具体的な計画である「保健セクター近代化プログラム1998-2002」を策定し、世銀の支援によって実施している。世銀は1998年9月から4年間で、プライマリー・ヘルス・ケア、病院機能の近代化、保健省強化、社会保障システムの近代化、プロジェクト・マネージメントなどへ24百万ドルの資金援助を約束している7。
(3)我が国支援の評価
一般的に、保健医療分野は基礎生活(BHN)を満たすための重要な一分野と位置付けられており、我が国の重点分野である社会開発・貧困対策においても当分野に対する援助の必要性について指摘されている。
1990年以降、我が国が初めて実施した一般プロジェクト無償協力は「医療機材整備計画」(1991-1992年)であった。その後2000年までに、「グラナダ病院建設計画」、「児童保健強化計画(一次、二次)」の3案件が実施されており、社会開発・貧困対策分野における支援の56.6%(41.99億円)を占める。また、同分野へは1995~2001年の7年間に草の根無償案件で23件のプロジェクトを支援している(総額でUS1.21百万ドル)。その内容は医療従事機関への機材供与を中心に、衛生環境整備、リプロダクティブ・ヘルス支援、プライマリー・ヘルス・ケアなど多岐にわたる支援である。また、保健医療セクターに含まれていないが、広義の意味での公衆衛生に係る水供給やゴミ処理に係るプロジェクトなども実施されている。草の根無償資金協力で実施された保健衛生分野の支援は次表に示すとおりである。
| 表6.1.2-5 草の根無償協力保健分野の案件リスト | ||||||||||||
|
||||||||||||
| (出典)在ニカラグァ日本大使館 |
また、技術協力では、1992年以降現在までに協力隊員51人(派遣人数累計の23.4%)、専門家12人(派遣人数累計の15.2%)が派遣されている。また、専門家に関しては、災害救助のための緊急医療チームを含むと、その数は35人にのぼり、専門家派遣人数全体の44.3%を占める。
前述の通り、保健省では保健セクターの近代化、地方分権化を図ることにより保健医療サービスの質・量の向上を目指しており、我が国が行ってきた「医療機材整備計画」「グラナダ病院建設計画」「児童保健強化」の支援は、政府が推進する政策と合致しており、妥当なプログラムであったと判断される。
特記されることは、グラナダ病院建設(現名称:日本ニカラグァ友好病院)による効果である。同病院はグラナダ県周辺のトップレファレル病院として適切な診療機能を備えた病院であり、グラナダ県のみならず周辺県の住民へもトップレベルの医療サービスが提供できるようになったことである。病院のキャパシティの拡大と診療機能の改善によって、同病院の患者数は1.9倍に増加、外科手術は1.6倍にも増している。受益者インタビューでも、90%の病院関係者及び87.5%の患者が「病院建設によって生活が改善した」と答えている。
同病院の財務状況は、検査料など有料サービスによる2000年度の収入がC$2,298,952.82(約US$170,293)に達し、2001年度にはさらに10%程度の収入増を見込んでいる。企業からの寄付を募ったりバザーを開催したりと、財政自立発展性を高めていることも確認できた。また、グラナダ病院の運用・管理能力も高く、運用効果の持続性は高いと評価される。
現在実施中の「グラナダ地域保健強化プロジェクト」(プロ技)は本調査での評価対象ではないが、グラナダSILAISをカウンターパートに、グラナダ県地域保健の強化を通じた住民の健康向上を図っている。本プロジェクトは上述の「グラナダ病院」と連携を取っており、一次医療の質の向上のみならず二次医療の連携といった点からも地域保健のモデル・システムとなりうるものと考えられる。グラナダ病院は、現在一次レベルの医療施設から紹介のない患者を直接診療するケースも多く、レファレルシステムの構築には至っていないことから、同プロジェクトによりグラナダ地域の地域保健の状況が改善されると、二次レベルの病院施設の機能向上、財政負担の軽減へと繋がるものと考えられる。
「医療機材整備計画」及び「児童保健強化計画」は、資機材供与を通じて実施された案件である。それぞれの案件において、資機材は目標どおり調達されており、特に前者は我が国初の無償資金協力であったことから、同案件の実施を通じて我が国との関係がより親密になり、その後の案件に繋がったことも指摘し感謝の意を表明していた。しかし、保健省の財政不足から、供与された医療機材の維持管理が難しい側面も認められ、2001年には医療機材の専門家が派遣されている。
一方、「児童保健強化計画」については、保健省が財源不足であり基礎医薬品の整備さえできない状況にあることから、我が国から供与される医薬品に対する需要は高いことが確認されたほか、ネブライザーやソーラー式冷蔵庫などの供与機材の使用頻度も高いことが確認された。特に、貧困地域に指定される北中部地域では、電気のない地域も多く、以前は医療施設でワクチン保存ができなかったが、我が国の援助により供与されたソーラー式冷蔵庫でのワクチン保存が可能となったため、道路事情が悪い雨季のワクチンの運搬を、別の時期にずらすことが可能になったという。これにより、以前は医療従事者の間で疑問視されていたワクチンの効能について安心できるようになったと評価されている。また、訪問したいくつかの保健センター支所の医療従事者によると、我が国から供与されている医薬品(主に呼吸器系疾患治療)に対する需要は高く、次の供給がある前に薬品が品切れになってしまうことも多々あるとのことである。
事例(3):グラナダ病院建設計画
計画時における本件に対するニカラグァ政府の政策におけるニーズと優先度は高かった。また、評価時点でも病院機能の強化(独立採算性の促進、施設設備の改善、運営強化、一次レベル施設との連携の強化、住民への情報公開、サービスの質の向上、救急サービスの情報整備とその利用)に対するニーズは高く、本事業の妥当性は維持されていた。効果としては、本病院はトップレファラル病院として適切な診療機能を得ることができるようになった。これによりグラナダ県のみならず周辺県から患者が訪れるようになり、波及効果も確認された。 |
事例(4):児童保健強化計画
計画時における本件に対するニカラグァ政府の政策におけるニーズと優先度は高かった。また、一般無償案件としての採択も妥当であった。評価時点でも急性呼吸器系疾患及び急性下痢症は乳児及び5才未満児死亡率、罹患率の上位であり、基本的な医薬品整備、ワクチン及びコールドチェーン体制の整備及び呼吸器性疾患治療用のネブライザーに対するニーズは高く、本事業の妥当性は維持されている。当初計画予定の医療機材・医薬品は全て調達され、成果(アウトプット)目標は達成された。また、日本による呼吸器疾患のための医薬品は特に使用頻度が高く、インパクトも大きいことが確認された。 |
(4)教訓と提言
(教訓)
1991年から現在までの援助実績を見ると、保健衛生セクターでの支援は病院機能強化と地域保健の強化を主体に行われてきたと理解される。それぞれの実施をとおして得られた教訓は以下の2点に集約できよう。
- 1) 病院強化
- 医療機材の供与及び病院建設は、二次医療の質を向上させる需要が高かったことが背景にあったと理解される。しかし、慢性的な財政不足が短期的に解消される見込みは少なく、供与された機材の維持管理費の捻出が困難な状況にあり、問題のひとつとなっている。現在、世銀により保健セクター近代化計画が推進されているものの、逼迫する財政の中では各病院経営が独自採算性を取る体制を確立するまでに至っていない。自立化に向けての方策を考える必要があったと思料される。
- 2) 地域保健強化
- 医薬品・栄養材料などの供給体制は整備されており、供給過程でのロスも少ないとの評価を受けているにも係らず、末端レベルでの医薬品不足は深刻である。これは財源不足と需要予測の仕方に問題があるとされる。我が国の医薬品供与など一次医療強化に繋がる援助は、地方の医療従事者に特に高く評価されており、今後も需要の高い援助分野と考えられるが適宜、需要予測の見直しを十分に行い、医薬品が末端レベルに行き渡るよう供与することが望まれる。
(提言)
これまでの支援・現状及び政策目標を踏まえて、保健衛生分野での協力では以下の3点を提言する。
- 1) フォローアップ
- 保健省の財源不足のため医療機材及び病院施設の維持管理が難しいことは指摘したとおりである。各病院が独立採算性を確立するまでは、フォローアップとしての援助が必要とされよう。技術協力による医療機材の管理実施者への技術移転や、破損機材の部品購入費の捻出方法など、病院経営へのアドバイスも有効な支援と考えられる。
- 2) 地域保健強化
- 現状では末端の一次医療の質を改善するには及ばず、住民の健康向上のための新しいプロジェクトを実施することも難しい。かかる状況から、一次医療従事者の質の向上と地域住民の参加を通じて健康向上に直接寄与する地域保健強化は有効な手段であり、これまでも多くの地域保健プロジェクトが各国ドナー、NGOなどにより実施されている。今後は、グラナダ県の病院と地域保健プロジェクトをモデルとして、他地域への展開も考えていくことが望ましい。地域保健強化においては、一次医療従事者の再訓練が重要な課題であり、技術移転はOJTを行いながら可能であることから、例えば保健省配属の協力隊員に数ヶ月ごとに各地で活動してもらうなどの試みることも考えられる。また、地域住民の参加によるプライマリー・ヘルス・ケア概念の推進は、地域医療に欠かせない要素である。よって、地域で活動する栄養士や村落開発普及員などの協力隊員との連携により、プロジェクトを展開させることも検討に値しよう。
- 3) プログラム・アプローチ
- 保健衛生分野における上位目標と具体的戦略を示した日本のプログラム・アプローチは策定されていない。そのため、我が国援助がモデル医療機関の改善を目指すのか、あるいは地域住民を直接裨益対象として健康向上を目指しているのか明確ではない。政府の政策が行政面での改革を中心に地域医療向上への波及効果を狙うものであることから、我が国支援の焦点をどのサブ・セクターに絞るのかを示すことが望ましい。そのためにはまず、政策対話をもとにした同セクターの具体的な援助戦略の策定、各国援助機関との協調、それに基づく技術・資金協力の計画策定が求められていると思料される。
(1) 現状と課題
第2章2.2の社会情勢で述べたように、国民全人口の47.9%が所得貧困及び所得極貧困層に属する8。貧困及び極貧困層は都市部(30.5%)より農村部(68.5%)に多く、地理的には北中部地域から大西洋岸地域に多く分布する(貧困地図参照)。地域別貧困層の割合は全体的には減少傾向にあるものの、極貧層においては太平洋岸都市部及び大西洋岸の都市部・農村部で増加傾向にあり、貧困層においては全国的に都市部でも増加しており、必ずしも貧困が改善されていないことが確認できる(表6.1.3-1)。特に深刻なのは大西洋岸地域での貧困層及び極貧層の増加であり、極貧層の割合は都市部では17.0%、農村部では41.4%にものぼる。
| 表6.1.3-1 地域別貧困率の推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)JICA/国際協力総合研修所(2001)貧困削減に関する基礎研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貧困・極貧困層が抱える問題点の一つとして、公共サービスへのアクセスの悪さがあげられる。貧困層の65.4%は農村住民であり、54.2%はインフラの発達していない中部地域あるいは大西洋岸側に居住しており(表6.1.3-2)、地理的条件から公共サービスへのアクセスが難しい。
| 表6.1.3-2 貧困人口の地域別内訳 | ||||||||||
| 単位:% | ||||||||||
|
||||||||||
| (出典)ニカラグァ政府Perfil y Caracteristicas de los Pobres en Nicaragua(2001) |
同様に、基礎生活(BHN)に係る公共施設へのアクセスも悪い(表6-1-3-2)。学校あるいは保健センターに行くのに、非貧困層より貧困・極貧層は長い時間を費やす。また、1993年に行われた生活水準家計調査9によれば、病気になった際に非貧困層は91.5%が疾病への処置を取るのに対し、貧困層では55.5%、極貧層では35.7%のみが何らかの処置を取る。このように公共サービスへのアクセスの問題は、地理的な問題のみならず、経済的な背景が影響している。
| 表6.1.3-3 貧困レベルと社会開発指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)ニカラグァ政府Perfil y Caracteristicas de los Pobres en Nicaragua(2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つまり、貧困レベルと社会開発指標には密接な関係があり、図6.1.3-1に示すような貧困の悪循環を生み出していることが想定できる。例えば、乳幼児栄養不良の割合は貧困の度合いが強まるほど栄養不良児の割合は高まっており10、公共サービスへのアクセスの問題とも重なって、健康状態が悪化し社会的脆弱性を拡大する。あるいは経済・地理的な理由から就学機会を失い、文盲であるため雇用の選択及び機会が制限される。従って社会的脆弱性(人間貧困)を拡大し所得貧困から抜け出すことができないといった図式である。
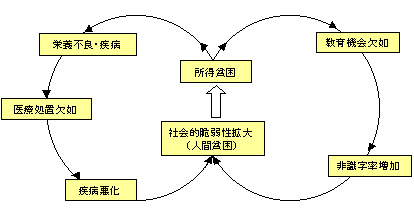 |
| 図6.1.3-1 貧困の悪循環の例 |
(2)貧困対策政策
第2章2.3で既に述べたように、1990年内戦終結を機に発足したチャモロ政権は、経済再建を目的にマクロ経済に焦点を当て、インフレ抑制と規制緩和・自由化を推進しつつ、構造調整計画を導入した。同政権は1991年には1991-1995年の中期的計画を含む経済プログラムを発表したが、経済構造改革と安定化を進めるに当り、貧困者に過重な負担がかからないよう補完的なプログラムとして緊急社会投資基金FISEを設立した他、失業者のための職業訓練、小企業に対する融資プログラム、医療援助の特別プログラムなどを内容とする社会救済キャンペーンを展開した。その後1996年に発足したアレマン政権は、基本的にチャモロ政権の民主化・自由経済路線を踏襲するとともに公共部門における人員削減、サービス部門の民営化などを推進していた折に、1998年のハリケーン・ミッチに襲われた。その被害は大きく、災害からの復興が重要な課題となり、同政権は国家再建計画を策定するに至った。本計画では1999年から2001年を対象とした社会資本の再建を目指している。
世銀指導下で上記の生活水準家計調査を2度にわたり行い、成長強化・貧困削減戦略(SGPRS)を策定している。これは2001年以降2005年までの基本的政策ラインであり、2015年を最終的な目標達成年としている(詳細は第2章2.5を参照)。これらの計画策定は大統領府主体で推進されており、SGPRSが現段階における国家開発計画に当る。同時に各国ドナーに本計画の実施への協力が呼びかけられている。SGPRSの具体案は以下のとおり。
- 極貧率を17.5%削減する。政府の最優先目標であり、極貧率を2005年までに14.3%、2015年までに9.5%に削減する。
- 初等教育就学率を75%から83.4%に引き上げる。
- 妊産婦死亡率を10万件当たり148人から129人に引き下げる。
- 乳児死亡率を1000人当たり40人から32人に引き下げる。
- 5歳未満の幼児死亡率を1000人当たり50人から37人に引き下げる。
- 15-19歳のパートナーを持つ女性のうち、家族計画への需要が充足されない割合を24.8%までに削減する
- 20‐24歳のパートナーを持つ女性のうち、家族計画への需要が充足されない割合を18%まで削減する
- 持続可能な開発のための国家戦略の実施(持続可能な開発のための国家戦略を2005年までに実施する
(3)我が国援助の評価
社会開発・貧困対策分野における我が国援助の基本方針として「未だ経済発展の素地が整っていない同国においては、経済改革の底支えのため保健・医療、教育、低所得者住宅、農業水産振興分野への協力が重要である」と掲げており、貧困層を対象とする低所得向上、貧困人口が従事する農業水産振興(但し農業インフラ整備関連を除く)が貧困対策への具体的援助案件と考えられる。
1990年以降2000年までに15.12億円が貧困対策分野に投入されている。その援助の内容は、低所得者住宅建設計画(1990、1991、1992年の3期)、生活困窮者支援計画(1994年)、大西洋北部零細漁業開発計画(1994年)である。また、貧困地区を対象あるいは貧困人口・社会的弱者を対象とした1994年以降の草の根無償資金協力では42案件が取り上げられており、総供与額はUS1,485百ドルにのぼる。草の根無償資金協力案件の内訳は、表6.1.3-4に示すとおりである。
| 表6.1.3-4 草の根無償案件の内訳 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| (出典)在ニカラグァ日本大使館 |
さらに技術協力では、専門家は貧困対策に1名、零細漁業関連に3名が派遣されている他、漁業共同組合に1名の協力隊員が派遣されている。また、貧困層が農村地域に集中しており、農村開発が直接貧困対策に繋がることを考慮すると、農業分野への援助も貧困対策の一環と見なすことも可能であり、農業分野の協力は専門家11名(専門家派遣全体人数の13.9%)、協力隊員32名(協力隊派遣全体人数の14.7%)にのぼる。
「ニ」国はかつて貧困及び極貧層を対象とした「貧困対策」への政策策定を行ってこなかった。しかし、貧困に係る調査としては1993年に「生活水準家計調査」が実施されており、地域格差を含む貧困プロファイルは描かれている。我が国の貧困対策分野における援助は、無償資金協力で低所得者を対象にプロジェクトを実施した他、貧困・極貧層の割合が高い大西洋岸地域において実施されており、これらの援助対象は妥当であったと考えられる。しかし、「ニ」国政府においても我が国の援助方針においても「貧困対策」における具体的な戦略と目標値が設定されていなかったことから、より具体的に妥当性を検討することはできない。
貧困対策分野における援助の総合的インパクトは、所得向上を目的とした個別案件の裨益効果以外に、基礎生活(BHN)分野に係るセクターからの波及効果が大きいと考えられる。これは図6.1.3-1に示したように「貧困」には複雑な要素が絡んでおり、「所得向上」と共に教育、保健医療、水供給などの基礎生活の拡充が「貧困対策」としての役割を担うからであり、かかる理由から貧困地区で実施された社会開発案件は、貧困緩和に貢献をしていると考えられる。貧困地区で実施された案件の数と各県の貧困状況に関しては第3章で述べたとおり、一般プロジェクト無償では4件(7.5%)、草の根無償資金協力に関しては32件(19.9%)が人口の8割が極貧とされる6県(リバス、マドリス、ヒノテガ、マタガルパ、ボアコ、リオ・サン・ファン)と1特別区R.A.A.N.において実施されている(詳細は第3章 表3.3-5 案件実施件数と貧困状況を参照)。
当分野における我が国援助のひとつに、大西洋北部零細漁業開発計画により実施された小型漁船供与が挙げられる。水産資源が豊富である「ニ」国にとって水産部門は重要であるが、財政不足により水産資源開発は行われていない。また、本案件の対象地区である大西洋岸地域は水産資源が豊かであるにも係らず、十分に利用されておらず、貧困・極貧層の割合は92%にも及ぶ。既存の資源を利用し、彼らの所得向上に繋がる本件のような援助は各家庭の貧困対策としての効果が大きいだけでなく、地域振興にも繋がる。残念ながら、本案件による所得向上にかかわる定量的なデータは入手できなかったが、実施機関である水産局は供与された44隻の小型漁船に対し漁民から返済金を回収し次の融資への基金を設け、自助努力により持続性を維持していることが確認されている。
事例(5):草の根無償資金協力「エンパルメ・デ・ボアコ児童食堂建設計画」
父母からの寄付(食料と1戸当たり月約10コルドバ)、NGO(世界食料計画、フィールド・チルドレン等)による食料支援により、本件食堂で提供される食料(代)および維持管理費が確保されている。婦人達がボランティアとして持ち回りで料理をし、月曜日から金曜日まで給食を提供している。食料確保の一環として、自家菜園つくりも予定している。本件施設において、現地の大学生やNGOが父母に対して栄養・公衆衛生に関する教育も併せて実施している。児童への給食提供のみでなく、父母への栄養・公衆衛生に関する改善の教育も一貫して実施している。 |
(4)教訓と提言
(教訓)
貧困対策分野における我が国の援助は、所得向上を対象とした支援がここでの評価対象であるが、第6章6-1、6-2で述べた基礎生活の拡充による波及効果も大きい。これらの援助を通じて得られた教訓は以下の3点である。
- 1) 裨益対象人口の限定
- これまでの援助は、ある特定地域を対象として行われたり、低所得者とされるがその全容が明らかではない層に対して行われていた。この理由として、「二」国における貧困プロファイルが未策定であり、対象人口を限定することが難しかったことがあげられる。しかし、貧困のプロファイルが出来上ったので、これを活用すれば今後は貧困・極貧層を直接裨益人口とした案件形成が可能となる。
- 2) 経済的貧困
- これまでの援助は、社会的弱者を対象とした基礎生活分野の拡充に重点を置いてきたといえよう。一方、「二」国の貧困は深刻な問題であるにも係らず、貧困層の経済活動を活性化するための援助は少なかった。今後は地方及び貧困地域を対象とした経済活性化を導くような援助が求められよう。
- 3) 基礎生活分野
- 基礎生活分野における無償資金協力は、高い評価を受けている。これまでの案件の効果が高かったことから、当分野への援助は今後も有効であるといえよう。特に現在「二」国政府の財政状況は悪く、今後も基礎生活分野への投資が難しいことを考慮すると、基礎生活分野への支援は、国民の生活改善のために必要な援助とされよう。
(提言)
得られた教訓をもとに、提言として以下の3点が挙げられる。
- 1) 案件の採択
- 貧困プロファイルが作成され、「貧困対策」の対象となる地域、あるいは層が明らかにされている。よって今後は「貧困対策」に分類される案件の採択に関しては、裨益対象人口がいかなるステータスにあるのかを十分に分析し、案件の妥当性を確認することが必要となろう。また、裨益対象の絞込みといった意味では、一般プロジェクト無償よりもむしろ草の根無償資金協力による支援を行うほうが、より効果的であると考えられる。
- 2) 所得貧困の緩和
- 「ニ」国は農業国であるとともに水産資源に恵まれており、農業・水産業におけるポテンシャルは大きい。また、貧困層の7割近くが農村部に居住していることから、農業・水産業への支援は直接貧困層の所得向上に繋がると考えられる。我が国援助が、農業・水産業への支援を基盤として「二」国の持続的な貧困削減への貢献を目指すならば、技術的・資金の両面で実施することが必要であろう。例えば貧困層を対象に技術協力を実施しながら、マイクロ・クレジットを提供することが考えられる。マイクロ・クレジットは資金回収が難しく、失敗に終わるケースも少なくないが、開発調査を利用して既存の母体で、組織・運営管理が問題なく行われている組合などを選び出した上で、実証調査を行うことは検討に値する。
- 3) 基礎生活分野
- 裨益人口の基礎生活の改善においては、裨益人口へ直接的援助を投入する方が、即時的な効果が得られる。各共同体で住民のニーズに基づいた優先順位を決定し、それにより案件の要請が行われるというのは草の根無償資金協力の概念にも当てはまり、今後は草の根無償資金協力を中心に基礎生活分野に援助することが望まれる。また、草の根無償を束ねて管理するプログラム・マネジメントの方策を打出すことも検討に値しよう。
1 Fondo de Inversion Social de Emergencia, 1991年11月設立。
2 Fondo Social Suplimentario, 1998年
3 第2次初等学校建設計画基本設計調査
4 2000年までの実績額(ODA白書1991-2000年及び国際協力事業団年報2001年度版)より算出。
5 1994-2000年の人口増加率(世界銀行データベース)
6 受益者75人(教師25人、生徒36人、保護者14人)に対して2001年10月に実施、詳細は別添を参照
7 World Bank ホームページ
8 ニカラグァ政府作成のPerfil y Caracteristicas de los Pobres en Nicaragua(2001)による。貧困層は「必要カロリー摂取量を取っている家計の月支出総額」極貧層は「必要カロリー摂取量を取っている家計の月食費総額」を貧困ラインとしている。
9 ニカラグァ政府Encuesta Nacional de Hogares sobre Medicion de Nivel de Vida(1993)
10 都市部非貧困層で14.3%、貧困層で22.0%、極貧困層で34.5%、農村部においては非貧困層で22.1%、貧困層で35.1%、農村部では44.4%