3.3 形態別動向
我が国ODAの形態別援助スキームは、大きく分けて有償資金協力、無償資金協力、技術協力に分けられる。近年のODA形態別援助額においては、有償資金協力を含む政府貸付等は減少傾向にあり、贈与比率(無償資金協力と技術協力を合わせた割合)を高めている(表3.3-1)。しかし、1997年のアジア通貨・金融危機に対するアジア諸国支援を行った結果、1998年以降政府貸付金が全体の4割以上を占めるに至った。
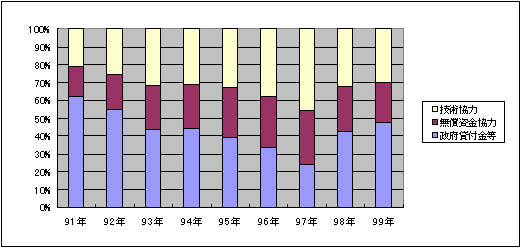 |
| (出典)ODA白書(1991年~2000年)より作成 |
| 図3.3-1 二国間ODA全体における形態別配分の推移 |
対中米7カ国における形態別援助金額は年により増減があるものの、その構成については二国間ODA全体における動向と同様に政府貸付金等は減少傾向にあり、贈与額は増大している(表3.3-2)。1991年から1999年における無償資金協力は平均16.6%の増加率を、技術協力は5.6%の増加率を示している。
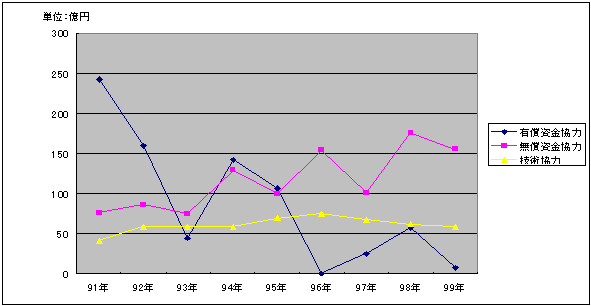 |
| (出典)ODA白書(1991年~2000年)より作成 |
| 図3.3-2 対中米7カ国における形態別援助金額 |
また、中南米への援助の特徴は、図3.3-3に見るように1996年以降無償資金協力のシェアが常に50%を越えていることにある。特に1999年には、前年に起きたハリケーン・ミッチによる災害復興を目的とした援助が実施され、無償資金協力は70%に達している。
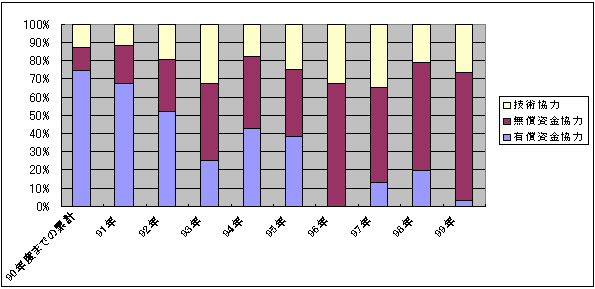 |
| (出典)ODA白書(1991年~2000年)より作成 |
| 図3.3-3 中米7カ国における形態別内訳の推移 |
図3.3-4に示すように、「ニ」国においても贈与比率は高く、1991年から1999年における贈与比率は74.4%である。「ニ」国は重債務貧困国であり、2001年8月にHIPCプログラム申請のための成長強化・貧困削減戦略(GPRS)が正式に承認されている。かかる状況から、1991年以降実施された有償資金協力は、1991年構造調整借款、94年経済復興計画(第二期)に対する円借款、1999年の債務繰延べのみである。
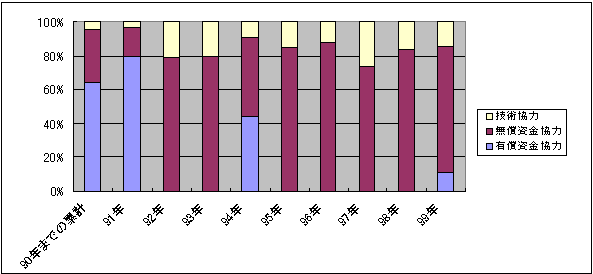 |
| (出典)ODA白書(1991年~2000年)より作成成 |
| 図3.3-4 「ニ」国における形態別推移 |
無償資金協力は、経済的収益性が低い基礎生活分野の拡充を目指すものであり、我が国の対「ニ」国援助方針に重点分野として掲げられた、社会開発・貧困対策、環境分野への援助に向けられている。「ニ」国援助の中心的役割を担うスキームは、一般プロジェクト無償、食糧増産援助、草の根無償、ノンプロジェクト無償、文化無償などである。
1991年から1999年までの対「ニ」国無償資金協力の内訳を見ると、一般プロジェクト無償(水産無償・緊急無償を含む)27案件が実施され、無償資金協力全体の63.51%、220.23億円が供与された。食糧増産援助は1991年以降毎年実施されており、47億円、13.59%にのぼる。草の根無償援助は138件実施され、5.91億円(1.71%)が供与された。ノンプロジェクト無償による供与額は70億円に達し、構成比は20.24%を占める。文化無償は2.64億円であり、0.76%を占める。
「ニ」国における一般無償資金協力は1件当り金額が数億円のプロジェクトが中心であり、草の根無償資金の原則上限1,000万円に比べその供与額は大きく、申請から実施までの期間は草の根無償では数週間から数ヶ月であるのに対し、一般無償では通常2~3年を要する。草の根無償資金協力は地方政府あるいは地域のNGOや学校など地域住民組織が裨益団体となり、地域住民が直接裨益することから、対象を貧困地域に定めるなどの戦略が工夫されている。実際、さまざまな制約から一般プロジェクト無償などの大型案件でカバーしきれない地域の住民への自助努力支援が、草の根無償資金協力により行われている。表3.3-1は各県における草の根無償資金協力と一般プロジェクト無償の実施件数とその構成比、それぞれの県の貧困状況を示したものである。「ニ」国政府作成の貧困地図において人口の8割が極貧とされる6県1地方区では、全国展開のプロジェクトを除いて、それらの県を対象とした無償資金協力案件は全体の7.5%しか行われていないのに対し、草の根無償資金協力では総案件件数の19.9%がこれらの県で実施されたプロジェクトである。
| 表3.3-1 案件実施件数と貧困状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1. (出典)在ニカラグァ日本大使館
*2.(出典)ODA白書及びJICA年報。数県にまたがる案件に関しては、各県ごとに1件としてカウントし、全国規模で展開している案件は全国展開とした。 *3.(出典)ニカラグァ政府作成Mapa de Pobreza Extrema de Nicaragua(2001年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ニ」国における1991年から1999年の人材育成・技術移転に関わる技術協力は、総額78.467億円で、年平均1.18%の増加率を示す。しかし、対「ニ」国援助全体におけるシェアは、1997年に26.7%まで伸びたものの、ODA全体及び中米7カ国の傾向と比べ、平均12.8%とエル・サルバドルに次いで低い割合である(表3.3-2)。
| 表3.3-2 各国ODA供与額における技術協力の割合(1991~1999年累計) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| (出典)外務省・国際協力事業団 |
人数実績においては、表3.3-3に示すとおり、1991年から専門家・協力隊の派遣が始まり、述べ90名の専門家と188名の協力隊員が派遣されているほか、1991年以降の研修員の受け入れ人数も述べ369名にのぼる。しかし、これは1991年から1999年に供与された中米7カ国の技術協力援助額のうち13%、受け入れ研修生総数の14.1%、専門家人数の8.2%、協力隊員数の16.2%を占めるにすぎない。
| 表3.3-3 ニカラグァ国に対する技術協力・人数実績の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)外務省・国際協力事業団 |

