2.3 経済情勢
ニカラグァはラテンアメリカの最貧困の一つであり、一人当たりのGDPはラテンアメリカの平均額の3分の1にすぎない(2001年に493ドル)。所得貧困では国民の約半分(47.9%)、基本的ニーズ水準では国民の72.6%が貧困層に属するという厳しい貧困状況におかれている。しかしながら、図表2.3-1に見るように、ニカラグァは1960年代から1970年代後半にかけて高度成長を遂げていた。一人当たりのGDPは、ピーク時の1977年には1,153ドルと現在の倍以上の水準にあった。だが、この高度成長は、外国貯蓄に依存した投資拡大、国際市場の活況、中米共同市場の拡大という例外的な好条件に恵まれたものであり、さらに成長の果実の大半がソモサ一族に独占されるなど、持続不能なモデルであったと受取られる。
| 表2.3-1 一人当たりの実質GDPの推移(1980年米国ドル換算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *暫定値 (出典)ニカラグァ中央銀行資料より作成 |
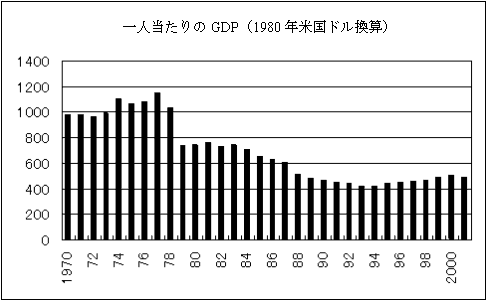 |
| (出典)ニカラグァ中央銀行資料より作成 |
| 図2.3-1 一人当たりの実質GDPの推移 |
ニカラグァ経済は1978年から1990年にかけて戦時経済とも呼びうる危機の時代に突入する。1978から1979年にかけて実質一人当たりのGDPが40%も低下した後、1980から1984年にかけて毎年平均マイナス3%のペースで経済が縮小していった。
革命と内戦に加えて、主要な貿易相手であった米国の経済制裁政策による打撃、サンディニスタ政権の国家主導型経済政策の欠陥と混乱の結果、マクロ経済の不均衡が拡大し、対外債務が肥大化して1980年代後半に破局的状態を迎える。1988から1993年にかけて国民に厳しい痛みを強いるドラスティックな経済安定化政策の導入を余儀なくされた。1994年以降は、経済回復と貧困減少局面を迎えるが、1990年代末に至っても一人当たりGDPは1960年代の半分程度に留まっており、回復への歩みは遅く不安定である(図表2.3-1及び表2.3-2)。
| 表2.3-2 実質GDP成長率 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| *暫定値 (出典)ニカラグァ中央銀行 |
1993年から1998年にかけてのニカラグァの限界資本産出係数(ICOR)は6.3であり、途上国でも高水準に位置する。これは1ポイントの経済成長を達成するために6.3ポイントの投資が必要とされたことを意味する。すなわち、ニカラグァ経済が潜在的に有する回復能力と豊富な未利用国内資源の存在を考慮するならば、回復局面に入ったとは言え、この間の経済成長率の低さには驚くべきものがある。GDP比で34%にも達する外資の流入、さらに同27%もの国内投資という異常に高い投資水準が持続不能なことは指摘するまでもない。投資の低生産性の主因究明と解決が、持続的成長と貧困削減への課題とされる。
高度成長への制約要因として、以下の諸点が指摘される。
| 表2.3-3 マクロ経済不均衡の構図(GDP比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)ニカラグァ中央銀行資料より作成 |
| 表2.3-4 政府財政構造(対GDP比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)ニカラグァ中央銀行資料より作成 |
| 表2.3-5 国際収支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *暫定値 (出典)ニカラグァ中央銀行 |
| 表2.3-6 財政収支と経常収支(対GDP比) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)ニカラグァ中央銀行 |
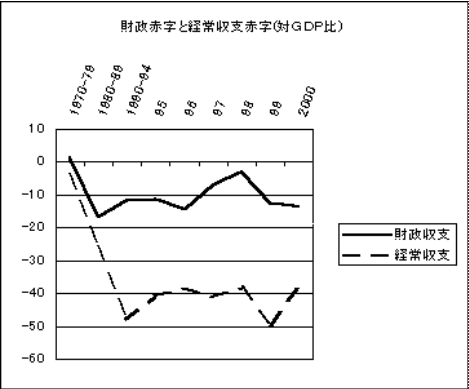 |
| (出典)ニカラグァ中央銀行資料より作成 |
| 図2.3-2 財政収支と経常収支(対GDP比) |
| 表2.3-7 需給構造(対GDP比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)ニカラグァ中央銀行資料より作成 |
| 2) | 弱体かつ不透明な金融制度。BANIC(ニカラグァ商工銀行)の破綻などの金融危機によって、国民は新たに550百万ドルもの負担を背負い込むことになった。国を代表する金融機関の不透明な経営の結果、パリクラブでの債務減免分を上回るような負担が国民に押し付けられており、金融制度の監視能力の強化が緊急の課題とされる。さらに、ニカラグァの金融機関は、管理コストの高さ、主要都市への過剰集中、中長期貯蓄と融資の極端な不足などの問題を従来から抱え込んだままであり、長期成長に不可欠な金融仲介機能を果たしていない。 |
| 3) | 弱体な所有権。2.1の政治情勢でも指摘したとおり、不動産所有権をめぐる係争の継続が依然として土地・資産市場の発達の最大の障害である。また、農業投資と生産の多角化の制約要因でもあり、貧困が集中する農村の開発を遅らせている。 |
| 4) | 技術の遅れと低生産性。1990年代における牧畜と農業の成長は、低利用の労働力の投入増大と粗放的な栽培面積の量的拡大の結果である。低生産性の表れとして実質賃金が1990年代を通じて年間平均で6%も低下している。賃金低下を補うために労働時間を延長したうえ、女性や子供などの労働力を追加するという成長と貧困緩和は一過性の出来事にすぎず、持続性にも欠けるため好ましくない。農業フロンティアも消滅しつつあり、生態系の持続可能性も損なわれている。投資効率の低さは、農業・牧畜・製造業における極端な生産性の低さと品質管理の遅れと表裏一体の関係にある。 |
| 表2.3-8 部門別GDP構成(1980年価格比: %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)ニカラグァ中央銀行 |
| 表2.3-9 部門別GDP変動率(1980年価格: %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)ニカラグァ中央銀行 |
| 5) | 人的資本の遅れ。歳出の半分以上を社会支出に当てている政府の努力は高く評価でき、平均余命や乳児死亡率、純初等教育就学率では着実な改善がみられる(表2.3-10)。だが、初等教育を修了する子供は、わずか36%(農村部では9%)に留まっており、生産性向上の大きな足かせとなっている。これは社会支出の内訳の歪み、及びターゲティングの不足に起因する。さらに、高教育・熟練労働者の海外流出が深刻な問題となっている。内戦がもたらした社会的協力・信頼関係、すなわち社会資本の破壊も依然として深刻な問題である。 |
| 表2.3-10 社会指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| *PRSPにおける数値目標 (出典) The Republic of Nicaragua, Poverty Reduction Strategy Paper |
| 6) | インフラ整備の遅れ。内戦と自然災害により、ラテンアメリカで最もインフラ整備が遅れた国の一つとなっている。主要道路や橋、教育・保健医療関連施設などの再建が進められているものの、手付かずの分野・地域が多く残されている。発電、通信、港湾インフラには多額の資金導入が欠かせない。インフラ整備の遅れは、ニカラグァの生産コスト高と国際競争力の低下の主因である。 |
| 7) | 自然災害への脆弱性。地理・地勢的要因による様々な自然災害及び生態系の劣化のために農業生産に深刻な悪影響がでている。インフラ・生産設備・住居への被害も大きい。防災システムの整備も重要課題の一つである。 |
| 8) | 交易条件の悪化。主要輸出産品は一次産品であり、多角化が遅れているために、国際市場の値動きに高度の脆弱性をもった経済構造となっている。コーヒー価格の暴落はニカラグァ経済の先行きに暗雲を投げかけている。 |
| 9) | 公的支出の効率性。1990年代を通じて公的部門の支出がGDPの40%、財政赤字はGDPの10%にも達していた。だが、政府は公共部門の削減へ向けて、一連の措置を実施した。
|
| 10) | 低い貧困削減効果。多額の国際援助に依存する社会支出の増大にもかかわらず、貧困削減効果が低い。社会投資プログラムの策定・実行に際して、貧困層へのターゲティングが不十分であったためである。 |
| 11) | 対外債務返済。内戦終結による国防費削減という「平和の配当」はGDPの25%にも匹敵する規模だったが、大半がドナー国及び国際金融機関との関係正常化のための債務返済に充てられた。債務返済率は80年代半ばのGDP比1%から1990年代末には8~9%にまで拡大している。重債務貧困国(HIPC)への債務減免メカニズムによる実質的な削減効果は2%弱とみられ、債務削減措置への過大な期待は慎むべきである。 |
(1)低成長・低インフレ・失業増大
- 外貨制約が厳しくなり、国際収支の不均衡是正に回せる使途制約のない外貨の流入が低落傾向にある。外貨制約はニカラグァの成長率を大きく抑制する要因である。
- 2000年の自治体選挙、2001年の総選挙という2年連続の「政治の年」のため、投資が手控えられた。民間投資では4%、公的投資は援助減少のため16%も削減され、成長率の低落に直接つながった。
- 米国の景気後退はラテンアメリカ全域に悪影響を及ぼしており、対米経済依存度の高いニカラグアにとっても大きな打撃である。
- コーヒー価格暴落と石油価格の高値傾向は交易条件の悪化をもたらし、経常収支の赤字のさらなる拡大と輸入能力の削減が懸念される。
- 国内各地での旱魃被害が深刻化しており、貧困状況の悪化が懸念される。
- インフレ率は8%台で推移するものと見られ、マクロ経済の不均衡が貧困層に与える悪影響は緩和される。
- 総失業(完全失業と不完全雇用による労働力の未利用分合計)は25%前後で推移し、労働力の不完全利用が貧困の主因の一つとなっている。
- コーヒー価格の暴落による輸出収入の減少の結果、
- 経常収支の赤字補填は、援助流入と民営化資金への依存度を強め、不足分は外貨準備切り崩しで補うことを余儀なくされる。
- 2000年8月から1年間で4銀行が破綻しており、国民に新たに550百万ドルの負担を強いられることとなった。これは将来の購買力が奪われたことを意味する。
対象期間は2001年後半であり、合意ベースは実質成長率3%、インフレ率8%であった。主な内容は以下のとおりである。
1) 財政政策
- 名目歳出額を2000年と同水準に据え置く
- 公債利払いを除く経常赤字を2001年後半にGDP比9%まで削減
- 公債利払いと外資依存固定投資を除く歳出総額をGDP比11%に削減。
- 金融システムの監視能力の強化。
- 外貨準備高を236.7百万ドルまで増額
- 上記目的達成には、歳出削減、国営電話公社(ENITEL)とニカラグァ発電公社(ENEL)の民営化資金流入、ならびにIDB国際収支支援金の拠出が不可欠となる。
- 金融制度強化
- 通信・電気民営化
- 社会保障改革
- 統治能力改善(予算編成・歳出プロセスの透明化とモニター、所有権解決に向けた分権化)
- 司法制度改革
(5) 今後の展望
ボラーニョス政権は、ニカラグァの債務削減・貧困削減・構造改革と長期成長の命運を握っている。新政権は発足早々にもIMFとの間で3年間のPRGF合意を締結する必要があろう。貧困削減戦略は既に1年間履行しており、2003年にはHIPCの合意点に到達する可能性がある。その前提として、大規模な財政調整(根底的な税制改革を含む)、輸出拡大努力が不可欠となる。また、PRSPの内容の現実的見直しも必要となる。とくに成長率と投資予測は、かなりの下方修正が必要となろう。主な不安材料は、米国経済を中心とする国際経済の景気動向と国外貯蓄の利用可能性であり、ドナー及びニカラグァ政府の双方がPRSP実施に向けた財源不足に落入る心配もあり、プログラムの不履行問題に備える必要があろう。

