2.2 社会情勢
(1)貧困状況
ニカラグァはラテンアメリカの最貧困の一つであり、一人当たりGDPはラテンアメリカ諸国の平均値の3分の1にすぎない。消費貧困では国民の約半分、基本的ニーズ水準による貧困指数からすると、国民の78.7%が貧困層(慣性的貧困と恒常的貧困の合計)に属する。
| 表2.2-1 貧困分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)統合家庭・最近貧困家庭・慢性的貧困家庭・恒常的貧困家庭とは、消費水準及び基本的ニーズの充足度に応じて下記の表のように定義される。
(出典) INEC, Perfil y caracteristicas de los pobres de Nicaragua, EMNV98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
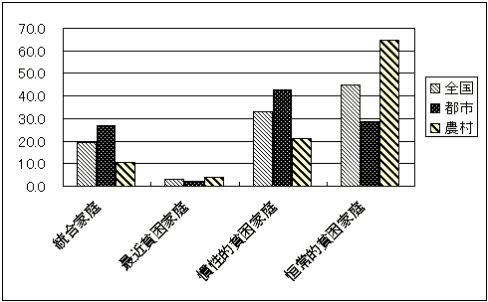 |
| (出典) INEC, Perfil y caracteristicas de los pobres de Nicaragua, EMNV98. |
| 図2.2-1 貧困分布 |
| 表2.2-2 地域別貧困分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典) INEC, Perfil y caracteristicas de los pobres de Nicaragua, EMNV98 |
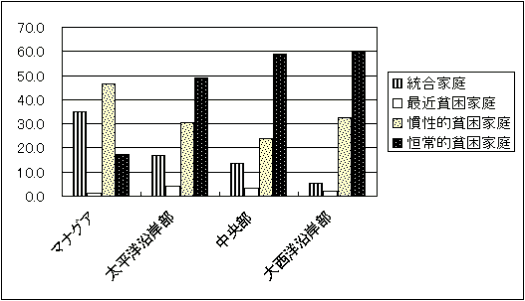 |
| (出典) INEC, Perfil y caracteristicas de los pobres de Nicaragua, EMNV98. |
| 図2.2-2 地域別貧困分布 |
図表2.2-1からニカラグァにおける貧困は圧倒的に農村部における現象であることが分かる。国民の54.3%が都市住民であるが、その69.5%は非貧困層である。反面、貧困層の65.4%は農村居住者であり、とりわけ消費及び基本的ニーズの両基準において貧困層に該当する恒常的貧困家庭が農村部の64.5%を占めており、極めて深刻な事態となっている。
マナグアの恒常的貧困家庭が17.3%であるのに対し、大西洋沿岸部では60%、中央部で58.9%と地域格差も大きい(表2.2-2)。
1993年と1998年の調査を較べると、全国レベルでは極貧層が2.1%、貧困層が2.4%低下しており、貧困比率は減少傾向にある。ただし、人口増加率がこれを上回るため、絶対数では増加している。
| 表2.2-3 貧困率の変化(1993/1998年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典) INEC, Perfil y caracteristicas de los pobres de Nicaragua, EMNV98. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993年と1998年の統計から得られる経済成長の貧困弾力性は0.915、最貧弾力性は1.603である。すなわち、一人当たり実質経済成長1%ごとに貧困層が0.915ポイント、極貧層が1.603ポイント減少することになる。この間のニカラグァの一人当たり成長率は(所得増加の代替変数)は1.2%であった。このペースが続くならば、2015年までの貧困率の減少は20%程度にすぎず、37.9%が貧困層に留まったままとなる。同様に、2015年の極貧率も13.7%に留まる。極貧率を2015年までに半減するには、一人当たり年間2%の成長率が達成される必要があるが、ニカラグァの現状からみて困難である。従って、2015年までに極貧層を半減させるという成長強化・貧困削減戦略(SGPRS)における最優先目標の達成には、極貧層をターゲットとする特別プログラムの立案・執行が欠かせない(SGPRSについては2.5.2を参照)。
表2.2-3に見るとおり、マナグアにおける貧困層の大幅な減少とは対照的に、太平洋沿岸部の都市及び大西洋沿岸部の都市と農村(極貧層)において貧困が著しく増加している。これは経済安定化・構造調整政策のコストと便益が地域的に不平等に配分された結果である。マナグアにおいては自由化と規制緩和により金融、商業、通信などの高賃金部門の雇用が拡大した反面、太平洋沿岸部の製造業と農業が大きな打撃を受けた。大西洋沿岸部の農村部では貧困層が減少する一方、極貧層が11%も増加しており、貧困の深化が進行するという危機的状態にある。この地域に対する特別プログラムが必要とされる。
(2)所得・消費格差
所得格差を示す指数であるジニ係数1はニカラグアでは50.0であり、ラテンアメリカ諸国のの平均値50.8にほぼ等しいが、ラテンアメリカは世界的に見て最も不平等な地域であることに留意する必要がある。消費でみると上位20%が総消費の51.3%、下位20%はわずか5.3%という格差が生じている。都市部では上位20%と下位20%の消費格差は9倍以上にも達する。
ニカラグァでは最上層10%への集中が著しい反面、国民の80%の消費を合計しても半分に達しない(表2.2-4)。富の不平等な分配及び基本的サービス利用における格差が低成長を持続させ、貧困を悪化させることは、国際的に実証されている。高度な不平等を低成長と貧困悪化に転換する回路とは、人的物的資本への低投資である。最貧層の出生率は最富裕層の3倍であり、この状況が続くならば不平等がさらに悪化することになる。
| 表2.2-4 不平等の諸指標(1998年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)INEC, Perfil y caracteristicas de los pobres de Nicaragua, EMNV98 |
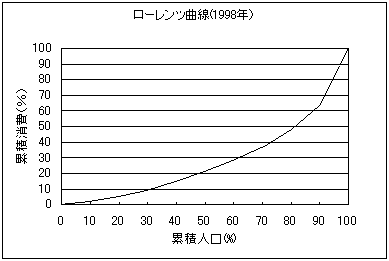 |
| (出典)INEC, Perfil y caracteristicas de los pobres de Nicaragua, EMNV98より作成 |
| 図2.2-3 不平等の諸指標 |
| 表2.2-5 居住地域・階層別消費内(1998年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)INEC, Perfil y caracteristicas de los pobres de Nicaragua, EMNV98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 貧困の経済的次元2
| 1) | ニカラグァでは貧困と失業・不完全就業の間に高い相関性がある。特に女性世帯主の場合に著しい。 |
| 2) | 貧困層ほど不動産の所有権が確定せず、貧困が助長されている。ニカラグァでは土地の5分の4が未登記状態にある。登記された土地の大半も不正確な登記で紛争の種になっている。登記制度の改革は極めて遅く、官僚的かつ恣意的であり、かえって紛争を複雑化させる要因となっている。所有権の確定問題は貧困層の生活設計、生産・投資決定、さらに居住地域にも大きな影響を及ぼす重要な問題である。 |
| 3) | 貧困層ほど公共サービスとインフラへのアクセスが不利となっている(表2.2-5)。 |
| 4) | 社会開発部門の劣悪賃金が社会支出の増大効果を相殺している。教員の質と教育効果には高い相関関係があるが、教員と看護婦の賃金は農業部門についで二番目に低いため、有能な人材が社会サービス部門から流出している。 |
| 5) | 1990年代中期から貧困家庭の家計に占める社会サービス支出比率が激増している。とくに保健医療及び教育費の増大が著しい。これは貧困層のサービス・アクセスの持続性を損なう危険をもたらす。医療費における支出増加率は、極貧家庭は100%、貧困家庭は77%にも達している。保健省の経常予算の40%が薬剤費であるにもかかわらず、貧困層には届いておらず、貧困層自身は医療支出の80%を民間薬剤購入に支出している。 |
| 表2.2-6 教育・保健アクセス度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出典)INEC, Perfil y caracteristicas de los pobres de Nicaragua, EMNV98 |
(4)人的資本と貧困
| 1) | 高出生率と高依存人口数。ニカラグァの出生率はラテン・アメリカ最高水準にあるうえ、貧困層になるほど出生率が高く、依存人口数が増える傾向にあり、貧困の拡大再生産の一因となっている。貧困層をターゲットとするリプロダクティブヘルスと家族計画が効果的に運営されてこなかったことが伺える。 |
| 2) | 貧困と就学状態の間には高い相関関係がある。識字率は改善しているものの、極貧層の40%近くが依然として非識字者に留まっている。極貧家庭の就学対象年齢(6~18歳)の半分が未就学状態にある(非貧困層では、わずか16%にすぎない)。平均就学年数は貧困層で3.1年、極貧層では2.3年にすぎない。 |
| 3) | 保健医療サービスへのアクセス度でも大きな不平等が存在する。サービスを受けるのに必要な移動時間と距離は極貧層と非貧困層では3倍の相違(表2.2-5)がある。また、極貧層の子供たちは非貧困層の子供たちに較べて、50%も病気にかかる頻度が高い。 |
| 4) | 貧困と栄養不良の間には強い相関関係が存在する。 |
(5)脆弱性と周縁性
| 1) | 天災への高い脆弱性が貧困問題の解決を困難にしてきた。火山噴火、ハリケーン、地震、旱魃、山火事、洪水などの被害が頻繁に発生しており、生態系の悪化に加えて資産・インフラに多大の被害がもたらされてきた。最近でもエル・ニーニョ、ハリケーン・ミッチ、ラ・ニーニャなどが経済成長率を鈍化させ、貧困層の就業と生活に打撃を与えている。貧困層は不適切な居住形態と居住地、低貯蓄、低社会資本のために、とりわけ自然災害への脆弱性をもつ。 |
| 2) | 貧困家庭が主観的に捉える最大の脆弱性は食料不足に起因する栄養不良である。加えて都市部貧困層では非熟練労働者の就業機会不足、農村部では土地をはじめとする生産要素へのアクセス不足が指摘されている。 |
| 3) | 貧困層は労働市場や社会保障制度、司法制度などに関する基本的情報へのアクセスに欠ける。 |
| 4) | ジェンダーの不平等も著しい。初等教育の就学率では女子が男子を上回るが、雇用機会や賃金水準では女性が不利な立場に置かれている。 |
| 5) | ニカラグァのエスニック・先住民集団(ミスキート、スモ、ラマ、クリオールら)が居住する大西洋沿岸部はニカラグァの最貧地帯であり、政治経済的に周縁化されてきた。 |
1 ジニ係数とは、図2.2-3に示されるように所得と人口を累積した曲線(ローレンツ曲線)と45度線の間の面積の比率であり、理論的には最小値ゼロ(完全な平等)から最大値1(一人に全所得が集中)の間をとりうるが、現実的には大半の国が0.25から0.60の間に収まっている。
2 本項及び(4)人的資本と貧困、(5)脆弱性と周縁性の記述は、PRSPの貧困プロフィール並びに世界銀行の調査に基づいている。詳細なデータについては、World Bank, Nicaragua Poverty Assessment, Volume 2: Annexes, February 21, 2001, Report No.20488-NIを参照。

