3-4.マルチ・バイ協力の効果
協力の効果は、「有効性」、「インパクト」および「自立発展性」の3つの観点から評価する。なお、UNICEF連携とUNFPA連携では目標設定等が異なることから、各観点から別々に検証することとする。
(1) UNICEF
最初に、これまでのUNICEF連携による協力実績を整理すると、1989年に5ヵ国で開始されて以来、2001年度までに35ヵ国で実施され、総額約101億円が供与されている(図 3-8)。供与額の変遷をみると、1996年をピークとして1998年まで下降したが、再び上昇傾向にある様子が見て取れる。EPIは減少傾向にある。
UNICEF連携分で今回の現地調査対象国をみると、供与総額の順に、ヴィエトナム(10億9,970万円)、カンボジア(9億8,660万円)、ラオス(7億5,750万円)、ザンビア(4億1,590万円)、タンザニア(3億1,610万円)、となっている。
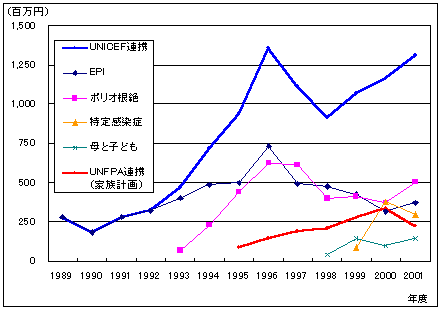
図3-8 供与額の変遷(UNICEF、UNFPA)
各国ワクチンの必要量とマルチ・バイ協力による供給量の割合を、入手できた限られたデータでみると、タンザニアにおけるポリオワクチンの必要量のうち、1999年は80%、2001年は100%を占めている。ザンビアにおいては、日本から供与された定期予防接種用のワクチン額とUNICEFのワクチン供給額を比較すると、マルチ・バイ協力が占めている割合が平均して約2割程度を占めていた。なお、1995年から2001年まで、定期予防接種用のBCG、はしかのワクチンは全てマルチ・バイ協力による供与であった。このように、本スキームはEPIで必要なワクチンの供給に大きく貢献してきたことが分かる。
「ロジックの流れ」(図 3-1)によると、UNICEF連携によるアウトプット目標は「ワクチン接種率の向上」である。現地調査国におけるワクチン接種率は、ヴィエトナム、ザンビアにおいては非常に高いレベルに達している(表 3-7)。各国のワクチン接種率とマルチ・バイ協力によって供与されたワクチン量(額)の関係についてのデータは入手できなかったが、参考までにカンボジアにおけるマルチ・バイ協力によって供与されたルーティン用ワクチンと全体の額との比較を表 3-8に示す。また、タンザニアでは部分的一斉投与(SNIDs)に用いられるポリオワクチンの80~100%がマルチ・バイ協力によるものである。
これらのことからもマルチ・バイ協力が各国レベルの目標達成に直接的に大きく寄与していると判断できよう。
ただし、ラオスとカンボジアではワクチン接種率が近年低下傾向にある。一般的な傾向として、EPIがある程度の接種率まで達していても、ポリオ根絶のためのNID(全国一斉投与)が始まると、UNICEFから人材育成やロジスティックの支援があり保健スタッフには特別手当が支給されるNIDの方に人手が集中する結果となり、定期予防接種率は低下傾向になることが指摘されている。ラオスでも同様の指摘があり、加えてポリオ根絶宣言後予防接種に対するインセンティブが低下していること、またEPI活動を全面的に支援していたプロジェクト方式技術協力が2001年9月に終了し同等レベルの成果を持続することの困難さを招いていること等も低下傾向の理由として挙げられている。
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
| ラオス | ポリオ | 22 | 27 | 26 | 58 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 57 | 55 |
| 三種混合 | 22 | 23 | 25 | 48 | 54 | 58 | 60 | 53 | 52 | 52 | 40 | |
| BCG | 34 | 34 | 42 | 69 | 59 | 62 | 58 | 54 | 59 | 58 | 60 | |
| ヴィエトナム | ポリオ | - | - | - | - | - | 94 | 95 | 94 | 93 | 96 | 96 |
| 三種混合 | - | - | - | - | - | 94 | 95 | 94 | 93 | 96 | 96 | |
| BCG | - | - | - | - | - | 95 | 96 | 94 | 95 | 94 | 97 | |
| カンボジア | ポリオ | - | - | 36 | 54 | 80 | 75 | 70 | 64 | 65 | 71 | 72 |
| 三種混合 | - | - | 35 | 53 | 75 | 74 | 70 | 64 | 64 | 71 | 72 | |
| BCG | - | - | 57 | 78 | 95 | 88 | 82 | 76 | 78 | 83 | 80 | |
| タンザニア | ポリオ | 70 | 80 | 83 | 84 | 79 | 73 | 79 | 75 | 74 | - | - |
| 三種混合 | 76 | 83 | 83 | 84 | 81 | 72 | 79 | 74 | 76 | - | - | |
| BCG | 93 | 99 | 94 | 92 | 88 | 80 | 82 | 83 | 87 | - | - | |
| ザンビア | ポリオ | 94 | 60 | 67 | 89 | 85 | 93 | 78 | 73 | 72 | - | - |
| 三種混合 | 95 | 61 | 61 | 86 | 82 | 83 | 82 | 70 | 92 | 76 | - | |
| BCG | 98 | 88 | 92 | 100 | 98 | 100 | 94 | 86 | 87 | 100 | - | |
| 出所: | ラオス:ラオス保健省資料(1991-2000)、WHO Country Report 2002(2001)
ヴィエトナム:WHO Country Report 2002(1996-2001) カンボジア:WHO Country Report 2002(1996-1999) タンザニア:タンザニア保健省資料(1991-1999) ザンビア:ザンビア保健省資料(1991-1999)、WHO資料(2000) |
| (単位:1,000US$) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 出所:Aspects of Health and Nutrition Issues and Activities in Cambodia, Nov.12, 2002, UNICEF Cambodia |
(2) UNFPA
これまでのUNFPA連携による協力実績を整理すると、1995年に4ヵ国で開始されて以来、2001年度までに19ヵ国で実施され、総額約14.6億円が供与されている。今回の現地調査対象国でみると、実施年度回数、供与総額の順に、ラオス(3回、5,000万円)、カンボジア(2回、1,820万円)、ヴィエトナム(4回、8,010万円)、タンザニア(5回、1億60万円)、ザンビア(2回、2,250万円)、となっている。このうち、現在協力を実施中の国は、ラオス、カンボジア、ザンビアの3ヵ国である。
ロジックの流れの整理(図 3-2)によると、UNFPA連携によるアウトプット目標は「リプロダクティブ・ヘルスサービスへのアクセスの向上」である。その指標としては、妊産婦健診受診率、避妊具(薬)配布・販売数、サービスへのアクセスへの拡大(避妊サービス受給者数、避妊実行率等)、専門技能者立会いの下での出産割合23、などが考えられる。しかし、基本的に現地対象国の保健統計の整備状態が悪く、評価に耐え得るデータを入手することはできなかった。ただしタンザニアでは、ある程度の状況調査や中間・最終評価を実施しており、協力効果を測る参考となる(表 3-9、表 3-10)。
タンザニアの場合、1997年~2001年までの5年間供与24されており、その供与総額は1億60万円である。同国のUNFPAプログラムでは、具体的な目標として、産前健診や産後健診の受診、避妊や性感染症予防、施設分娩や乳幼児に関わるサービス(乳幼児の成長モニタリングなど)の受診の増加を目指している。本プログラムは、UMATI(実施主体のNGO)が養成している地域保健・家族計画推進員の活動(家族計画や保健教育・カウンセリング)に必要な保健施設のサービスの改善とそのサービスの利用促進を目指していた。対象地域は4県であり、4県内の232施設の31.9%に本件からの機材が供与されている。
|
||||||||||||||||||||||||
| 出所:各県保健局資料およびUNFPAが実施した「1999年現状調査」 |
|
||||||||||||||||||
| 出所:タンザニアUNFPA「最終評価報告書」2002年4月 |
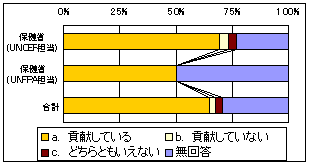 |
| 図3-9 マルチ・バイ協力の保健プログラム達成への貢献度 |
定性的な情報では、タンザニア、ザンビアにおいて、機材供与およびそれに伴って可能となったサービスの種類の増加によって、人々の保健施設に対する信頼感が増し、妊産婦や乳幼児の保健施設へのアクセス向上につながっているという結果が得られた。これらの情報は、機材やサービスが拡充することによって、本スキームのアウトプットである「リプロダクティブ・ヘルスサービスへのアクセスの拡大」に結びつくことを示唆するものであり、プログラム目標の達成度の進展が見られる。
一方、マルチ・バイ協力実施国の保健省担当者に対するアンケート調査の結果(図 3-9)によると、マルチ・バイ協力が自国の保健プログラムの達成に貢献している度合いは両機関の合計で65%であり、予想以上に良好な結果となっている。機関ごとにみると、UNICEF連携(69%)に対して、UNFPA連携(50%)はやや低く、両者の間に開きが見られる。これは実績期間の長さと量によるところが大きいと思われる。
(3) 他スキームとの連携による相乗効果
UNFPA本部がマルチ・バイ協力の成功例としてあげている国はヴィエトナム、ザンビア、メキシコ、トルコ、フィリピンである。UNFPA現地事務所とJICA事務所との協調が進んでいることが要因である。加えて、ヴィエトナムでは、もともとUNFPAのプログラムを実施してきたジョイセフがプロジェクト方式技術協力に協力している関係で、日本側の技術・UNFPAの技術・資機材の3つが一体になることによって相乗効果を生み出している。また、ラオスにおいては、その協調促進の背景には、プロジェクト方式技術協力(小児感染症予防プロジェクト)や研修事業等、ODAあるいはNGOの協力が入っていることが特徴である。例えば、今回の現地調査結果でもヴィエトナムにおける「リプロダクティブ・ヘルス・プロジェクト」では、カウンターパートが供与資機材を用いながら自発的に普及活動を行えるようになった。また郡保健局スタッフにより実施される両親学級を通じ、男性の妊産婦の健康に対する理解が高まるなど、そのインパクトの大きさ・効率性の高さが際立っている。タンザニアのUNFPA連携マルチ・バイ協力の場合では、UNFPA現地事務所の関与が希薄ではあったものの、協力開始当初に抱えていた供与資機材遅配等の問題を、タンザニア政府(保健省)や現地NGOと協調しながら、JICA事務所やジョイセフと連携しつつモニタリングおよび評価調査を行い、実施システムの効率化を図っている。
(1) 中期的アウトカム(参考)
・UNICEF
中期的アウトカム目標である「感染症罹患率の低下」については、現地調査対象国の保健省から信頼性の高いデータを入手することができなかった。参考までにWHOから出されている感染症報告数を見る(表 3-11)。
| (ラオス) | 1980 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ジフテリア | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 麻疹 | 1,380 | 2,168 | 671 | 4,613 | 2,302 | 332 | 94 |
| 百日咳 | 2,718 | 856 | 90 | 49 | 133 | 80 | 111 |
| ポリオ | 1,166 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新生児破傷風 | - | 4 | 12 | 17 | 18 | 21 | 17 |
| 破傷風 | 1,015 | 27 | 17 | - | 27 | 39 | 35 |
| 黄熱病 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| (ヴィエトナム) | 1980 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ジフテリア | 1,730 | 509 | 152 | 130 | 81 | 113 | 133 |
| 麻疹 | 86,901 | 8,175 | 6,507 | 11,690 | 14,134 | 16,512 | 12,058 |
| 百日咳 | 96,577 | 4,095 | 1,565 | 1,182 | 903 | 1,426 | 1,242 |
| ポリオ | 1,741 | 723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新生児破傷風 | - | 313 | 257 | 266 | 219 | 142 | 104 |
| 破傷風 | 1,948 | 628 | 165 | 401 | 685 | 267 | 177 |
| 黄熱病 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| (カンボジア) | 1980 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ジフテリア | 1,559 | 179 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 麻疹 | 32,240 | 2,473 | 3,826 | 1,993 | 13,827 | 12,237 | 3,761 |
| 百日咳 | 86,334 | 1,690 | 1,665 | 438 | 618 | 2,068 | 4,714 |
| ポリオ | 591 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新生児破傷風 | - | - | 34 | 84 | 173 | 295 | 165 |
| 破傷風 | 2,089 | 219 | 238 | 321 | 425 | 169 | 913 |
| 黄熱病 | - | - | 0 | - | - | - |
| (タンザニア) | 1980 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ジフテリア | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| 麻疹 | 63,100 | 14,920 | 7,287 | 10,023 | 5,887 | 14,649 | 11,847 |
| 百日咳 | 2,788 | 243 | - | - | - | - | 0 |
| ポリオ | 91 | 3 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 新生児破傷風 | 652 | 28 | 21 | 34 | 40 | 48 | 41 |
| 破傷風 | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 黄熱病 | - | 0 | - | - | - | - |
| (ザンビア) | 1980 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ジフテリア | 12 | 4 | 0 | - | 68 | 0 | 50 |
| 麻疹 | 98,659 | 6,748 | 7,140 | - | 23,518 | 30,930 | 16,997 |
| 百日咳 | 21,232 | 200 | 0 | - | 1,051 | 0 | 953 |
| ポリオ | 276 | 79 | 5 | - | 29 | 0 | 3 |
| 新生児破傷風 | - | 57 | 34 | - | 161 | 130 | 39 |
| 破傷風 | 409 | 57 | 11 | - | 261 | 193 | 62 |
| 黄熱病 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ラオスにおいては、ポリオは2000年に根絶宣言、ジフテリアは減少しているが、百日咳については1990年代後半より横ばい状態にある。ヴィエトナムについては、ラオス同様、2000年にポリオ根絶宣言がなされている。麻疹、百日咳ともに1990年に比し、最近では顕著に減少していることがわかる。カンボジアでもポリオ根絶宣言が出されているが、麻疹、百日咳は1980年ほどではないものの、最近は報告件数が増加している。タンザニアは、ここ3年間はポリオの発生が報告されていないが、麻疹は最近では横ばい状態であり、ザンビアにおいては、概してどの疾患においても年次による高低が激しく、改善傾向は認められない。ポリオも今だに発症が報告されている。これらのデータからはEPIの効果をみることはまだ難しい状況と判断される。
また、特筆すべきアウトカムとして挙げられるのが、2000年10月WHO西太平洋地域においてポリオ根絶宣言がなされ、2005年に全世界ポリオ根絶宣言が予定されていることである。このアウトカムは非常に分かりやすいと同時に、日本の尽力も大きく、1ドナー国である日本のプレゼンスを発揮できたといえる。
・UNFPA
中期的アウトカム目標である「リプロダクティブ・ヘルスの向上」を測る指標として、合計特殊出生率、避妊実行率、専門技能者立会いの下での出産割合が考えられる。
現地調査対象5ヵ国を1995年と2000年のデータで比較すると、合計特殊出生率(図 3-10)、専門技能者立会いの下での出産割合(図 3-11)、避妊実行率(図 3-12、図 3-13)において、ヴィエトナムが他の4国と比べてもともと優れているのに加え、5年間でさらに改善されている様子が読み取れる。ただし、本スキームによる中期的アウトカムレベルでの貢献は確認できなかった。その他の国でも改善は見られるものの、MDGsの目標25にはほど遠いレベルである。
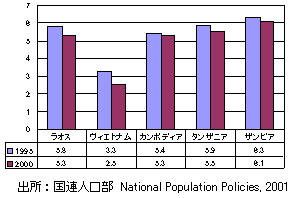 |
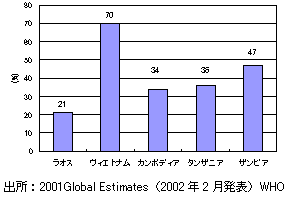 |
| 図3-10 合計特殊出生率 | 図3-11 専門技能者立会いの下での出産割合 |
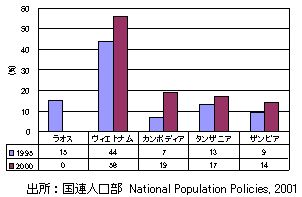 |
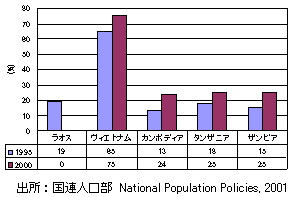 |
| 図3-12 避妊実行率(近代的方法) | 図3-13 避妊実行率(全ての方法) |
(2) 長期的アウトカム(参考)
長期的アウトカムは、乳児死亡率、5歳未満児死亡率、妊産婦死亡率等で測るところであるが、このレベルに対するマルチ・バイ協力の影響を特定するのは容易ではないため、参考にとどめる。今回入手できた、乳児死亡率(図 3-14)、5歳未満児死亡率(図 3-15)の推移を示す。全体的には、どの国においても減少しており改善傾向にあるといえよう。
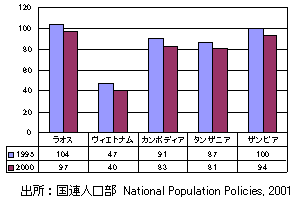 |
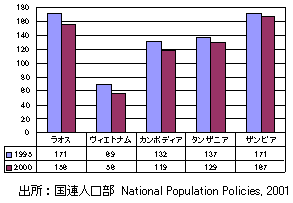 |
| 図3-14 乳児死亡率(出生千対) | 図3-15 5歳未満児死亡率(出生千対) |
(3) 予期していなかったインパクト
マルチ・バイ協力は当然のことながら、UNICEF、UNFPAとの対話が必須であり、そのことにより結果的に現地レベルにおいて在外公館、JICA在外事務所、UNICEF/UNFPA、他ドナーおよびコミュニティとのコミュニケーションが進んだと指摘する声が聞かれた。また、経験豊富なUNICEF/UNFPAおよびWHO/WPROと共に開発援助を実施できたことは、そのノウハウを学ぶことができ、また最新の援助分野における援助動向などの情報も入ってくるため、日本側の援助関係者のキャパシティを向上させたという観察もある。そういう意味で我が国の援助人材のさらなる強化につながるという隠れたインパクトの意義は小さくない。
自立発展性については各国の現時点での自立発展度を検証し、本スキームの貢献度を検証する。
アンケート結果でみると、「配布、配送」、「保健医療関係者の技術能力」、「組織の運営管理能力」といった項目で、3~4割くらいの関係者が能力の向上につながったとみている。
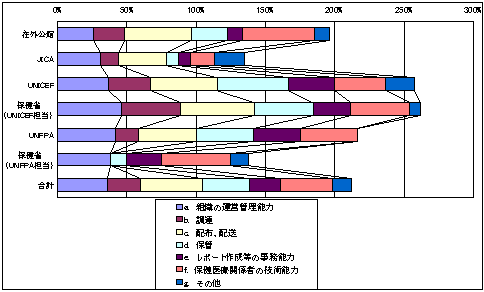
図3-16 マルチ・バイ協力による相手国の能力向上
(1) 政策立案能力
現地調査5ヵ国において、総じて政策立案能力は一定レベルに達していることが確認された。
UNICEFを通じたEPI事業については、長年にわたるICC会合を始めとしたUNICEFやWHOおよび日本側との共同作業を通じて、被援助国は政策策定段階で的確なアドバイスを受けており、各国独自のEPI5ヵ年計画を策定するなど、政策立案能力向上に貢献したことが見てとれる。UNFPAについても、各国においてほぼ問題ないレベルに達しているように見受けられたが、協力実績が少ないことから、本スキームによる貢献かどうかは判断できない。
一般にSWAPsが強力に進められている国(タンザニア、ザンビア)においては、財政的にはドナーに依存しているものの、例えば地方分権化政策に沿って保健セクター改革を進めた結果、国全体として保健セクターにおける政策立案能力が着実に向上していることが見られたことは特筆に値する。
ヴィエトナム以外の現地調査対象国において、保健セクター改革が展開されており、保健行政のスリム化、保健事業実施主体の地方行政への委譲が進められている。これらの国(特にタンザニア、カンボジア)においては、その過渡期の弊害として、委譲に伴う予算措置がなされていないため、地方保健行政の財源不足と人材不足が深刻な問題となっており、マルチ・バイ協力の実施上の大きな阻害要因となっている。ただし、ザンビアにおいては保健セクター改革開始後10年が経過し過渡期の混乱も落ち着き、財政的な自立への道のりは遠いものの、地方保健局レベルの能力が一般的に高まっており、政策立案能力についてはほぼ問題ないレベルに達していることが確認された。
以上の考察から、政策立案能力の向上については、SWAPsの正のインパクトが大きく、マルチ・バイ協力の貢献を特定することは難しい。ただし、地方保健行政のキャパシティ・ビルディングの強化は全ての国で必要な状況であり、本スキームの協力においては、供与資機材が効率的に配布され、かつ適正に活用されるためにも、計画段階において先方政府の予算状況や現地職員のキャパシティに十分配慮することが不可欠と思われる。
(2) 実施体制
総じて、UNICEF連携においては、長年に亘る「計画→調達→通関→保管→配布→投与」の各プロセスにUNICEFおよび日本(西太平洋地域はWPROも含む)が関わることによって、被援助国政府保健省はEPIに関する実施計画や効率的な実施のためのアドバイスを受けることができたため、配布、輸送システムの設置および改善などに見られるように、確実に実施体制、その能力は向上していると見ることができる。
また、SWAPs推進国(タンザニア、ザンビア)においては、その過程でキャパシティ・ビルディングの向上、オーナーシップの醸成が進んでおり、さらに両国とも地方分権化も進められていることから、少なからず中央と地方のネットワークが構築されつつあることが確認された。これらの状況は、実施体制において自立発展性が高まりつつあることを示している。他方、カンボジアにおいても保健セクター改革が実施されており保健サービスの地方委譲が進んでいるが、こちらは過渡期であるが故の実施体制の脆弱さが露呈している。ただし、いずれの現象も本スキームによる直接的な貢献は確認できなかった。
(3) 予算
表 3-12に、現地調査対象5ヵ国の人口・社会・経済指標を示す。ヴィエトナム以外は、後発開発途上国である。公的保健支出のGDPに占める割合は、ザンビアが3.6%で一番高いものの他は1%前後と低い(因みに、スウェーデン6.6%、日本5.7%、韓国2.4%、ケニア2.4%、タイ1.9%)。外部からの人口分野への援助の一人あたり概算は、ザンビアがもっとも高く、続いてカンボジア、タンザニア、ラオス、ヴィエトナムの順となっている。いずれも、ドナーに多くを依存しているというのが実態で、現時点では財政的な自立発展性は非常に低いといわざるを得ない。
| DACによる分類 | 人口 (100万人) (2002) |
1人当たりのGNI注 (US$) (2000) |
公的保健支出(%) (GDPに占める割合) |
外部からの人口援助26 (1,000US$) (カッコ内は 1人あたり概算) |
|
| ラオス | 後発開発途上国 | 5.5 | 1,540 | 1.2 | 2,104 (0.38) |
| ヴィエトナム | 低所得国 | 80.2 | 2,000 | 0.8 | 17,039 (0.21) |
| カンボジア | 後発開発途上国 | 13.8 | 1,440 | 0.6 | 21,362 (1.55) |
| タンザニア | 後発開発途上国 | 36.8 | 520 | 1.3 | 30,502 (0.83) |
| ザンビア | 後発開発途上国 | 10.9 | 750 | 3.6 | 17,092 (1.57) |
参考までに、唯一入手できたラオスにおけるEPI関連予算における自国調達割合は、0.1%~12.4%と低位で推移している。JICAの投入をみると、2000年は58.6%、2001年は34.7%を占め高い。また、ヴィエトナムでもEPI予算の5割は日本が供与しているといわれている。
| 1992年 | 1994年 | 1996年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | |
| ラオス政府 | 0.1% | 0.3% | 8.2% | 12.4% | 2.4% | 4.2% | 4.9% |
| UNICEF | 42.2% | 51.1% | 60.8% | 21.0% | 19.6% | 27.7% | 34.7% |
| WHO | 8.5% | 15.5% | 12.7% | 1.3% | 5.4% | 5.5% | 12.8% |
| JICA | 26.0% | 18.8% | 18.3% | 26.0% | 46.2% | 58.6% | 43.9% |
| その他 | 23.1 | 11.6 | 0.0 | 39.3 | 26.4 | 3.7 | 3.6 |
| 合計 (US$) |
100.0% (1,384,807) |
100.0% (1,914,584) |
100.0% (1,190,179) |
100.0% (1,944,200) |
100.0% (2,502,147) |
100.0% (1,380,057) |
100.0% (1,279,923) |
出所:1996年以前は「ラオス人民民主共和国人口基礎調査団報告書」(1997年4月)JICA医療協力部
1998年以降は「Plan of Action EPI and Polio Eradication」各年版、MOH発行
しかし多くの国で自立への自助努力は認められる。例えば、ヴィエトナムでは、量的にはまだ自立するまではいかないが、ワクチンやコンドームの自国製造が始まっている。タンザニアでは、コンドーム供与等においてコストシェアリング(ソーシャルマーケティング)の導入が開始された。ザンビアでは「ワクチン自立イニシアティブ」を2000年に策定しその実施に向けて意欲をみせている(ただし、拠出実績は今だにゼロ)。ワクチン調達の100%をドナーに依存している状況から、徐々に自国資金に移行する計画が立案されている。
(4) 人的資源
UNICEFとの連携が始まった80年代後半と比べれば人的資源のキャパシティは向上しているということができよう。特にEPIに特化したプログラムでは実施体制が確立していることから、定期予防接種の事業運営には支障がないレベルの人材が育成されているといえる。
ただし、近年の地方分権化や保健セクター改革にともなってタンザニア、ザンビア、カンボジア、ラオスにおいて、権限だけが地方に委譲され予算が委譲されてないケースや、地方保健行政の人材育成が間に合わない、そのための予算が確保できないといった状況にあり、そういう意味で、地方における人的資源の自立発展性については、まだ厳しい状況にあるといえる。タンザニアではこれらの問題に対応するために、NGOの比較優位性を活かした政府の手の届かない分野でのNGOとの協力やパートナーシップが進められている。NGO側でも積極的に政府と協力する姿勢をみせており、社会サービスの担い手に育ちつつある。
23 「専門技能者立会いの下での出産」:国の報告に基づく、きちんとした技術を有する保健要員または立会人、すなわち医師(専門医またはそれ以外の医師)および/または通常分娩だけではなく産科合併症の診断・処置ができる助産技能を有するものの立会いの下での出産である。出所:世界人口白書(UNFPA)、2002
24 予算上5年間であるが、実際は4年間のみ。
25 ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals):1. 極度の貧困と飢餓の撲滅、2. 初等教育の完全普及、3. ジェンダーの平等、女性のエンパワーメントの達成、4. 子供の死亡率削減、5. 妊産婦の健康の改善、6. HIV/エイズ、マラリアなどの疾病の蔓延防止、7. 持続可能な環境作り、8. グローバルな開発パートナーシップの構築
26 各国の人口分野の活動に対して、1999年に行われた対外援助の総額

