3-3.マルチ・バイ協力のプロセス
マルチ・バイ協力のプロセスは、UNICEF、UNFPAによって状況が異なることから、ここでは、UNICEF、UNFPAそれぞれの機関に分けて評価を行う。それぞれの機関ごとに、実施プロセスは「策定過程」、「実施の効率性」の2つの観点から評価する。
まず、本協力スキームにおける両機関の協力実績の差(UNCEFとは1989年より14年目、UNFPAとは1995年より8年目)が非常に大きく、それが効率性の発現に影響を及ぼしていることを認識しておく必要がある。
政策対話については、UNICEFとは毎年定例の年次協議を実施しているが、UNFPAについてはマルチ・バイ協力に関する定期的な協議は開催されていない。前述したように、UNICEFはスキーム策定段階から駐日事務所の役割が大きく、合同ミッションなどにも参加し案件形成に大きく関与しているが、UNFPAはそうではない。
UNICEFは実施機関であるため、現地事務所においてプログラム実施にあたる職員を配置しているが、UNFPAは実施を他機関に委託することも多い(最近は裨益国政府に委託することが多くなってきたが、国際NGO、現地NGOなどにも委託)。そもそもUNICEFとUNFPAでは現地事務所の体制、組織力、予算額に大きな差があることは否めない。UNFPA本部はUNFPA現地事務所のキャパシティの脆弱性について認識している。
UNICEFに対しては、資機材の調達・運搬の経費および手数料としてその購入金額の8%をハンドリング・チャージとして提供しているが、UNFPAについては調達に関与していないことから、持ち出しになる場合もある(タンザニア)。
これら両機関のプロセス関与に加えて、被援助国側の状況(財政的自立度、保健セクター改革の進展度、地方分権化の進捗状況など)が、マルチ・バイ協力の実施プロセスに大きく影響している。
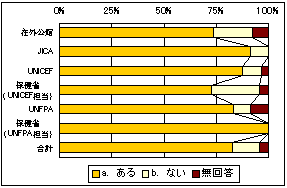 |
| 図3-7 マルチ・バイ協力の改善すべき点の有無 |
| 在外公館 | JICA | UNICEF | 保健省 UNICEF 担当 |
UNFPA | 保健省 UNFPA 担当 |
合計 | |
| 案件形成時に日本、相手国、国連機関の協議が十分にされていない。 | 8 | 13 | 8 | 8 | 6 | 6 | 49 |
| 30% | 57% | 24% | 31% | 50% | 75% | 38% | |
| 申請手続きが煩雑である。 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 32 |
| 22% | 35% | 21% | 15% | 42% | 25% | 25% | |
| 調達資機材の供給と需要が合致していない。 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| 15% | 9% | 12% | 15% | 8% | 38% | 14% | |
| 資機材の調達に対する日本の実施体制が不十分である。 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4% | 4% | 0% | 4% | 17% | 0% | 4% | |
| 資機材の調達に対する国連機関の実施体制が不十分である。 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4% | 17% | 0% | 12% | 8% | 13% | 8% | |
| 資機材の配布・配送に対する相手国の実施体制が不十分である。 | 9 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 |
| 33% | 30% | 39% | 35% | 25% | 13% | 33% | |
| 資機材の保管に対する相手国の実施体制が不十分である。 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 30 |
| 30% | 17% | 33% | 15% | 17% | 13% | 23% | |
| 資機材の配布・配送に対する国連機関の支援が不十分である。 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 7% | 17% | 3% | 12% | 17% | 13% | 10% | |
| 資機材活用状況に対するモニタリングが行われていない。 | 8 | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | 42 |
| 30% | 74% | 27% | 12% | 33% | 13% | 33% | |
| 上で選択した課題について具体的にお書きください: | 3 | 8 | 0 | 4 | 6 | 3 | 24 |
| 11% | 35% | 0% | 15% | 50% | 38% | 19% | |
| その他(具体的にお書きください) | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 34 |
| 22% | 39% | 27% | 23% | 8% | 38% | 26% |
モニタリングに関しては、「資機材活用状況に対するモニタリングが行われていない」では、JICA(74%)、在外公館(30%)が多い傾向にあり、中でもJICAの多さが際立っている。これは日本側がモニタリングの未整備を重く受け止めている表れと思われる。また、モニタリングをどの機関が実施しているかという問いには、相手国、国連機関(UNICEF/UNFPA)の割合が高いものの、日本という回答もあり、また複数の機関を挙げる者が多数いることから、複数の機関が連携しているか、バラバラに実施されているか、各国によって実施状況がかなりまちまちであることの表れと考えられる。
(1) 策定過程
本スキームは1988年5月に第1回日本・UNICEF協議が開催され、1989年7月にはUNICEFの推薦を受けた最初の5ヵ国に対して調査団が派遣され、それら5ヵ国に対して協力が開始された。その後毎年の日本外務省とUNICEF本部の年次協議を経て、対象国を増加してきている(2001年までで合計35ヵ国)。年次協議においては、毎年実施状況のレビューや問題点の確認と対処がなされ、より効率的・効果的実施に向けて改善がなされてきている。また、一連の計画策定→レビュー→フィードバックの過程において、駐日事務所は積極的に調整役を担い、重要な役割を果たしてきた。以上から、意思決定レベル(駐日事務所を含む本部レベル)でのマルチ・バイ協力策定過程は妥当であるといえる。
また現地調査を実施した国々では、UNICEFとの連携については長年の実績を経て、ほぼ各国において、本スキームの位置付け、役割分担、流れが確立されている(表 3-5)。ワクチン投与計画に関する計画策定は、当該国保健省、JICA、UNICEF、WHO現地事務所(WPRO地域)が参加する関係機関調整委員会(ICC)会合等ドナー調整会議において行われており、現地レベルでの計画策定過程も妥当である。具体的に現地調査実施国の状況をみると、策定過程にはほぼ問題はない。
また、前述したようにUNICEFの予防接種拡大計画(EPI)は、そもそもWHOの1974年決議により子供の6大疾患の予防接種推進を目指し、その後1988年の第41回WHO総会において「2000年までにポリオを地球上から根絶する」という目標が掲げられたことが推進力となり、WHO西太平洋地域事務所(WPRO)管轄地域においては、2000年ポリオ根絶達成まで、両機関が車の両輪のように強力に連携してきた。
| ラオス | ヴィエトナム | カンボジア | タンザニア | ザンビア | |
| 実施年 | 1989年~2001年 | 1993年~2001年 | 1992年~2001年 | 1995年~2002年 | 1989年~2001年 |
| 策定過程 | ICC年4回開催。 EPI5ヵ年計画が策定されている。 |
ICC年4回開催。 EPI5ヵ年計画が策定されている。 |
保健分野の政策の大きな枠組みはドナー支援の調整機関である調整委員会(COCOM)で協議されている→毎月開催。 EPI5ヵ年計画が策定されている。 |
ICC年2回開催。 ICCによって調整が行われている。ICCを通じて、EPI5ヵ年計画および部分的一斉投与(SNID)計画が策定されている。 策定過程には、JICA保健計画専門家が積極的に関与している。 SWAPsによって、保健セクターの会合が頻繁に行われており、援助協調が進んでいる。 |
SWAPsが進行しており、ICCによって上位レベルの政策対話を実施、計画の策定・調整を実施。 EPI5ヵ年計画が策定されている。 |
| 要請 | 効率的である。 ICC協議→保健省要請書作成(UNCEF、WHOの指導)→UNICEF駐日事務所、 WHOマニラ本部でチェック→JICAへ提出→大使館へ提出。 |
効率的である。 ICC協議→保健省要請書作成(UNCEF、WHOの指導)→UNICEF駐日事務所、 WHOマニラ本部でチェック→JICAへ提出→保健省から大使館へ提出。 |
効率的である。 保健省要請書作成(UNCEF、WHOの指導)→UNICEF駐日事務所、 WHOマニラ本部でチェック→JICAへ提出→保健省から大使館へ提出。 ワクチンの量や配布先については、保健省、UNICEF、WHOと毎年定期協議によって決定。 |
ICCでの調整→保健省によるワクチンニーズ予測→UNICEFからアドバイス→JICAのスキームにあわせて要請書作成→提出。 「母と子供の健康対策」については、保健省、UNICEF、JICA専門家との協議を重ねた上で地域のニーズに合った要請を策定。 |
ICCでの調整→UNICEFからアドバイス→JICAのスキームにあわせて要請書作成→提出。JICAはUNICEFに対して要請内容の確認をするプロセスが構築されている。 |
| 調達 | システムは出来上がっており効率的である。 調達はUNICEF。年2回の調達。 オランダで国際競争入札。ワクチンは製薬会社から直接配送。 |
同左 | 同左 ただし「母と子供の健康対策」の必須医薬品については、調達はJICA。2000年度に調達業者が複数になったこと等から申請から到着まで18ヶ月を要した。 |
同左 ただし「母と子供の健康対策」の必須医薬品については、JICAが調達(本邦・現地)を実施している。しかし特に問題はなし。 |
同左 |
| 配布 | 通関手続き以降は保健省。 ワクチンは中央保管庫、機材は中央機材倉庫に運ばれ適正に保管・管理されている。在庫管理も問題なし。県からの要請に従って支給される。県保健局職員が中央倉庫まで取りに来る。県から郡、郡からヘルスセンターと配布される。 山間地への道路事情の悪さ、特に雨季には交通遮断地域など、全国の3割がアクセス困難地域で、予防接種率向上の大きな阻害要因。 |
空港まではJICA、通関手続き以降は保健省。 4ヶ所のワクチン保管庫で保管・管理。在庫管理も問題なし。 中央から省へは、保健省管轄の公社が配送。省から県へは県保健局が取りに行く。県からコミューンレベルまでは交通アクセスの悪さ、保管用冷蔵庫等の不足などの理由で、効率性にやや問題あり。 |
空港まではJICA、通関手続き以降は保健省。 資機材は2ヶ所の中央倉庫に、ワクチンは1ヶ所の倉庫で中央から県へは、3ヶ月に一度保健省が配布数。ワクチンは州保健局→オペレーショナル・ディストリクト保健局→ヘルスセンターに配布される。 オペレーショナル・ディストリクト保健局レベル以下の配布は、交通アクセスの悪さ、保管用冷蔵庫等の不足などの理由で、効率性にやや問題あり。 |
空港まではJICA、通関手続き以降は保健省。 中央から州保健管理局へ、その後県保健管理局へと配送される。申請は県から州を通じて中央に上げられ、要請に応じて配送される。県から末端の保健施設までは県の責任で配布。EPIに関しては、中央から末端までシステムが完成しており、効率的である。 「母と子供の健康対策」については、開始以降地方分権化が進んだこと、末端の施設に配布する際パッケージを小分けするという煩雑で大きな作業が発生すること等の理由により、活動進捗に遅れが見られる。 |
空港まではJICA、通関手続き以降は保健省。郡保健局が直接、中央保管庫まで取りに来るシステム。遠方の郡にとってはたいへんな負担となっている。郡から末端の保健施設までは、保健施設側が取りに来ることになっている。末端の交通アクセスが大きな課題となっている。 |
| モニタリング | 定期予防接種に関するモニタリングは各県・郡保健局ベースで独自に実施している。 予防接種実施記録は定型フォーマットがあり、ワクチン在庫管理簿もあり適切に管理が行われている。資機材管理点検システムもある。 モニタリングは適切に行われているが、課題は問題が発見された際に解決するための予算がないことである |
保健省が主体となり、UNICEF、WHOと共同して、県保健局レベルでモニタリング対象の県を無作為に抽出して実施。 予防接種実施記録は定型フォーマットがあり、ワクチン在庫管理簿もあり適切に管理が行われている。資機材管理点検システムもある。 |
保健省が主体となり、UNICEF、WHOと共同で実施。「母と子供の健康対策」については、郡レベルで実施。 予防接種実施記録は定型フォーマットがあり、ワクチン在庫管理簿もあり適切に管理が行われている。資機材管理点検システムもある。必須医薬品についても、オペレーショナル・ディストリクト医薬品倉庫で適切に在庫管理が実施されている。 |
EPIに関するモニタリングは確立されている。「母と子供の健康対策」については活動が始まったばかりで、まだ十分なモニタリング体制はない。 | 定期予防接種については、地方分権化が進展しているため、部ベースで独自に実施している。 末端レベルにおいてもワクチン、資機材は適切に管理されており、モニタリング体制に問題がない。 モニタリングは適切に行われているが、課題は問題が発見された際に解決するための予算がないことである |
(2) 実施の効率性
定量的なコストベネフィットの把握は本調査では不可能であったため、ここでは、主に現地調査における定性的な評価を試みた(表 3-5)。
現地ヒアリングによると、EPIプログラムに関してはICC会合を中心とした関係者会議で十分な協議が行われており、また実施体制は長年の実績の上に、各国で策定が義務付けられているEPI5ヵ年計画に沿ってほぼ確立されており、各プロセスはスムーズに流れており、効率性は概ね良好である。前出のアンケート結果においても、UNICEFとの連携に関しては比較的問題点を指摘する声は少なく、現地の声と一致している。ただし、「母と子供の健康対策」は1998年から始まったスキームで2001年度までに8ヵ国で実施されているが、調達はJICAが行う場合とUNICEFが行う場合があり、体制がまだ十分に確立されていない状態である。1)調達の遅れ、2)供与機材の多様化による事務量の増大、3)モニタリングの未実施、などの問題が指摘されている。カンボジアにおいては2000年度申請分の要請品目が多岐にわたっていたこと、カンボジア国内での調達が困難な品目があったこと、さらには調達価格が当初見積りより高くなったこと等により2001年度に繰越すことになり、その結果供与資機材の到着に18ヶ月の遅れが生じている。また、供与機材の選定の妥当性、調達など、ワクチン調達に見られるようなUNICEFの比較優位性は発揮されておらずやや効率性に欠ける部分が見られる。
その他問題点として、地方における配送・配布において、保健省予算の絶対的不足によるアクセスが困難な地域へのアウトリーチ率の低さ(ラオス)、コールド・チェーンのキャパシティの問題(ラオス、ヴィエトナム、ザンビア)、保健セクター改革と分権化が影響した地方保健当局のキャパシティの脆弱さ(ラオス、カンボジア、タンザニア、ザンビア)など外部条件による阻害要因が多く指摘されている。アンケート結果にある「資機材の配布・配送に対する相手国の実施体制が不十分である」という指摘は、この部分を指していると推察される。
また、カンボジアにおいてはBCGワクチンの廃棄率の問題が指摘された(86%)。これは一つのバイアルの容量が20回分と大きいことに比し、農村で行われるアウトリーチ接種活動では1バイアルを消費できるほどの接種人数を確保できず、またBCGワクチンは最後の使用から6時間経過後には廃棄する必要があるために、残ったワクチンを廃棄せざるを得ない結果であると説明された21。バイアルのサイズを小さくすれば、理論上廃棄率は改善されるが、逆にコスト高になるという面がある他、世界的にワクチンの供給量が減っているため、現場のニーズに応えるためにはいかなるサイズのバイアルであっても調達可能なものを購入せざるを得ない。この解決策として例えばアウトリーチ中心の活動からヘルスセンターでの定期接種を推進していくことが考えられる。ラオスにおいては、ADシリンジ(使い捨て注射器)の不法投棄の問題が指摘された。この問題に関しては保健省、UNICEFおよびWHOが共同で対策(高温度焼却炉の設置と適切な利用の徹底)を講じているところであり、今後の改善状況を見守る必要がある。
供与された資機材の活用状況モニタリングについては、現地調査およびアンケート調査では、現場担当者レベルでは実施されているとの認識である。UNICEF本部の話では、UNICEF駐日事務所が雛型を提示し各国事務所が現状をとりまとめ、駐日事務所と本部に送るシステムがあるという。しかし、その内容は「需要予測・物流管理・活動報告」にとどまっており、供与資機材の活用状況のモニタリング結果が、実施プロセス全体に還元されず、システムの効率化に十分に活かされていない22。また、それらのモニタリングについての結果報告は日本外務省へは正式に報告されていない。
(1) 策定過程
<意思決定機関レベル>
本スキームは1994年1月に、外務省技術協力課とUNFPA本部事務局次長によって取り交わされた合意確認書によって開始されている。対象国の選定などの企画段階からのUNFPAの関与はなく、マルチ・バイ協力実施に関しても定期的な年次協議は行われていない。UNFPA本部は本スキームの企画段階からの参加を望んでいるが、いまだ実現していない。
現場レベルでは、表 3-6にみるように、実施国によって実施主体、実施体制が異なる。
| ラオス | ヴィエトナム | カンボジア | タンザニア | ザンビア | |
| 実施年 | 2001年~ | 1998年~2001年 | 2000年~2003年 | 1997年~2000年 | 2000年~2003年 |
| 策定過程 | 保健省とUNFPAの合同で現状調査→ドナーを含む年次会議→RH計画策定→保健省内作業管理委員会で計画承認→保健省、UNFPAが申請案検討。 JICA事務所とUNFPA事務所間では定期協議はなく、必要に応じて協議。 |
人口家族子供委員会(CPFC)が実施主体。計画はUNFPAと共同で策定。 政策対話は行われていない。 |
保健省とUNFPAの協議により計画策定。政策対話は調整委員会(COCOM)では行われていない。 | GIIプロ形によって策定。 NGO(タンザニア家族計画協会:UMATI)とジョイセフの協調案件。関係5機関で覚書締結。UMATIが実施主体 UNFPAのカントリープログラムに含まれていないのが問題 |
難民居住区を対象。 現場ではYMCAが実施主体。 当初からUNFPA主体で案件形成。 本スキームに特化した政策対話の場は設定していない。UNFPAと保健省、JICAと保健省といった個別の場で調整。UNFPAとJICAとの定期協議はないが、コミュニケーションは活発。 |
| 要請 | JICA、保健省、UNFPAで申請内容協議→保健省が申請書作成→提出。 JICA側が供与額の約半分をプロ技の機材供与に使用しているのに対し、UNFPA側は、避妊具(薬)の供与のみを希望、引き続き調整が必要。 |
CPFCがA4フォーム作成→UNFPAチェック→JICA、計画投資省、在外公館へ提出。 初年度は、プロ技への活用考慮、それ以降はUNFPAのプログラムに沿って申請。 特に問題なし。 |
内容を保健省、UNFPA、JICAの3者で協議して決定→保健省がA4フォーム作成→提出。 特に問題なし。 保健省とUNFPAの関係良好。 WHOが保健省に対し政策面、マネージメント面での助言。 |
UMATI中心に現場のニーズに基づき策定→保健省→計画庁→大使館、JICAへ提出 JICA専門家(保健協力計画)の指導あり。 1999年度以降の要請は、同年実施の現状調査(後述)結果に基づいて作成。 UNFPAと保健省本庁との関与はほとんどなし。 |
UNFPA主導で申請書策定→保健省。 保健省の関与少ない。 要請書作成や資機材の妥当性の検証など、JICA事務所、UNFPAが多大な役割を担っており、職員の負担になっている。 |
| 調達 (現地調達を優先) |
調達はJICA。一部現地調達。通関手続きは保健省実施。 UNFPA側が希望する経口避妊薬はラオスで調達できず、第三国調達に変更(1年遅れの原因)。 現地調達については、現地業者の業務能力が低いため入札図書作成や手配にJICA職員が全面的に支援しており、大きな負担になっている→遅れの原因。 |
現地調達。 特に問題なし。 |
JICAが現地調達。2000年度資機材は2001年度に繰越。 | JICAが調達、一部を除きほとんど現地調達。 97年度以来、ほぼ1年遅れで到着・配布。 2000年度の申請リストは基礎的医療機材から消耗品まで77項目にわたり、現地調達でも手続きが煩雑なために多大な時間を要する。 要請から到着までに時間がかかる |
オランダからの第三国調達。 到着の遅延、調達数のミス、到着時に使用期限が半年の薬品、など問題が散見。 第三国調達は、効率性、正確性の点から課題がある。今後は基本的に現地調達を優先する方針。 |
| 配布 | 空港到着まではJICA、通関手続き以降は保健省。 中央資機材倉庫に運ばれ適正に保管・管理されている。在庫管理も問題なし。地方からの要請に従って配送される。 山間地への道路事情の悪さ、特に雨季には交通遮断地域あり。ただし、本スキームでは比較的アクセスが容易なところへ配布されており今のところ問題はなし。 |
空港到着まではJICA、通関手続き以降は保健省。 3ヶ所の保健省倉庫で保管・管理。在庫管理も問題なし。 省または郡への配布は年1回のみ。地方の倉庫容量からすると1年分の保管は厳しい。数回に分けての配布が望ましい。地方山間部への交通アクセスは困難なところもある。 |
現在までの供与資機材は現地調達。一旦保健省倉庫に保管。本件では未だ地方への配送実績はないが、他の医療品については、輸送を業者に委託している。 現在までに到着した資機材は、目的別に計画的に配布されている。 |
空港に到着後JICAとUMATIが検証。1回目は医療器具・薬品管理部を経由して地方へ配送。2回目以降、配送は民間業者に委託。各施設への配布はUMATIが行っている。 | 空港到着まではJICA,通関手続き以降はUNFPA、中央倉庫管理と地方への配送は保健省が担当。現地での配布はUNFPA、在庫管理・利用はYMCAが中心となっている。 |
| モニタリング | モニタリングはまだ実施されていない。JICAプロ技に供与されたものはJICA側で、避妊具(薬)についてはUNFPAが実施する予定。 | 98年度分はJICA負担、99年度、00年度分はUNFPA負担で、現地コンサルタントに委託し、評価調査実施中。(CPFCは関与していない)。しかし恒久的な体制は考えられていない。 | 資機材は届いたばかりで、未実施。UNFPAの見解では、保健省が実施し、UNFPAが支援する体制が望ましい。 | 1999年、JICAの発案・支援で、現状調査(対象78施設)を実施。 | YMCA中心に実施。UNFPAに対しても定期的にモニタリング報告を実施。内容は在庫管理と利用状況の把握。この報告を基に、UNFPAは「フィードバックレポート」を四半期ベースでJICA事務所に提出している。 |
(2) 実施の効率性
定量的なコストベネフィットの把握は本調査では不可能であったため、定性的な評価にとどめた(表 3-6)。
2,000万円という限度額の割に、総じて調整や手続きに係る事務量や各スタッフへの負担の膨大さが現地調査で指摘された。これは、制度の実績が少ないことに加えて、要請ベースで対応しようとしている点、現地調達を優先している点などがその要因と考えられる。
現地ヒアリング結果によると、5ヵ国中ヴィエトナム以外の4ヵ国で調達の遅れ(半年~1年半の遅れ)、調達上のミスなどが報告されている。ラオスにおいては、現地調達を行う予定でいたがUNFPA希望の仕様のものが調達不可能で第三国調達となったため2001年度申請分が2002年度供与となった。カンボジアにおいてはUNICEF連携の場合と同様の理由により、18ヶ月の遅れが生じている。またタンザニア・ザンビアにおいては要請機材が多岐にわたるために調達に手間取り、毎年度1年遅れで機材が到着しているということである。これらは、JICA側の予算時期による制約、申請手続きの煩雑さ、現地業者の入札業務能力の未成熟、現地事務所のキャパシティの問題や本スキームに対する不十分な理解、本部の対応の遅れなど、諸般の事情が指摘されている。特に、SWAPs推進国(タンザニア、ザンビア)においては、ニーズの積み上げ方式による要請に力点を置くあまり、現場の関係機関(特にUNFPA事務所、JICA事務所)に負荷がかかり、非効率的な面が指摘されている。
ヴィエトナムにおいては調達上の大きな問題は見受けられなかったが、これは申請資機材品目が比較的少なく、調達手続きが煩雑にならなかったことと、調達の際のJICA現地事務所と先方政府およびUNFPAの連携が適切に行われていたことによるものと考えられる。また、JICAのリプロダクティブ・ヘルス・プロジェクト(プロジェクト方式技術協力)がその設立以前より家族計画国際協力財団(ジョイセフ)のプロジェクトとしてUNFPA現地事務所と密な対話を重ねてきており、JICAとUNFPAとの連携を促進する上で重要な役割を果たしている。
資機材の活用状況モニタリングについては、現地調査およびアンケート調査から、保健省、UNFPAともに実施されているとの認識があるが、UNFPAではその認識がやや低い。UNFPA本部でのインタビューでは、「本スキームではUNFPAに全く資金が入らず、日本のバイの援助に対してUNFPAが資金も無いままにどのように関わってゆくのか不明であり、また日本側の調達のためクオリティの面でのUNFPA側のコントロールができない。」、「UNFPA本部はカントリープログラムに含まれていないことが、モニタリング等へのUNFPAの経費捻出を困難にしている要因となっている。」などを指摘している。
また、ラオスの例を見ると、人口家族計画分野の資機材(マルチ・バイ協力による供与資機材を含む)の活用状況モニタリングは保健省が行っているが、その報告書は母子保健センターレベルでとどまっており、JICAおよびUNFPAには提出されていない。
21 WHOでは、一度バイアルを開けても、一定の条件下(期限切れでない、バイアルが浸水していない、次回使用時まで4週間を越えない等)で冷蔵庫に保管すれば、次回に使用可という方法を推進し始めているが、これはある特定のワクチン(経口ポリオ、三種混合、破傷風、ジフテリア、B型肝炎など)のみ適用できるだけで、BCGや麻疹、黄熱病には適用できない。
22 この問題に対処するため、UNICEFでは2002年の雛型を改定している。

