3-2.マルチ・バイ協力の理論
マルチ・バイ協力の理論は、「スキームの明確化」、「各関係機関の政策・上位目標との整合性」、「マルチ・バイ協力の比較優位性」、「日本のプレゼンス」、「世界的潮流」の5つの観点から妥当性を評価する。
マルチ・バイ協力のスキームが明確になっているか、また、それらは関係者間で共有されているかを検証した。
最初に、本スキームに係わっている実施機関および関係者はその立場の違いによってマルチ・バイ協力への認識、評価が異なるため、ここで整理しておくと、表 3-1のようになる。
| 意思決定レベル | 現場レベル | ||
| UNICEF本部 | UNICEF駐日事務所 | UNICEF現地事務所 | 裨益国保健省UNICEF担当 |
| UNFPA本部 | UNFPA東京事務所 (2002年9月開設) |
UNFPA現地事務所 | 裨益国保健省UNFPA担当 |
| WHO現地事務所(WPRO) | |||
| 日本外務省 | 在外大使館 | ||
| JICA | 在外事務所 | ||
本スキームに関する意思決定レベルにおいては、本スキームの目的、意義、役割分担等が概念的には整理され、共有されているといえる。
UNICEF連携マルチ・バイ協力においては現場レベルにおいてかなり役割が明確になっている。しかし、UNFPAとの連携では、保健省において「システムに対する理解度」や「役割の明確さ」が低い(図 3-3、図 3-4)。これは、タンザニアのように保健省が実施主体になっていない国があることが一因と考えられる。加えて、UNICEFに比べマルチ・バイ協力を通しての日本との協力実績が少ないこともあって、UNFPAでは各関係者の役割の整理が十分でないこともその理由の一つであろう。
UNFPA連携マルチ・バイ協力では、UNFPA側は資機材の「通関→保管→配布」サイクル全体を運営管理することになっているが、UNFPA東京事務所は、資機材の「調達」を日本側が行うことになっているために、資金の流れがUNFPAを通らないまま、日本側が調達した資機材をUNFPAが「通関→保管→配布」することに対して疑問が生じたとして、スキームの位置付けがいま一つ不明確であるために、UNFPA側の当事者意識が失われたことを指摘している。また、UNICEFがスキーム策定段階から積極的に関与し、日本と共同で作り上げてきた経緯があるのに対して、UNFPAは既に日本とUNICEFとの間で出来上がったスキームを応用する立場にあったため、スキーム策定段階への関与が希薄であった点も大きい。
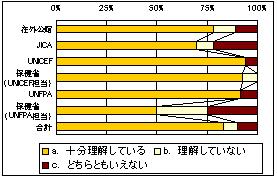 |
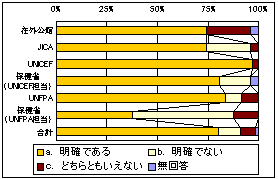 |
| 図3-3 マルチ・バイ協力のシステムに対する理解度 | 図3-4 マルチ・バイ協力における各機関の役割の明確さ |
(1) 世界的潮流との整合性
1980年代末から1990年代にかけて国際的なドナー社会は、これまで一向に成果があがらない経済成長に偏重した援助を反省し、貧困削減を中心課題に据えた「個の重視」への援助へと大きく方針を転換している。1996年の開発援助委員会(DAC)上級会合において採択された「21世紀に向けて:開発協力を通じた貢献(通称「DAC新開発戦略」)」はその流れのなかで数値目標を示し、2000年9月の国連総会で採択されたミレニアム開発目標(MDGs)は基本的に「DAC新開発戦略」の目標を拡充したものである。マルチ・バイ協力は「健康は、全ての人が望む欲求であり、地域社会、国家という大きな社会単位、ひいては地球規模でも、健全な社会形成を進めるためには不可欠な要素12」であることを基本理念としており、ミクロからのアプローチという点で世界的な潮流と合致しており、またその分野も世界的潮流の中に包含されるものである。
|
||||||||||||||||||||||||
また、そもそもUNICEF連携のマルチ・バイ協力は、WHOが1974年に予防接種拡大計画(Expanded Program on Immunization: EPI)を決議し、世界中のすべての子供がジフテリア・百日咳・破傷風・麻疹・ポリオ・結核の6大疾患の予防接種が受けられるよう推進しており、1988年の第41回WHO総会において「2000年までにポリオを地球上から根絶する」という目標を掲げたことを背景に開始されたものである。なお、当時日本は消耗品をバイ協力では供与できないとの原則があったため、マルチ・バイ協力によりUNICEFと連携することで消耗品の供与が可能となった。
一方、1994年9月カイロにおいて開催された「国際人口開発会議(International Conference on Population and Development: ICPD)において、人口問題に対するアプローチはリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康/権利)が中心概念となったことにより、人口政策の焦点がマクロ(国レベル)からミクロ(個人レベル)へと大きくシフトした。UNFPA連携のマルチ・バイ協力は、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツに配慮した家族計画の普及を図るとともに、人口増加率の根本的原因となっている高い乳幼児・妊産婦死亡率、劣悪な環境衛生、低い教育水準、低い女性の社会的地位などの問題を解決する13」ための協力とされており、人口分野の世界的潮流にも合致している。
(2) 日本の援助政策との整合性
まず最初に、我が国のODA政策の基本方針である「政府開発援助大綱」(1992年6月30日閣議決定)は、ODA重点項目として5項目を挙げており、その一つは、「地球的規模の問題への取組み」、「基礎生活分野(BHN)等」であり、これは先に整理した「マルチ・バイ協力のロジックの流れ」の、中期的・長期的アウトカムと一致している。この方針は1998年1月に発表された「21世紀に向けてのODA改革懇談会」(最終報告要旨)においても貫かれ、この最終報告書は「ODAが実現すべき目的」の基本認識として3点を挙げ、その一つとして、「地球的課題の克服」として、「人間の安全保障」といった観点から、人口爆発、エイズなどの感染症への対応の重要性を示している14。
こうした流れの中で、我が国は「人口・エイズに関する地球規模的イニシアティブ(Global Issues Initiative on Population and AIDS: GII)」(1994年2月)を発表した。これは日本が国際社会に対して初めて特定分野の国際協力戦略を打ち出したものであるといえよう。GIIは、人口・家族計画への直接的協力に加え、女性と子供の健康に関わる基礎的保健医療、初等教育、女性の地位向上等、いわば間接的に人口・エイズの抑制に資する協力も含めた包括的アプローチをとっている。従って、UNFPA/ UNICEF連携のマルチ・バイ協力がGIIの中に位置付けられることは明らかであろう。タンザニア国ではGIIの一環としてプロジェクト形成調査団が派遣され、UNFPA連携マルチ・バイ協力が開始されている。また、UNFPA連携のマルチ・バイ協力は、日本は消耗品をバイ協力では供与できない原則がありながら、GIIにより日本も消耗品に対する支援が必要となってきたことの背景から生み出されたスキームである。
GII終了に引き続き、日本は2000年7月の九州・沖縄サミットで、「沖縄感染症対策イニシアティブ(Okinawa Infectious Diseases Initiative: IDI)」を発表した。IDIは、GIIにおける取組みの延長線上という位置付けの下、(HIV/AIDS、結核、マラリア・寄生虫およびポリオを中心とした)感染症の問題を貧困削減の中心課題の一つとしている。本スキームもこの戦略に合致したものであると位置付けられる。
(3) 国連機関(UNICEF/UNFPA)とのカントリープログラムとの整合性
マルチ・バイ協力は、UNICEF、UNFPAともに各国のカントリープログラム15の目指すべき方向性にはほぼ合致している(図 3-5)。例えば、ザンビアにおけるUNFPAとのマルチ・バイ協力では難民居住地への協力を行っており、ザンビア保健省の関与はほとんどないものの、UNFPAのカントリープログラムに組み入れられているため、JICA、UNFPA双方で重要性の高い事業と認識されており、UNFPA主導で順調に運営されている。一方、タンザニアにおけるUNFPAとのマルチ・バイ協力のように、案件形成時には関係機関との十分な協議の基に「覚書」が交わされ、各機関の役割が明記されたにもかかわらず、UNFPAのカントリープログラムに盛り込まれていないために、いざ協力が始まると役割分担が「覚書」通りには機能しなかった。カントリープログラムの中に盛り込まれていないために、運営予算が捻出できず、必要なスタッフの配置がなされず、担当するスタッフにとっては本来業務以外の位置付けとなり、大きな負担となっている。また、担当スタッフのTORが設定されず、効率性を欠く原因ともなっていた。これらの事例から、マルチ・バイ協力は基本的に国連機関のカントリープログラムとの連携によって機能するスキームであり、カントリープログラムへの設定は必須であろう。
マルチ・バイ協力をUNFPAのカントリープログラムに組み入れることが難しい理由として、UNFPA東京事務所は、日本の資金協力が単年度予算で組まれているが、UNFPAのカントリープログラムは4~5年で策定されていることを指摘している。
(4) 被援助国の保健政策・ニーズとの整合性
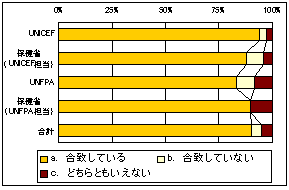 |
| 図3-5 マルチ・バイ協力と保健プログラムの合致度 |
(1) 消耗品の供与
他のスキームと比較し、マルチ・バイ協力の優位性としてまず挙げられるのは、これまでニーズが高いにも関わらず日本が供与することができなかったワクチンや避妊具(薬)の供与が可能となったことである。ICPDの公約に基づいた国際社会からの援助が、現状では十分に得られていないことから、今後も圧倒的な不足が予想されている避妊具(薬)(4章、図 4-1)への援助を行っていく意義は非常に大きい17。また、今日では無償資金協力によって消耗品の供与が可能となっているが、マルチ・バイ協力はそのための扉を開いたといえよう。ただし、1993年から無償資金協力18で消耗品の供与が可能となったことで、当時の「消耗品供与が行える唯一の手段」という魅力は失われつつある。
他方、無償資金協力を除くバイ協力を考えた場合、資機材供与が可能なのは、機材供与事業のみである。ただし、この事業は、個別派遣専門家、青年海外協力隊員が任国において技術協力活動を行うに際して必要な機材、および各国からの研修員がそれぞれの国に帰国した後に日本での研修により習得した技術を普及させるに際して必要な機材を供与することを目的としており、単独で消耗品を供与するには、別途専門家等の人的投入を行う、またはより多くの現地職員に対して日本での研修を行わなければならず、コストも時間も多く必要であることは明らかであることから、機材供与事業によってマルチ・バイ協力と同等に消耗品を供与することは困難と考えられる。
(2) 国連機関(UNICEF/UNFPA)との連携による比較優位性
現地調査結果から各国政府・関係者は国連機関に対して信頼感を持っており、その信頼感をベースとして本マルチ・バイ協力がスムーズに実施されているという強い印象を得た。何よりも、国連機関に対する信頼感を媒体として各国における本協力が運営されている点は、本スキームの前提であり狙いであることから、その点に関してはバイ協力と比較して優位性を発揮していると高く評価できる。
技術的比較優位性に関しても、UNICEF/UNFPAはその担当する分野において長期にわたる経験があり、そのノウハウの蓄積があることから、非常に高いといえる。特にUNFPAの対象とする人口家族計画分野においては、農業や鉱工業など他の分野と比べて日本の協力実績が少ない分野であり、また人材も限られているため、この分野での協力の可能性が広がった意義は大きい。
調達に関しては、UNICEFは世界のワクチンの40%を調達しているという実績をもち、その信頼性は極めて高い。またポリオをはじめとする感染症のワクチンは、近年製薬会社にとって製造販売するメリットが少なくなり19製造を中止するところが多くなってきている中で、UNICEFとしてはその対策として、世界的なワクチン需要を一括して大量発注することで製薬会社のインセンティブを高め、安定的かつ安価にワクチンを確保することを可能としている。一方、UNFPAの方は、避妊具(薬)の安価な調達が可能であり、優位性を有しているといえる(表 3-3)。しかしながら、現在は改善されつつあるものの、以前はUNFPAの希望した避妊具(薬)の仕様が日本製品の規格や薬事法に合わなかったために、その供与の多くが見送られた経緯がある。途上国のニーズが避妊具(薬)に特化されず、多様なニーズがあるため、リプロダクティブ・ヘルス分野に高い専門性を有するUNFPA側からすれば、その比較優位性を十分に活かせないでいる。しかし、リプロダクティブ・ヘルスにおいては、避妊具(薬)の他にも様々な援助ニーズがあることはこれまでの協力実績で明らかである。
UNFPAとの連携においては、JICA調達を前提としているが故に、日本としては係る資機材の選定やモニタリング等に関するアドバイス等ソフトな連携を求めたと考える。ただし、UNFPAとの連携を考えるのであれば、UNFPAの技術的比較優位性を十分に活かせる連携を今後考えるべきであろう。
|
|||||||||||||||||||||
| 注)注射薬は注射器と針を含む。
UNFPAの価格は製品会社との長期契約価格。 USAID価格は"USAID 2002 Contraceptive Procurement Guide and Product Catalog"に基づく。 表はメーカーに関わらず、最も安価な避妊具(薬)の価格で示した。 |
|||||||||||||||||||||
| 出所:UNFPA作成資料 |
(3) その他
今回の現地調査で、例外的にザンビアではUNFPA現地事務所の協力で日本政府が直接関与することが困難な地域(難民居住地)への介入が行われており、ある意味で日本の援助の守備範囲を広げる可能性のヒントとなっている。
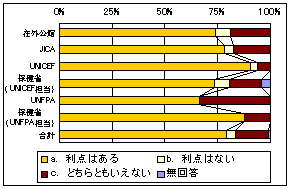 |
| 図3-6 マルチ・バイ協力における 他のスキームと比較した利点の有無 |
一方、今回現地調査のタンザニアやザンビアの見られたようにSWAPs先進国においては、ドナー協調の進む中、コモン・バスケット方式を取り入れており、そこではUNICEF/UNFPAとの連携を軸とした本スキームの位置付けが難しく、JICA現地事務所は苦慮している。
(1) スキームとしての認知度
日本のプレゼンスをみるにあたり、関係機関におけるマルチ・バイ協力事業の認知度が参考になる。
これまでのUNICEFに対する協力は13年間で35ヵ国に総額約101億円(2001年まで)を供与しており、現在では年額が約10億円超の規模となっている。また、UNFPAとの連携は1994年20に始まったが、8年間で19ヵ国に約14.6億円を供与している。一方、各国レベルでみると、援助限度額はUNICEFが年間4,000万円まで、UNFPAが年間2,000万円までと、他のスキーム(無償や技術協力)に比べるとかなりの小額である。
供与額の少なさが必ずしも本スキームの認知度を左右する要因にはならないが、無償資金協力による大規模な資機材供与があるような国では、現地保健省担当者が「マルチ・バイ協力」スキームという名称を知らず、他のスキームの一部と認識している事実(ラオス)もある意味でいたしかたないと考えざるを得ない。従って、他のスキームと比較して供与額が小額である本スキームの認知度を上げるには、マルチ・バイ協力事業が単なる資機材供与事業ではなく、日本、先方政府および国連機関(UNICEF/UNFPA)のそれぞれの優位性を活かした、特色のあるスキームであることを先方政府、国連機関等関係者に十分に理解してもらうことが必要であろう。
(2) ヴィジビリティの確保
「日本のプレゼンスの向上」も、一つの波及的なアウトカムとしてとらえることができる。「日本のプレゼンスの向上」のための一つの手段としてヴィジビリティを高めることがある。そもそも本スキームにおいては直接的にヴィジビリティを高めることを必ずしも重視していない。しかし、UNICEFは日本のヴィジビリティ確保に配慮はしており、供与機材の引渡し時のセレモニーやメディアの活用、キャンペーン用Tシャツの配布、供与機材の梱包に日本のODAシールを添付するなどの対応をしている。例えばザンビアでは、ヘルスポストのスタッフがJICAを含む各ドナーのロゴ入りエプロンや帽子を着用するなど、認知度の向上に努めている。しかし、セレモニーによる中央の首脳陣への認識を高めたり、テレビやラジオ活用による一般への広報は未だ限定的であり、またODAシールはコールド・チェーン機材には貼付されるものの、配布の中間過程で梱包が解かれると、細かな供与機材は小口に分けられ、その時点以降、関係者にとっては、UNICEFやUNFPAから来た供与物資として認識されているのが現状である。
そもそも日本のプレゼンスを高めるためには、もっと根本的な戦略を明確に打ち出す必要がある。UNICEF連携のマルチ・バイ協力のように、ポリオ根絶などのわかりやすいアウトカムの設定と目標達成によって日本の高いプレゼンスを発揮できると考えるべきであろう。その意味では、UNFPA連携の場合は、UNFPA自身の目標であるリプロダクティブ・ヘルス/ライツに対しては、感染症に対するワクチンのような「特効薬」がなく、末端レベルの関係者に対しては分かりやすい目標を設定しにくいという課題を抱えている。
12 JICA医療協力部パンフレット「自立への支援」より抜粋。
13 JICA医療協力部パンフレット「自立への支援」より抜粋。
14 『我が国の政府開発援助 上巻』(2000年)外務省経済協力局編。
15 被援助国に対する国連機関の5ヵ年の援助方針。
16 Sector Wide Approaches;個々の援助国が独立のプロジェクトを独自に実施しても効果は限られること、維持・管理や人件費の手当に困難を来たしている途上国が多いことなどから、全国民を対象にサービス提供のシステムを構築することが不可欠な保健や教育などの分野について、途上国政府が援助国、国際機関等と緊密に協議・調整の上開発計画を策定し、このような計画に沿って開発や援助を進めていくという「セクター・ワイド・アプローチ」の試みがアフリカ諸国を中心として行われている。(「我が国の政府開発援助(2000年)」)
17 ICPD(1994)において、各国は基本的なリプロダクティブ・ヘルスと人口のプログラム実施のために2000年に必要になる170億ドルの1/3、すなわち57億ドルを国際社会が提供することで合意した(残り2/3は援助を必要とする国自身が拠出)。2000年にはプログラムの支出総額は109億ドルで、援助額は総計でわずか26億ドルであった。これは支出合計の1/4以下であり、公約した金額の半分以下であった。(世界人口白書、2002)
18 中国へポリオワクチンの供与実績あり。
19 非常に安価であり、また根絶に向かっているため需要が減少する傾向にあり、製薬会社にとって製造を続けるメリットがない。
20 UNFPA連携マルチ・バイ協力の資機材供与は1995年から開始された。

