第3章 評価結果
3-1.マルチ・バイ協力のロジックの整理
2章で概観したように、マルチ・バイ協力の開始にあたり「日本とUNICEF」および「日本とUNFPA」の間で取り交わされた合意文書10には、それぞれの国連機関との協力の目的と実施におけるガイドラインが定められている。従ってスキームのねらいとしている目的、アウトラインはある。しかし、各裨益国レベルでみると、マルチ・バイ協力が最終的に何を目指した事業であるのか、マルチ・バイ協力の目指すべき“目標”や“ロジック”が明確になっておらず、現地JICA事務所、UNICEF/UNFPA各現地事務所、保健省等関係者間で共有されていないのが現状であった。
そこで本評価を行う最初のステップとして、プログラムセオリーに基づいて、各裨益国レベルでマルチ・バイ協力が何を目標として、どのようなロジック(因果関係)に基づいて実施されているのかを整理した。既存資料、関係者ヒアリング、アンケートなどを基に作成した「ロジックの流れ」が図 3-1、図 3-2ある。被援助国における理論過程として、「投入→活動→結果→アウトカム(成果)」という大きな目標体系に整理した。実際UNICEFにおいては、各国ごとに予防接種5ヵ年計画が策定されている。
このように、国連機関のプログラムを骨格とする目標体系を設定することは可能であるが、マルチ・バイ協力はこれらのUNICEF、UNFPAにおける投入・活動の中ではほんの一部に過ぎず、アウトカムレベルの指標に変化があったとしても、それがマルチ・バイ協力の貢献であるかどうかを検証することは難しい。従って、本評価においては基本的に、直接の因果関係が特定できるアウトプットレベルまでを実証的な評価の対象とし、アウトカムレベルは参考程度にとどめることとした。
また、この「ロジックの流れ」に基づき、「理論」、「プロセス」、「効果」の観点から評価を行った。基本的には5ヵ国の現地調査を基に評価を行ったが、5ヵ国のケーススタディを補完し、一般化するために、マルチ・バイ協力全実施国についてのアンケート調査結果11を用いた(詳細は付属資料参照)。
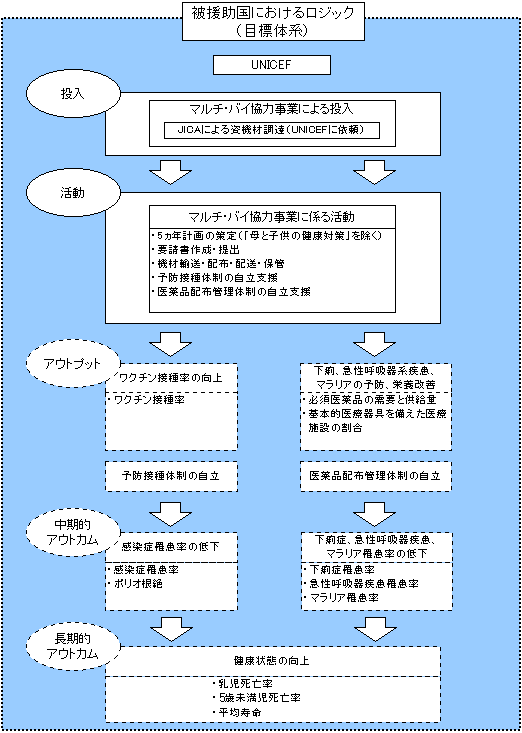
図3-1 UNICEF連携マルチ・バイ協力のロジックの流れ
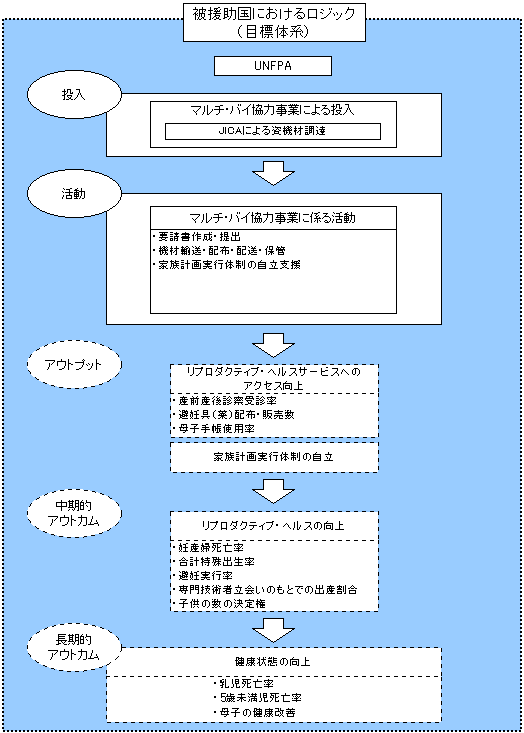
図3-2 UNFPA連携マルチ・バイ協力のロジックの流れ
10 UNICEFとの1990年6月4日付け合意文書:Confirmation of Cooperation, MULTI-BI Cooperation between the Government of Japan and UNICEF in EPI (Expanded Programme on Immunization)
UNFPA との1994年11月18日付け合意文書:Confirmation of MULTI-BI Cooperation between the Government of Japan and UNFPA
11 全体の有効回収率は56%と高くはないが、現地調査結果と同様の傾向を示しており、傾向を概観するには妥当と判断した。

