2-3.マルチ・バイ協力の流れ
UNICEFとUNFPAとのマルチ・バイ協力の流れには大きな相違点がある。この相違は、主に調達方法と扱う供与機材品目の2つに起因している。まず調達方法については、UNICEFとのマルチ・バイ協力ではワクチンなどの調達から当該国への運搬までの過程をUNICEFに任せているが、UNFPAとのマルチ・バイ協力では、人口・家族計画に関わる供与資機材などの調達をすべて日本側(本邦調達の場合と現地調達の場合がある)が実施することになっている。この背景には、UNICEFは援助実施機関としての十分な経験を有しており、またUNIPACと呼ばれるUNICEF物資センター(コペンハーゲン)を有し、大型機材からワクチンのように特別な保存設備を必要とする医薬品まで様々な物資を取り扱うことが可能であるが、UNFPAは基金・資金供与機関としての機能が主であり、援助実施機関としての経験は浅いなど、UNFPAに調達を任せるうえでの比較優位性が協力開始当初に認められなかったためである。また取り扱う供与機材品目についても、UNCEFの場合はワクチンや注射針などの医療機材を本邦調達よりも安価で確実に調達できるという比較優位性が協力開始当初の調査で明らかとなっていた。一方、UNFPAの場合は、「日本で認可されていない避妊具・避妊薬は利用されるのが日本でなくとも供与できない」という日本側の原則に加え、当初の供与品目が視聴覚機材などに偏らざるを得なかった事情により、特にUNFPA経由の調達に比較優位性がないとの判断がなされた。この他、途上国地域における援助実績、人材・組織規模(含む現地事務所の機能・人員)にも違いがある。上記を踏まえて、ここではUNICEFとUNFPAを分けて、マルチ・バイ協力の流れを示す。
2-2-1項で言及したUNICEFとのマルチ・バイ協力における取り扱い要領(EPI)には、図 2-1のような概念図が示されている(但し、一部調査団が加筆)。
以下に、「EPI」を例に、5ヵ年計画の作成から活用状況報告までの一般的な実施プロセスを示す(注)取り扱い要領より一部抜粋)。
(1)5ヵ年計画と要請書(A4フォーム)の作成・提出 - 当該国の保健省などがUNICEF、WHO/WPRO各事務所(WPRO管轄地域のみ、以下同様)の指導を得ながらEPI(予防接種拡大計画)にかかる5ヵ年計画を策定し、在外公館に提出する。この5ヵ年計画に基づき、保健省などは各年毎に要請書(A4フォーム)を作成し、在外公館に提出する。
- また、UNICEFは駐日事務所へ、WHO/WPRO各事務所はWHO/WPRO本部へ、A4フォームのアドバンスドコピーを送り、チェックを受けたあとに被援助国から在外公館へ提出するという手順を踏んでいる。事前に被援助国、国連機関(UNICEF、WHO/WPRO)で申請内容のチェックを行い、効率化を図っている。
- また、UNICEFは駐日事務所へ、WHO/WPRO各事務所はWHO/WPRO本部へ、A4フォームのアドバンスドコピーを送り、チェックを受けたあとに被援助国から在外公館へ提出するという手順を踏んでいる。事前に被援助国、国連機関(UNICEF、WHO/WPRO)で申請内容のチェックを行い、効率化を図っている。
(2)当該年度計画策定協議の実施 - 外務本省からの正式採択通報を受け、現地JICA事務所、UNICEF現地事務所、WHO/WPRO各事務所は連携し、先方政府と協議した上で、先方政府の要請書作成をサポートする。供与機材に関する仕様、および数量について、また正式要請書の素案段階で、要請機材についての仕様目的、配置場所など、案件の妥当性に関する重要な要素は要請書の別紙で明らかにされる。
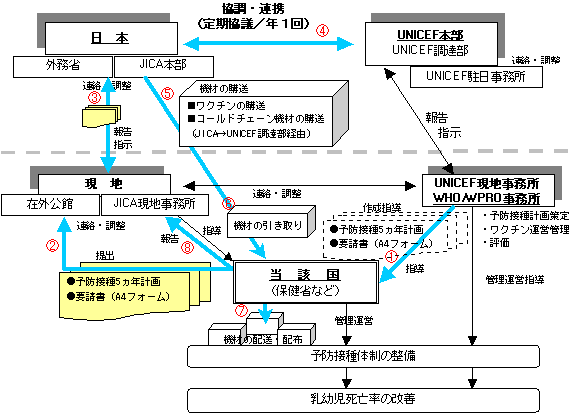
図2-1 UNICEF連携マルチ・バイ協力実施概念図 (3)要請書の受理と送付 - 在外公館は、受理した5ヵ年計画および要請書を、本省に送付する。
(4)日本政府外務省による要請書の確認 - 本省は、要請書をJICA本部に送付の上、供与品目などの検討を依頼する。JICA本部は供与品目、数量を必要に応じてUNICEF駐日事務所やWHO/WPRO等と精査、確認した上で、外務省(本省)に対して本件の実施協議を行う。これをうけ、外務本省は、供与品目・数量、供与額などを最終決定し、JICA本部に通報すると共に在外公館にも通報する。
(5)機材の購送 - JICA本部はUNICEFへ発注後、機材の購送進捗についてUNICEF調達部を通じて、当該国在外公館、JICA事務所(または当該国を所管するJICA事務所)の他、UNICEF駐日事務所およびUNICEF現地事務所に通報する。JICA事務所がない国については、当該国在外公館がUNICEF現地事務所と相談の上、先方政府機関に通報する。
機材の引き取り - 先方政府が機材の検品、保管およびその他の業務を行い、UNICEF現地事務所、WHO/WPRO各事務所並びに在外公館、JICA現地事務所が必要に応じて側面的に支援する。また、引渡し式典などの実施に際し、在外公館、JICA事務所、UNICEF現地事務所並びにWHO/WPRO各事務所は連携し、協力について適宜プレスなどに広報する。
(6)機材の配布・配送および保管 - 先方政府は、供与機材が計画された場所へ迅速かつ効果的に分配されるための輸送業務を行うことについて主たる責任を担い、在外公館、JICA現地事務所、UNICEF現地事務所並びにWHO/WPRO各事務所の協力を得て配布を行う。
(7)機材の活用状況についての報告 - 先方政府は、UNICEF現地事務所並びにWHO/WPRO各事務所の協力を得て供与機材の活用状況を取りまとめ日本側に報告する。UNICEF現地事務所およびWHO/WPRO各事務所は、この活用状況に対する報告に基づき、先方政府を適宜指導し、指導内容についても日本側に報告する。在外公館およびJICA現地事務所は必要に応じ指導にも参画し、相手国政府からの提出報告と合わせて本省およびJICA本部に報告する。
- 注)国々が広く点在している太平洋諸国のように、連携を強化するために地域会議や合意形成など相互協調を図るために独自の手段を取っている地域もある。
2-2-2項で言及したUNFPAとのマルチ・バイ協力における実施要領には、図 2-2のような概念図が示されている(但し、一部調査団が加筆)。
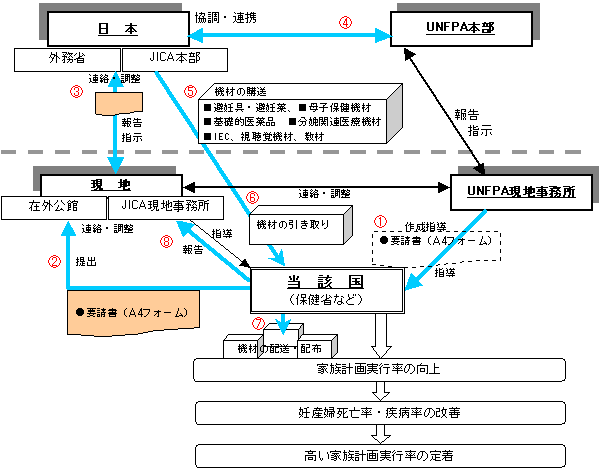
図2-2 UNFPA連携マルチ・バイ協力実施概念図
以下に、要請書の作成から活用報告までの一般的な実施プロセスを示す(UNFPAとの取り扱い要領を参考とした)。
(1)要請書(A4フォーム)の作成・提出 - 当該国の保健省などがUNFPAの指導を得ながら各年毎に要請書(A4フォーム)を作成し、在外公館に提出する。
(2)当該年度計画策定協議の実施 - 外務本省からの正式採択通報を受け、現地JICA事務所、UNFPA現地事務所が連携し、先方政府と協議した上で、先方政府の要請書作成をサポートする。供与機材に関する仕様、および数量について、また正式要請書の素案段階で、要請機材についての仕様目的、配置場所など、案件の妥当性に関する重要な要素を要請書の別紙で明らかにする。
(3)要請書の受理と送付 - 在外公館は、受理した要請書を本省に送付する。
(4)日本政府外務省による要請書の確認 - 本省は、要請書をJICA本部に送付の上、供与品目などの検討を依頼する。JICA本部は供与品目、数量を精査、確認した上で、外務省(本省)に対して本件の実施協議を行う。これを受け、外務本省は、供与品目・数量、供与額などを最終決定し、JICA本部に通報すると共に在外公館にも通報する。
(5)機材の購送 - JICA本部は資機材を調達・輸送する(本邦調達と現地調達の場合がある)。機材の購送進捗について、当該国在外公館、JICA事務所(または当該国を所管するJICA事務所)、UNFPA現地事務所に通報する。JICA事務所がない国については、当該国在外公館がUNFPA現地事務所と相談の上、先方政府機関に通報する。
(6)機材の引き取り - 先方政府が機材の検品、保管およびその他の業務を行い、UNFPA現地事務所、在外公館、JICA現地事務所が必要に応じて側面的に支援する。また、引渡し式典などの実施に際し、在外公館、JICA事務所、UNFPA現地事務所は連携し、協力について適宜プレスなどに広報する。
(7)機材の配布・配送および保管 - 先方政府は、供与機材が計画された場所へ迅速かつ効果的に分配されるための輸送業務を行うことについて主たる責任を担い、在外公館、JICA現地事務所、UNFPA現地事務所の協力を得て配布を行う。
(8)機材の活用状況についての報告 - 先方政府は、UNFPA現地事務所の協力を得て供与機材の活用状況を取りまとめ日本側に報告する。UNFPA現地事務所は、この活用状況に対する報告に基づき、先方政府を適宜指導し、指導内容についても日本側に報告する。在外公館およびJICA現地事務所は必要に応じ指導にも参画し、相手国政府からの提出報告と合わせて本省およびJICA本部に報告する
- また、先方政府は日本やUNFPAなどの指導を受けつつ、家族計画の啓蒙・普及・母子保健活動を推進する。

