2 マルチ・バイ協力の概況
2-1 マルチ・バイ協力の経緯
UNICEF連携のマルチ・バイ協力は、世界保健機構(以下、WHO)が1974年に予防接種拡大計画(Expanded Program on Immunization: EPI)を決議し、世界中のすべての子供がジフテリア・百日咳・破傷風・麻疹・ポリオ・結核の6大疾患の予防接種が受けられるよう推進していること、1988年の第41回WHO総会において「2000年までにポリオを地球上から根絶する」という目標が掲げられたことが背景にあって開始された。また、当時日本は消耗品を二国間協力(Bilateral Cooperation)では供与できない原則があったが、マルチ・バイ協力はUNICEFが実施しているプログラム(Multilateral Cooperation)と連携することによりワクチンなどの消耗品の供与が可能となった最初のスキームである。
一方、1994年9月カイロにおいて開催された「国際人口開発会議(International Conference on Population and Development: ICPD)において、人口問題に対するアプローチはリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康/権利)が中心概念となったことにより、人口政策の焦点がマクロ(国レベル)からミクロ(個人レベル)へと大きくシフトした。リプロダクティブ・ヘルスの向上のためには、避妊具(薬)などの消耗品が必需品であり、またそのニーズも高い。UNFPA連携マルチ・バイ協力も、これまで我が国の機材供与の対象とはしていなかった消耗品、すなわち避妊具(薬)、その他簡易医療機材などを機材供与することを目的に開始された。
以上のような経緯で実施されるに至ったUNICEFおよびUNFPAとの連携によるマルチ・バイ協力の特徴をまとめると、(1)国際社会が協調して取組むべき課題に国連機関と連携・協調することで、(2)消耗品の供与などこれまで我が国のODAが認可していなかった二国間協力(機材供与)の形を可能とし、さらに(3)供与機材が効率的かつ効果的に当該国で使用されることで、(4)日本の貢献が広く認識され、途上国におけるプレゼンスを高めようとする日本側のねらいから生まれたスキームといえよう。同時に、UNICEF/UNFPAにとっても、日本が明確に両機関が実施するプログラムに参加することでプログラムの実施が促進されるとともに、資金面に余裕が生じるなどのメリットがある。
2-2 マルチ・バイ協力の実施プロセス
今回評価の対象としたマルチ・バイ協力の概要を表 2-1に示す。
UNICEF連携
|
||||||||||||||||
UNFPA連携
|
||||||||||||||||
UNICEF連携では「感染症対策特別機材供与1」と「母と子のための健康対策特別機材供与」が、UNFPA連携では「人口・家族計画特別機材供与」が実施されている。要請書の作成や資機材の配送・配布・保管などの実施主体はあくまでも当該国であり、UNICEF/UNFPAはそれぞれのプロセスにおいて適切なサポートをすることとされている。またUNICEFとUNFPAとのマルチ・バイ協力におけるプロセスの大きな相違点として挙げられるのが、UNICEFとのマルチ・バイ協力ではワクチンなどの資機材の調達から当該国への運搬までの過程をUNICEFに一任しているが2、UNFPAとのマルチ・バイ協力では、人口家族計画に関わる供与資機材などの調達をすべて日本側(本邦調達の場合と現地調達の場合がある)が実施することになっている点である。
2-3 マルチ・バイ協力の実績
我が国とUNICEFとのマルチ・バイ協力は1989年から実施が始まり(2002度で14年目)、延べ35ヵ国を対象に協力が行われてきた。また、UNFPAとの連携は1995年(合意確認書の取り交わしは1994年)からで、19ヵ国を対象に協力が実施されてきた。図 2-1は、UNICEFおよびUNFPAとのマルチ・バイ協力の実績を年次別に示したものであるが、これによると、マルチ・バイ協力はスキーム開始当初から順調にその実績を伸ばしてきたことが分かる。特にUNICEF側の実施額の伸びは大きく、ポリオ対策への協力が開始された1993年度以降急速にその実施額が大きくなり、1996年をピークに一時減少傾向にあったが、特定感染症への協力が始まり再び上昇傾向にある。一方UNFPAの予算の延びは緩やかなものである。このため、UNICEFとUNFPAとのこれまでの実施総額(累計)を比較すると、UNICEFが総額101.6億円、UNFPAが総額14.6億円と日本側の投入金額にはかなりの相違がある。
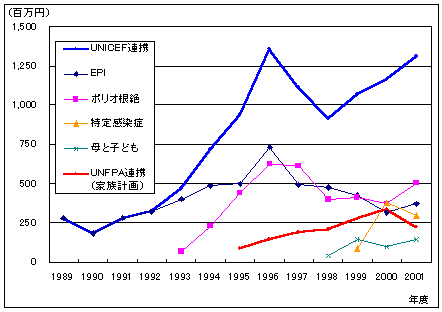
図2-1 UNICEFおよびUNFPAとのマルチ・バイ協力における年次別実績の推移
地域別のマルチ・バイ協力における実施額(累計)は、UNICEFおよびUNFPAともにアジア地域への協力が過半数以上、またアフリカ地域については約4割程度と同じような傾向を示している。しかしながら、UNICEFの場合は協力の対象別にみていくと、ポリオ根絶に関しては約7割がアジアを対象としており、「アジア地域のポリオ根絶」という日本側の明確な方針の下でマルチ・バイ協力が実施されてきたことがわかる。
1 「EPI」、「ポリオ根絶」、「特定感染症」の3種類が実施されている。また「特定感染症」としては、これまで「麻疹」、「新生児破傷風」、「リンパ性フィラリア」が実施されている。
2 ただし「母と子供のための健康対策特別機材供与」は日本側の調達である。

