第6章 シンクタンクによる評価
金融セクター(フィリピン)
| ■ | 三和総合研究所 | 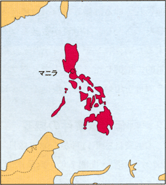 |
〈評価対象プロジェクトの概要〉
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、期間、金額 | プロジェクトの概要 |
| 金融セクター借款 | 有償資金協力 | 89年度、89年~93年 400億円 |
我が国は、1980年代の金融危機後のフィリピンの金融セクターの脆弱性の改善を目的として、世界銀行と協調し、同国金融セクターに対する構造調整融資を行った。 |
1.調査のフレームワーク
本調査は、1989年11月から93年12月の間にフィリピン共和国に対して行われた金融セクター構造調整融資が、同国の金融セクターの問題解決にどの程度寄与し、その後の経済成長にどの程度貢献したかを検証することを目的としたものである。
融資開始当時のフィリピンは1980年代前半の金融危機から立ち直るべくIMFの支援の下で二大政府系金融機関であるDBP・PNBの改革を経て(86年~87年)いたが、なお中央銀行の監督能力の低さや民間金融機関の信頼性欠如、長期融資機能の欠如といった問題を抱える状況であった。本融資は、こうした状況を改善するため、世界銀行、OECFが協調して実施したものである。
ただし、金融セクターの改革には、法律改正、スタッフの教育など改革に比較的長期間を必要とする部分が存在するなど一定期間を要するため、こうした改革を評価対象とするためには、定量的なデータが確保されるのを待つ必要がある。この点、本融資については最終ディスバース(1993年)を考慮すると既に短期的・中期的成果は顕在化していると考えられ、本調査は時宜を得たものととらえられる。また、このように短期的・中期的な視点を踏まえ本融資を評価するとの観点から、本調査では97年以降のアジアの通貨危機と本融資との関係を検証することも調査対象としている。
本融資の評価は外務省経済協力局評価室『ノン・プロジェクト援助評価ガイドライン』(1998年3月)で整理されている評価5項目(目標達成度・効率性・インパクト・計画の妥当性・自律発展性)と整合的に実施した。ただし、本融資が金融セクターに対する構造調整融資であることに鑑み、まず政策の実施状況を把握するため、コンディショナリティの達成を確認するとともに、金融セクターのパフォーマンス改善動向を定量的に把握した。その上で、パフォーマンスの改善がフィリピン経済に与えたインパクトについて上記評価5項目を用いながら、現地インタビュー調査に基づき、定性的かつ定量的に評価を行った。
2.評価対象案件の概要
本融資は1989年11月から93年12月(当初2年間の予定を延期)に実施され、日本の援助額は400億円(金利2.7%・据置き期間7年・返済期間25年)に相当し、援助形態は商品借款、調達条件は一般アンタイドで実施されたものである。
また、関係国際機関として、世界銀行(IBRD)が1989年5月から93年12月に金融セクターの構造調整を目的として300万米ドルを融資している。日本は、当機関と協調して本融資を行った。
3.コンディショナリティの達成状況
本融資に際してフィリピンに提示されたコンディショナリティは概ね達成されたものと評価することができ、さらに現在のフィリピンの金融セクターにもプラスの効果を及ぼしているととらえられる。本融資のコンディショナリティは、大きく5項目で構成されている。第一に商業銀行に対する中央銀行の監督・規制の適正化、第二に預金者保護を目的としたフィリピン預金保険会社(PDIC)の役割強化、第三に銀行システムにおける中間費用の縮小促進、第四に長期資金の流動化と有効活用の促進、第五に中央銀行の財務内容の改善(世銀による追加事項)である。
(イ)商業銀行に対する中央銀行の監督・規制の適正化
本項目は、商業銀行に対する中央銀行の監督・規制の適正化に資する法律の改正と手続の改善で構成されている。本コンディショナリティは、中央銀行の独立性や商業銀行に対する業務停止命令権、マネタリーボード(Monetary Board)の構成員の資格要件などを規定する新中央銀行法の成立(93年)、及び中央銀行に対する商業銀行の各種報告様式の標準化など手続の改正をもって、ほぼ適切に実施・達成されている。ただし、当初予定されていた一般会計原則(GAAP)の見直しなど達成されていない部分も存在している。
(ロ)預金者保護を目的としたフィリピン預金保険会社(PDIC)の役割強化
本項目の具体的内容は、PDICを破産銀行管財人として明確に位置づけること、及び財務体質の強化や要員の強化などを通じてPDICの組織を強化することであった。92年に成立した改正フィリピン預金保険会社(PDIC)法は、これらについて規定しており、本法に基づいてPDICは従来中央銀行により実施されていた経営困難に陥った金融機関に対する引き受け・清算という役割を独立した監督権限を有する機関として合法的に担うことが可能となった。従って、本項目に係るコンディショナリティは概ね達成されたと判断することができる。ただし、PDICの検査官の質向上、組織・権限の強化など今後改善すべき課題も残っている。
(ハ)銀行システムにおける中間費用の縮小促進
本項目の内容は、まず銀行間の競争促進によるマージンの圧縮である。これについては、商業銀行の新規支店開設、銀行ライセンス発効、合併・吸収による弱体銀行の統合促進に関するガイドラインの発行によって達成されていると判断できる。また、金融取引に関係する諸税の削減・撤廃については、金融機関に対する5%の総収入税(gross receipt tax)の廃止は財政的配慮から見送られ、一部変更にとどまったものの、フィリピンでは1997年から包括的税制改革(Comprehensive Tax Reform)が実施されている。従って、当該コンディショナリティは改革を促す契機になったものとして評価できよう。その他のコンディショナリティとして債権回収の手続費用を削減するための改正法案の議会提出が求められたが、これについても達成されている。
(ニ)長期資金の流動化と有効活用の促進
本項目の具体的内容は、中央銀行からフィリピン開発銀行(DBP)等への制度金融機能の移管、DBPのホールセラー機能拡充、新規制度金融に対する市場金利の適用であった。まず、中央銀行の信用割当がDBPへ移管されるとともに、農業貸付基金はフィリピン土地銀行の所管となり、制度金融機能の移転がはかられた。また、1992年のDBPの総融資額に占めるホールセール融資の割合は34%という目標に対して38%に達しており、現在はほぼ6割となっている。従って、これらのコンディショナリティは達成されていると評価することができる。なお、新規制度金融に対する市場金利の適用については、フィリピンの実施表明をもってコンディショナリティは達成されている。商業銀行が貸出利率を市場状況などに基づき独自に決定が可能なこと、及び金利に関して中央銀行に対して報告する義務がないことを考慮すると、本コンディショナリティは実質的にも達成されていると判断できよう。
(ホ)中央銀行の財務内容の改善(世銀による追加事項)
本項目については、中央銀行が抱えていた負債を新中央銀行(BSP)から切り離す再建委員会を創設し、BSPから過去の損失を清算する措置がとられた。その上で、中央政府に対するBSPの貸出金の返済義務づけやBSPに対する政府証券の市場価格での発行など、BSPの財務状態の強化と公開市場操作の余地拡大を意図する政策が実施された。現在までBSPの財務内容は、資産が常に負債を上回るなど改善を見せており、これらの措置に改善効果があったものと評価できよう。
4.評価5項目による評価
本融資を評価5項目(目標達成度・効率性・インパクト・計画の妥当性・自律発展性)の観点から検証すると、全体として高い評価を与えることができる。
(イ)目標達成度
目標達成度については、外貨準備高、経常収支、GDP成長率、インフレ率、政府財政、政府債務残高といったマクロ経済指標を中心に検討を行ったところ、各々の指標からはフィリピンのマクロ経済状況が概して改善の方向にあることが得られた。また、法改正、ガイドラインその他の制度の確立など、ほぼ全ての分野で目標は達成されており、本融資の貢献度は大きかったものと評価される。
(ロ)効率性
効率性の観点からは、資金ディスバース後の資機材調達、資機材調達の価格、エンド・ユーザーに対する資機材の販売、各トランシェ段階におけるODA資金のディスバース状況、構造調整計画のタイムスケジュールについて評価を実施した。資機材の調達、見返り資金の活用については適切に行われている。一方、中央銀行法を中心とした法改正の際に、国会における審議のため予定以上の時間を費やすなどコンディショナリティの達成に遅れが出たため、最終トランシェのリリースがずれこむなど、当初の計画と実際の資金のディスバースにずれが生じた部分もある。しかしながら、ディスバース自体は適切な時期に行われており、効率性は維持されたと評価することができる。
(ハ)インパクト
インパクトとしては、エンド・ユーザーによる調達資機材活用を通じたインパクト、日本との二国間関係に対する影響、見返り資金活用プロジェクトのフィリピン開発に対するインパクト、構造調整の社会的なインパクトについて評価を行った。フィリピンからの日本に対する輸出入も上昇基調にあるほか、本融資が銀行協会や民間金融セクターから実物経済の発展に寄与しているなど高い評価を得ていることから、概ねプラスのインパクトが認められた。特に、フィリピンが本融資を用いた輸入決済により直接生産部門の拡大を達成し、輸出を通じた経済成長を達成するとともに、それを支える国内基盤として金融セクターの信用拡大を達成していった点が特筆される。すなわち、本融資が銀行の預金残高の拡大、収益率の改善を通じ、フィリピンの内需部門の効率性改善に貢献したことが評価できる。
(ニ)計画の妥当性
計画の妥当性については、資金の迅速な供与、資機材調達の適正性・有効性、融資のタイミング・金額の妥当性、部門調整計画全体における当該融資案件の位置づけ、構造調整計画設計の適切性等について検討した。フィリピン政府の行政能力(institutional capability)に対する期待が大きすぎ、これが融資スケジュールを遅らせる要因になったものと考えられるが、時間は要したものの、最終的にはコンディショナリティはほぼ達成されており、妥当性の観点からも大きな問題はなかったものと評価できる。
(ホ)自立発展性
自立発展性については、構造調整計画に対するフィリピンの対応、達成済コンディショナリティ及び改善されたマクロ経済指標の現在の状況などについて評価を行った。援助実施時、フィリピン政府は本融資案件の終了後も主体的に金融セクターの構造改善に取り組んでおり、自立性の観点からも大きな前進があったものと評価することができる。中央銀行の監督機能や、PDICの監督機能強化の必要性、長期資金の一層の流動性確保など、依然残された課題が存在することからさらなる支援の必要はあるものの、これは自立性の欠如を意味するものではなく、一層の自立性獲得のための新たなステップであると判断される。
5.提言
総合的な観点から判断すると、本融資は成功した案件として位置づけることができる。特に、本調査を通じて得られる全体的な提言は、大きく三点に集約される。第一に長期的視点からの評価の必要性である。構造調整融資に関しては、実際の援助実施期間内に被援助国の構造的問題が全て解決されるわけではなく、その評価には一定期間の経過が必要とされる。このため、第二点としてモニタリングシステム構築の必要性が示唆される。一般に、構造調整プログラムの成果を確認するには、貸付完了後も一定期間の継続したモニタリングが不可欠である。また、第三にアジア通貨危機による追加支援の必要性である。フィリピンの金融セクターはASEANの他の国々に比べ、通貨危機にもかかわらず良好なパフォーマンスは見せている。しかし、通貨危機後のパフォーマンスを通じて、フィリピン金融セクターがさらに改革を必要としている部分も浮き彫りにされており、特に本融資における教訓を活かし、ノンプロジェクト型融資が一層効率的に実施されることが期待される。

