7.電力開発と環境保全(シリア)
(現地調査期間:1998年12月10日~12月20日)
| ■ | 株式会社国際経済研究所 主席研究員 |
畑中 美樹 | 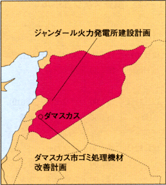 |
〈評価対象プロジェクトの概要〉
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |
| ジャンダール火力発電所建設計画 | 有償資金協力 | 91年度、515.98億円 | 電力不足を解消すべくシリア中西部ジャンダールにコンバイド・サイクル発電所(600メガワット)を建設するもの。第1ステージ(ガスタービン(100メガワット×4))と第2ステージ(スチーム・タービン(100メガワット×2))との間の技術的調整が重要な案件であり、1990年4月よりシリア側より要請があった。 |
| ダマスカス市ごみ処理機材改善計画 | 無償資金協力 | 95年度、6.24億円 | シリア政府は財政事情の厳しいダマスカス市清掃局が道幅の狭い地域にも進入可能な小型の清掃車輛を導入することによりごみ収集問題の解決を図るとともに、最終処分用の機材を導入することによりゴミを埋め立て処分することを目的として、必要な機材(コンパクター、ダンプカー、ブルドーザー、ホイルコーダ等)の購入資金につき要請があった。 |
1 評価調査の概要
1-1 調査方針
(1)目的:
有識者の客観的かつ専門的な視点を活かして、日本の対シリア政府開発援助案件に対する評価を行い、その結果を対象案件のフォローアップに役立たせるとともに、当該国に対する我が国の援助政策全般にフィードバックし、援助計画策定・実施等の改善に資する。
(2)対象案件:
対象案件は、我が国政府がシリアに於いて実施している有償・無償・プロジェクト方式技術協力・草の根無償の4つの援助形態のうち有償・無償から代表的案件を1件ずつ選択した。対象案件は以下の2案件である。
- ジャンダール火力発電所建設計画(有償資金協力)
- ダマスカス市ごみ処理機材改善計画(無償資金協力)
(3)評価手法:
既存資料レビュー/関係者聞き取り調査/事業サイト視察等による資料収集、並びに評価5項目による分析
- 個別評価:目標の階層(案件目的等)を明らかにし、それに基づいて目標達成度、効率性、当初計画の妥当性、自立発展性、インパクト等を評価し、教訓と提言を導き出した。
- 横断的評価:個別評価の結果を横断的に分析し、セクター・レベル、政策レベルの評価を行った。
1-2 調査スケジュール
| 月日 | 時間 | 行程 |
| 12月10日(木曜日) | 11時50分 | 成田出発(NH205) |
| 16時30分 | パリ到著 | |
| 12月11日(金曜日) | 13時00分 | パリ出発(AF610) |
| 18時50分 | ダマスカス到着 | |
| 12月12日(土曜日) | 9時30分 | 打合わせ |
| 10時00分 | シ政府企画省 | |
| 12時00分 | シ政府ダマスカス県庁 | |
| 20時00分 | ダマスカス県知事表敬 | |
| 12月13日(日曜日) | 11時00分 | シ政府発送電公社 |
| 14時00分 | JICA事務所表敬 | |
| 12月14日(月曜日) | 10時00分 | シ政府電力省 |
| 10時30分 | ダマスカス出発 | |
| 12時00分 | ジャンダール火力発電所 | |
| 17時30分 | ホムス着 | |
| 12月15日(火曜日) | 9時30分 | ホムス発 |
| 10時00分 | ジャンダール火力発電所 | |
| 10時30分 | 電力技術研修所 | |
| 13時30分 | 同上発 | |
| 14時45分 | ダマスカス着 | |
| 12月16日(水曜日) | 10時00分 | シ政府ダマスカス県庁清掃局 |
| 11時15分 | 収集ごみ積み替え施設視察 | |
| 12時10分 | ごみ採取処分場視察 | |
| 12時30分 | 収集ごみ肥料化施設視察 | |
| 19時30分 | 旧市街ごみ収集・清招現場視察 | |
| 12月17日(木曜日) | 午前 | 大使館報告内容検討 |
| 13時00分 | 大使飴報告 | |
| 12月18日(金曜日) | 終日 | 評価調査取りまとめ |
| 12月19日(土曜日) | 7時35分 | ダマスカス出発(AF613) |
| 11時50分 | パリ到着 | |
| 18時30分 | パリ出発(NH206) | |
| 12月20日(日曜日) | 14時05分 | 成田到着 |
2 個別案件に対する評価
2-1 有償資金協力案件:「ジャンダール火力発電所建設計画」
(1)案件概要
| 1.事業名 | ジャンダール火力発電所建設計面 |
| 2.事業概略 | 2.1期間 |
| F/S:90.1
L/A:91.6 施工:93.4~95.12 |
|
| 2.2援助形態 | |
| 有償資金協力 | |
| 2.3援助担当期開 | |
| 海外経済協力基金 | |
| 3.被援助国内体制 | 3.1窓口機関 |
| 企画省 | |
| 3.2所轄官庁 | |
| 電力省 | |
| 3.3実施期間 | |
| 電力公社(当時)、現在は2分割され発送電公社(PEEGT) | |
| 4.目標の階層 | 4.1目的 |
| 国内の電力不足を緩和し、電力の安定供給化を実現すると共に、国産天然ガスの有効利用を図る | |
| 4.2事業目標 | |
| 電力の安定供給を演じた国民生活の安定。国民経済の発展及び天然ガス利用による石油抽出の増加を通じた外貨獲得機会の拡大 | |
| 4.3活動・アウトプット | |
| 計画策定、工場建設 | |
| 4.4投入 | |
| [日本側] 515億9,800万円 |
|
| [被援助国側] 133億3,700万円(ローカルコスト) |
|
| 4.5裨益対象 | |
| 一般国民 | |
| 5.備考 |
「ジャンダール火力発電所建設計画」
(2)評価結果概要
本案件については、電力の国内需給における当該発電所の貢献度及び運営、維持・補修の適切性を重点項目として評価に望んだ。
1)目標達成度及びインパクト
電力需用に関しては計画当初の予測通り、国内需要が年平均8%(1990~96年)で著しく増加しており、当該発電所は国内最大の発電シェア(98年1月~11月実績で約20%)を持つ発電所として電力の安定的供給を通じて、シリア経済の発展に大きく貢献しているとの評価を得ている。
2)効率性
発電所の運営、維持、補修の現状については、熱効率46%、平均操業率70%を達成しており、当初の期待に沿った成果をあげている。ただし、維持・補修については運転開始から約3年しか経過していないため、より高度の技術の求められる今後の維持・補修時での対応の有劣が、本プロジェクトの正否の鍵となることが予想される。
3)妥当性
シリアの開発において電力供給力の拡大に高い優先順位が与えられてきたことに加え、近年豊富な天然ガスの埋蔵が確認されていることからして、熱効率、柔軟性に優れ、さらに環境保全上も望ましいガス・タービン・スチーム・タービンから成るコンバインド・サイクル発電所の建設は、目的の設定においても妥当であったといえる。
4)自主発展性
当該発電所の運営、維持・補修は、ほぼ発電所の所在地であるホムス地域出身の職員にて行われており、機材施設も整然と配置され有効に活用されている。しかし、当該発電所がシリア発のコンバインド・サイクル発電所であり、十分な知識、経験を有する専門家が少ないため、今後については職員の訓練が必要であるものの、資金的余裕のないことが、これからの課題となると予想される。
【外務省コメント】職員の訓練が必要という点については、無償資金協力「電力技術研修所建設計画」(1996、97年度:計16.71億円)にてジャンダール発電所敷地横に研修所を作り、98年度より個別専門家派遣によりフォローをしている。
(3)教訓と提言
プロジェクトは、シリアの開発計画上の高優先順位であった電力不足の解消に対応すべく計画され、適切に実施されている。もっとも、コンバインド・サイクル発電所の建設については、天然ガス資源の有効利用や熱効率性・柔軟性の高さ、環境保全への貢献の諸点からは妥当と言えるものの、運転開始一定期間経過後の高価な部品の頻繁な取替えや維持・補修のための追加訓練によるさらなる知識の取得の必要性を含めたトータル・コストを考慮すると、熱効率性・柔軟性はやや落ちるとしても、天然ガスを熱源とする通常型の発電所の推進も検討に値する。また、運転開始一定期間経過後に対応しうる職員の不在は、今後の事業の発展を考えた場合、深刻な課題であるので、高度の知識・技術の必要とされる維持・補修のための技術移転の強化策が求められる。
さらに、一定期間経過後の部品取替えについては、当初から予測されることであるので、費用はシリア負担となることの認識化、明確化の事前徹底が必要である。
2-2 無償資金協力案件:「ダマスカス市ごみ処理機材改善計画」
(1)案件概要
| 1.事業名 | ダマスカス市ごみ処理機材改善計画 |
| 2.事業概略 | 2.1期間 |
| E/N:96.3.23 | |
| 2.2援助形態 | |
| 無償資金協力 | |
| 2.3援助担当機関 | |
| 国際協力事業団 | |
| 3.披援助国内体制 | 3.1窓口機関 |
| 企画省 | |
| 3.2所轄官庁 | |
| 地方自治省 | |
| 3.3実施機関 | |
| ダマスカス市 | |
| 4.目標の階層 | 4.1目的 |
| 道路幅の狭い旧市街地城・丘陵地域への小型清掃車輌の導入と埋め立て処分の可能な機材の導入によるダマスカス市のごみ収集処理サービスの向上を図る | |
| 4.2事業目標 | |
| ごみ収集処理サービスの改善によるダマスカス市の衛生状態の改善及び環境保全の向上 | |
| 4.3活動・アウトプット | |
| 計画策定、機材設置 | |
| 4.4投入 | |
| [日本側] 6億2,400万円 |
|
| [披援助国側] ローカルコスト |
|
| 4.5裨益対象 | |
| ダマスカス市民 | |
| 5.備考 |
「ダマスカス市ごみ処理機材改善計画」
(2)評価結果概要
本案件では、効率的なごみ収集運営及びダマスカス市のごみ最終処分時の衛生状態の改善、環境の保全に対するインパクトをポイントに評価を行った。
1)目標達成度及びインパクト
小型の清掃車輌の投入以後は、年間修理車両数が約3割減ったことで清掃局の維持費用が節約され、さらに道幅の狭い地域に導入可能になったことで、ごみ処理量が増大している。加えて、コンパクター、ダンプカー、ブルドーザー等の新機器材の投入でごみの埋め立て処分が可能となり、はえの発生やプラスチック袋の空中浮遊、或いは異臭がなくなっており、プロジェクトの効果が認められる。
2)効率性
新規投入のごみ処理機材はすべて有効活用され、保管状況は良好であった。また、小型車両の投入により、旧式の大型車両の稼動時間は著しく短縮されていた。ただし、収集ごみの積み替え施設が小さく、作業効率に若干支障が見うけられた。また、最終処分場については、現在の埋め立て方式への転換で、利用可能期間が4年延長され2002年までとなっているものの、早晩、許容量の限界に達する感がある。
3)妥当性
ごみ収集の効率化及び最終処分場の環境保全は、ダマスカス市の政策上、高い優先順位が与えられていることからして、小型車両及び必要機材の供与は、目的の設定において妥当であったと言える。ただし、ごみの収集・処理の効率をいっそう高めるには、収集ごみの積み替え施設の整備が必要である。
4)自主発展性
清掃車両及び最終処分場の管理・維持はダマスカス市清掃局の職員により独自に行われており、今後も支障は認められない。但し、ダマスカス市のごみ収集・最終処分に関わる財政収支状況は、ごみ収集・処分料金の市民からの徴収が不完全であることから、大幅赤字になっているため、他方で市の財政負担要因となっている。今後、ごみ収集・処分業務をさらに向上させていくためには、料金徴収の徹底化による財政事情の改善が不可欠である。
(3)教訓と提言
本案件は、ダマスカス市民が便益を得られるという性質により知名度も高く、加えて、日本からの援助である旨が英語、アラビア語で銘記されたステッカーを貼った車両がごみ収集のため市内を絶えず走り廻っていることから、日本によるODAの宣伝効果も大きい。ただし、ダマスカス市の著しい人口増加に伴うごみ発生量の急増という現実から考慮して、今後数年で現在の最終処分場のみでは対応できず、新処分場への移転を余儀なくされることが予想される。今後収集ごみの効率的処分については、収集ごみの仕分けセンター、医療ごみの処理施設の確立によるトータル・システムでの対応が不可欠である。また、供与車両のいっそうの有効利用を図る観点から、車両維持・補修に必要な知識・技術の供与を目的とする訓練コースの新設も必要であろう。
3 横断的提言
3-1 セクター・レベルの提言
従来、我が国の対シリア援助は、同国が中東和平プロセス当事国として和平達成の鍵を握る最重要国であり、同国の安定的な経済発展が同国のみならず中東地域の平和と安定にとって極めて重要な意味を持つとの考えから、中東和平の推進の一環として、シリア国民の生活向上に資する援助を重視してきた。とりわけ、シリアの開発計画上の最優先課題であった電力分野を特に重視すると共に、近年人口増加、経済開発の進展により顕在化してきた環境分野にも焦点を合て、ごみ処理機材の整備への協力を行ってきた。同国の開発ニーズ等に鑑みて、この傾向に大きな変更はないものの、現地政府当局者との協議においては、農業、灌漑、肥料プラント、アグロ・インダストリー、運輸・通信の各分野が、現業開発計画(1996~2000年)での優先項目との説明があった。ただし、電力分野についても、既存発電所のリハビリ、コンバインド・サイクル化及びあらゆるプロジェクトでの環境保全が新たな優先課題との説明が加えられた。電力不足が解消された状況から鑑みて、我が国としては基盤産業でしかも外貨の獲得にも貢献しうる農業・灌漑プロジェクトや電力分野での高度訓練協力、ごみ処理のいっそうの効率化、環境保全化を一層推進する必要があろう。
3-2 政案レベルの提言
開発援助事業においては、経済開発及び人道的支援といった面はもちろんであるが、プロジェクト及び援助国について現地住民に広く知られるための配慮も必要である。この意味で今回対象とした「ジャンダール火力発電所建設」及び「ダマスカスごみ処理機材改善計画」は、いずれも住民に広く知られ高い評価を得ていた好例であった。一般国民の生活の改善・安定化に資するこうした案件は引き続き実施する必要があろう。
ただし、我が国の対シリア援助は同国が中東和平プロセスの当事国として和平達成の鍵を握る重要国であるとの判断のもとに行われていることに鑑みて、今後の援助の実施に際しては、中東和平プロセスとの関連性を持たせることもひとつの考え方である。具体的には、電力セクターや要請がなされている運輸セクターにおける協力のみならず、中東地域の和平安定化に資することを目的に進められてきた中東和平多国間プロセスの中での経済的テーマである環境作業部会、水資源作業部会への参加を促す形での、環境案件、水資源案件の推進も必要と考えられる。
さらに、シリアは依然援助への依存度が高い中、政府に財政的余力が乏しいことから、自立発展性のあるプロジェクト形成のために不可欠な職員の訓練が不十分となる傾向が強い。このため、今後のプロジェクト形成に際しては、供与機材の運転及びその後の維持・補修に関わる訓練プログラムを事前に組むことが有益と考えられる。
発展途上国への援助の供与に際しては、対象国の文化的・社会的・宗教的状況への配慮が必要となることが少なくなく、アラブ諸国もその例外ではない。アラブ諸国への援助の供与に際しては、援助国側が事前に以下の諸点を十分理解しておくことが、援助の成果をあげるうえで肝要である。
第一は、シリアを含むアラブ諸国ではイスラム教徒が大宗を占めることから、豊かな者が貧しい者に施しを与えるという、いわゆる喜捨の考え方が根強いことである。このため、アラブ世界では、世界第二位の経済力を持つ日本が依然発展途上国にある諸国を支援するのは当然との考え方をしがちなことが少なくない。
第二は、アラブ世界で欧州諸国の植民地支配を経験した諸国が多いことから、一般的に西側先進国に対して愛憎相半ばする(アンビバレント)感情を抱いていることである。このことが、援助国への猜疑心につながりがちであり、援助実施時の被援助国との細かな条件面等での意見の食い違いを生み易い。こうした傾向は、かつての冷戦下で反西側的政策を採ってきた諸国で特に強い。
第三は、アラブ等の中東地域では時間感覚が往々にして西側世界とは異なることである。このため援助実施の各段階で、援助国は対象案件が当初のスケジュール通りに進まないことに、苛立ちを覚えがちとなる一方、被援助国も自国の様々な事情に配慮せず対象案件をスケジュール通りに進ませようとする援助国の姿勢に不満を募らせがちである。
要は、援助国がアラブ世界のこうした文化的、社会的、宗教的特質を十分に理解した上で、援助の成果の上がる方向へと被援助国の対応を誘導して行くことが必要となってくる。ただし、それであるからと言って被援助国を甘やかすということでは決してなく、忍耐と寛容の精神により、被援助国に我が国の援助の考え方や援助方針、或いは援助案件の考え方や援助案件を通じて被援助国に期待されているその後の努力のあり方等を、植え付けて行くということである。
上記に鑑みて、我が国の対シリア援助では、我が国の対シリア援助方針、援助を通じてシリア側に期待していること、或いは、援助案件の自立的発展のためにシリア側に求められること等をいっそう徹底化・明確化すると共に、我が国側の援助関係者においても、シリア側の抱いている不満内容を充分吸い上げ、その解消に向け我が国及びシリア側の双方に求められる対応策を整理することも必要であろう。

