4.経済再生への協力のあり方(タイ)
(現地調査期間:1998年11月28日~12月5日)
| ■ | 日本経済新聞社論説副主幹 | 土谷 英夫 | 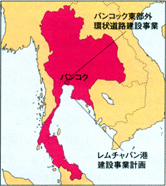 |
〈評価対象プロジェクトの概要〉
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |
| レムチャバン港建設事業計画 | 有償資金協力 | 84年度、41.72億円
85年度、122.83億円 89年度、64.36億円 |
東部臨港開発計画の一環として、レムチャバン地区にバンコク(クロントイ)港の代替機能を持つ港湾を整備し、物流の向上をはかる。 |
| バンコック東部外環状道路建設事業 | 有償資金協力 | 89年度、129.58億円
93年度、124.73億円 |
バンコク外環状の一環として同市東側に約64キロメートルのバイパスを建設する。 |
| 電話網拡充事業 | 有償資金協力 | 89年度、153.18億円
91年度、45.98億円 |
タイ国内の電話需要に対処するため加入者ケーブルの新増設を行う。 |
1 はじめに
(1)日・タイの経済協力関係
経済発展のテイクオフに成功したタイは、開発途上国から中進国のカテゴリーに進んでおり、わが国の経済協力も、原則として有償協力に絞られている。(アジア経済危機対策の緊急無償援助等は除く)。タイは、わが国の2国間援助実績(1997年までの累計)でインドネシア、中国、フィリピンに次ぐ第4位の受取国であり、同国へのドナーとして、わが国は2位のドイツ以下をはるかに引き離す圧倒的第1位の援助供与国となっている。
今回の評価は、いずれも海外経済協力基金(OECF)を通じて供与した経済・社会インフラ整備に係わる円借款3件(港湾、道路、情報通信)について実施した。
タイは1997年7月のバーツ急落で、いわゆる「アジア経済危機」の端緒となった。現在、救済融資を受けた国際通貨基金(IMF)との合意の下、経済の建て直しに取り組み、わが国も「新宮沢構想」の一環として、同国の経済再生を支援している。こうした状況を踏まえ、評価にあたっては、単にプロジェクトの適否だけでなく、マクロ経済の視点から、経済再生に資する協力のあり方について教訓を導くことに意を用いた。
(2)タイ経済危機の背景
アジア経済危機の原因を、国際資本移動の自由化に伴う、短期資本の急激な流出入に求める見方がある。しかし、それは危機を引き起こした一因に過ぎない。タイに限れば、通貨危機勃発の前年の96年に、すでに輸出が伸び悩み、経常収支が悪化し、実質成長率も鈍化するという実体経済面の赤信号が点滅していた。
タイは、すでに輸出の8割を工業製品が占める工業品輸出国だが、中国が1994年の人民元の33%切下げを契機に「輸出主導型成長」の目標を鮮明にし、工業品輸出国化を加速したことにより、96年以降、特に労働集約製品の市場を中国に奪われる傾向が顕著になった。さらに、95年後半以降の円高修正で、通貨バーツを事実上ドルにペッグしていたタイの輸出品は、日本および第3国市場で、日本製品との競争条件が悪化した。
一方、資本取引の面では、1990年のIMF8条国移行、93年のオフショア市場開設などで、資本自由化、外資導入チャネルの整備が進んだ結果、海外からの証券投資、短期借入が急増した。政府部門は、健全財政を堅持してきたが、民間主体の外資導入増は、不動産バブルをもたらした。即ち、過大評価の為替レート→経常収支赤字拡大→外資によるファイナンス→不動産向け融資急拡大→不動産バブル崩壊、という経過である。
タイ政府は、金融機関の整理に大ナタを振るうなど、巨額の不良債権を抱えた金融セクターの再編に取り組んでいるが、バブルの後始末と銀行部門の健全化は経済再生の要件の一つに過ぎない。1997年マイナス成長となった実体経済は「底を」打ったとの見方が有力だが、危機以前の高度成長軌道に戻るのは容易ではない。輸出主導型成長の限界、世界的な製造業の設備過剰などを踏まえた実体経済の変革が不可欠であろう。今後のわが国の対タイ経済協力のあり方を論じるにも、そうした問題意識が求められる。
2 レムチャバン商業港建設事業
(1)事業の目的と概要
東部臨海開発プロジェクトの一環として、バンコクの南東約110キロメートルのレムチャバン地区に、東部臨海地区の工業団地の主要商業港(原材料や資本財の輸入と製品の輸出)として、また、大型船の入港が困難なバンコク港(クロントイ港)の代替機能も合わせ持つ深海港(deep-sea port)を建設するものである。全体計画は3段階(phase 1~3)から成る。1991年に開港し、現在phase 1をほぼ完成、phase 2に着工している。
今回、評価調査対象とした円借款の対象に含まれる事業は、phase 1のしゅんせつ・埋め立て、護岸整備、防波堤整備、係留施設の一部の整備、施工管理のコンサルタント費用などである。
(2)東部臨海開発との関係
東部臨海開発プロジェクトは、1970年代にシャム湾での天然ガス田発見を契機に、天然ガス利用の重化学工業を東部臨海地区に立地しようとの構想から発展した。80年代初頭タイ政府が本格検討に着手、日本政府は計画立案段階から同プロジェクトに積極的に協力してきた。財政難から計画が休止した時期もあったが、現在は重化学工業に限らず、自動車メーカーをはじめ多様な業種が進出し、タイ有数の工業地区となっている。
バンコク東南方のチョンブリ、チャチェンサオ、ラオンの3県を中心とするこの地域での日本の経済協力は、国際協力事業団(JICA)による開発調査実績12件、OECFによる円借款供与実績16事業27件、約1,788億円にのぼり、内容も工業団地、港湾、道路、鉄道、ダム、送水管など多岐に渡っており、レムチャバン港は、その中で、商業港として位置づけられている。(港湾では他に工業港としてマプタプット港もある)
(3)クロントイ港の限界
首都バンコクの中心部に近いクロントイ地区に位置するバンコク港は、過去半世紀の間、タイの主要港の地位にあったが、近年、タイの経済発展に伴う貿易量の急拡大、バンコクの過密化などの環境変化に対応しきれず、その限界が露呈してきた。
実際、バンコク港を視察して驚くのは、あまりにも都心に近いことである。このため、港に出入りする車両が、悪名高いバンコクの交通渋滞に輪をかけている。バンコク港自身、能力増強のための近代化計画を進めているが、その場所的制約は逃れがたい。
制約の第一が、同港が、バンコクを貫くチャオプラヤ川岸に開かれた河川港であることである。喫水が8.2メートルと浅く、最大でも12,000トン、コンテナ積載900 TEU(20フィートコンテナ換算個数)クラスの船しか入港できない。
世界の海運界は、コスト引下げを目指し、「Panamax」(パナマ運河を通行可能な最大級の船)や、さらにひと回り大きい「Post Panamax」などと呼ばれる大型船を投入する方向にあり、水深の浅いバンコク港では到底対応できない。
(4)レムチャバン港の現況
円借款対象のphase 1開発は、北桟橋(North pier)にA0~A5の6ターミナル、南桟橋(South pier)にB1~B5の5ターミナルの計11ターミナルから成る。そのうち、7ターミナル(A4、A5、B1~B5)については、Consession方式またはリースで民間企業が運営、維持、管理を行っている。
A0、A1(水深6.5メートル)を除き、水深14メートルで5万トン級のPanamax貨物船の入港が可能である。コンテナターミナルはB1~4が各300メートルのバース、敷地10.5ヘクタール、B5は長さ400メートルのバースと敷地18ヘクタールを確保している。同港の貨物取扱量の約8割がコンテナだが、埠頭までタイ国鉄の引込み線が設置されており、コンテナ輸送の約3割が貨車輸送となっている。また、バンコク―チョンブリ高速道路の開通(1998年12月)により道路輸送面での利便性も向上した。
1991年の開港以来、順調に貨物取扱量を増やし、96年からは北米定期航路のコンテナ船が寄港するようになり、現在4海運グループが北米定期航路(内1航路は欧州にも回航)を、それぞれ週1回の運行をしている。97会計年度には、コンテナ扱い量が103.6万TEUと初めて100万の大台に乗り、タイ全体の45%を占めるにいたった。98会計年度は142.4万TEUでバンコク港を凌駕している。
Phase 1終了時点の年間コンテナ扱い能力は約150万TEUで、すでに限界に近づいたとの判断からタイ港湾局は、Phase 2に着工している。2009年完成予定のPhase 2では、水深を16メートルに掘り下げ、総延長3,400メートルの埠頭に6つのコンテナターミナルを建設、同港の年間コンテナ取扱能力を500万TEU以上に拡大するもので、その第一段階として、長さ500メートルバースを持つ年間取扱能力60万TEUのC3ターミナルが、1999年中に完成、2000年から運用開始される予定である。さらに、その後、約850万TEUへの能力拡大を目指すPhase 3も計画され、用地も確保されている。
港湾当局者によればPhase 1の総事業費の約7割を円借款により充当した。Phase 2工事が、円借款の対象にならなかったのは、港湾局が円借款プロジェクトの条件である国際競争入札を行わず、Phase 1の工事を請け負った地場ゼネコンのイタルタイ社と契約したためである。このためPhase 2の事業費は、約6割をタイ政府の資金に依存している。港湾当局者は、円借款を受けられなかったのは、自分たちの手続き上の失敗と認めている。
(5)評価と展望
前述の東部臨海地区の工業集積の進展、バンコク(クロントイ)港の限界、レムチャバン港の国際的な認知度などから、本プロジェクトの有用性は裏付けられよう。取扱貨物量がバンコク港を抜きタイの港湾中最大になったこと、タイ国政府が自らの判断でレムチャバン港の拡張(Phase 2の着工)に踏み切ったこと、北米定期航路のコンテナ船の寄港地となったこと、物流専門誌「Cargo News Asia」が、同港をシンガポール、香港、マニラ、クランと並んで東南アジア地域のベスト5港湾と評価したことも、その根拠になる。
港湾の運営に関しても、港湾局直営の1埠頭を除き、コンテナ・バースを含む他の埠頭をConcession方式またはリースで民間に運用を委ねているのも懸命なやり方であろう。
ただ、アジア経済危機を経て、同港の業績に陰りが見られることも事実である。コンテナターミナルを運営する民間会社への聞き取り調査によれば、調査時点で輸入コンテナの6、7割は空箱ということであった。不況による輸入量の激減が、輸出品収納に使う中身の入っていないコンテナだけの「輸入」を増やしているわけで、表面的な扱い貨物量の増加ばかりを喜んではいられない。
また、Phase 2で増設されるバースもConcession方式で民間に運用を委ねる方針だが、調査時点では、2000年開業予定のC3バースについて民間からの応募はゼロの状態であった。港湾局の計画では2009年までにPhase 2を終え、その後新たな10カ年計画で、Phase 3の拡張に取り組む段取りだが、これらの計画は、経済危機以前の高度成長を前提とした需要予測がもとになっていると思われる。現実の貨物需要の動向しだいで、また、タイ政府の財政的な制約によって、Phase2工事の遅延やPhase 3計画の繰延べ、または凍結などの選択肢が浮上する可能性は否定できない。
同港の将来を予見する場合、シャム湾の湾奥にあり、東南アジア地区のハブ港湾として確固たる地位を占めるシンガポールに近いという地理的条件を無視できない。即ちシンガポールから大型船で約20時間、小型船で30数時間という近すぎる距離は、ラムチャバンを、東南アジアのハブポートになりにくくしている。しかし、同港が山岳国のラオス、東隣のカンボジアを含む、いわゆる「バーツ経済圏」の中心港になる潜在的可能性は十分ある。そのためには、両国と結ぶ高速道路の整備などが鍵を握ろう。
3 バンコク東部外環状道路建設事業
(1)事業の目的と概要
混雑著しいバンコク市内の通過交通をバイパスさせる「外環状道路」計画のうち、東側部分となる高速国道(バンパイン-バンプリ間、約64キロメートル)の建設。前述の東部臨海開発の支援プロジェクトも兼ね、バンコク-チョンブリ間の高速国道(円借案件)と結んで、東部臨海地区からバンコク市北方にいたる道路交通の時間距離の大幅短縮が可能になる。事業主は、運輸通信省の道路局(DOH=Department of Highways)で、総事業のうち約80%がDOH自己資金で、約20%が円借款である。同時開通のバンコク―チョンブリ道路とともに、DOHが所管する最初の有料高速道路でもある。
(2)バンコク市内の道路事情
バンコクの道路渋滞のひどさは、世界的に知れ渡っており、調査期間中にも1時間に数キロしか進まない渋滞を体験した。原因は、「多すぎる車・少なすぎる道路」にある。バンコクの道路密度は、内環状道路の内側でも8.1キロメートル/・(1990年)で、先進国の都市では道路密度が低いとされる東京23区の13.6キロメートル/・に比べても著しく見劣りする。
チャオプラヤ川沿いの湿地帯に建設されたバンコクが、交通手段を張り巡らされた運河(舟運)にもっぱら依存してきた歴史が大きく影響している。本格的な道路整備が始まったのは、19世紀半ば以降であり、道路整備が遅れたまま、高度成長とモータリゼーションを迎えてしまったのである。バンコク特有の問題として、Soiと呼ばれる脇道の多くが袋小路になったり、またSoi同士を連絡する道が少ないことがある。このため一つのSoiからすぐ隣のSoiに行くにもいったん表の幹線道路に出なければならず、主要道路に車が集中して渋滞させる原因になっている。
1980年代から建設された日本の首都高にあたる高速道路交通(ETA)所管の「Express way」は、あまり渋滞もなく機能しているように見えた。また、大量公共輸送機関としてBOT方式(Build Operate and Transfer、民間が建設・運用し一定期間後、政府に譲渡する=日本でPFIと呼ばれている手法に類似)による高架鉄道がほぼ完成、調査時点で試運転の段階にあり、地下鉄も着工している。道路交通への緩和効果が期待される。
(3)東部外環状道路の現況
アジア大会の開催に間に合わせて、1998年12月初頭に開通した。今回調査期間中のことであり、開通2日目に現地を視察し、実際に走行した。
国際競争入札により、16工区中15工区をコスト面で優位性を持つタイの地場建設業者が落札、施工した。当初は1996年12月の完成予定であったが、土地収容が遅れたこと、軟弱地盤の箇所の一部設計変更があったこと、95年に洪水に見舞われ、当局が150日の遅延を容認したこと、97年7月の通貨切下げ・経済危機に伴う建設業者への打撃に配慮して当局が180日の遅廷を容認したこと、などで完成が2年3か月ほど遅れた。
上下各2車線だが、用地は幅100メートルを確保しており、交通量の増大に対応して、上下線とも現行車線の内側、外側に各1車線の増設が可能(最大8車線)である。料金設定は4輪普通車で、ほぼ1キロメートルにつき1バーツの計算で、道路本線上に2か所の料金所を設け、それぞれ30バーツ(4輪普通車)徴収する。(ただし開通から一定期間は無料開放)。調査時点が開通直後で一般への周知がまだ徹底していないためか、交通量は少なく、車の流れは円滑だった(現在、交通量は多くなっている。)。周辺は水田など農地が多く、のどやかな風景が広がるが、道路開通に伴い商業施設や住宅などの進出の動きがあり、周辺地価は上昇している。
外環状道路計画は、バンコク市を囲む2等辺三角形に近い形をしており、最初に左辺にあたる西側約63キロメートルが開通(無料開放)、今回、右辺の東側が開通した。底辺にあたる南側33キロメートルは未着工でDOHによれば、特許道路(Concession Highway)として、いわゆるBOT方式での建設を計画している。
(4)評価と展望
バンコク市内の交通混雑を緩和するため、通過交通を市外に出す外環状道路の建設は不可欠である。インターチェンジで接続するバンコク―チョンブリ高速道路と同時開通したことで、東部臨海地区から北部および東北部への道路輸送の時間短縮効果も期待できる。
DOHのTraffic Divisionの1997年7月時点の調査では、東部外環道路の北側の起点であるバンパインでは、同道路と交わる国道1号線で日に約12万台の交通量(39%が大型車)があり、うち3万台が新道路にシフトすると見込まれている。調査時点が開通直後のため、新道路の交通量や渋滞緩和効果などを定量的に把握する実績データは得られなかった。DOHによれば、Planning Divisionが、建設終了1年後(99年11月)に評価を実施することになっており、援助供与側としても、結果をチェックする必要がある。
なお、建設地がチャオプラヤ川流域の軟弱地盤であるため、タイで初めての道路盛土に対する本格的な軟弱地盤処理工法が導入された。これを契機に、雨期があり湿地が多いタイで新技術の普及が期待される。
環状道路は、環が完結してこそ意味がある。未通の南部部分もなるべく早く建設すべきだろう。だが、DOHが意図するBOT(Build, operate and Transfer Scheme(注))方式での建設には問題も多い。空港付近から都心に至るドンムアン有料道路(1994年12月開通=15.5キロメートル)のように、もともと交通量がきわめて多いルートで、成功した事例もあるが、当局が料金水準などに介入して、民間事業者が計画を中止したケースもある。経済危機によって民間企業のリスク負担能力が低下していると見られるだけに、BOT方式の道路建設が円滑に進むかどうか予断を許さない。
タイ政府は都市間有料高速道路(Inter-city Mortorway)計画を推進している。もともとJICAの提案(1989年)を下敷きにしており、13路線、総延長4,150キロメートルの高速道路網を整備する計画で、建設費用は4,723.6億バーツ(うち土地収容に656億バーツ)と推計している。完成すれば、燃料や時間短縮の結果、金額に換算して、年間495.6億バーツの節約が期待できると推計している。高速道路の必要性は認めるが、計画で気がかりな点は、高速道路網がバンコクを要に放射状に形成されることで、いわゆる「ストロー効果」で、かえってバンコクの一極集中を助長しないか、という点である。
バンコク市の交通問題では、道路を管轄する機関が、多岐にわたり、いわゆる縦割りの弊害で、総合的な対策がなかなかできない問題がある。また、道路建設などのハード面に加え、交通信号システム、交通標識・表示、取締り警察官の対応など、ソフト面の改善の余地も大きい。タイ政府も陸上交通調整委員会(Office of the Commission for the Management of Land Traffic=OCMLT)を設け、遅まきながら調整に乗り出している。わが国は1998年にOCMLT向けに同機関を調整窓口にした交通政策・計画の立案や、交通施設改善プロジェクトに初の円借款41億円余の供与を決めた。効果を見守りたい。
(注)BOT方式(Build, Operate and Transfer scheme)先進国企業が開発途上国において、インフラストラクチャー・プラント等を建設し、その総資金の回収を一定期間自らが操業した売上げにより回収した後、当該国の政府機関等に所有権を譲渡する方式。他方、建設期間後直ちに資産は移転し、操業を委託する方式をBTO方式(Build, Transfer and Operate scheme)と言う。
4 電話網拡充事業
(1)事業の目的と概要
タイ国内の電話需要の急増に対処するため、タイ電話公社(TOT=Telephone Organization of Thailand)が、タイ全土に交換機増設・更新、加入者ケーブルの新増設を行う。調査対象の円借款は、1990年会計年度に加入者ケーブル敷設工事を始めた交換局、および91年会計年度に工事を始めた交換局管内のケーブル敷設工事費、資材・機材購入費の外貨分。すでに貸付が実行され、工事も完了している。
(2)事業の現状
円借款対象事業で整備された無人交換局を、現地調査した。バンコク北方のPathumthani県にあるNong SuaとSananrakの2局である。農村地帯で付近の国道沿いには商業施設や住宅(農家以外の)進出も観察された。2局とも「無人」とはいうものの敷地内に番人小屋ともいうべき建物があり、番人(メインテナンスの技術者ではない)が、鍵を保管し、交換局の設備、機材の盗難などに備えた見張り役をしていた。1局はNEC製の、1局はNEC製とシーメンス製の交換機を備えていた。
付近の銀行支店で、交換局設置以前との変化を聞き取り聴取すると、電話設置が可能となったことで、地域に移り住む住民が増えたということであった。
なお、本借款以降の第7次経済社会開発計画(1992~96年)においては、電話普及率100人当たり10を目指し、TOT自身による回線増設に加え、TOTがテレコムアジア(TA)とTT&Tの民間事業者2社にConcessionを与え、BTO(Build, Transfer and Operate scheme)方式での電話網建設を推進している。また、TOTがタイの国有企業の民営化第1号に指定され99年から、その最初のプロセスが始まる。
(3)評価と展望
電話網は、情報化社会の基礎的インフラである。長らくタイ国内電話の独占事業者であったTOTへの円借款は1968年の第一次借款以来、累計で千億円を優に超えており、タイの電話網充実に果たした役割は大きい。評価者は70年代に数度タイを訪れ、バンコク市内の通話もなかなかつながらない電話事情の悪さを身をもって体験しただけに隔世の感がある。ただ、近年、BTO方式による民間事業者の参入があり、TOT自身も民営化を模索しており、新たな円借款の要請はなくなっている。
1998年7月時点の統計によれば、タイの電話回線数は499.9万回線で、100人当たり8.11に達している。ただ、内訳はバンコクエリアが276.8万回線と半分以上を占める。バンコク市内の電話普及率は、すでに先進国並みに到達しているが、地方の普及は遅れ格差が歴然としている。地方の電話網充実が急務だが、民間会社によるConcession方式では、民間業者に普遍的な整備を義務づけていないため、地方でも採算の合う比較的人口の集中した地域(都市)が優先され、人口密度も所得も低い農村部などは後回しになるのは当然であろう。またTOT自体も民営化され、収益が重視されるようになれば、地域格差の是正は容易ではあるまい。
TOTによれば、アジア開発銀行(ADB)より1億ドルの借款を受け、約4,500か所(3,500集落を含む)に長距離公衆電話を設置するプロジェクトを進めており、2年以内に整備されるという。携帯電話の普及も二百数十万台に達しているが、日本に比べても価格が高く、所得水準を考慮すれば、バンコクなど都市部での普及が先になり、地方の貧しい地域でケーブル回線の未整備を補完する役割を果たすとは考えにくい。なお、携帯電話の出現で、500キロメートル以上の長距離では、固定電話(1分18バーツ)、携帯電話(同12バーツ)の逆転が起きている。また、固定電話の市内通話は通話時間にかかわらず1回3バーツで、料金体系の見直しが課題になっている。
第8次経済社会開発5カ年計画では、電話普及率を2001年までに100人あたり20という目標を定めている。しかし、経済危機に遭遇し、外資系の民間事業者がバーツ切下げで打撃を受け、回線増設は足踏みしており、計画の達成は困難な情勢である。
5 まとめと提言
(1)バンコク一極集中の是正
個々のプロジェクトの評価を超えて、タイの社会資本整備全般について、横断的な問題点として、以下のような諸点が指摘できよう。
(イ)経済危機に遭遇したことで、高度成長時代に策定した社会資本整備計画の基礎となる需要予測(例えば港湾貨物取扱量)が下方修正される可能性がある (ロ)IMFとの合意で緊縮財政を迫られており、政府の公共投資削減が継続中のプロジェクトの進捗を遅らせる可能性がある (ハ)財政上の制約からConcessionn(BOT方式)への期待が強まろうが、経済危機で民間部門もリスク負担能力が低下している (ニ)以上の結果、タイの社会資本整備が全般的にスローダウンする懸念があり、一方で円借款への期待が高まることが考えられる。
以上を踏まえ、今後のインフラ整備に対する協力で留意すべき点を考えてみたい。
タイ社会の大きな歪みは、バンコクへの一極集中、その裏側の地方の貧困である。バンコクの人口は700万人に迫り、タイの人口の1割を超えている。第2位の都市はその20分の1の規模である。また、タイのGDPの約半分をバンコクが占めており、いわゆる「首座都市」の地位にある。バンコクと、その他地域の格差は、おしなべて広がっており、一人当たり所得では、最も貧しい東北部と10対1もの格差がついている。
タイ国民全体の福祉向上には、社会資本の整備も含め地方の生活水準の底上げが不可欠である。その場合、BOT方式には限界がある。採算性が優先されるため、どうしても人口、富が集積するバンコクとその周辺に投資が偏ることになる。BOTへの過度の依存は、一極集中を助長しかねない。地方の社会資本整備は、やはり公的セクターが中心になるべきであろう。財政資金の不足を補う円借款による協力の余地がある。
(2)製造業・輸出主導型の見直し
格差是正には、地方での雇用創出が不可欠である。何もなかった地に一大工業地区を建設したという意味で「無から有」を生んだ東部臨海地区開発は一つのモデルだが、バンコクから100キロメートル余りという立地は、見方によっては大バンコク圏の拡大とも言えなくもない。また、これまで製造業中心の開発が、新規雇用の大半を吸収してきたが、世界的な製造業の設備過剰という状況下では、総花的な工業化は禁物で、タイが比較優位を持つ分野を見極めた上で、重点化をはかるべきである。例えば、東南アジアの中では、比較的早くから外資が進出し、関連産業の集積が進んでいる自動車産業などは、その候補である。
アジア、中南米、東欧などの新興工業国の相次ぐ世界市場への参入により、製造業の育成→輸出主導型成長という成長戦略は、見直しを迫られる。内需の重視や、工業製品輸出以外の外貨獲得手段の開発に努める必要があろう。内需の拡大の一方策として公共投資の活用がある。タイのように社会資本の整備が不十分である一方、財政の黒字を維持してきた国に対し、一律に緊縮財政を求めるIMF流のやり方は、疑問なしとしない。
タイの場合、製造業以外では農業の見直しがあげられよう。就労人口の半分が農業だが、タイの土地生産性は米で比較すると、先進国はもとより、インド、バングラデシュ、ミャンマーなどアジアの発展途上国よりも低い水準にある。中国などの所得向上のためにも、有力な輸出産業として農業の生産性の引き上げ必要だ。また、21世紀の世界的成長産業として「観光」が注目されているが、ホスピタリティーに富む国民性は、タイの見えざる資産である。農業や観光のインフラの整備などでも、わが国が協力する余地は大きい。
タイの弱点として、初等教育の普及率や識字率が高いのに、中等教育に進む比率がフィリピンやインドネシアなど、一人当たり所得でタイより貧しい近隣国より低いことがあげられる。タイの国際競争力を考える上で看過できない。製造業の付加価値の引上げや、情報、サービス、観光など第3次産業の興隆にも中等教育の拡充は不可欠だ。
(3)円借款のPRに工夫を
なお、タイに限らず円借款全般について以下の点に配慮を求めたい。日本人専門家の現地での活躍ぶりが、庶民の目に映りやすい「顔が見える」無償の技術協力などと異なり、円借款は、借款供与先機関には感謝されても、一般の人達に「日本の協力事業」であることが伝わりにくい。例えばバンコクのチャオプラヤ川に架かる橋の大半が、円借款協力によるものだが、バンコク市民で、そのことを知る人は少ない。円借款一般について、日本からの援助であることを、もっとPRする工夫が欲しい。
調査スケジュール
| 月日 | 時間 | 行程 |
| 11月28日(土曜日) | 11時00分 | 成田発JL717 |
| 17時00分 | バンコク着 大使館およぴOECF事務所と打ち合わせ |
|
| 11月29日(日曜日) | 10時00分 | バンコク(クロントイ)港現地視察 |
| 13時00分 ~17時00分 |
首都高速道路(Express Way)全区間ほかバンコク市内の円借款対象の全通路、橋梁、陸橋等の走行・視察 | |
| 11月30日(月曜日) | 10時00分 ~13時00分 |
Della Grand Pacific Hotel~王宮付近を往復。往路Express Way復路一般道路で平日の道路状況走行体験 |
| 15時00分 | OECF事務所訪問。各プロジェクトの説明を受ける。 | |
| 12月1日(火曜日) | 10:00 | タイ電話公社訪問。Mr. Pongprayoon(Vice President)はじめProject Management, Financial Management, Loan Management各sectorの幹部より説明。 |
| 13時00分 ~16時00分 |
Nong Sua, Sanarak両無人交換局現地調査 Senior Engineering StaffのMr. Sintanakulらから説明。 | |
| 12月2日(水曜日) | 10時00分 | 道路局訪問 Mr. Ruthirakanok(借款管理部Director)からプロジェクト概要の説明。 |
| 11時00分 | バンコク外環状東部道路の現地走行調査。Project Managerから施工管理、工法等の説明。 | |
| 14時00分 | バンコク―チョンブリ道路経由パタヤヘ | |
| 16時30分 | パタヤ着 | |
| 12月3日(木曜日) | 9時00分 | レムチャバン港湾局訪問Mr. Mankong(Asst. Managing Drector)よりプロジェクトの概況、将来像の説明。 |
| 10時30分 | レムチャバン港現地調査パシフィック・コンサルタンツ社から説明。 | |
| 13時00分 | Easrern Sea Laem Chabang Terminal社訪問。 | |
| 16時30分 | バンコク着。 | |
| 12月4日(金曜日) | 9時00分 | NTTバンコク事務所でタイ電話事情の説明を受ける。 |
| 12月5日(土曜日) | 8時30分 | バンコク発JL708で帰国。 |
インタビュー先リスト
- Telephone Organization of Thailand(TOT)
Vice President Samran Pongprayoon
Senior Director, Sector of Financial Management Waraporn Suwanakitti
Assistant Senior Director, Project Planning Sector Sujet Muchtisarn
Senior Engineering Staff, Department of Project Management Pairat Sintanakul - Department of Highways(DOH)
Director, Loans Control Division Jeerawat Ruthirakanok - Laem Chabang Port
Assistant Managing Drector Pichade Mankong - Pacific Consultant International
Project Manager Moriyoshi Sakurada
Engineer Edmund I. C. Hong - Nippon Koei Co,
Senior Highway Engineer Mineo Endo - Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co,
President Toshiki Kobayashi - NTT Bangkok Representative Office
Deputy General Manager Naoki Kajita
以上のほか、邦銀タイ現地法人幹部、日本メディアのバンコク支局特派員らから非公式に経済・金融情勢などの説明を受けた。また、日本国内の港湾・海運関係者、タイ駐在経験のあるビジネスマン、ジャーナリストからも情報提供を受けた。
収集資料リスト
| OECF Contribution to Thailand | OECF Banbkok Office 98/5 | |
| ANNUAL REPORT(96年版) | Telephone Organization of Thailand | |
| 同上(97年タイ語版) | 同上 | |
| Deteils of Loan Disbursements | 同上 | |
| LAEM CHABANG PORT | Port Authority of Thailand | |
| Performance of Laem Chabang Port | 同上 | |
| バンコク東部外環状道路建設事業概要 | OECF | |
| レムチャバン商業港建設事業概要 | 同上 | |
| タイ電話網拡充事業概要 | 同上 | |
| 東部臨海開発計画の概要 | 同上 | |
| タイの電気通信事情について | NTTバンコク事務所 98/11 | |
| タイ経済の長期展望 山沢成康 JCER PAPER No.55 | 日本経済研究センター 99/2 | |
| 我が国の政府開発援助の実施状況(97年度)に関する年次報告 | 大蔵省印刷局 98/9 | |
| アジア通貨危機に学ぶ | 外国為替等審議会 アジア金融・資本市場部会 98/5/19 | |
| アジアの大都市[1]バンコク | 大阪市立大学経済研究所監修98/9/5発行 日本評論社 | |
| タイ経済入門〔第2版〕 | 原田泰 井野靖久 著 98/8/10発行 日本評論社 | |
| ほかに BANKOK POST 等タイ現地紙の関連記事 | ||

