3.農業開発とジェンダー(ラオス)
(現地調査期間:1998年10月22日~10月31日)
| ■ | 敬愛大学国際学部教授 | 星野 昌子 | 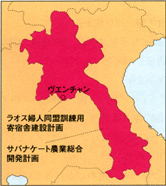 |
〈評価対象プロジェクトの概要〉
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |
| サバナケート農業総合開発計画 | 開発調査 無償資金協力 |
93年度、4.98億円 94年度、4.76億円 95年度、12,51億円 |
ラオス政府は同国南部の中心地であるサバナケートにおける灌概事業を中心とした本計画を策定し、同国政府の要請に応じ、農業支援センターの建設、灌慨用堰および用水路の建設、農村道30㎞の改修、灌慨施設の維持管理機材、普及用機材の調達を実施した。 |
| ラオス婦人同盟訓練用寄宿舎建設計画 | 草の根無償資金協力 | 95年度、82,027ドル | ラオス婦人同盟は、ラオス人民革命党の一機関として、ラオスの女性の地位の向上、女性の生活、福祉の改善のための活動を全国的規模で行っているが、首都ヴィエンチャンの訓練センターには宿泊施設がないために地方からの参加者に対する効果的な訓練が出来ない状況である。そこで、ラオスの婦人の活動を支援するために、同センターに25~30人が宿泊できる訓練用寄宿舎を建設する。 |
I はじめに
評価者は1965年、青年海外協力隊員としてラオスに赴任し、6年間首都ヴィエンチャンで日本語教育に従事した。
ラオスにおける我が国ODAの経緯は、1966年より有償、無償資金協力で開発されたナムグムダムをはじめ、当時実施されていた上水道開発、空港整備等々を土台に、75年からの社会主義革命政権時代を経て、新経済メカニズム開発以降へと引き継がれて来た。91年からは継続して、援助国間のトップドナーとしての位置を占めるに至っている。
1995年の実績では、対ラオス援助全体の31.9%、対ラオス二国間援助の41%を占めている。
現在では、住民との対話を重視する農村開発、インフラ整備、社会開発及び多様な分野での草の根援助の増大へと移行している。LLDCであることから、1996年10月に、ナムルック水力発電所建設計画に対し、特例として円借款を供与していることを除けば、従来どおり無償、技術協力が中心である。今回暼見しただけでも、評価者が滞在した60年後半においては、想像だにしなかった変化を遂げている。
その変化は一言えば「量から質への変換」である。主な理由として、環境保全という世界的課題、UNDPが第5回ラオス国別援助計画(1992~96年)に挙げる「人的資源開発」、そして我が国ODAの基本方針「国造りは人造りから」に「住民参加」の考え方が加ったことによると考える。
II 調査日程
| 月日 | 時間 | 行程 |
| 10月22日(木曜日) | 11時00分 | 成田発(JL717) |
| 15時15分 | バンコク着 | |
| 10月23日(金曜日) | 10時30分 | バンコク発(TG690) |
| 11時40分 | ヴィエンチャン着 ブリーフィング(於:ホテル)
在ラオス日本大使館 JICAとの打ち合わせ |
|
| 10月24日(土曜日) | 08時30分 | ホテル発(陸路約5時間)途中参考視察
「1996年度草の根無償案件「カムアン県環境保全研修センター」(於:タケク) |
| 17時00分 | サバナケート着 | |
| 10月25日(日曜日) | 08時30分 | 「サバナケート農業総合開発計画」視察 |
| 09時00分 | 農業支援センター | |
| 11時00分 | 農民リーダーとの集会(於:支援センター) | |
| 13時00分 | KM35プロジェクト(H.Bak地区及びダム) | |
| 13時45分 | 丘陵ラオ居住村訪問、住民との対話 | |
| 15時00分 | 低地ラオ居住村訪問、住民との対話 | |
| 10月26日(月曜日) | 08時10分 | スカズム・サバナケート県副知事表敬 |
| 09時15分 | ナ・ケー農業訓練センター視察
サバナケート橋梁建設予定地 |
|
| 13時30分 | KM35プロジェクト(H.Xay地区)
低地ラオ居住村訪問、住民との対話 |
|
| 15時00分 | 村人による歓迎の集い(バーンー儀式と懇親会) | |
| 10月27日(火曜日) | 08時30分 | 参考視察
1997年度無償「第二次国道十三号線橋梁改修計画」 |
| 16時00分 | ヴィエンチャン着 | |
| 10月28日(水曜日) | 09時15分 | 「1995年度草の根無償案件、ラオス婦人同盟寄宿舎建設」視察 同行 |
| 10時45分 | 各県からの研修生と面会(寄宿舎食堂) | |
| 11時30分 | 参考視察「高等技術電子学校」
「バス修理工場」「シーサタナク地区病院」等 |
|
| 10月29日(木曜日) | 09時00分 | 参考視察「1995年度プロジェクト技術協力・1996年度草の根無償案件、ヴィエンチャン県農業農村開発計画」 |
| 10月30日(金曜日) | 10時30分 | ヴィエンチャン発(TG691) |
| 11時35分 | バンコク着 | |
| 10月31日(土曜日) | 08時45分 | バンコク発(JL708) |
| 16時35分 | 成日着 |
III 個別対象事業に対する評価
III-1.サバナケート農業総合開発事業
(1)事業概要
イ、背景
ラオス農業はGDPの約60%、農民は人口の約72%を占め、農業生産が国家経済の鍵を握る。農業開発は、第一次・第二次及び第三次5ヶ年計画の基本政策に則って実施されたが、ヴィエンチャン平原に集中したため、結果として極端な地域格差が生じた。
政府は地域格差の是正と、地域毎の食料自給体制を確立する政策に則って、1990年に農業開発に大きな可能性をもつと思われるサバナケート県の農業総合開発計画の策定を決定した。90年末から93年9月までの、JICAによる調査の結果、サバナケート県のホワイ・バック上流及びナム・プー両地区の灌漑施設、農業支援センター、農村道路(改修)、生活用水の給水施設などの建設、ならびに機材供与を日本の無償資金(93~95年度:総額22.25億円)により実施した。
ロ、目的
- (a)食糧生産、特に雨季作の安定と生産性の向上を図る。
- (b)乾季水稲作付面積拡大と作付作物の多様化。
- (c)新しい方式の生産、営農技術の普及拡大。
- (d)地区内の物流の円滑化。
- (e)周辺農村住民の生活基盤改良、保健衛生条件の改善。
ハ、対象地域
首都ヴィエンチャンの東南約500キロメートル、県都サバナケートの東南35~40キロメートル、年間降雨量1,384ミリメートル。灌漑対象地域ホワイ・バック上流地及びナム・プー地区の農家戸数2,504戸、人口13,753人、灌漑施設建設のための対象面積はホワイ・バック上流地区950ヘクタール、ダム有効貯水量14,541,000・ナム・プー(ホワイ・サイ上流)地区410ヘクタール。
(2)評価
イ、評価の目的
上記農業用ダム、用水路、農道、支援センターの建設は計画通り完成し、今回は灌漑・給水の効用、食糧生産の増大、作付けの多様化、農業普及状況、農民の自主性、機材運用状況等についての評価を目的として視察を行った。
評価のために必要な情報は、事前に経協局評価室により提供された諸資料に加え、現地では、以下の方々から入手した。ホワイ・バック上流地区2ヶ村(丘陵ラオ居住村と低地ラオ居住村)の住民、及びホワイ・サイ地区の水利組合理事級農民リーダー諸氏、ランシー農業省灌漑局長、スックカスーム、サバナケート県副知事、農業支援センター所長並びに両副所長、JICA派遣専門家、協力隊員、企業関係者等。
ロ、評価の結果
(a)ダム建設自体について(参考)
今回は事後評価であり、ダム建設自体の可否を論ずることは含まれていない。しかし評価者は長期に亘ってNGOを通して国際協力に係わってきたため、「ダム建設は百害あって、一利無し」とする先入感が強い。従って、農民の方々を中心に、このダム建設についてしばしば質問したが、「被害を受けた、或いはダムが無かった時の方が良かった」という意見には出遇わなかった。
ダムの規模が小さいこと、人口密度が低いことから、代替地がそれまで居住していたところより肥沃であったり、川や道路に近くて条件が良かったりしたことが原因と推察した。ランシー農林灌漑局長によれば、ダム建設によって水没した家屋は13軒、対立を生じたのは一家族それも代替地に関する交渉の段階で、3ヶ月で円満解決に至ったとのことであった。
(b)プロジェクトの理念とラオス側の方針
国レベルでは双方の合致について確信に満ちている。それを受けて地方自治体はこのマスタープランに100%応えようと懸命に努力しているという印象を得た。県レベル以下においては、本プロジェクトの運用が始ったばかりで、ローカルの利益に合致すると確信を持てるまでに、もう少し時間が必要だと考えている。
(c)他組織との関係
サバナケートには、UNDP、IFAD、ADB、EUその他の組織が関わりを持つが、日本の当案件に対して、理念、活動地の衝突、オーバーラップその他の齟齬は生じなかった。
(d)事業の効用、成果
灌漑・給水の効果は大きく、サバナケート県のみならず他地域にも大きなインパクトを与えている。県内は勿論のこと、隣接県の行政関係者や農民が毎週見学や研修のため現場を訪れている。食糧生産も増加の傾向にあり、作付けの多様化も見られる。
そのため、「サバナケートは既に道路、電気もあるのだから、もっと遠隔の地、例えば山間部などで実施して欲しかった」との苦情が寄せられているとのことであった。
(e)農民の自主性
評価者はかねてから「権限を持たない一般の人々の心に、『遣る気』の火を点すことができないプロジェクトは失敗に終わる」と考えている。そこで村の住民(男女とも)とこの点にしぼって現地語で対話を行った。
先づ現在中心的役割を果している「水利組合」は、どのように作られているか。上から決められたものではないのか。結果として以下のことが解った。
水利組合は、以前からあった農民組織が再編成されたものだが、参加は強制されていない。自由意志に任されている。しかし干ばつの際、水路の成果を見て、参加させて欲しいと申し出るケースが多く、組合員は次第に増加している。
第三次水路の建設には、農民自身が農業振興銀行(Agriculture Promotion Bank; APB)から資金を借りて実施しているのを見ても、農民の自主的参加は顕著であると評価した。
(f)「開発における女性(WID)」の視点から
ホワイ・バック地区の2ヶ村並びにナム・プー地区のいづれにおいても、現在女性は水利管理の技術指導を受けてはいないが、水路修理には参加している。しかし伝統的習慣により、男性は結婚の際、妻の両親の所有する土地に家等建てて住むことや、不動産は末子(多くの場合、娘)が相続するために、銀行から金を借りることができるのは女性である。評価者がこの点について、ランシー氏に質問したところ、「私が農林省局長であっても、銀行から金を借りる場合は、妻の名義で行います」との返事であった。
従って、先に述べた農民がADBから金を借りて第3次水路を建設する場合、妻もリスクを背負う。開発の受益者に止まらず、女性も自ら主体的に開発に参画している。
(g)農業支援センターの機材管理状況
ブルドーザー、ホイルローダー、バックホー、モーターグレーダー、ダンプトラック、散水車、スペアパーツ等の機材の管理は県と政府が行っている。遠方に貸し出すと管理が困難なので、近隣地域への貸し出しが多い。遠隔地における需要に応え難いという難点が残るが、現状では止むを得ないと思われる。
日本が機材を供与しても、スペアパーツの補給が充分でないため、放置されてしまうケースに、評価者はソマリアやエチオピアで出遇ったため、この点について質問したが、機材の選定に当たり、この土地でよく使用されていて、タイで部品調達できる機材を選んだので、パーツ不足等の問題は生じていないとのことであった。
(h)ラオス政府による今後の計画
このプロジェクトのハード面は既に整い、行政、住民双方から評価が高いので、次の段階として、
- (i)研修、訓練の強化
- (ii)良い指導者によるリーダー組織の強化
- (iii)米の増産とライスバンク(30キログラム~40キログラム)の設置
- (iv)換金可能な良質の米、野菜、豆、ピーナッツ等の耕作指導
- (v)魚の養殖
- (vi)成果物をどう売るかという視点の育成、市場調査の導入(大がかりな調査ではなく、農民が身近なところで新しい考え方で調べる)
等の展開を希望し、引き続き日本から指導者を求めている。
(3)教訓と提言
イ、農民の本音を汲み上げる
外国からの援助事業に関する評価視察者と、受益当事者が対話を行う場合、一般に次のような場面が展開される。あらかじめ選ばれた代表が謝辞を述べ、評価には参考にならない挨拶が繰り返されることになる。
今回も例外ではなかったが、一通りの終了を待って、評価者から「お言葉は有難く承るが、訪問の目的は謝辞を聴いたり、次の要望を聞くことではない。この事業に対する不満や改良への提案などあれば是非伺いたい」と促したところ、次のような発言があった。
「雨季の水不足が解消されたこと、又乾季の耕作がこの事業によって可能になったことは本当に嬉しい。しかし自分達はラオス政府、日本人専門家、協力隊員がすすめる粳米ではなく、昔から我々が作ってきた餅米をもっと作りたい」。
数名の代表者が賛意を表し、それ以外の多数も頷いている。「それはどんな理由からですか」との質問に対し、彼等は以下のように改良種粳米と在来種餅米を比較した。
-
(a)在来種の長所
長期に亘って使える。生産が安定している。土が悪くて水も少ない所でも育つ。香りが良い。多くの人が使っていて売り易い。期間がずれても栽培できる。たくさんの実が付く。少しなら水に倒れても育つ。病虫害に強い。化学肥料が要らないから、金がかからない。 -
(b)在来種の短所
いくつかの品種は食べると固い。茎が細い。栽培期間が長い。株分かれが少ない。生産力が低い。 -
(c)改良種の長所
生産力が高い。株分かれが多い。生産期間が短い。二期作が可能。倒れにくい。食べて柔らかい。 -
(d)改良種の短所
病気にかかり易い。土の栄養を吸い盡くす。大量の肥料を食う。水が充分無いと栽培できない。3年しか種が取れない。現金が手許にないと耕作ができないので大都市に男女とも出稼ぎが必要になる。家族一緒に生活したいので、改良種への移行をためらう。 - (e)農民の感性に適合する速度の変化
以上(a)~(d)の発表をする時の彼等は挨拶の時とは違って、真剣に本音を発していると思われた。そして低地ラオの人々に比べて、より厳しい条件にあった丘陵地出身の人々が、一段と真剣であることに感銘を受けた。これは干魃・洪水の年には自給できなかった過去の経験や、現金収入を求めて都市への出稼ぎを経験したことから来る「自衛本能」で、尊重する必要があると考える。
ランシー灌漑局長も、「粳米は市場価格が50%も高いのに、農民は餅米を作ってしまう。町中では粳米の需要が高く、現在はタイから輸入している。自給できるようになれば良いのだが……」と困惑しておられた。
評価者は米作りの専門家ではないので、適確な判断に欠けるかも知れない。しかしこの辺りは充分考える必要があるのではないか。換金作物栽培を奨励し、自給自足農業からの脱却を余りに急げば、折角自主的に関わろうとしている農民の意欲を削ぐことになる。化学肥料への依存を避け、有機肥料の作り方も教えるべきである。折角ともされた「遣る気」の火を消してしまっては、この事業の最終評価の定価にも関わるだけでなく、ラオスの真の国造りも望めないのではないか。
ラオス政府が産業化、近代化を急ぎ、GDPの増加を望むことも理解できるが、「安定した自給農業」に農民が確信を持てず、不安を抱いている。安心できる状態づくりが第一であり、その暁にはゆとりができて、新しい優良種や多様な農作物作付けに対する意欲も自づから生まれるであろう。何よりも彼等の意識に見合った速度の変化を支援する姿勢が望まれる。
ロ、人材派遣の今後
(a)求められる人材像
この事業の目的を達成するには、今後も長期に亘る指導者の派遣が必要である。指導の内容は、知識、考え方や技術の訓練に止まらず、生活習慣の伝達にも及ばざるを得ない。例えば水利組合の理事達でさえ、次のように語る。「今までは天の恵みに任かせて、苦しいことも多かったが楽なこともあった。今は水を得て、いろいろな可能性も出てきた代りに、時には夜も安心して眠れない。‘ざりがに’や‘もぐら’、‘ねずみ’などが土手に穴をあけて水が流れてしまうので、修理に追われ大変だ」。且っての日本の農村では当然であったことも、馴れぬ彼等にとっては難しいようだ。
そのような状況の下、現在派遣されている専門家や隊員の懸命なご盡力は印象的であった。しかし今後息長く対応するためには、日本の省庁や企業出身の方々や若者ではなく、長年農業にたずさわって来た昔のやり方を知っておられる中高年の方々の参加が望ましい。それもJICAの既存の枠組みの中で、専門家やシニアボランティアとしてリクルートされるのではない形が望ましいと考える。
(b)自治体及びNGOとの連携
例えば近年、国際協力への関心が高まりつつある自治体とNGO、それも我が国とラオス双方の4者協力に持ち込み、それをODAが支援する可能性は無いのだろうか。
我が国においてもNGO-ODAプロジェクト(フィリピン「家族計画・母子保健」AMDA、筑波大学医学部とODA、等)や、研修員受入れ分野におけるNGO-ODA協力(OISCA、InternationalとODA)、自治体-ODAプロジェクト(ネパール「公衆衛生」(埼玉県とODA)等、年々協力のケースは増加の傾向にある。
しかし評価者がここで提案したいのは、日本ではまだ始まっていない国際協力の型である。即ち、「ラオス側自治体=サバナケート県」、「ラオス側NGO=水利組合」という2者に対し、「日本側いづれかの自治体」と「その地域に本拠を置くNGO(中高年の農民を捲き込む可能性をもつ団体)」という2者、合わせて4者が立案の段階から対等に参加し、これをODAが支援するという新しい型である。
(c)3 オランダにおける参考例
(i)概要
この型による4者協力は1980年代からオランダの複数の自治体がニカラグアの自治体との間で開始し、例えばユトレヒト市――レオン市の間では、熱帯果樹栽培や都市と農村における町づくり計画等、オランダ政府やEUからの特別補助金を得て成果を挙げている。特徴として双方のNGOが現場レベルで活動していることが挙げられる。
(ii)対等なパートナーシップ
協力のメリットはニカラグア(レオン市側)に多くあると言えるが、オランダ(ユトレヒト側)が学ぶこと、例えば市民に対する開発教育の情報受信などがあり、双方は常に対等な関係を保っている。問題は両市で解決するのみならず、毎年行われる評価にも、双方が対等に関与する。
(iii)自助努力の促進
先ずは被援助国の地域の人々にとって、欠くことの出来ない条件は何かを、住民自身が洗い出し、必要なデータを提供するところから始まり、他の三者を捲き込むという、「小さく始めて積上げる、ボトムアップ方式」だが、開始から約10年後の1993年には事業はオランダの手を離れ、レオン市と住民組織にゆだねられるケースも出ている。
(以上は、1997年11月、評価者が総理府対外経済審議会委員としてニカラグアを訪れた際の参考調査の中から得たもので、詳細は研究ノート、「オランダ――ニカラグア間の開発協力に見る、自治体-NGO-ODAの連携」星野「敬愛大学国際研究」第2号/98年11月を参照されたい。)
我が国においても、1996年4月に地域からの国際協力のために、自治体・NGO・市民の間の連携を目指す緩やかなネットワーク組織として、「自治体国際協力推進会議」が誕生した。現在は調査研究、国際会議への参加、シンポジウム開催そして政策提言を行っているが、将来的には、本件(サバナケート農業総合開発事業の運用面でのフォローアップ)等への参加意欲も生まれる可能性があると考える。
III-2.ラオス婦人同盟訓練所用寄宿舎建設事業
(1)事業概要
イ、背景
ラオス婦人同盟は、ラオス人民革命党の一機関として、ラオスの女性の地位の向上、女性の生活、福祉の改善のための活動を全国的規模で行っている。1995年に北京で開催された、国連第4回世界女性会議にも代表団を派遣して、ラオス女性の活動ぶり等について発表を行っている。
ロ、目的
同婦人同盟としては、今後全国の女性代表を同盟の本部がある首都ヴィエンチャンの訓練センターに招いて、セミナー、ワークショップ等行っていきたいとの希望があった。同センターには宿泊施設がないために、地方からの参加者に対する効果的な訓練ができず、ラオスの全国的女性活動の推進を計る上で、多大な支障をきたしていた。木造2階建て、25~30人が宿泊できる訓練用寄宿舎を建設し、活動を支援することを目的とした。
ハ、経過
1996年10月工事完了、ラオス婦人同盟の事務所に接する敷地内に建設された寄宿舎の総工費は約8万2千ドル、同年12月にラオス側に引渡しが行われた。遠隔地の女性たち及びその家族の生活改善に役立つだけでなく、この国の社会経済に与える効果が期待されている。
(2)評価
イ、評価の目的
ブアボン婦人同盟副委員長との一時間余に亘る質疑応答、寄宿舎、授業参観や受講者との対話を通して、訓練の内容、参加者の人選方法、施設の活用状況等を評価する。
ロ、評価の結果
(a)訓練コースは、男女の役割り(性別役割分業からの完全脱却と男女共同参画社会の実現)、職業訓練の計画の立て方、プロジェクトの計画の立て方の三つに絞っている。
男女共同参画社会の考え方は北京会議以降の世界の方向性に合致している。訓練の内容は、既存の訓練に従わせるのではなく、地域の必要に応じて、それぞれの参加者が、自ら立案する力を付けさせようとしており、方向性は前向きである。一人一人のエンパワーメントに力点が置かれているところは北京会議の結果を充分に取り入れている。
(b)関心が寄せられている分野は、農業、畜産、織物、縫製、生け花、そして最近では外国語研修の必要を感じている。
(c)地方からの参加者の選考については、各県に基準を提示して、人選を任せている。中央で指名するようなことは行っていない。評価者は、人選において年令、生まれ(何系ラオであるか、家柄、有力者との関係の有無など)に関係なく、参加の意志を持つ女性が参加できるような、民主的なものであるかどうかは、このプログラムにとって重要であると考え、質問を重ねた。
「現在は公募は行っていない」、とのことであった。評価者は「将来的には、公募と推薦の併用が望ましい」旨、ブアボン婦人同盟副委員長に伝えたところ、「将来的にはその方向で検討したい」との返事を得た。
(d)女性分野に対する協力の今後
ラオス婦人同盟は中国の婦女連などと同じく、政府の一機関であるが、国連世界女性会議などにはNGOとして参加している。国際的には「QUANGO(quasi-NGOの略、疑似NGO)」と呼ばれる「政府主導の民間団体」である。社会主義国では、結社の自由が無いから当然のことだが、ちなみに民主国家であっても日本や旧西ドイツにはQUANGOが多いと、国際社会ではみなされている。
ブアボン副委員長によれば、「ラオス婦人同盟は政府の重要な一機関であり、首脳部は待遇その他、人民革命党により手厚く取扱われていることに誇りを持っている」とのことである。このことは充分評価されて然るべきではあるが、地域における自発的な女性の力は発揮され難い。
評価者はラオス側の事情に口をさしはさむ意図は全く無い。しかしながら少数ではあってもNGO的な、ボトムアップの活動の誕生がラオスにも散見される現在、今後我が国のODAが女性分野で協力する場合、引き続き当同盟を通して行うかどうかは、課題として検討する必要がある。
(e)WIDの考え方について
WIDは改めて述べるまでもなく「WOMEN IN DEVELOPMENT(開発における女性)」の略語で、一口に言えば、「女性が自ら開発に参画すること」を意味する。その裏には「従来のように女性が開発の単なる受益者とされていたことからの脱却」の意味が含まれている。しかし我が国では二つの理由で、一般に間違って解釈されて来た。一つはWIDが「開発と女性」と同格に並べて訳され、普及したこと。もう一つは「開発」自体の意味を狭義に捕えて、開発という行為に主体が忘れ去られたことによる。(「開発」についてはP.394を参照いただきたい)
又JICAではWIDを「途上国の女性を援助すること」と解説している場合があり、我が国の広い地域に亘っての女性行政に、誤った概念を生じさせる原因となっている。
UNDPによる「HUMAN DEVOLOPMENT REPORT 1995」によれば、人間開発指数(HDI)の世界順位において、174ヶ国中、日本は3位、ラオスは138位と大差がある。
一方「GENDER-RELATED DEVELOPMENT INDEX(GDI)(ジェンダー、社会的・文化的性差関連の開発指数)」では、日本は8位、ラオスは96位となる。GDIの算出にも、HDIと同様、平均予期命年数や識字率が含まれるため、日本は当然優位に立つ。しかしGDI算出のための一項目、例えば収入の男・女比率は日本35.7%(女性)対64.3%(男性)であるのに対し、ラオスでは37.8%(女性)対62.2%(男性)と平等度が日本より高く、ラオスのこの比率はノールウェイのそれに等しい。
又UNDPのこの報告書(P.76~77)はHDIの順位からGDIの順位を引いた数値をも国別に示し、プラスになる場合は、平均的人間開発の達成度に比べて、より良い男・女平等度を示すとしている。HDIマイナスGDIの数値は、日本、マイナス5、ラオス、プラス4である。即ち日本は平均的人間開発の達成度に比べて男女平等度が低いということになる。
このように我が国女性は健康と教育において優れているので、その点で途上国を指導・支援する資格を有するが、逆に途上国から学ばねばならぬ点もあることを充分考慮しつつ、今後のWID案件に対応する必要がある。
IV あとがき(開発への私見とともに)
はじめにも述べたように評価者は1965年からラオスで生活したが、71年には、ベトナム戦の激化に伴い、ラオスを離れてタイに移り住んだ。ラオスは75年に社会主義体制に移行したが、86年には解放と市場経済の導入に道を開いた。
この間、隣国にいて且つての教え子たちが難民となって、メコン河を越えて逃がれてくるのを難民キャンプを訪れて助けたり、1980年の日本国際ボランティアセンター設立後は、組織的救援活動に追われていたが、「難民たちが帰って行けるラオス」の再建は常に心から離れなかった。
1989年にラオス政府は、国連と西側諸国のODAならびにNGO関係者を招いて、解放後初の「経済協力に関する国際会議」を首都で開催し、評価者も日本のNGOを代表して参加した。18年ぶりであった。
NGOの財政は逼迫して航空券には手が届かず水路入国したため、タードゥアでの入国検査は誠に厳しく、カメラは没収された。西側の人間とラオス国民が接触することへの監視もあると聞き、旧友は古びたビルの屋上から手を振ってくれたが、こちらから振り返すことは遠慮するという有り様であった。
今回再訪の機会に恵まれて、都市・農村のいづれにおいても、昔ながらの素朴な笑顔に触れることができた。又我が国の一貫した協力現場の数々を訪れて喜びに堪えない。同時にこの国の健全な発展を心から願っている。
最後に開発についての私見を述べさせていただき、報告を終えたい。
17年間をラオスとタイで生活し、その間国際協力に関わった期間も長かったので、ラオス人やタイ人が「開発」(カーン・パタナー)という言葉によって意味するものには、「自分自身や村の成長・進歩」が含まれていることに慣れ親しんで来た。つまり「パタナー」という行為の主体が重視されていて、価値者自身もその意味で「開発」という言葉を使って来た。
ところが1982年に帰国すると、日本人が「開発」からイメージするものは、道路、港湾、ダム、レジャー施設などの、人間にとって便利なもの、経済効率を上げる物(多くの場合、自然破壊を伴う)であることに気付いた。つまり開発という行為の主体ではなく、対象のみに関心が向っているのである。そこから生まれるのが、「日本は高度に開発された国」という意識であり、「途上国を日本並みに引き上げてあげたい」に繋がる。
英和大辞典でDEVELOPMENTを引いて見た。発育、発達、成長、進展、開発、拡張などとあり、例文には人間精神の発達、虫から蝶へ、子どもが大人に、潜在的な可能性が低度から高度の段階に移行すること、などと続く。私が理解する英・仏・ラオ・タイ語での使われ方と合致する。自動詞的使用と他動詞的使用の双方が含まれているとも言える。それに対して日本語では他動詞的にのみ使われていると感じた。
その後1996年に協力隊機関誌「クロスロード」の新年号で、竜谷大学経済学部教授、中村尚司氏が「協力隊講座」の中で書かれた文章に出遇い、疑問を解くことができた。氏は、日本語ではDEVELOPという行為の対象に関心が向う時、「開発する」という訳語を使う。用例として、新田を開発する、資源を開発するを挙げておられる。しかしDEVELOPという行為の主体に関心が向う時には、「発展」という別の語を用いる。用例として、事件が発展する、男女関係が発展する。英語のDEVELOPMENTには、双方の意味が含まれている。従って日本では官公庁においても、訳語の統一ができていない。DEVELOPING COUNTRYを、外務省では開発途上国、通産省では発展途上国、経企庁では途上国のようにそれぞれ異なる訳語を用いる。そして中村氏は「開発を考える時、対象ではなく主体に関心を向けなければならない」と述べておられる。
以上を踏まえて、評価者は「開発」を次のように考えたい。
「開発」とは、人間、社会そして自然の中にある潜在的な可能性が自由に発揮されて、より公正な社会の構築に役立つよう、その阻外要因を取り除く行為である。
今回の評価対象事業の一つである「サバナケート農業総合開発事業にこれを当てはめると、この地域に灌漑施設を建設するという行為によって、自然(土壌・地形・河川・降雨量等々)が持つ潜在的可能性が引き出され、結果として、雨季作の安定と生産性の向上や乾季水稲作付面積の拡大や、多様な作物の作付けを可能にした。この意味において効果的な「自然」を対象とした開発であったと評価することができる。
同時に開発行為の主体である農民たちが、人工的な水利用に伴う、ライフスタイルの変化を自分のものとして、支援センターを利用しつつ自主的に活用できるようになって、初めてこの事業による開発が対象と主体双方に充分留意されたものとなる。プログラムはまさにその方向で進んでいることを評価したい。
農民リーダーの一人が語った言葉が印象的であった。「トゥン・ニャンダイ・コ・ターム、ハオ・エーン・トーン・パタナー(何はともあれ、我々自身が進歩しなければならない)」。
以上

