2.家族計画・母子保健プロジェクト(フィリピン)
(現地調査期間:1998年9月6日~9月19日)
| ■ | 津田塾大学国際関係学科教授 | 菊地京子 | 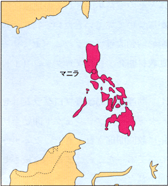 |
| ■ | 東京都立大学大学院 社会科学研究科社会人類学専攻 |
石井洋子 | |
| ■ | 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科国際関係学専攻 |
小林由美 |
〈評価対象プロジェクトの概要〉
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | 協力の内容 |
| フィリピン家族計画・母子保健プロジェクト | プロジェクト方式技術協力 | 1992年度~97年度 | (1)タラック州における家族計画母子保健サービス提供体制の改善、(2)住民参加の促進による地域保健活動の活性化、(3)家族計画母子保健に携わる人員の能力向上を通じて、タラック州における家族計画母子保健活動を改善する |
〈第一部〉
1.はじめに
本稿は、1998年9月6日から同月19日の期間に行なわれた「フィリピン家族計画・母子保健プロジェクト」の評価調査報告である。
評価チームは、本調査を、以下の2つの観点に沿って行なうこととした。すなわち、
- (1)同プロジェクトは、地域住民のニーズにかなったものか
- (2)同プロジェクトは、ジェンダーの視点に配慮されたものか
という点である。特に地域住民への影響を確認するため、調査日程の後半では、村落での参与観察を行ない、「住民の生の声をなるべく多く聞く」という点を重視した。本稿では、開発プロジェクトの立案・運営サイドに、できるだけ実現可能な改善点を提示することに努めたつもりである。また、2週間という限られた調査期間のため、調査が必ずしも十分であったとは言い難いが、同プロジェクトの関係者を始め、より多くの人々に、本評価報告が読まれ、プロジェクトの今後の展開に少しでもフィードバックされることを願っている。
2.フィリピン家族計画・母子保健プロジェクト
1992年に開始された本プロジェクトは、フェーズIにおいてはタルラック州をパイロットエリアとして行われてきたが、97年からのフェーズIIでは第三行政区が管轄するタルラック州を含む計6州に拡大され、活動が展開されている。
ここでは、フェーズI、IIを踏まえ、本プロジェクトが家族計画・母子保健を中心とした地域医療活動自体とその受益集団としての地域住民に、どのような影響を与えたのか、また、どのような成果が得られたのかについて見ていきたい。特に、現段階で行われている、「人造り」・「住民参加」を基本理念とした、助産婦活動改善プログラム(セミナー支援)、母子健康手帳導入プログラム、協同薬局支援プログラム、視聴覚教材開発・普及プログラム(IEC活動)の4つの活動を中心に、評価と改善点の提示を行なうこととする。
(1)助産婦活動改善プログラム(セミナー支援)
セミナーはプロジェクト開始当初から、地域の保健医療従事者を対象に、知識の普及・定着を目的として年に数回開催されてきた。セミナー参加体験者への聞き取り調査では、セミナーが彼女たちの活動にとって有益であったこと、また、今後もセミナーが開催されれば参加の希望があること、など肯定的な意見が多く聞かれた。
セミナーの中でも特に言及されていたのは「インターパーソナル・コミュニケーションスキル」セミナーで、これは、日頃、患者とのコミュニケーションに苦慮している地域の医療従事者からの要望に応えて計画されたセミナーであった。患者にどのように問いかければ、症状を的確に把握出来るか、あるいは、患者の相談ごとに真摯に対応する姿勢など、具体的な手法が示されたのは効果的であったと思われる。医療現場のニーズを積極的にとり上げ、プログラムへ迅速に反映させたことが関係者の間で高く評価されていた点である。
しかし、セミナーはすべての医療従事者に提供されていたわけではなく、あくまでも選択された人々のみが参加できる仕組みであった。したがって今後は、これまでに参加経験のない男性を含めた非参加者に対しても広く、均等な機会を提供できるよう、より活発な広報活動が望まれる。また、本プロジェクトの現地専門家からは、セミナー参加者に対して、知識の浸透についての追跡調査を実施する予定があると聞いたが、その結果次第では、さらに、技術移転を徹底させるためにもフォローアップセミナーの開催が有効と思われる。
(2)母子健康手帳導入プログラム
フェーズ1において、2つの地域を対象として作成された母子健康手帳に関しては、 (1) 制作費が高い、(2)「歯」に関するページが少ない、(3)記入がしにくい、などの反省点にもとづき、フェーズIIにおいては低価格の改訂版を作成し、その利用の促進が図られる予定である。これまで、フィリピンにおいては産前・産後と系統だったカルテがなかったため、母子健康手帳が果たす役割に期待が寄せられている。さらには、妊婦や母親が家に手帳を持ち帰って夫に見せることで、男性の育児への関心を高め、積極的な参加を促すきっかけとなるであろう。
しかし、製作費に関して、関係者からは、今後、フィリピン側のみで負担することへの懸念が表明され、その持続可能性に不安があるとのコメントを得た。母子健康手帳は無料配布されるのが一般的であるので、フィリピンにおいてもそれが実行されるのが望ましいが、財源確保が今後の課題である。地方自治体の医療分野への確実な予算配分を促すためのJICA側からの何らかの働きかけが必要であると同時に、所得創出プロジェクトとの連携を図り、受益者負担を可能な限り抑えるための新たな戦略が必要である。
(3)協同薬局支援プログラム
協同薬局支援プログラムとは、SMBK(Samahang Manggagawa ng Binhing Kalusugan・Seed of Health)という現地NGOとの連携により始まった、住民自身の出資・運営による協同薬局(Botika Binhiと呼ばれる)への支援プログラムである。住民による組織造り、独自の資金調達手段の確保、および、基礎的な保険機能の考え方の促進という試み自体は、十分に評価に値するものであり、その将来の展望も期待できる。しかし、現時点で状況を観察する限り、同じ趣旨のもとに開始された事業であっても、地域住民の受け入れ方、会員数や運営状況には地域によって大きな差が見られる。したがって今後は地域、または各薬局ごとの実態の把握が不可欠であるとともに、それぞれの問題に応じた、住民や薬局運営者へのフォローアップ態勢を整える必要があろう(詳しくは3を参照)。
(4)視聴覚教材開発・普及プログラム(Information, Education and Communication活動)
タルラック州の社会・文化に合った健康教育用教材を作成したいという州保健局側からの要望に応えて、同プログラムでは保健教育従事者向けの情報伝達機器の操作指導、ポスター・カレンダー・家族計画/母子保健ミニライブラリーの作成が行われ、また教育ビデオの制作と上映会が開催されている。さらに1997年からは、助産婦やヘルス・ボランティア(バランガイ・ヘルスワーカーと呼ばれる)による人形劇が実施されている。
夜間、ビデオを搭載した車両が各村を巡回して、「お母さんテレビ(TV99)」と名づけられたビデオ教材シリーズを上映している。評価チームが見学した上映会では、この地域で最近流行している「デング熱」と「衛生環境」についてのビデオが娯楽映画の合間に上映されていた。集まった約120人前後の住民(半数が子供、大人のうち約60~70%が女性、残り30~40%が男性)は、画面に食い入るようにしてビデオを見ていが、参加者へのインタビューでは、「面白い」・「役にたつ」などの意見が多く、関心の高さが見て取れた。こうした催しはテレビがあまり普及していない地域では、IEC活動の普及に大きな成果を挙げるであろう。また、男性の観客に対して、上映会で見たいビデオを聞いたところ、「家庭菜園の作り方」「農業に関連したもの」「子育てについて」「ドラックについて」「安全管理・治安」「薬草について」などの回答があった。上映本数の中にこうした要望を加えることが、一層多くの男性を上映会に動員し、ひいては保健医療分野への興味を促すインセンティヴになるであろう。IEC活動は、住民への直接的な働きかけであるとともに、住民のニーズにも配慮した有益な活動であることが窺えた。また本プログラムは単にサービスの提供だけではなく、住民への知識の浸透に関する事後調査が行われていたことは評価に値する。関係者の熱意や努力がプログラムの遂行に大きく反映された好例と言えよう。
(5)プロジェクト全体について
以上、見てきたように、本プロジェクトは概ね効果的に機能していると言える。現地専門家によると、統計上も、タルラック州での乳児死亡数は、プロジェクト開始時の1992年が15.26/1,000人であったものが、97年には9.66/1,000人まで減少しており、さらに、95年の人口増加率においても、国家全体の平均値の2.2%に対し、タルラック州では1.8%と全国水準に比べ低い数値を得ていることが示されている。こうした統計的数値と、プロジェクト実施との関連を直接結び付けるのは短絡的かもしれないが、ある程度の関連性は指摘できよう。また、母子保健・家族計画プロジェクトの性質上、成果は必ずしも短期間に、かつ、数字のみで計れるものではないため、長期的に観察することが必要であるし、さらに、広範な波及効果をも観測することが肝要であろう。
最後に、各プログラムに共通する今後の課題として、これまでプログラムにアクセスしていなかった人々の動員を目指した広報活動の強化や、地元の女性グループや村人のネットワークを利用した、プロジェクトの普及活動が望まれる。
3.村落調査を通して見たプロジェクト
本章は、村落調査を通して観察された村人たち生活の実態と、聞き取り調査による住民の生の声から、プロジェクトを見直し、改善策を提案するのが目的である。対象村は、人口1,250人のカリパヤン村である。
カリパヤン村は、タルラック州のほぼ中心にある州保健局から15キロメートルほど離れた、田園風景の美しいのどかな農村である。生活基盤の整備の点では、タルラック州の中でも遅れをとっている地域で、調査時点では電気と水道の設備は敷設されていなかった。同村の世帯数は、265であるが、村人の多くは親族関係で結びついている。カリパヤン村は、フィリピンの他の地方農村と同様に、薬や医療へのアクセスが貧しく、診療を受けるためには5ペソ(≒15円)を支払い、人々の足代わりであるトライセクル(三輪タクシー)に乗って、町の医療施設(Rural Health Unit)へ出向かなくてはならない。
村人の「医療」に対する見解は概ね、次の2点に集約できることが聞き取り調査で判明した。
- 病院に行っても、薬がない。大抵は処方箋をもらって町の薬局で買うが、値段が高すぎて買えない場合もある。
- 町の私立病院の医者の中には、金儲けのことばかり考える者が多くて尊敬できない。フィリピンには医者の数がそもそも少ない。
すなわち、カリパヤン村では、たとえ多少の経済的余裕があったとしても、近辺に利用できる医療設備が不足しているし、また、村人の大半は家計の中に占める医療関連の出費を負担に思っている状況があることが分る。こうした地域では、前述の「協同薬局」が極めて効果的であろう。筆者のホストマザーは、同村に複数存在する協同薬局の責任者であったが、彼女の自宅に設けられている協同薬局には、1日に5~6人の村人が薬を買いに訪れていた。ホストマザーと筆者の2人で村の中を歩いている際にも、「~の薬はないですか?」と家の中から大声で尋ねられたことがあり、協同薬局の情報は村の隅々にまで普及していることが窺えた。こうした状況から、95年に開始され、徐々に整備されてきた村の協同薬局は、今や村人にとって必要不可欠な存在にまでなっていると言える。
しかしながら、協同薬局の責任者や同村村長の話から、あるいは、ある薬局の事例を通して、薬局管理者の中には薬に関する知識が必ずしも十分ではない場合があるとの問題点が確認された。扱う薬は十数種類であったが、「どういった症状の場合には、あの薬よりもこの薬の方が良い」というレヴェルの知識が不十分だと言える。また、「この薬は何に使うのか?」という質問に対して、適確に返答できない場合が希に見られた。今後の改善策として考えられるのは、症状と薬の対照ボードを作成して知識の普及をはかることが考えられる。また、対照ボードが既に作成されているのなら、必要とされている地域に早急に、満遍なく配布すべきであろう。
次に、こうした人々に対する、セミナー参加の促進と再教育について考えてみたい。この件に関する問題は、現状では、セミナーに出席するための交通費を薬局管理者自身が負担しなければならないということである。つまり、あまり「繁盛」していない薬局の経営状態では、交通費が出せないのである。村長の話に依ると、こうした状況が生み出された背景の一つには、協同薬局の乱立による「客の奪い合い」があって、採算の取れない協同薬局が出現してしまうそうである。したがって、協同薬局の開設に当っては利用者数の予測と、配置を十分考慮しなければならないであろう。村の協同薬局が小さいながらも、採算のとれる経営を行えるようになれば、薬局管理者の交通費負担の問題も、運営費として計上することで解決されるのではないだろうか。また、セミナーでの再教育が必要と思われる薬局管理者への参加要請もしやすくなるであろう。
また、ある薬局経営者の苦情の中には、薬の入手方法が煩雑で問題が多い、扱える薬の種類が少なすぎるというものもあった。必要な薬は同プログラムを支援するNGOから仕入れるのであるが、薬局経営者によると、注文とは異なる種類の薬が届いたり、供給が遅れて何度も足を運んで取りに行かなくてはならない場合も多々あったという。ここでも、遠隔地での薬局経営をめぐるコミュニケーション不足が気にかかる。
一方、薬の調達に関しては、薬草利用を主とする民間医療を再認識する必要もあるだろう。カリパヤン村での調査中、腕を骨折した小学生の男の子がヒロット(Hilot:伝統的産婆)であるお婆さんから治療を受けていた。お婆さんは、ココナッツオイルを用いて男の子の骨折部一面をマッサージして関節を伸ばし、火で熱したタグンバオ(Tagumbao)の葉を患部に5~6枚あてて布で縛り、簀巻きで巻いていた。治療は20~25分程度で終わったが、男の子は次の日も同じ治療を受けており、痛みはだいぶ減少していたようであった。
村人の話によると、そのお婆さんは、以前は赤ん坊を取りあげたり、様々な治療を行なっていたというが、現在は感染症を恐れて出血を伴わない症状のみを扱うという。お婆さんの住む家では、多くの種類の薬草が栽培されており、村には薬草に関する知識が存在し、また、薬草を用いた治療が現在でも実践されている。
村のヘルス・ボランティアは、すでに薬草の栽培と利用を村人に奨励しており、カリパヤン村で収集された資料にも、55%の世帯で薬草畑が作られていると記されている。協同薬局の充実と並行して、民間医療としての薬草の重要性を再認識することが必要であろう。
4.ジェンダーの視点から見たプロジェクト
ここでは、ジェンダー(社会的・文化的性差)の視点から、受益者であるべき人々の生活や社会のあり方を通して、プロジェクトを見ていきたい。
フィリピンでは、母子保健や家族計画の分野は、女性の領域だという考え方が浸透している。調査時に行われていた子供対象の「麻疹予防接種キャンペーン」では、付添人の99%が母親や女性親族であったし、医療施設で働く人々(助産婦や看護婦)やヘルス・ボランティアもほとんどが女性であった。避妊も女性たちが考えるべきことであると看做されているふしがある。
そうした現状を見ると、「家族計画・母子保健プロジェクト」が女性を中心に考えられて立案されるのは無理もないであろう。実際に本プロジェクトでは、直接的に男性に焦点を当てて組まれたプログラムはない。しかし、現地専門家やカウンターパートが既に気付いているように、男性に働きかけることは、本プロジェクトの目的にも叶った、大切な作業なのである。
それでは、男性が母子保健や医療・家族計画に対して、より意識を高めるように働きかけるにはどうしたらよいだろうか。
まず第一に、男性が自らの健康を管理するという意識を持つように奨励することであろう。女性ばかりが集まっている医療施設に、男性が入りにくいと思うのは当然であろう。とくに、家族計画に関して、男性が医療の現場に気軽に足を運べるようにするには、環境を整える必要があろう。男性の持つ衛生観や、病気への取り組みなどを調査するとともに、男性が家族計画・母子保健という考え方に馴染めるような、また、実践の現場に直接的に接触できるような戦略をたてることが大切である。
また、男性のヘルス・ボランティアを募集するのも一つの方法ではないだろうか。この提案に関して助産婦たちに打診したところ、「自分たちの仕事がやりにくくなる」・「男性のヘルス・ボランティアは仕事をしないのではないか」など、憂慮する声も聞かれた。確かに現状からすれば、コミュニケーションや仕事に対する認識の違い等、様々なやりにくい面も出てくるであろう。しかし、それらを克服してでも、ヘルス・ボランティアに男性を積極的に起用することは有意義であると思う。例えば、医療をめぐる話題に関して、男性が男性に伝えることのほうが、異性同士よりも容易な場合が多々ある。避妊や生殖に関する悩みや相談、プライバシーに関わる会話などに関しては、特にそうであろう。さらに、現地専門家も述べていたように、フェーズ・で開始した「人形劇」を各地で開催するには、男性の助けが必要となってくる。また、保健教育のためのビデオ上映会が行われる際には、より多くの男性の参加を呼びかけるために、男性のヘルス・ボランティアの個人的ネットワークを用いることもできる。家族計画・母子保健は、男女がともに考えるべきことであり、女性偏重である本プロジェクトのあり方も、可能なところから随時変更していく必要があると思われる。
一方さきほど触れたように、パイロット地域で用いられている近代的避妊方法の対象はほとんどが女性であった。『フィリピン人口調査93年』の統計によると、パイロット地域を含む中部ルソン地域では、30.9%が近代的避妊方法を利用しており、その半分以上が女性の不妊手術(19.1%)、次に多いのが経口避妊薬(9.4%)である。近代的避妊方法の中でも、男性側の意志によって実践されるのは、男性の不妊手術とコンドームの使用であるが、前者の利用率は皆無であり、後者は1.3%と若干はあるものの、全体から見ればほんの僅かな割合である。
女性ばかりが避妊を行っていることに対して、カリパヤン村では特に目立った苦情は聞かれなかった。しかし、不妊手術を行った複数の女性によると、雨が降る寒い日や、重労働を行った日には腹痛がひどくなる人も少なくないという。一方、徐々に利用者を増やしているのが女性に打つホルモン注射である。ホルモン注射は、一度接種すると3ヶ月間の避妊の有効期間があるために扱いが簡易であるが、同方法が広く普及しているケニアの例を見ると、不妊症や流血、高血圧などの副作用が報告されている。
本プロジェクトは、母子保健・家族計画の啓発活動や人づくりの分野に重点をおいているため、現時点では、避妊薬の投与による副作用に関する問題は直接、取り上げる必要はないのかもしれない。しかし、今後起こりうる問題として、上記の点も決して看過されるべきではなく、避妊方法に関する男性の役割分担や、副作用の恐ろしさなどの情報の伝達、あるいは、他機関が与える避妊薬の安全性へのチェック等、本プロジェクトの関連事項として配慮すべき課題であろう。
以上、プロジェクトの対象者である人々の日常生活や、ジェンダーの視点から本プロジェクトについて見てきた。調査村での観察に依ると、村の男性たちは、仕事から戻ると赤ん坊をあやしたり、子供の遊び相手になるなど決して子供に無関心であるわけではないし、また、男性の家庭内労働への協力も相対的に高いと言われている。母子保健・家族計画プロジェクトは、ともすると、女性のみをターゲット・グループにしがちであるが、フィリピン社会の基層文化には元来、ジェンダー・フリーな発想が認められるので、本プロジェクトへの男性の参画を促すことも方法次第では、可能なのではないだろうか。
5.他援助機関・国内政治情勢との関わり
フィリピンでは、家族計画に関係する予算のほとんどを国外からの支援に依存しており、実際、多くの外国援助機関、国際機関による家族計画/母子保健プロジェクトが遂行されている。本プロジェクトもUSAID(米国援助庁)へのIEC教材の提供、JHPIEGO(ジョ-ンズ・ホプキンス大学リプロダクティブ・ヘルス教育国際プログラム)からの母子保健手帳への協力など、他の援助機関との相互協力態勢がとられている。前述の、SMBKとの連係に依る協同薬局支援や、JOICFP(家族計画国際協力財団)で開発されたマグネキットやエプロン教材の利用など、NGOとの連携も進んできている。
今回の調査では, UNICEF(ユニセフ)、USAID、UNFPA(国連人口基金)、 ADB(アジア開発銀行)、JOICFP、フィリピン大学・人口研究所、アテネオ・ド・マニラ大学・社会学部などの関係者へのインタビューを実施したところ、これらの機関が本プロジェクトを高く評価しているとの回答を得た。セミナー開催、母子保健手帳の普及、地域住民への啓発活動を通じて人造りに重点がおかれている点が高い評価の由縁であった。ただし、一部には日本のODAはもっぱら機材供与のみという誤解や他の援助機関との連携強化に向けた日本側の情報提供が必ずしも十分ではないとの指摘があったため、今後はこれらの点に関するより積極的な働きかけが重要であろう。
一方、今回の調査においていたるところで聞かれたのが、1991年地方自治法の施行とその後の権限委譲よる現場での混乱であった。権限委譲により、これまで国からの一括した政策下で管理されていた予算の配分、薬の配給システムなどが、州立病院以下の医療現場においては州政府や町役場の意向によって決定されることになったため、医療現場における薬の絶対的な不足、施設管理のための予算不足、また地方自治体の保健医療分野への低い予算配分、それに伴う活動資金不足など、さまざまな問題が発生している。
医療現場での混乱は、上述の個別プロジェクトとは一見直接的な関係はないように思えるが、当プロジェクトの目的である「地域の保健医療体制の充実」にとっては、明らかに負の要因であり、問題解決に向けた何らかの働きかけが必要である。
対応策の一つとして、地方自治体の行政官を対象に、保健医療分野の重要性を認識してもらうためのセミナーの開催が考えられる。現状では、地方自治体の予算は、多くの場合において首長の人気獲得のため、インフラなどの目に見える、効果の明らかな事業につぎ込まれてしまう場合が多い。したがって、セミナーを開催し、保健医療事業の重要性を訴えると同時に、当分野への投資が将来的な地域の発展にも寄与するものであること、住民のニーズに基づいて保険医療分野の充実を図ることは、インフラ整備を行うことと同様に人気獲得の手段になりうること等、認識を高めるための働きかけを行うことは、状況改善に向けての重要な第一歩になりうると考える。
6.おわりに
さて、今後のプロジェクトの自立発展性について考えてみたい。カウンターパートの何人かは、(1)将来的にはモニタリングや評価に関しても独自で行なえるようにしていきたい、(2)地域レヴェルにも技術的サポートを与え、地域でやりくりが出来るようにしていきたい、との希望を述べている。
現段階においては、カウンターパート側から具体案は未だ提示されてはいないが、本プロジェクトの地域的拡大を主眼にしたフェーズIIが終了した後、プロジェクトの持続性を達成するには、やはりフェーズIIIへの継続の可能性が求められよう。フィリピン国内の、今後の政治情勢や経済状況を好意的に予測したとしても、フェーズIIIの展開は日本側の協力なしには難しいと言わざるを得ない。また、フェーズIで達成された成果が地域的拡大の中で行われようとしているフェーズIIでそのまま、同じように得られるか疑問の残る点である。しかし、こうした懸念があるとしても、フィリピンにおける地域社会の発展への協力を推進する方針に変更が生じないのならば、プロジェクトは継続して行われるべきであろうし、自立への支援が不可欠であろう。その際、プロジェクト継続の是非の判断基準は、やはり、住民のニーズに沿ったプログラムが組まれているかという点である。
次に「フィリピン班」の創設について言及したい。現在、JICA内では創設へ向けての検討が始められていると聞いたが、是非ともその実現を期待したい。本案件のような、対象地域の人々の生き方に直接関係するプロジェクトは、人々の価値観やセクシュアリティーに深く関わる、微妙な問題を含んでいるので、こうした分野での支援態勢は、地域住民の保健医療に対する考え方だけではなく、フィリピン社会に見られる普遍的な価値観や行動様式を視野に入れた包括的な予備調査と、その結果導き出された方針に沿って、プロジェクトが遂行されることが望ましい。人類学や人文地理学、地域研究など、様々な分野でフィリピン研究を行っている専門家たちが、事前調査から協議・実施、さらに、評価に至るまで一貫して関与できることが、プロジェクトの地域社会に与えるインパクトを通時的に観察したり、プロジェクトの改善を常に提案できるという点で効果的であるからである。
さて、全体を総括すると、1992年から開始された本プロジェクトは、パイロット地域における保健医療環境を少しでも向上させようという現地専門家たちの熱意と、それに応えた現地のカウンターパート、および地域住民たちの努力に拠って、当初の目標を概ね達成できた案件として高く評価できる。機材供与などのハード面での支援よりも、関係者の尽力に依存したソフト面での協力が優位な案件であるとの印象を強くした。前述した若干の問題点についても、関係者間の緊密な情報交換によって改善され、本プロジェクトが今後も順調に展開していくことが望まれる。
最後に、評価案件の選択に関しての提案をしたい。今回、評価チームが評価を依頼された母子保健・家族計画プロジェクトは、現在、フィリピンで展開されているプロジェクトの中でも「最優良案件」と報告されているプロジェクトであった。ODA大綱の中ですでに位置づけられているように、「援助の効果的・効率的実施」の手段が「評価の充実」だとするのならば、「成功」を収めている案件だけではなく、むしろ、より改善策を見出すべき案件にも目を向けることが必要なのではないだろうか。

