2.モンゴル
| ■廣野 良吉 | 成蹊大学名誉教授(団長)) | 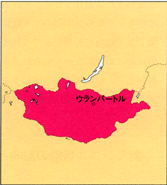 |
| ■吉田 恒昭 | 東京大学工学部教授 | |
| ■栗林 純夫 | 東京国際大学経済学部教授 | |
| ■石井 幸造 | 財団法人国際開発センター研究員 | |
| ■二階堂幸弘 | 外務省経済協力局評価室長 | |
| ■佐川 昌也 | 外務省経済協力局評価室事務官 |
1.モンゴル社会経済概況
モンゴル社会経済の課題
- 回復傾向にあるモンゴル経済であるが、カシミヤや金・銅など一次産品に依存した産業構造は国際市場価格の動向に大きく左右されるなど、経済基盤は脆弱なままである。最近ではアジア経済危機の影響によるアジア市場でのモンゴル主要産品の需要減少、あるいはそれに伴う世界市場での一次産品の価格低下により政府財源の大部分を占める主要輸出企業からの税収が減少するなど、経済への悪影響も生じ始めている。
- 銅輸出額の減少に伴う税収減に加え、公務員の給与支払を増額したことから、1998年のモンゴルの財政赤字は97年の681億トゥグルクから975億トゥグルクへと増加し、対GDP比11.6%に達している。99年度暫定予算では、状況はさらに悪化し、歳入2,274億トゥグルクに対し歳出は3,389億トゥグルクで1,114億トゥグルクの赤字が見込まれており、援助依存体質に改善は見られない。モンゴル政府は税制の更なる整備、歳入源の多様化を図るとともに、歳出削減努力を講じる必要がある。
- 個別産業分野においても依然として多くの課題を抱えている。農業部門においては、国内食肉価格の低下と国際市場におけるカシミア価格の低迷により、家畜数の増加とカシミア製品の増産効果が低減されている。また、農牧草地の私的所有権の問題も未解決のままである。工業部門は1997年は前年比約2.3%の成長を達成したものの、銅生産、金採掘など鉱物生産への依存度が依然として高く、他の製造業部門の多くは低迷している。また、金融部門は未だ未整備であり、モンゴルにおける経済成長の足枷となっている。金融セクターにおけるさらなる改革、強化、キャパシティー・ビルディングが必要であり、特にモンゴル中央銀行の機能強化はモンゴル経済の発展に向け不可欠である。
- 多くの問題を抱えるモンゴル経済の課題は、経済成長というよりも、むしろ経済後退の歯止めと社会混乱の解消であると言える。そのためには、1997年7月にIMFと合意した拡大構造調整融資(ESAF: Enhanced Structural Adjustment Facility)プログラムに基づき同年11月13日の国家大会議で決議された98年の社会・経済発展の基本指針の達成に向け、国民への負担を最小限に抑えつつ、可能なかぎり努力する必要がある。
- 市場経済化への移行に伴い社会面でも大きな問題が生じている。特に失業者の増加とそれに伴う貧困層の拡大が大きな問題となっている。120万人の労働者人口のうち20万~30万人(17~25%)が失業者であると推測されており、さらに世界銀行の推定によると貧困ライン以下の人口が全人口の36%を占めるとされている。これら貧困層のうち最貧困層の3分の2は地方の小都市に在住していると推測されている。
- モンゴル政府は21世紀までの初めに貧困家庭数を現在の半数にまで減少させることを目指しているが、その達成には年間5~6%の経済成長率を達成・維持し、さらに失業者あるいは年間10万人と予想される新規就業者の雇用吸収源を確保する必要がある。特に地方における貧困撲滅に向けては、経済成長のみならず、人材育成、専門技術付与、収入源の多様化も必要となる。
2.対モンゴル援助の動向と我が国援助の位置づけ
モンゴル政府の開発政策・援助ニーズと我が国援助の整合性
(1)経済改革プログラムの実施直後(1991~92年)
日本政府は1991年に6,100万ドルの対モンゴル支援を約束するとともに、市民生活の安定化、インフラ支援、輸出振興・輸入代替のための投資支援・人材育成に重点を置き援助を実施することを公表している。この期間における日本の主な援助としては、
1)商品借款
2)食糧援助、食糧増産援助
3)経済インフラ(生産基盤関連のインフラ)の整備(通信設備整備、ウランバートル第4火力発電所改修など)
4)基礎生活支援(社会福祉計画など)
5)ノン・プロジェクト無償
などが挙げられる。モンゴルが市場経済移行を開始した直後であり深刻な経常収支危機に直面していたことから、我が国が実施した商品借款などの緊急支援型の援助はこれら危機回避に向けての適切な援助であったと言える。また、その他援助に関しても支援国会合で表明されたモンゴル側の援助ニーズと整合性を持った援助であったと判断できよう。
(2)経済転換期(1993~95年)
モンゴル経済が転換期を迎えたこともあり、この期間中に援助ニーズの重点は緊急的な経常収支危機への対応から中長期的視野を考慮に入れた開発援助へと移行し始めた。日本の援助も緊急支援型援助から、プロジェクト型援助が増加し始めている。この期間の日本の主な援助として、
1)経済インフラ整備(鉄道輸送力整備計画、ロックアスファルト舗装道路計画、公共輸送力改善計画など)
2)食糧援助、農牧畜業振興(食肉加工施設整備計画、乳製品加工施設整備計画、穀物貯蔵庫建設計画など)
3)基礎生活支援(基礎的医療機材整備計画など)
4)草の根無償援助
などが挙げられ、特にインフラ関連のプロジェクト型援助、農牧業セクター加工部門の生産性向上に係る援助を中心に実施している。これら援助は第3回支援国会合で重要と認識されたインフラ整備、農牧業の復興、社会インフラ(生活基盤・生活環境施設関連のインフラ)の整備と整合するものである。また、1993~95年にかけては技術協力として専門家派遣数、並びに研修員受入数が増加している。これら協力はソフト部門に重点を置いたMDP(Management Development Programme)の戦略目標に対応するものであると言えよう。さらに、第3回支援国会合で重要と認識された鉱業の復興・回復に対応する形で、プロジェクト方式技術協力として地質鉱物資源研究所が開始されており、技術協力は大きな進展を見せた。この期間においては草の根無償援助も増加している。草の根無償援助は小額であるもののその効果は大きく、この時期に援助数が増加したことの意義は大きい。
(3)議会民主制への体制移行後(1996年以降)
この期間において、モンゴルの援助ニーズはこれまでの経済インフラ重視の姿勢から、経済・金融・財政運営に係る知的支援・人材育成などソフト型支援、あるいは中小企業・輸出志向型企業育成を含む産業育成へとその重点が移行している。日本の援助も「家畜感染症診断技術改善計画」、「母と子の健康」といった2つのプロジェクト方式技術協力を開始するなどソフト・インフラ面への支援を拡大し、援助は多様化している。1996年以降のその他の日本の対モンゴル援助としては、
1)経済インフラ整備(炭鉱総合開発計画、ロックアスファルト舗装道路計画、村落発電施設改修計画など)
2)基礎生活支援(給水施設改修計画など)
3)ノン・プロジェクト無償
4)食糧援助・食糧増産援助
5)草の根無償援助
などが実施されている。また、ソフト型支援に向けての専門家の派遣数も急増している。特筆すべきことは、同期間において一般プロジェクト無償「村落発電施設改修計画」や草の根無償援助によりディーゼル発電機供与を地方において展開したことであり、これら援助はMAP 21の目標である「地方組織の能力強化」、あるいは「地方レベルにおける事業実施効率の改善」に合致するものである。また、ソフト型支援に援助の重点は移っているとはいえ、経済インフラの整備はモンゴルの産業育成あるいはエネルギーの自給に不可欠であり、炭鉱総合開発、舗装道路計画などの援助はいずれもモンゴルの開発政策、あるいは援助ニーズに合致するものである。
対モンゴル援助の国際的動向
- 援助国会議として、「モンゴル支援国会合(Mongolia Assistance Group Meeting」があり、1997年7月に開催された第6回会合では、モンゴル政府から「経済改革とセクター戦略1998~2000年(Economic Reform and Sector Strategies 98-2000」が提出され、モンゴル政府の経済改革に係る3つの中期重点課題;(イ)マクロ経済の安定、(ロ)構造改革と民間セクターの活性化、(ハ)公的部門管理改革(税制改革、財政支出管理と行政改革、社会サービス提供に係る改革、国営企業改革、社会保障水準の維持)、が示されるとともに、セクター別(経済インフラ、産業/サービスセクター、農業/天然資源、社会セクター、環境)重点課題が提示された。
- モンゴルへのODA総額は年々増加傾向にあり、1997年には前年より約4,500万ドル増加し、248.2百万ドル(二国間援助が118.1百万ドル、国際機関による援助が128.6百万ドル)に達している。援助主体別では、DAC諸国の中では日本がトップで、次いでドイツ、アメリカ、デンマーク、オランダの順で続く。国際機関では、ADB、IDA、IMF、UNDPの順で援助額が大きく、過去において援助額の多かったIMFからの援助は減少傾向にある。
- 援助分野別でみると、モンゴル経済が安定期に入ったことを受け、現在では当初の人道的緊急援助から中長期的な経済開発計画を基本としたものへと移行しつつあり、モンゴル国内経済の構造改革、社会セクターの問題点の克服、人的資源の活用の3点にその焦点があてられている。
- ドイツの援助は、資金協力に関してはインフラ開発や中小企業育成、技術協力では自然保護、農業振興、国有企業民営化支援、各部門における人材育成などを優先分野として援助の約50%ずつをハード・インフラとソフト・インフラに振り分け実施している。ドイツはTACIS(Technical Assistance for CIS)プログラムによる構造・制度改革、企業育成・金融開発、インフラ開発を中心とした対モンゴル援助にも協力しており、今後は二国間援助の割合を徐々に下げ、マルチとしての援助に重点を移していく傾向にある。
- 米国は、USAID(米国援助庁)がモンゴルの民主化強化、民間セクター育成を援助戦略に置き、主にエネルギー部門、銀行改革を中心に援助を実施している。しかし、冷戦の終結、財政事情もあり米国の対モンゴル援助姿勢は消極化しつつある。
- 1997年の援助額が4位であるデンマークは教育部門を中心にソフト・インフラの充実を優先的に進めている。また、80年代には対モンゴル援助の最大供与国であったロシアは、その援助規模は大幅に縮小しているものの、91、92年の2年間に総額8,800万ドルのローン貸与を実施しており、主に発電所施設の改善、機関車車輌の購入に使用されている。
- 国際機関ではアジア開発銀行(ADB)が対モンゴル援助最大のドナー機関であり、近年では特に金融セクター支援を中心としたの経済管理分野、エネルギー部門、教育セクター開発等の人材育成に重点を置き援助を実施している。また、世界銀行グループからの支援としてはIDAが最貧国を対象とした無利子の借款を実施しており、1998年5月末までの累計で10のプロジェクトに対し164百万ドルのローンがコミットされている。当初の国際収支支援型援助や経済マネジメントに係る技術協力から、近年では、貧困緩和、インフラ整備、構造改革(特に金融・産業部門)へとその重点は移行している。IMFは拡大構造調整融資(ESAF)として93~96年に6,500万ドルの融資を行い、さらに97~99年の間に4,800万ドルの支援実施を承認している。また、UNDPは、貧困緩和・人的資源開発、ガバナンス(市場経済移行支援)、環境・資源管理、の3つに重点を置き援助を実施している。UNDPはモンゴル国内における国連関連機関の活動統括、並びに各ドナー間の調整業務を行っており、モンゴル援助においては重要な役割を担っている。
我が国の対モンゴル援助動向
- 我が国は、1)モンゴルが民主化ならびに市場経済化への移行を進めていること、2)モンゴルの政局安定・経済発展が周辺地域の政治・経済安定に重要であること、3)市場経済移行期であることに加え、経済基盤の未整備、貧困層の拡大などの問題をかかえ援助ニーズが大きいこと、などを踏まえ、1991年以降対モンゴル援助が本格化している。以来二国間・国際機関を通じ最大の援助供与国となっている。
- 無償資金協力では、発電所・通信/運輸関連のインフラ部門、農牧畜業分野(食肉加工施設/乳製品加工施設整備、穀物貯蔵庫建設)への援助、並びに食糧援助、食糧増産援助、ノン・プロジェクト無償などを実施している。97年度には、アスファルト舗装道路建設の他、ウランバートル市における給水施設改修や村落発電施設改修が実施された。また、草の根無償も供与されており、最近では地方における発電機供与や医療協力、小中学校の電化を中心とした援助を実施している。
- 技術協力では市場経済移行に向けての人材育成・制度強化を支援しており、1997年度までに619名の研修員受入、235人の専門家を派遣している。また、94年にプロジェクト方式技術協力として「地質鉱物資源研究所」が実施されたのに続き、97年には「家畜感染症診断技術改善計画」、「母と子の健康」が開始されている。さらに開発調査として97年度には「市場経済化支援事前調査」など8件が実施されている。
- 有償資金協力では、1991、92年に総額72.95億円の商品借款を実施した後、93年、94年には鉄道輸送力整備計画、95年にはウランバートル第4火力発電所改修、96、97年には炭鉱開発計画に対し借款を行っている。
- 1997年3月に派遣された経済協力総合調査団とモンゴル側の協議を踏まえ、(イ)産業振興のための経済基盤及び条件整備(エネルギー、運輸、通信等のインフラの本格的リハビリ)、(ロ)市場経済移行のための知的支援、人材育成(経済政策、法制度・行財政改革)、(ハ)農業・牧畜業振興(長期的農業計画の策定、協同組合の運営体制・農畜産物流通体制の整備、農業技術の開発・普及等)、(ニ)基礎生活支援(教育、保健・医療、水供給)、の4つを我が国の対モンゴル援助重点分野としており、従来のハード・インフラ中心の援助からソフト・インフラも含めた幅広い援助を行っていく方向にある。
3.モンゴルの援助吸収能力
援助受入体制に係る課題
- 対外関係省内の貿易・経済協力局が援助供与側との折衝窓口、並びにモンゴル側省庁間の調整機関として一応の責務を持つに至っているが、多額・多様な援助案件を扱うには専任職員の数が限られており、今後は体制強化を図る必要がある。資金援助とモンゴルの国家開発計画や財政との関係を考慮すると貿易・経済協力局と大蔵省内の関連部署を統合した形の新しい窓口機関を設置することが望まれる。
- モンゴル側のODA実施までのシステムが問題視されることが多いことを受け、モンゴル側はODA実施メカニズム改革に向けた委員会を1998年5月に設置している。さらに99年2月にはODAの管理と規制の強化に向けワーキンググループを設置しており、これらモンゴル側のODA受入・実施能力の向上に向けての努力は評価に値するとともに、今後の動向が注目される。
援助吸収能力に係る課題
- モンゴルにおける援助吸収に関しては、援助実施に係る組織・人的能力の不足、援助に関する制度の未整備、援助計画管理・資金管理能力の不足、援助プロジェクトの運営・維持管理費の不足(特に地方レベルにおいて)、ローカルコスト(内貨)負担能力の不足、省庁間の調整不足、援助資金の流れに係る透明性の不足、など様々な問題が存在する。
- モンゴル側の人的資源・能力の不足が援助を受け入れるにあたっての最大の問題となっている。これら人的資源・能力の不足は、それに伴う援助計画管理・資金管理能力の不足と相俟って、各種援助プロジェクトの初期段階における実施の遅れ、あるいは契約済み援助プロジェクトの実施不履行につながるケースが多い。
- 援助実施に際しての制度の未整備も問題であり、分野別のプロジェクトにおいては各省庁間で競合することが多い。また、モンゴル側責任部門とドナー側との意志疎通の不足からプロジェクト実施段階において双方のプロジェクトに対する理解の相違が出てくるケースもある。
- モンゴル政府はこれまで援助プロジェクトの計画、実施、管理・運営に係る国内の人材育成に力を入れなかった。援助の拡大に伴い、この問題はますます顕在化してくるものと思われる。援助プロジェクトを順調に消化していくためにも、援助受入を手際よく遂行できる公共部門の人材を確保/育成することが急務であり、研修システムの充実と、援助国からモンゴル援助関連組織への専門家の派遣による知識・経験・技術の供与が望まれる。
- モンゴル政府は各ドナーの援助形態・方策に対する理解を深めるとともに、援助プロジェクトの創出・計画・実施・モニタリング・評価に係る独自能力の向上を図る必要がある。加えて省庁間の援助調整機能をさらに強化していく必要もあろう。
- また、直接的な収益創出機能を持たない援助案件の急増は、モンゴルの脆弱な国家予算を圧迫しかねない。しかし、現実にはモンゴルにおける援助資金の多くはこれまでインフラ整備に割り当てられていることから、これらインフラプロジェクト完了後に必要な運転・維持管理コストはモンゴル政府の財政に大きな負担となりかねない。よって援助プロジェクト終了後に生じるモンゴル政府の財政負担を軽減するため、ドナー側が年間ODA供与額のうち一定金額を共同管理する信託基金を設置する、あるいは食糧援助、食料増産援助、ノン・プロジェクト無償の見返り資金を活用することで終了プロジェクトの運転・維持管理コストをカバーしていくことも考慮すべきであろう。
- 現地においてはドナー側にも課題が存在する。モンゴル現地ではUNDPが中心となり月例ローカル・ドナー会合が開催されており、主要ドナー国・機関の代表が情報交換・援助調整を行っている。しかし、各ドナーの援助実施計画に関してはまだ透明性が十分ではなく、同会合の機能をさらに向上させる必要がある。
- また、援助吸収能力以外の問題として対外債務問題が存在する。公式対外債務総額は1997年末時点において605百万ドルで、モンゴルGDPの約64%を占める。この総額は国際的水準から見るとさほど高い数値ではなく、返済期間も非常に譲許的なものとなっている。問題は旧ソ連への債務であり、在モンゴルロシア大使館によるとその総額は170億ドルと言われている。モンゴル側は返済が不可能な状況にあり、99年5月に予定されている第2回目の両国の協議会の動きに注視する必要がある。
4.我が国の対モンゴル援助についての総合的評価と今後の方向性
総論
- 我が国が対モンゴル援助を本格化した1991、92年に重点的に実施した国際収支支援型の緊急援助は、モンゴル経済の危機的状況の回避に向けての緊急救済措置として大きな役割を果たしたと言える。計量的な貢献度についての正確な判断は難しいが、その後のモンゴル経済立ち直りの基盤作りに貢献した点でこれら援助は高く評価されるべきであろう。
- 対モンゴル援助を実施していくうえで認識すべき点は、市場経済への体制移行は非常に困難で時間を要するプロセスであるということである。我が国の援助はこの点を十分に踏まえ、援助を継続し、さらには増大させてきた。1994年以降はモンゴルの経済成長率はプラスに転じ、経済開発パフォーマンスも改善し始めたわけであるが、これは、我が国が緊急援助に引き続きタイムリーな形で経済・社会インフラの整備に重点を置き援助プログラムを実施してきたことと無関係ではなかろう。最大のドナー国である我が国によるこれら援助が実施されなかったならば、モンゴルの経済安定化はさらに時間を要したであろうことは容易に推測できる。
- 政策支援・人材育成支援についても、我が国は他の援助国・機関に先駆けて実施してきた。我が国の対モンゴル政策支援活動はこれまでの活動とは異なった特徴を持った形で実施され、時期的、内容的、広報的にも大きな成果を収めたと言える。今後さらに改善すべき点はあるものの、これらソフト面における支援はモンゴルの体制移行ならびに各部門における援助の効率的な実施に貢献している。
- 我が国援助に対するモンゴル側の評価も高いものであった。電気、給水、バス、道路舗装などの基本インフラ整備に対する支援は政府役人のみならず、一般の国民が実感できる形の援助であることから広く認知されていることは特筆に値する。地方における電化プロジェクトも高い評価を受けており、さらなる拡張を望む声が強い。同プロジェクトに関しては、今後、維持・管理の問題が発生することが予想されることから各地域の自助努力による解決を考慮に入れ援助を継続していく必要がある。
- 以上、市場経済化移行に向けての我が国の援助の継続が非常に重要であったことを、我が国の過去の援助は物語っている。農業プロジェクトなど一部モンゴル側の政策転換により必ずしも効果的・効率的な援助となっていない案件も存在するのは事実であるが、市場経済への移行過渡期においては、援助に関しても試行錯誤は避けられない。また、市場経済システムの導入は時間を要するプロセスでもあることから、対モンゴル支援については長期的視野を持って進めていく必要がある。
- 援助を本格化した1990年から現在に至る10年間は、我が国にとっても対モンゴル援助に関する学習期間、あるいは市場経済化支援に向けての基盤作りを行ってきた10年間であると言えよう。我が国が対モンゴル援助を継続していくことは、モンゴルの市場経済体制の充実・安定に向けての大前提であり、今後10年間はさらなるインフラ整備を行い、モンゴルの将来の発展に向け加速をつける必要がある。
- モンゴル側、ドナー側とも認識していることではあるが、これまでの経済安定化から地方の発展・開発を含めモンゴルの自立的発展を見据えた援助の更なる展開を図る必要がある。日本はすでに地方における電化プロジェクトに着手しているが、長期的にみて同プロジェクトのインパクトはかなり大きいと予想され、今後も地方における社会開発関連の優良プロジェクトの発掘や草の根無償資金協力のニーズは高いと思われる。
分野別評価
1)経済復興と社会安定化のためのインフラ整備
- 過去における我が国のインフラ部門への援助は、緊急度の高い分野に始まり、その後は援助の規模、質ともモンゴルの開発ニーズとの整合性が図られた形で実施されてきたことは評価できる。
- インフラの持続的管理・発展には技術移転→技術保守→技術の自立というフローが不可欠となるが、我が国の援助はこの点を認識したうえで技術移転と人材育成にも配慮がなされている。特に、「通信施設整備計画」においては適切な資金援助・技術協力によってインフラ施設と技術の改善・革新を行いつつ、事業経営そのものの安定化・健全化を実現させており、今後のモンゴルにおける公共インフラ分野における援助モデルとして認識されるべきであろう。
- 今後の我が国の対モンゴルインフラ部門への援助については、マクロ計画・改革との整合性のあるプロジェクトの選択と援助内容の高度化が要求されることになると思われる。具体的にはインフラサービスの向上と事業の財務的自立化の両立を目的とした総合的視点からの援助タイプの組み合わせが必要であり、技術援助、資金援助、経営改善指導は三位一体であるという認識のもとに援助を考えるべきであろう。また、技術移転を主目的とする援助に関しては、その普及可能性を基準としてプロジェクトの選択を行うべきであり、経済的効率性の評価が重要となる。
- さらに我が国の対モンゴルインフラ部門への援助は規模が大きいことから、セクター政策・計画・調整の分野と全体的インフラ投資の整合性、およびインフラ事業経営に係る財務的健全性の確保を目的とした法律・制度改革を見据える専門家を政策立案・調整レベルに対し派遣するべきであると思われる。また、援助プロジェクトの規模については、事業実施主体の財務的収益の視点から算出した価格を基に需要予測を行い、それに基づき規模を決定すべきであろう。
2)市場経済移行のための知的支援、人材育成
- 1991年に始まった我が国の対モンゴルの知的支援(政策支援)、人材育成支援であるが、他援助国・国際機関(UNDPを除く)に先駆け実施したことは高く評価できる。
- 政策支援における我が国の対モンゴル支援は、1)モンゴル側からの要請ならびに国際機関・国内外NGOとの協力にて実施されたこと、2)学問的中立性と脱イデオロギーを基礎において実施したこと、3)モンゴル国民の価値観・希望等を考慮したこと、4)モンゴル側との共同研究を行い両者間の合意を図るとともにシンポジウムの開催により関係者の意志・見解の疎通を図ったこと、5)日本国内に「モンゴル開発政策支援グループ」を設立したこと、6)日本政府との意見交換を頻繁に行い支援を確保できたこと、など、これまでとは異なった特徴を持って実施されてきている。これら特徴を持ってして、我が国の知的(政策)支援・人材育成支援はモンゴルの知的基盤の強化に大きく貢献してきた。
- しかし、欧米諸国の政策支援によくある大型の現地常駐顧問団とは異なり、我が国の場合は現地常駐の政策顧問の数は限られており、モンゴル側の多様かつ緊急の要請に対応し得なかった面は否めない。また、予算的・制度的にも制約・限界があったことから本来果たすべき成果を成しえていないことも事実であり、このことは個別専門家派遣についても当てはまる。
- 日本におけるモンゴル人の学位取得プログラムの導入が未だ充実していないことも今後の課題として挙げられよう。今後はこれら課題の解決を図るとともに、知的支援・人材育成に係る技術協力に関しても、モンゴル側の主体性・調整能力の不足の解消、援助供与国/機関間での援助調整・協力の強化、研修内容の改善、派遣個別専門家のソースの拡大、などに向けた方策を実施していく必要がある。
3)農業・牧畜業振興
- 我が国の対モンゴル農牧畜業への援助は、牧畜業が同国の基本産業であるとの観点から重視しており、我が国にとってなじみの薄い遊牧形態での家畜生産部門ではなく、加工部門と食糧増産型援助に重点を置き援助を実施してきたことは一応の合理性を持つものであったと言える。
- 緊急度の高い食糧援助から農牧業関連加工部門へと推移してきた援助の流れは、基本的にはモンゴル側ニーズに合致するものであり、また民生の安定に貢献してきたことは評価できる。しかし、各プロジェクト実施に際しては需要予測、コスト計算予測の精度不足などが十分でなかった面はある。これら課題についてはその後のフォローアップ調査に基いた対策により改善されつつある。
- 我が国の同部門に対する援助は、設備改修・機材供与が中心であったが、これら設備・機材の稼働に係る運転資金をモンゴル側が十分に確保できなかった点は、今後の援助実施に際しての教訓として留意すべきであろう。また、それら設備・機材供与の対象が限定的であったこと、あるいは設備・機材設置におけるモンゴル側との分担に関しての見通しの不足など、プロジェクト効果の将来予測も含め基本的にプロジェクト実施の事前段階での慎重さに疑問が残る点が指摘される。今後実施するプロジェクト案件については計画の策定をより慎重に行うべきであろう。
4)産業育成
- モンゴルでは多くの新興中小企業が台頭しつつあり、活発な経済活動を展開しつつある。このような背景の中、新たな産業振興に向けての支援が求められているわけであるが、我が国はこれまで緊急の重点分野として、インフラ部門、農牧業部門、保健・医療部門に重点を置き援助を展開してきたため、こうした要請に対し十分には応えていない。
- 産業振興の視点から、これまでなされたきた我が国の援助スキームは以下の項目に要約されよう。
(1)外国直接投資導入政策立案に関する知的支援、(2)機材供与がなされた事業体へのフォローアップ調査と同時に進められた経営指導、(3)JICA開発投融資による馬肉生産輸出事業への融資、(4)農牧産業省への中小企業育成のための専門家の長期派遣及びこれに関連した専門家の短期派遣
(1)、(2)では、これまで的確な政策提言がかなりの具体性をもって実施されてきたとはいえ、産業、とくに中小企業振興策としては、その具体性に乏しいという制約があった。また(3)については、モンゴルの牧畜産業の発展に大きく貢献するものと期待されるものとはいえ、未だ比較的小規模の展開に止まっている。98年になってようやく(4)が実現されたが、この中小企業育成の専門家派遣は、現地での各種セミナーの開催などを通じて高い評価を受けている。 - 今後は工場・事業所の稼働率の引き上げを目的とした中小企業支援のための新たな金融方式の構築を積極的に支援するとともに、中小企業向け融資制度構築に向けての支援も必要となる。また、税制、外資導入、新産業育成(ソフトウエア産業など)に係る専門家の派遣、研修員の受入なども充実させるべきであろう。
5)基礎生活支援(教育、保健・医療部門)
- 我が国の教育、保健・医療部門に関する援助は機材供与を中心に実施されてきた。これら援助に対してはモンゴル側からも高い評価を得ているとともに、機材のメンテナンス状態も基本的には良好に保たれている。研修生の受入などとも相俟って、基礎生活支援に関してはソフトとハードの両面で大きく貢献してきたと言えよう。
- また、近年の草の根無償による地方教育施設の整備や村落の電化計画は、地方の自立を促すうえでも重要なスキームであるとともに、地元でも大きな支持を得ている。
- 教育分野においては地方の各種学校の充実に向けた支援を行うとともに、我が国ODAとの関連を重視した人選による留学生の受入、あるいは供与機材のメンテナンスに係る技術の取得を目的とした技術系人材の高専等における受入などを進めていく必要がある。また、保健・医療分野においては、供与した機材、ならびにそれに付随する消耗品の管理(現状モニタリングなど)にも注意を注ぎながら援助を継続していく必要がある。
- 基礎生活支援の分野は今後さらなる拡充を求められていることから、より効率的・効果的で持続性と自助努力を促す援助形態を創出していく必要がある。
今後の援助の方向性
- モンゴルにおける今後の最大の課題は、現在人口の約36%を占める貧困層の生活水準を引き上げるための貧困対策である。特に地方における貧困問題は深刻化しており、この問題は今後も根強く残るものと思われる。この課題の解決に向けては、社会セクターへの支援、特に地方においてさらなる援助を展開していくことはもちろん、マクロ経済の安定・維持が不可欠であり、我が国としても忍耐強く援助を継続していく必要がある。
- 援助をより効果的・効率的に実施するためにはモンゴル側も自身の援助受入調整問題の解決に向け努力を行う必要がある。閣僚レベル・局長レベルの海外援助調整委員会を設置したこと、またODA実施メカニズムの改革に向け委員会やワーキンググループを設立したことは一応の評価に値するものの、これらモンゴル側の動きが実際の援助運営に活かされるかどうかについては今後見極めていく必要がある。
- 援助調整以外の援助吸収能力についてもモンゴル側は多くの問題を抱えていることはすでに指摘した通りである。ドナー国による支援、例えば専門家の派遣による知識・経験・技術の供与も必要であろうが、基本的にはモンゴル側のイニシアチブにより人的・制度的能力の向上に努めていくことが肝要である。
- 我が国としては、草の根無償援助の拡充、NGOとの協力による援助、政策レベル中枢への専門家の派遣、などを進めていくとともに、以下に挙げる部門における援助強化の必要性を感じる。今後、これら分野における援助を実施することにより、モンゴルにおける市場経済システムの確立に向けてさらなる貢献を行っていくべきであろう。
(イ)中小企業育成
(ロ)地方分権化に向けての支援(地方における人材育成、保健・医療、教育部門)
(ハ)地方独自産業の育成
(ニ)財政/金融政策部門における人材育成支援のさらなる強化(特に徴税システム)
(ホ)我が国援助の重点的各省、特にインフラ開発省大臣官房における政策立案支援と各実施エージェンシーへの公共投資計画(PIP)・民営化支援と人材育成支援強化
(ヘ)環境(特に都市部における産業廃棄物処理、家庭ゴミ処理対策/施設の強化) - また、今後のソフトウェア開発を中心としたモンゴルの産業発展を考えると、JOCVの地方展開を含め、コンピュータ部門を中心とした人材育成を図ることも急務であると思われる。

