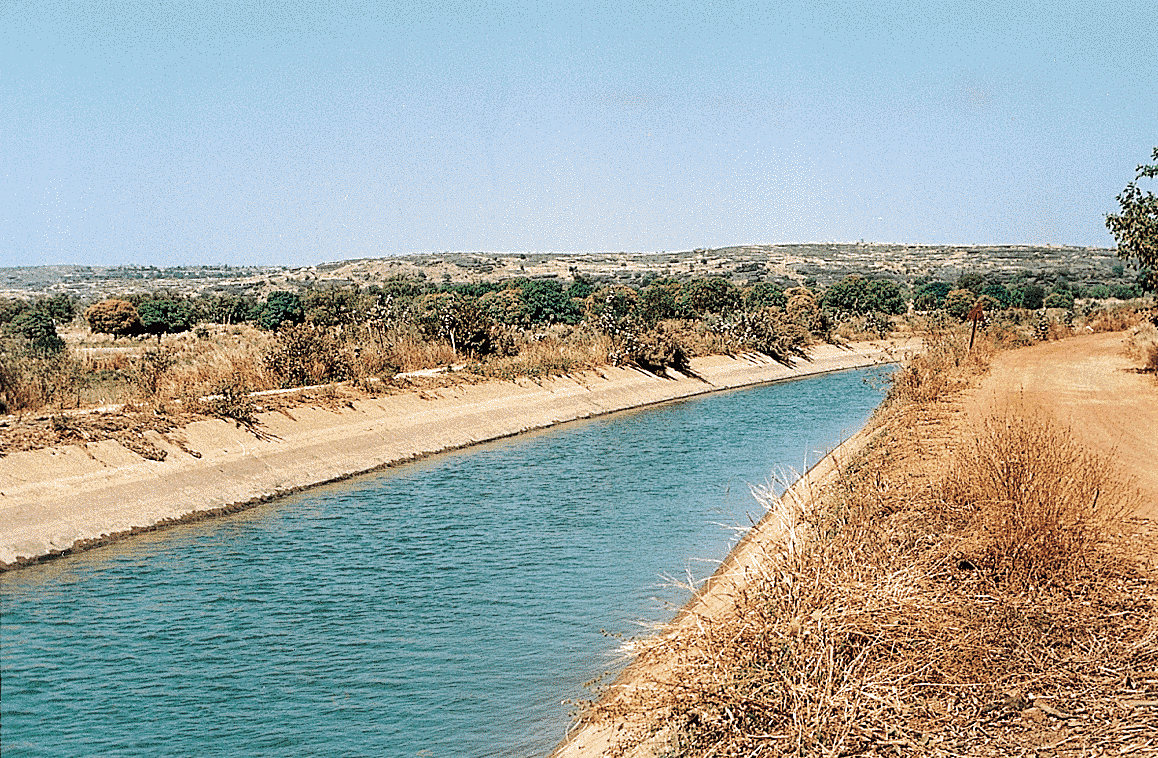マリ バギンダ農業開発計画
(1998年2月、在セネガル大使館)
| 援助形態 | 無償資金協力 |
| 協力年度 | 1986年度、87年度 |
| 協力金額 | 1986年度5.50億円、87年度7.32億円 |
| 相手国実施機関 | 農業省 |
| 協力の内容 | ソトバ、バギンダにおける幹線水路漏水部および付帯構造物の改修、デモンストレーション農場の建設により、バギンダ地区の農業の近代化、土地基盤の整備、付帯的生産施設および社会環境施設の整備を図り、地域経済の振興を図る。 |
〈評価要旨〉
1 効率性
本協力による水路改修、農場建設等は、おおむね計画通り効率的に実施された。
2 目標達成度
放棄されていた農地の再活性化および農地の整備による米収穫高の向上、都市部または外国へ流出していた労働人口の農村部への帰還、穀物以外の野菜等の商品作物栽培による収入の安定化等の目標が達成された。
3 インパクト
食糧自給の確保、雇用の創出(失業率の低下)、農村収入の安定化、農村人口の定着等があげられる。
4 妥当性
1980年にJICAが実施したバギンダ地区農業開発計画実施調査を踏まえ本件を選定しており、必要性、緊急性が適切に判断され、マリ国家開発計画での優先性も確保されている。
5 自立発展性
水路の維持管理はバギンダ・オペレーションと農村住民の参加により行われ、村民の自主性を促すシステムが採用されている。維持管理費用は国家から手当されており、また、個人収入により農作拡大も行われていることから、全体として適切な維持管理体制がとられている。土地使用料の徴収により水路拡充も行われている。
6 環境及びジェンダーへの配慮・影響
当初の計画自体がすでに環境保全型であり、放置されていた国土整備にも貢献している。水路の設置により、確実に水資源が確保されるようになり、従来近隣の井戸等へ水汲みに出かけていた女性の重労働が軽減され、安定した生活用水の確保が可能となった。
7 今後必要とされるフォローアップ
さらなる農業生産性の向上、維持管理体制の改善、流通機構の改革、農村の再組織化、村民の啓蒙等の指導が可能と思われる。また、水路導入部付近に敷設されているソトバ水力発電所で使用されている水資源の有効活用のためには、技術協力が考えられる。