第6章 国際専門家による評価
都市の生活環境(エジプト)
(現地調査期間1998年3月22日~26日)
- ヨーロッパ評価専門家センター(C3E) ジャック・トゥールモンド
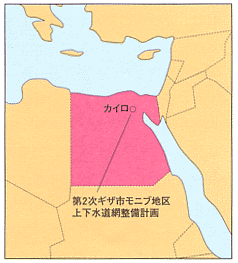
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |
| 第2次ギザ市モニブ地区上下水道網整備計画 | 無償資金協力 |
93年度、 15.27億円 94年度、 23.86億円 95年度、 15.62億円 96年度、 3.14億円 |
大カイロ圏モニブ地区の生活環境を改善するため、日本の無償資金協力により、浄水場の拡張工事、配水管の敷設、送水ポンプの建設を行う。 |
概要と結論
評価対象となったこのプロジェクトの実施が決定されたのは、1993年である。湾岸危機の終了と和平プロセスの開始により、エジプトは中東における和平促進と域内の安定の鍵を握る難しい役割を担っており、当時からエジプトヘの援助は優先課題とみなされてきた。この国の社会的な安定を維持するために、特段の注意が払われたのである。
(1) 何十年にもわたって、大カイロ圏はエジプト最大の人口増加地域であり、基本的なインフラ整備が人口増加に追いつかない状態であった。約1千万人の人口を抱えるこの都市の生活状態の悪化は、社会の安定を揺るがしかねない危険をはらんでいた。そのため、この10年間一貫して、この地域の生活状態の改善は日本の援助の優先課題であった。最近の「国別評価」では、この方針が今もなお妥当であると評価されている(「7.(2)大カイロ圏の衛生改善援助の正当性」参照)。
(2) 大カイロ圏の人口増大は、主に貧しい世帯が住む不法占拠地域で起こっている。これらの地域では、住民の基本的ニーズの多くが満たされていない。地元当局によると、最も深刻な問題は病院、衛生的環境、学校、電気、舗装道路の不足であるという(「7.(1)モニブ地区選定の妥当性」参照)。これらの基本的ニーズの中で、市場経済の面からもエジプトの公共政策の面からも実現がもっとも難しいものの1つが、衛生的環境である。その理由は、上下水道網の基本的な構造が非常に老朽化しており、規模もまったく不十分だからである。上・下水道庁も、上下水道を運営するための必要な財源をほとんど確保できておらず、保守と改良工事はエジプト政府に依存している。都市水道は現行の「エジプト長期展望計画1983-2002」の中でも最優先課題のひとつになっているが、エジプト政府は衛生ニーズに応えるという問題に対処できないでいる(「4.プロジェクトの成果」参照)。本評価調査は、不法占拠で都市化した地域の衛生改善に対する援助が妥当であうたことを、確認する。
(3)評価対象のプロジェクトは、ギザ市モニブ地区の衛生状態を改善するものである。大カイロ圏の周辺部には、不法占拠に始まる都市化地域が十数ヶ所あり、モニブ地区はそのひとつである。モニブ地区の人口は現在20万人。この数は、大カイロ圏の1年当たりの人口増加とほぼ同数である。本評価調査は、モニブ地域を選定したことが妥当であったことを確認する(「7.(1) モニブ地区選定の妥当性」参照)。
(4) プロジェクトは上下水道整備のための「大カイロ圏・マスタープラン」に従って設計された。いくつかの援助国がこのプランの実施に関わっているため、各国間の調整が必要である。評価の過程で、上下水幹線については調整が非常に効果的に行われてきたことが判明した。一方、水道計画立案という点からは、プロジェクトは決して効率的とはいえない形で別の国際援助プロジェクトと交錯してしまった。しかし、さまざまな援助国の関与についての現在の意志決定システムを十分に考慮すれば、このような矛盾が避けられなかったことが分かる。この意志決定システムが柔軟性に富んでいるという利点はあるものの、矛盾の危険をはらむのは不可避のようである。このように、援助国の調整のあり方には問題があることが判明した。援助国協調の長所と弱点についての再評価が行われる場合には、この問題が想起されるべきである(「3.(4) 援助国間の調整」参照)。
(5) 工事はスケジュールどおりに遂行され、コストの超過もなかった。質の面でも問題のないことが確認された。完成した施設は1996年8月、正式にオープンし、完成式典にはエジプト首相や日本国大使が出席した。施設にはすべて、日本の援助で建設されたことが明示されている。
(6) プロジェクトが実施された結果、以前はごく基本的なニーズも満たされていなかった地域の20万人の住民に対し非常に質の高い飲料水が十分に供給されるようになった。モニブ地域の住民は、それまで非常に厳しい状況だった下水の問題で悩まされることがなくなった。プロジェクトのおかげで、住民、とりわけ女性と子供の生活環境が非常に大きく向上した。評価調査では住民たちの高い満足が確認された。効果という点で、このプロジェクトは「非常に成功した」と見なすことができる(「4.プロジェクトの成果」参照)。
(7) 住民ひとり当たりのコストは、約4万3,700円(1,100エジプトポンド)であった。この数字を、他国で実施された日本の援助プロジェクト、とりわけ非常に効率的だったとされたプロジェクトと比較すれば、興味深い結果が得られたであろう。残念ながら、外務省には上下水道分野のプロジェクトについてのそのような体系的な記録はないようである。今後の特定テーマ評価でこの点を追求することを推奨したい(「4.プロジェクトの成果」参照)。
(8) 操業開始から1年以上が経過した時点で、施設はよく保守されており、技術的にも良好である。今回の評価では、プロジェクト自体は「自立発展性が高い」と確認された。
(9) 自立発展性の意味をより高度な視点から考えた場合には、この用語は、エジプトが国際援助なしに大カイロ圏の全住民のニーズに応える上下水道網を維持・発展させる能力として理解すべきである。技術面に関して言えば、この意味での自立発展性は達成されている。しかし、財源の面では状況は異なる。事実、現在の水道料金は、大カイロ圏の発展と同じペースで水道網を適正に維持・拡大するために必要な料金の4分の1以下である。料金は引きあげられてきているが、十分な財政的自立発展性を確保するためには依然として非常に低いままである。料金政策は国家レベルで決定されるという。つまり、プロジェクトに関与している人々にはこの問題の責任はない。しかし、本評価調査の結果としては、広義の自立発展性については「問題あり」と結論づけなければならない。
(10) プロジェクトのインパクトは多岐に渡っている。以前は多くの住民が汚染された井戸水を飲んでいたこともあり、インパクトがもっとも顕著だったのは健康が改善されたことである。モニブ地区での1回の現地調査だけでは、環境に与えた効果を即座に見つけることはできなかった。それは、ゴミの収集という厳しい問題がまだ手つかずで残っているからである。しかしながら、プロジェクトによってモニブ地区のもっとも深刻な汚染問題のひとつが解決されたことは確認できた。
(11) 技術研修において、特に日本の施工業者が数人のエジプト人技術者を雇用し訓練を行ったことによってプロジェクトは副次的にプラスの効果を生んだ。この効果は、ギザ市で日本の援助による3連続プロジェクトを10年以上にわたって同じ企業が請け負ってきたことによって、さらに強められた。
(12) 日本の無償資金協力の規定では、コンサルタントと施工業者は双方とも日本企業であることが求められる。この規定によって、質の高い工事をスケジュールどおりに完成させることができた。しかも、プロジェクトは、これら2社のカイロ事務所を強化することに決定的な役割を演じた。いずれの事務所もエジプト経済の一部となり、多くの人的交流を通じて公共セクター、民間セクターに深く根を下ろしている。しかし、このプラスの副次的効果は持続されない慣れもある。これらのカイロ事務所は日本の援助プロジェクトにほぼ100%依存しているからである。もし日本からエジプトヘの援助が停止すれば、両社とも撤退する可能性がある。エジプト人技術者たちが習得した知識は個人レベルでエジプト国内に残るが、企業としての基盤はない。本評価調査が示すとおり、日本の無償資金協力がエジプト企業や日・エジプト合弁企業によって利用されない限り、これらのプラスの副次的効果は限定的なものである。これらの規定の長所と弱点が再評価される場合には、この問題が想起されるべきである(「4.プロジェクトの効果」参照)。
(13) この評価に貢献した関係者は、プロジェクトの効果を判断する主な基準の1つとして、エジプト人と日本人のパートナーシップや友好関係を高めることに成功したかどうかということを挙げている。プロジェクトは、さまざまな場面(公的機関や民間の管理上層部、工事期間における企業間の調整作業、日本企業によるエジプト人技術者や労働者の雇用、完成した施設の上下水道当局への引き渡し、施設運営責任者への研修など)で、日本とエジプトのパートナーシップを醸成した。プロジェクトという枠組みの中で、これらのチャネルは日本人とエジプト人との人的交流を500例も生み出した。しかもその多くがその後も続く交流となっている。評価の過程でも、上層部の人的交流が十数例確認され、そのほとんどが友好的かつ持続的であることが証明されている(「4.プロジェクトの効果」参照)。
1 プロジェクトの資源
当項と次の項では、評価対象である「モニブ地区プロジェクト(フェーズ2)」として知られるプロジェクトのみについて述べている。
(1) 財源
日本は政府開発援助として、プロジェクトに約58億円(1億5,100万エジプトポンド1)を割り当てた。この資金でプロジェクトの主要工事の費用を賄うことができ、費用の超過はなかった。主要工事以外に、エジプト当局は概算で2億円(500万エジプトポンド)の付随工事を行った。
脚注(1):1992年の為替レートでは1エジプトポンドは39円だったが、1998年には38円となった。
(2) 人的資源
日本側からは、4者がプロジェクトに参加した。第1は日本国大使館の経済班で、常勤スタッフは5名。主に決定段階に参加した(概算で6人/月)。第2は国際協力事業団(JICA)のカイロ事務所で、常勤スタッフは7名。プロジェクトの初期段階で大いに活躍した(概算で6人/月)。第3は日本のコンサルタントで、基本設計調査期間、スタッフは6名(概算で30人/月)。工事中はフルタイムの技術者が2名(概算で60人/月)。第4は施工業者で、建設中は15名の技術者(日本人とエジプト人が約半分ずつ)、およびエジプト人の技師・労働者300名が参加した。
エジプト側からは、ギザ市がプロジェクト・マネージャーを1名指名しただけで、プロジェクト自体に対してほとんど人的資源は投入されなかった。しかし、後で述べるとおり、エジプト側はこの共同プロジェクトに対して多数の人材と多額の資金を投入している。
(3) 組織的資源
準備段階で、役割が次のように分担されることになった。日本国大使館の経済班がプロジェクトの管理面について、カイロのJICA事務所がプロジェクトの技術面について、各々最初の調査を行った。ここではエジプトの国際協力省との接触もあった。予備段階で、基本設計調査が日本のコンサルタント会社(以下「コンサルタント」)に発注された。決定は両国政府の交換公文という形で行われた。
無償資金がエジプトに供与されると、JICAは日本当局の代理という目立たないフォロー役の立場を維持し、正式な責任はエジプト側に移転した。調整の責任はギザ州が、実行の責任はギザ市が、それぞれ担った。無償資金を供与されると、ギザ市はプロジェクト管理責任者としてエジプト技術者を指名した。この人物は市の常任コンサルタントである。5つの関係者を代表する技術者たちによって、運営委員会が設立された。参加したのは、ギザ市、プロジェクトが実施される地域(南ギザ)、大カイロ圏の上水道庁及び下水道庁、モニブ地区での水道関連工事の管理を担当するエジプト企業(エンジニアリング・コンサルティング事務所)である。
日本の無償資金協力による事業は、日本の企業によって実施されなければならない。したがって、ギザ市は詳細な設計調査とプロジェクトの監督をコンサルタントに外注した。工事そのものは入札によって日本の建設会社(以下「施工業者」)に外注された。施工業者は毎月、コンサルタントに報告を行った。施工業者は施設の建設を請け負い、資材の調達を管理した。資材調達は主にエジプトと日本で行った。施工業者は、現地の資機材供給や役務提供を受けるために、約20社のエジプト企業と下請け契約を結んだ。
完成した施設は、大カイロ圏上水道庁(GCWA)と大カイロ圏下水道庁(GOSD)により操業が開始された。
日本とエジプトの当局は、共同の監督システムを確立しておらず、工事に関する共同の終了時評価も行われていない。
2 プロジェクト建設施設
モニブ地区、南ギザ地区、ギザ市、大カイロ圏の上下水道網整備を完了に寄与するため、プロジェクトでは3つの主要な工事を行った。基本設計調査は1992年6月から12月にかけて実施され、400ページの報告書にまとめられた。この調査は質の非常に高いものとして評価されており、この評価報告の作成にもたいへん役立った。
決定は1993年になされた。工事は1994年2月に開始され、計画された期間内の1996年7月に完了した。工事は当初の計画どおりに実現した。これらの工事は、表1の網かけ部分である。
| A | 南ギザ浄水場:処理能力を140,000㎡/日から175,000㎡/日に増大(35,000㎡/日増) | 1996 | 評価対象のプロジェクト |
| B | 配水幹線:総延長2.3キロメートル、直径1,200ミリメートルの幹線を敷設 | 1996 | 評価対象のプロジェクト |
| C | 配水本管:総延長70キロメートル、直径100~800ミリメートルの本管を敷設 | 日本の無資金協力&エジプト側の自己資金による工事(フェーズ1) | |
| D | 配水枝管:約2万カ所の連結1:事とメーター設置 | 同上(フェーズ1) | |
| E | 排水本管:総延長約70キロメートルの本管を建設 | 同上(フェーズ1) | |
| F | 排水幹線:総延長1.8キロメートル、直径1,800~2,000ミリメートルの幹線を敷設 | 1994 | 日本の無資金協力による工事(フェーズ1) |
| G | アブナムロス排水:総延長約5キロメートル、直径2,000~2,500ミリメートルの幹線を建設 |
1996 ? |
エジプト側による工事 |
| H | 送水ポンプ場No.5:ポンプ3基の建設(処理能力はいずれも毎秒1.6㎡) | 1996 | 評価対象のプロジェクト |
| I | 排水幹線およびポンプ場:総延長約12キロメートルの幹線とポンプ場2ヶ所を建設 |
1996 ? |
USAIDプロジェクト |
| J | アブラワシュ下水処理プラント:200万人分の汚水を処理する新プラントの建設 | 1992 | USAIDプロジェクト |
工事中、事故や大きな混乱は報告されなかった。反対に、配水幹線の建設により鉄道の運行に大混乱を生じかねない2地点で推進工法が採用されたと報告されている。さらに、既存の施設を保護するために振動の少ない鉄矢板土留土法が使用されたが、その当時、このような工法を扱えそうなエジプト企業はわずかであった。直面した困難は、主にモニブ地区が不法に占拠/発展してきたことに由来していた。建物も道路も当局の監督外で造られたため、既存の地下施設については、地図にも図面にも記録がなかったのである。この問題は、施工業者が掘削作業に先立って徹底的に試掘を行うことで克服された。また、プロジェクトに必要な資機材の輸入にも、免税処理のために通関手続きが遅れることが何度かあったが、ギザ市が日本企業のために必要な関税を納付し、その後エジプト財務省から払い戻しを受けるという方法で解決した。評価報告作成にあたりプロジェクトのサイト調査を実施したが、これにより完成した施設が良好に機能していることが確認された。施設完成から1年半が過ぎ、南ギザ浄水場(表1:A)は需要に応じて35,000~37,000㎡/日を供給している(計画では35,000㎡/日)。同時点において、下水ポンプ場(表1:H)は平均20,000㎡/日を送水しており、これはこの施設の能力の約4分の1に当たる。プロジェクトの建設の質は最高であると評価されている。サイト調査では、施設や機械類の修理状態も非常に良いことが確認された。エジプトの全ての基準から見て、南ギザ浄水場が供給する水道水の水質は非常に高い。サイト調査の日に9種類の化学的・生物学的指標が計測されたが、全てエジプトの国内基準の限度内だった。9つの指標を平均すると、0を「許容できる」、10を「非常に良い」、という計測値に対して「8」の成績であった。
建設期間が終了した時点で、施工業者は詳細な完了報告書を作成した。この報告書はコンサルタントのチェックを受けた後、最終的にギザ市により受領された。短い報告書がJICAと日本大使館に送付された。
1996年8月、施設は式典をもって正式に操業を開始した。この式典にはエジプト首相や日本国大使も出席した(付録4参照)。施設にはすべて、アラビア語と英語でそれらの施設が日本により供与されたことが明示されている。
3 関連プロジェクト
(1) モニブ地区(フェーズ1)
このプロジェクトは1993年1月に開始され、1996年2月に終了した。建設の一部は日本の援助によるもので(21億円、5,400万エジプトポンド相当)、その他はエジプトが出資した(約400万エジプトポンド、16億円相当)。
エジプトが担当した部分は、モニブ地区全域の配水本管(最大直径800ミリメートル)と排水本管の建設などである。両本管とも、それぞれ総延長が約70キロメートルで、合計して140キロメートルとなる(表1:CおよびE)。エジプトの担当部分には、配水枝管とメーターの設置も含まれ、その数は2万件にものぼる(表1:D)。本管への配管工事が迅速に完了したことによって、モニブ地区のすべての建物がプロジェクトの恩恵を受けるようになったことは特筆に値する。一方、日本は本管の資機材を調達し、推進工法を用いて総延長1.8キロメートルの排水幹線(直径1,800~2,000ミリメートル)を建設した(表1:F)。
エジプトが出資した工事の責任は、正式にはギザ市が担っていたが、監督はエジプトの民間企業(エンジニアリング・コンサルタント会社)に委託されている。工事はエジプト企業9社が請け負った。このうち1社が施工業者で、残り8社は下請け業者である。日本の資金援助による工事は、フェーズ2と非常によく似た組織構成、つまり同じ日本企業2社がそれぞれコンサルタントと施工業者をつとめることで実施された。
フェーズ1については、まだ評価は行われていない。
(2) その他の関連プロジェクト
(1) 南ギザ浄水場
南ギザ浄水場は、1970年にチェコスロバキアの援助で建設され、当初の給水能力は140,000㎡/日であった。1992年には、老朽化のため60%の過負荷運転となっていた。サイト調査時点では、旧施設が幾分か改善され、235,000㎡/日を給水していた。また、サイト調査時点ではフランスの援助プロジェクトによって新たな拡張工事が行われている最中であった。この第3プラントの規模は、日本がモニブ地区プロジェクト(フェーズ2)で援助したプラント(35,000㎡/日)よりもはるかに大きい(200,000㎡/日)。
(2) オムラニア地区プロジェクト
オムラニアのプロジェクトは、大カイロ圏の給水分野における日本の最初の無償資金協力プロジェクトである。工事は1989年6月に開始され、1991年2月に終了した。総工費は22億円(5,700万エジプトポンド)にのぼった。このプロジェクトは、モニブ地区プロジェクトの3分の1程度の狭い地域に対して実施された。オムラニアとモニブは距離的には近接しているが、技術的には、両者の上下水道網は別々の独立したシステムになっている。
オムラニア地区プロジェクトは、公式には評価されていないが、たいへん成功したという報告を受けた。このプロジェクトによって、その後10年にも及ぶパートナーシップが誕生した。このプロジェクトの成功を記念して、オムラニア主要道路の1つが「日本通り(Japan Street)」と名づけられた。
(3) 南ピラミッド地区プロジェクト
これは、カイロの給水分野における第4の日本の援助プロジェクトである。プロジェクトは、モニブ地区プロジェクトの5倍程度の広い地域に対して実施され、配水幹線、浄水池、配水ステーションが建設されることになっている。本評価調査時・工事は開始直後であった。総工費は40億円(1億300万エジプトポンド)と予定している。モニブ地区プロジェクト(フェーズ2)で建設された配水幹線および排水送水ポンプ場が利用されることになっているため、このプロジェクトは技術的にモニブ地区のプロジェクトとリンクしている。
組織構成はエジプト側・日本側とも、モニブ地区プロジェクト(フェーズ2)と同じである。つまり、10年以上にわたって同じ技術者のグループが緊密な関係を保つということである。この新プロジェクトが実施されること自体が、モニブ地区プロジェクト(フェーズ1.2)を肯定的に評価できるという証である。この継続的な協力関係の意義については、後に述べる(「プロジェクトの効果」参照)。
(4) 排水幹線
ギザ市は、モニブ地区の排水幹線と排水送水ポンプ場とを接続するために必要な工事を請け負った。この工事は、総延長約5キロメートルのアブナムロス排水(直径2,000~2,500ミリメートル)を建設するものである(表1:G)。エジプトによるこれらの付帯プロジェクトは1996年に完了し、モニブ地区への飲料水の提供が開始された。
同時に、排水送水ポンプ場は排水幹線(総延長約12㎞)と2カ所のポンプ場を通じて、排水処理プラントに接続された(表1:1)。これらのプロジェクトはUSAIDの援助で実現した。
(5) 排水処理プラント
アブラワシュ下水処理プラントは、1990年から1993年にかけて建設された。ギザ市の主要地域(人口約250万人)から排出される汚水を処理することができる。この新プラントはUSAIDによって建設された。
(6) どのプロジェクトによる成果か?
上下水道網は複雑で、いろいろと相互に接続されたネットワークになっている。したがって、上下水道網を部分的に改良する個別プロジェクトがどれだけ効果を上げたかを正確に評価するのは困難である。事実、各々のプロジェクトは、多くの過去のプロジェクトの恩恵を受けていると同時に、将来のプロジェクトで使用される施設の一部を提供しているとも言える。個別プロジェクトの成果を評価するためには、大まかな推計を行わざるを得ない。本プロジェクトについて概算すると次のようである。
- モニブ地区の住民は、評価対象のモニブ地区プロジェクト(フェーズ2)とそれに先立つ同地区のプロジェクト(フェーズ1)の双方から恩恵を受けている。後者には、エジプト側と日本側が資金提供している。これらのプロジェクトの資金額は、総計で約99億円(2億1,700万エジプトポンド)にのぼる。
- 南ギザ浄水場の拡張工事は、チェコスロバキアの援助によるプラントが過負荷運転を強いられ、老朽化していた時期に行われた。短期的に見れば、フェーズ2による拡張工事は、モニブ地区のみならず南ギザ全体の上水道ニーズに追いつくためのひとつの方策だったと考えられる。現在、浄水場では大規模な第2の拡張工事が行われている。つまり、南ギザの給水に関する全般的な問題はほどなく解決されるということであり、中期的に見れば、フェーズ2のプロジェクトは特にモニブ地区のニーズに対応したものであると考えられる。
- 配水幹線(表1:B)、排水送水ポンプ場(表1:H)、フェーズ1で建設された排水幹線(表1:F)は、被益対象が同じであるという特徴がある。いずれもモニブ地区のために必要であり、いずれもギザ市の南部と西部にまたがるより広範な上下水道の一部分である。これらの施設規模は、モニブ地区のニーズのみならず、上下水道網全体に適合している。その点では、モニブの住民だけが対象だとは言えない。その一方でモニブ地区は、エジプトとUSAIDによる総延長17キロメートルの排水幹線の恩恵も受けている。大まかに見積ると、モニブ地区プロジェクト(フェーズ1・2)によって建設された幹線やポンプ場は、上下水道網全体の改善に寄与し、その程度はモニブ地区が上下水道網全体から受けた恩恵に匹敵すると言える。このことから、モニブ地区が受けた恩恵は、モニブ地区プロジェクト(フェーズ1・2)のおかげであり、評価対象のプロジェクト(フェーズ2)のみの効果とは言えない。
- もし排水処理プラントがなければ、モニブ地区の住民はプロジェクトの恩恵を十分に享受できないであろう。したがって、プロジェクトからの恩恵の一一部は、アブラワシュ下水処理プラントを建設したUSAIDプロジェクトのおかげと考えるべきである。本評価報告の作成中に、このUSAIDプロジェクトの効果を推計することはできなかった。将来は、このような推計を基本設計調査に含めることを推奨したい。次の表は、恩恵の10%をUSAIDプロジェクトによるものとする、まったくの推量に基づくものである。この項をまとめると表2のようになる。
| 工事 |
費用 (単位:億円) |
モニブ地区にかかった費用 | うち配水 | うち排水 | |
|
B、C、D、 E、F |
モニブ(フェーズ1) |
日本:21 エジプト:17 |
38 | 12 | 26 |
| A、B、H | モニブ(フェーズ2) |
日本:57 エジプト:2 |
59 | 44 | 15 |
| G、1 | アブラワシュ下水処理プラントヘの排水幹線 | ???? | 0 | 0 | |
| J | アブラワシュト水処理プラント | ???? | 11(非常に大まかな推計) | 11 | |
| 合計 | 108 | 56 | 52 |
(4) 援助国間の調整
プロジェクト(フェーズ1・2)は、上下水道に関する大カイロ圏の戦略的計画に沿って設計された。プロジェクトに伴う日本・エジプト両国の多くの調整作業は、結果的に非常に成功した。
複数の援助国がこの計画の実施に関わっているため、調整作業が必要であった。上下水道幹線については、この調整が非常に効果的になされてきていることが証明された。特に排水については、総延長20キロメートルの幹線、3カ所の下水送水ポンプ場、大規模な排水処理施設のすべてが、エジプト、アメリカ、日本のプロジェクトにより4年間で完成されたことは特筆に値する。
しかし、南ギザ浄水場の場合、評価対象のプロジェクトと他の国際援助プロジェクトとの関係は効果的とは言いがたい。日本のプロジェクトは、容量を大幅に上回る操業を強いられていた旧施設の給水能力(140,000㎡/日)をわずかながら改善するため、35,000㎡/日を供給するプラントを建設した。このプロジェクトが完了した1年半後、フランスの援助によって第2の拡張工事(200,000㎡)が行われている。当初から1件の大規模な拡張工事を行えばスケール・メリットが得られたはずなのだが、現状では、将来の浄水場が3つの異なる技術による3つのプラントを持つことになってしまった。日本が基本設計調査を行っていた頃、フランスはプロジェクトの準備を進めていたのだが、意志決定の過程で遅れが生じた。フランスを待っていたら、モニブの住民たちに飲料水を供給できるのは3年後になっていたであろう。つまり、プロジェクトを期間内に開始するためには、3万5,000㎡のプラントを建設するという決定は不可避だったのである。
短期間に2つのプラントを別々に建設することで、技術的な非効率が生じた。この非効率の原因が、さまざまな援助国の参加を調整するための現行の意志決定システムにあるのは明確である。このシステムは次のように機能しているという。各援助国は、エジプトの国際協力省と援助取極について定期的に交渉を行う。衛生分野では、関連する取極は毎年2~3件である。国際協力省は上・下水道庁に対して、これらの取極で創出された機会についての情報を提供する。具体的には、供与されるのがソフト・ローンなのか、グラントなのか、予算のシーリングが高いか、低いか、組織面の制約があるかなどである。一方、上・下水道庁は毎年、国際協力省に実施候補プロジェクトのリストを提出する。資金待ちのプロジェクトが20~30件あり、数年待たされるプロジェクトも多いという。援助国は、自国の優先政策にもっとも適したプロジェクトを選択する。例えて言うなら、国際協力省という「市場」において、プロジェクトを供給するエジプトの「サプライヤー」とプロジェクトを求める援助国の「バイヤー」とが出会うと理解すればよい。供給が需要と一致すれば、援助側と被援助側のさまざまな制約を調整するために、関連プロジェクトが策定される。このシステムには柔軟性という利点がある。モニブ地区の住民たちは「上手な援助調整」によるよりも3年も早く、飲料水の供給を受けることができた。このことが、この柔軟なシステムの利点を明確に実証している。
エジプトにおけるグラントやローンを調整するために、さまざまな努力がなされている。国連開発計画(UNDP)は定例の「援助国会議」を開催している。また、分野ごとのサブ援助国会議も開催され、そのひとつに水問題がある(灌漑が優先課題だという)。援助国会議は主にプロジェクトに関する情報交換の場である。上述のように、本評価調査の結果から見ると、援助国の調整には問題がある。援助国間の調整の長所と弱点について改めて論じられる場合には、この問題が思い起こされるべきである。非効率を避けるために調整を強化すべきなのだろうか、それとも柔軟性を享受するために現状を維持すべきなのだろうか?
4 プロジェクトの成果
評価の時点で、プロジェクトはモニブ地区のほぼ100%の世帯に便益を与えていることが確認された。1990年当時、飲料水の供給を受けていたのはわずか5%、排水管については0%であった。モニブ地区の人口は10年前の13万人から、現在は20万人に増大した。世帯数は3万、建物数は2万と見られる。地区全体に供給される飲料水の量は、30,000㎡/日、住民1人当たり150召/日である。公共水道網の漏水を計算に入れると、平均して1人当たり130リットル/日となり、1990年の10~20リットルから飛躍的に改善した。水不足は解消され、路上を汚水が流れることもなくなった。
基本的な水道料金は、0.12エジプトポンド(4.6円)/立方メートルである。平均使用量を20立方メートル/月とし、30立方メートル/月以上使用する「大量使用者」には、より高い料金が課される。工場向けの水道料金は、基本料金の約6倍となる。モニブ地区の平均的世帯は、年間約24エジプトポンド(900円)を支払っており、料金の支払は順調である。飲料水の供給を受ける以前、住民たちは民間のタンク車から飲料水20リットル当たり0.5エジプトポンドという料金で買わざるを得ず、汚水タンクからの汚水のくみ取りにも1㎡当たり1エジプトポンドを支払わなければならなかった。つまり、以前は飲料水1リットル当たりの総コストは、現在の200倍だった。住民の多くはこのような高額な水を買うことができず、公共水栓に行かざるを得なかった。だが、それらは多くの場合、100メートル以上離れた場所にあり、しかも非常に混雑していた。そのため水栓の周囲では喧嘩になることもあったという。女性たちは洗濯用の清潔な水を切望していた。ひどく汚染された自家用の井戸を使用していた住民もあった。汚水タンクのほとんどはくみ取りが行われず、汚水が路上にあふれ出ていた。ロバに引かれたタンクで運ばれる汚水が路上の悪臭をさらに悪化させていた。
プロジェクトが開始される以前、ギザ市議会の代議員たちは、いつも住民からの圧力にさらされていたという。地区住民が集団で水不足や不備な排水システムの不便さを訴えていたからである。現在は、ほとんど不満は聞かれなくなったとのことである。
本評価報告時点では、プロジェクトの効果を次のように査定することができる。プロジェクトが実施された結果、以前はごく基本的なニーズも満たされていなかった地域の20万人の住民が非常に質の高い飲料水を十分に供給されるようになった。モニブ地域の住民は、それまで非常に厳しい状況だった排水の問題で悩まされることがなくなった。プロジェクトのおかげで、住民、とりわけ女性と子供の生活環境が非常に大きく改善された。評価調査では住民たちの高い満足が確認された。したがって、このプロジェクトは効果という点で「非常に成功した」と考えられる。
また、プロジェクトの成果の効率を査定することも有用であろう。表2によれば、モニブ地区への便益提供コストは108億円と見積られる。このコストを今日恩恵を受けている住民の数(20万人)との関連で論じることもできるが、将来プロジェクトの恩恵を受けられる人口(2005~2010年の24万7,000人)から効率を査定する方が公正であろう。この数字から計算すると、1人当たりのコストは4万3,700円(1,100エジプトポンド)である。この数字を、他国で実施された日本の援助プロジェクト、特に基準プロジェクト(非常に効率的だったとされたプロジェクト)と比較すれば、興味深い結果が得られたであろう。残念ながら、本評価報告時点では、日本の外務省には基準プロジェクトに関する特別な記録はないようである。上下水道の分野についての次回の評価では、この点を追求することを推奨したい。
5 プロジェクトの自立発展性
サイト調査で、施設はよく保守されており、優れた技術者の管理下にあることが確認された。大カイロ圏の上水道庁が、水の使用量を各建物ごと、あるいはしばしば建物内の各世帯ごとに計測していることが報告された。使用量に応じて料金が実際に課せられ、料金は通常の場合、徴収されている。モニブ地区プロジェクトに限って言えば、自立発展性という意味で「非常に成功した」プロジェクトであると評価できる。
自立発展性の意味をより高度な視点から考えると、この用語は「エジプトが国際援助なしに大カイロ圏の全住民に上下水道を提供する能力」として理解される。技術面では、機械・電気設備のほとんどを今後も輸入に頼らざるをえないとしても、技術面に関する限りエジプトはそのような能力を備えていると考えられる。大カイロ圏の上水道庁は、13の浄水場を通じて540万㎡/日の上水を供給している。スタッフとして460名の技術者と建築技師を有している。上水道庁は、各施設の設備の遠隔操作、漏水の検出、GIS(地図情報システム)など、近代的テクノロジーを駆使している。大カイロ圏下水道庁も、必要な技術的ノウハウを有していると報告されている。エジプト企業は、ほとんどすべての種類の調査、建設、管などの基本的資材の調達を請け負う能力を備えている。少なくとも3社のエジプト企業が推進工法による作業を始めている。本評価時以前から、上水道庁はUSAIDの援助を受けて管理運営の改善や人材育成を目指したプロジェクトを実施している。
一方、財政面を重視するならば、自立発展性は望めそうにない。事実、現在の基本的な水道料金(0.12エジプトポンド/立方メートル)は、大カイロ圏の発展と同じペースで水道網を適正に維持・拡大するために必要な料金(0.56エジプトポンド/立方メートル)の4分の1以下である。基本設計調査では料金体制の再調整計画について触れており、大カイロ圏上水道庁は現在も水道料金の引き上げを望んでいる。事実、水道料金は1992年から1997年にかけて40%引き上げられている。しかし、この値上げはエジプトのインフレ率ほど高かったとは言えず、つまり実質的には大幅な値上げはなかったことになる。しかも、水道料金は1998年、国政レベルの決定により凍結されている。この点についてはいずれのプロジェクト関係者にも責任はないところであるが、評価としては広義の自立発展性については「問題あり」と結論づけなければならない。
6 プロジェクトのインパクト
プロジェクトのインパクトは多岐に亘っている。特に以前は多くの住民が汚染された井戸水を飲んでいたこともあり、もっとも顕著なのは健康状態の改善である。本評価調査では、健康問題について詳しい調査は行わなかった。
モニブ地区での1回のサイト調査だけでは、環境に与えたインパクトを即座に見つけることはできなかった。それは、ゴミ収集という厳しい問題がまだ手つかずで残っているからである。しかし、プロジェクト前後の比較を行うと、環境にプラスのインパクトを与えたことが判る。1992年、住民13万人分の汚水はさまざまな方法で地下水またはナイル川へ送水されていた。具体的には、堀への直接投棄、汚水タンクからの漏出、汚水タンクからあふれて路上に流出、のナイル川に注ぐゾモール運河への収集された汚水投棄などである。しかし1998年、住民20万人分の汚水は完全に収集され、砂漠地帯に新しく建設されたアブラワシュ下水処理プラントに送水されている。したがって、プロジェクトはモニブ地区のもっとも深刻な汚染問題のひとつを解決したと言える。このように下水に関しては、予想外の価値あるインパクトがあったと報告されている。
水の供給は、防災という意味からも非常によい効果をもたらしている。過去には非常に難しかった火災への効果的対処が、現在は可能になった。
エジプト人専門家に対する技術訓練という点で、プロジェクトは優れた副次的効果を生んだ。これは特に、日本の施工業者が十数人のエジプト人技術者を雇用し訓練を行ったことによる。この効果は、ギザ市で日本の援助による3件の継続的プロジェクトを10年以上にわたって同じ企業が請け負ってきたことによって、さらに強められた。これらのエジプト人技術者のひとりは、本評価調査にも貢献してくれた。この技術者は、今では日本の技術に関して10年以上の経験を持ち、日本での研修にも何度か参加している。
日本の無償資金協力の規定では、コンサルタントと施工業者は双方とも日本企業であることが求められる。この規定によって、質の高い工事をスケジュールどおりに完成させることができた。さらに、プロジェクトは、これら2社のカイロ事務所を強化することに決定的な役割を演じた。いずれの事務所もエジプト経済の一部となり、多くの人的交流を通じて公共セクター、民間セクターに深く根を下ろしている。しかし、このプラスの副次的効果の持続性については懸念もある。これらのカイロ事務所は日本の援助プロジェクトにほぼ100%依存しているからである。もし日本の対エジプト援助が終了すれば、両事務所とも撤退する可能性がある。エジプト人技術者たちが吸収した知識は個人レベルでエジプト国内に残るが、企業としての基盤はない。本評価報告が示すとおり、日本の無償資金協力プロジェクトがエジプト企業や日・エジプト合弁企業により実施されない限り、これらのプラスの副次的効果は限られたものとなってしまう。これらの規定の長所と弱点についての再評価が行われる場合にはこの問題が想起されるべきである。
プロジェクトの効果を査定する際、評価に貢献した人々が非常に興味を示したのは、エジプト人と日本人のパートナーシップや友好関係への効果についてである。表3は、プロジェクトによってパートナーシップや友好関係が継続的にいかに高められるかを示す、3つのチャネルを略説したものである。
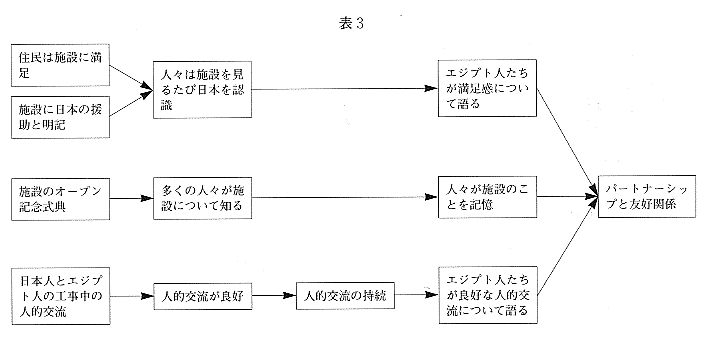
上段のチャネルは、20万人の住民が施設に満足しているという事実から始まり、住民が日本の援助による施設であると認識しているという仮説をもとに進む。さらに、住民が永続的に日本の援助を意識すると仮定しなければならない。しかし、実際はこの仮定どおりにはならないだろう。すぐに他の多くの施設工事(道路、電気設備など)と混同される可能性があるからである。日本の援助であると明示すれば、確かに効果はあるだろうが、それを定期的に目にする住民はわずかである。上段最後の枠は、住民が日本の援助に好意的な発言をするという仮定である。
中段のチャネルは、数百万人が新聞でエジプト首相と日本大使が共同で施設のオープンに立ち会ったという記事を読んだという事実から始まる。これは人々が記事に気づき、さらにそれを永続的に記憶すると仮定しなければならない。日本が年に1~2件のプロジェクトを実施すれば、これらの仮定は現実になる。だが、日本の援助に対する認識も、他の援助国の施設がオープンすれば、すぐに置き換えられてしまうであろう。
下段のチャネルは、プロジェクトは日本人とエジプト人の間に約500例の人的交流を生んだという事実から始まる。それらの人的交流には、10以上の公的機関や民間企業の上層部も含まれている。人的交流の多くは、工事中の企業間の調整作業から生じている。日本の施行業者は工事期間中、約300名の労働者をおもにモニブ地区から雇い入れ、新施設の操業を担当する約20名のエジプト人スタッフを訓練した。プロジェクトという枠組みの中で、このようなパートナーシップのチャネルは、日本人とエジプト人との間に約500例の人的交流を生み出し、その多くがその後も持続している。また、評価調査では10例以上の上層レベルでの交流も観察された。これらの多くが友好的かつ持続的であることが確認された。もしこの評価報告の範囲を大カイロ圏で10年以上に渡って実施されている一連の衛生関連プロジェクトにまで拡大すれば、1,000例以上の人的交流が始まっていると言えるであろう。完全な評価報告を行うためには、これらの人的交流についてより綿密な分析が必要である。
モニブ地区プロジェクトの場合、持続的なパートナーシップの構築という点では、下段のチャネルが群を抜いてもっとも効果的だったと思われる。したがって、この評価調査から得られた1つの教訓として言えるのは、日本の当局はあらゆる適当な手段を使って人的交流の構築・改善・継続を支援すべきであるということである。具体的には、相互の語学研修や訪日などが挙げられる。支援する日本人スタッフにも無償資金のごく一部を割り当て、エジプト人パートナーたちの最善の人的交流をはかり、その交流を数年にわたって育んでゆくのが良いかもしれない。
7 プロジェクトの妥当性
(1) モニブ地区選定の妥当性
大カイロ圏の人口増大(年率1.2%)は主に、貧しい世帯が占拠した地区の非公式な都市化という形で現れている。これらの地区の多くは、年率5~10%で成長している。モニブ地区は、大カイロ圏を取り囲む10以上の不法占拠地区のひとつであった。モニブ地区の人口は現在20万人で、この数は大カイロ圏の1年当たりの人口増加とほぼ同じ数である。モニブ地区の平均的世帯の年収は3,000エジプトポンド(14万円)で、基本最低額(大まかに見積って年間1,500エジプトポンド)を多少上回っているが、平均的なエジプト人の年収(2万エジプトポンド)を大幅に下回っている。この点は将来的に変わるかも知れないが、地価や住居費もモニブ地区は大カイロ圏でもっとも安い地区である。したがって、モニブ地区は大カイロ圏の中でもっとも貧しい地区であることが確認された。
モニブ地区のような地域では、住民の基本的ニーズの多くが満たされていない。地元選出の代議員たちによると、最も深刻な問題は病院、衛生的環境、学校、電気、舗装道路の不足であるという。これらの基本的ニーズの中で、市場経済の面からもエジプトの公共政策の面からも実現がもっとも難しいのが、衛生的環境であり、その理由についてはすでに述べた(「プロジェクトの成果」参照)。これらの理由から、モニブ地区を選定したことは「非常に妥当である」と見なされる。
(2) 大カイロ圏の衛生改善援助の妥当性
評価対象となったこのプロジェクトの実施が決定されたのは、1993年である。湾岸危機の終了と和平プロセスの開始により、エジプトは中東和平促進と域内の安定の鍵を握る難しい役割を担っており、当時からエジプトヘの援助は優先課題とみなされてきた。この国の社会的な安定を維持するために、特段の注意が払われたのである。
何十年にもわたって、大カイロ圏はエジプト最大の人口増加地域であり、基本的なインフラ整備が人口増加に追いつかない状態である。数百万人の人口を抱えるこの都市の生活状態の悪化は、社会の安定を揺るがしかねない危険をはらんでいた。そのため、この10年間一貫して、この地域の生活状態の改善が日本の援助の優先課題であった。最近の「国別評価」では、この方針が今もなお適切であるとして、次のような表現で評価している。「日本はこの国の社会経済を安定させる一助となるセクターを優先すべきである。つまり、貧困層や経済的弱者に貢献する分野への援助である。…」
日本の援助方針は、公共インフラ整備、特に都市部の給水を最優先課題に掲げる「エジプト長期展望計画1983-2002」および最近の「エジプト5カ年計画(1987-1997)」に沿ったものである。

