7 文化の多様性を考慮した開発援助(ミクロネシア)
(現地調査期間:1997年9月3日~13日)
- 早稲田大学理工学部教授 菊地 靖
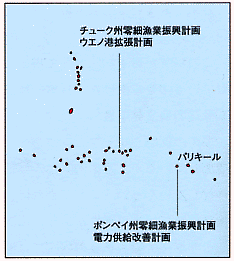
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |
| 零細漁業振興計画 | 無償資金協力 |
92年度、 1.00億円 |
製氷・保存施設、倉庫、管理室の設置及び天水タンク、保冷箱等の供与 |
| 電力供給改善計画 | 無償資金協力 |
92年度、 10.30億円 |
発電設備(発電機等)、配電設備(ケーブル、リレー等)の設置及びトラック等の供与 |
| チューク州零細漁業振興計画 | 無償資金協力 |
94年度、 1.16億円 |
製氷・保存施設、倉庫、管理室等の設置及び計量器、トラック等の供与。 |
| ウエノ港拡張計画 | 無償資金協力 |
93年度、 10.54億円 94年度、 9.90億円 |
岸壁補強・拡張、俊漢、コンテナヤードの整備、航路標識の整備 |
1 はじめに
今回の調査の対象地域は、ミクロネシア連邦(人口、約10万)のポンペイ(Phonpei)州とチューク(Chuuk)州の二州である。同連邦は、600余りの島々からなっているが、主としてヤップ(Yap)、チューク、ポンペイおよび、コスラエ(Kosrae)の四つの島々を中心に、それぞれの州が連邦内での独立した行政区を形成している。住民一人当たりの平均年収は1993年で、1,900米ドルと、太洋州でも比較的高い。しかし、この数字は同連邦の生産性を的確に表していると言うより、見せかけの数字であって、実際には、1986年に米国の信託統治から、「米国との自由連合」というかたちで、まがりなりの独立を果たした国の住民一人当りの平均年収として捉えるべきであろう。すなわち、ミクロネシア連邦の国家財政の53%はアメリカとの協定によるコンパクトマネーに支えられており、この財政支援は2001年まで継続されることになっている(Asian Development Bank:1997/8)。さらに、アメリカ以外の諸国からのグラントも15%を占めている。つまり、国家財政の68%は諸外国からの援助によっているのである。
つぎに、ミクロネシアの経済と社会の特徴として挙げられるのは、雇用形態であろう。同国では、発展途上国の雇用形態としては異例とも言うべき状況がみられる。つまり雇用人口の70パーセントが、サービス業従事者なのである。
サービス業の割合が高いのは、通常、高度に発達した先進工業国に見られる状況である。同国の場合、サービス業には教員と一般公務員が含まれているが、これらの割り合いが44%を占めている。そして、これらの業種に携わる人々が貨幣経済の主流となっているが、彼らの給料の供給源はアメリカからのコンパクトマネーなのである。つまり、従来、自給自足経済の中で生活を営んできた住民達が、1985年の独立を契機に急激に膨張した現金経済活動の中で、現金収入が得られる職種(例えば、公務員など)を志向するようになった。一方、農林・漁業従事者の数が、1980年には16.7%あったものが、1994年の統計では9.3%にまで激減した。月額収入を比較すると、公務員は、民間企業労働者の2.7倍の給料を得ている。こうした収入の著しい差が、人々を公務員に駆り立てる大きな要因となっている。そして、公務員を採用する際に、通常、・彼らの固有の文化的価値観に基づいた、血縁温情主義や身びいき主義が公然と行われるため、既存の公務員の親戚縁者が登用される傾向にある。このような行為は暗黙の了解として公に批判されることはないと言われている。
2 個別評価
(1) 零細漁業振興計画
氷文化の導入は零細漁民に対してだけではなく、島民全体の生活様式に大きな変化を与えつつある。その具体的な住民へのインパクトは、食料を保存するという発想がうまれたことや美味なる味覚の発見だけではなく、農村地域における小売商店での冷温方法による商品の長期保存と、それによって鮮度の高い食品の供給が可能になったことである。
当プロジェクトの第一の目的は、零細漁業の振興である。つまり、沿岸零細漁民の生活向上につながる援助として実施されたものであった。しかし、零細漁民は魚を売って得た収入で、期限切れに近い輸入缶詰(魚、コーンビーフ)を購入するため、自分たちで捕った鮮魚を食べようとしない傾向にある。急激な現金経済の導入により、アメリカ流の大規模スーパーマーケットの出店が相次ぎ、現地で「TVフード」と呼ばれている冷凍食品が住民の間に急速に普及してきている。さらに、米(カリフォルニア米)の販売と米食の習慣が平行して上昇傾向にある。こうした現象を見ると、彼らの固有の食生活がアメリカ的な食生活へと変化しつつあることが窺われる。このような変化が、現金経済活動を活性化することは確かであるが、しかし一方では、現金による消費活動が活発になればなるほど住民に貧困感や貧富の差を日常的に感じさせることになり、一層、現金獲得志向が強まって住民感情を物質主義へと急激に変化させつつある。自分達で捕獲した鮮魚や農産物(タロ、パンの実など)を主食とする習慣を取り戻すには、簡単でバラエティに富んだ調理を紹介するような食物調理教室の導入が急務であろう。自分たちで捕獲した新鮮な魚を美味しく食べるための<調理法工夫>といったミニ・プロジェクトは、自家消費のための漁業の活性化だけではなくて、彼等の食生活の改善にも有効であろう。
当該計画の運営管理に関する問題は、製氷を直接管理しているNational Fishery Corporationの職員が経営管理の知識を十分持っていないために、製造販売の収支が明確でないことである。氷の販売価格はスコップ一杯7セントで、1日2トンが販売されているが、製造コストとの収支バランスが全く考慮されていない。公的な決算表によるとプラント作業要員二人の給料を差し引いても毎月、平均約2,000ドル近くの収益が見込まれているはずであるが、実際には、毎月1,500ドルが州政府によって補填されているとのことである。職員の説明によると、機械の補修費、燃料費(ガソリン)、電気代や製氷用の水の代金などに消えてしまうとのことであった。しかし、8月の決算表の上では、2,966.20ドルの収益が銀行に預金されていると言うことになっている。また、本来、氷運搬用として供与されたトラックが他の部署で使用されていた。
一般住民の製氷プロジェクトヘの関心は大変高いが、中南部の住民にとっては既存の製氷工場への交通の便が悪いために、氷の購入に不便を感じており、南部にも製氷プロジェクトを設立してほしいと強く望んでいる。また、住民は、週に二日(金曜日と日曜日)の休業が、氷の利用に不便であるとして、改善を求めている。
(2) 電カ供給改善計画
現在、ポンペイの島民のほとんどの世帯(3,610世帯;1994年現在)が電気の恩恵に浴している。中でも、テレビの普及が目覚ましく、住民が映像文化に触れる機会が急速に増え、娯楽はもとより、多くの知識を吸収する場が提供されるようになった。このような状況は、ひとえに日本からの援助によって、5メガワット分の電力が増強されたことによるものである。しかし、オーストラリア人技師はポンペイ島での6%以上にも及ぶ爆発的人口増加(全国平均1.9%)によって、電力不足が、1998年から1999年にかけて起こるであろうと予測していた。さらに、同技師はこの火力発電所の維持運営に関して、技術・管理の面でポンペイ人に委ねることに危倶を感じていて、すべてを移管するには50年ほどかかるであろうと言っていた。エネルギーの供給は国の近代化を支えるに最も重要な要件の一つである。この社会経済発展の要である電力プラントの維持管理を外国人に依存している今日の状況は異常であり、早晩ミクロネシア人にとって代わらねばならない。そのためにも、電気技術者と経営管理の専門家の養成が急務である。
電気使用料はほぼアメリカ本土なみで、一時間当たり、一キロワットの使用量が15.1セントである。この額は住民にとってかなりの負担となっているが、ポンペイでは、近年、主都コロニアから農村部や新開地への移住が盛んになってきており、その促進要因の一つとなっているのが電気の普及である。政府は、このような人口拡散現象が都市整備上、また、自然環境の保全上、好ましい傾向であると評価しており、今後も、地方における電気の普及事業に関心を示している。次に近代文化と固有文化との衝突から生じる問題として、以下のような事例が見られた。住民の固有文化への強い執着が電気料金の集金に支障をきたしたり、電信柱設置用の土地の借地料をめぐるいざこざの原因となる場合がある。電気の普及は、前述のように住民にとって大変な文化的インパクトを与えているが、一方では、彼らの固有の価値観と近代的価値観との間に葛藤があり、それをどのように解決するかが、電力公社と関連の組織・企業にとっての当面の重要な課題である。ポンペイでは、今日でも、ナーンマルキ(Nahnmwarh)と呼ばれている伝統的チーフが隠然たる社会的・政治的権力を持っている。したがって、一般住民は近代的社会ルールと伝統的ルールの狭間で心理的葛藤を強いられている。人々は、母系血縁原理に基づいた拡大家族制のなかで、血縁者間のしがらみを断ち切ることが出来ないというジレンマに悩まされている。一つの例を挙げると、電力公社が、その地域のチーフから電気使用料を徴収しようとしたところ、支払いを拒否されるということが起こった。現在の電力公社のマネージャーは、チーフと同じ氏族集団に属しており、彼自身が次期チーフの地位を継承する立場にあるため、現チーフに電気料の支払いを強要することをためらわざるを得なかった。徴収しにくい理由は、チーフが氏族集団の構成員のために、氏族内のさまざまな問題の解決や個人的な相談のために夜も電灯を使っているおり、それは一種の公務として扱われるべきと主張しているからである。さらに、マネージャーは、チーフには現金収入がないという事実を知っているため、敢えて請求しにくかったという理由もある。このような状況のもとでは、絶対的権力を持っている伝統的チーフに楯突くことは、血縁原理の認識が強く求められるポンペイの固有文化のなかでは許されないことである。
(3) チューク州零細漁業振興計画
ポンペイと少々異なって、チュークでは製氷業務は週6日間操業されており、住民からは、消費者への配慮が十分なされているとの評価を得ている。当地でも、氷の用途は大変広く、捕獲魚の保存、一般食料の保存、あるいは、バーなどのビールの冷蔵から葬式時の死体の保存にまで使用されている。製氷施設は零細漁民だけではなく、ポンペイと同様に、一般住民に広く利益を与えていると評価されている。しかし、問題は製氷のための水の獲得である。チューク州の水道設備が老朽化しているために、給水が十分で無く、製氷には雨水と、業者からの購入する水が使われている。水の購入代金が高いために、州政府からの補填が必要とされている。
チュークの製氷工場は5トンの製氷能力を持っているが、上記のように、氷を多目的に使用するには十分な供給規模に至っていない。1997年5月の選挙で新しい知事が選出されたために、チューク州零細漁業施設の長も交代させられていて、彼はこの選挙前後の製氷作業に関する詳細を全く把握していなかった。こうした状況は経営管理体制の継続性の欠如と言わざるをえない。
さらに、機械操作技術の問題として指摘されたことは、電圧の自動制御装置がないということである。したがって、電圧が一定に制御出来ないために二機の製氷機を同時に稼働できないのは、機械の構造的欠陥と技術者の専門的知識の欠如に因るものである。また、同時に製氷のための水槽にひび割れがあり、水利用の効率が極めて悪いという、プロジェクト実施上の基本的な欠陥がみられる。
本プロジェクトにより供与された最新のコンピューターは使用されていないまま放置されていた。住民にとって奏功性の高いプロジェクトであるが、十分な経営能力と、今後の具体的な展望が欠けているため、現段階では、将来性については危惧せざるを得ない。したがって、チュークに関しても、適正な電力供給の方策が早急に具体化される必要があろう。
(4) ウエノ港拡張計画
ウエノ港は、拡張後、マグロの中継集積基地、およびコンテナ集積基地としての機能を果たしている。しかし、残念なことに、入港する船舶数は少ない。具体的にはチューク州交通局の統計(1997年)によると、1995年には、3社の船会社が利用しており、年間43隻が入港し、1996年には2社の船舶33隻が利用しただけである。チューク州はミクロネシア連邦で最大の人口を抱えながら、生活の基本的なインフラ整備(電力、道路交通機関、水道)が全く整備されていないので、折角の援助プロジェクトも機能的な役割が果たせないでいる。ウエノ港拡張計画もその例にもれず、他の機関設備との連携が十分でないために、当初予測した利用数を下回る結果となっているので、今後、船舶の商業的利用のインセンティブをつくり出すことが必要であろう。援助投資の効率をあげるためにまず考えなければならないことは、港湾の使用を機能的に活性化するための方策を探ることだろう。当地が、マグロ漁業海域の中心に位置しているという利点を見逃してはならない。マグロ漁業集積基地として港を活性化するために、空港設備の充実と航空機による日本への直行便や周辺地域(東南アジアや北米西海岸)への輸送と梱包基地への道がある。たとえば、日本への直行空輸だけでもコンスタントに行なわれれば、港や空港だけではなく、一連の関連事業も活性化されるであろう。すなわち、単一のプロジェクトだけに注目するのではなく、その周辺の関連事業をも視野に入れた包括的な取り組みが効果的なのではなかろうか、本計画においても、単にウエノ港の整備に留まらず、他の機関設備との連係を考慮に入れた総合的なプロジェクトの策定が望まれるのである。さらに、プロジェクトの円滑な実施のためには、これまで随所で述べてきた人材育成、すなわち、それぞれの分野における専門家の養成が必須条件となろう。
3 開発人類学的評価方法と提言
ミクロネシアでは、ヤップ州を除いて他の3州は母系制親族構造を基盤とした社会である。開発人類学の見地から社会経済開発の実施状況を見ると、開発プロジェクトの効率や奏功性を左右する主要因は、その社会が非血縁集団と家族関係を超越して共同体を形成することが出来るかどうかにかかっているのである。したがって、援助国は社会経済開発の実施にあたって、その社会がどのようなタイプの共同体を持っているか、あるいは共同体を形成する潜在的可能性を持っているかどうかを事前に把握しておかなければならない。その際、出来る限りその社会の固有文化が社会経済開発の実施手法に取り入れられるように注意をはらうべきである。そのために地域研究者と調査が行われる現地の研究者と予備的共同調査が必要である。通常、母系制社会においては、こども達は母親の親族集団に成員権(メンバーシップ)をもっており、父親とは異なる集団に属している。このように個人が両親のどちらか一方の親族集団に帰属している社会を総称して単系制社会とよんでいる。一般に母系制社会では女性が、主として土地の所有権をもっており、夫(男性)がその管理と運営権を妻(女性)と分担して二人で財産管理を行うので、日本のような父系的傾向の強い社会と比べると、その管理方法はより複雑である。
今回の調査対象地域であったポンペイとチュークは母系社会であるため、こども達は、母親の財産やタイトルを相続・継承する権利をもっている。とくに、土地の所有権は女性に属している。母系制では、一般に財産相続が母から娘へと行われるが、こども達の養育(社会化)は、主としてこども達の母方のオジによって行われる。したがって、母方のオジは、社会的父として実父よりも親しみを持ってこども達に接している。しかし、実父が抱えている、父と子の結びつき(父性愛)と、制度的なオジ・オイの関係から求められる社会的父としての義務との間にある情愛の葛藤は、母系制社会の男性がもつジレンマである。たとえば、相続の対象となる不動産に関して、父は成員権を異にしている実子への相続は慣習法的に不可能であることを知っているが、心情的には血肉を分けた実子にも相続させたいと思う父性的な愛情と、自分の出身集団(出自集団)内での期待された行動とが相反するために、男性(夫)側に心理的苦悩が内在している場合が多いのである。
さてポンペイとチュークの社会では、今日もなお人々の社会行動様式のなかで典型的な母系制社会の価値観がかなり残っている。たとえば、伝統的に既婚男性は、結婚当初は妻方に同居するが、集団内での地位は必ずしも安定していない。やがて、実子たちの成長とともに実家へ帰り、自分の姉妹のこどもたちの面倒を見なければならなかったが、今日では、若い世代においては夫が妻子から離れて生活することはほとんどなくなっている。しかし、財産権については、従来どおり妻が握っているし、また、実家においても、社会的父としての役割が軽減されてきたために、男性は勢い政治に関与することに生きがいを見い出だすようになってきた。以上のような、ポンペイやチュークの男性の行動様式の変化は、母系制崩壊の一つの過程であると言えるであろうが、同様な現象は、ホンジュラスのガリフナ族や、インドネシアのミナンカバウ族など、他の母系社会にも見られる。
血縁関係の強い集団原理を基盤とした社会では、血縁認識が社会行動様式を規制して、非血縁者に対して常に猜疑の対象とみなす傾向がある。すなわち、自己を中心とした血縁基盤による拡大家族としての利益集団(氏族集団)が帰属認識の中核になっており、血縁集団の「自己中心的志向」の価値観に基づいた行動様式が、自分の所属している親戚縁者から期待されているのである。
このような社会の特徴として指摘できるのは、非血縁者や集団は不信と猜疑が交錯した人間関係を全面には出せないが、社会行動様式の根底には強く存在していることを全員が承知していることである。それでは、これらの社会ではどのようにして人間関係がつくられているか?多くの社会では、非常に現実的、あるいは実利的に人間関係が形成される傾向にある。前述のように、血縁原理に基づいた社会関係は、私的(インフォーマル)な人間関係を強力に支え、人間本来の情実に基づいた人格観的関係へと人々を導き、二者間の『損得関係原理』を合理化する働きがある。たとえば、ポンペイやチュークの社会では、公務員採用のところで説明したようにインフォーマルな人間関係(『私的構造原理』)を背景として、血縁を優先する方式が採用され、将来の保証となる関係を成立させる。このような方法が、彼らにとって最も実利的な方策なのである。政府や官公庁などの社会レベルでの人間関係を見ても、常に顔と顔との私的関係が重視されて、二者間の損得関係原理がフォーマルな関係(『公的構造原理』)に優先して利害関係が成立する。ポンペイやチュークのような血縁意識の強い社会においては、このようなインフォーマルな人間関係が唯一の信頼できる相互扶助関係として機能している。さらに、小地域での固有文化の不可視的な重みと社会的規制力は、人々の日常生活におけるあらゆる社会的行動様式を統制しているのである。したがって、特に若い世代は自分の所属する氏族内(血縁集団内)での評価を無視できず、親族仲間の評判をとても気にかけがちである。前述のチーフから電気使用料の徴収に非常に気を使っていたポンペイ人のマネージャーが、固有文化と近代的企業文化との狭間で悩んでいる姿は『私的構造原理』と『公的構造原理』との間の葛藤を象徴的に示している。彼は私の、「どのようにチーフを説得するのか」という質問に対して、次のように答えてくれた。まず、氏族集団のメンバーからのチーフヘの貢ぎ物(豚、パンの実や魚)を売って現金を手に入れる方法をナーンマルキ(Nahnmwarki)に進言して、了解してもらい、次に、近代的支払い方法への理解を求めて、現金での支払いを受けることに成功して、問題を解決したそうである。このケースのように、ドラスティックな形での進行は早急には望めるものではなく、通常、近代化による固有文化の価値観の変化は、制度的変化に比べて、かなりの時間的経過をK要とするものである。
開発政策の策定に際しては、それぞれの地域の時代的特殊性を考慮して、社会経済開発計画が立案されるべきである。つまり文化的多様性に則した形での開発が望まれるのである。ミクロネシアのように、固有文化の影響を強く残している国への社会経済開発援助の最も必要な要件は、被援助国の自助努力で、何が、どの程度まで出来るかについて政府と住民とが対話の中で模索し、両者自身によって決定してもらうことである。この方法は住民が開発計画へのアイデンティティをもつ誘因となるであろう。その際、住民代表としてチーフの参加を得ることが絶対条件である。このような手続きを採れば、若干開発計画の施行が遅れる可能性は高いが、住民参加型の開発計画が実現できるという利点が生じる。住民のコミットメントは、自助努力発揚への相乗効果となることは確実である。とくに、母系性社会では、女性の役割の重要性を考慮せずには開発の効果が半減してしまう。さらに、地域文化に則した開発計画立案には、地元の研究者や、援助国の地域研究者の助言を求めることが大切である。
社会発展や経済開発に関して、ミクロネシアのように血縁温情主義が強く残存している社会では、拡大家族の認識レベルを超えた社会や国家レベルヘの意識の萌芽が急速にうまれるとは望めない。そこで、こどもだけではなく、成人をも対象にした長期的な開発教育を通して、自決・自助努力とは何か、あるいは共同体とは何かを考える機会をつくり、さらに、自分たちの国はなんぞやという国学(Nationalolgy)としてのミクロネシア学の創造への動機づけが必要である。
開発プロジェクトと固有文化との有効な関係と予備調査のあり方について考えてみよう。社会人類学は早くから、現地の固有文化と技術が社会経済開発の推進母体となると強調してきた。たとえば、ミクロネシア社会の固有文化に潜んでいる価値観や技術を社会経済開発へ有効に利用するような、開発方法の発掘が真剣に考慮されなければならない。ひとつの方法として、予備調査の段階から地域研究の専門家である人類学者を開発経済学者や政治学者たちとの共同調査に参加させることが有効な方法の一つである。人類学者を含めた社会経済開発の予備調査や事後評価の方法は、1980年初頭に、タイ国のKhon Kaen Universityと英国のSussex Universityとの共同研究で開発されたRapid Rural Appraisal(RRA)法とParticipatry Ruyal Appraisal(PRA)法であるが、「グループによる短期間調査方法」として、現在、欧米諸国の公的機関で採用されている。この調査法の特徴は、グループによって、総合的な現地調査を行って、固有文化を研究しようとする点にあり、経費と時間の節減のために調査期間の短縮がうたわれている。したがって、通常、調査期間は、10日から14日間をめやすとしている。調査期間が短いからといって、調査内容が粗雑であるということは決してなく、むしろ効率よく良質の資料を収集することを目ざしている。地域研究者を中心として調査では、無駄な資料を極力排除して、かつ地域研究者がもっている豊富な、地域の人間関係を最大限利用することによって効果的な資料収集が可能となる。私が開発したRapid Research Method(RRM)は、社会人類学者も経済学者と同じような早さで的確な現地調査が可能であることを示している。つまり、RRA法とPRA法の、二つの調査法に加え、RRMは新たにインターネットを利用して、事前に現地の人類学者と綿密な調査の調整を図ることを提言している。すなわち、調査に赴く前に、Eメールで「調査項目表」を現地研究者に送り、数回にわたって意見交換をする。そして、現地の特性を十分加味した調査項目を作成しておくことによって、期間と費用の節減と正確な資料と情報の収集を可能にするのである。
最後に、文化の多様性を考慮した開発方法について次のような提言をしたい。社会経済開発政策を立案するとき、文化の多様性を考慮することが開発計画の実施にとって、文化効率の観点から極めて効果的で、かつ、人間中心志向型の開発を促進させる重要な要因となるからである。たとえば、ミクロネシア連邦のような、今でも官僚制度や社会認識の発達が遅れている地域では、大規模開発プロジェクトよりも、前述のような血縁共同体を中心とした小地域開発やジェンダー間のバランスのとれた開発、あるいは、固有文化に根ざしたミニプロジェクトが有効であろう。とくに自助努力を喚起するために、本来定着しにくい新しい外部技術や制度と、固有文化との接点を可能なかぎり政策策定の段階で発見することが重要である。そうすることによって、ミクロネシア人が新しい文化へのアイデンティティをもてるような機会を提供すると同時に、自助努力発揚への相乗効果が期待できると予測される。
附記:評価調査の第一段階として私がミクロネシアで同国の外務次官を訪問した際に、アジア開発銀行の経済開発プロジェクトの派遣要員として同国に滞在していたボストン経済開発研究所の研究員(アメリカ人)が同席していて、ミクロネシア経済に関する説明のすべてを行っていたが、この事実は当該国の政策決定の自立性の欠如と、官僚制度の幼弱性を象徴的に物語っているとの印象を受けた。
4 参考文献
Asian Development Bank. 1997.
Fedarated States of Micronesia: 1996 Economic Report ADB.
Ashby, G. 1993. Something of Value
Micronesian and Beliefs. Revised Edition. Rainy Day Press, Ponpei
Gardner, K & D. Lewis. 1996.
Anthropology, Development and The Post-Modern Challenge. Pluto Press. London.
Oliver, D. L. 1989.
Native Cultures of the Pacific Islands. University of Hawaii Press.
牛島巌 1987.『ヤップ島の社会と交換』、弘文堂、東京
World Bank Publication. 1993.
Development in Practice: Sustaining Rapid Development in East Asia and Pacific. The World Bank. Washington DC.
State Government. 1996.
States Census Reports of Ponpei and Chuuk. Ponpei & Chuuk.

