6 保健医療分野での協力と開発(ボリビア)
(現地調査期間:1998年3月2日~3月8日)
- 東京慈恵会医科大学教授 天木 嘉清
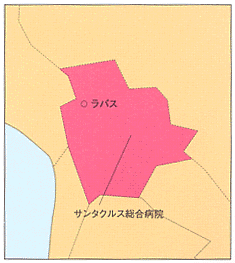
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |
| サンタクルス総合病院建設計画 | 無償資金協力 |
83年度、 5.05億円 84年度、 18.47億円 85年度、 18.48億円 |
ボリビアは東部の中心都市サンタクルス市に「サンタクルス総合病院」の建設計画を策定、これに必要な施設の建設及び医療機材を供与した。 |
| サンタクルス総合病院 | プロジェクト方式技術協力 |
87年12月~ 92年11月 |
サンタクルス市は近年急速に人口が増加しつつあり、同市唯一の総合病院が老朽化したために、サンタクルス市における総合病院建設の無償資金協力を行った。同病院の完成が目前となった1985年5月に内科、小児科、婦人科、病院管理、X線検査、臨床検査、病理、医療機器管理の各分野について技術協力の要請があった。この要請に基づき、内科、外科、小児科、病院管理、看護、病理の各分野について技術協力を行うこととし、まず第1次医療の整備を行い、最終的には第3次医療が可能な病院とすることを目標に協力を実施した。 |
| サンタクルス医療供給システム | プロジェクト方式技術協力 |
94年12月~ 99年11月 |
サンタクルス病院を拠点とした初期医療サービスの提供、救急外来システムの確立、更なる財政的自立に向けての病院管理部門の強化及び診察部門の拡充のための教育システムの充実についてプロジェクト方式技術協力による技術協力を実施中。 |
1 評価調査の概要
(1) 調査目的
ボリビアにおける保健、医療案件を対象に評価調査を実施し、我が国協力の効果等を検証するとともに、同国に対する保健、医療分野での協力、開発のあり方について検討、提言を行う。評価対象はサンタクルス総合病院である。ボリビアのサンタクルス総合病院は1983年に建設が開始され、1986年4月に完成した。ボリビア政府は、我が国に対して病院建設のみならず、病院管理、内科、外科、婦人科、小児科、臨床検査、病理、医療機器管理の各分野におけるプロジェクト方式による技術協力も要請してきた。今回の調査は、無償資金協力による病院建設(機材供与を含む)並びに第1次プロジェクト方式技術協力(1987年12月より92年11月)及びその延長として現在実施中の技術協力を対象に有識者評価調査を行うことが主目的であるが、それと同時にサンタクルスのオキナワ移住地診療所及びラパスにおける小児リハビリセンターに対する草の根無償の視察も行った。
関係者との懇談ではサンタクルスにおいては県、市の行政担当官、病院関係者、ラパスにおいては保健省、大蔵省、現地JICA事務所、国際機関等と懇談の機会を持った。
(2) 評価手法
現地調査に先だって本プロジェクトに関係する報告書類の査読、外務省中南米局担当課よりの現地の政治、経済状況の説明、JICA関係者から現地でのプロジェクトの活動状況の説明などにより事前の勉強会を行った。現地調査では病院外関係者と病院内関係者の両者に対して懇談が行われた。前者はサンタクルスにおいては県、市の行政担当官、JICA関係者、ラパスにおいては保健者、大蔵省、JICA、国際機関の関係者であり、後者は日本から派遣されている医師、技術者、ナース指導者、現地の医師、現地のナース、技術者、病院管理者、さらに外来に来ている患者、入院患者などである。建物、供与器材の可動状況の点検なども行った。
2 評価結果
(1) 計画の妥当性
ボリビア国サンタクルス市には、国立病院として100年の歴史を有するサンファンデデイオス病院が存在していたが、建物も器材も極めて古く、この24年間に急速に増加した市民の医療需要に応えられない状態にあるためボリビア国はわが国に対して無償資金協力を要請してきた。これに対して我が国は200床の総合病院を建設することを決定した。
当時ボリビア最大の州であるサンタクルス州のサンタクルス市は、将来の人口増加が予想されており、総合病院の建設がこの地に計画された。この計画は正しかったか?この答はサンタクルス市が現在では人口の増加率ではボリビア第一の都市であり、この病院がサンタクルス市の医療の中核となっている現状をみるなら当初の選択は適正であったと思う。また、このサンタクルス総合病院は完成後、「日本病院」と命名され、日本の協力に対するボリビア側の感謝の気持ちが表明されている。
(2) 病院建物の視察
外観は一部塗装の剥げた部分があるものの、外来、病室、手術室、検査室等は大きな破損部分は見当たらず充分に機能を果たしている。初期の計画では200床であり、その当時は200床で十分であったと思われる。現状では患者数も増加し、増床が計画されている。最初から大きな構想を立てるのではなく、まず200床位から始めて、周囲の状況に併せて病床を増やして行くやり方はよかったと思われる。
(3) 病院各部署の視察
1)小児科
乳児死亡の低下がこの国の保健政策の目玉となっている。病院建設当時から小児科を充実させようとの意気込みが感じられた。1996年に母子保健法ができ、5才以下の子供は無償で治療が受けられるようになった。この法律により、全国から他にはこのような施設がないことから、多くの患者が殺到し、病院はパンク状態である。
小児1CUについて関係者より下記のような声があった。
- (1) 6床あるが常に満床である。もう少し病床を増やして欲しい。
- (2) 人工呼吸器がもう少し欲しい。
- (3) 専門の看護婦が少ない。
- (4) 難しい症例が増えた。もう少し技術移転が欲しい。
- (5) 薬品の種類と量が充分ではなく、また、管理が悪い。
2)産科
- (1) 1996年の母子保健法により、妊婦は無料でお産ができることから、多くの妊婦が病院に押し掛けてくる。その50%は正常分娩患者である。このふるいわけが今後の課題である。
- (2) 日本病院の努力で、1994年に比べ1997年では乳児死亡率は114/1,000人が70/1,000人に、妊婦死亡率は、48/1,000人が35/1,000人にそれぞれ減少した。この病院のはたす役割の大きな事を物語っている。
3)画像診断部
この科は病院の収入の大きな割合を占めている。内視鏡科、放射線科(CT検査、エコー検査、レントゲン検査が含まれる)、中央検査(心電図、負荷試験に心電計検査)等、幅広い分野である。したがって、供与した器材も番多かった。
- (1) 内視鏡、CT、エコー等の内には古い器械もあるが、有効に使われており、可動率もよい。
- (2) 6チャンネルの心電計が壊れ1チャンネルしか使えない状況にあった。そのため負荷心電図がとれず、また胸部誘導の心電図が1チャンネルでは狭心症、心筋梗塞等をチェックできない。早急に修理するか又は補充が必要である。有効に用いているので、ほとんどの機材は可動できるが、なかにはこのような機材もある。
4)検査室
- (1) 器械が壊れた時に修理しようとする努力の欠如。
- (2) 検査結果の精度が低下していた。
過去には検査項目20項日中、1項目のみ正しいという時もあった。精度管理プログラムを作り現状では精度の向上がみられる。
5)放射線科
- (1) 器械の選択は正しかった。ボリビアで一番よい施設である。
- (2) この科のスタッフがストライキの中心となっていることが頭痛の種である。
6)外科
- (1) 手術前は5室あり、その内の1つは無菌手術室であった。手術件数は年間2,500位である。
- (2) 手術室には電気メス、麻酔機、モニター、X線透視装置等の機材が供与されている。機材の稼働率はよかった。
- (3) 手術室内のX線透視装置は現在壊れていて、修理に多額の費用を要するので、新しいのを購入したほうがよいとの意見であった。
7)看護科
- (1) 現地のナースは検温、血圧測定等を教えればやるが、その意味を理解していない。異常値がでても報告しない、異常値の意味が分かっていない。
- (2) 看護教育の基本的知識レベルの低さがあり、技術移転には時間を要する。
- (3) 現在までに看護婦の10%が日本で研修を受けているが、帰国後、修得してきた技術を自分のみに温存し、皆に伝達しない傾向が見られる。
8)病院管理部
- (1) この病院が開設された1987年より91年までの専門家派遣数と器材供与の年次経過を表1に示している。器材の供与は88年を最高に92年には最低値を示している。高額なものは供給済みの現状を示している。
- (2) 表2に入院患者数の年次変化を示す。1990年から増加し、94年には6500人に達している。この病院が地域医療に入りこんでいく姿を示している。
| 年度 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 合計 | 92 |
|
長期 短期 |
40 | 410 | 511 | 714 | 617 | 2652 |
6(4) 12(3) |
| 研修員 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19 | 6 |
| 機材 | 0 | 72 | 45 | 43 | 57 | 217 | 27 |
| L・C | 0 | 0.5 | 5.2 | 5.7 | 3.5 | 14,9 | 8.9 |
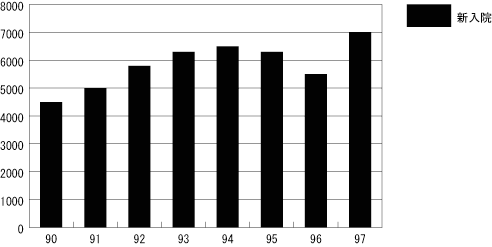
- (3) 救急外来の患者数は表3のごとく年々増加の傾向を示し、現在は開院時の二倍以上を数えている。救急部の増設が急務である。
| 診療科 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 |
| 内科 | 6,070 | 6,861 | 7,615 | 7,400 | 8,147 | 10,023 | 9,696 | 10,322 |
| 外科 | 4,793 | 5,180 | 5,577 | 4,989 | 5,932 | 6,098 | 4,648 | 5,284 |
| 小児科 | 5,415 | 6,496 | 6,858 | 6,715 | 7,216 | 8,815 | 9,041 | 13,906 |
| 産婦人科 | 236 | 1,455 | 1,963 | 1,371 | 2,287 | 2,943 | 2,789 | 4,585 |
| その他 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16,569 | 19,992 | 22,013 | 20,475 | 23,582 | 27,879 | 26,174 | 34,097 |
- (4) 病院収入については1996年以前では収入の70%が上乗せ給料分であった。そのため、借金が出て、必要な消耗品や機材が買えない状況になっていた。1996年新病院長になり、この上乗せ給料支給を停止したことにより、病院の収入により維持管理費がだせるようになった。市からの援助は年間210万ドル、病院の収入年間140万ドルで維持がなされている。
9)保守管理部
- (1) プロジェクトで供与された機材は12年も経っているので修理が多くなりつつある。部品調達が難しい。
- (2) 今後とも供与する機材については故障した時にその部品の補充が容易にできる、すなわち代理店が自国にあるか近隣諸国にあることを十分考慮していくことが重要である。日本から取り寄せると時間の無駄となる。
- (3) 機材の保守管理センターを作るべきであるとの意見がある。
- (4) 機械の故障に対して現地の人の無関心、無気力も目立つ。国民性の違いがあるのか?
- (5) 日本に研修に行った技術員が帰国後に日本病院の賃金が安いため、他病院に行ってしまった例がある。
10)その他の病院の施設の視察
外来では、薬を購買する薬局、診療費の自己負担額を決めるカウンセラーが配置されていた。この病院について患者に評判を聞いたところ、この病院の評判は良く、100?の遠隔地から来ている患者もいた。病院内には学生用の講義室、図書室もあった。近い将来救急室の拡張のための用地も用意されており、一部では工事が始まっていた。
(3) 医療機材の選定
内視鏡、心電計、超音波診断装置等のなかにはすでに10年以上もたち、耐用年限をすぎているものもあるが、現在可動しているものが大部分(約90%)である。その意味では故障の少ない維持の楽な機材選定は正しかったといえる。一次プロジェクトでは呼吸器、感染症、消化器疾患、乳幼児疾患を主とし、特殊の医療心臓外科、脳外科は対象外にしたため、プロジェクトにより供与された機材は一次医療に見合った選択であったと,思われる。
(4) 技術移転についての評価
医師、看護婦、検査技師等多くの病院関係者が日本に研修に行き技術移転が行われている。この技術移転は単なる技術を学んでくるのみではなく、日本の社会機構、文化を見聞することにより、自分たちの再発見、再認識を可能にする。これは目にみえない効果であるが現地のスタッフと懇談してみて感じた印象である。一方帰国後学んできた知識、技術を同僚に伝授するのを嫌う風潮もあるとも聞かれた。それに対する対策として、1)帰国後移転された技術知識を現地の人々に伝授するシステムを作るための方策を考える、2)現地のスタッフを均等に日本へ研修のために派遣することも再考を要するのではないか。吸収力の強い、今後指導的立場になる、若い人たちを中心に人物選考を行う、3)日本から指導者を呼んで現地で教育する、などの対策も必要である。
日本から医師の派遣は、短期間の派遣では現地の人の信頼を得にくく、数年単位で行う必要を感じた。この都市が人口増加のため交通外傷が増加するのが予想され、脳外科医などの派遣も必要である。
(5) 目標達成度
プロジェクトの効果の具体的な形として、日本病院の努力で、1994年に比べ1997年では乳児死亡は114人/1,000人から70人/1,000人に、妊婦死亡率は48人/1,000人が35人/1,000人にそれぞれ減少した。乳児死亡率、妊婦死亡率の減少はプロジェクトの主な目標の一つである。この病院のはたす役割の大きな事を示している。
新入院患者数は1990年は4,500人が95年には5,500人に、更に97年には7,000人と増加をみている。
外来に来ている患者とのインタビューでは、この病院の重要性、医師、看護スタッフらは信頼がおけると語っていた。
この病院が日本病院として現地では、名が通っており、地元の人たちのみならずボリビア全土に信頼を得ている印象を受けた。日本の経済援助で建設された病院との知識は一般の人々にも浸透していた。
(6) 今後の自立発展性
多くの医師、ナース、スタッフが育ち86年に比べ医師、ナースの職員数は現在では1.5,2.0倍にそれぞれ増加しているが、臨床的レベルは低い。今後、特に、救急、集中治療、心臓外科など三次医療にこの病院が移行していくということであれば、器材、スタッフの投入継続がなかったら、いままでの物的、人的資源の投与が無に帰す可能性があり、三次医療として自立の可能性があるまで支援の継続が必要である。
ボリビアでも私立の病院では優秀な医師、高度の医療器材を準備出来る所もあるが、国民の大多数を占める低所得者層が亭受できる医療施設はボリビア国の保健政策、保健行政そのものがまだ未熟のため一つもなく、この病院がボリビアが期待する一般市民のために開かれた三次医療施設になっていくものと思う。
例えば、今回視察したオキナワ診療所のような所が第一次医療を受け持ち、二次、三次の高度医療は日本病院が受け持つといった連携が必要である。その意味からももう少しこの病院の支援が必要である。
(7) 行政側の対応
サンタクルス県保健局長、サンタクルス市保健課長、USAID、UNDP、JICA、保健・年金省保健次官、大蔵省公共投資次官、と一連の会議を行った。この席上、当方よりは、1)市と国との二つの命令系統を一本化する、2)職能別の全国レベルのストライキは病院の運営に多大の支障を来たすので政府レベルの取り組みが必要、3)医師給料、地位の改善、4)現在、日本は経済的に低迷しているが、その状況下での援助であるとの認識を有して頂きたい、5)永続的な保健政策の確立が必要である、6)日本病院は日本の協力による代表的な病院であり、この存続は日本のODA活動にも影響を与える、等の諸点について指摘を行った。
(8) 提言
今後この日本病院が一人立ちしていくためには、我々日本側の問題とともにボリビア側の医療政策そのものに起因すると思われる問題も避けて通ることは出来ない。今回の評価活動を通じて感じた問題点のいくつかは次のとおりである。
1) 度々起こるストライキ問題
この病院を運営していく上での不安定要素の一つになっている。内政の問題であるが、気長に市、国の代表との話し合いを通じよい解決策を出すように努力すべきである。
2) 給与の問題
医師の給与が低く、サンタクルス日本病院の医師が本俸のみでは不足のため他病院に出ている。そのため常勤医がおらず、患者管理がおろそかになる事態を招いている。公立病院医師の身分保障について国の政策として対応を考えていかねばならない。
3) 市、国の命令の二系統をどのように一本化するか。
この問題は病院運営が円滑に行われない一因になっている。この問題は日本側の枠外の問題であるが、国、市当局に一本化についての対応を要請すべきである。
4) 供与器材の維持、修理は重要である。この業務を行うメインテナンス・センターを現地に作る等の方策も必要である。

