5.南米のインフラ設備(エクアドル)
(現地調査期間:1997年8月11日~15日)
- 経団連国際本部長 島本 明憲
- 国際本部総括グループ長 早川 勝
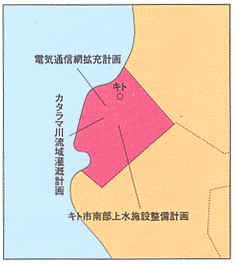
| プロジェクト名 | 協力形態 | 供与金額・協力期間 | プロジェクトの概要 |
|
電気通信網拡充計画 |
有償資金協力 | 86年度76.70億円 | エクアドルの通信事情改善のため策定された電気通信網拡充4カ年計画(1985~88年)の一環として、首都キト、主要商業都市グァヤキルおよび産業、観光、輸出(石油、農産物)港として重要な地方都市(エスメラルダ、ミラグロ等)における電話需要に応えるため、交換機、伝送設備等を整備することにより、電話網の拡充ならびに近代化を図るものである。 |
|
カタラマ川流域灌漸計画 |
有償資金協力 | 86年度85.94億円 | エクアドル第1の商業都市グァヤキルの北東約90キロメートルのカタラマ川流域において、総面積6,450ヘクタールの灌漸開発を行ない、米、大豆、とうもろこし等の生産の増大と農業生産性の向上を図るとともに、農家所得の確保と地域経済の発展に資そうとするものである。本計画は、シビンベ川(カタラマ川の支流)を水源としてカタラマ川の左岸の灌漸開発を図るシビンベ計画と、カタラマ川の水をポンプで揚水して同川右岸の灌漸開発を図るカタラマ計画の二つの計画より構成されている。 |
| キト市南部上水施設整備計画 | 無償資金協力 |
96年度4.57億円 97年度13.07億円 |
キト市およびその周辺地域の人口は、過去10年間に年間3%と急激に増加し、現在140万人を超え、水不足が深刻な問題となっている。特にキト市南部地域の低所得者層が居住する高台居住地区では給水施設の整備が立ち遅れており、給水車や浅井戸を利用した不便な生活を余儀なくされている。このため、エクアドル政府の「キト市南部上水施設整備計画」にもとづき、導水施設等の建設、改修および資機材の購入資金を供与するものである。 |
はじめに
1997年8月中旬、エクアドルに対する有償資金協力プロジェクト(2件)および無償資金協力プロジェクト(1件)を評価するため、現地を調査するとともに、現地のエクアドルおよび日本の関係者よりヒアリングを行なった。
1. 最初に評価時点における両国関係およびエクアドルの政治、経済情勢の概要について評価者が感じたことを明らかにしておきたい。
(1) エクアドルと日本との関係は良好であり、今後の発展が期待できる。これまでのエクアドルと日本の関係は、日系人が多いブラジル、ペルーおよびメキシコほど緊密ではなかった。しかし、近年エクアドルにおいてもアジア・太平洋地域への関心が芽生えつつあり、経済大国としての日本の地位を認識し、日本との関係強化に大きな関心を抱き始めてきている。本年7月に作成されたエクアドルの長期戦略策定のための作業文書である「エクアドル2025」においても、第1にアンデス・グループヘの積極的参加、第2にMercosurとの統合、およびこれらをベースとして米州自由貿易地域への対応準備をめざすとともに、アジア・太平洋諸国への接近の必要性が調われている。
今後の両国関係の方向として、食糧、エネルギーおよび資源という視点から、太平洋に面したエクアドルを再評価すべきではないかと考える。
(2) エクアドルの政治は、調査時点においてはかなり難しい情況にあると認識される。その象徴的な事象は、本年2月に暫定大統領が誕生し、その任期は来年の8月までであることである。ただし、暫定大統領誕生の過程で、最悪の事態が生じなかった点において、エクアドル社会がそれなりに成熟しつつあるとも感じた。最近における政権の推移は以下の通りである。
1992年8月~96年8月 ドゥラン・バジェン大統領(任期4年・現行憲法上再選禁止)
1996年8月~97年2月 ブカラン大統領(国会により解任)
1997年2月~98年8月 アラルコン暫定大統領
(3) エクアドルの現在の経済情勢に関し、前述の「エクアドル2025」から要点を拾い出すと以下の通りである。
エクアドルの経済安定・調整計画は、マクロ経済の大きな不均衡を克服することにあり、その基本的な課題はインフレの収束と財政の均衡にあった。かかる政策の結果として、物価の上昇が止まったことは重要であるが、公的財政の均衡は回復せず、経済成長は伸び悩み、貧困層の困窮度が増し、国民の生活水準は悪化した。
1996年の国内総生産の伸び率は2%台で、人口の伸び以下であった。一人当たり国内総生産は1,600ドルで、これはマイナス0.1%の伸びに相当し、最近の7年間で最低の水準であった。
1997年については、政治的な安定および多くの投資プロジェクトが実行されることにより、3.3%の成長が予想される。この基調は1998年においても継続されようが、物価はほぼ30%の上昇、為替は21%程度の切り下げがあるものと見込まれる。金利、為替およびインフレヘの圧力を回避するため、預金準備率は1997年4月1日より2%引き上げられ、12%となった。粗固定資本形成は1996年においてマイナス1.8%であったが、1997年においては約5%になるものと見込まれている。とくに、石油部門に対する投資が増大した。
また、家計の消費性向は賃金の調整があったため、2.7%増が見込まれ、政府部門の消費は0.2%増が見込まれている。財政収支の赤字は国内総生産比4.7%で、9億7,870万ドルである。ただし、本年6月12日に採用された措置により本年末の目標値は国内総生産比2.7%とされている。こうした財政収支の悪化により失業問題が先鋭化し、1996年の失業率は10.4%、潜在的失業率は43.4%であった。1997年5月の世帯当たりの基礎生計費は160万スクレで、収入は93.6万スクレしかない状況にある。
対外面においては、輸入が民間部門の活動が活発化しているため10.1%増となり、他方輸出は1996年の3.6%増の勢いが継続しており、その大半の理由は非伝統的な工業製品および石油の輸出増にある。経常収支の赤字額は6億5,400万ドル、資本収支の黒字額は8億4,900万ドルで、1997年末の外貨準備高は1996年末の水準をこえる18億3,200万ドルに達しよう。
2. こうした政治・経済情勢は、今後も時間を要するカタラマ川流域灌漸計画に影響を与える可能性もある。既に終了している電気通信プロジェクトでは、プロジェクトの評価とは直接の関係はないが、EMETELの総裁は自社の年報が発行されていることを知らず、また真先の話題が電気通信との関係が不明な見本市展示会場の建設プロジェクトであったりし、自己の責務に関して、自覚がなさそうであった。また、CONADEの長官代行は何でも良いから実績を挙げようとの態度であった。さらに、EMETELの入札問題においても、自己の政権の下で片付けておくという性急さもあるように見受けた。これらはいずれも、政権の暫定性を色濃く暗示しているといえる。
しかし、進行中のカタラマ川流域灌概計画およびキト市南部上水道施設整備計画においては、プロジェクト自体を担っているエクアドルの関係者の士気は必ずしも落ちていないと感じた。なお、現地の日本大使館は、プロジェクトを成功させようとする立場から、こうしたエクアドル側の対応に対して、忍耐強く自助努力を引きだす方向に誘導されていた。
3. 日程のうち、エクアドル政府関係者、UNDP、スペイン大使館関係者、アンデスの声/邦人関係者については、個々のプロジェクトの評価に必ずしも直接関係しない面もあるが、プロジェクト実施の上での環境として重要な意味を持つと思われるので、ここで簡単に面談内容をまとめておきたい。
(1)エクアドル政府関係者(直接のプロジェクト関係者は除く)
(イ)外務省経済協力局局長代理
多くの国から援助を受けているが、日本からの援助は重要な位置を占めている。(当方から触れない内に)透明性が重要である(と強調)。援助受け入れの窓口として、日本大使館と良く連絡を取っている。賃金は大蔵省の公的債務局、事業の詳細は各省、そして連絡の窓口・協定の作成は自分のところであるが、プロジェクトの状況については注視し、大臣を通じて大統領に意見を具申している。なお、官民の関係については、以前は官がすべてをやろうとしていたが、現在では民営化の時代で、民間との関係を大事にしており、うまくいっている。
(ロ) 大蔵省公的債務局長
EMETELは民営化の方向にある(事実、8月12日に訪問したが、その日の夜の国会にて民営化のための法案が可決された)。灌漑事業に関連して、当方から受益者負担の原則について質問したところ、目下それは考えていない、との回答があった。また、農民からの税金について質問したところ、これについても目下は期待していない、とのことであった。
(ハ) 国家開発審議会(CONADE)長官代行
開発プロジェクトについては、当然ながら優先順位をつけて選択する。選定は大統領、中銀総裁、CONADE長官および大蔵大臣による。EMETELの株式の35%を年末までに売却する予定で、残りの55%は政府、10%は労働組合がそれぞれ保有することとなる。
カタラマ川流域灌漑計画の問題点は土地の収用にある。なお、債務に関連して、ベルギー、スイスおよびドイツは一部を放棄しており、日本については金利を低減してくれれば有り難いが、いずれにしても日本の援助に大いに期待している。
(同代行との面談においてはJICA派遣専門家が同席した。なお、「エクアドル2025」は同専門家より入手した。)
(2) UNDP臨時代表
中央政府の組織に頼らず、即ちエクアドル政府と結びつかず、地方自治体と提携して、事業を展開している。そして、支援対象プロジェクトとして、保健、衛生的なものを選択している(これも一つの考え方であると感じた)。
(3) 在エクアドルスペイン大使館公使
エクアドルについて指摘したいことは、第1が貧富の差が大きいこと、第2が収賄の構造があること、第3が法的な枠組みが未整備であること、第4がエクアドル側の自助努力を望むことの4点である(この最後の点については自助努力を実現する上での基盤が弱く、開発独裁もやむをえないとの日本側関係者の意見もあった)。
なお、第3の指摘に関連して、日本側の消息通より、スペインの投資家が太平洋側のエスメラルダスに土地を購入し、事業をしょうとしたところ、別の地主が現れ、裁判となり、結局敗訴となり、撤退したとの話を聞いていたので、同じスペイン語の人で、文化・習慣も似ている人が敗退するようでは、法的にみて相当に難しい国情にあると感じた。
(4) アンデスの声/邦人関係者
(イ) アンデスの声の概要
昭和6年に設置された、キトからの短波放送(キトが中心の世界地図)である。南米の日系社会に向けた日本語の発信センター(日本語放送の開始は昭和39年)リスナーと手紙のやり取りを通じ、南米に生きる日系人一人ひとりを励まし続ける。青年海外協力隊隊員もリスナーである。
(ロ) 援助に関し日本政府に望むこと
日本週間というイベントよりも常置的な文化センターが望ましい。
日本語を学習したい人がいるし、日本人学校もないので、日本語センターが必要ではないか。
(ハ) 援助ということ
与える、与えられるという関係だけではいけない。
どんなに小さくとも与えられた者が与えられる側にまわるサイクルを考えるべきである。
心が通ずるようにしなければならない(金額ではない)。
本当のニーズを探すべきだ。
過去にアメリカ等に搾取されてきたので、今、援助してもらうことが当たり前との考えがあり、家庭で親からこの考えを教えられている。
(ニ) エクアドルの最近よくなった点、悪くなった点
よくなった点は、自分達でやらなくてはならぬとの意識が出てきたことであり、悪くなった点は犯罪が増加していることである。
4. キトおよびグアヤキルの2都市において、それぞれ1回、JICA派遣専門家および青年海外協力隊の人たちと懇談する機会があり、その活動ぶりについて承知できたことは、たまたま「協力隊を育てる会」の理事を仰せつかっている身にとり有益な機会となった。
また、エクアドルの経済人であるキト商業会議所の幹部と面談する機会があた。残念ながら、たまたま先方は日本については関心を有していたが、日本の援助について何も知らなく、そうした面からPRの不足とその必要性を感じた。
[個別案件の評価]
1 電気通信網拡充事業
本プロジェクトは、1985年1月にF/Sが完成し、88年2月にL/Aが締結され、93年10月に事業が終了した案件である。その後、95年10月に通信特別法が成立し、株式の35%が国際入札にて売却され、民営化されることとなった。ただし、評価時点である97年8月においては入札は実施されていない。このように、本プロジェクトは計画から事業の終了までに多くの年月が経過し、かつ評価時点も事業の終了からかなり日時を経過していること、および計画の受け皿の体制も変わることを最初に述べておきたい。
計画が構想された時点におけるエクアドルは、中南米の中でも電話の普及が遅れており(1983年末の100人当たり電話機数は3.2台)、その改善は同国の経済・社会の発展にとり急務であった。そのため、エクアドル電気通信公社は、電気通信基礎設備と各種サービスの拡張および改善を目的とした電気通信拡充4カ年計画(85~88年)を策定し、同計画に基づき経済的有利性の高いデジタル交換機の導入(30万回線)および伝送路網の整備などを図ることとした(計画における電話普及率の達成目標は、全国レベルでは100人当たり3.8台)本プロジェクトは同計画の一環として実施されたものであり、これにより1988年末までに回線数は既存の59,950回線から128,900回線へと容量が倍増することが見込まれた。
ところで、本プロジェクトにおいて多くの年月を経過した要因は、1つには1987年3月の地震により経済情勢の悪化がもたらされ、円借款の返済の遅れが発生し、L/Aの調印が遅延したこと、2つにはコンサルタント契約に関し政権の交代(88年)により見直しとなり締結が遅れたこと、などがあった。さらに、92年8月、エクアドル電気通信公社は通信監督局とエクアドル電気通信会社とに分離された。
前述のように1995年10月、通信特別改正法が成立し、民営化に向かうこととなったが、96年は大統領選挙、政権交代で忙しく、97年2月に大統領の罷免という事態が生じ、アラルコン暫定大統領の下で97年8月、電気通信にかんする特別法の改革法案が議会を通過し、同年10月半ばに民営化のための国際入札が実施されることとなった。
結局、事業が長期化する中で、円高および技術革新に伴うデジタル交換機の価格低下等により、当初予定の機器部分予算73億円に対し、実質は33億円で事業は終了した。
エクアドルの100人当たりの電話機普及台数は、1988年末に対する計画数値は3.8台であったが、95年末についてはエクアドル電気通信会社の95年版年報によれば、6.1台となっている。なお、94年末では6台弱とされており、同時期のペルーは3.31台であった(中南米の平均は8.4台)。エクアドル、とくにキトの電話はかかりにくく、混線が生じがちである。また、公衆電話の設置も極めて少なく、町に「電話貸します(Prestamos Telefono)」の看板がかかっている。公衆電話は1通話1,000スクレであるが、これは1,500スクレである。
20代後半の女性技術者によると、日本製の機器は合理的で、故障した回線を特定することが非常に容易であるという。また、日本の技術協力は教育・訓練、機器の据え付け、実習および保証にあり、機器およびサービスともに非常に良いと話していた。通信監督局の長官の評価は、(1)日本は友人であり、日本の技術を知っておきたいので、今後とも日本の技術協力を受けたい、(2)日本の機器およびサービスは良いが、コンサルの内容が複雑で、時間がかかる、という点にあった。
日本製の電気通信機器のエクアドルにおけるシェアは10数%といわれているが、その評判は良い。民営化される中で、日本が行える国際貢献の具体的な手段ないし協力対象として引き続き電気通信機器を活かしていく方策を探求すべきであると感じた。また、電気通信に関する日本の技術協力についても評判は良く、期待もされている。機器と関連付け、手続きを簡素化して技術協力を継続していくべきであると考える。他の地域において、あるいは長年の経験から案件として、対象として良いと評価の決まったものにてついては、おそらくマニュアル化もされ、審査も早いのであろうが、さらに決定を早める努力が必要であると思う。結局、円借にしろ、技術協力にしろ、審査・決定のための時間を短縮することが、コストの削減にもつながるのではないだろうか。
2 カタラマ川流域灌漸事業
本プロジェクトは1982年7月にF/Sが完成し、前述の電気通信網拡充事業と同じ88年2月にL/Aが締結され、96年5月より工事が実施され、97年8月時点では進捗率10%程度で、これから工事がたけなわになる案件である。
本プロジェクトが構想されたのは、エクアドルが当時、米などの農産物を輸入に依存しており、都市化の進展や食生活の改善による食料需要の増大に対応した自給力の強化が課題となっていたことにあった。他方、対象地区を含むグアヤス川流域は南米の中でも肥沃な土壌を有しているといわれるものの、乾期(5~11月)における土壌水分不足と雨期における堪水被害が同地域の農業生産の増大と農業生産性の向上を妨げる大きな要因となっており、全流域の中の一部であるカタラマ川流域の灌漑と排水改良を実施して耕作面積の拡大と米、大豆、とうもろこし等の増産を図り、農家所得の確保と地域経済の発展に資することを目的とした。
プロジェクト・サイトヘの道程は、エクアドル第一の商業都市で、港湾都市であるGUAYAQUILからサイトに最も近い町VENTANASまで約120キロメートル、車で約2時間の距離で、その町から車で約20分である。この間、一望の平野で、高低差70メートルといわれている。民家は高床が殆どであった。道路は片側一車線であったが、状態は比較的良かった。サイトヘの途上およびサイトで一番目についたものはバナナ農園であった。ノボアの他、米系のDOLEもみられた。他の作物としては米、大豆、カカオ、ともろこしがみられた。
ところで、本プロジェクトにおいてもF/Sが完成してから工事が実施になるまでに多くの時間が費やされている。F/Sは電気通信網拡充事業よりも2年半前の1982年7月に完成したが、その後同拡充事業とほぼ同じ経過をたどり、一緒に88年2月にL/A締結となった。その後、本件においては、(1)政権交代に伴う実施機関の長の交代、新政権の下での前政権の事業の見直し等があったこと、(2)工事業者にかかわる入札において現地ローカル業者とブラジル業者との競争が裁判となり、この裁判で1年間を要したこと、などがあり、前述のように工事開始は96年5月であった。
工事の概要は土工事90%、コンフリートエ事(ポンプ場、サイフォン、橋など)10%である。工事自体はそれ程難しくはないようであるが、冒頭述べたように、進捗度は10%程度と余り進んでいない。その要因として、1997年はEl nino現象による予想外の降雨で思うように工事が進まず、また97年3月、豪雨のため建設中のポンプ場でダムが決壊し、ポンプ場が冠水したことが挙げられる。なお、工事に関連して、前述の通り競争入札では現地のローカル企業が落札したと述べたが、その過程で工期を30ヵ月と見積もった経緯があること記しておきたい。
もう1つの問題点は土地収用の遅れである(処理すべき案件が500件あるとされ、1997年8月の時点でその内の300件が処理され、やっと目処がついたと現地当局はみている)。これは埋め返すので、収用マターではないが、サイトにはバナナ農園が多数あり、その1つのノボアの農薬散布用の飛行場が工事にひっかかり、散布しない時期に掘り返し、管を埋めて元に戻すという制約があった。なお、バナナ農園は運河は利用しないが、排水路は利用するとのことである。従って、農薬の残留分が流出することに注意が必要である。中央の国家開発審議会のValencia長官代行は、降雨の工事への影響よりも、むしろ土地収用の遅れを懸念していた。
サイトの農民の反応は、洪水対策と乾期対策の両方に有効であり、完工すれば収量は3倍になると期待している。しかし、何時になったら完成するのかという気持ちも生じており、日本の援助という理解は一般的には浸透していない。ただし、上層の農民は知っている。サイトの町に入る直前に日の丸の入った看板が1つだけ目についた(看板を多く立てると不慮の事故も生じかねないので自粛しているとのことであった)。ただし、収量3倍増は、運河も1年に1ヵ月は掃除が必要で、そうはいかないとのことである。
本プロジェクトの実施母体であるグアヤス川流域開発公社(CEDEGE)の現地首脳は、これまでこの地域において、本プロジェクトも含めて4つの灌漑事業を実施してきたが、資金不足により水路に草が茂り、用水路の管理がうまくいっていないので、本プロジェクトについては竣工後1年間程度はCEDEGEで管理し、2~3年目からは会社組織で対応したいと述べていた。こうした点に関連してAndrade大蔵省公的債務局長は受益者負担とか農民からの税金ということは考えていないと述べていた。先のことではあるが、サイトの貧農からの税金は無理としても、CEDEGEのいうように会社組織で対応する上で、収量の上がった分のいくらかは管理費用として徴収しないと、それこそ水路に草が茂ってしまう訳で、今からそういう思想を普及すべきであると感じた。
上の思想の普及に関連して、先のことであるが、単位当たりの収入が向上する作物を研究する試験場を設置したらどうかと考える。理想論であろうが、受益者の支払い能力も向上する。翻って、本プロジェクトの構想が生まれたのは、わが国の大規模な農業協力であるブラジルのセラード開発構想に遅れること僅か7~8年の80年であることを指摘したい。しかし、その進展度合いはずっと遅い。ここで、セラード開発を持ち出すのは唐突のそしりを受けかねないかもしれないが、見ることはなしにCEDEGEの現地首脳の机の上をみたら、なんとセラード開発公社CPAの書類がのっていたことを付け加え、そのそしりを免れたい。要するに、灌漑事業の先に、作物試験場なり、生産会社などの設置・設立を今から用意し、成果を拡充していく方途を研究しておくべきである。
「エクアドル2025」によれば、2025年のエクアドルの人口は、現在の倍の2,200万人となり、太平洋岸は60%と見込んでいる。単純に計算して1,320万人である。現在の人口は1,200万人で太平洋側は40%で、同じく単純に計算して480万人である。840万人が増える。農業部門で吸収すべき部分も相当に大きい筈である。逆に、太平洋側では日本、中国、ASEAN諸国がある。21世紀におけるこれらの諸国の食糧事情については楽観論、悲観論さまざまあるが、例えば中国についていえば、少なくとも工業化・宅地化による農地および農業労働者の減少と所得向上による動物性蛋白質への移行による穀物需要の増大(鶏1キログラムは穀物2キログラム、豚1キログラムは穀物4キログラム)は極めて蓋然性が高く、中国がどの程度国内でこれを処理するか注目される。日本についても程度の差こそあれ、こうしたことは生ずるであろうし、また中国その他の影響を受ける可能性がある。今からこそ、エクアドルの農業開発に協力することを検討すべきである。
なお、カタラマ川流域はグアヤス川流域という全体の中の一部であり、そのカタラマ川流域の一部において日本の円借款事業が対象としている面積は6,450ヘクタールである。因みにグアヤス川流域全体は362万ヘクタールの広さを有している。さらにいえば、太平洋岸としては、このグアヤス川流域の他、エスメラルダス川流域があり、その面積は212万ヘクタールである。当然、その地形はすべてが距離120キロメートルで、高低差70メートルという訳ではないし、すべてにおいて灌漑が必要という訳でもないであろう。すでに農地として有効に活用されているところもあるであろう。しかし、840万人が、自国のみならず他国のために、そして日本の農業技術を活用して働ける農地が太平洋岸にあるといえよう。
3 キト市南部上水施設整備計画
本プロジェクトは、1994年6月、エクアドル政府がキト市南部の未給水地区への水道水供給および既存給水区域の出水不良解消を目的とした「キト市南部上水施設整備計画」を策定し、この計画実施のための導水施設などの建設、改修および資機材の購入に必要な資金につき、日本政府の無償資金協力を要請してきたことに端を発している。なお、エクアドル政府の計画作成に先立つ1996年5月、米州開発銀行(IDB)の援助により、「既設および建設中の水供給システム報告書(現在、キト市の水道に関しての上位計画書)」が作成され、これらの未給水地区の問題解決のため、「既設のジョア系統の湧水を表流水と分離して管路により導水し、配水池で滅菌することにより、良質で、低コストの飲料水を未給水地区(キト市南西部高台地区)に供給する」という提案がなされた経緯がある。
無償資金協力が担当する本計画は「キト市南部上水施設整備計画」の一部についてであり、他はキト市上下水道公社(EMAAP-Q)が自己資金で実施している。
本プロジェクトは、改めて言うまでもなく、人口増加率が高い(過去10年間、年間約3%)首都のキト市およびその周辺において、社会問題となっている水不足対策である。人口の39%が住む北部地域は、2000年の需要に見合った処理能力が確保され、配水網の整備も進められている。しかし、人口の46%、約65万人が住む南部地域のうち、特に高台住居地区(主に低所得者層18万人居住)では給水設備の整備の立ち後れ、給水車による配水や浅井戸を利用した不便な日常生活(使用水量1人当たり20~30リッター/日)を余儀なくされている。このような状況のため、同地区では水を原因とする疾病が多く、乳幼児の死亡率が1,000人当たり82人と他地区より高いという報告があり、衛生的な飲料水の安定供給のための給水施設の整備が急務となっている。
本プロジェクトは、無償資金協力の要請(1994年6月)から、事前調査団の派遣、基本設計・実施設計の完了、入札そして着工(96年12月)までの間の時間は比較的短く、スムーズに進んだと言えよう。工事も技術的には大きな問題もなく、順調に進捗している。キト市上下水道公社(EMAAP-Q)の総裁も日本の技術力を評価していた。同総裁によれば、キト市における未給水地域は10%であり、この10%は南西部のジョア地区および北西部である。上水は衛生上も重要であり、こうしたところの未給水地域を早急に給水化していくことは望ましい。本件はその一部を給水化したものであり、さらに、下水はどうかという点が気にかかる所であり、これへの協力も必要である。同総裁は、未給水地域が残っているいるところがら、引き続き日本の支援を期待している。有償でも良いから日本の技術と資金の協力を得たいということになるかどうか。それには、公社側からみた価格、品質および納期に対応しているかという点が重要になろう。
品質という点でひとつ気が付いたことは、埋設する鋼管の耐用年数は50年であるとされており、日本人の現場の人々は鋼管自体は大丈夫であるが、そこを流れる水との相性の問題もあり、適切なメインテナンスを要すると述べており、こうした面での教育も必要である。なお、鋼管の溶接には8名の専任を選び、良く教育した上で作業をさせているとのことであった。
また、本プロジェクトの仕様単位の問題であるが、エクアドル側はインチを譲らなかった。世界的にみても多く採用されているメートル、即ち日本仕様をPRし、それを採用した方が設計、施工上も良いと思う。
日本側工事とエクアドル側工事の区分にかかわる問題も気にかかった。即ち日本側が上流を担当しているため、エクアドル国民には目につかない。PRが必要であろう。また、下流はエクアドル側が担当しているが、果たして工事を同時並行的に実施できるのか、という問題である。同時に完工しなければ、効果が遅れるし、一方が、資金面等の理由で工事が中止にでもなったら、元も子もないので、この点は十分注意する必要があろう。本件においては、幸いにも現地側も熱心で、例えばポンプ場用の高圧電線の電柱も近くまで工事されている。なお、ポンプ場は建屋がようやく姿をみせたところである。総裁の説明では、日本側の工事は1998年2月までに完工するであろうし、公社側の工事は同年の3月までに完了するとしている。
[今後の対エクアドル経済協力への若干のコメント]
最後に、今後の対エクアドル経済協力に関し、若干コメントしたい。
- エクアドルという一国に対し、少ない資源を如何に有効に活用するか戦略性が求められている。両国のニーズ、プロジェクトを通ずる両国の相互理解の増進など、いろいろの目標がある。逆に、大使館員は少ない。戦略的な案件の発掘のためには、官民の連携、複数の専門家の協力が不可欠である。必ずしも、館員を増員しなくとも短期あるいは巡回の形で対応するのも一つの方法である。
- エクアドルの発展の余地は大きい。石油の確認埋蔵量はそれ程多くはないが、こうした石油および食糧増産の余地が大きいこと等を考えると、日本ばかりでなく、アジアにおける将来のエネルギーおよび食糧問題をにらみ、ペルーと領土問題があるにせよ、経済協力の対象国として、エクアドルが太平洋岸にあることにもっと着目して良い。
- 協力分野のひとつとして、自然保護がある。エクアドル北部に2万haの広大なマングローブ域があり、その南端の原生林は生態系が豊かだと言われている。地球規模でマングローブ林破壊が進む現在、その保全に日本が協力することも意義あるものであろう。これは、観光資源として活用され、同国の発展にも寄与しよう。

