4.西アフリカの漁業振興(セネガル・モーリタニア)
(現地調査期間:1997年10月25日~11月9日)
- 龍谷大学経済学部教授 大林 稔
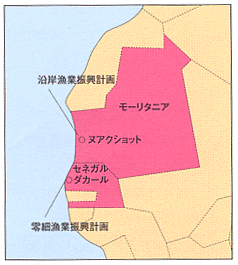
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの内容 |
|
零細漁業振興計画 (セネガル) |
無償資金協力 |
93年度、 1.62億円 |
セネガルの零細な漁業を近代化し、漁獲量を増大させるため、日本の無償資金協力により、小型漁船、漁具などの漁業用機材を調達する。 |
|
沿岸漁業振興計画 (モーリタニア) |
無償資金協力 |
91年度、 3.58億円、 93年度、 5.50億円 |
モーリタニアの沿岸漁業を近代化し、漁獲量を増大させるため、日本の無償資金協力により、小型漁船、漁具などの漁業用機材を調達する。 |
はじめに
本評価のための現地調査はセネガル、モーリタニア両国において1997年10月25日から11月9日、日本発から帰着まで全行程15日間で実施された。外務省制作の「有識者評価マニュアル(1996)」によれば、有識者評価とは事後評価の一形態であり、個別プロジェクトの評価を行うと同時に、政策レベルでの教訓と提言を求めるものである。また客観性・中立性・有識者の専門性がいかされることが求められている。さらに評価視点が独自性に富んでいることが特色であるとも述べられている。筆者も以上の要求に応えるように心がけた。全体を通して「独自性」のある評価となっていることを願う。
本評価では、プロジェクトの執行状況の詳細な評価は行わなかった。すでに通常の評価がJICAおよび外務省によって実施済みであり、重複は避けるべきだと考えたからである。またプロジェクトの社会経済的な影響評価も行わなかった。短時間の調査では実施不可能であること、基礎となるべきプロジェクト執行前の調査が行われていないことの2点が理由である。しかし資機材の運用が適切に行われ、プロジェクト業務が円滑に進行していることは確認できた。とりわけ現地専門家の努力には頭の下がる思いであった。
本評価は、より術臓的であるよう試みた。すなわち大局的に見たプロジェクト目標の達成状況、達成状況とプロジェクト環境(自然的・制度的)との関係に焦点を置いた。こうした点はプロジェクトサイクルに組み込まれた通常の評価では、必ずしも重視されない。本評価の独自性は、おそらくここに見出されるであろう。
ミシラ漁業センターの現地調査には、セネガル人コンサルタントの参加をえた。その報告は本報告書に取り入れると同時に、本論の補遺として添付したので参照していただきたい。評価にかぎらず全ての経済協力関連の調査は、相手国への技術協力の一環である。全ての調査団は現地の人々との協動で行われ、その成果は必ず両国に提供されるべきものであると筆者は信じている。セネガルにおける現地コンサルタントの参加も、こうした方向へのささやかな試みであった。今後、アフリカ人とのパートナーシップが制度化されることを望む。
1 セネガルの漁業
(1) セネガルの経済と国際協力
(イ) 人口および経済動向
セネガルは面積196,722平方キロメートルで、サヘル地域に位置し、西アフリカ海岸に面する。環境面では砂漠化の進行と土壌の侵食が深刻な問題となっている。
人口は880万人で、1960年の独立以来年率3%で急成長している。都市化率は42%(1995)と、アフリカでは高水準にある。一人当たり所得は600ドル(1995)でセネガルは低所得国グループに属する。1965~90年の一人当たり成長率は年平均0.6%のマイナスであった。1995年の経済構造(GDP配分)は農業20%工業18%製造業12%サービス62%となっている。なお工業化率は80年代に低下した。一方、1990年の雇用構造を見ると、農業のシェアが76%に達しているのに工業は7%にすぎず、雇用と生産の構成のずれが目立つ。
他のアフリカ諸国同様、セネガルも対外債務の累積に苦しんでいる。セネガルの債務問題の特徴は、繰り延べの困難な多国間債務の債務総額における比率が48%(1995)と、アフリカ平均の2倍に達していることである。なお、セネガルはアフリカでも一人当たり援助受取額がもっとも高いグループに属し、援助の対GNP比は17.2%(1994)に達している。
セネガルは80年代から構造調整に取り組んできたが、1994年1月のCFAフランの切り下げにより、ようやくその効果が表れてきた。1995年4.8%、1996年5.6%と久方ぶりにGDP成長率が人口増加率を上回り、1997年も4.7%の成長を維持する見込みである。構造改革が進展すれば、今後も成長が持続することが期待される。
(口) 日本の協力
セネガルはアフリカにおける第5番目の援助受け取り国であり(DAC1997)、非英語圏では突出した受益国である。日本の1994年の対セネガル援助供与額は6.1万ドルで、フランス(11.5万ドル)、クウェート(11.1万ドル)に次いで二国間援助第三位の額となった。日本の援助はセネガルが受け取った総援助総額の11分の1、二国間援助総額の7分の1にあたる(UNDP、1996)。
日本の対セネガル協力の中心は無償資金協力で、1976~1996年度の累計額の約70%を占める。同期間における漁業関連案件の無償における割合は7.8%である。ただし1990年以降は大規模な漁業案件がなく、無償におけるシェアは12.9%(1976~90)から1.4%(1991~96)へと低下している。
これまでの漁業関連案件は以下の通りである。
| 年度 | 無償資金協力水産案件 | 億円 |
| 1976 | 漁業振興計画 | 3.5 |
| 1978 | 漁業開発計画 | 5 |
| 1981 | 水産物冷蔵流通計画 | 6 |
| 1983 | 漁業海洋調査船建造計画 | 6.4 |
| 1985 | 沿岸漁業振興計画 | 4.08 |
| 1987 | 零細漁業振興計画 | 7.71 |
| 1989 | ダカール中央卸売魚市場建設計画 | 12.05 |
| 1992 | 沿岸漁業振興計画 | 2.34 |
| 1993 | 零細漁業振興計画 | 1.62 |
| 48.7 | ||
(2) 漁業と漁業資源の現状
(イ) 漁業生産の動向と構成:優勢な零細漁業
海洋漁業はセネガル経済の主要生産部門の一つとなっている。水産物は最大の輸出品目であり、漁業はGDPの約11%を占めている。他方漁業が雇用全体に占める割合は5.9%である。
セネガル漁業の中心は零細漁業であり、65%前後のシェアを保っている。漁獲量が頭打ちであるにもかかわらず、零細漁業の漁民数は増加を続けており、また発動機付きカヌーの数はさらに高率で増加している。好漁に恵まれた1992年、1996年を除けば、ここ数年間の漁獲量はほぼ40万トン強で推移しており、92年・96年には45万トンを超えている。
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1996/1991 | |
| 零細漁業 | 283,706.8 | 285,778 | 266,954 | 282,799.2 | 266,346 | 327,894.1 | 116% |
| 大型船 | 89,041.7 | 807,583 | 79,458.5 | 82,043.2 | 92,310 | 88,788 | 100% |
| 外国船(陸揚げせず) | 49,483 | 90,438.5 | 70,626 | 73,074 | 50,312 | 49,188 | 99% |
| 計 | 422,231.5 | 456,974.8 | 417,038.5 | 437,916.4 | 408,968 | 465,870.1 | 110% |
| 零細漁業のシェア | 67% | 63% | 64% | 65% | 65% | 70% | |
| Ministere de la peche et des transports maritimes | |||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1996/1991 | |
| 発動機付きカヌー | 6,979 | 7,072 | 7,281 | 6,674 | 8,716 | 9,348 | 134% |
| 帆走カヌー | 3,921 | 3,552 | 3,652 | 3,058 | 1,535 | 2,288 | 58% |
| 漁民 | 48,914 | 49,007 | 49,138 | 52,498 | 51,734 | 57,067 | 117% |
| Ministere de la peche et des transports maritimes | |||||||
(口) 危機に瀕する漁業資源
セネガルの漁業資源は、近年減少している。
| 大型漁業 | 零細漁業 | 計 | 資源量推定 | |
| 沿海表層魚 | 46,162 | 208,282 | 254,444 | 173,000~248,000 |
| 18% | 82% | 100% | ||
| 沿海底層魚 | 35,132 | 57,462 | 92,594 | 125,000~130,000 |
| 38% | 62% | 100% | ||
| 深海魚 | 35,881 | 0 | 35,881 | 25,000~30,000 |
| 100% | 100% | |||
| Ministere de la peche et des transports maritimes | ||||
(ハ) 漁業政策
調査時点では、資源管理の強化を目指して、当局が漁業法の改訂とその実施のための行動計画を準備中であった。行動計画の準備の中で零細漁業への規制導入は重要な役割をあたえられていた。行動計画の中心は各漁区毎に漁業許可証を発行することであり、これによって資源の保護を達成しようとしている。零細漁業に対する規制と行動計画の策定のために、関係者による全国諮問委員会の組織化も予定されていた。
ただし資源の保護のためには、法改正と行動計画の策定に加えて、法を施行し、計画を実施する政治的意思と人的・物的資源および制度的能力が必要である。しかし主要ドナーからは、セネガル政府の政治的意思不足を懸念する声が上がっていた。また分散的な零細漁業への規制には、制度的な能力も十分ではないため、外部からの支援が必要と見られている。
(二) 水産資源の地域管理
セネガルの水産資源は、ギニア湾の大陸棚資源と大西洋を回遊する資源からなる、各国にまたがる共有資源である。こうした共有資源の管理には、関連諸国間の協力が不可欠である。このため漁業政策の調整と資源管理における協力を目指して、漁業資源を共有する6カ国(カーボ・ヴェルデ、ギニア・ビサウ、ガンビア、ギニア、モーリタニア、セネガル)は地域漁業委員会Sub-Regional Fisheries Commission(SRFC)を組織している。これら6カ国は1997年3月に第一回円卓会議を開催した。しかし、委員会自体の資金不足がその活動を制約している。
日本は地域漁業委員会の活動に対する支援はおこなっておらず(FAO,EUが支援)、円卓会議には他の主要ドナーがすべて出席したにもかかわらず、日本は代表を送っていない。
2 セネガル零細漁業振興計画1987年度,1993年度
(1) プロジェクトの概要
(イ) プロジェクトの対象地域と沿革
ミシラ村はセネガル南西部ファティック州に属し、首都ダカールの南東約210キロメートルにある州都ファティックから南に約60キロメートルに位置する大西洋に望む漁村である。同村に水揚げされる漁獲量は全国漁獲量の0.45%である(1991年)。1988年計画当時、ミシラ村の状況は概略次のようであった。人口は約1300人、電気、水道、通信等は未整備で、幹線へのアクセス道路は未整備で雨期には通行に支障をきたした。飲料水は塩分が多く含まれる浅井戸に依存していた。1980年以来漁業の発展がみられ、周辺サルーン諸島の漁船や、移動ピローグ漁船の集積及び補給基地としても利用されていた。
本計画はミシラに漁業支援のためのセンターを建設し、セネガル南部の漁業拠点の一つとすることを目指したものであった。日本は1987年度計画によってセンターの建設のため資金協力を行い、またその運営のための機材供与と技術協力を実施した。1993年度計画ではセンターの老朽設備の修理改善と漁業機材の新規購入を行い、技術協力を継続した。
(口) 1988年計画の概要
- (a) 目的
- (i) 漁業センター建設による産物流通網の改善
- (ii) 漁具資材・試験機材導入による零細漁業生産の増加と生産物の品質向上
- (iii) 地域の経済開発と漁民の生活水準改善
- (iv) 国民への動物性蛋白の供給増加
- (b) 協力内容
- 施設建設:
- 管理棟、ワークショップ、網修理場、薫製棟・乾燥場、製氷施設棟、桟橋、道路・橋梁
- 機材供与:
- 製氷機(2)、冷蔵庫(2)、発電機(4)、ピックアップ(1)、保冷車(1)、ワークショップ機材、貯氷コンテナ1トン(5)、加工機材、漁具、試験船(6)他
- 関連技術協力:
- 専門家(2)、協力隊(1)
- (c) その他
- 交換公文締結日:
- 1988年4月22日
- 供与額:
- 7.71億円
- 引き渡し日:
- 1989年3月
- 先方関係機関:
- 漁業海運省
- 資金形態:
- 無償
(ハ) 1994年計画の概要
- (a) 目的
- (i) ミシラ漁業センターの施設・設備の維持
- (ii) 地域漁民・加工人等への指導・支援活動の補充・拡充
- (iii)地域の漁業振興
- (b) 協力内容
- 資機材供与:
- 製氷機、発電機用予備品(1)、給水車および貯水タンク(1)、カヌー型FRP漁船(8)、ディーゼル船外機(1)、漁具資材(1)、加工用機器(1)、航海・漁労用器具・安全器具(1)、防熱コンテナー(12)、保冷車(1)
- 関連技術協力:
- 専門家2名、協力隊1名
- (c) その他
- 交換公文締結日:
- 1994年5月26日
- 供与額:
- 1.62億円
- 引き渡し日:
- 1995年3月31日
- 先方関係機関:
- 漁業海運省
- 資金形態:
- 無償
(2) 目標の達成状況
1993年度計画にはセンター支援の全体が明らかになる目標設定がなされていないので、1987年度計画の設定した目的にそってみてゆくこととする。1993年度計画は前計画の目的と戦略を引き継いでおり、評価上問題はないと思われれる。
機材の導入は円滑に、またその利用は適切に行われていることを確認した。
(イ) 目的1. 漁業センター建設によって水産物流通網を改善する
目標とされた民間中心の水産物流通網の改善はあまり進んでおらず、逆にセンター自身の販売額が大きく増加している。1987年度計画は、センターをミシうおよび近辺の漁民のみならず、シンサルーン南部海域での「生産・加工・流通・補給拠点」とすることを目標としている。この目標達成のために民間仲買を介した流通網の確立を目指し、センター自身は民間流通の補完にとどまるべきであるとしている。しかし大・中規模仲買人の参入はみられず、むしろ地域におけるセンターの独自買い付け・出荷の役割が増大している。
流通網改善に関連して、すでに1993年度計画の基本設計調査報告書(以下1993年度計画)は、大・中規模仲買人の参入が進んでいないと指摘している。同計画の分析は、概要次の通りである:
計画策定時点では、大・中規模仲買人が参入する基本条件は整っている。センターがミシラ全体の水揚げ量増加に努力すれば、ミシラは民間の生産・流通拠点となりうる。その結果センターの氷とサービス販売、施設利用費が増加してセンターの経営も好転するはずである。
現実には、大・中規模仲買人の参入の停滞と裏腹に、センターの買い付けが1990年から95年のあいだに85トンから381トンヘと4倍強に増加している。後述するように、ミシラヘの道路は改善され、通信インフラ等も整備されつつあり、仲買人参入の遅れの原因は、インフラ不足以外に求められねばならない。流通網整備はプロジェクトの最大の目標であり、これが依然実現の方向がみえない以上、本格的調査を行うべきであろう。
(口) 目的2. 漁具資材・試験機材導入による零細漁業生産の増加と生産物の品質向上
(a) 生産
ミシラ地区全体の水揚げ量は、プロジェクトの初期に大幅に増加したが、その後は停滞していると推定される。ミシラヘの水揚げ全体が1989年から1992年に50%増加したこと、就業漁民数、船舶数は停滞していたこと(したがって生産増は生産性向上によるものであろう)は確認されているが、その後のデータは収集されていない。ただし1992年の時点では、年間水揚げ量は1988年計画の見通し2,221トンを下回る1,522トンであった。現地での聞き取りによっても、ミシラ全体の水揚げは停滞していると推定される。これは沿海資源全体が減少傾向にあるためと考えられる。
(b) 生産物の品質向上
氷販売量は1990年から1996年の間に約3.5倍となっており、生産物の流通時の品質向上に大きく貢献している。ただし販売量の上昇はセンターの魚買い付け量の増加に起因するものであり、民間流通支援がどの程度強化されたかは明らかでない。
センターでは、日本人専門家の指導により電気炉による薫製とあげかまぼこが試作されている。しかしともに生産費が高いため、製品は高価である。その結果、普及先は在留邦人や高級飲食店等にかぎられており、一般民衆の栄養改善への貢献はあまり期待できない。従って開発中の加工技術は適切と言えない。
民間への技術移転は全く進んでいない。これは狭隘な市場、高額の投資等(機材は高価で輸入品である)から、民間業者が関心を示さないことが原因と考えられる。またセンターの幹部がこの業務を営利事業と考え、潜在的競争相手の民間に技術移転することに熱心でない印象も受けた。
加工技術は、専門家からセンター職員へは移転している。しかし技術移転を受ける職員の在職期間が短いため自立的・永続的な技術維持が保証されているとはいえない。
(c) 訓練・教育、試験機材の利用・漁業情報の提供
センター独自の研修は現在では行われていない。単発セミナーの会場貸しないしは委託セミナーのみである。1991年から95年まで行われた研修では、30人が修了し、うち19人が漁業に従事している。修了者の絶対数は少なく、漁業への定着率も高くはない。専門家によれば、当初計画された研修(非漁民の基礎からの7ヵ月の研修は基本設計書に含まれていなかった)は現地のニーズに適合していなかったため、現在では行われていないという。
漁業情報の調査・提供は十分ではない。試験機材として導入されたFRP船の運行は漁業事業として行われ、試験情報は収集されていない。
伝統的な加工を行う婦人への指導、組織化、信用供与などは成果を上げている。しかし残念ながら、専門家の個人的努力に負うところが多く、センター事業としての取り組みは弱い。このため地区全体の魚の加工技術へ充分な影響を及ぼすまでは至っていない。
(ハ) 目的3. 地域の経済開発と漁民の生活水準改善
ミシラ村の人口は1987年度計画発足時の約2倍の2,600人に増加したと見られている。セネガル政府によれば家屋数は10%の増加にとどまっているが、物品販売や食事を供する店は8から21に増加した(Ministere de la peche et des transports maritimes, 1997b)。これから見るに、センターはミシラ村の規模拡大にかなりの影響を及ぼしたと見ることができる。
村の社会基盤整備は順調に進んでいる。産院と診療所が完成し、学級数は倍増した。また幹線への道路は舗装され、電話が施設された。インフラストラクチャーの整備が進んだ理由は、人口が増加したこと、センターの存在により政治的重要性が増したこと、センターのバックアップがあること(例えば診療所の電気はセンターが供給している)の3点に求められる。
ただし、1987,1993両年度計画は、1987年度段階におけるミシラの総生産の5-10倍にあたる規模の投資であることを忘れてはならない。この相対的に「巨額の」投資の乗数効果は、私見ではあるが村内を視察した印象では、あまり大きくないないように思える。他方、「巨大」な投資は地域の経済・政治関係に多大な影響をあたえていると推測されるが、これについては今日まで調査は行われていない。
(ニ) 目的4. 国民への動物性蛋白の供給増加
すでに述べたように、ミシラの水揚げ量は、プロジェクト発足以来大幅に増加、その後停滞していると見られる。したがって1987年度計画は動物性蛋白の供給を増加させたと考えられる。ただしデータが収集されておらず、量的な計測はできなかったし、この増加分が全国的にみてネットの増加か、他地区からのシフトなのかは判断できなかった。
(3) 漁業センターの運営について
1987年度計画はセンターを「開放型」の施設と位置づけている。それによれば、センターが生産・流通に関与することは最小限にとどめ、「基盤施設や加工場を・・漁民、加工人、仲買人に提供」し、彼らによる生産・流通拡大を支援する。センターは彼らへの援助事業(技術指導、施設提供)にみずからの役割を限定する。民間が提供できない一部サービス(修理、部品と漁具の販売、既存ルートにのらない魚種の流通)は例外的にセンターが実施するとしている。1987年度計画は同時に「センター自身の収益で(その運営を)賄える計画とすることが必要である」と述べている。上記2点は、セネガルが実施し始めていた構造調整政策、具体的には緊縮財政、公的部門の縮小と民間活力の支援という政策にそったものであった。
1993年度計画はこの方針が具体化していないことを指摘し、センターの開放施設型機関への早急な転換と、仲買業務からの撤退、職員数の半減による独立採算達成という劇的な措置を提案している。
以下、開放型施設と財政自立の2点について、調査団の評価を述べる。
(イ) 施設の開放、民間支援
1993年度計画の方針(開放施設型機関への早急な転換、仲買業務からの撤退、職員数の半減)は尊重されていない。センターは発足以来、民間支援施設としてではなく、一貫して生産流通企業の活動の拡張に努めている。これは1987年・1993年度両計画に反した政策である。
センターは自ら船主として漁業経営を行っている。漁民研修はセンターが船主となった漁民の請け負い操業化している。すでに指摘したように、センターは民間流通の補完ではなく、ミシラ最大の流通業者となっている。加工品開発は、技術の普及より製品の独自販売拡大を目指している。資機材の低額販売の売り上げはごくわずかである。修理対象は外部の機材は少なく、ほとんどセンター所有の機材である。氷販売も大半がセンター関連の水産物に使用されている。訓練、普及の規模は限定されている。一般漁民への情報提供は不活発である。さらに近年は生産拡大のために木造船を購入、他方、雑貨・食糧の小売りにまで手を広げている。雇用人員も増加している。1990年、1994年と1996年を比較すると、公務員を含む常雇は14名、24名から36名へ、臨時雇いの労働日は514日から2064日、2265日と増加している。こうしてセンターは小さな村では巨大な事業体となりつつある。
(口) 「財政自立」と問題点
1987年度計画は、事業評価をプラスと判定するにあたって、センターの経営が黒字(減価償却および公務員給与別)となる見通しを最大の根拠としている。しかし1993年までセンターの経営は赤字で推移した。
政府の補助が停止された1994年以降、逆にセンター財政は黒字に転換し、自力で新規投資(木造船建造他)を開始するまでになった。経営が1994年以降好転しセンターの財政自立という目標が達成された要因は次の3点であると思われる。
- 所長の交代により経営が改善された結果、生産・売り上げが増加した。
- 1994年計画による新規投資が生産増を招いた。
- 高価格魚種が好漁であった。
財政自立の達成によって、センターの公的目的と、経営体としての性格の間に矛盾が顕在化してきた。具体的には、民間支援の弱まり、民業との競合、経営の透明性の3点である。
(a) 民間支援の弱まり
3 (イ)で指摘した施設の開放、民間支援の弱まりは、センター経営の好転と裏腹の現象である。理由は、経営の改善努力は、利益部門への努力の集中を求めるが、利益のでない外部向けサービスである研修、普及等の活動を刺激するものではないからである。その結果、研修、普及は日本の専門家に任せてしまう現象がみられる。しかし、開放型からの乖離をセンター幹部の責任に帰すことはできないだろう。財政自立(補助金の打ち切り)は政府の方針であり、センターがこれを実現しようとすれば、利益のあがる部門に資源を移転するのは当然であろう。
(b) 民間事業との競合
センターの「財政自立」は、主要スタッフ(公務員)賃金の政府負担と、日本の援助に支えられ、かつ納税義務がないという特権に支えられている。こうした特権は、事業体が民間の提供しえない公共財を提供することと引き換えにあたえられているものである。センターが自らの基盤施設や加工場を漁民、加工人、仲買人に提供するといういわば公共財提供の任務を十分果たず、営利活動を柱とするなら、一般漁民や民間流通業者と不当に競合し、圧迫している可能性もある。
(c) 透明性現行の「財政自立」方式は、政府の補助金打ち切りと引き換えに、幹部に利益を自由に処分できる権利をあたえているフシがある。つまり幹部に経営改善のインセンティブはあたえるものの、幹部による利益配分、公益目的の部門の放棄、住民の「搾取」などの危険をともなうことも考えられる。
(4) 教訓と提言
(イ) センター事業の再考
従来、日本はセネガル政府と本プロジェクトについて協議を行ってきていると承知しているが、センターの財政健全化と社会目的が矛盾しない運営形態を、日本はセネガル政府と改めて協議すべきと考える。財政自立の追求と、民間支援や住民サービスのような非営利の公共財提供の両立をはかるには、公共財提供の実績に応じてインセンティブ(補助金・援助供与)をあたえるなどの仕組みを作ることが必要であろう。具体的には、非営利の公共サービスは直接税金で行うか、センターに出来高制の補助金を支給させて実施させることなどが考えられる。他方センターの営利部門があれば、むしろ民営化することが望ましい。(セネガル政府の政策大綱は漁業センターや冷蔵施設の民営化を行うとしている。(Gouvernment du Senegal, 1996)
センターが公的部門にとどまるかぎり、財務監査体制を確立する必要がある。制度的には監査主体をセネガル政府とし、住民と日本側にも参加と情報の開示を保証するのが適当であろう。日本側参加者はセネガルの公的部門の経営に関する知識があれば日本人である必要はなく、世銀のコンサルタント経験がある者などに委託することが適当であろう。
(口) 適正技術・機材の選択
資機材(センターの施設の原材料を含む)はできるかぎり現地産、ないしは現地で容易にかつ廉価で入手・修理が可能なものとする。これにより維持コストの削減、雇用の創出をはかることができる。
現行の加工技術開発は見直しをはかる。見直しのポイントは現地の人々が、わずかな資本と簡単な訓練で、かつ「儲かる商売」として取り入れられる技術とすることである。具体的には、以下の三点に留意するべきであろう。
- (a) 現地で入手可能でかつ廉価な材料を使用する
- (b) すでにある程度普及している加工技術を改良する
- (c) 市場性があり、高い収益性が見込まれる生産技術を開発する加えて、技術普及と信用供与、市場作り(宣伝、品質保証マーク制定など)を通した支援が組織されねばならない。現在行われている婦人グループ支援の経験を基礎にすることができよう。
(ハ) 地域開発業務の明確化
これまで地域開発はプロジェクトの間接的成果として期待されてきた。今後ミシラの地域開発に日本が支援を行うかについては、十分な議論が必要である。私見では、セネガル全体の地域開発の優先順位を考慮した場合、人口が小さいミシラ地区にさらに支援を集中するのは適当でない。また地域開発は単にインフラを建設するものではなく、地域に対する深い知識と住民との協同作業を求めるものである。日本の制度的能力からみて取り組みには慎重を期すことが必要である。
仮に日本がミシラの地域開発支援に取り組むのであれば、センター支援とは切り離したプロジェクト設計を行うのが妥当であろう。社会経済的な基礎調査を実施し、それを基準に支援の社会・経済的評価とモニター体制を作るなどの作業が必要となる。ついでこれを基礎に、地域開発のための行動計画を作成しなければならない。計画は地域住民主導の参加を経て策定されるべきである。日本および現地のNGOの(長期派遣を含めた)協力を求めるのが妥当であろう。行動計画はセンターの現行の業務とは相対的に独立した、新規の任務となるであろう。現地経済の規模を考慮し、過大な投資は避けるよう心がける必要がある。
3 モーリタニアの漁業
(1) モーリタニアの経済と国際協力
(イ) 人口および経済動向
国土・気候:
面積約100万平方キロメートル人口230万人、人口は年率2.5%(1990~95)で急速に増加しており、とりわけ都市人口増加率は年平均6.8%(同期間)と世界でも最も高いグループに属する。このため全人口に占める都市人口の割合は1980年には29%であったが、1995年には54%に上昇した。
国土の90%以上は砂漠に覆われており、他方可耕地は0.5%にすぎない。セネガル川流域のわずかな範囲を除けば、可耕地はない。38%で放牧が行われている。
経済構造:
一人当たり所得は460ドルだが(世銀、1998)人間開発指数は150位で、一人当たりGDP順位より15位も低い。(UNDP、1998)
モーリタニアの近代産業は、鉄鉱業および漁業の二つからなり、輸出はこの2部門のみが占めている。水産品は輸出の60%をしめ(鉄鉱石は40%)、また国家歳入において入漁料、漁業賦課金等漁業関連収入は20~25%を占めている。両セクターとも国内消費が極めて小さく(漁業は生産量の4%)、また雇用の規模が小さい。反面、牧畜を中心とする農業は労働力の64%を雇用している。
1986年以降、同国政府は、経済の自由化を進めてきたが、1992年以来さらに本格的な構造調整に取り組んだ。その結果1993-95年の成長率は4.8%と目標を上回った。また財政赤字は対GDP比11%(1992~93)から、5.3%(1996)の黒字に転じた。
(口) 国際協力
UNDP(1995)によれば、1994年の援助支出額をみると、モーリタニアにとってもっとも重要なドナーはフランスであった。日本はEU、IDAと並んで、フランスに次ぐ第2位のドナーとなっている。同年の漁業部門への援助は、援助全体の3.2%を占めた。日本の対モーリタニア援助における同部門のシェア協力は12.9%であり、日本が他のドナーより漁業協力を重視していることが知れる。さらに、UNDPのデータでは、日本の出資によるヌアクショット魚市場建設プロジェクトは漁業援助に分類されていない。これを漁業援助にカウントし直すと、漁業部門のシェアは対モーリタニア援助全体で6.1%に上昇、日本の援助におけるシェアは40.7%に上昇し、日本の漁業重視が一層際だってくる。日本はモーリタニア側から見ても、漁業部門における主要ドナーである。1994年の漁業支援全体における日本のシェアは70%(魚市場建設含む)である。
次に、長期的傾向を紹介する。日本のODA白書1997によれば、1977~1996年の対モーリタニア援助累計において、漁業部門の支援は無償資金協力の20%、ODA全体の12%であった。
(2) 漁業と漁業資源の現状
(イ) 大型船と輸出向け生産の支配
モーリタニアの漁業は、大型外国船の支配と、大半が輸出向けであることに特徴づけられる。漁獲量は年間40~50万トンと推定されており、うち96~98%が大規模漁業(90%が外国船)によるものである。そして大型漁業は漁獲の全量を、零細漁業も約半分を輸出している。漁業がこのように外部志向である理由は、同国における漁業生産の歴史が浅く、また魚介類の消費も普及していないことに求められる。モーリタニア国民一人当たりの消費量は年間6㎏程度といわれるが、これは日本の66.7キログラム(1992~1994平均)より少ないのはもちろん、隣国セネガルの27.1キログラム(同)と比較しても4分の一の水準である。なお、近年頭足類の資源の減少が顕著であると指摘されている。
(ロ)漁業政策と国際協力
漁業分野の政策は、大規模漁業と零細漁業双方の振興および調査・資源管理の強化を柱としている。零細漁業の漁獲量は、全体の2~4%にすぎないが、政府は雇用機会の創出、沿岸漁民の生活向上、地域振興を目的として、近代漁業に対してその保護と振興をはかっている。具体的にはヌアクショットおよび主要漁村の漁業基盤の整備、漁民に対する融資制度の確立と技術指導の推進を掲げている。主な具体策としては以下のものがある:
- 頭足類に対する禁漁期間の設定(9/10月)、零細漁業の保護、既存の村以外での漁の禁止、ジェライフ以北の動力船禁止の強化。
- 零細漁業への監視体制の強化。
- 零細漁民への訓練、教育の強化。
- 漁港、市場等のインフラ整備
- 協同組合の育成
- 信用組合組織化の加速と、フランス以外からの資金援助獲得
- 漁民証発行、漁船登録証の徹底、外国人漁民の漁労制限(セネガル人漁民を指す:大林)、統計整備等による零細漁業管理強化。
- 漁民の犠牲者が多いことに鑑み、漁船の安全対策を進める。
UNDPによれば、1994年の漁業部門援助において、進行中のプロジェクトではドイツとフランスがほぼ同規模であり、執行額ではフランスが6割を占める。
4 モーリタニア・イスラム共和国沿岸漁業振興計画 1994年度
(1) プロジェクトの概要
(イ) プロジェクトの対象地域
対象地域はヌアクショットとヌアディブの間に位置するイムラゲン漁村および同国最南端の漁村ディアゴである。今回視察したイムラゲン漁村は、約260キロメートルの海岸線にそって点在する13の漁民集落である。プロジェクト開始以前の状況は、概略以下のようであった。
イムラゲン漁村のうち、チミリス岬以北、すなわちバンダルゲン国立公園内に位置する漁村では動力船の使用が禁止されている。そのため帆船による漁が行われていた。生産性は低く、漁獲物販売の機会も少なく、多くの漁民は出稼ぎ漁をおこなっていた。他方内陸の牧畜民が難民化して流入したため、生活の困窮度が高まっていた。
チミリス岬以南ではにべ巻き刺し網漁が盛んで、日本がかつて供与したディーゼル機関搭載のFRP船が利用されていたが、老朽化が進んでいた。
イムラゲン地域は水源が皆無であり、南部はヌアクショットからの給水車、北部はヌアディブからの給水船により水の供給を受けていた。人口増に伴う需要増にもかかわらず給水車の老朽化により給水量は低下していた。
(口) 先行する日本の協力
当該地域には、1991年零細漁業振興計画により、日本より船内機関付き漁船(27)、船外機付き漁船(2)、ディーゼル船外機(3)、ガソリン船外機、ニベ網、ボラ網(18)、給水車(1)、水運搬船(1)、給水タンク(2)、ワークショップ(1)、支援車(1)が1992年に供与された。漁業生産機材は漁民に販売され、代金は零細漁業振興資金として管理・運用された。
プロジェクト対象地域にある漁村の1993年の人口および漁船数は以下の通りであった。JICA 1994aは、特に北部地区では動力船一隻あたりの漁民数が多く、当時約14人であり、南部地方では、動力船一隻あたりの漁民数は約8人となっている。
| 人口 | 家族数 | 漁民数 | 帆付船 | 船外機船 | 船内機船 | |
| 南部地区 | 1691 | 519 | 527 | 0 | 43 | 21 |
| 北部地区 | 1,034 | 304 | 36 | 53 | 18 | 2 |
| 計 | 2,725 | 823 | 889 | 53 | 61 | 23 |
| 北部 | 37.9% | 36.9% | 40.7% | |||
| JICA 1994aより作成 | ||||||
(ハ) プロジェクトの目的
- (1) 漁業生産活動の支援
- (2) 漁民の収入増加、生活条件の向上、就業機会の創出
- (3) モーリタニア国民に対する食糧供給の増加
(ニ)協力の内容
- (a) 漁業生産機材供与
- 船内機関付き漁船 43隻
- 船外機付き漁船 2隻
- ディーゼル船外機 61台
- 漁具資材 1式
- (b) 漁業活動支援機材
- 造水機 1式
- 給水車 3台
- 給水タンク 23個
- 工具セット 5セット
- 通信機 4セット
- 漁民指導用活動車 2台
- (c) 専門家派遣
- 機関整備・漁業振興計画
- 1992年2月~1996年
- 漁業専門家派遣予定
- (d) その他
- 資金形態:無償資金
- 交換公文締結日:1994年4月5日
- 供与額:5.5億円
- 引き渡し日:1995年3月31日
- 先方関係機関:漁業海洋経済省零細漁業局
- (e) 関連協力事業
- 1977年度 漁業振興計画(6億円)
- 1981年度 漁業振興計画(10億円)
- 1991年度 沿岸漁業振興計画(3.58億円)
- 1994年度 ヌアクショット魚市場建設計画(8.65億円)
- 1995年度 水産調査船建造計画(11.46億円)
(2) 目的の達成状況
(イ) 目的1. 漁業生産活動の支援
供与された資機材の利用状況は、支援対象が地理的に分散しているため直接確認できたのは一部のみである。政府側資料および、直接視認できた事例にたよって評価を行った結果、資機材はほぼ順調に使用されていることを確認した。
(口) 目的2. 漁民の収入増加、生活条件の向上、就業機会の創出
漁業は売り値の高いぼらその他高級魚に集中しており、動力船漁獲の売り上げは相当に高いと推測される。ただし収入金額は不明である。またプロジェクトでは漁民一人当たり約30万円が投資されていることになる。
(ハ) 目的3. モーリタニア国民に対する食糧供給の増加
この目的達成には、本プロジェクトの設計は不適切であると思われる。モーリタニアにおける漁業生産は国内消費を大きく上回っており、消費用の魚は物理的には不足していない。仮に国民が必要な魚を入手できないとすれば、それは生産の増加をはかっても解決されず、他の手段を取ることが必要である。
たとえば魚の価格が高く、国内消費者が買える値段では市場に出回らない場合がこれに当たる。モーリタニアの漁業生産物の大半は輸出されているため、価格は国際市場によって決定されてしまうので、こうしたことは十分起こりうるであろう。この場合は輸出に課税する、国内市場向けに価格補助を行う、間接的補助をおこなう(インフラの整備、低利の信用供与等)などの方法により、輸出の一部を国内消費に転換させることができる。こうした政策をとることなく、零細漁民に生産用具をあたえた場合、かれらも輸出向け生産を増加させるだけであろう。
本プロジェクトのサイトにおいても、漁民は輸出用のたこ、からすみや都市向けの高級魚生産に努力を集中しており、プロジェクトは外資獲得には役立っているが、直接「食糧供給の増加」には貢献していない。なお、たこ漁の普及は日本の専門家の指導が根付いたものであるとされている。
(注:なお、卵をからすみ用に利用したボラやニベは干物(ボラを利用したシュレハ、その他の魚を利用したゲジ)に加工され、モーリタニア内陸部まで運ばれ消費されており、モーリタニア国民への食糧供給の増加にもつながっている。98年度対モーリタニア水産無償「零細漁村開発計画」においては、更なる漁獲物の有効利用を図るために、加工場を含めた基盤整備を行い、今後特に女性を対象とした加工技術の研修などがUNICEFやNGOにより行われることが期待されている(出所:1989年11月JICA作成「零細漁村開発計画基本設計報告書」)。)
(3) 妥当性
(イ) 国立公園への脅威
プロジェクト対象のイムラゲン漁村の北部地区は89年に世界遺産に指定されたバンダルゲン国立公園内に位置し、動力船による漁業は禁じられている。同公園は西大西洋における魚の重要な産卵地帯であるとされている。他のドナーからは、日本の支援する漁民が公園内で操業する危険は大きいとの強い批判が出ている。JICA 1994aは、1)人口増加率が高い、2)動力船が不足しているという二つの理由から、動力船数を漁民10人に1隻の割合まで増加させることをプロジェクト目標としている。この比率は同国の沿岸漁業では最低のレベルであるが、「同地域漁民に最小限度の就労機会を確保することが可能となる」と述べている。さらにJICA 1994aは動力船導入の条件として以下の3点をあげている。
- (i) 公園の規則を遵守し、公園区域内での操業は行わない。
- (ii) 漁船はマンガールにおいて管理し、同漁村を基地としてチミリス岬以南の海域で操業する。
- (iii) 零細漁業局は漁民を指導、監督して上記事項を厳守させる。
上記の条件の実施状況に関し、現地を訪問したUNOPS西アフリカ地域事務所長(公園管理プロジェクトを支援)は、おそらくモーリタニア政府側の提供する資料によるものと推定されるが、日本の機材を装備した船が公園内で操業していると批判している。他方零細漁業局は公園内操業禁止を「指導・監督」する制度的能力にかける。漁業省も零細漁船の実効性ある監視がほとんど行われていないことを認めている。
JICA 1994aではマンガール村は南部地区に分類されていたが、JICA 1997aでは北部地区、すなわち公園内に分類されている。またチミリス岬以南の一部も国立公園内に含まれることとになる。この違いがなにに起因するものなのかは、確認することができなかった。この分類の変更にしたがって表4を調整すると、表5のようになり、本プロジェクトの対象は、漁民のうち公園内居住の漁民数が63%、家族数が70%に達する。したがって公園保護の立場からは、本プロジェクトが潜在的脅威となりうるので、したがって表5の認識にたてば、今後は北部地区における漁業の動力化を差しひかえるかどうか検討すべきであろう。
| 人口 | 家族数 | 漁民数 | 帆付船 | 船外機船 | 船内機船 | |
| 南部地区 | 875 | 245 | 332 | 0 | 30 | 14 |
| 北部地区 | 1,850 | 578 | 557 | 53 | 31 | 9 |
| 計 | 2,725 | 823 | 889 | 53 | 61 | 23 |
| 北部 | 67.9% | 70.2% | 62.7% | |||
| JICA 1994a,1997aより作成 | ||||||
マンガール村はイムラゲン漁村の中核でイムラゲン全体の27%に相当し、最大数の動力船が配分されている。調査団も同村に宿泊したが、法的に同村が公園内に位置するか否かにかかわらず、漁業活動が公園に直接影響する位置に同村があることは間違いない。したがって、本プロジェクトにおいてマンガールを優遇したのは、環境上は不適切であると言える。(注:なお、後述の(5)(イ)の注参照。)
本プロジェクトの設計にあたって、環境上の諸問題が十分検討されなかったことはその他の点にもうかがえる。第一に、本プロジェクトの目的そのものが漁業生産の振興に限定されており、国立公園保護は含まれていない。第二に公園保護については文書上で確認してはいるものの、その実効性の検討、実効性確保のための支援などは考慮されていない。第三に、基本設計調査にも環境への考慮は払われていない。
(口) 資源管理の軽視
余裕があると見られていた同国の漁業資源は、特定の魚種(特に蛸)にかぎってではあるが、近年急速に枯渇しつつある。同国政府は漁業規制を導入しているものの、ドナーからは輸出収入維持を優先させ、乱獲を放置しているとの批判が強くなされている。またIMF、世界銀行からは、漁業収入が財政の放漫化を助長しているとの批判がなされている。
(4) 自立発展性
(イ) 漁村の自立性
サイトにおける漁業および村落は、援助による補助金により発展している。しかし水のない砂漠での漁村そのものが、外部(政府ないしは援助)からの資金なしに自立するとは考えにくい。したがって援助がなくなった場合、漁村が自力で水を購入するのは困難と思われ、モーリタニア政府は水供給に資金を投入することが必要となろう。したがって村の規模が一定以上に拡大した場合は、財政上の負担が過大となる恐れがある。
(ロ) 見返り資金
モーリタニア当局は、日本の漁業機材売却の見返り資金を積極的に利用している。前プロジェクトの見返り資金42,000,000ウギアのうち33,000,000ウギアは回転資金としてさらにアルミおよび船舶の購入にあてられ、9,000,000ウギアが3年間(時期不明)モーリタニア漁業省零細漁業局の活動資金として利用されている。ちなみに1993年の局予算は3,869,400ウギアであるから、同局の見返り資金への依存度は相当に高いことが知れる。プロジェクト終了に伴い、零細漁業支援業務全般に支障をきたす恐れがある。
(5) 社会的公正
(イ) 船舶・機材の売却・分配方法
先行する1992年計画では、資機材の売却資金は回転資金として、資機材、とりわけ船舶の追加購入にあてることとされていた。本プロジェクトでも回転資金の名が継承されているが、船舶をはじめとする資機材の追加購入に関する記述はみあたらない。
モーリタニア政府によれば、資機材販売代金の返済は、22.4%弱である(1997年9月30日返済済み額/期日到来の返済額。JICA 1997aでは17%となっている)。これは前プロジェクトの返済率82%(1993年末JICA1994a、JICA 1997dでは66%)という実績を大きく下回っている。JICA 1994aは、1992年計画における漁船の売却・配分を、返済率が高かったことを理由に「成功を収めた」と評価している。本プロジェクトの返済率は低水準にとどまっているのであるから、成功とはいえず、何らかの問題があったと推定される。
資機材の分配の公正さについては、事前の指示はあるものの、事後評価がない。1992年プロジェクト、本プロジェクトともに基本設計(JICA 1992,JICA 1994a)において漁船の保有状況が漁民間で均等化するよう、配分の優先順位を示している。しかし分配の事後評価方法についてはJICA1992は触れていない。JICA 1994aにも、前プロジェクトのこの点についての総括はなく、本プロジェクトにおける分配の適正さについての事後評価を想定していない。
本調査団の所見では、マンガールと他村のあいだには、かなりの所得格差があるように見受けられた。
(注:その後、マンガールの他の零細漁村についてもセネガル政府の優先順位に基づき順次整備されている。)
(6) 教訓と提言
(イ) 国立公園保護を優先する
バンダルゲン公園内近隣地域での漁獲能力増強や人口増につながる支援は控えるべきである。公園での密猟は、大西洋の海洋資源に悪影響を及ぼすと推定されている。漁民の人数がかぎられているうちに、適切な措置を取る必要があろう。
(注:1998年度の「零細漁村開発計画」においては、国立公園への配慮から計画サイトを変更し、基本設計計画も通常1回のところを2回実施し、さらに、各国ドナーの理解を得た上で実施しており、今後とも、同公園を水産資源再生産の場として保護しつつ、沿岸漁船のライセンス化、漁獲量の的確な把握、有効利用の促進により、漁獲努力量の不適切な増加に歯止めをかける方向で各国ドナーの理解も得つつ、協力していく方針である。なお、モーリタニア漁業省の取り締まり能力も主としてドイツ、EUの協力による監視船の供与により、格段に向上している。)
(口) 資源管理への政策対話と支援を
他のドナーと協調して、モーリタニア政府との政策対話と資源管理への支援の強化をはかるべきである。モーリタニアの資源管理強化は、同国から大量の水産物を輸入する日本にとっても、重要な課題である。ドナーグループで検討されているように、資源保護を漁業支援のコンディショナリティーとすることも検討されるべきであろう。
(ハ) 援助の中長期的影響に関する協議を
沿岸開発の中長期的な計画と援助のインパクトについて、モーリタニア政府、他のドナーとともに十分に調査、協議を行うことが望ましい。またそのためには、住民の社会経済状態に関する基礎調査が必要である。
零細漁業開発は、沿岸における村落開発戦略と結び付けて検討される必要がある。この地域では、本来小人数で移動型の漁民が漁業を行っていたもので、多くの村はむしろ移動漁民の「キャンプ地」であったと思われる。現在でもイムラゲンの平均家族構成員数は3.3人しかない。内陸からの難民の流入および外部からの援助や補助金の供与により人口は急速に増加し、定着民の規模も増加してきた。しかし本地域での開発の促進と本格的な定着漁村の発展は、水の不在のため、生存基盤の極めて脆弱な集落を膨張させることになっている。また給水等へのコストが増大しつづける結果を招く。将来は水道の施設も含む本格的開発を進めるのか、補助の上限を明らかにして、村落規模拡大に天井をもうけるのかなど、他の代替案と比較検討を行う必要がある。
(二) 格差拡大に配慮を
貧困層に重点をおいた住民のプロジェクト運営委員会の組織を求める。下からの参加により、日本の支援が村落間や個人間の格差を拡大することのないよう、支援方式を改善する必要がある。
(ホ) 見返り資金の適切な利用・管理を
回転資金/見返り資金の使途について、モーリタニア当局と事前の協議および事後の監査制度を一層整備するべきである。基金の使用は毎年事前に日本国政府と協議されねばならず、またモーリタニア政府は日本政府の求めに応じて基金の預金報告、使用報告をすると定められているが、一部実行されていない。事前の計画提出を促すとともに、日本のモーリタニアにおける制度的能力および透明性の確保の点からみれば、事後の監査を現地の監査事務所に依頼するのが妥当と思われる。
5 総括
セネガル・モーリタニア両国に共通する日本の水産関連協力への提言を要約すると、以下のようである。
(1) 生産増から資源管理の強化へ
零細漁民への小規模船舶および発動機の普及は、日本をはじめとするドナーの支援をえて大きな成果を上げてきたことが確認できた。しかし今日では、ギニア湾岸の資源は危機にさらされている。水産部門の有力ドナーとして、日本は生産増強から、水産資源管理支援へと、早急に、かつ大胆に援助を転換しなければならない。この地域で捕獲され、日本で消費されている水産資源の量をも考慮すると、日本は資源枯渇の責任を問われるか、資源保全の支援者とみられるかの岐路にあるともいえる。海洋資源は国境を越えた広がりを持つため、資源管理には地域的な協力が不可欠である。したがってギニア湾岸の地域漁業委員会(SRFC)支援を実施することが強く推奨される。具体的には、SRFC事務局への各種支援、地域会議開催への支援などが検討されるべきであろう。
(2) 増産と近代化から雇用拡大と貧困者支援へ
零細漁業支援の目的を、生産増・近代化から雇用の安定・拡大へと転換するべきである。従来行ってきた零細漁業の機械化支援は、資源の保全のためには、次の二つの場合以外、今後は抑制しなければならない。
- 近代漁業の生産が大幅に規制されて、資源に余裕が生じた場合
- 資源が未だ豊富な魚種の開発の場合雇用の安定・拡大のためには、マイクロ金融、伝統漁船の改善、安全体制や保険制度作りなどの支援を行う必要がある。
流通・加工部門においては、これまで鮮魚流通を軸に近代化を支援してきた。しかし今後はその目的を、低所得層の水産物消費の中心を占める常温保存の加工品の供給・流通拡大へと転換するべきである。新規の技術導入は避け、労働集約的で伝統的な加工業と流通業を支援することが必要となろう。
(3) 公的部門より自営業への支援を
零細漁業支援成功の最大の原因は、支援が自営漁民に直接なされたところにある。他方公的施設(漁業センター、水産市場等)への支援は、さまざまな障害に遭遇しており、また投資効率も低い。これはアフリカの公的部門が経済危機を経て再編過程にあるためである。漁業のみならず水産加工・流通部門においても、零細自営業者に直接届く援助形態を優先することが効果的であろう。例えば小型船舶用発動機に対して行われたように、機材や運搬手段の補助金つき販売・マイクロ金融の組織等が考えられる。またマイクロ規模のインフラ(地方市場、小規模の船着き場等)支援も重要である。なお、インフラストラクチャー支援については、行政部門への協力は最小限にとどめるべきである。とりわけ担当部門に様々な支援サービス機能を求めるのは、適当でない。インフラは税金ないし利用料で維持し、支援サービスは民間業者に依存することが持続性確保には適当であろう。
(4) 透明性の向上を
アフリカの公的部門は移行期にある。中央政府、独立部門を問わず、部分的な自主財政化が進んでいる。自主財政化は事業の持続性を増加させる反面、財務の不透明化の危険をはらんでいる。相手国政府主体の、日本側および現地住民が参加し、かつ完全な情報開示を伴う監査を条件づけることが必要である。なお、監査結果は両国において公表されるよう、制度化することが望ましい。
外務省1997a「セネガル共和国概要」(アフリカ第一課)
外務省1997b「セネガル共和国概要」(在セネガル大使館)
外務省1997c「我が国の政府開発援助ODA白書下巻(国別援助)」
外務省1997「在外交館評価調査結果報告モーリタニア沿岸漁業振興計画」
外務省1991年3月「在外公館評価調査報告セネガル零細漁業計画」
国際協力事業団1988「セネガル共和国零細漁業振興計画基本設計調査報告書」
国際協力事業団1992「モーリタニア・イスラム共和国沿岸漁業振興計画基本設計調査報告書」
国際協力事業団1994a「モーリタニア・イスラム共和国沿岸漁業振興計画基本設計調査報告書」
国際協力事業団1995「セネガル国別援助検討会報告書」
国際協力事業団1997a「モーリタニア国マンガール漁村開発計画基本設計調査インセプションレポート」
国際協力事業団1997b「セネガル共和国国別援助実施指針」
国際協力事業団1997c「セネガル事務所業務概要」
国際協力事業団1997d「モーリタニア国マンガール漁村開発計画基本設計調査団中間報告書」
国際協力事業団セネガル国漁業海運省1994「セネガル共和国零細漁業振興計画基本設計調査報告書」
国際協力事業団セネガル国海運漁業省1997「セネガル国北部漁業地区振興計画調査ドラフトファイナルレポート」
国際経済学会編1998「開発と世界システムー市場経済・援助・環境一国際経済第49号(第56回全国大会報告号)」
国際連行食糧機関「主要国食糧需給表」国際食糧農業協会1996
国連開発計画1997「貧困と人間開発」国際協力出版会
社団法人日本林業技術協会1995「セネガル共和国苗木育成場整備計画(第2次)基本設計調査報告書」
世界銀行1997「世界開発報告1997開発における国家の役割」東洋経済新報社
African Development Bank 1997, African Development Report 1997, Oxford University Press
Ambassade de France en Mauritanie 1997, Cooperation Francaise en Mauritanie: Previsions au titre de 1997.
Banque Mondiale 1997, Le Partenariat: Mauritanie.
Centre de Formation Professionnelle et Technique, Senegal/Japon, Presentation du Centre.
DAC 1996, Development Co-operation, Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee.
FMI 1997, Le FMI conclut les consultations au titre del'article IV avec le Senegal. 1996, Ministere de la peche et des transports maritimes du Senegal, Le Senegal: des mutations 1997.
Gouvemement du Senegal, novembre 1996, Documemnt-cadre de politique economique et financiere pour 1996-99.
Jean-Claude Berthelemy, Abdoulaye Seck and Ann Vourch 1997,Growth In Senegal: A Lost Oppartunity, OECD.
JICA 1997, Proces-verbal des discussions sur l'etude du concept de base pour le projet de village de peche de Mamghar en Republique Islamique de Mauhtanie.
Ministere de la peche et des transports maritimes 1992, Resultats generaux de la peche artisanale Senegalaise: Annee 1992.
Ministere de la Peche et des transports maritimes 1993, Resultats generaux de la peche maritime Senegalaise Annee 1993.
Ministere de la peche et des transports maritimes 1994, Resultats generaux de la peche artisanale Senegalaise: Annee 1994.
Ministere de la Peche et des transports maritimes 1995, Resultats generaux de la peche maritime Senegalaise Annee 1995.
Ministere de la peche et des transports maritimes 1996, Resultats generaux de la peche artisanale Senegalaise: Annee 1996.
Ministere de la peche et des transports maritimes 1997, Requete d'extension et de consolidation du Centre de peche de Missirah.
Ministere de la Peche et des transports maritimes 1997, Resultats generaux de la peche maritime Senegalaise Annee 1997.
Ministere de la sante publique et del'action sociale du Senegal 1996, Plan national d'action sociale 1997-2006.
Ministere des affaires etrangeres de la France 1997, Cooperation francaise en Mauritanie: Previsions au titre de 1997.
Ministere des affaires etrangeres de la France, L'aide publique francaise au developpement en Mauritanie, 15ans de cooperation francaise en Mauritanie.
Ministre des peches et del'economie maritime de la Mauritanie 1996, Plan d'action pour la peche artisanale.
Moustapha Kasse 1996, L'etat, la technicien et le banquier face aux de fis du monde rural Senegalais. Nouvelles Editions Africaines du Senegal Centre de recherches economiques appliquees.
PNUD 1996, Cooperation pour le developpement: Senegal 1994.
PNUD 1997, Cooperation pour le developpement: Senegal 1995.
PNUD 1994, Co-operation au developpement 1993: Mauritanie.
PNUD 1995, Co-operation au developpement 1994: Mauritanie.
Sub-regional Fisheries Commission 1997, Report of The 1st Round Table Conference With Partnersin Development UNDP
Sub-regional Fishehes Co㎜ission 1997, Round Table conference. UNDP
UNDP 1997, Interoffice Memorandum.
Yacine Kane, Rapport devaluation sur le projet de Missirah du 261097 au 07-11-97.
補遺 現地コンサルタント(Mame Yacine KANE)作成
「ミシラ漁業センター報告書」仮訳(原文(仏文)省略)
概要
海洋漁業は、国家経済の主要なセクターの一つとなっており、第一次産業の国内総生産の約11%を占めている。
1996年には、水揚げ高は16%伸びたが、漁獲の大部分が沿岸零細漁民によるため売上高は若干低下した。
セクター全体の業績の基礎となる零細漁業は、漁獲高が23%伸びている。
輸出量は3%伸び、輸出額は1.6億CFAフランになるものと見られる。これにより、漁業はセネガルの輸出品の中で第一位を占めている。
60万人近くの人が、直接的、間接的に漁業により生計を立てている。
国民の動物性蛋白質の必要量の大部分は、魚及びその派生製品により賄われている。
零細漁業のサブ・セクターは経済的社会的に活況を呈している。
零細漁業の飛躍的な発展は、漁獲技術の近代化、製品の付加価値化、鮮魚の流通改善、魚加工業の発展、漁業センターの基礎的インフラの整備、漁業活動に対する信用供与によるものである。しかしながら、この発展、経済的社会的飛躍にも拘わらず、漁業は様々な制約に直面している。これらの制約は、漁業資源の減少、経済の自由化政策及び生産セクターからの国の撤退、CFAフランの切り下げ、国際経済環境の厳しさという大きな出来事に伴う根本的な変化という中で生じているものである。
この状況に対して、漁業資源管理を改善すること、制約条件と生産拡大方法を明らかにするための研究を行いながら生産を拡大すること、漁獲の特質をより良く活用することが何よりも急務である。
国が、資金供与国・機関の協力を得て、より良い調整の枠組みを築くことが出来るようになることが必要である。
漁業の各部門間の接触は既に行われており、漁業セクター開発についてのマスター・プランが1998年に策定されることになっている。
評価調査の背景
無償資金協力の枠組みで、セネガルは、ミシラ漁業センター設立計画に対し、日本政府より2次に亘り資金供与(1989、1994年)を受けた。
1989年の第1次資金供与は、第7次開発計画の零細漁業振興に沿ったものであった。
このセクターの目的は、特に南部地域における零細漁業の振興であった:重点は、新しい漁業技法に適応できる漁民の育成、生鮮品の加工及び流通網の整備に置かれていた。
1994年の1億6千2百万円の第2次資金供与は、資機材の補填によるセンターの機能強化が目的であった。
流通、加工、生産及びセンターの運営に関する一連の提言がなされたが、これはセンターが、第一次基本設計報告書に述べられているセンターの目的を維持しつつセンターを独立採算制に導くためのものであった。
このセンターの目的とは、
- ミシラ漁業センターを、サルーム諸島の鮮魚の生産及び同諸島の開発促進のための拠点とすること、
- 流通網を整備すること、
- センター運営のために独立採算制を確立すること、である。
これらの提言を踏まえ、我々は、我々の結論及び提言を纏める前に、これらの目標が達成されたか、このプロジェクトの直接的、間接的効果は何であったのかの検証を行った。
直接的効果
生産活動は強化された(漁民数の増加、漁船(ピローグ)の増加、域外漁民からの買い上げの開始(表参照))。
- 加工技術が強化、改善された(乾燥技術、カマボコの生産、魚の低温薫製…)
- 漁業関連活動が強化された(氷の販売、モーターの修理、漁具の販売…)
- 仲買人がセンターで仕入れをするようになるにつれて、民間流通網が発達した。
- 1994年以来、センターは独立採算運営を行っている。産物の販売(氷、鮮魚及び、又は加工品)によりセンターの運営経費を賄うと共に、その余剰収益により約55百万CFAフランにのぼるセンターへの追加的投資(表参照、図書館の建設及び備品整備、売店・電話センターの建設、当初カマボコの加工用に当てられていた棟の拡張)を行うことが可能となった。
- 女性の加工就労者は、クレジットを受けられるように経済利益グループ(GIE)及びGIE連合に組織された。
- 漁民は、操業の安全性の強化と生活の向上に向けて、新しい漁業技術の訓練を受けた。
間接的効果
- 周辺住民への食料及び蛋白質の供給
- 住民の生活向上
- 当該地域の活動に対する大きなインパクト
- 女性加工就労者に対する信用供与
- 財政的、経済的及び社会的生活設計への支援(漁民の定住化)
- 食糧自給
- ミシラ住民への社会的インパクト(患者の移送及び緊急移送、モスク及び診療所の電化、村の電化(実施中)、若年者の雇用、住民の散在の解消、飲料水の常時供給)
財政的考察
今回の評価では、プロジェクトの財政的側面に重点を置いていない。せいぜい言えることは、現状に適合するためにセンターの方針に対し新しい指針が与えられたことである。
この新しい方針は、センターの財政的自立を可能にするものである。
結論及び提言
ミシラ・プロジェクトの総合的評価は、全体として良好である。しかしながら、センターのより良い運営のためにいくつかの提言を行う。
- センターは、漁民がより自己管理し、より責任を持ち、より自立するよう指導を行うべきである。
- 漁民のみならず加工に従事する女性も含めた人材育成について、新しい戦略を打ち立てるべきである。
- センターの機材(漁船(ピローグ)、加工用機械)を更新するために、センターは、地元の機材の利用促進を目指すべきである。これにより、機材関連分野の発展や地元漁民特有のニーズにより良く適合させることが出来るとの利点があろう。
- 加工については、伝統的技術に重点を置くべきであり、どの様な方法でこれらの技術を改善できるか検討するべきである。
1998年に、見積額130百万CFAフランでツバクターミシラ区間の(道路の)リハビリ・プロジェクトが予定されている。このプロジェクトにより、漁業製品の品質及びミシラ住民の生活条件の改善が期待される。このレベルでは、まだやることが残っていると思われる。
ミシラのプロジェクトを別とすれば、漁業全体として見れば、次のような問題点が依然として残っている。
- 漁業資源の管理
- 水揚げされた魚の価格安定
- 商業流通網の整備
- 零細加工業については、漁業活動への信用供与と資金調達の仕組み
- 人材育成
- 漁業資源の過剰開発、漁船(ピローグ)係留地の増大に伴う漁場の縮小、資源枯渇という事実に基づけば、重点は、生産の増大よりも、むしろ、資源の最適管理と合理的開発に置かれるべきである。
- 資源保護という良き政策のためには、法整備が強化されるべきである。
- 漁業ライセンスの認可に関する新しい政策
- 漁業水域の画定、漁網の規制
- 追跡、取り締まり及び監視の強化
- 政府は、脈絡なく資金が投入されるのを防ぎ、また、投資がより効果的なものになるよう、漁業セクターに投資を行う全てのドナー間の協調と調整を図るための最適の枠組みをつくるためにセクター投資計画を策定すべきである。
- 漁業分野における将来取られるであろう全ての活動のために、ドナー調整委員会が設置されるべきである。
附属
調査団メンバー
ミシラにおける調査日程
面会者リスト
センターの活動報告書(1990~1996)より抜粋した諸表
調査団メンバー
大林 稔 龍谷大学経済学部教授
鈴木 恵子 外務省経済協力局評価室課長補佐
Mame Yacine KANEコンサルタント(エコノミスト)
現地調査日程
日付行程及び調査内容
1997年
- 10月26日
- 大林、鈴木ダカール着
- 27日
- 在セネガル大使館表敬、二木書記官と協議
- JICAと協議
- 昼食
- DIAGAGUEYE漁業海運省漁業局長訪問、協議
- 28日
- ミシラへ移動、現地での調査・協議・データ収集及び仲買人、漁民、漁村民との懇談
- 29日
- セネガル側及び日本側関係者との意見交換
- ダカールへ移動
- 30日
- 他のドナーとの意見交換
- *カナダ大使館:Paul LACHANGE参事官
- *世銀:Abdoulaye SECK常駐代表
- *仏開発公庫:Alain CELESTE所長
- Yves MALPEL所長代理
- 31日
- 他のドナーとの意見交換
- *FAO:MBODJ所長
- *UNDP:TH10UNE経済担当
- 11月5日
- 地域漁業委員会からのヒアリング:Boubakary NOIAYE事務局長
- 6日
- USAID:Robert NAVINプログラム課長
- 仏協力省
- 漁業海運省:Diaga GUEYE漁業局長
- Sogui DIOUF首相顧問(漁業担当)
面談者リスト
- Paul LACHANCE
- カナダ大使館協力担当参事官
- Alain CALESTE
- 仏開発公庫所長
- Yves MALPEL
- 仏開発公庫所長代理
- Mamadou DIOUF
- ミシラ漁業センター所長
- Marcel TINE
- ミシラ漁業センター生産部長
- Mamadou SENE
- ミシラ漁業センター資材部長
- Moussa GUEYE
- ミシラ漁業センター機械部長
- Ibrahima LO
- ミシラ漁業センター人事部長
- Sidiya DIOUF
- ミシラ漁業センター加工部長
- Ruffin GBAGUIDI
- ミシラ漁業センター指導部長
- Fily DIENE
- ミシラ漁業センター渉外部長
- Masaki OIKAWA
- 派遣専門家
- Sadio SENGHOR
- ミシラ村長
- Diaho GADIO
- 女性加工作業就労者代表
- Ousseynou NDOUR
- 仲買人
- Nancy HARME
- ミシラ保健所所長
- El Hadji Arfang NDONG
- 漁民
- Ndiamba DIOUF
- 漁民
- Diaga DIOUF
- 漁業海運省漁業局長
- Fay E
- 漁業海運省漁業局人事課長
- Abdoulaye SECK
- 世銀エコノミスト
- Sagar DRAME
- 経済財務計画省
- KHOULE
- 経済財務計画省経済資金協力局漁業担当
- Sogui DI0UF
- 首相顧問(漁業担当)
- 二木一等書記官
- 日本大使館経済協力担当
| 年 | ミシラ漁業センターの生産高(トン) | その他の生産高(トン) |
| 1990 | 84.51 | |
| 1991 | 160.10 | |
| 1992 | 189.56 | |
| 1993 | 188.91 | |
| 1994 | 243.25 | |
| 1995 | 341.98 | 38.66 |
| 1996 | 307.10 | 39.40 |
| 1997年1~6月 | 96.27 | 85.46 |
| 年 | 製氷量(キログラム) | 補足購入量(キログラム) |
| 1990 | 84.51 | |
| 1991 | 16,010 | |
| 1992 | 189.56 | |
| 1993 | 188.91 | |
| 1994 | 243.25 | |
| 1995 | 341.98 | 19,500 |
| 1996 | 307.10 | 13,750 |
| 1997年1~7月 | 96.27 | 60,950 |
製氷量は、漁獲生産高の変化に従って変動している。漁獲生産高の増加時に、製氷量が増加している。
|
項 年 |
購入 | 販売 | 売買 価格差 (CFAフラン) |
||||
| 購入量(キログラム) |
購入額 (CFAフラン) |
1キロの価格(フラン/キログラム) | 販売量(キログラム) |
販売額 (CFAフラン) |
1キロの 価格 (フラン/㎏) |
||
| 1990 | 84.51 | 12,212,977 | 144.50 | 84.50 | 17,972,524 | 212.69 | +68.25 |
| 1991 | 160.10 | 29,763,900 | 185.90 | 160.10 | 38,117,452 | 238.00 | 52.10 |
| 1992 | 189.56 | 34,401,061 | 181.50 | 189.56 | 43,605,307 | 230.00 | 48.50 |
| 1993 | 186.91 | 28,262,637 | 151.20 | 179.89 | 41,655,093 | 231.55 | 80.35 |
| 1994 | 243.25 | 30,989,862 | 127.40 | 234.40 | 55,252,610 | 235.70 | 108.30 |
| 1995 | 380.64 | 73,336,335 | 192.70 | 371.21 | 122,900,629 | 331.10 | 138.40 |
| 1996 | 346.50 | 70,846,828 | 204.50 | 337.51 | 113,547,270 | 336.40 | 131.90 |
購入量は、1990年の84.5キログラムから1996年には346.5キログラムに増加した。
年平均の増加量は45.6キログラム。但し、1996年は1995年に比べ大きく減少(34.1キログラム減)。
|
項
|
販売 | 加工製品用 | 個人消費 | |||
|
量 (キログラム) |
額 (CFAフラン) |
量 (キログラム) |
額 (CFAフラン) |
量 (キログラム) |
額 (CFAフラン) |
|
| 1990 | 123,718 | 4,239,565 | - | - | - | - |
| 1991 | 126,488 | 4,558,910 | - | - | - | - |
| 1992 | 126,997 | 5,241,710 | - | - | - | - |
| 1993 | 206,673 | 7,831,345 | - | - | - | - |
| 1994 | 239,172 | 10,781,221 | 63,588 | 1,887,625 | 8,261 | 247,830 |
| 1995 | 316,859 | 16,010,440 | 110,018 | 3,480,340 | 10,174 | 808,760 |
| 1996 | 424,244 | 19,168,445 | 127,237 | 3,817,710 | 15,504 | 456,120 |
製氷分配量の継続的な増加は、鮮魚生産量、つまり漁獲高の増大と関係がある。
購入量は、1990年の84.5キログラムから1996年には346.5キログラムに増加した。
年平均の増加量は45.6キログラム。但し、1996年は1995年に比べ大きく減少(34.1キログラム減)。
製氷分配量の継続的な増加は、鮮魚生産量、つまり漁獲高の増大と関係がある。
1996年の生産量567トンのうち、概ね75%が漁民や仲買人に販売され、22.5%がセンターの加工製品用、残りが個人消費用に使用された。漁獲量が多い時期には、ミシラ漁業センターの製氷量では足りず、外部からの氷購入が必要になることもある。
氷が加工製品用(カマボコ加工)に使用されるようになったのは、1994年からである。
|
年 販売先 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| 小売商 | 76,128.90 18,685,394 |
80,502.10 22141542 |
||||||
| 地元仲買人 | 15,536.50 5,350,740 |
28,837,50 8,566,678 |
49,590.60 9,726,828 |
52,558.10 1,066,7033 |
6,3497.80 15,002892 |
45,862.80 18,973230 |
44,716.10 18867180 |
|
| 地元ホテル | 981.10 560030 |
1,810.20 1220560 |
||||||
| 周辺村落 | 25,533.20 1,731,294 |
5,989.40 331,186 |
2,879.20 149,650 |
80,215.50 6139121 |
67,040.20 5725766 |
73,713.20 5776,612 |
||
| 小計 | 41,069.70 7,082,038 |
34,826.90 8,897,864 |
52,436.80 9,870,478 |
52,558.10 10,667033 |
143,713.30 21,142,013 |
190,013.00 43,944,420 |
200,786.60 48,005894 |
|
| Gossas | 330.20 98,070 |
|||||||
|
Fatick |
個人 | 2,149.20 748,820 |
1,549.00 891,925 |
2,534,10 1748,035 |
||||
| 市場 | 305.80 73,300 |
880.40 179400 |
||||||
| 小計 | 2,149.20 748,820 |
1,854.80 965,225 |
3,414.50 1927435 |
|||||
|
Kaolac |
個人 | 3,479.70 1873,645 |
5,075.00 2670,125 |
|||||
| 市場 | 6,815.30 499,950 |
19,170.40 2,522,400 |
29,912.80 5,764,860 |
42,127.10 10,608460 |
29,264,90 10505,990 |
14,415.80 4754,850 |
7,532.60 1,417300 |
|
| 小計 | 6,815.30 499,950 |
19,170.40 2,522,400 |
29,912.80 5,764,860 |
42,127.10 10608460 |
29,264.90 10,505,990 |
17,895.50 6638.495 |
12,607.60 4087425 |
|
| Mbour | 3,493.60 890,715 |
|||||||
| Thies | 5,875.60 1,708,700 |
9,046.20 2,879,950 |
||||||
| Diourbel | 1,186.60 398,550 |
2,505.00 875,350 |
||||||
| Mbacke | 144.00 420,000 |
414.00 116,500 |
||||||
| Touba | 2,830.80 868,500 |
2,999.40 995,050 |
||||||
|
a k a r |
個 人 |
700.00 447,580 |
1,953.40 1,289,160 |
|||||
| 会 社 |
4,575.00 3,690,380 |
1,263.20 955,010 |
||||||
| 独立業者 | 83,907.90 39,839,695 |
84,471.10 45,379,900 |
||||||
| 市 場 |
36,633.00 8,672,088 |
76,758,90 22,191,140 |
76,486.60 21,368,212 |
85,205,80 20,379,600 |
61,423.50 23,604,605 |
58,230.50 23,844,530 |
18,103.80 7,035,294 |
|
| 小計 | 36,633.00 8,672,088 |
76,758.90 22,191,140 |
76,486.60 21,368,212 |
85,205.80 20,379,600 |
61,423.50 236,046 |
147,413.40 67,822,185 |
10,5737.50 54,659,366 |
|
| 加工用 | 6,774.85 2,195,803 |
5,828.55 2,427,609 |
||||||
| Echatillons | 1,189.10 340,180 |
1,913,60 590,551 |
||||||
| 上段 販売量 (キログラム) 下段 販売額 (CFAフラン) | ||||||||
1995年以降、民間販売網が活性化した。
センターの製品は、他の地方(Touba、Fatick他)や民間販売網(ホテル、個人等。Fatickの個人は1992年の348件から、95年には576件、96年には690件に拡大)に売却されるようになった。
|
年 販売先 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| 小売商 | 245 | 275 | ||||||
| 地元仲買人 | 344 | 297 | 196 | 203 | 236 | 414 | 412 | |
| 地元ホテル | 571 | 674 | ||||||
| 周辺村落 | 68 | 55 | 50 | 76 | 85 | 78 | ||
| Gossas | 297 | |||||||
| Fatick | 個人 | 348 | 576 | 690 | ||||
| 市場 | 240 | 204 | ||||||
|
Fatick 小計 |
348 | 408 | 447 | |||||
| Kaolack | 個人 | 538 | 526 | |||||
| 市場 | 73 | 131 | 193 | 252 | 360 | 330 | 188 | |
|
Kaolack 小計 |
73 | 131 | 193 | 252 | 360 | 434 | 357 | |
| Mbour | 255 | |||||||
| Thies | 291 | 318 | ||||||
| Diourbel | 336 | 349 | ||||||
| Mbacke | 292 | 281 | ||||||
| Touba | 307 | 332 | ||||||
| a k a r |
個人 | 639 | 660 | |||||
| 会社 | 807 | 756 | ||||||
| 独立業者 | 475 | 537 | ||||||
| 市場 | 237 | 289 | 279 | 239 | 384 | 409 | 387 | |
|
Dakar 小計 |
237 | 289 | 279 | 239 | 384 | 582.50 | 585 | |
1キロ当たり平均売上げ指数は、会社(輸出用魚種)、ホテル、個人のレベルでより高くなっている。
これに対し、市場での売上げ指数は、相対的に低くなっている。
|
年 製品 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 合計 |
|
KONG 薫製 |
623.80 232,019 |
4,291.57 1,518,555 |
2,738.60 1,079,113 |
9,00 2,700 |
80.00 28,000 |
7,742.97 2,860,387 |
||
|
OTOLITHE 干物 |
14.20 7,100 |
88.40 30,435 |
102.60 37,535 |
|||||
|
舌平目 干物 |
167.00 49,670 |
657.10 73,480 |
824.10 123,150 |
|||||
|
カニ 干物 |
6.00 4,320 |
166.00 42,400 |
229.45 98,270 |
186.00 65,750 |
150.00 57,800 |
72.00 24,000 |
818.45 292.540 |
|
|
PAGNE 干物 |
12.00 2,160 |
60.00 9,450 |
121.00 13,050 |
31.00 18,600 |
2.00 2,000 |
226.00 45,260 |
||
|
GUEDJ ONG |
13.00 3,900 |
640.00 320,000 |
653.00 323,900 |
|||||
|
カキ 干物 |
2.00 960 |
19.00 4,700 |
325.00 48,600 |
329.50 98,300 |
229.00 69,560 |
124.00 34,350 |
1,091.50 256,470 |
|
|
TAMBA DlANG |
789.10 261,187 |
260.95 78,284 |
10.00 4,500 |
1,060.05 343,971 |
||||
| 合計 | 1,607.10 553,876 |
5,317.98 1,708,194 |
2,983.60 1,135,663 |
684.45 162,620 |
1,329.50 530,650 |
390.00 120,360 |
206.00 62,850 |
12,518.63 4,283,213 |
| 上段:販売量 下段:販売額 | ||||||||
1991年、カニ、l'arche、カキの加工が開始された。
加工には、衛生と質を特に重視した手作業による加工技術が使用された。
|
年 製品 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 合計 |
| 舌平目 | 10.30 51,260 |
27.95 125,000 |
0.32 1,600 |
38.57 177,860 |
||||
| バラクーダ | 9.80 39,200 |
9.80 39,200 |
||||||
| シイラ | 13.90 55,600 |
9.10 36,400 |
23.00 92,000 |
|||||
| カジキ | 171.79 859,816 |
179.93 948,655 |
161,06 886,550 |
362,25 1,502,875 |
8223 886,760 |
108.01 1,295,180 |
1,065.27 6,359,836 |
|
| カピテーヌ | 97.69 318,576 |
143.32 573,340 |
78.30 313,200 |
176.45 704,323 |
314.35 1,230,260 |
210.60 1,266,710 |
1,020.71 4,406,409 |
|
| サワラ | 28.28 98,980 |
74.84 216,850 |
43.72 158,005 |
105.10 420,842 |
155.86 728,435 |
175.10 874,540 |
582.91 2,542,652 |
|
| 牛タン | 29.05 131,200 |
19.93 139.510 |
5.02 35,140 |
54.00 305,850 |
||||
| イカ | 0.32 1,600 |
87.19 293,350 |
70.77 280,735 |
91.80 220,765 |
20,95 146,650 |
217.04 943,100 |
||
| マグロ | 9.12 40,672 |
7.88 31,500 |
17.00 72,172 |
|||||
| 合計 | 317.50 1,370,904 |
544.80 2,328,495 |
363.27 1,656,490 |
764.60 2,980,005 |
572.37 2,984,965 |
519.69 3,618,220 |
3,082.31 14,939,079 |
|
| 上段:販売量 下段:販売額 | ||||||||
1994年以降、カジキ、カピテーヌ、サワラ、イカ、牛タン(アジア系社会により珍重されている)を除き、試験生産品目の殆どの生産が停止された。
この試験加工は、あまり決定的ではなかった。
日常的に行われている加工は、手作業で加工する魚種にとどまっている。
|
年 製品 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 合計 |
| カマボコ | 1,148 311,300 |
3,662 825,260 |
2,637 523,400 |
6,964 1,453,200 |
7,987 2,210,930 |
4,774 1,379,400 |
27,172 6,703,490 |
|
|
イカ・ ボール |
198 52,750 |
581 97,500 |
1,434 418,650 |
575 168,800 |
2,788 737,700 |
|||
|
カニ・ ボール |
78 19,500 |
339 83,500 |
891 314,900 |
1,380 406,100 |
2,688 824,000 |
|||
| すり身 | 50.50 63,950 |
15.00 30,000 |
65.50 93,950 |
|||||
| チクワ | 3.00 600 |
3,00 600 |
||||||
| ハンバーグ | 132.00 21,300 |
71.00 13,300 |
203.00 34,600 |
|||||
| 合計 | 375,250 | 825,860 | 616,950 | 1,647,500 | 2,974,480 | 1,954,300 | 8,394,340 | |
|
上段:販売量(かまぽこ、イカ・ボール、カニボール:販売数、すり身、ちくわ:販売重量) 下段:販売額 |
||||||||
1990年から試験生産が開始された製品のうち、カマボコ以外は、新たな機材が到着しそれによる生産が増加した1993年、1994年には生産されていない。
加工製品は、加工用鮮魚が入手できるようになったことに加え、新たな機材が到着したことにより、大きく増加した(カマボコは、1993年の2,637個に対し1994年は6,924個)。
1996年の生産減少は、漁獲の漸減に起因している。
このような生産動向は、カニ・ボールについても観察される。
|
年 薫製品 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 合計 |
| イワシ | 26.91 67,275 |
290.00 10,375 |
316.91 77,650 |
|||||
| ボンガ | 0.99 2,725 |
0.99 2,725 |
||||||
| コング | 39.30 29,650 |
1,094.56 455,385 |
1,264.40 578,840 |
18.70 11,220 |
16.61 71,780 |
2,453,57 1,146,875 |
||
| エイ | 107,46 49,160 |
107.46 49,160 |
||||||
| 合計 | 60.29 32,375 |
1,228.93 571,820 |
1,554.40 589,215 |
18,70 11,220 |
16.61 71,780 |
2,878.93 1,276,410 |
||
| 上段:販売量 下段 販売額 | ||||||||
|
車種 輸送先 |
ISUZU | lVECO | NISSAN | PLATRAU | CABSTAR | TOYOTA |
| Toubacouta | 5,000 | 7,000 | - | 10,000 | - | - |
| Karang Sokone | 7,000 | 10,000 | 15,000 | 17,500 | 25,000 | 15,000 |
| Passy | 12,500 | 20,000 | 23,500 | 25,000 | 30,000 | 23,500 |
| holack | 20,000 | 26,000 | 30,000 | 32,500 | 36,000 | 30,000 |
| Mbour | 45,000 | 50,000 | 59,000 | 70,000 | 75,000 | 59,000 |
| Dakar | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 83,000 | 65,000 |
|
利用者 輸送先 |
民間 | 関係当局 | 軍 |
その他 行政機関 |
|
| 小型漁船 | 大型漁船 | ||||
| Ile des oiseaux | 20,000 | 32,000 | - | - | 燃料費 |
| Djinack | 20,000 | 32,000 | 無料 | 無料 | 燃料費 |
| Betenty | 20,000 | 32,000 | 無料 | 無料 | 燃料費 |
| Bossinkang | 20,000 | 32,000 | 無料 | 無料 | 燃料費 |
| 年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| 公務員 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| 常勤職員 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| 契約職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
臨時職員 (日) |
514 | 1,077 | 597 | 1,395 | 1,064 | 2,748 | 2,265 |
| 新規採用 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 辞職 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 職員合計 |
14人+ 514日 |
18人+ 1077日 |
19人+ 597日 |
21人+ 1395日 |
24人+ 1064日 |
30人+ 2748日 |
36人+ 2265日 |
| 総人件費 | 10,283,089 | 14,273,156 | 16,902,228 | 18,660,780 | 22,147,220 | 24,951,786 | 31,454,863 |
ミシラ漁業センターの雇用構造の変化を見ると、現在同センターが、セネガル国内で重要であることが分かる。
公務員は、1990年の2人から1996には12人に、常勤職員は11人から17人に、契約職員は0人から5人に増加した。
| 近郊地域 | Kaolack | Diourbel | Mbacke | Touba | Thies | Dakakr | |
| 産物供給 | 12 | 1 | 5 | ||||
| 製氷供給 | 223 | ||||||
| 市場仲買 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 車両レンタル | 3 | 4 |
民間販売網は、徐々に発達してきている。
- 近郊の仲買業者は、主にセンター製造の氷を供給している。
- どの市場にも、業者が1つは参入している。
- ダカールの5つの仲介業者は、センターの産物を供給している。
- 車両レンタルは、近郊以外でも発達している。
| 年 |
生産量 (キログラム) |
| 1987 | 159,110 |
| 1988 | 182,617 |
| 1989 | 109,335 |
| 1990 | 182,914 |
| 1991 | 168,195 |
| 1992 | 194,730 |
| 1993 | 142,810 |
| 1994 | 160,201 |
| 1995 | 155,309 |
| 1996 | 132,415 |
人材育成のための活動
1991年から1995年までに35人の若年漁民を訓練した。35人のうち19人が漁業に従事しており、うち16人がミシラで就労している。(下表参照)。
| 年 | 受講者 | 修了者 | 未了者 | 現在の就労状況 | ||
| 漁業 | その他 | |||||
| ミシラ | その他 | |||||
| I期 1991 | 10 | 9 | 1 | 7 | - | 2 |
| II期 1992 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| III期 1993 | 4 | 4 | 0 | 2 | - | 2 |
| IV期 1994 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 2 |
| V期 1995 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 2 |
| 合計 | 35 | 30 | 5 | 16 | 3 | 11 |
1994年以降、一定の社会人を対象にした実践的人材育成のための実習とセミナーがミシラ漁業センターで実施されている(下表参照)。
人材育成
1 漁民訓練生
訓練コースは、若年者を小規模漁業に就労させることにより社会・経済生活に参加させることを目的としている。
これは、同時に、雇用の創出と小規模漁業の発達に貢献する。
ミシラ漁業センターは、1991年から1995年の間に、漁民の訓練コースを5回実施した。
訓練期間:7ヵ月
訓練生の構成とプロフィール:
- 年齢:15歳~30歳
- 身体的・精神的に健常な者
- 教育レベル:フランス語の読み書き、計算のできる者もしくは、アラビア語による教育を受けた者
| 一般訓練(理論) | 技能訓練(実習) |
|
フランス語 基礎保健 漁業経営 航海 HBモーター機械学 地域社会組織 海上での安全 水産品の保存 小規模漁業の規則 |
漁法 水泳 HBモーター技法 航海 |
| 年 | 受講者 | 修了者 | 未了者 | 現在の就労状況 | ||
| 漁業 | その他 | |||||
| ミシラ | その他 | |||||
| I期 1991 | 10 | 9 | 1 | 7 | - | 2 |
| II期 1992 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| III期 1993 | 4 | 4 | 0 | 2 | - | 2 |
| IV期 1994 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 2 |
| V期 1995 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 2 |
| 合計 | 35 | 30 | 5 | 16 | 3 | 11 |
35人の訓練生のうち、30人が実際に訓練を終了した。30人のうち19人が小規模漁業に従事している。就労地は16人がミシラ、3人がミシラ以外である。
| 年 | テーマ | 期間 | 日数 | 共催者 | 参加者 |
| 1994 |
漁法 ヤマハHBモーターの保守と修理 海上実習 |
7月11~22日 | 12日 | ONFP | 漁民9人 |
| 1995 |
定置網の引き上げ方 ヤマハHBモーターの保守 海上実習 |
11月13~23日 | 11日 | ONFP | 漁民8人 |
| 1996 |
手作業による水産物加工: 「衛生と品質」 |
11月4~9日 | 6日 | UNDP |
婦人加工就 労者30人 |
| 1996 |
ヤンマー27cvHBモーター: 予防・保守・修理 |
12月16~21日 | 6日 | ONFP | 漁民14人 |
| 1996 |
小規模漁業用漁具の技法 水産物の技法 |
5月26日~6月3日 | 9日 | JICA |
CNFTPM の生徒14人 |
| 1997 |
漁業経営 ヤンマー27cvHBモーター: 予防・保守・修理 |
7月28日~8月2日 | 7日 | ONFP | 漁民12人 |
| 流し網 | 包囲網 | 釣り竿 | 定置網 | |
|
ヤンマー27cv デイーゼル 漁船員 船長 |
24,531F 36,795F(1.5) |
137,481F 206,220F 船主(1.5) |
||
|
エセンス・ ヤマハ 漁船員 船長 |
37,273F 55,910F 船主(1.5) |
3,360F 5,040F |
ミシラ漁業センターの流し網による平均収入は、サメとエイ、家族消費用の一定量など漁民が保持できる漁種を考慮に入れて算定しなければならない。また、漁船員と家族のための食費(鮮魚一匹当たり平均5,000F)も考慮しなければならない。
このような状況の下、ミシラ漁業センターは雇用を創出、強化するとともに、人口流出を抑制している。
| 借り手 | 人数 | 借入金額 | 借入日 | 月償還額 | 償還回数 | 既償還額 | 償還期限 | 償還総額 |
|
G.I.E. Santa Yalla |
14 |
2,000,000 |
1996/4/19 |
12,820 18,980 |
9 |
1,735,840 |
1997/1 |
2,280,600 |
|
G.I.E. Fass Diom |
15 |
2,000,000 |
1996/4/19 |
12,820 18,980 |
9 | 1,523,400 | 1997/1 |
2,285,100 |
|
G.I.E. Femmesde Missirah |
13 | 1,800,000 | 1996/4/19 |
12,820 18,980 |
9 | 1,566,020 | 1997/1 | 2,054,340 |
|
G.I.E. And Ieef |
15 | 1,500,000 | 1996/4/19 | 12,820 | 9 | 1,269,180 | 1997/1 | 1,730,700 |
|
G.I.E. Fode Senghor |
15 | 1,500,000 | 1996/4/19 | 12,820 | 9 | 1,320,460 | 1997/1 | 1,730,700 |
|
G.I.E. Ibra Niasse |
15 | 1,500,000 | 1996/4/19 | 12,820 | 9 | 1,256,360 | 1997/1 | 1,730,700 |
| 合計 | 87 | 10,300,00 | 1996/4/19 |
償還率は第1期分が100%、第2期分が85%である(1996は不漁であった)。
信用供与は、下表のような動向を示している水産加工活動にも影響を与えた。
| 年 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|
生産量 (キログラム) |
109,335 | 203,814 | 168,195 | 195,730 | 130,458 | 160,201 | 159,468.50 | 142,105 |
運搬面でのもう一つの支援策は、車両輸送に対し補助金を供与することにより、最終加工品の国外市場への輸送と平均販売価格が低い(125F/キログラム)加工用鮮魚の販売を支援することである。

