3 住民の生活向上(ジンバブエ)
(現地調査期間:1997年12月12日~19日)
- 毎日新聞東京本社論説室論説委員 河野 健一
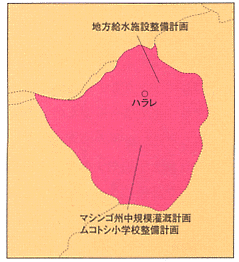
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |
| 地方給水施設整備計画 | 無償資金協力 |
93年度、 7.77億円 94年度、 1.64億円 |
住民の生活を改善するため無償資金協力により深井戸掘削のための機材を供与すると共に技術指導を実施する。 |
| マシンゴ州中規模灌漑計画(第2期) |
無償資金協力 |
90年度、 9.98億円 |
乾燥地帯であるマシンゴ州における農業生産性を高めるため、無償資金協力により灌漸用中規模ダム及びダムから村落の調整池に至る送水路等付帯施設を整備する。 |
| ムコトシ小学校整備計画 | 草の根無償資金協力 |
92年度、 約270万円 95年度、 69万円 |
教育環境を改善するため、草の根無償資金協力によりムコトシ小学校の老朽化した校舎を改修し、教育に必要な機材を供与する。 |
1 調査方針
(1) 目的
南アフリカ共和国におけるアパルトヘイト体制の終焉と黒人政権の成立、アンゴラなど紛争地域における内戦の一応の終息によって、南部アフリカは相対的に安定してきて、新たな発展のチャンスを迎えている。この情勢転換を機に、欧米は資源外交など戦略的視点から南部アフリカ諸国への援助強化に乗り出し、日本も公的援助の対象としてアフリカ重視を強めている。
ジンバブエは南アフリカに先駆け1980年に白人支配を脱して独立し、相対的に安定した政治状況のもとで経済建設に取り組んできた。ジンバブエに対する援助が国づくりにどう貢献したかは、南部アフリカに対する日本の今後の援助政策の構築に当たって多くの示唆を含んでいると思われる。
こうした認識に立ち、相手側政府機関担当者や受益者である住民との率直な意見交換を通じ、事業のニーズ適合性や有効性を「受ける側」がどう評価しているか聞き出し、今後の援助計画の策定、実施に役立ちそうな提言・教訓を引き出すことを今回の調査の眼目とした。
(2) 対象案件
すでに実施ずみの案件から下記の3つの無償資金協力事業を選び、現地調査を行った。
- (1) 地方給水施設整備計画のうち、東マショナランド州UMP地区の深井戸掘削事業
- (2) マシンゴ州中規模灌漑計画のうち、ムサベレワ・ダム建設および送水路など付帯施設整備事業
- (3) ムコトシ小学校整備計画(草の根無償資金協力による事業)
これに加え、ジンバブエに対する技術協力の実効性評価の一環として、日本で研修を受けたジンバブエの専門家3人と、現地で活動している海外青年協力隊員7人に会い、意見・感想を聞いた。
(3) 評価手法
調査では事業サイトの視察、ジンバブエ側受入れ機関の担当者とのインタビュー、受益者である住民からのヒアリングなど現地の生の声、生の情報を可能な限り多く入手することに努めた。援助の有効性を判定するうえで最も重要なのは援助を受ける側の評価であるからだ。
もちろん、公平かつ客観的な評価を行うため、外務省経済協力局やJICA提供の資料に目を通し、現地の日本大使館やJICA事務所の説明を聞いた。これとジンバブエ側から得た情報・意見と突き合わせ、総合的な評価に立って報告書を作成した。
2 個別案件に対する評価
(1) 無償資金協力案件「地方給水施設整備計画」(IおよびII期)
(イ) 案件概要
- 1) 交換公文署名日:1994年1月(I期)および8月(II期)
- 2) 供与限度額:7億7,700万円(I期)、1億6,400万円(II期)
- 3) 事業内容
農業はジンバブエの人口の7割を支える基幹産業であるが、少数の白人が経営する大規模商業農園(commercial land)と多数派の黒人が共有地(communal land)で営む小規模・零細農業の二重構造から成っている。ジンバブエの国土の4分の1は降雨量の少ない高原性乾燥地帯で占められているが、黒人経営の農地はとりわけ乾燥がひどく、地味がやせた地域に集中している。しかも灌漑施設が整っていないため、栽培作物がトウモロコシなど少数品目に限定され、生産性が低いうえ早魅被害を受けやすい状況にある。
電気、水道、道路など産業インフラや生活環境の整備についても同様の二重構造がある。歴代の白人政権は白人居住区についてはこれらの施設を整備したが、黒人農民居住地は無視する方針を取った。独立後もこの植民地支配の負の遺産というべき格差はたいして是正されないまま残っており、経済・社会建設上の最大の課題となっている。
ジンバブエ政府は農村の生活環境改善のため1983年に全国で計36,000本の深井戸を掘削する計画を立て、給水率を55%まで高めた。だが、資金不足と掘削機器の老朽化で整備事業の進捗にブレーキがかかった。さらに92年の大早魅では多数の浅井戸が枯渇した。この旱魃では飢餓など深刻な被害が出た。ジンバブエ政府は安定した水源確保が急務であるとして深井戸掘削を軸とする地方給水施設整備計画を立てた。このうち、約15万人の人口に対し170本しか深井戸のない東マショナランド州ウェザ地区およびUMP地区を対象とした400本の深井戸整備事業のための機器供与(1期)と40本の深井戸掘削による技術指導(II期)を日本に求めてきた。日本政府は無償資金協力でこの要請に応えることを決定し、1期分として車両搭載型掘削機、工具、コンプレッサー、クレーン付きトラック、牽引トラック、ピックアップ・トラック、ワゴン車、電気検層機、水中ポンプ、鋼管ケーシングなどを95年2月までに供与した。さらに深井戸掘削技術の移転のため96年3月までに40本の深井戸を掘削した。 - 4) 相手国受入れ機関:水質源開発省および土地・農業省
- 5) 受益者:深井戸から生活用水を得る周辺農村住民
- 6) 視察対象:技術移転のために掘削した40本の深井戸のうち、首都ハラレの北東約160キロにあるUMP地区ムタワタワ村(Mutawatawa)にある深井戸(深さ80メートル)と井戸水を利用している村落を視察した。現場に向かう途中、郡都ムレワ(Murehwa)の州政府の行政事務所に立ち寄り、担当者から事業の進捗状況や日本の支援の評価を聞いた。
(口) 評価概要
- 1) 目標達成度および事業進捗状況:日本側は約束した機器の引き渡しと40本の井戸掘削による技術移転をすでに終えている。井戸掘削事業は技術移転を受けたジンバブエの技術者によって順調に進められており・ムレワにある州行政事務所の掘削監督官であるJoachim Rashiraji氏の話では、ウェザ地区およびUMP地区の計画目標400本のうち1997年12月現在で309本が完工・供用済みで、残りの井戸も98年末までに掘り終わる見込みという。目標達成度および事業の進捗状況は満足すべきものといえる。
- 2) 事業の必要性:郡都ムレワまでは舗装道路であったが、そこから先は未舗装の凸凹道だった。UMP地区は花岡岩が円蓋状に露出した丘陵地帯で、ところどころ小川が見られたものの、概して荒涼とした風景であった。道路沿いには伝統的な泥壁に茅葺きの丸小屋から成る集落は散見され、電気も通じていない後発地域である。
ジンバブエの近代化は都市部および白人経営の大農園や鉱山周辺にしか及んでおらず、これ以外の地方は未開発のまま取り残され、一つの国の中に近代社会と前近代社会が並存するモザイク構造となっている。しかもジンバブエの人口の7割以上は地方の農村部に集中している。給水事業は近代化から取り残された地方の住民の生活向上に直結する事業であり、生命維持に不可欠な水の安定供給につながる深井戸掘削は人道的見地からも現地住民の切実な願いに適つた支援といえる。 - 3) 全体的な評価:まず、ムタワタワ村の住民の評価は極めて高い。「日本からの客」と聞いて、村の主婦たちが盛装して我々を出迎えてくれた。住民の話だと、井戸ができる前は往復5時間かけて7キロ離れた川まで水汲みに行くのが女性たちの日課だった。川の水は野牛、ヒヒ、象など野生動物と共用で、水質は極めて悪く、乳幼児は下痢などに悩まされた。その川も旱魃時には枯れ、飲み水に不自由する苦労が続いたという。
深井戸が完成して村の生活は一変した。村の人口は250人ほどで、居住地は井戸から500メートル以内にある。このため水汲み作業に費やす労力は劇的に軽減され、女性たちは浮いた時間を農作業や家事に振り向けられるようになった。いつでも清潔で冷たい水を入手できるようになって心身両面で大きな解放感を得たし、下痢など乳幼児の病気も減った。深井戸には洗濯場も設けられ、女性たちの新しいコミュニケーションの場となっている。
住民の1人で、井戸の維持管理委員会のメンバーでもあるEnesia Nyazemaさんの家を訪ね、台所を見学した。家は井戸から徒歩で約10分の高台にあり、4棟の丸小屋から成っていた。その1棟に家族全体のための台所があった。台所には井戸から汲んだ水が大きなプラスチックのバケツにたくわえられていて、この水を炊事に使うとのことであった。「川への水汲みに午前7時から正午までかかっていた以前に比べ、井戸ができたお蔭で日々の暮らしは格段に楽になった」と彼女は何度も感謝の言葉を述べた。素朴な農婦の言葉は作りものではないと判断できる。
井戸1本で村の生活に革命的変化が生じたわけで、費用対効果から見ても極めて効率のよい援助事業といえる。事業の全体評価も非常によい。
土地・農業省のチチコ次長と水資源開発省のチョが部長は、日本が供与した機器と伝授した深井戸掘削技術の双方に「欧米をしのぐ高い水準」と折り紙を付けた。ノルウェーなど欧州の国もジンバブ工で井戸を掘ったが、せいぜい深さ60~80メートル程度のものであり、100メートルを超す深井戸掘りの技術は日本の独壇場という。
今回の無償援助に先立って、1983年にジンバブエの水資源開発事業が発進した直後に日本は2基の掘削機、4台のトラックなどを持ち込み、80本の深井戸を掘った。この作業を通じて井戸掘削技術を伝授した。その掘削機を使ってこれまで6,000本の井戸を掘ったが、機械は今でも立派に動いており、極めて耐久性が高いとのことであった。89年に日本は深さ750メートルまで掘れる新型掘削機を追加供与したが、92年、93年の旱魃で浅井戸が枯れたとき、この機械を投入して3か月間に67本の深井戸を掘り、被災地の窮状を緩和できたという。今回の追加支援で日本から供与された機器や車両を使うことによってジンバブエの深井戸の掘削技術がさらに向上し、給水事業が順調に進展することを期待していると、チチコ、チョガ両氏は述べた。
深井戸のサイト視察は1か所のみだったが、ムタワタワ村の住民の声と受入れ政府機関の担当者とのインタビューから推して、給水施設整備事業が全体として高い評価を受け、感謝されていると見てよい。 - 4) 施設の維持管理:ムタワタワの井戸の管理態勢についてムレワの行政事務所で調整担当副部長のColison Maricumo氏と女性フィールドオフィサーであるFloritan Chirazuさんに聞いた。
ジンバブエの農村では伝統的な共同体組織が今も機能しており、これが中心となって井戸の維持管理に当たっている。ムタワタワ村では村長が責任者になって住民の中から選ばれたメンバーで管理委員会を結成している。委員は任期1年で、動物の侵入防止のために井戸周辺に設けられた柵や手動ポンプの点検・修理を行っている。手動ポンプの部品は国内調達でき、簡単な故障は村の住民が修理するという。難しい保守・修理作業は行政事務所駐在の技術者が行う。現場で見た限り、井戸はきちんと作動しており、柵で囲まれた水汲み場や共同洗濯場は除草や掃除が行き届き、住民が給水源を大切にしていることがうかがえた。 - 5) 提言:12月はジンバブエの夏であり、本来なら雨季に当たるが、1997年も旱魃気味だとかで、ムタワタワ村の畑のトウモロコシはほとんど育っていなかった。
生活用水と併せて、灌漑面でも山間部の農村を助けることができれば、日本の援助効果は一層、高まる。ダムや用水路を建設するのが地形や経費の面で無理であるなら、深井戸を水源にしたスプリンクラー方式の灌漑施設の整備を検討できないだろうか。スプリンクラーや加圧ポンプを動かすには電気が必要であるが、日本が得意とする太陽熱発電技術を導入すれば、電力問題はクリアーできるのではないか。
ジンバブエの発展段階に則して援助の質的進化を図る必要がある。これまでの給水、灌漑、医療、教育といった部門別の縦割的な援助のやり方を見直し、複数の分野を束ねた複合的な援助方式の導入を見当すべき時期ではないだろうか。ODA予算は限られているので、こうした新方式の援助を広範囲にわたって実施するのは不可能であろう。ならば、幾つかの地点に絞ってモデル・プロジェクトを実施すればよい。その有効性が確認きれれば、他の援助供与国に同様プロジェクトの実施を働きかけることも可能ではないか。
(2) マシンゴ州中規模灌漑計画(全V期のうちII期分)
(イ) 案件概要
- 1) 交換公文署名日:1990年7月10日
- 2) 供与限度額:9億9,800万円
- 3) 事業内容
ジンバブエの南部に位置するマシンゴ州はとくに降雨量が少ない乾燥地帯で、年間降雨量は600ミリにすぎない。このためコミュナルランドにおける小規模農業の生産性は極めて低く、旱魃被害が頻発している。
ジンバブエ政府は独立以来、白人政権が無視してきたコミュナルランドの灌漑施設整備を進めてきたが、資金面で事業推進に限界があるため、マシンゴ州中規模灌漑計画の一環として6つの灌漑用中規模ダムの建設とダムから村落の調整池に至る送水路など付帯施設の整備について日本に協力を要請した。これと併せ、ダム建設や農作物の圃場造成に必要な機械の供与も求めてきた。日本政府は無償資金協力で要請に応じ、I期からV期に分けて事業を実施した。 - 4) 相手国受入れ機関:土地・農業省および水質源開発省
- 5) 受益者:農家109所帯、住民合計740人。灌漑農地は計38ヘクタール(これは視察対象ダムの受益地区のみの数字)
- 6) 視察対象:視察したのはII期に行った事業で、対象はマシンゴ州(Masvingo)南西部の山間地に位置するムサベレマ(Musaverema)に建設されたダムと、そのダムで灌漑されたムサベレマ村の営農実態である。ダムと付帯施設は完工・供用開始ずみ。ダムは堤長1,800メートル、堤高13.2メートルのロックフィル式、満水時の有効貯水量は665万トンである。ダムと農地は全長7キロのサイフォン式送水路で結ばれている。ダムから引いた水は村内に設けられた調整池に溜められ、小規模の用水路を通じて畑に導かれる。ダム、送水路、調整池の建設までが日本の援助で実施され、その他の施設はジンバブエ側の負担で整備された。
ダムと村は州都マシンゴ市から南アフリカ国境に向けて南下する幹線道路から未舗装の道に分け入った奥地にあり、ジンバブエ人の運転手が何度も道に迷う僻地だった。マシンゴからダム到着までに車で4時間近くかかった。地方給水施設計画の調査で訪れた、ムタワタワ村と同様、村には電気が通じておらず、村に設置してあった送水用ポンプはエンジン駆動の発電機で運転していた。
(口) 評価概要
- 1) 目標達成度および事業進捗状況:水資源開発省マシンゴ州事務所の水利技師であるAlois Chamiti氏によれば、計画は順調に実施された。
- 2) 事業の必要性:チチコ氏提供の論文(同氏が国連食糧農業機関(FAO)に提出用に準備中だった論文の草稿)に詳しく説明されているように、農業が国内総生産(GDP)に占める比率はおよそ15%で製造業の32%に及ばないが、全人口の約70%を支え、輸出の45%を稼ぎ出す基幹産業である。
しかしながら、農業の二重構造はジンバブエの経済建設と社会発展を妨げる障害となっている。大規模商業農園が煙草、綿花、大豆、トウモロコシ、野菜、果物など多様な作物を栽培し、牛、羊の大規模放牧も行って世界屈指の高い生産性をあげているのに対し、黒人共有地における零細農業の栽培品目はトウモロコシなどごく少数に限定され、生産性も極めて低い。未灌漑地域では自家消費の食糧をまかなうのが精一杯で、旱魃時の被害も大きい。
ジンバブエの発展のためには黒人経営の農業の底上げが不可欠であり、それを実現するには、灌漑施設の整備を行わなければならない。後述のムサベレマ村の農民からの聞き取り調査結果が示すように、またチチコ氏の論文で指摘されているように、灌漑施設の整備は生活用水供給施設の整備にもまして、農村に革命的変化を及ぼす。ジンバブエは降雨量を除けば日照、温度など農業に適した自然条件に恵まれている。灌漑施設が整備されれば、一毛作だったトウモロコシは三毛作が可能になり、生産性は4~5倍にもはね上がり、それに応じて所得も飛躍的に伸びる。栽培できる作物の種類も多様になり、ビタミンに富む野菜の栽培は食生活を豊かにして住民の健康増進につながる。野菜類はトウモロコシなど穀物に比べて付加価値が高いので、輸送手段と販売市場が確保できれば、さらなる所得増を実現できる。
農業の生産性が急上昇すれば、同じ耕地面積が養える人数は増える。この結果、雇用創出効果によって農村部の失業が緩和でき、都市への人口流失に歯止めがかかる。また、旱魃時には周辺の被災地に食糧を供給する救援センターの役割も果たせる。所得が増えれば子供を学校に通わせる余裕が生じ、識字率の向上と労働力の質的向上が期待できる。
このように灌漑施設の整備は一石二鳥・三鳥の効果が期待でき、事業の必要性は極めて高い。日本がこのプロジェクトを応援したのは、ODAの趣旨に合致すると判断する。ただし、後述するように、世界屈指の豪著な生活を享受している白人支配層は黒人居住地の農業振興と生活環境設備をもっと支援すべきではないか、という疑問は残る。 - 3) 全体的評価:灌漑施設はムサベレマの農民に多大な恩恵をもたらしていた。訪問時、畑ではトウモロコシが栽培されていたが、村民で構成する施設管理委員会の委員長であるVengai Shoriha氏によれば、以前は一毛作だったのに、灌漑後は三毛作となった。畑0.1ヘクタール当たりの年収は諸経費を引いたネットで約2,000ジンバブエ・ドルと以前の4~5倍になったという。.村では人参、タマネギ、トマトなど野菜類の栽培も始めていた。いまのところは自家消費と周辺住民への供給にとどまっているが、都市部に市場を開拓する計画を立てている。ムサベレマ村はこれまで何度も灌漑被害を経験した。ダム建設によって安定した農業経営が可能になったことが住民にとって最大の恩恵である。住民は増えた所得を貧弱な家の増改築や子供の就学費用、被服費などに充てているとのことであった。Shoriha氏の家を訪ねたところ、両親用の小屋を新築中だった。同様の経済効果は灌漑施設が整備された全農村に及んでいると見てよい。
チチコ次長によれば、灌漑による農業の生産性向上は控え目に見積もって4~5倍になる。1ヘクタールの農地が養える人数は40~50人に増え、村の住民ならず周辺地域の労働力を吸収でき、失業の緩和と都会への人口流出防止につながる。野菜栽培の所得増加効果は極めて大きい。1ヘクタール当たりの年収はトウモロコシだと700ジンバブエ・ドルだが、野菜だと20倍の14,000ドルになる。ただし、輸送手段の欠如(輸送手段があってもコストが高い)や市場開拓が壁となっている。また、灌漑された農村では、鶏などの飼育による食肉生産や貯水池を利用した養魚など生産活動の多様化が始まっているという。
ムサベレマ村での実態視察、住民からのヒアリング、チチコ次長とのインタビュー結果を総合して、中規模灌漑事業への支援は現地のニーズに合致し、多大の成果をあげていると判断できる。ただし、ジンバブエ全体で1,600万ヘクタールに及ぶ小規模・零細農地のうち、灌漑されているのはわずか9,000ヘクタールにすぎない。灌漑事業はまだ初期段階にあり、ジンバブエの発展のためには今後、さらに規模を広げて推進する必要がある。 - 4) 施設の維持管理:ダム本体と送水ポンプなど付帯設備はマシンゴ市の水資源開発省と土地・農業省の出先事務所が維持・管理している。ダム脇には管理棟が設けられ、堤の下には動物の侵入防止の柵が張られ、我々が視察した時も監視員が巡回していた。堤に生えた草を動物が食い荒らすと、堤が脆くなるからだ。
調整池と用水路は村の住民で結成した管理委員会が維持・管理に当たっている。委員会は委員長以下7人から成り、選挙で選ばれる。ムサベレマ村にとって灌漑農業は「初めて体験する新しい文化」であり、施設の共同管理の必要性も含めて住民に対する啓蒙・宣伝活動が委員会の重要な仕事である。このため、委員会の下に宣伝、新種の農作物の市場開拓などを任務とする小委員会が設けられ、事実上、住民全員の参加による施設の維持・管理と村おこしの努力が行われている。こうした活動の軸になっているのは、ムタワタワ村と同様に伝統的な共同体組織であり、とくに女性が農作業でも施設の維持管理でも中心的な役割を果たしている。今後、新規の灌漑施設支援事業の実施に際して、対象村落に事前の趣旨説明や啓蒙活動を行う場合、女性を重視する必要があろう。
施設の維持管理は概ね適切に行われているようであったが、現地で会った巡回技師によれば、送水用ポンプの予備部品が不足しているとのことだった。現在はまだ設備、機器が新しいので問題が生じていないが、今後、年数の経過とともに故障や部品交換の必要が増えてくる。その将来への備えができていないことに懸念を感じた。フォローアップ調査のため現地訪問中だった三祐コンサルタンツの杉本氏は、「予備部品は援助予算の中に組み込まれているが、施設の修理や部品購入のための修繕積立を始めるなど、今後に向けて住民が自助努力を強める必要がある。家を新築するカネの一部を積立に回すよう、住民を啓蒙すべきだ」と指摘した。傾聴すべき意見である。 - 5) 教訓と提言:チチコ次長によれば、灌漑施設が建設された直後、住民の間に住血吸虫症をはじめ感染症が広がるケースが多発した。調査の結果、便所が整備されていないので、感染症を持つ者の排便が用水に流れ込む。その水を他の住民が飲用し、連鎖的に感染が広がったことが判明した。ジンバブエ政府はこれを教訓にして、灌漑施設を整備する際、便所と用水路の間に十分、距離を置き、また、灌漑用水を飲用に供しないよう指導しているという。しかし、長年、天水を飲用してきた村落の住民にすれば、「灌漑用水を飲むな」と言われても、納得しにくい面があるだろう。援助供与国は灌漑施設の整備に際して、農業用貯水池の水を飲用に供せるよう、飲料水用の浄水装置や配水管、共同水汲み場も併設すべきではないか。また、衛生知識の普及活動も助けてやるべきだ。給水施設の項で述べたのと同様、ここでも土木・建築と医療・衛生という異なる分野を統合した横断的・複合的援助が求められているように思える。
既に指摘したように、灌漑農業は地方の農民にとって「新しいカルチャー」であり、最大限の開発効果を引き出すには住民への啓蒙・教育活動というソフト面からの補強が必要である。チチコ次長は住民教育のために、農民を対象とした長期研修センターを日本の支援で地方に整備したいとの希望を表明した。センターでは灌漑施設の維持管理法、新しい作物の栽培法、肥料・農薬・種子の管理に関する知識、小型農機の扱い方、生産物の品質管理と市場開拓といったテーマの研修を実施する。
研修所には宿泊施設を設け、研修は数か月単位の長期にわたって行う。近隣農村から研修生を受入れ、修了者はそれぞれの村で新知識普及の先頭に立ってもらうというのが、チチコ次長の構想である。灌漑設備支援事業のフォローアップとして、日本はこの要請に応えてよいと思う。経費に限りがあるであろうから、1~2か所に絞ってモデル・ケース的に実施すればよい。「広く、薄く」資金を投入しなければならない場合もあるであろうが、少数の事業に資金を集中的に投入して、受益国で話題となるような突出したモデルを構築することも援助政策として有効ではないだろうか。一点集中式援助は受益側国民に日本のイメージを強く印象づける効果があると思う。
(3) 草の根無償資金協力「ムコトシ小学校整備計画」(I期およびII期)
(イ) 案件概要
- 1) 贈与契約締結日:1993年2月26日(1期)および96年3月13日(II期)
- 2) 供与限度額:20,912米ドル(1期)、7,010米ドル(II期)
- 3) 事業内容
ムコトシ小学校はマシンゴ州の州都マシンゴから南西に車で約1時間30分の農村部にあり、隣接地に中学校(secondary school)も併設されている。1956年創設で、1年生から7年生まで517人が通学し、教職員はFred Chomutare校長以下13人、校舎は5棟、教室数は11である。校舎が老朽化し、屋根に穴が開くなど傷みがひどくなったが、貧しい父母には校舎修理資金が出せなかった。州知事は日本大使館を通じ校舎改修工事の支援を要請し、日本側は草の根無償資金協力で対応した。
工事は1993年6月から94年4月までのI期と、96年4月から同年11月までのII期に分けて実施された。I、II期を合わせて、校舎棟の屋根のトタン張替え、屋根を支える棟木の交換、壁の塗り替え、学校の回りの防護フェンス設置、児童用勉強机と長椅子の購入、教職員用の机・椅子の購入、黒板の据付、サッカーおよびネットボール用のゴールポストの設置が実施された。 - 4) 相手国受入れ機関:ムコトシ小学校
- 5) 受益者:ムコトシ小学校の児童、教職員、児童の父母
- 6) 視察対象:ムコトシ小学校。訪問時、学校は夏休みだったが、教職員全員と30人余りの父母が我々を出迎え、ジュースや鶏肉料理などを用意して歓迎パーティを開いてくれた。児童も10数人、学校に遊びに来ていた。チョムターレ校長にインタビューしたほか、他の教員や隣接の中学校の校長、父母から地域の教育事情、日本の援助に関する感想を聞いた。
(口) 評価概要
- 1) 目標達成度:計画分の事業は完了している。改修前はろくに家具がなかった教室内には黒板、長机、長椅子などが据付られていた。職員室も執務机などがそろい、整理整頓が行き届いていた。ただし、同校には予算の関係で改修できなかった校舎が1棟(3教室、1事務室)残っている。屋根には穴があき、窓ガラスも破れ、授業には使われていない。校長はこの棟の改修についても日本の支援を希望していた。
- 2) 事業の必要性:義務教育施設の整備は本来、州政府など公的機関がやるべきことであり、日本の支援を仰ぐのは他者依存の嫌いがないわけではない。しかし、植民地支配の負の遺産は教育分野にも残っており、白人政府は黒人のための教育をないがしろにした。そのため、地方の黒人居住区における教育施設の整備は遅れているし、マシンゴ州政府の財政に余裕がないことも確かなようである。ジンバブエ政府が義務教育を有料化したことも、貧しい家庭にとって大きな負担となっている。ムコトシ小学校に子供を通わせている約180所帯はトウモロコシ栽培の農家であり、所得水準が低く、授業料に加えて校舎改修費を拠出する余力がないのも事実である。こうした事情を考慮すれば、同校の校舎改修事業を草の根無償資金協力の対象にしたことは、妥当であったと言えよう。ただし、給水事業の項でも指摘したように、過去の植民地支配の弊害を是正する意味でも、富裕白人層が義務教育施設の整備に資金援助を行うべきではないか、という疑問は残る。
- 3) 全体的な評価:チョムターレ校長は1986年に赴任したベテランで、教職員や父母の尊敬を勝ち得ている人格者とのことだった。マシンゴ州知事が同校を選んで日本に資金援助を要請したのも、校長の人物・力量を見込み、州内僻地のモデル校にしたいとの意図からではなかったかと推定される。校長は小切手による支払い内容や日付、改修工事の内容や購入家具の内訳など実に几帳面に記録を取っており、そこから抜粋した資料を我々に手渡した。改修の効果についても丁寧に説明し、何度も謝意を表明した。日本の尽力は校長を通じて父母たちによく理解されており、懇親会では感謝の言葉が相次いだ。校長は日本との縁をさらに深めるとともに、同規模の日本の学校と姉妹関係を結び、手紙や絵の交換などを通じた交流を行いたいとの希望を表明した。これほど心底から感謝されている以上、援助は成功であったと言えよう。
- 4) 施設の維持管理:教職員と父母が協力して校舎を管理しており、問題はない。
- 5) 提言:ムコトシ校にさらに日本の援助を集中的に注ぎ込み、教育支援のモデル校にすることを提言したい。日本からは90人を超える派遣教員がジンバブエに送り込まれている。教員たちはそれぞれに頑張っているが、多くの学校に分散配置されているため、その貢献度がジンバブエ国民に必ずしもはっきりと認識されていない嫌いがある。ムコトシ校をいわば一点集中的に支援し、他州にも知られるような教育内容の充実した学校に育てていけば、「日本はなんと教育に熱心なことか」と話題を呼び、日本のODAを強く印象づけることになると思う。
当面の具体策として次のような事業を提案したい。
- (i) 残る1棟の改修を支援する。
- (ii) ジンバブエの子供は音楽が好きだが、ムコトシ校には楽器がほとんどない。校長が要望するマリンバ、エレクトーンを寄贈し、地域の音楽教育のモデル校にする。マシンゴ市内の学校には日本から音楽担当の教師が派遣されている。この教師に月に2~3回程度、ムコトシに出張してもらい、同校の教員に楽器の奏法を教授してもらう。できれば、野球やソフトボールなどスポーツ担当の派遣教師の出張指導があれば、学校のカリキュラムは一層、多様になるだろう。
- (iii) 姉妹校についても、JICAが日本の新聞社に協力を要請して、子供向けの新聞紙上で呼びかければ、必ず応募があるはずだ。
- (iv) 娯楽の少ない農村であるから、日本式の運動会や学校のグラウンドを利用した盆踊り大会などを開催すれば父母も取り込んだ地域ぐるみの日本キャンペーンになる。
- (v) ムコトシ小学校の卒業生を対象に奨学金を創設し、毎年1名を選んで大学など上級学校に進学する道を開いてやる。ライオンズ・クラブなど日本の民間団体に資金協力を求めることも可能であろう。
3 総括的提言
(1) 援助をめぐるジンバブエと日本、日本の政府と国民の間にある認識ギャップに関する提言
ジンバブエに対する援助を論じる場合、同国の二重構造は避けて通れない問題である。白人支配層は世界でもトップクラスの高い生活水準を享受しながら、人口の大多数を占める黒人住民の生活向上には意を配らず、飲用水確保のための深井戸一つ掘ってやらなかった。黒人たちは川や沼の水を野生動物と共用で飲んだ。白人にとって、黒人は動物並の存在にすぎなかったのだ。この過酷な植民地支配が今なお残る二重構造の根源である。
ジンバブエの現政権は土地や企業の接収といった手段で、資産・富を強制的に再配分すれば大規模な白人の国外流出をもたらし、結果として国内経済が窮地に追い込まれるとの認識に立ち、穏健な段階的改革路線をとっている。この路線はそれなりに合理性を持っているが、植民地時代以来の白人の特権的地位と利権を温存する結果にもなっている。
河野はチチコ次長をはじめジンバブエの政策担当者とこの問題を論じた結果、二重構造の解消が息の長い仕事にならざるを得ず、旱魃や飢餓など当面の問題に取り組むには日本など先進国の援助を求めざるを得ない苦しい内情がよく分かった。
しかし、大多数の日本国民にとってアフリカは未知の遠い大陸であり、まして植民地支配の負の遺産の清算がいかに難しいか、ほとんど理解されていない。素朴な国民感情からすれば、自分たちよりも遥かに贅沢な生活をしている白人富裕層がいるのに、なぜ日本国民の税金でジンバブエの経済建設を支援しなければならないのか、富裕な白人にカネを出させればよいではないか、という疑問が生じるのも無理はない。
河野はチチコ次長との対談内容を「開発と援助」のテーマでまとめ、毎日新聞に掲載した(1998年2月16日付朝刊「争点・論点」欄)。この記事に対して、読者から封書や電子メールで複数の感想文が寄せられたが、そのほとんどは黒人層の貧苦をよそに富をむさぼる白人支配層の偽善と狡猾さに対する素朴な憤りを表明した内容であった。チチコ氏やチョが氏の苦衷の思いは記事で伝えたつもりだったが、読者には十分に分かってもらえなかったようだ。
この「彼我の認識ギャップ」をどう埋めるかが、ジンバブエや類似の二重構造を持つ国々を対象にしたODAに国民の理解と支持を取り付けるうえで、最大のポイントであろう。
日本政府が今後、対アフリカ支援を強めるのであれば、国民レベルでのアフリカ理解を高めていく努力が必要であろう。外務省がからんだものも含めて、欧米や中国、東南アジアなどをテーマとするシンポジウム、講演会は頻繁に開かれるが、アフリカに関するものは皆無に近い。JICAの帰国協力隊員や専門家、アフリカ諸国の在日大使館、あるいは日本で学んで第一線で活躍している人たちなど幅広い協力を得て、アフリカを知ってもらうキャンペーンを展開すべきだろう。アフリカには先進国で失われた豊かな人間性が残っており、それに直に触れると多大の魅力を感じる。河野も初めて南部アフリカを訪ねて、文明の毒にスポイルされていない人々の心情の優しさ、虚飾のなさに魅かれた。アフリカ・キャンペーンは、工夫さえすれば、多大の成果をあげられると思う。
(2) 日本の援助政策の長所と短所
チチコ氏をはじめ現地でインタビューしたジンバブエの農業開発担当者に、欧米など他国と比較しての日本の援助の長所と短所を聞いた。
長所として指摘されたのが、ジンバブエ側の要望や意見に耳を傾け、それを援助内容や実施計画に取り入れようとする姿勢だった。欧米には「受入れ国は供与国の方針に従うのが当たり前」という風潮が強く、ジンバブエの担当者との間でしばしば険しい対立が生じるという。
大規模経営が主流の米国や英国と違って、日本は自国の農業が小規模経営主体であるので、ジンバブエのコミュナルランド農業が直面する問題を直観的に理解してくれるのではないか、との指摘もあった。日本にとってアフリカは植民地支配で手を汚していない処女地である。欧米とひと味違ったソフトな姿勢を今後も維持すべきだろう。
短所としては、援助の要請を受けた後、計画の立案、決定、実施までに時間がかかりすぎるとの指摘があった。官僚制はどの国にもあることとはいえ、緩急序あり、ケース・バイ・ケースで迅速な処理を要する案件には、それなりに対応したい。
援助実施後のフォローアップ・サービスも日本の援助の長所として高く評価されている。今後とも継続し、フォローアップで得られた情報を後の援助にフィードバックすることが肝要であろう。
(3) 重点主義、傾斜路線の勧め
アフリカは広く、援助を必要とする国も数多い。一つの国をとっても、援助対象となる分野が限りなくある。低成長と財政改革の時代を迎え、日本のODA予算と取り巻く環境は今後、厳しさを増す。
そこで、対アフリカ援助を展開するに当たって、「広く、浅く」の総花小割り主義ではなく、資金を「狭く、深く」配分する傾斜注入路線を採るべきではないか。もともと欧米の影響力が強いアフリカで、独自色があり、しかも受入れ側に強いインパクトを及ぼす援助を行うには、事業を厳選し、資金を重点配分するのが得策であろう。
幾つかの具体案は個別評価の「提言」の欄で示したが、日本が得意とするものと受入れ側のニーズをきっちり照らし合わせ、量より質のプロジェクトを組む[眼力」が、効果のある援助を可能にする決め手の一つではないだろうか。
4 技術協力をめぐる感想と提言
(1) 趣旨
ジンバブエ滞在中、日本での研修経験者および現地赴任中の青年海外協力隊員と面談した。研修経験者からは、(1)日本での研修内容とその成果、(2)改善に向けての希望や注文…を聞いた。また、協力隊員からは(1)活動内容とその成果、(2)直面している問題や課題、(3)JICAや受入れ国への希望や注文…を聞いた。その中から、今後の参考になりそうなものを抜粋、紹介する。
(2) 帰国研修生の意見と要望
面談した研修経験者は以下の3人である。
David Mfote 男性。土地・農業省で灌漑事業を担当する文官。
Sophia Tsvakwi 女性。水資源開発省で土地利用計画の立案を担当する文官。
Alois Chamiti 男性。水資源開発省マシンゴ州事務所で灌漑事業を担当する技官。
3人とも整備の行き届いた日本の農業インフラに強い印象を受け、また、日本の農業の主流が小規模経営であることに親近感を覚えたとのことであった。
3人の評価では、視察先の選定は概ね適切で、技術者であるChamiti氏の場合、日本のサイフォン式水路やロックフィル式ダムの視察が参考になったとのことだった。
3人の意見、希望は以下のように集約できる。
- (1) 日本の農業経営の実態をもっと詳しく知りたい。栽培作物の種類、肥料や農薬の使い方、産品の貯蔵・輸送・販売の仕組み、農協など共同組織の役割、灌漑施設の維持管理などを学ぶため、農村に一定期間、滞在したい。
- (2) 農民のほか、日本の普通の市民と触れ合う機会がもっとほしい。
- (3) 日本のよい面だけでなく、貧しい人々の居住地や治安の悪い所なども見たい。
- (4) 英国など欧州諸国での研修には2年、3年の長期に及ぶものがある。日本も長期研修制度を創設してほしい。それが無理なら、せめて滞在期間を数か月程度に延ばしてほしい。
中国や東南アジアと違って、アフリカは遠い。日本で研修を受ける機会はおそらく一生に一度のチャンスであろう。農村での生活体験など研修期間の延長を検討してもよいではないか。
(3) 協力隊員の意見と要望
面談した協力隊員は下記の7人である。
近松 佳郎 コンピューターのプログラム技術者。ジンバブエ大蔵省勤務。
後藤 理 体育担当派遣教師。野球・ソフトボール指導。
西端 慶也 音楽専門家。教育スポーツ省で音楽教育のシラバス作成を担当。
中田 一昭 NTT派遣の技術者。電話回線設置を指導。
松本 廣年 福井三菱自動車派遣の技術者。車検業務を指導。
古川 淳也 体育担当派遣教師。体育一般を指導。
千葉 幸恵 音楽担当派遣教師。マシンゴ市内の中学校勤務
隊員たちはいずれも意欲旺盛で、現地社会に溶け込み、使命感を持って職務に取り組んでいるとの印象を受けた。国境の壁を軽々と超えてやりたいことをやる若者たちの思い切りのよさに、河野も含めた中高年世代との違いを感じた。
隊員たちの意見と要望は下記のように集約できる。
- (1) 欧米諸国の援助事業と比べると、日本の事業はプレゼンス感が薄く、ジンバブエのマスコミに取り上げられることも格段に少ない。本当に必要な援助かどうか、首を傾げる案件もある。対象をもっとピンポイントに絞るべきだ。援助内容のスクラップ・アンド・ビルドが必要。
- (2) ジンバブエの国民は概して几帳面で、基礎的な技術力もあるが、積極性に欠ける。指示された事はそれなりにこなすが、自ら進んでやる意欲が足りない。自主性、積極性を育てるような援助が必要。
- (3) ジンバブエの国民には物を大事に使う気持ちが欠けている。壊れれば、修理もせずに放置するので、無駄が多い。すべての案件で機器、用具の維持管理の大切さを徹底して教え込むことが必要。
- (4) 学校の予算が少なく、父母が貧しいので、ささやかな備品の購入やイベントの開催に苦労する。野球の学校対抗試合をやろうにも、会場までのバス代が払えない。本来の業務遂行に伴う派生費用も援助計画に織り込んでほしい。
河野からは、隊員たちの待遇改善を提言したい。第一に、在勤中に隊員に渡す金額を引き上げるべきだと思う。JICAは「協力隊員はボランティア」という前提に立ち、給与ではなく、生活に必要なだけの額を支給する方針をとっている。ジンバブエの場合、隊員に支給されるのは月額410ドル。これに加え、帰国後の当座の生活維持のために日本の留守口座に月額9万9,700円が積み立てられている。
しかし、隊員の半分は教員などの職を辞めて入隊している。「得べかりし利益」の喪失や帰国後の再就職の難しさなど多大の経済的犠牲を払っている。「ボランティア活動だから」という建前論だけで、その犠牲に目をつぶるのは現実的ではない。職場を辞めて入隊してきた者に対しては、せめて月々の積立金を大卒初任給程度に引き上げてやるべきだ。大学を休学してきた学生隊員や復職が可能な企業派遣隊員との間で処遇上の差異が生じるのは止むを得ない。
第二に、協力隊活動への参加と任務を終えた帰国隊員の再就職が容易になるよう、関係機関や民間企業への働きかけを強めるべきだ。
協力隊参加のための休職を認めている企業は1,097社にとどまる。教員を含む地方公務員についても、休職など身分措置を認めている自治体はまだ限られている。世界各国で活動している隊員約2,000人の半数が退職者であり、その中には多くの「元教員」が含まれている。
ドイツなどでは、海外で協力隊と同様の活動をしてきた者はプラス・アルファの評価を受け、再就職が難しくないと聞く。自治省、文部省、通産省などの関係省庁、経団連など経済団体へ働きかけ、隊員たちの帰国後の人生設計が容易になるような環境づくりに力を入れてほしい。日本の学校ではいじめや非行、犯罪の広がりが問題になっている。派遣教師としてアフリカなどでたくましく生きてきたタフな精神を持つ教師こそ、「荒れる学校」の立て直しに打ってつけの人材ではないか。帰国隊員には企業にとっても有用な人材が多いはずだ。
JICAは協力隊への入隊PRだけでなく、帰国隊員の生活設計支援にもっと力を入れるべきであろう。
(注)評価調査実施後のフォローアップ状況
(1) マシンゴ州中規模灌漑計画
97年度に再活性専門家の派遣、および98年度にポンプ部品等資機材購送を実施済。
(2) 青年海外協力隊
- (イ) 進路相談カウンセリング体制の強化9年度→10年度→11年度
- (a) 平成10年度・11年度進路相談カウンセラーの増員(10名→15名→18名)
- (b) 「帰国隊員進路相談マニュアル」の作成・配布
- (口) 進路関連情報の充実
- (a) 進路情報ニュースレターの発行
- (b) 国際協力分野、大学(院)及び留学関連情報誌の配布
- (ハ) 関係省庁との連携・協力
- (a) 外務省から全省庁に対し、現職参加促進及び帰国隊員の積極活用について依頼
- (b) 文部省から各県教育委員会に対し、現職参加に関するアンケート調査実施。
- (c) 全国教育委員会人事担当課長会議において教員の現職参加促進と帰国隊員の教員としての採用促進について発言を得る
- (d) 労働省から各都道府県知事に対し「青年海外協力隊員就職支援事業実施要領」に関する通達発信。
- 各都道府県に帰国隊員の就職相談を重点的に行うための「重点ハローワーク」設置
- 帰国を控えた隊員に対する求人情報等の送付
- 帰国隊員に対するきめ細かな職業相談、職業紹介の実施
- 現職参加制度普及のための啓発活動の実施
- JICA国内機関等が実施する進路相談への協力
- (二) 民間企業への働きかけの強化
- (a) 企業懇談会を通じた帰国隊員に対する就職支援、現職参加の促進依頼(経団連等)
- (b) 帰国隊員採用実績企業に対する「帰国予定隊員名簿」の送付による求人開拓
- (ホ) 地方自治体への働きかけ教育委員会への現職参加促進、帰国隊員採用促進に関する働きかけの強化
- (へ) その他
- (a) 帰国隊員の就職に関する意識調査の実施
- (b) 共済会資金による帰国隊員を対象とする奨学金制度の確立
- (c) 国際公務員に関する説明会を訓練中の隊員候補生を対象に実施

