2.水資源の有効利用(ヨルダン)
(現地調査期間:1997年11月29日~12月5日)
- 宇都宮大学国際学部教授 清水 学
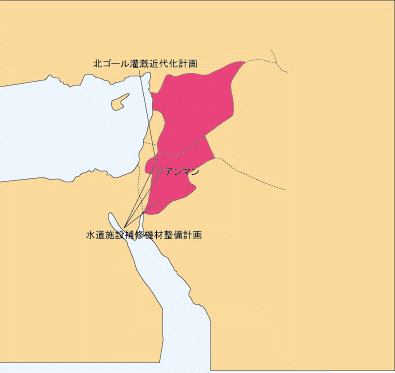
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |
| 北ゴール灌漑近代化計画 |
有償資金協力 |
88年度、40.80億円 | ヨルダン川東岸北部の北ゴール地域において、灌漑用水の節約及び農作物の生産増加のため、円借款により、水路方式・灌漑方式の変更及び新規灌漑を行う。 |
| 水道施設補修機材整備計画 |
無償資金協力 |
94年度、6.60億円 | ヨルダンの水道施設の老朽化による使途不明水を減少させるため、日本の無償資金協力により、3つの修理工場(中央修理工場と2つの地方修理工場)を対象に、水道施設の補修機材などを整備する。 |
はじめに
ここでは途上国開発・援助問題に関心を有し、かつ中東地域の研究者としての視点からヨルダンに対する援助を北ゴール灌漸近代化計画(有償資金協力)と水道施設補修機材整備計画(無償資金協力)の2プロジェクトの評価を行い、私見を付け加えたい。これは1997年11月に現地調査を行い現地のサイトに実際に足を運び、そこで得た資料、印象をもとにしたが、同時にヨルダンに対する援助の意義と目的、さらにそのなかで水資源の確保、利用の特別の重要性についても言及し、両プロジェクトがヨルダン経済発展に占める意義についても指摘しておいた。
1.ヨルダン援助の重要性と水間題
(1) 中東におけるヨルダンの重要性
ヨルダンは中東・アラブ世界において人口430万人程の小国であるにもかかわらず、その置かれた地政学的条件のなかで極めて重要な役割を果たしてきた。東はイラクと国境を接し、西はイスラエルと国境を接するとともにパレスチナ問題において鍵となるヨルダン川西岸がヨルダン川を挟んで西に展開している。また北にシリア、南にサウディアラビアと国境を接している。いうまでもなく中東において最も政治的に緊張している2つの核のうち1つは湾岸であり、もう一つの核はイスラエル・アラブ紛争であり地域的にはパレスチナ人が多数居住するヨルダン川西岸とガザ回廊である。
日本は輸入原油の約8割を湾岸に依存しており、湾岸の政治的安定性に深い関心を寄せざるを得ない。また近年日本の国際的役割の拡大に伴い、中東和平プロセスにも積極的に関与するようになってきた。ヨルダンは湾岸とパレスチナ問題に挟まれながら70年代初頭以降、周辺諸国とは極めて対照的な形で政治的安定性を長く維持することができた。ヨルダンの政治的安定性がなければ湾岸問題とイスラエル・パレスチナ紛争が直接連動し、一層中東情勢は不安定になったことは間違いない。また第一次大戦以降元フセイン国王の祖父に当たるアブドッラーがヨルダンを統治し、その弟のファイサルがイラクを統治したように、ヨルダンとイラクは歴史的に深い関係を持つと同時に、ヨルダンにとってイラクは今日において最も重要な貿易相手国である。
バランス感覚にすぐれたフセイン国王はこのような極めて複雑な政治力学が働く世界で、中東の2大紛争であるイスラエル・パレスチナ紛争、湾岸の対立を緩和するうえで独自の貢献を行ってきた。1989以降政治の民主化をかなり大胆に進めるとともに、94年にはアラブ諸国のなかではエジプトに次いで2番目にイスラエルと国交を樹立した。アラブ・イスラエル双方に太いパイプを持つフセイン国王に対して中東紛争の当事者であるPLOアラファート議長とイスラエル側指導者の信頼感は厚い。
対ヨルダン援助を評価するに際して、単に一途上国への援助という観点ではなく、湾岸・中東和平という2つの中東の政治課題との関連のなかで位置づけることが重要である。
(2) 日本の援助
日本は対ヨルダン2国間援助では91年~95年で見ると米国、ドイツを抜いて断然トップの地位を占め、総額の3分の1を占めている。日本は米国、ドイツ両国を合わせた額よりも多くなっている。ヨルダンにとって日本の援助はインフラ整備の中核を占めているが故に、日本の援助理念のありかたは一層注目されるようになっている。
| 日本 | 893.5(34.9%) |
| EU | 382.1(14.9%) |
| 米国 | 285.0(11.1%) |
| ドイツ | 281.6(11.0%) |
| UNRWA | 275.2(10.8%) |
| バイ・マルティ総額 | 2559.1(100.0%) |
日本の援助がヨルダンの経済的政治的安定性に寄与することが求められているが、以下の点を常時踏まえておくことが重要であると思われる。フセイン国王の政治体制を支えてきたのが国内政治、国際政治の両バランスをとる政策であったが、今後の安定性を保障するのは何よりも国民の生活の安定である。経済的社会的な不安定要因を事前に除去するという「紛争事前防止」を目的とする援助という考え方はヨルダンに適応できるでろう。
第1に、ヨルダンは最貧国ではないが、地域格差が激しく、また首都アンマンにおいても貧富の格差が激しいことである。また人口構成において6割、首都アンマンでは7割の人口がパレスチナ人と言われ、一部にはパレスチナ人難民キャンプが存在している。このようななかで社会的安定性の確保という観点からも、BHNに沿った援助は相変わらず重要である。また周辺の政治情勢で国内の経済状況が著しく影響を受ける。ヨルダンは1991年の湾岸戦争とその後のイラクの経済的疲弊などの否定的影響を受けた。イラクはヨルダンの工業製品にとって最大の市場であり、イラクの経済困難はヨルダン経済を直撃する。1990年の一人当たりGDPは1775米ドルであったが、96年には1634米ドル弱にまで低落した。その結果ヨルダンは、1993年に日本の無償資金援助協力の適格国となった。
第2に、ヨルダンは産油国ではなく燐鉱石、カリなどを除くと見るべき資源が少ない、従って労働力の高度化、つまりヒト造りに関連した援助が独自の重要性を持っている。アラブ世界のなかでは高等教育を受けた者も多く、その潜在力を無視すべきではない。
第3に、ヨルダンにとってイスラエル、イラクなど強大な隣国との関係が決定的な意味を持つ。イスラエルとは何らかの経済統合は不可避と思われるが、そのためにもヨルダン経済の自立性を強化することは重要である。現在イスラエル経済の発展段階との格差は極めて大きく、ヨルダンは経済的に従属させられるのではないかとおそれている。
(3) 水問題の重要性
今回評価の対象とした二つのプロジェクトのうち、水道施設補修機材整備計画(無償資金協力)は生活用水の供給確保と効率的使用を目的としており、第1のBHNに関連するプロジェクトである。北ゴール灌漑近代化計画(有償資金協力)は灌漑用水の効率的使用に関連しており、第3の経済的自立計画に関連するものである。これは上下水道の整備や灌漑用水の効率的使用及び再利用を目的とするものである。
なぜならばヨルダン、イスラエル、パレスチナ地域はシリア、レバノン、エジプトなど周辺諸国と比較してもとりわけ深刻な水不足に悩んでおり、中東和平の焦点となっているヨルダン川西岸、ガザ、イスラエル占領下のゴラン高原では水問題も重要な係争問題に含まれている。ヨルダンにおいて水不足が強く意識されるようになったのは70年代初頭である。現在水資源はヨルダンで最も不足している資源という認識が共有されている。人口増加と工業化の要請が水に対する需要を高めており、94年のイスラエルとの和平条約についても水の配分が重要な課題となった。
今後、必要な量と質の両面における水資源の確保を巡る抗争が中東地域の国際的緊張の原因となりうることが各界から指摘されている。特に1991年の湾岸戦争以降、アラブ世界で水と国際紛争に関する研究書が数多く出版されており、水と紛争・戦争とを結びつけて議論することが多くなっている。ヨルダンではすでに水消費量は再生可能淡水資源の20%を超えている。2005年を過ぎると淡水資源は全て利用し尽くされることになり、国内で開発すべき水資源は存在しなくなる。水を巡る中東諸国間の紛争はアラブ・イスラエル紛争より深刻で広範な問題となる可能性を指摘する識者も少なくはない。その意味で水供給の増加及び効率的使用に関する援助は単に民生、農工業の発展という視点と関連して潜在的な紛争を事前に予防する意味を持っており、その主旨のメッセージを明示的に提示することは国際平和に資するという日本の援助理念に基本的に合致するものと思われる。
1997年4月26日のヨルダン閣議で新たな水戦略が決定されている。そこでは何よりも現在および将来の水利用の持続可能性に重点が置かれている。水は量的に不足するだけではなく質の低下も深刻で、現在この水戦略をさらに具体化する作業が進められている。2000年の段階でヨルダンの一人あたり再生可能水は年間160立米とされているが、これは水についての「貧困ライン」とされる年間1人当たり500立米の消費量の実に3分の1以下である。このまま放置すると2025年には90立米にまで低下すると見込まれる。この問題を解決するため表面水、地下水、化石水、都市で生産される使用済み水の再処理、準塩水、さらに海水の淡水化など全てを含めた計画を立てなければならない。現在不足分を高地の化石水の過剰汲み上げによって補っており、水質の低下を引き起こしている。塩分を含む化石水がまだ利用されていない水資源に過ぎない。世銀も塩分を含む地下水の利用可能性の検討を次の課題の一つとして勧告している。
さらに水の消費に関してはできるだけ公平に、特に納得しうる家庭用水消費、それ以外の農業、工業、観光などの水消費を考慮に入れなければならない。水戦略では一人当たり1日当たり100リトルの家庭用水の供給を最小限の目標としている。 また経済的に採算にのる脱塩水などの非伝統的水資源の確保が必要となる可能性もある。化石水の利用に関しては持続的水の取得可能性が問題とされなければならない。ヨルダン水灌漑省は今後14年間で50億ドル規模の投資が不可欠であると見ている。ヨルダンの置かれた状況から見て水入手の限界コストは国際的基準から見てもかなり高く付くことが見込まれている。
ヨルダンはヨルダン川以外は天水に依存せざるを得ないが、降水量は極めて少ない乾燥地域に位置しており、急増した人口に対応するための生活用水の確保が特に重要となっている。ヨルダン川が海面下を流れているのに対し、人口の3分の1が密集している首都アンマンやザルカなどの都市は海抜800メートルの所にあり、そこにポンプで水を引き上げる(日本も別プロジェクトで支援)という困難な条件のもとにある。他方唯一の農業地帯であるヨルダン川流域では灌漑用水の確保と並んで効率的使用の課題が重要になっている。また水質汚染、質の低下、資源の枯渇に対して特別の注意が向けられなければならない。
ヨルダンの水・灌漑行政は水灌漑省の管轄であり、その下に水管理庁(WAJ)とヨルダン渓谷庁(JVA)がある。水灌漑省は全体としての計画を立て、実際の施行については両庁が分担している。両者の役割分担については再調整が進行中である。
2.北ゴール灌漑近代化計画(有償資金協力)
(1) 計画の概要
このプロジェクトの目的は、全体として乾燥地帯に位置するヨルダンのなかで主たる農業地域であるヨルダン川流域の灌漑の近代化を通じて農業生産の安定化と近代化を図ろうとするものである。プロジェクト・サイトは北ゴール地域で、北はヤルムーク川、南はワディ・ラジーブ、東側の境界はキング・アブドッラー運河、西側の境界はヨルダン川に挟まれた7,000~8,000ヘクタールの既灌漑地であるが、900ヘクタールの新規灌漑地開発も行う。既灌漑地を対象に配水路方式を開水路から加圧パイプラインに転換するとともに、スプリンクラーなどの地表灌漸方式から点滴灌漑方式へ変更を行い、それによって新規灌漑地開発も可能にしょうとするものである。本計画では、ポンプ場10カ所設置し、加圧パイプライン277キロメートル、農道76キロメートルの造成を目的とする。この北ゴール灌漑近代化計画は、1993年1月に着工され1997年1月に完成した。なおヨルダン渓谷の灌漑用水の管理や農業を中心とする地域開発などは水灌漑省のもとのヨルダン渓谷庁(JVA)の監督下にある。このプロジェクトのファイナンスは80%が日本の有償資金供与、20%がローカルコストであった。
これはステージII地域として知られる26,000ヘクタールの灌漑地を対象とする大きなプロジェクトの一部を構成する。このプロジェクトで3つの部分に分けられたものの第3(最終)段階に該当する。第1の非コントロール流域プロジェクト(14.5キロメートルの延長)と第2の中間ヨルダン渓谷プロジェクトに次ぐもので北ゴール転換プロジェクトである。第1段階は1984年1月から88年4月にかけて完成し、第2段階は87年1月から91年10月にかけて完成した。
(2) 評価と問題点
それでは実施の効率性、目標達成度、インパクト、妥当性、自立発展性を考えた場合、このプロジェクトはどう評価すべきであろうか。
現地を視察した際、ポンプ・ステーションとそれによる配水システムの実施状況を見たが、開水路から加圧パイプラインにしたことによって農民の水利用意識に大きなインパクトを与えたことが看取できた。ヨルダン政府は新水戦略において一般市民に対して水不足についての一般的認識を深めることを要求しているが、このようにコスト意識を喚起する形は最も効果的であろう。以前は非収入水(Non-Revenue WaterあるいはUnaccountable Waterと呼ばれ通常、メーター漏れ、盗水及び漏水・蒸発水を指し、これらいずれによっても説明し得ない水は不明水という)の比率が約50%であったのが、基本的に使用水量がメーターでチェックされるようになったため大幅に減少したことは間違いない。非収入水の場合、水管理庁の収入がその分減少することを意味し、非収入水の大幅減少は歳入増加に寄与する。これが農民の省水意識を強化し、コスト意識もあいまって農業生産の合理化に資することが期待されている。なお関連業界の情報によれば、日本における非収入水は上水道に限ってみると10%程度と言われる。終戦直後は40%程度であり、その意味で非収入水を減少させることは先進国であっても必ずしも容易ではないようである。
評者は1990年代初頭のヨルダン渓谷の農民調査を行ったが、温室栽培など新たな農法を積極的に摂取しようとする農民が決して少なくないという印象を持った。ヨルダン渓谷の別の地域の同種のプロジェクトと相まって農民の意識革命に寄与していると見られる。ヨルダン渓谷では全体としての灌漑効率性は1994年の57%が95年には68%にまで高まったとされる。この向上にこのプロジェクトは寄与していると見られる。農地で恒常的に灌漑水が提供されていないのは16%程度といわれる。
さらに点滴灌漑(ドリップ農法)の導入は、現段階では省水と土地生産性向上を両立させる最先端の方法である。イスラエルでドリップ灌漑は広範に発達したがヨルダン渓谷の農民はそれを知る立場にあったために、容易に導入できたと見られる。一般的にイスラエルからの農業技術の移転がヨルダン渓谷で試みられている。現在南部で2つのパイロット・プロジェクトが進行している。一つはイスラエルのアグレスコ社がIFCの支援を受け、種なし葡萄(マークスオエンサー)、すいか、チェリーの栽培とそのマーケティングを行っているのである。ヨルダンとイスラエルの価格差を利用したもので、葡萄の場合、一箱当たり3ドルであるのに対しヨルダンでは60セントで5分の1となっている。アグレスコはこの価格差を利用しており、同社を通じれば、ヨルダンの農民も儲かるし、イスラエルの企業も利益に与れるという論理である。
当プロジェクト該当地域のクロッピング・パタンを見ると、59%が野菜(トマト、ナス、キュウリ、コショウ、ウリ、ジャガイモ、カリフラワー、豆、タマネギ、ニンニク、モロヘヤ、メロン、ほうれん草、レタス、トウモロコシ)、26%が柑橘類、バナナ、葡萄などで7%が小麦、大麦などとなっており、野菜が中心になっている。
以上の点を勘案すると本プロジェクトは着眼点からいっても優良案件であると見てよい。また、この効果は一時的なものではなく、持続性を持ちうるものである。なお現場の幾人かの話を総合すると、ポンプ場の管理人の任命方式にはネポティスム(身内ひいき)があるようだ。これはヨルダン社会の構造的問題であり、国外からこの問題は関与すべき性格ではないが、これによって管理上で不正があったり、ポンプの維持に問題がないよう、最小条件に注意を喚起する必要があろう。
ただしヨルダン渓谷で経済的理由からこれを利用できる農民と利用できない農民の間に格差が生じる可能性がある。これを補うために米USAIDのもとでアドバイス・プログラムがあり、農民に対する具体的な指導が行われている。その点ではハードとソフトの援助の一層の調整が望まれる。なお、ヨルダン渓谷の農業経営の実態は必ずしも明らかではないが、自作経営が48%、小作経営が46%、他の6%が自小作という数字が出されている。エジプトや東南アジアなどからの出稼ぎ労働者が農業労働者として働いており、雇用労働に依存した農業経営が見られる。ヨルダンが若年層の失業問題に悩み、出稼ぎ労働が広範に見られながら、他方ではエジプトなどから出稼ぎ労働力を輸入するという複雑な労働市場となっている。
最大の課題の一つはヨルダンの経済発展戦略における農業、とりわけヨルダン渓谷の戦略であろう。これは本プロジェクトとは直接関連はないが、ヨルダンで日本モデルを意識した産業政策が議論されている折り、それを具体化するにはヨルダン農業は国内消費か輸出産業かなどその位置づけに留意する必要がある。ヨルダンのトマト、キュウリは輸出商品にはならないが、葡萄、ナツメヤシは欧州・米国の市場向けでは展望がある。
3.水道施設補修機材整備計画(無償資金協力)
(1) プロジェクトの内容
水道施設補修機材供与計画を無償資金協力案件として取り上げたのは、上水道供給の緊喫性という点からすれば適切な着眼点であった。計画の目的は水道施設の修理工場における補修機材、自動車、トラック、トレーラーの整備にあり、それによって水道施設の維持管理能力の改善を目的としたものである。ザルカの中央ワークショップと北部(イルビッド)と南部(マアン)に地方ワークショップがあり、合計3カ所で作業を行っている。水道施設の破損あるいはトラブルが生じた際に、現場に行って直ちに補修ができるようにし、円滑な水道事業を行うことを目的とするものである。そのためには補修用機材を現場に運ぶトラックなど輸送機械の保守管理が重要な仕事となる。このセンターを管理しているのは水灌漑省の下にある水管理庁であり、同庁のワークショップ局が現場の運営を行っている。年間総ローカル・コストは200万ヨルダン・ディナール(JD)である。
主要機材は中央センターに集中している。中央センターは首都アンマンに隣接する工業都市ザルカにあり、地理的には広義の首都圏を管轄している。ワークショップは建屋はヨルダン側、機材は日本側が提供した形になっている。提供機材は水道施設の維持管理用の車両やポンプ等を修理・整備するために使用される。機材の種類は多岐にわたっており、工作機械、車両修理・整備用機械、車両検査用機材、修理・工作車両等、水中ポンプ、モーター類修理・整備用機材、パソコン、工具等を含んでいる。総額6億6,000万円に相当する。
機材供与は既に1996年3月に完了しており、フォローアップとして、事後現況調査がローカルのコンサルタントによって2年後および5年後に行われる。第1回の事後現況調査は97年8月に実施された。
(2) 評価と問題点
(イ) センターの印象
このプロジェクトは日本の援助姿勢を示すものとして積極的に受け取られている。現にアンマンのセンターにはアラビア語だけではあるが日本の援助によるものであることを記念する碑も建てられている。日本の援助の一つの象徴として、それだけ高い評価と期待を受けているとみてよいであろう。センター所長の発言からしても社会的に与えたインパクトは大きかったといってよい。ヨルダン政府が水道事業近代化のシンボルとしてこのセンターを位置づけているのがわかる。
この計画の理念自体は時宜を得たものであり、BHNに寄与する無償資金供与案件としては妥当である。新しく建てられたワークショップ・センターは機材設置と同時に作業を行う場所である。センターは広々とした敷地で、機器設置のレイアウトも効率的になされているように見えた。従業員数は事務管理部門も含め370人である。頻繁に水道の保守管理用のトラックなどの車両がセンターに出入りしており、作業場の労働者の労働態度はアラブ諸国のいくつかの工場を見た印象と比較すると積極的で効率的であるように見えた。これは敷地の広さとレイアウトも関連しているが、作業場がクリーンである。
地方ワークショップとしてはイルビッドを訪問した。センターと比較すると予定されている建て屋はややみすぼらしく小さなものであるが、これは緊急に修理を要する場合に対応できればよく、本格的な修理の場合はセンターで行うから問題はない。しかし現場との連絡システムなどで改善の余地がありそうである。
(ロ) 利用度と持続性
日本から供与された機材は全体として有効に利用されていると思われたが、イルビッドの地方ワークショップは建て屋の建設がローカルサイドの事情で遅れたこともあって、近くの暫定的な場所に置かれたものもあった。これは日本側の責任ではなくヨルダン側の問題である。このような事態はローカルコストが絡んでいる場合生じやすい問題である。
ただし極く一部ではあるが使いこなせていないホウィール・バランサーなど部分的に未稼働の機器がある。これについては現場の者から訴えがあった。しかし、日本側が一方的に相対的にレベルの高い機器を押しつけたわけではない。機器の選定のプロセスを見るとヨルダン側の希望を考慮に入れて双方の協議の末に行ったものである。また通常の機材の引き渡しの条件としてメーカーによる2週間ほどの教育が含まれており、本プロジェクトに関しても各機材の使用法に関して現場で説明され、その時点では問題がなかったことが認められている。
このような場合、現地スタッフを再訓練するアフターケアの別の援助案件が必要かどうかが問題になるが、現段階ではまだヨルダン側に自らの方法で解決の可能性を追求させた方がよいのではないかと思われる。ヨルダンの労働力は近隣諸国と比較しても概して質が高く、必要な人材を国内に見出すことも不可能ではないと思われる。それでも不可能であることが判った場合のみ、また相手側の要望がより具体的で明確になった場合のみ、次の対策を検討すべきであろう。
ローカル・コンサルタントによる第1回の事後現況調査において、上記ホウィール・バランサー以外の別の機材についても作動していないというクレームが記されているが、日本側にはそのことがセンターあるいは水灌漑省から伝えられていないことを見ると、ヨルダン側の自主管理能力を待つ以外はないのではないかと思われる。ヨルダンはそれだけのことが期待されてよいアラブ世界では民度の高い国である。
なおヨルダンの工学技術教育の一つの特徴は、ソ連で訓練を受けた者も以外に多いことである。最もコストが安い留学先であり、さまざまな援助措置を受けたため、多くの者がソ連に留学した。もちろん自然科学・工学以外の人文・社会科学の分野では制約を受けていた。アンマンのセンター長もソ連で工学を修得した人であった。ヨルダンで工場などでよくみかけることであるが、ソ連で訓練を受けた技術者が西側の機械技術を再度学ぶという過程を経ることを余儀なくされている。数年前、アンマンの1職業訓練所を見学したことがあったが、訓練に使用する機械器具はかつてソ連から援助で得たものを使用していた。その場合、機械器具に対応した技術訓練に限られ、実際の労働現場では必ずしも役に立たないという事例があったのを見ている。技術移転が機械器具によって異なる効果を生むという事例である。
(3) 第1回の事後現況調査と関連して
ローカルのコンサルタントによる1997年8月に行った第1回の事後現況調査では、このプロジェクトに対する高い評価が与えられている。これによると、日本の援助後このセンターの活動は活発化し、供与機材の利用頻度も高い。従来以上に作業が迅速に行われるようになり、水道諸施設が故障した場合の修理に要する時間が縮小した。現段階でザルカのルシフェにあるセンターでは50%の故障件数をとり扱い、イルビッドでは10%、マアンでは7%をとり扱っている。イルビッドではさらに拡張計画があり、このプロジェクトの持続可能性については問題がないとしている。この評価が示すように、上記一部の機材を除いてヨルダン側での自主管理による持続可能性については信頼してよいのではないかと思われる。
4.総合的提案
上記2プロジェクトはヨルダンの緊急な必要に対応したもので、成功例として評価しうるものであるが、付加的コメントを行いたい。
ヨルダンは歴史的伝統的に援助を受けるのに慣れている国である。経済的自立を側面から援助する努力は援助供与国として引き続き必要であるが、日本の援助の規模が相対的に大きいところがら与えるインパクトは予想以上に大きい。一例として今回の対象プロジェクト評価の対象には入っていないが北部でのシェイク・フセイン・ブリッジの建設はイスラエル・ヨルダン経済関係に大きなインパクトを与える。つまりイスラエルのハイファとヨルダン第2の都市イルビッド、特にそこでの工業団地とを直接最短で結びつけることになる。ヨルダンにとってアカバ港とは異なる別のルートが開けることのほか、両国関係を一層緊密化させる契機となりうる。現在米国とイスラエルの間には自由貿易協定があり、イスラエル製品は農産物などを除いて米国市場に無税で輸出することができる。今回イルビッド工業団地においてイスラエル資本が合弁として参加している企業の場合、そこでの製品はイスラエル製品と同等の資格で米国との自由貿易協定の対象とされることになった。ヨルダン国内にはイスラエル経済への従属が一層強まるとする警戒論と、新たなチャンス到来という積極論の二つがある。またこのことはヨルダンより賃金水準の高いパレスチナ自治区では不安の目で見られている。
そのためヨルダン政府との間での調整はもちろん重要であるが、単なる要請主義にとどまることなく、日本としては開発のグランド・デザインについてできるだけ積極的に関与して行くべき客観的要請があると思われる。また援助国・機関の間の案件の調整が引き続き必要である。同時に現在、日本の産業政策に対する関心が高まっているが、このような際にこそ灌漑近代化計画などを開発戦略における農業の位置づけと関連づけて議論して行く姿勢、つまり政策化志向の発言が日本にとっても必要であろう。中東和平プロセスの進展(これはイスラエル政府の硬化した姿勢もあって予期した以上に遅れているが、和平プロセス自体は不可逆的である)にともない、ヨルダンはイスラエル、パレスチナ自治区との経済関係のビジョンが問われている。農業一つとってもイスラエル、ヨルダン、パレスチナの間での競争・競合さらに協力がある。この3地域が何らかの経済的地域協力を展望しなければならないことは所与の歴史的文化的経済的関係を見る限り必然的である。その意味で日本側でこの3国・地域を包括するようないくつかの協カビジョンを出すという試みに踏み込んでもよいのではないかと思われる。現に第3国援助としてヨルダンにおいてパレスチナ自治区を対象とした職業訓練も行われており、その端緒的試みは既に行われている。特にヨルダン渓谷の開発、さらに水資源問題はヨルダンにとっても「和平連関プロジェクト」として位置づけられる必要がある。これは最初に述べた「危機事前防止援助」と「産業政策」を組み合わせた発想といってもよい。もちろん試行錯誤は避けられない。これには専門家グループをつくって提案を出させてもよい。
またやや蛇足となるかも知れないが、漏水防止についての支援は極めて意味のあるものであり、今後本格的にハード・ソフト両面で促進することが望ましい。これは財政収入確保と水の効率的使用の双方に役立つものであり、単に灌漑用水のみならず上水道にとっても必要であろう。
特に今回の評価対象とも関連するが、水供給問題はちょうどイスラエル・ヨルダン・パレスチナ自治区をひとつのまとまった単位として検討するのが地形的に最も現実的であり、現に世銀もこのような視点から調査を開始している。イスラエルとヨルダンが94年に和平条約に辿り着けたのも、イスラエルによる部分的水供給の約束の取り付けが基本的に合意されたからである。またイスラエルとパレスチナ側の和平プロセス上の懸案事項にはエルサレム問題、ユダヤ人入植地、パレスチナ難民の帰還権のほか、西岸の地下水利用に関する利害対立がある。

