第5章 有識者による評価
1.青島の運輸インフラ(中国)
(現地調査期間:1997年10月5日~11日)
- 静岡県立大学国際関係学部教授 小浜裕久
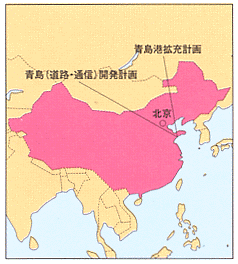
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |
| 青島港拡充計画 |
有償資金協力(円借款) |
84年度、22.03億円 85年度、39.37億円 86年度、26.20億円 87年度、86.83億円 88年度、130.43億円 89年度、265.14億円 |
河北地域の重要港である青島港の貨物取扱い能力を増強するため、円借款により、前湾地区に新規バースを建設するとともに、後背地である膠県との間に約40キロメートルの鉄道を建設する。 |
| 青島(道路・通信)開発計画 |
有償資金協力(円借款) |
90年度、128.34億円 |
青島市の慢性的な交通渋滞を緩和するため、円借款により、青島市街と前湾地区とを結ぶ67.7キロメートルの高速道路を建設する(通信の部分は、今回の評価の対象とはしなかった)。 |
1. 対中国援助方針
『ODA白書』によると、中国に対する日本の国別援助の基本方針は、以下のようなものである。
1 日本の援助対象国としての位置づけ
中国に対する日本の援助は、1997年までの支出純額合計で、インドネシアについで第2の受取り国になっている。その背景として、以下の5点をあげている。
- (1) 地理的に近く政治的、歴史的、文化的に密接な関係にある、
- (2) 日本と中国の安定的発展が、地域さらには世界の平和・繁栄につながる、
- (3) 経済関係の広がり、
- (4) 中国が対外開放政策と経済改革を進めていること、
- (5) 援助需要が高いこと。
(4)の「中国が対外開放政策と経済改革を進めていること」というのは1992年6月の閣議決定された「ODA大綱」の原則の(4)にある「市場志向型経済導入の努力」に留意する、ということに合致するが、「ODA大綱」の原則には、「民主化の進展」、「基本的人権の保障」にも留意するとあり、このあたりは議論が分かれるところだろう。
2 援助の重点地域・重点分野
重点地域・領域として、有償資金協力を中心に経済インフラの整備に資するとともに、地域間のバランス、農業開発にも留意し、無償資金協力、技術協力は、特に内陸部を重視し、貧困地域の基礎生活分野に重点的に援助するとある。
これを受けて(1)経済インフラ、(2)農業、(3)環境、(4)保健・医療、(5)人造りの5点が、重点分野として示されている。とくに(1)経済インフラは、中国の経済発展のボトルネックとなっている運輸、通信、電力等の経済インフラの整備の遅れの解消に向け援助するとされる。
我々が行った事後評価は、有償資金協力によるインフラ整備、特に運輸・交通部門への援助の一環である。運輸・交通部門の援助は、施設建設による輸送能力の拡大、輸送の効率化のための維持・管理技術の向上に資する援助を行うものとされている。
2. わが国の対中援助
先にも述べたように、これまでの援助額累計で見ると、日本の対中国援助はインドネシアに次いで第2位である。しかし、単年でみると、日本の二国間援助の最大の受取り国は、最近ではインドネシアだったり中国だったりしている。
表1は、最近の対中国援助を見たものである。年によってバラツキはあるが、大体全体の6割から7割が円借款で、残りが贈与である。贈与の大半は技術協力である。日本の援助は二国間では圧倒的に大きく、国際機関の援助はIDAが第一位である。表2は、1990年以降の主要な対中国援助の国別・国際機関別援助実績を見たものである。二国間援助が全体の6割から7割を占めており、その5割から6割が日本の援助であることが分かる。国際機関による援助の8割以上はIDAによるものである。年によって、日本の援助額がIDAの援助額より大きい場合もあれば逆の場合もある。
| 贈与 | 政府貸付 (支出純額 :10合計ドル) | |||||
| 無償資金協力 | 技術協力 | 計 | 支出総額 | 支出純額 | ||
| 1993 | 54.43 | 245,06 | 299.49 | 1,189.06 | 1,051.19 | 1,350.67 |
| 1994 | 99.42 | 246.91 | 346.33 | 1,298.46 | 1,133.08 | 1,479.41 |
| 1995 | 83.12 | 304.75 | 387.87 | 1,216.08 | 992.28 | 1,380.15 |
| 1996 | 24.99 | 303.73 | 328.72 | 774.08 | 533.01 | 861.73 |
| 1997 | 15.42 | 251.77 | 267.19 | 556.75 | 309.66 | 576.85 |
| 累計 | 717.91 | 2,294.50 | 3,012.41 | 10,228.70 | 9,082.15 | 12,094.56 |
| (5.9) | (19.0) | (24.9) | - | (75.1) | (100.0) | |
注:( )は、合計に対するシェア。
| [金額] | ||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| 二国間援助計 | 1,511.7 | 1,252.5 | 2,077.3 | 2,239.8 | 2,393.9 | 2,531.3 | 1,670.9 | 1,228.6 |
| 日本 | 723.0 | 585.3 | 1,050.8 | 1,350.7 | 1,479.4 | 1,380.2 | 861.7 | 576.9 |
| ドイツ | 228.9 | 107.1 | 192.8 | 247.8 | 300.0 | 6841 | 4611 | 381.9 |
| フランス | 88.0 | 138.5 | 153.4 | 102.6 | 97.7 | 91.2 | 97,2 | 50.1 |
|
国際機関 援助計 |
586.1 | 740,5 | 960.7 | 1030.0 | 820.0 | 967.5 | 928.3 | 841.0 |
| IDA | 505.0 | 610.0 | 789.9 | 865.1 | 671.0 | 798.2 | 790.7 | 687.1 |
| 総計 | 2,092.5 | 1,998.7 | 3,049.6 | 3,271.2 | 3,238.4 | 3,534.4 | 2,617.6 | 2,040.3 |
| [シェア] | ||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| 二国間援助計 | 72.2 | 62,7 | 68.1 | 68.5 | 73.9 | 71.6 | 63.8 | 602 |
| 日本 | 34.6 | 293 | 345 | 413 | 457 | 391 | 329 | 283 |
| ドイツ | 10.9 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 9.3 | 19.4 | 17.6 | 18.7 |
| フランス | 4.2 | 6.9 | 5.0 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 3.7 | 2.5 |
|
国際機関 援助計 |
28.0 | 37.0 | 31.5 | 31.5 | 25.3 | 27.4 | 35.5 | 41.2 |
| IDA | 24.1 | 30.5 | 25.9 | 26.4 | 20.7 | 22.6 | 30.2 | 33.7 |
| 総計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注:数字は、ODA支出純額。
金額的に見て日本の対中国援助の中心である円借款は、改革・開放政策が始まった直後の1980年4月に始まった(注1)。それ以降現在まで承諾された円借款は総額2兆2,609億円、借款契約件数は239件に上る。対中円借款は、日本の円借款供与国91カ国(1999年1月末時点)の中で、承諾金額累計でインドネシアに次いで第2位である。その対象分野も、経済インフラから環境改善事業まで多岐にわたっている(注2)。
これまでの対中円借款は、中国の5カ年計画に対応する形で、国家重点プロジェクトを中心に供与されてきており、円借款もラウンド方式、すなわち5~6年を一つのラウンド(対象期間)として供与額及び対象案件の大枠を事前に合意する方式で供与されてきている。その間、「資金環流措置」による追加的な円借款も供与されている。
第1次円借款(1979~84年度)は、7案件3,309億円、第2次円借款(1984~89年度)は、17案件5,400億円、第3次円借款(1990~95年度)は、52案件8,100億円が供与されている。第1次円借款から第2次円借款前半(1979~87年度)は、石炭輸送を中心として運輸インフラ整備事業に
重点的に融資している。第2次円借款後半の1988年度から第3次円借款にかけては、天安門事件(1989年6月)はあったものの、改革開放政策が加速された時期に当たり、それまでの運輸プロジェクトに加えて、都市部の上下水道及びガス供給事業、都市間の通信事業、農業生産性向上のための肥料工場、開発拠点のインフラ整備なども対象となった。
海外経済協力基金の資料(『円借款の貢献事例』、1997年3月)などに拠れば、中国国内で電化されている鉄道の38%が円借款によるものだし、港湾に関しては、359のバースの建設に円借款が供与されており、これは中国全体の主要バースの13%に当たる。これ以外にも発電設備の3%、化学肥料増産の25%が円借款によるものとされている。
現在進行中の第4次円借款は、中国の第9次5カ年計画(1996~2000年)に対応しており、1998年度までの3年間とそれ以降2000年度までの2年間に分けて総枠を協議する形となっている。1996~98年度の3年間では、40案件5,800億円が供与される計画であり、1999~2000年度については、28案件3,900億円が供与されることになっている。
表3は、セクター別の対中国円借款の概要を見たものである。運輸セクターが大きく、これまでの日本の円借款の半分弱が運輸部門への融資である。運輸部門の中では、鉄道、ついで港湾に対する援助が大きい。
| 借款承諾 | 契約本数 | ||
| 借款承諾額(100万円) | 借款承諾額シェア(%) | ||
| 運輸セクター | 1,069,572 | 47.3 | 115 |
| 鉄道 | 577,787 | 25.6 | 53 |
| 港湾 | 272,625 | 12.1 | 40 |
| 道路 | 86,726 | 3.8 | 6 |
| 橋 | 23,927 | 1.1 | 6 |
| 空港 | 108,510 | 4.8 | 10 |
| 通信セクター | 116,949 | 5.2 | 16 |
| 電力・ガス | 476,667 | 21.1 | 40 |
| 発電所 | 399,613 | 17.7 | 31 |
| 送配電 | 31,383 | 1.4 | 2 |
| ガス | 20,712 | 0.9 | 3 |
| 農林・水産 | 124,024 | 5.5 | 21 |
|
灌漑・治水・ 干拓鉱工業 |
22,535 | 1.0 | 4 |
| 鉱工業 | 100,999 | 4.5 | 3 |
| 社会的サービス | 220,127 | 9.7 | 35 |
| 非環境案件 | |||
| 行政機能強化 | 24,070 | 1.1 | 4 |
| 環境案件 | 196,057 | 87 | 31 |
| 上下水道・衛生 | 102,274 | 4.5 | 16 |
| 総合的環境保全 | 93,783 | 4.1 | 15 |
| 商品借款 | 130,000 | 5.7 | 5 |
| 総計 | 2,260,873 | 100.0 | 239 |
3. 評価案件の概要
1 青島港拡充計画
青島港拡充計画は第2次円借款として行われ、その融資額は570億円、完成は1994年11月である。この事業目的は、青島港の増大する貨物輸送需要に対応し、恒常化する滞船状況を緩和するため、前湾地区に新規バースを建設し、合わせて後背地との輸送力強化を図るために黄島(前湾地区)~膠県間に鉄道を建設する、というものである。
図1に見るように、膠州湾の入口の東側が青島市で旧港があり、西側が黄島(前湾地区)で、この新港の拡充プロジェクトに円借款がついているということである。青島市港湾局は旧港に隣接してあり、港湾局の建物の屋上から旧港を見ると、長い歴史を感じさせる古い設備の中、石炭と鉱石の積み出しが行われていた。船が大変混んでいるという印象はなかったが、コンテナの扱いもかなりあるという印象であった。
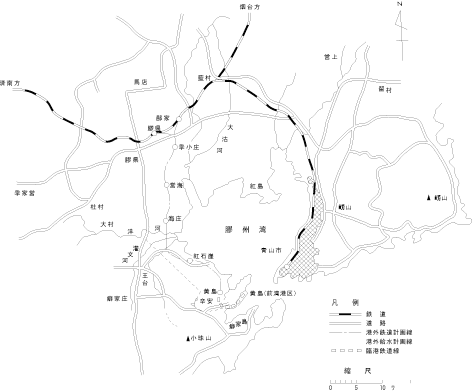
青島港は山東半島膠州湾にあり、黄海に面していて水域面積は420万平方キロである。年間を通じて凍らない。中国では数少ない天然の良港である。黄河流域と太平洋西岸の重要な中継港であり、国際貿易と海上輸送のターミナルである。青島港は稼働埠頭11基、稼働バース48基であり、1万トン以上のバースは25基ある。1996年の取扱量は6,000万トン余であり、1997年は7,000万トン弱である。
青島港は世界130以上の国土地域の450以上の港と貿易している。交通条件はきわめてよく、鉄道は、膠済線と膠黄線を通じて、京広線、京九線という大動脈とつながっている。道路は、済青高速道路、環膠州湾高速道路、青咽高速道路を通じて全国の道路網とつながっている。後背地は広く、山東、河南、河北、山西、陵西、甘粛、内蒙古、新彊、四川、貴州等へのアクセスがよい。
青島港は、旧港区、黄港区、前湾新港区の3つの部分からなっている。旧港区は、青島市の中心に隣接し、100年の歴史を有する。青島油港は中国の二大原油中継基地の一つであり、専用の油埠頭が2基あり、5万立方メートル規模のタンクが12基ある。
本援助案件である前湾港区は、青島経済新区にあり、前湾第1期工事の6基の深水バースは1993年に完成し、稼働を開始している。このプロジェクトは、第7次及び第8次5カ年計画の重要案件である。設計上の年間取扱量は1,700万トンである。その内訳は、(1)3.5万トン、5万トン級石炭バースで1,500万トン、(2)2.5万トン級木材バース1基、2万トン級雑貨バース2基で200万トンである。1996年の取扱量は1,129万トン、1997年は1,700万トンになると見込まれている。ここには、鉄道は膠黄線、道路は環膠州湾高速道路が通じている。
2 青島開発計画(道路)
青島開発計画(道路)は第3次円借款として行われ、その融資額は88億円、完成は1996年4月である(注3)。
青島市は中国における経済特別計画都市、沿岸開放都市、経済中心都市にあげられており、国家開発計画の重要な拠点として発達しつつある。しかし、青島市の道路状況は全国的な道路網とのリンクが不十分であり、かつ市街地の出入り道路が少ないことから交通問題が起こっていた。さらに、黄島地区の開発が進められていることから、幹線道路の整備が強く求められたわけである。
本融資案件は、青島旧港から黄島地区にいたる総延長67.7Km、4車線の環膠州湾高速道路の建設である。21の橋、7つのインターチェンジ、10の料金所、コントロールセンターを含む。
環膠州湾高速道路が出来る前は、この区間は舗装されていない細い道があるだけで、青島市街・旧港と黄島地区はフェリーで結ばれていた。このフェリーは現在も運行されており、上記調査スケジュールにあるように、我々も、旧市街から環膠州湾高速道路で黄島地区へ行き、帰りはフェリーで青島市に戻った。
本事業の効果としては、(1)交通事故及び貨物破損の減少、(2)フェリーの混雑緩和、(3)青島港の取扱量増加、(4)青島市の交通緩和、(5)周辺地域の経済発展および観光開発、(6)外国資本の誘致、などが考えられていた。
4. 現地調査所感
青島市を見た印象は落ち着いた散策するに適した美しい海岸地域と、経済活動が動きつつある地区が両方あるように見受けられた。しかしながら落ち着いた古い都市という感じで、深セン市のような挨っぽい建設途上といった印象はない。
青島港拡充計画(前湾港)の第1期工事だけで、16,000人の労働者が雇用されたと言われる。我々が現地調査を行った1997年10月時点では、前湾港は第2期工事中であった。第1期工事は完成していてすでに港は稼働しており、主な取扱い商品は、石炭、鉱石、化学肥料であった。前湾港の水深は、約14メートル。現地調査の日は5万トン級の船が停泊しており、1隻は石炭積み出し中であり、もう1隻は鉱石をおろしていた。ここは山東省の勝利油田の原油積出港であるが、現地調査の時は原油のバースには船はいなかった。
環膠州湾高速道路(青島市~黄島)は、所要時間35分くらいである。料金は、マイクロバスで23元(1元=15円)。通行している車は、トラックが中心で、東名のすいているときから、乗用車をほとんど抜いたような印象であった。環膠州湾高速道路コントロールセンターは日本と同じ近代的設備で、道路の運行状況をきちんと監視しているように見受けられた。機材は世界中からきており、円借款のアンタイドの実態を垣間見ることが出来た。
5. 全体的評価
1984年9月に出された青島港拡充計画のフィージビリティ調査(F/S)では、滞船費用節減、貨物輸送時間節減、付加価値増加、雇用促進、地域開発促進、国内産業育成といった効果が考えられている。このうち、滞船費用節減、貨物輸送時間節減、付加価値増加の効果のみを考慮した基本ケースの経済内部収益率は12.2%である。
青島旧港はすぐ後ろが市街地であり、大規模な拡張の余地はない。改革開放政策の結果、中国の経済発展は加速化されており、物流量が急速に拡大しつつあり、港湾取扱い量も急増している。天然の良港の利を活かし、図1に見られるように膠州湾入口の旧港の反対側あって新規開発の余地のある前湾港を開発することは、開発計画の視点から経済合理的な選択だったといえる。
黄島前湾部は新港建設が始まるまでは全くの漁村であった。鉄道のアクセスもなく、道路も在来的道路のみで、旧市街との連絡は先にも述べたようにフェリーがもっぱらであった。新港の建設と新しい鉄道支線(黄島~膠県間)を建設し、さらに環膠州湾高速道路を建設するプロジェクトに対して円借款が供与されたことは、青島・膠州湾地域の開発にとって、大きく貢献するものと判断される。
新港、新しい鉄道支線(黄島~膠県間)、環膠州湾高速道路の建設によって滞船費用が節減され、貨物輸送時間節減の効果がもたらされることは疑問の余地がない。我々が現地調査を行った時点では、まだ前湾港の第2期工事中で、全体的評価を下すことは出来ないが、船積み・荷下ろしの現場をいくつか見た印象としても、滞船時間・荷役時間が節減されたと考えられる。
新港のバース建設について最初の計画が何度か変更されたようであるが、これも、中国の急速な経済発展、それに伴う構造変化によるものと考えられる。事後評価としては、青島新港建設による、貨物輸送量全体の増大およびその間接効果で判断すべきであると考えられる。
環膠州湾高速道路の建設効果として先に述べた効果のうち、交通事故及び貨物破損の減少、フェリーの混雑緩和、青島港の取扱量増加、周辺地域の経済発展には間違いなく寄与していると考えられる。ただし、観光開発、外国資本の誘致、といった効果については、調査時点でははっきりした効果は確認できなかった。
注
- 以下の記述は、海外経済協力基金『対中円借款の概要』(1999年1月)、「OECFニューズレター」(1999年3月号)に拠っ ている。
- すべての案件リストについては、上記『対中円借款の概要』参照。
- 青島開発計画にはこれ以外にもやはり第3次円借款として行われた青島開発計画(通信)および青島開発計画(上水道・下水道)があり、その融資額はそれぞれ40億円、25億円であるが、そのプロジェクトは今回の評価には含まれていない。

