第2章 NGOプロジェクトの評価(「シャプラニール=市民による海外協力の会」の事例)
1. 活動内容の概要
(1) 会の設立の経緯と組織、予算
1972年の春、混乱と貧困の中にあった独立直後のバングラデシュに「バングラデシュ復興農業奉仕団」が派遣された。シャプラニールは、その参加メンバーが帰国後に設立した「ヘルプ・バングラデシュ・コミティ(HBC)」を前身とする、日本の代表的NGOの一つである。バングラデシュ農村部(96年からはネパールでも活動を開始)で相互扶助的な組合(ショミティ)活動を通し貧困層の自立を目指した協力活動を行っている。またそれとともに、日本国内では講演・交流等による海外協力への啓蒙活動、およびバングラデシュの貧困層が作った手工芸品の販売などによる活動の資金作りを行っている。
日本国内での組織は、会員約3,900名、運営委員約20名、事務局スタッフ12名からなる。海外の主な活動地であるバングラデシュの組織は、日本人駐在員が現在1名(97年11月現在)、現地スタッフ113名、受益者であるショミティの組合員は12,884名(97年3月現在)となっている。96年から活動が始まったネパールでは、日本人駐在員が一名派遣され、現地のNGOと共同で貧困層への支援活動を行っている。
1997年度のシャプラニールの予算は収入が2億1,300万円。内訳は、会費が3,000万円、一般寄付が3,500万円、国内活動収入が700万円、事業収入が9,800万円、民間助成金が2,000万円、国際ボランティア貯金が800万円、政府補助金が1,500万円である。自己財源率(総収入に占める会費、一般寄付、活動収入等の割合)は62.6%を目指している。支出は2億1,642万円で、うち海外活動費(日本人駐在員の手当てを含む)は8,700万円(支出の41%)を予定している。
| プロジェクト名 | 地域名 |
組合数 (男性・性) |
組合員数 (男性・女性) |
職員数 (男性・女性) |
組合の成熟度(D、Eグレードの割合) *3 |
|
ポイラ CDOl *1 |
マニクゴンジ県ギオル郡 | 120(30,90) | 1,916(496,1,420) | 16(12,4) | 8.3% |
| ナラヤンプールCDC | ノルシンデイ県ベラボ郡 | 169(58,111) | 2,962(1,039,1,923) | 20(16,4) | 15.8% |
|
アムラボ CDC |
ノルシンデイ県ベラボ郡 | 151(48,103) | 2,546(846,1,700) | 17(13,4) | 8.6% |
|
イショルゴンジ 1CDC |
マイメンシン県イショルゴンジ郡 | 153(86,67) | 2,480(1,418,1,062) | 19(15,4) | 6.5% |
|
イショルゴンジ 2CDC |
マイメンシン県イショルゴンジ郡 | 162(97,65) | 2,980(1,822,1,158) | 18(14,4) | 3.7% |
| 合計 | ------ | 755(319,436) | 12,884(5,621,7,263) | 90(70,20) | 8.5% |
| ダッカ事務所 | ダッカ市 | ------- | -------- | 23(18,5) *2 | ------- |
注 2 ダッカ事務所職員のうち2名は男性日本人(1997年11月現在は男性1人)。
注 3 A~Eまで5段階あり、Eが最も成熟度が高い。グレード付けの基準は表3の注1を参照。
出所 Annual Report 1996-97, Shapla Neer-Bangladesh
(2) バングラデシュ国内における活動の概要
1) 活動のエリアと方法
シャプラニールは首都ダッカに事務所を構えるとともに、バングラデシュの3県の5地区で約1万3,000人の貧困層を対象に、ショミティと呼ばれる相互扶助的な小組合を通して支援活動を行っている。活動地区の概要は、第1表に示したとおりである。支援活動の方法は、先ず15~25人程度からなるショミティを一定の基準を満たす貧しい住民に自分たちで作ってもらう。そして、各地区にあるシャプラニールのオフィス(Community Development Center:CDC)で働いているフィールドオーガナイザー(F.0.)がこのショミティを通じて、組合員の意識向上へのモチベーション、ショミティ活動の具体的指導、ショミティおよびその組合員への各種サービス提供を行う(第1図)。ショミティ担当のF.0.は一人当たり平均17のショミティの面倒をみている。
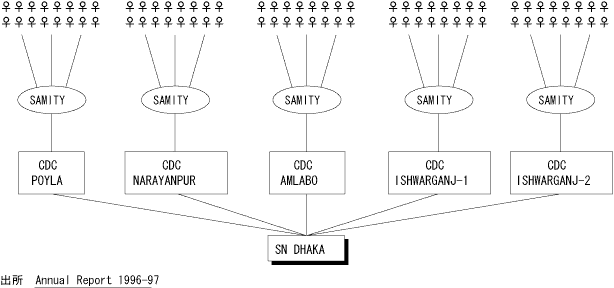
イスラム教徒がマジョリティであるバングラデシュの社会・文化への配慮等から、ショミティは男女別々に作られる。サービスの重複を防ぐため、原則として1世帯から一人しかシャプラニールのショミティのメンバーになれず、組合員およびその家族が他のNGOの組合員になることも認められていない。また、シャプラニールは貧困層を対象にしたターゲットアプローチをとっているため、組合員になるには、1.5エーカー(地域により2エーカー)以上の農地を所有していないことなどの条件を満たす必要がある。
| 事業名 | プログラム |
| 能力形成事業 |
グループ発展&モチベーションプログラム 成人識字教育プログラム ・成人識字教育フォローアップ ・ライブラリープログラム ・シャプラションバッド(雑誌)発行 グループ研修プログラム 保健教育プログラム 文化プログラム ジェンダー問題&発展 |
| サービス提供事業 |
手押しポンプ井戸 衛生トイレ 児童教育プログラム 持続的環境プログラム |
| 経済発展事業 |
経済事業&農業発展 所得向上活動(IGA) ・新しい所得向上プログラムの開発 ・活動資金の増大 技術研修・職業研修 |
ショミティのメンバーは定期的(週に一度)のミーティングを持ち、ショミティ活動の課題、それぞれが抱える問題などについて話し合う。それとともに、ショミティ活動の中心となっている定期貯金(額はそれぞれのショミティで決める)の積み立てを行う。F.O.は定期的にこのショミティのミーティングに参加し、活動を指導する。
2) シャプラニールの事業の概要
ショミティ活動を通じた貧困層へのシャプラニールの支援事業は、(1)能力形成事業、(2)サービス提供事業、(3)経済発展事業の3つに分類される(第2表)。
このうち最も重視されているのは、貧困層の自立に必要な最低の知識(特に成人識字教育を重視)や意識の向上を目的とした能力形成事業である。
サービス提供事業は、本来なら政府が行うべき保健衛生や初等教育など各種のサービスが貧困層に必ずしも届いていないバングラデシュ農村の現実に鑑み、それらのサービスをシャプラニールが肩代わりして行う応急処置的な事業である。
貧困層の自立に必要な能力がある程度形成されたあとで行われる経済開発事業は、所得向上プログラム、技術研修、ローン提供などにより、貧困層の経済的向上を目指している。
2.活動現場の視察の概要
共同評価チームによるシャプラニールの活動現場視察は、以下のようなスケジュールで行われた。
まず10月29日にシャプラニールダッカ事務所においてシャプラニールの現地スタッフから、シャプラニールの活動の目的と内容についてかなり詳しい説明を受けた。
翌30日には、バングラデシュ政府側の外国援助の窓口である大蔵省経済関係局(Economic Relations Division, Ministry of Finance)の次官補(Additional Secretary)であるShahel Ahamed氏から、政府がNGOについてどのように考えているかヒアリングを行った。また、その際日本のODAに対する率直な感想を聞くこともできた。
31日には、シャプラニールのプロジェクト実施地区の一つであるノルシンディ(Narshingdi)県のナラヤンプール(Narayanpur)CDCに移動し、F.O.等のスタッフから活動内容等について説明を受けた。ちなみに、ナラヤンプールCDCは、第1表から分かるようにショミティの成熟度が高く、シャプラニールのプロジェクト地区の中では最も成功している地区である。
11月1日には、6人の共同評価チームを二つのグループに分け、シャプラニールの現地スタッフの案内で、各グループ6ショミティ(計12ショミティ)を視察し、ショミティの組合員からシャプラニールのショミティ活動に対しヒアリング調査を行った。視察したショミティは女性ショミティが8(内成人識字教育クラス2)、男性ショミティ4(内成人識字教育クラス2)であった。比較的成熟度の高いショミティから低いショミティと、多様なショミティを見ることができた。
11月2日は、小学校をドロップアウトしたり、就学年齢に達しても就学していない貧しい村人の子供たち(必ずしもシャプラニールの組合員の子弟を対象にしてない)を復学させるためにシャプラニールで行っている補習授業(5年生までを対象)を視察した。その後で、補習授業を受けている子供たちが通っている近くの小学校を訪問して、校長先生から公共教育の課題等についてヒアリングを行った。午後は、ナラヤンプールCDCがあるベラボ(Belabo)郡の郡役場、畜産発展センター(Livestock Development Center)、病院などにおいて政府機関とNGOの協力(連携)活動や調整についてヒアリングを行った。
3.シャプラニールの活動評価
以上の調査によって得られた結果を評価基準リストに沿って整理していこう。
(1) 持続性
1) 活動の持続性
シャプラニールの活動の持続性についてはいくつかの観点に分けて考える必要がある。まず、人(スタッフ)・資金・組織についてであるが、シャプラニールは25年にわたってバングラデシュで協力活動を行ってきた団体である。日本国内の支援組織もしっかりしており、協力活動が突然停止することはないと考えられる。
| グレード | ナラヤンプール | アムラボ | ポイラ | イショルゴンジー1 | イショルゴンジー2 | 合計 |
| A | 45(26.6) | 41(27.2) | 46(38.3) | 57(37.3) | 70(43.2) | 259(34.3) |
| B | 49(29.0) | 47(31.1) | 28(23.3) | 41(26.8) | 58(35.8) | 223(29.5) |
| C | 50(29.6) | 50(33.1) | 36(30.0) | 45(29.4) | 28(17.3) | 209(27.7) |
| D | 15(8.9) | 8(5.3) | 4(3.3) | 7(4.6) | 6(3.7) | 40(5.3) |
| E | 10(5.9) | 5(3.3) | 6(5.0) | 3(2.0) | 0(0.0) | 24(3.2) |
| 合計 | 169(100.0) | 151(100.0) | 120(100.0) | 153(100.0) | 162(100.0) | 755(100.0) |
注 1 シュミティのグレード付けの基準は、以下の通り。(1)組合員一人あたりの資金量、(2)(利益/資金)の割合、(3)決議案作成が組合員自身でできるか、(4)討論内容の記録、(5)決定事項の実施状況、(6)簿記記帳ができるか、(7)会計の理解、(8)話し合いへの参加度、(9)資金の利用効率、(10)社会活動への参加度最低のAグレードは、一人当たり資金が200タカ(約600円)未満、簿記は自分たちでできず、会計が理解できない、社会活動への参加がない、という状態。最高のEグレードは、一人当たり資金量が1,600タカ(約4,800円)以上、簿記はCDCの助けがあれば2人以上が可能、会計は4人以上が理解、資金の70%以上が有効に利用されている、といった状態。
2 97/98年度は、D、Eグレードの全ショミティに対する比率を20%以上にすることを目標としている。
しかし、後で見るようにバングラデシュにおけるシャプラニールの支援は、貧困層が組織化され社会的・経済的に自立していくための触媒機能と考えられるべきである。特定のグループに継続してずっと恩恵を与え続けることがシャプラニールの目的であってはならず、自立を支援し、自立した組合からは順次手を引いていかなくてはならない。そうした視点からすると、シャプラニールが行った支援活動の効果が、シャプラニールなしでも持続することが必要である。シャプラニールの年次報告書ではショミティの成熟度についてグレード付けを行っているが、成熟度が高いD、Eグレードは全体の1割以下で、成熟度の低いA、Bグレードが6割以上を占めている(第3表)。シャプラニールの関与がなくなったり減少した場合、成熟度の低い多くのショミティが活動を続けることは困難だと思われる。97年度にはD、Eグレードのショミティの割合を20%以上に引き上げることが目標とされており、結果が注目される。
ただ、我々共同評価チームが成熟度の低いA、Bグレードのショミティの活動を視察した限りでは、「たとえシャプラニールの支援がなくなっても定期的なミーティングと貯金活動は続けていきたい」という意向が強いようであった。貯金によって組合員が経済的な安定を得られること、ミーティングによって色々な悩み事を話し合えること、会計簿の記帳の仕方を学んだことなどが、シャプラニールなしでもショミティ活動が継続する大きな要因といえそうである。
余談ではあるが、貯金と相互融資を核とするショミティの活動は、日本でもかつて広範に見られた頼母子講と共通性が高い。こうした組織は、貨幣経済がある程度発達し、かつ銀行や信用組合などフォーマルな金融機関の発達が十分ではない社会で広範に存在するものである。現在のバングラデシュの農村部でも、貯金組合(ションチョイ・ショミティ)と呼ばれる自生的な貯金・貸し付けグループが叢生している。そうした意味で、シャプラニールが採っているショミティ方式は非常に自然な方法であり、それだけシャプラニールなしでも持続する可能性が高いといえよう。シャプラニールは、こうしたショミティ形成のきっかけとなり、会計簿の記入方法を指導し、ともすれば会計の不明瞭性から解体しがちなショミティをフィールドスタッフの指導によって支えるという意味で、ショミティ活動にとって触媒機能・安定化機能を果たしているといえよう。
一方、現在シャプラニールの活動の中心となっている成人識字教育、意識向上のモチベーション、保健衛生サービス、融資供与などは、シャプラニールなしでは継続不可能であろう。ただ、こうしたサービスは永続的にシャプラニールによって提供されるべきものでもない。成人識字教育は一度行われるだけだし、意識向上モティベーションもいつまでも行われるものでもない。保健衛生サービスなど行政・民間医療機関が行っているものは、シャプラニールが最初は肩代わりしたり仲介役とはなっても、貧困層が力を付けたり、行政が貧困層にも目を向けるようになれば、シャプラニールの肩代わり的・仲介的役割は終了するはずのものである。ローン供与についても、貯蓄などによってショミティの自己資金が充実したり、銀行等フォーマルな金融機関から借入れられる力がつけば、シャプラニールの役割は必要がなくなるだろう。
2) 0wnership
シャプラニールの活動が受益者である組合員や運営を行っているスタッフにとってどの程度自分達のものとして主体的に担われているか、つまりどの程度組合員やスタッフがシャプラニールの活動に対してownershipを持っているかについて見てみよう。
ショミティのメンバー達にとってショミティは自分たちのものと受けとめられているようである。ショミティ活動により各組合員の貯金がたまり、またその運用によって得た利益が増大していくのが実感としてわかる。その額は彼らの生活からすれば非常に大きな額である。シャプラニールは貯金と運用利益からなるショミティの資金を随時組合員の間で分配することを認めていない。そのためその資金が直接組合員の現在の生活向上にはつながらないものの、それは明らかに将来の投資や消費への資金であり、生活の危機に直面した時の備えである。また、他の多くのNGOと違ってシャプラニールはショミティの資金(貯金十運用利益)をショミティ自身の管理にまかせている。このようなことが、ショミティに対するownershipを高める最大の要因であろう。また、気の置けない仲間達と日々の生活の悩みなどについて話し合えることができるショミティ活動は、組合員にとって楽しいものと捉えられているようである。決して成熟度が高い方ではないショミティを我々が視察した時にも、「たとえシャプラニールがなくなっても私たちのミーティングと貯金活動は続けていきたい」という話であったが、これはショミティの組合員がショミティ活動にはっきりとしたownershipをもっていることを示していると考えてよいだろう。
しかし、既に見たようにシャプラニールが各ショミティや組合員に提供するプログラムはかなり一方通行的なものである。そのサービスを受けるか否かの選択はショミティの側にあるにしても、ショミティはやはりサービスに対して受け身であると考えられる。後で提案するように、CDC運営への各ショミティ代表の参加など、シャプラニールのプログラム自体に対するownershipの向上が今後の課題であろう。
次に、シャプラニールに対するスタッフのownership意識について簡単にみたい。シャプラニールのスタッフは、シャプラニールの職員として社会改善に取り組んでいることに対して、満足感を持っているようである。しかし、彼らスタッフは完全にシャプラニールの被雇用者であり、能力とやる気に欠けると見られると日本の雇用慣行では考えられないほど容易に解雇されてしまう(ただし、これはバングラデシュでは通常のことであるらしい)。スタッフの業務能力や態度に対する厳しい管理が、特権意識に甘んじがちな行政機関に比べて、シャプラニールを緊張感があり能率の高い組織にしているという側面は否定できない。しかし、こうした状況ではシャプラニールのスタッフがシャプラニールという団体に対してどの程度のownershipを持っているかは若干疑問である。
聞くところによれば、現在シャプラニールが直接運営しているナラヤンプールCDCはかつてその地域住民による独立したNGOであり、シャプラニールとはパートナーの関係にあった。放漫経営など問題点が少なくなかったらしいが、活動に対するownershipという点では当時の方が高かったと考えられる。
現在シャプラニールでは、バングラデシュ現地事務所の独立性を高めるような改革議論も進んでいるという。現地スタッフのownershipの向上は今後の課題の一つであろう。
3) 能力形成度
シャプラニールの目的は、政府の開発行政から取り残されがちな貧困層が力を付け、社会・経済的に自立するために支援をすることである。だから、そのための能力形成プロジェクトはシャプラニール活動の核となっている。シャプラニールの活動は主に相互扶助的なショミティを通して行われるから、ショミティ活動のメリットを最大限に生かすようにグループ活動の利点についてのモチベーションを与え、ショミティの円滑な運営を可能にするためにシャプラニールは様々な研修を行っている。バングラデシュ事務所の総支出の実に52%がこのグループの発展とモチベーションに使われている(第4表)。これらの研修は、(1)グループ運営研修、(2)会計簿記研修、(3)社会意識向上研修、である。昨年度(96/97年度)は(1)、(2)、(3)のそれぞれで、560人、460人、100人の組合員の研修を行った。当初の目標に対する達成率は95~100%であった。年次報告書によれば、こうしたグループ運営研修を受けたショミティは、研修を受けていないショミティに比べて意思決定、組合運営、会計等において優れており、研修の効果が見られるという。その他にも能力形成事業として、保健衛生教育、文化プログラム(重婚の問題性、社会的不正、女性の権利、環境問題等の社会性の高い問題をテーマとした演劇)、女性の地位向上プログラムをおこなっている。
(2) 妥当性
1) 女性の参加とエンパワーメント
シャプラニールの能力形成事業の中には「ジェンダー関係&開発プログラム」があり、男女平等意識を高める活動を行っている。また、組合員の56.4%(1997年3月現在)は女性であり、しかも近年女性ショミティや女性組合員の比率は上昇傾向にある。識字教育、女性の権利についてのモチベーション、所得向上プログラムなどを通して、意識面・経済面での女性の地位が向上していることがうかがえる。「ショミティを始める前は知らない男性と話したりできなかった」という女性組合員達の話を聞いていると、ショミティ活動によって女性たちの意識が明らかに向上していることがわかる。近々行われる村議会選挙にシャプラニールの女性組合員の何人かが立候補するという報告もあり、社会的にも地位向上が明らかにみられる。組合員の妻を持つ夫も、妻がショミティ活動をすることで家族への貢献(貯金、トイレや手押しポンプ井戸の廉価購入、農地の借入、子どもの教育等)が期待でき、協力的なようである。
ただ、組合員に占める女性の比率が50%以上であるにもかかわらず、スタッフの中の女性の割合は20%程度と組合員の男女比からすると少ない。バングラデシュという男性中心の社会を率先して変えていくためにも、もっと女性スタッフの数を増やしてもよいのではないか。
| 支出項目 | 金額(タカ) | 構成比(%) |
| ダッカ事務所管理運営 | 1,395,015.65 | 6.2 |
| 中央研修所 | 602,842.00 | 2.7 |
| グループの発展とモチベーションプログラム | 11,602,693.65 | 51.6 |
| グループ研修プログラム | 869,410.00 | 3.9 |
| 成人識字教育 | 1,521,874.00 | 6.8 |
| 保健教育プログラム | 498,955.00 | 2.2 |
| 文化プログラム | 121,239.00 | 0.5 |
| 保健衛生プログラム | 1,546,466.00 | 6,9 |
| 児童教育プログラム | 1,548,780.00 | 6.9 |
| 持続的環境プログラム | 237,129.00 | 1.1 |
| 経済開発プログラム | 579,996.00 | 2、6 |
| スタッフ開発プログラム | 156,473.25 | 0.7 |
| 設備投資 | 355,756.00 | 1.6 |
| グラミンバンクサーベイ | 708,781,00 | 3.2 |
| リハビリテーションプログラム | 757,108.00 | 3.4 |
| 合計 | 22,502,518.55 | 100.0 |
注1 融資事業は別会計。
注2 日本人駐在員の手当てはここには含まれない。
2) 最底辺への到達度
シャプラニールは、貧困層を支援の対象としたターゲット・アプローチをとっており、受益者は一定の経済水準以下の貧困層に限定されている。しかし、その基準の一つである所有農地面積の上限は1.5エーカー(地域によっては2エーカー)と比較的高い。これは、中程度の経済層もシャプラニールの組合員になれることを意味している。全くの土地なし層などかなり貧しい層がかなりシャプラニールの組合員になっているのは確かだが、組合員の経済階層分布などのデータはなく、最底辺層がどの程度シャプラニールの組合員となっているのかはっきりしたことは分からない。
バングラデシュの農村部には、物乞いをしなくては生活できないような土地なしの一人暮らしの老人や夫に死なれた貧しい女性、心身に障害を持つ人々など、社会の慈善によってしか生活できない人が少数ながら存在する。そうした真に最底辺の人々までシャプラニールの直接の恩恵は届いていないようである。つまり、シャプラニールの活動は、貧困層ではあっても自らの組織とシャプラニールの支援により自立できるような、一定の力を持つ人々を対象に行われている。もちろんこれはシャプラニールの問題というよりは、ショミティ(組合)方式のアプローチが持つ限界といえる。
ただ、シャプラニールは直接こうした真に最底辺層を支援対象にはしていないが、現地でのヒアリングによれば、ショミティは医者に行くお金がない貧しい人などに募金を行うなど社会活動をおこなうケースが多いようである。シャプラニールの活動は、間接的には社会の最底辺層へのある程度の貢献をしているといえる。
3) 自然環境への配慮
シャプラニールの活動には、サービス提供事業の一環として持続的環境プログラムが盛り込まれている。これは、植樹プログラムと有機農業プログラムからなる。
植樹プログラムは、組合員が家屋敷の周りなどに樹を植えられるように、経済性が高い果樹や用材用の樹木の苗を安価で販売することを目的としている。今回訪問したショミティでの聞き取りによると、組合員は植樹の重要性をかなりよく理解しているようであった。
また有機農業プログラムでは、有機農業の技術研修を受けた10人のスタッフが組合員の中の希望者に対して技術指導を行っている。また、各CDCには事務所の敷地内で有機農業のデモンストレーションがなされている。多くの組合員は農民であり、自分でも農薬を使用することから農薬の危険性に対しては身を持って知っていた。ただ、農薬や化学肥料を使わなくては市場で売れるような農産物がなかなか効率よく生産できないのも事実である。農薬・化学肥料などをあまり使わなくても農産物を生産できるような技術があったら教えて欲しいと、こちらが要請されるような状況であった。とはいうものの、「DDTが手に入れば非常に効率よく農業ができる」という者もいて、農薬の正しい知識が普及してはいないようである(DDTは急性毒性は弱いが、生物体内に濃縮され、生殖能力などに損傷を与える。ほとんどの国では使用が禁止されている)。
環境保全型農業の技術習得に対しては潜在的ニーズは高い、というのが我々が得た感触であった。にも関わらず、有機農業技術の研修を受けた組合員の数は過去3年間で、全地区でも72名にすぎないという(全組合員の100分の1以下)。シャプラニールの組合員の間でも所得向上のために野菜栽培や高収量品種稲などの導入が進みつつあり、農薬や化学肥料の使用が拡大している。農薬の直接の被害者でもある組合員の健康を守り、環境や消費者への悪影響を防ぐためにも、環境保全型農業技術の普及に対する努力がシャプラニールでも一層期待される。
4) 住民の参加
シャプラニールの受益者は希望者が自分達でショミティを形成するという意味で、シャプラニールのショミティは住民の自発性を活動の出発点としている。しかし、ショミティとシャプラニールの関係は基本的にサービス提供者と受益者の関係であり、通常はシャプラニールが決めたサービスメニューの枠内での活動が行われる。また、ショミティの組合員がシャプラニールの運営に直接関わることはまだない。
もちろん、シャプラニールのサービスメニューの作成には、ショミティの組合員の意向も反映されるように努力されており、どのようなサービスをいつ受けるかなどは、ショミティが自分たちで決めることになっている。識字教育、ドロップアウトした子どもの補習教室、トイレやポンプ井戸など衛生設備の設置などではある程度の費用負担をショミティやメンバーにしてもらっており、シャプラニールのプログラムヘのownershipや参加意識が高まることを期待している。また、各ショミティの活動そのものは完全に組合員の自発的参加の下に行われている。シャプラニールのサービスに不満を持つショミティが他のNGOに乗り換えたり、逆に他のNGOの受益者だったグループがシャプラニールに乗り換えることもよくあるという。
(3) 目標達成度
計画目標の達成度
シャプラニールでは活動の上位目標として貧困層の自立を掲げているが、そのために、貧困層の(1)能力向上、(2)公共サービスヘのアクセス改善又はその暫定的な肩代わり、(3)所得向上プログラムの実施、を行っている。ここでは、シャプラニールの活動の中核である能力形成事業について見てみたい。シャプラニールではモチベーションプログラムによる意識向上や成人識字教育などにより、貧困から脱し自立するための能力向上(エンパワーメント)に重きを置いている。ちなみに、バングラデシュ農村部では成人識字率は33.6%と非常に低い(1995年)。読み書きや簡単な計算ができないことが、農村貧困層の自立にとって非常に大きな障害となっている。我々共同評価チームは成人識字教育を視察したので、これについて若干詳しく見てみよう。シャプラニールでは96/97年度に1,059人(男性611人、女性448人)—全組合員の8.2%に相当—が9ヶ月コースの成人識字教育を受けた。89/90年から96/97年までの成人識字教育プログラムを受けた組合員の累計は、年次報告書各年版によると9,415人に達している(第5表)。現在1万3,000人程度いる組合員の中には当初からの識字者で識字クラスを受ける必要がない人もいることを考えれば、組合員のかなりの割合が、成人識字教育プログラムの恩恵を受けたといえよう。
識字教育の教科書には生活改善のための知識や意識の向上をもたらすようなテーマ(保健衛生、家族計画、栄養改善、教育の必要性、女性の権利主張の重要性等)が盛り込まれている。また、このコースの終了時には、簡単な計算能力も身につくようなカリキュラムとなっている。実際に識字教育を受けている受講者に話を聞くと、文字が読み書きできることのメリットとして、看板やバスの座席番号が読めるようなって人に頼ることがなくなった、子どもに勉強を教えられるようになったなどの生活の変化があったと報告された。実際の生活上の利便性だけでなく、人に依存しなくてもよいという自信をつけるのに役立っているようである。また、途中でドロップアウトする受講者の割合は10%程度と低い。
シャプラニールのスタッフによると、こうした成人識字教育を受けた後ある程度の読み書きの習慣が定着するのは最終的には受講者の5~6割だという。しかし、識字教育の過程で教育の重要性を認識し、自分の子供たちには是非教育をつけさせたいという意見が受講者には圧倒的に多かった。成人識字教育の効果は、次世代に一層顕著に表れてくるのかもしれない。
| 年度 | 男性 | 女性 | 合計(A) | 組合員数(B) | (A)÷(B)(%) |
| 89/90 | 580 | 300 | 880 | 5,879 | 15.0 |
| 90/91 | 840 | 360 | 1,200 | 5,701 | 21.0 |
| 91/92 | 512 | 709 | 1,221 | 6,362 | 19.2 |
| 92/93 | 448 | 686 | 1,134 | 7,126 | 15.9 |
| 93/94 | 633 | 770 | 1,403 | 9,882 | 14.2 |
| 94/95 | 550 | 930 | 1,480 | ? | ? |
| 95/96 | 516 | 522 | 1,038 | ? | ? |
| 96/97 | 611 | 448 | 1,059 | 12,884 | 82 |
| 累計 | 4,690 | 4,725 | 9,415 | - | - |
注 組合員数に占める識字教育受講者数の割合が低下傾向にあるのは、組合員のうちの識字者の比率が高くなっていることなどから新たな受講適格者が減少しているため
(4) 効率性
1) 施設の効率性
シャプラニールの事務所や提供するサービス(簡易トイレ、手押しポンプ井戸、識字学校の小屋等)は、概して非常に質素である。サービスについては、ショミティ組合員の一定の自己負担も必要であり、現場の実情に合った施設・設備が選ばれていると考えられる。シャプラニールの施設の質素さは、我々が視察した政府援助資金による学校などの設備の立派さと対照的である。こうしたことから、シャプラニールは施設に関しては限られた資金を効率よく活用しているとみて良いだろう。
2) 事業の効率性
しかし、資金の使われかたは必ずしも全ての点で効率的とはいえない。例えば、1996/97年度のバングラデシュ事務所の総支出は約2,250万タカ(約6,750万円)だが、これをショミティの組合員一人当たりにすると1,747タカとなる。貧困世帯の平均的な年間所得をかりに12,O00タカ(月1,000タカ)とするとこれはその約15%に達する。シャプラニールと同様の活動をしている他のNGOと比較できるデータはないが、この組合員一人当たりの必要費用は、モチベーションや意識化に重点を置いていない他のNGOよりも多そうである。シャプラニールでは、これをこの団体が他のNGOよりもきめの細かいケアを行っているため、と説明している。
ただ、実際にある程度の経験を経たショミティでの聞き取りでは、「グループ活動のモチベーションなどは皆既によく理解しているのでもう必要ない」、といった意見も聞かれた。シャプラニールのバングラデシュ事務所の総支出額の52%がグループ発展とそのモチベーションに使われていることを考慮すると、グループ活動へのモチベーションをより効率化することが必要であろう。成熟したショミティから徐々にシャプラニールが関与を減らしていくことは、単なる経費節減という点から必要だけでなく、後で提言するように成熟したショミティのシャプラニールからの自立を実現するという点からも不可欠であろう。
3) 融資プロジェクトの効率性
次に融資の効率性について見てみたい。融資を中心とする所得向上事業は、シャプラニールの活動ではそれほどプライオリティが高いものではないが、それでも96/97年度のバングラデシュ事務所の総支出の31%に相当する(ただし融資事業は別会計になっている)。シャプラニールが96/97年度にショミティに提供した融資の額は組合員の貯金総額の1.1倍、ショミティの自己資金(貯金十利益)の50.7%に達している。組合員からも、ローン借入に対する期待が高い。その最大の理由はシャプラニールの提供するローンが低金利であることと考えられる。シャプラニールの金利は年利7%である。これに対して銀行は年利15.5%(このほかに元金の10%程度が賄賂として必要だという)、高利貸からの場合は実に月利10%(年利120%)というから、これらと比較してかなり低金利である。農村貧困層への融資機関として有名なグラミンバンクに比べても半分程度である。返済率は99%と極めて高く、融資の健全性は高い。
グラミンバンクや他のNGOと比べたシャプラニール融資の特徴は、組合員個人への融資ではなく、ショミティに貸出されることである。これはショミティの結束力を高める一方で、資金の使われかたが不効率になりやすい。つまり、組合員は直接個々の所得増大につながらないショミティ活動にはあまり手を掛けたくないから、ショミティに対するローンの多くは、手がかからずかつ安全な投資に向かうことになる。牛の飼育やジャガイモ栽培など生産活動に投資されるローンがある一方で、ローンのうち金額にして56%、件数にして47%と約半分は農地のモーゲージ(普通「ボンドック」と呼ばれる)、つまり、第三者に金を又貸しし、その利子として一定の農地の耕作権を得ることに使われる(第6表)。この場合、最終的に金を借りた人が金を返済しないかぎり、永久にこの農地の耕作権はショミティのものである。ショミティはこうして得た農地の耕作権をまた別の者に貸し(土地所有者本人の場合もある)、最終的に利回りにして15~20%程度の利益を得るのである。これは一種のローンの仲介であり、シャプラニールの低利融資と運用利回りの差を組合の収入とする。
こうして得た農地は最終的には組合員の誰か(農地を最も必要としている、組合員の中でも貧しい人が多いようである)に貸されることが多いようだから、シャプラニールの融資は組合員の生活改善に一定程度役立ってもいるのは事実である。見方によれば、シャプラニールのローンは貧困者の資産(農地の耕作権)を増やすソフトな土地改革としての役割を果たしている(ただし、土地の出し手が富裕層であるとして)。しかしこうした資金の使われかたは、少なくとも直接的には生産的投資ではなく、社会的にみればあまり効率的でない可能性がある(本当は、このローンの最終的借手がどのような目的でこの金を使っているかを調べなくてはいけない)。多くの場合最終的耕作者となる貧しいショミティ組合員もかなり高い地代(刈分け小作形態の場合収穫物の半分)を払わなくてはならないから、小作者となる貧しい組合員にとってもそれほど大きな収益をもたらさない。
一方、ショミティの自己資金の中から組合員・非組合員に貸出されるローンは商売の資金や農業投資、病人の治療などかなり有効に使われている。だがこの場合、利子は農村の一般利子、つまり年利にして50~120%と高利で、借りる額も少額にならざるをえないようである。シャプラニールが行う低利融資の恩恵は個々の組合員には効率的には届いていないといえそうである(以上ショミティの資金の流れについては第2図を参照)。また、返済率が極めて高いとはいえ、年7%の利子率では融資事業にかかるコストをまかないきれなく、融資の量も制限せざるを得ない。
| 投資計画 | ナラヤンプール | アムラボ | ポイラ | イショルゴンジ-1 | イショルゴンジ-2 | 合計 | 比率(%) | |
| 金額 | 件数 | |||||||
| 牛の飼育 | 155,400(11) | 83,000(8) | 88,500(4) | 325,500(20) | 163,000(9) | 815,400(52) | 11.7 | 12.7 |
| 肉牛肥育 | 30,000(6) | 29,000(6) | 35,000(7) | 23,000(6) | 23,000(5) | 140,000(30) | 2.0 | 7.3 |
| 土地のモーゲージ | 1,581,000(69) | 566,000(34) | 118,000(4) | 534,500(27) | 1,141,000(61) | 3,940,500(195) | 56.3 | 47.4 |
| 野菜栽培 | 34,000(2) | 1,000(1) | 35,000(3) | 0.5 | 0.7 | |||
| 乳牛 | 25,000(1) | 11,000(1) | 36,000(2) | 0.5 | 0.5 | |||
| 小商売 | 110,100(5) | 50,500(2) | 30,000(5) | 5,000(1) | 4,000(2) | 199,600(15) | 2.9 | 3.6 |
| ミシン購入 | 11,000(5) | 8,800(4) | 8,800(4) | 11,720(4) | 11,000(5) | 51,320(22) | 0.7 | 5.4 |
| 果樹のモーゲージ | 104,000(4) | 612,000(32) | 716,000(36) | 10.0 | 8.8 | |||
| リキシャの組み立て | 8,000(1) | 8,000(1) | 5,000(1) | 21,000(3) | 0.3 | 0.7 | ||
| ジヤガイモ栽培 | 767,500(35) | 767,500(35) | 11.0 | 8.5 | ||||
| リキシャ購入 | 22,000(2) | 31,600(3) | 36,000(2) | 89,600(7) | 1.3 | 1.7 | ||
| 稲作 | 14,600(6) | 146,000(6) | 2.1 | 1.5 | ||||
| 手織りばた | 8,000(1) | 5,000(1) | 13,000(2) | 0.2 | 0.5 | |||
| やぎ飼育 | 2,000(1) | 2,000(1) | 0.0 | 02 | ||||
| 竹細工 | 1,000(1) | 1,000(1) | 0.0 | 0.2 | ||||
| 浅管井戸購入 | 20,000(1) | 20,000(1) | 0.3 | 0.2 | ||||
| 合計 | 2,050,500(103) | 1,357,300(87) | 1,234,800(69) | 941,320(63) | 1,410,000(89) | 6,993,920(411) | 100.0 | 100.0 |
注括弧内は貸出件数
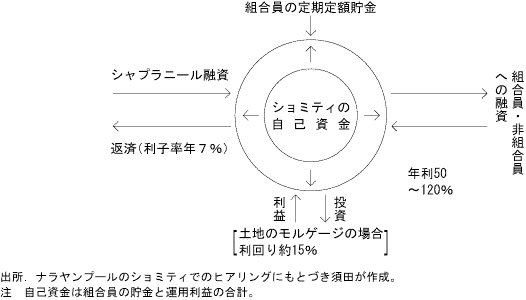
結論として、シャプラニールの融資事業は、ショミティの資金増大には大きな貢献をしているといえる。これは、ショミティの将来的な可能性を増大するが、一方でローンの多くが使われる土地や果樹のモーゲージ資金は必ずしも効率的に生産に投資されているとはいえないし、個々の組合員の当面の生活改善のためにもあまり効率的ではない。低利融資が必要でないショミティには市場金利(銀行並みの金利)で融資して融資事業は独立採算でやって行けるようにし、その一方で多くのショミティがニーズに合った額の融資にアクセスできるようにすることが必要である。それと同時に、各組合員が銀行並みの利子率で融資を得て生産活動や生活改善などに活用できるよう融資の仕組みを改善されることが期待される。 ショミティが将来シャプラニールから独立したとき、貯金・融資事業はその活動の中核の一つであると同時に数少ない財源となると考えられる。ショミティの自立を促すためにも、融資事業の独立採算化をなるべく早く実現することが必要であろう。
(5) インパクト
1) 貧困層の自立への貢献度
既に見てきたように、シャプラニールにとって貧困層の自立を支援することが活動の最大の目的である。相互扶助的なショミティ活動の推進、識字教育、保健衛生の知識普及、所得向上プログラムなどが組合員である貧困者層の社会的・経済的状況の改善に役立っていることは確かであろう。ショミティの約半数が自己資金の管理のために銀行に口座を持つなど、近代的な経済システムを利用する力も身につけつつある。とはいっても、実際にはシャプラニールから「卒業」して自分たちだけで自立した活動を行っているショミティはまだない。既に見たようにショミティの成熟度を示す調査によれば、成熟度の高いD、Eの比率はまだ全体の1割弱である。1997/98年度の目標はこの比率を倍にすることであるというが、「ショミティの自立」はこれからの大きな課題といえよう。ショミティがシャプラニールなど外部援助団体から自立し、自分たちが主役となって運営・発展していくような組織形成を実現することがシャプラニールの今後の最大の課題であろう。
2) Replicability(一般化の可能性)
シャプラニールの活動の拠り所となるショミティは、農村部でも叢生している自生的な貯金組合と基本的には同じであり、ショミティ方式は現地の実状にあった自然な方法であると考えられる。また、ショミティを受け皿とし、貧困層への識字教育など能力形成事業を中心とした支援もバングラデシュでは一般的で、かつ他のNGOでも十分な実績がある。こうしたことから、シャプラニールの援助の方法には一般性が十分あると結論できよう。
3) 行政および他のNGOとの整合性・補完性
大蔵省経済関係局でのヒアリングやジャーナリストに対する記者会見の席上では、バングラデシュではNGOと政府の間で活動の調整がうまく行われていないこと、およびNGO活動の活発化がともすれば二重政府化による混乱を生みかねないことに対する危機感がまだあることが示された。バングラデシュでは周知のように政府の行政能力があまり高くなく、かつ行政官が特権階級化していることなどのために行政が国民の多くを占める貧困層の方を必ずしも向いていない。このような国においては、NGOには政府に対するカウンターパワーとして政府を補完・牽制し、その機能向上・民主化をすすめる役割が期待されている。しかし、社会が成熟するに従い、NGOはその機能の多くを、国民を正統に代表する政府に譲り渡していくことになろう。従って、本来は行政が担う分野においてNGOと政府が無意味に競合するのは好ましくない。その点シャプラニールは、ドロップアウトした生徒の補習や保健衛生プログラムなどのサービス提供事業については、本来行政が行うべきサービスの一時的肩代わりという位置づけを行っており、行政サービスの補完的役割と自己を位置づけている。これは、シャプラニールがめざす貧困層のエンパワーメントとは、行政サービスを含めた各種資源に貧困層がアクセスできるようになることでもある、という考えによる。このような行政サービスとの協力と調整のため、シャプラニールのスタッフは各関係行政機関(郡行政官、病院、家畜センター、小学校等)と良好な連携を行っているようである。
ただ、融資プロジェクトに関してはシャプラニール(他のNGOも同様)と政府の間で借手である農村住民の奪い合いがあるなど、政府とシャプラニールの一層の調整が必要な分野もある。
また、他のNGOとの役割分担や地域分担という点では、シャプラニールの活動している地区がいずれもNGO密集地域であることもあり、他のNGOと競合関係にあるようである。
4. まとめと提言
シャプラニールは、組合(ショミティ)方式によって農村貧困層が自立できるようにきめの細かい支援を行っている。その事業の中心は相互扶助的な組合(ショミティ)活動を中心とした貧困者へのエンパワーメントである。短期ではあったが現場を見る限り、こうした活動の方法は妥当性を持ち、かなりの成果を生んでいるといえそうである。シャプラニールのこの成功の要因の第1はそのアプローチの適切さであり、第2にモラルが高く能力のあるスタッフを抱えていることであり、第3に受益者である貧困者の現状とニーズにあったきめの細かいサービスを行っていること、といえるだろう。行政との関係も良好であり、こうしたNGOが政府開発援助に参加することで、特に社会開発の分野におけるODAの質は改善すると考えられる。
とはいうものの、シャプラニールには既に見てきたように改善が期待される点が少なくないのもまた事実である。細かい点は繰り返さないが、最大の課題はショミティをなるべく早く成熟させ、成熟したショミティがシャプラニールから自立すること(シャプラニールからの「卒業」)、そしてシャプラニールがさらに多くの貧困層に自立のための機会を提供することであろう。大蔵省経済関係局でも指摘されたことだが、NGOの活動が集中している比較的裕福な地域がある一方で、NGOの活動がほとんど見られない、より貧困な地域がバングラデシュの大半を占めている。そうした地域でこそシャプラニールのようなNGOの活動がより強く期待されている。シャプラニールが支援するショミティとその組合員をなるべく早く自立させる道を確立すると同時に、シャプラニールの活動を必要としている他の地域に活動を移し続けていくような機動的な組織にかわっていくことが、今後の最大の課題であろう。
このようにショミティのシャプラニールからの自立は必要だが、それはシャプラニールが一定程度成熟したショミティヘの支援を単に取りやめることではないだろう。例えば、ショミティが自分たちの連合体を作り、これまでシャプラニールが行ってきた機能を自分たちで担うようになることが望ましい将来像の一つとして考えられる。具体的には、各CDCの活動範囲のショミティがメンバーとなる連合体を形成し、シャプラニールから独立して自分たちで運営するNGOをつくる。現在のCDCスタッフはその連合体の事務局になる。シャプラニールは連合会の対等なパートナーとなり情報提供など最低限のサポートをする。このような貧困層自身の組織づくりが成功するためにも、ショミティや組合員の自立とともに、有能でモラルが高く、自立心に満ちたスタッフの育成が不可欠となろう。もちろんその段階に至るまでの経過的措置として、サポートを一定期間続けることも必要であろう。
もう一つシャプラニールについて提言したいのは、コミュニティや、より広い社会・経済全体について一層認識を高めることである。シャプラニールがとってきたターゲット・アプローチは貧困層のエンパワーメントには効率的であったと思われる。貧困層の立場に立つというシャプラニールの立場を堅持しつつも、これからは社会全体のバランスのとれた発展なり安定性という、より大きな枠の中で貧困者への支援活動を行うことが必要になってこよう。シャプラニールが手を引いた後の貧困層の自立とは、彼らがコミュニティや地方政治・経済のなかに自分たちの場を見だしていくことを意味する。彼らがその担い手となり、そこで正当な地位を得るためにも、今以上に広い視点から社会での貧困層の位置づけを行っていくことが必要となろう。単に貧困者からの視点だけでなく社会全体から貧困者を見る視点は、シャプラニールなどNGOが地域住民の代表として行政と関わり(ODAとの関わりも含め)を強めていく過程で一層強くなると思われる。
<参考文献>
シャプラニール=市民による海外協力の会『NGO最前線』柏書房、1993年
中田豊一『援助原論』学陽書房、1994年
「はじめましてシャプラニールです」(活動案内)シャプラニール
「97年度会員総会報告」『南の風』シャプラニール、No.151、1997年7月
Annual Report. Shapla Neer-Bang1adesh、各年版

