第3章 合同評価
英国国際開発省(DFID)との合同評価(フィリピン)
(現地調査期間:1998年3月29日~4月10日)
(日本側)
- 牟田博光 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授
- 沼野太郎 国立教育研究所国際研究協力部国際教育協力室主任研究官
- 新井司郎 オーバーシーズ プロジェクトマネージメントコンサルタンツ
- 安仁屋賢 外務省経済協力局評価室
(英国側)
- セリア・メール Social Development Consultant
- スーザン・ダーストン Team Leader Advisor for Primary Community School Project Malawi by DfID
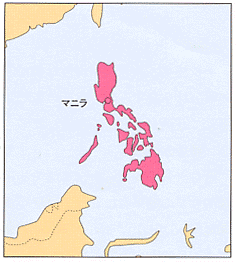
|
プロジェクト名 |
援助形態 |
協力年度、金額 |
協力の内容 |
| 学校校舎建設計画 | 無償資金協力 |
88年度、 25.76億円 90年度、 26.59億円 91年度、 27.45億円 92年度、 27.95億円 93年度、 29.20億円 |
台風等による自然損害を考慮して、教室 が不足して いる初等・中等学校に防災型プレハブ校舎を建設する。また黒板、机、椅子等の基本的な教育資機材を設置し、かつトイレの建設を行う。 |
|
教育施設拡充計画 |
無償資金協力 |
93年度、 |
児童・生徒数が増加して教室が不足している初等・中等学校に従来工法による防災型校舎を建設する。また、机、椅子などの資機材及び理科教育機器などの教材を整備し、かつトイレの建設を行う。 |
| 中学校教育機材整備計画 | 無償資金協力 |
90年度、 5.67億円 91年度、 5.98億円 |
教育機材の整備により、中等教育のレベル向上を図る。 |
1.調査方法
(1) 目的
経済協力開発機構(OECF)の開発援助委員会(DAC: Development Assistance Committee)は、1996年5月、施策方針「開発協力が寄与する21世紀の形成」を発表し、加盟国に対し開発目標の達成に向けてさらに協力するよう呼びかけた。日本および英国政府は、同方針に基づき、教育セクター案件に関する合同評価調査の実施を合意した。本調査は、両国が供与した事業に対し、
- a) 将来の開発援助の方向性や方法を捉えるため、
- b) 実施の妥当性、目標達成度、効果、効率性、および自立発展性の5つの評価視点に係わる実地検証と分析を行い、
- c) 開発計画の策定に係わる教訓を得るとともに、
- d) 可能な範囲で評価の方法・方式の改良を図る
ものである。
本評価調査は、合同評価の第1段階として、日本側がフィリピンにおいて実施した、
- a) 学校校舎建設計画
- b) 教育施設拡充計画
- c) 中等学校教育機材整備計画
の3つの無償案件を対象とする。
学校建築、教育機材供与は我が国が多くの経験を持つ援助分野であり、特に、「学校校舎建設計画」はその草分けをなすものである。また、英国が行っている基礎教育援助プロジェクトと対比する上でも適当と判断して評価案件として選定した。
(2) 評価の手法
既存資料のレビュー、事業や施策の立案機関、実施・モニタリングの担当機関(者)、受益者および国際機関などの関係者に対して聞取り調査と資料収集、および事業サイトの視察を行う。それにより、英国国際開発省(DfID)コンサルタントによる社会開発部門にかかわる検討を付加しながら、上記1項b)に示す評価5項目に即した調査分析を行い、セクターレベルおよび政策レベルの提言を行う。
2.フィリピンの教育環境
(1) 社会条件
フィリピンはおよそ7,100の島々からなる国で、少なくとも70以上の地方言語が使用されるなど、民族、文化、宗教における多様性はこの国の特色となっている。貧困はフィリピンでは依然として深刻な社会問題であり、特に農村において顕著である。半数以上の農村人口が貧困状態にあり、国全体の約3分の2の人口に相当するといわれる。都会における貧困問題は農村のものよりも程度は軽く、また急速な経済成長の恩恵も受けやすく、保健や教育サービスの供給も都市部の方が恵まれている。
現在までのところ、同国は他の東アジア諸国と同程度にまで経済成長を持続させ、貧困を緩和させるには至っていない。さらには、過去に於ける経済成長をみると収入格差が是正されると言うよりはむしろ拡大している。
また、教育や保健分野の諸指標は1960年代と1970年代に一定の改善が見られたものの、以後は進捗は停滞している。これは主に債務危機に付随する経済成長の弱さによるものであるが、ここ数年は経済も安定化し、政府も貧困対策に本腰を入れつつある。政府は「社会改革アジェンダ」を発表、貧困対策の方策を打ち出している。
(2) 政策
フィリピン政府は、国家開発計画の重要課題に位置づけられている「人的資源の育成」を推進するために、教育レベルの向上と地域間格差の漸減、工業化の促進を支える理工系人材の育成に力を注いでいる。
1982年に「初等教育普及計画」が、世界銀行の支援を得て教育施設、教育課程、教育担当者の開発、技術的な支援および研究・調査を目的として策定された。政府は教育機会の均等と就学率の向上を図るため、1983年、「教育開発5ヶ年計画(1983-87)」の実施を開始した。その結果、1982~83年には1,163万人であった初等・中等学校の児童・生徒数は、5年後の1987~88年には1,310万人へと12.6%増加した。しかしながら、就学児童・生徒数の上昇は人口増によってもたらされた表面的な数字であり、個々の家庭における所得や政府教育予算等の経済的な問題から、就学率自体の改善は大きくなかった。
その後、アキノ政権は、1986年2月、「中期国家開発計画(1987-92):Medium Term Philippine Development Plan」を発表し、社会的不平等の改善を図りながら、生活向上と経済成長を図ろうとした。教育はそのための重要な要因であり、1987年に発布された新憲法は、教育予算の最優先規定を明記し、1988年からの中等教育の無償制度の導入や各種奨学金の充実など、教育制度の整備`拡充も図られた。
「初等教育普及計画」に基づく初等学校卒業生が出る1988年、教育文化スポーツ省(DECS:Department of Education, Culture and Sports)は中等教育の総合的レベルアップをめざした「中等教育開発計画(SEDP:Secondary Education Development Program, 1988-93)」を策定した。カリキュラムの改善、教員養成、学校施設拡充などによって、アチーブメントテスト成績の改善、中途退学者数の低減、就学率の増加および対生徒教師割合の改善等を図った。「中等学校教育機材整備計画」は、このSEDPに基づき日本政府に要請された援助案件である。フィリピン政府は、日本政府の他にアジア開発銀行、オーストラリア(AIDAB)、アメリカ(USAID-ESF)、ドイツ(GTZ)およびカナダ(CIDA)にも支援を要請した。さらに、「中期国家開発計画」を改訂(1990~92)し、教育の質の向上と教育機構の改善に努めた。
同時期に、国家教育・人材養成計画が作られ1992年までの教育に関する目標値が設定された。学校校舎建設については、1992年までに、全国で40,252校の初等・中等学校教室建設が必要とされた。「学校校舎建設計画」は、この計画に基づいて日本政府に要請された援助案件である。1989年には基礎教育の改善のため、「万人のための教育:行動計画(1991-2000)」が策定された。計画期間中にすべてのフィリピン人に基礎教育を与えることを目指し、初等教育の質と効率の改善、すべての国民の識字などの目標を掲げた。
1992年6月に大統領に就任したラモス大統領は、ピナツボ火山の噴火や台風等自然災害、経済の停滞、治安の悪化、国論の分裂といった負の遺産を引き継いだが、電力対策や経済対策など各種政策の推進に努めた。1992年10月に政府が策定した「新中期国家開発計画(1993-98)」は、自然災害や人口増に対応した教育環境の改善を図り、人的資源の開発、国際競争力強化とそれによる持続的な経済成長を達成すると共に、貧困撲滅と社会的公平を実現しようとするものであり、自由化、規制緩和、分権化を打ち出している。ラモス大統領の掲げる「フィリピン2000」計画の中核をなしている。
新中期国家開発計画を受けて、DECSは「DECS中期国家開発計画(1993-98)」を策定した。「教育施設拡充計画」は、この計画に基づき、教室不足を緩和するためフィリピン政府が日本政府に要請した援助案件である。
DECSは1996年にこれまでの実績と課題に基づき、「万人のための教育」を継承発展する、今後10年間の教育政策の基本となる「基礎教育のためのマスタープラン1996-2005」を策定した。全員に対する質の高い基礎教育を目指し、現代化と学校ベースの管理運営強化による分権化を通じて、基礎教育の一層の普及と初等・中等教育における学習内容の理解率の向上などを目標にした。最終年度である2005年に、残留率を初等教育で85%、中等教育で87%にするなど、大幅な内部効率改善を目指している。「教育施設拡充計画」第4,5次もこの中に位置づけられている(1996)。
(3) 教育事情
フィリピンでは、普通初等・中等教育、ノンフォーマル教育、スポーツおよび文化を教育文化スポーツ省が担当する。教育行政は、国、広域行政区(自治区を含んで16)、州または市レベルに置かれる教育区(133)、さらにその下に置かれる学区(2,128)の4つのレベルで実施されている。高等教育は高等教育委員会、職業教育は技術教育・技能開発庁が担当する。 表1はフィリピンの学校教育体系を示している。初等教育は6歳から6年間初等学校で行われる。1996~97年において、該当年齢人口に占める初等学校在学者比率(純就学率)は94.3%、入学者の中で、所定の年限内に最終学年に到達した者の割合を表す残留率は72.1%である。中等教育は12歳から4年間、中等学校および中等職業学校で行われる。純就学率は62.6%、残留率は48.3%である(DECS,1997a)。就学率は上昇しているものの、退学率が高いなど内部効率が悪いため、残留率の向上は大きくない。
表1 フィリピンの学校教育体系
| 年齢 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 教育 | 初等教育 | 中等教育 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 高等教育(大学/大学院) |
3. 評価対象案件
本調査は、合同評価の第一段階として、日本側がフィリピンに於いて実施した次に示す3つの無償案件を対象とする。これらの案件はいずれも、自然災害や児童・生徒数増に起因する学校校舎不足と教育の地域間格差の緩和、教育レベルの向上のため、教育機会の均等化を通じ、人材開発を行い、地方部経済の活性化を図ろうとするものである。
(1) 学校校舎建設計画 Project for Constructing Primary and Secondary School Buildings(TRSBP:Typhoon Resistant School Building Project)
事業目標:台風等による自然損害を考慮して、教室が不足している初等・中等学校に防災型プレファブ校舎を建設する。また黒板、机、椅子等の基本的な教育資機材を設置し、かつトイレの建設を行う。
| 期 | B/D | E/N | 施工 |
| 1 | 06/15~07/04/88 | 10/24/88 | 02/10/89~02/18/90 |
| 2 | 01/14~02/05/90 | 07/13/90 | 10/06/90~09/25/91 |
| 3 | 02/20~03/14/91 | 08/21/91 | 11/01/91~10/15/92 |
| 4 | 03/31~04/18/92 | 08/07/92 | 10/29/92~11/03/93 |
| 5 | 12/03~12/22/92 | 07/15/93 | 10/28/93~11/30/94 |
| 期 | 日本側 | フィリピン側 |
| 1 | 25億7,600万円 | 4,898,400ペソ |
| 2 | 26億5,900万円 | 5,011,600ペソ |
| 3 | 27億4,500万円 | 3,886,000ペソ |
| 4 | 27億9,500万円 | 10,000,000ペソ |
| 5 | 29億2,000万円 | 10,205,000ペソ |
| 備考 | 学校校舎建設工事および機材・トイレ建設 | 解体、整地、水および電気工事関税を含まず |
援助形態: 無償資金協力
援助担当機関: 国際協力事業団
被援助国内体制 所轄官庁: 教育文化スポーツ省
実施機関: 教育開発事業実施部
(2) 教育施設拡充計画 EFIP:The Educational Facilities Improvement Program
事業目標:児童・生徒数が増加して教室が不足している初等・中等学校に従来工法による防災型校舎を建設する。また、机、椅子などの資機材、及び理科教育機器などの教材を整備し、かつトイレの建設を行う。
援助形態: 無償資金協力
援助担当: 機関国際協力事業団
被援助国内体制 所轄官庁: 教育文化スポーツ省
実施機関: 教育開発事業実施部
| 次 | B/D | E/N | 施工 |
| 1 | 02/21~03/15/93 | 08/16/93 | 11/12/93~11/15/94 |
| 2 | 11/09~12/09/93 | 07/15/94 | 12/13/94~12/09/95 |
| 3 | 03/01~04/10/95 | 09/26/95 | 02/10/96~11/14/96 |
| 4 | 02/05~03/14/96 | 09/25/96 | 01/13/97~11/03/97 |
| 1&2期 | (完了予定) | 12/10/97~11/31/98 |
| 次 | 日本側 | フィリピン側 | |
| 1 | 8億5,900万円 | 4,898,000ペソ | |
| 2 | 25億5,700万円 | 11,980,000ペソ | |
| 3 | 14億3,000万円 | 11,047,471ペソ | |
| 4 | 1期 | 12億3,300万円 | 18,385,590ペソ |
| 2期 | 12億2,800万円 | ||
| 備考 |
学校校舎建設工事・教育資機材 理数科機材、トイレ建設など |
解体、整地、水および電気工事関税を含まず | |
(3) 中等学校教育機材整備計画 SEIEP:Secondaly Education Instructional equipment Project
事業目標: 教育機材の整備により、中等教育のレベル向上を図る。
援助形態: 無償資金協力
援助担当機関: 国際協力事業団
被援助国内体制 所轄官庁: 教育文化スポーツ省
実施機関: 中等教育局
| 期 | B/D | E/N | 施工 |
| 1 | 02/26~03/11/90 | 04/25/91 | 11/30/91~02/12/92 |
| 2 | 01/29~02/12/92 | 04/13/92 | 12/15/92~02/16/93 |
| 期 | 日本側 | フィリピン側 |
|
1 2 |
5億6,700万円 5億9,800万円 |
6,570,000ペソ 13,400,000ペソ |
| 備考 | 科学、生物、化学、物理、技術家庭、化学薬品など | 運送、電気工事関税を含まず |
4 評価結果
(1) 学校校舎建設計画(TRSBP:1988~94)
(イ) 妥当性
(a) 教室の不足
「フィリピンは1984年以来多発した台風、特に1987年の二つの大型台風によって、全国的に多くの学校施設が被害を受け、大量の学校を修復する必要が生じた。また、就学率の上昇、中等学校の無償化による進学率の向上により、教室数が著しく不足した。そこで、全国で360校を選んで無償資金により校舎建設を行うことになった。案件の緊急性を重視し、工期短縮を優先してプレファブ工法による施設建設を実施した」(毛利建築設計事務所、1993)、というのが本計画の経緯とされている。
家族計画がうまくいかず、年平均2.2%(1988~93)の人口増加があることもあり、1988年度から1993年度の5年間で、初等学校児童数は7.7%、年平均1.5%の増加があった。また、1988年から始まった中等教育無償化政策により、中等学校への進学者が増え、同じ1988年度から1993年度の5年間で、中等学校生徒数は25.3%、年平均4.6%もの増加が見られた。児童・生徒数が増加する一方で、台風災害や政府の財政難の故に、教室の建設は思うように進まず、校舎不足の解消は困難であった。このような事態を改善するために、学校校舎を建設すること自体は極めて妥当性が高い。
(b) 校舎の仕様
しかし、問題はどの様な校舎を、どこに、どれだけ作るかである。本計画で建設されたのは耐台風構造の高価なプレファブ校舎である。基本設計調査報告書によれば、台風の被災を受けた学校を建て直すという緊急性があり、品質を管理でき、かつ工期の短いプレファブ校舎を選択したという。しかし、プレファブ校舎は現場での建築工期は確かに短いものの、製造、運搬に時間がかかり、資材製造から竣工までに約1年かかつている。
また、台風の大きな被災は1987年であり、本プロジェクトの第1期工事が完了したのは1990年である。視察した学校は全て大きな台風被災を受けておらず、単に児童・生徒数が急増している学校であり、むしろより本質的な課題である児童・生徒収容力の拡大に貢献したという方がふさわしい。視察した中に、台風によって屋根が飛ぶという災害を受けた学校もあったが、地方政府の資金によりすぐ修復され、日本の援助によるプレファブ校舎は児童・生徒数増加対策として建設されている。
年度によって書き方が異なるが、例えば1993年の基本設計調査報告書(第5期)によれば、どの学校に校舎を建設するかの学校選択は、台風によって校舎に多大な被害があった地域または学校で、その他の選定基準は次のような優先順位で決められることになっている(毛利建築設計事務所、1993)。
- (1) 建設敷地を所有し、校舎建設のための十分なスペースがあること
- (2) 教室数が非常に不足している学校
- (3) 他の基金や援助団体から援助を受けていないこと
- (4) プレファブ資材の搬入に必要な進入道路が確保されている学校等である。
プレファブ校舎が採用された最大の理由は品質管理上の問題があったためと考えられる。我が国は1977年以来途上国に対して学校校舎建設の援助を行ってきた。しかしそれらは限られた少数の場所において校舎建設を行うものであった。本計画は広範な地域に比較的単価の安い小規模初等・中等学校校舎を大量に建設する我が国最初のプロジェクトであったが、国内業者に施工監理や品質管理のノウハウはなかった。そのため、限られた期間内で大量に校舎を建設するという条件の中で、現場工期が短く、品質管理のしゃすいプレファブ校舎を選定したのであろう。
(ロ) 目標達成度
建設実績は表8の通りである。1988年に開始された無償中等教育を普及するために、建設する初等学校校舎と中等学校校舎の比は3対7と定められた。しかし、1993~94に行われた第5期計画は、ラモス政権の初等教育重視政策に沿って、7対3と逆転された。
日本の校舎建設は当初の目標通り完成しており、児童・生徒の収容力向上に貢献したと考えられる。普通教室として、初等学校529教室、中等学校861教室が建設されたが、学級規模をそれぞれ40人、42人と仮定し、2部制を想定すれば、初等学校で42,320人、中等学校で72,324人の収容可能性を高めた計算になる。これらは1993年度の総児童数の0.4%、総生徒数の1.6%に相当する。また、1988年度から1993年度の5年間に増加した児童数766,964人、生徒数928,880人のそれぞれ5.5%、7.8%に相当する。視察した学校ではすべて、校舎建設後も児童・生徒数が急増しており、教室不足を補うため、さらに新たな校舎を増設している学校も多い。DECS自身も1989~93年度の5年間に32,490教室を建設している。
| 期 | 竣工 | 行政区 | 初等学校 | 教室 | 中等学校 | 教室 | 実験室 |
| 1 | 1990年2月 | 5 | 22 | 75 | 50 | 164 | 50 |
| 2 | 1991年9月 | 8 | 22 | 84 | 47 | 195 | 47 |
| 3 | 1992年10月 | 2,4 | 22 | 75 | 50 | 199 | 50 |
| 4 | 1993年11月 | 6,10 | 22 | 79 | 50 | 195 | 50 |
| 5 | 1994年11月 | 1,3 | 53 | 53 | 22 | 108 | 22 |
| 計 | 141 | 529 | 219 | 861 | 219 |
(ハ) 効果
基本設計調査報告書によれば、年度によって異なるが、以下の事柄がプロジェクトの効果と期待されている。
- 就学機会の拡大(1~5期)
- 地域経済の活性化(1~5期)
- 地域住民への貢献(1~5期)
- 人的資源開発(2期)
- 人的資源と経済の改善(1期)
- 安定した教育(1期)
(a) 就学機会の拡大
国立初等・中等学校は無償であり、入学希望者は基本的に入学試験なしに受け入れられる。校舎に物理的余裕がない場合に、校長がとる経営方法は次の順である(DECS,1995)。
- (1) 1学級当たり児童・生徒数を増やす:都市部では1学級60人程度は普通で、視察した中等学校のうち、最も生徒数が多かったのは120人であり、40人程度を前提とした教室では椅子に座れないため、椅子を外に出して、生徒を床に座らせている。
- (2) PTAの協力などにより、簡易な仮設教室を作り、児童・生徒を収容する。
- (3) 実験室、家庭科実習室などをつぶし、普通教室にする。
- (3)1部制を2部制、2部制を3部制にする。
- (4) 国立中等学校で収容できない生徒は、私立中等学校へ収容を依頼し、授業料相当分を地方政府が肩代わりする。
このように、フィリピンでは、施設に余裕がないことを理由に児童・生徒の入学を拒否することは国立初等・中等学校ではない。「学校校舎建設計画」は、学校を新設したのではなく、既存の学校に校舎を建設していることから、機会拡大に寄与するところがいくらかあったとしても、建設した学級数だけ児童・生徒が純増した訳ではない。教室を建設した分だけ過密学級が解消され、児童・生徒に快適な学習環境を提供したと言う方が正確である場合もある。
地域のエリート校である科学中等学校へ校舎を建設した場合や、一般の国立中等学校校舎・設備がこれまで近所の私立学校へ通っていた生徒を引きつけた場合は、生徒が学校間を移動しただけとも言えるが、移動元の学校には余裕が生まれるため、全体として収容力が増加したことには変わりがない。
一方で、校舎建設の際想定された、初等学校40人、中等学校42人の学級規模は平均的な学級規模と比較して小さく、供与された椅子では足りずに、他から椅子を運んできたり、床に座ったりして授業を受けている場合もあり、先の計算以上の児童・生徒を収容できるとも考えられる。第1期の校舎供与校に対する1991年の調査では、最小学級は32人、最大は65人、50人前後が最も多かった。また、校長の56%が教室数を適切と思い、32%は少なすぎると思っていた(DECS,1994)。
しかし、教育へのアクセスを増やし、教室不足を緩和するために普通教室を供与したはずなのに、教室数に余裕が出たのか、視察した学校では別の使われ方をしているケースもあった。コンピュータ教室などの特別教室、実験準備室兼教員室などの例も見受けられ、建設した学級数に定員を掛けた数だけ児童・生徒が裨益した訳ではない。1991年のDECSによる調査では、予定通りの使われ方をしていたという調査結果があるところがら、最初は普通教室として利用されていても、校舎供与後、地元の資金で新しい校舎が建設され、教室数に余裕が出て、供与した校舎を特別教室に変更して利用している場合が多いと考えられる。構造が頑丈で、コンピュータ、薬品などの教材・教具の保管に適切なためであろう。
これは目的外使用として批判するよりも、自立発展の成果として、教室数に余裕が出来た成果と評価すべきかとも思われる。しかし、そうであれば、教室不足の緩和という役割は短期間で終えたと言うことであり、現地仕様と比較して耐用年数が長く頑丈な教室を作る必要があったか、仕様の水準を落として、その分、数を多く作った方が良かったのではないか、という疑問は残る。
(b) 地域経済の活性化
基本設計調査報告書では、地元経済の活性化に対する寄与についても期待している。しかし、品質確保のため校舎の基本的な部分は日本で製作され、地元で組み立てられるプレファブ資材である。第1期計画についていえば、援助総額の68.3%は日本から輸入したプレファブ資材等であり、これにプロジェクト管理費等を加えれば、援助資金の内、日本側に留まった資金は全体の74.9%となる。フィリピン人現場作業員に支払われる労務費は援助資金の2~3%程度で、校舎建設が地元の経済に寄与したところは大きくない。また、現場工期が短いため同じ作業員が別の場所でも同じ作業をする施工方法がとられ、実際に必要な労働者数も少ないところがら、労働者に対する技術移転の効果も限られている。第2期計画以降、現地で調達する資材の割合をいくらか増やすなどの努力はされているが、基本的な輸入プレファブ構造は変わらないため、現地調達率は大きく上昇していない。
しかし、フィリピン側は本計画を模範に自国の資材でプレファブの学校校舎建設を計画実施しており、技術移転が行われて長期的には経済の活性化に資したと評価できる。
(c) 地域住民への貢献
1991年の調査では、62%の学校ではPTAなどの集会に活用している。また、台風時の避難施設としての可能性は備えているが、視察した学校では大きな台風が来なかったこともあり、実際にそのような使われ方をした例はなかった。また現実に、フィリピン全土が台風の被害にさらされているわけではない。校舎建設の際の学校選択の基準として、「人口が多く、避難場所や他の緊急時に役立つ場所に位置している」という理由は第3期までの基本設計調査報告書には記載されているが、地域的に恵まれていない僻地の学校も計画対象となったため、第4期以降には削除されている。
(d) 人的資源の開発/人的資源と経済の改善
学校校舎建設によって、これまで学校に行けなかった子どもが学校に行けるようになれば、その純増分だけ人的資源が開発され、将来の経済発展に寄与すると一般に考えられるが、本計画がどれだけ児童・生徒の純増をもたらしたかの推定は、援助した学校と援助が無く学級数が変わらない学校との就学者数の比較を、社会経済的要因をコントロールした上で行えば理論上できるが、容易ではない。
視察した学校の一つに、州に1校しかないエリート校である科学技術中等学校がある。この学校では本計画による校舎建設によって定員を増加させることができた。将来の科学技術指導者養成に寄与したと言える。ただ、当初は普通教室として使われていたものの、その後新築校舎ができ教室に余裕ができたことから、現在ではコンピュータ教室等の特別教室として使われている。
(e) 安定した教育:児童・生徒、教師、学校運営への効果
新設教室が計画通りの教室として使われていれば、学習環境の向上により教育の質を高めたり、退学率を減少させたりするなど、内部効率を高める可能性はある。しかし、新設校舎は全国に点在しており、また、学校内で新設校舎を利用している児童・生徒の割合は小さいため、既存の統計を利用してそれを確かめることはできない。理科実験室が供与された中等学校では、実験の実施によって生徒の理解度が上昇することが期待されているが、実際にどの程度実験室が利用されているか、また、実験室の利用が本当に学力を高めたかどうかについては調査結果がない。本計画で作られた実験室も含め、SEDPによって建設された実験室の内、半分近くが目的通り使われておらず、実験に使われても、教材が少なく極少数の生徒だけが実験をして、大多数はただ見ているだけという調査結果もある(DECS,1995)。(無償課コメント:実験室については現場での必要性を検証した上で建設するとともに実験器具等についてもフィリピン国教育省と協議の上、国内の標準的な器具を必要数供与している。)
(f) アクセス拡大による就学率の地域間格差の是正
「学校校舎建設計画」は新しい場所にではなく、既存学校に校舎を建設したところがら、校舎建設がアクセス拡大に寄与して、就学機会の地域間格差を緩和した所は大きくないと考えられる。アクセス拡大には教室数の増加より通学距離の短縮の方が重要である。本計画で、本校舎から離れた場所に新たにアネックス校舎を建設した例があるが、これは学校新設と同様なので、アクセス拡大に寄与したと考えられる。
(g) その他の効果
校舎建設に当たって、教室の大きさを変更できるようパーティション設計が施されているが、このような設計は授業の仕方の柔軟性を高めている。しかし、隣室の音がうるさいという調査結果もある。また、身障者用の便所は、法律に基づいて作られてはいるが、すべての国立学校にあるわけではない。視察したいくつかの学校には実際に少数であるが身障者が在籍しており、これらの施設は身障者の就学可能性を高めたと考えられる。
(ニ) 効率性
(a) 完了率
校舎建設は第1期計画は遅れがあったものの、第2期以降はほぼ計画通り実施された。同様の学校校舎建設を行ったアジア開発銀行(ADB)のプロジェクトと比較して、計画期間内の完了率が高い。最も大きな理由はADBの援助による校舎建設は、個別に建設業者を決める入札を行うのに対し、日本の援助による校舎建設では、全部の学校をまとめて入札し元請けを決め、その後は入札がないため、事務的な手間がかからないためであること、請負者である日本企業が契約期間内の完工を保証していることが主な理由である。
現場での工期は日本の援助による校舎建設の方が短いものの、工場での製造、輸送などを勘案すれば、全体の工期はいずれも1年間とほぼ同じである。
(b) 建設単価
価格の問題は、単に金額だけではなく、強度等の品質の確保、期間内に工事が完了する等の工事の確実性、その当時のプロジェクトの背景、援助国の予算額等の様々な要因を考慮して総合的に考慮しなければ善し悪しが言えない。また、建設単価は校舎のタイプ、大きさ、建設場所など条件が異なり、かつ、直接工事費、間接工事費の内訳が異なるので、厳密な比較は容易ではない。しかし、この問題は重要であり、避けて通れない。
本計画のプレファブ校舎はADBのローンで建てた校舎と比較して高価であり、強度設計基準が似ている在来工法を使った耐台風設計であるRP-USBayanihanr-A型校舎と比較しても高くなっている。(DECS,1989;DECS,1994;国際協力事業団・毛利建築設計事務所、1996)。1993年から日本の援助で実施されている「教育施設拡充計画」で用いられている在来工法の校舎建設(工事期間も準備工事から引き渡しまで約1年とプレファブ校舎と同じ)と比較しても高価である。しかし一方で、プレファブ校舎は品質の高さ、品質の均一性、工期の遵守などの面では優れている。
DECSは費用効果分析報告書(1989)の中で設計強度を落としたり、国内製品を使ったりして費用を安くするように提言したが、当初予定された5年の間、ほぼ同じ設計で援助が実施された。援助はやってみなければ分からない事も多く、基本設計を修正するのも容易ではない。一旦計画を開始すれば数年は当初計画に従って実行するしか無いかも知れない。もしプレファブ校舎建設を途中で打ち切り、残りの期間は後の「教育施設拡充計画」で使用した在来工法の校舎を建設していれば、同じ援助金額でさらに多くの教室を供与できたと思われる。我が国にはそれまで広範な地域に在来工法を使って学校建設を行った経験がなく、ノウハウの習得に時間がかかったということもあろう。しかし、「学校校舎建設計画」第5期は単位費用が半分弱の「教育施設拡充計画」第1期と同時期に行われており、ノウハウの未修得が単位費用の高いプロジェクトを第5期まで継続する理由にはなりにくい。
一般に日本の援助は当初計画通り執行することをより重視する傾向があると思われるが、援助効果を重視し、必要な計画変更が容易に行われるような援助の仕組みを積極的に検討していく必要があろう。
(c) 土地の有効利用
都市部では校舎に利用できる土地は限られている。1階建てのプレファブ校舎を建てれば、場合によっては希少な校舎スペースを占有し、その後の土地有効活用を制限してしまう。本計画では大きなプレファブ資材を搬入するため、資材搬入に便利な道路に近い一番いい場所に校舎を建設している例も見受けられる。したがって、視察した学校の中には、まわりは傾斜地ばかりでその後自前で建設した2階建て、3階建て校舎を、台風の被害に遭いやすい斜面に建設せざるを得なかった例もあった。
供与校舎はその学校が必要としている校舎の一部でしかない場合もある。基本設計調査時に将来の児童・生徒数増加に伴う校舎増設予定を考慮して場所の選定を行っていれば、その学校にとってより効果の高い援助となったものも見受けられる。
(d) その他の問題
教室の規模に応じた標準的な数の机・椅子等を供与しているが、学校は机や椅子の数に基づいて児童・生徒を入学させている訳ではないため、現実の児童・生徒数に比して、供与した数は過小であり、机なしに授業を受ける児童・生徒もいる例も見受けられる。過密にはなるが、実状に合わせた机・椅子の供与も考えられてよい。
可動式パーティションなど、校舎設計上の工夫は良く、DECSの今後の設計に取り入れることがDECSの報告書などでも推奨されている。
(ホ) 自立発展性
(a) メインテナンス
日本の供与による校舎は基礎構造がしっかりしており、ペンキ塗り替えなど大きなメインテナンスなしに、長年にわたって使用できる。例えば、ADBローンによる校舎の最初の5年間のメインテナンス費用は、日本の供与による校舎に比べ31%増しと計算されている。しかし、長期的には様々な理由により破損する事も考えられるが、その場合、多くの部品は輸入品であるので、在来工法で作った校舎よりも補修に費用がかかると思われる。また、第1期校舎供与校の内、メインテナンスの費用を持っていたのは6%に過ぎないが、ほとんど電気、水道料金などに消えてしまう。教師のポケットマネーでメインテナンス費を賄う場合も多くあると指摘されている(DECS,1994)。
校舎は建築後のメインテナンスによって耐用年数を伸ばすことができる。適切なメインテナンスができるような管理、資金に関する体制づくりが重要である。国や地方自治体の努力と同時に、父母、地域住民、卒業生、篤志家など幅広い援助を得られるような工夫が必要であろう。
(b) 水の供給
水の供給施設はフィリピン側の分担になっているが、問題が多い。校舎完成から1年経った1991年の調査時点で、すでに初等学校の16%、中等学校の19%で水が流れない、鍵がかかっている、職員用になっているなどの理由で便所の使用が制限されている(DECS,1994)。それから6年後、視察した学校のほとんどにわたって、水の供給が作動していなかった。早い時期に壊れたようだが、実験室やトイレの利用に不便をきたしている。実験台は水が出ないので、必要に応じてバケツで水を汲んできたり、化学や生物など水を使う実験は別の実験室で行っている。
可動のジャロジー窓枠はアルミ製で壊れているものも多く見られた。修理に際して木板をガラス板に換えたところが多かったが、このように部品を地元で調達できることはメインテナンスにとって重要である。
(2) 教育施設拡充計画(EFIP:1993~98)
(イ) 妥当性
(a) 教室の不足
基礎教育の充実のため、各村(Barangay)に初等学校を最低1校、各市部(Municipality)に中等学校を最低1校建てることになっているが、1997年でも4,323の村に初等学校が無く、31の市部に中等学校が無い。就学年齢人口の増加に進学率の上昇が相まって、教室の不足はなかなか改善されず、常に校舎の新・増設が課題となっている。このため、本計画は6年間で約630校の初等・中等学校校舎を建設しようとするものである。供与するのは教室の他、机・イス、便所、及び理科実験室と基本的教材(中等学校だけ)である。このように教室が不足している学校に、校舎を建設するのは極めて妥当である。
(b) 校舎の仕様
問題は仕様、費用と場所である。「学校校舎建設計画」のプレファブ校舎は高価であったこと、フィリピンでの施工監理の経験を積んだことから、本計画ではフィリピン国内で調達できる資材を中心にした在来工法で校舎建設をすることにした。
第1次、第2次計画では、地域の事情に応じて大小10タイプの異なる規模の校舎が建設されたが、第3次計画以降、フィリピン政府の方針を踏まえ、校舎建設は1階建て3教室校舎に統一された。一律3教室とすることで、一部の都市大規模校への校舎建設の集中を避け、経済的に恵まれていない地方部で多くの学校を計画対象とし、そのことが教育の地域格差の拡大の緩和に貢献すると基本設計調査報告書に書かれている(国際協力事業団、毛利建築設計事務所、1996)。
しかし、一律3教室にすることと、大規模校への集中投資を避ける事とは別の次元の話である。また教育の地域格差の拡大の緩和への貢献を、具体的にどのような指標の変化で証拠立てるかも問題である。
地域が異なれば不足教室数も異なり、しかも予算の関係で一定数の教室しか建設できないため、一概に言うことは困難であるが、基本設計調査報告書の数字を基に計算してみると、第2次計画では対象校の不足教室合計に対する新設教室合計の割合(充足率)は36.7%であるのに対して、第4次計画では15.9%である。第4次計画で対象となった地域は不足教室数が全体として多いことに加え、1校3教室にしたため、対象校数が相対的に増えたことによるものと思われるが、充足率が極めて少ない学校もある。これでは供与校舎はシンボルにはなっても、学校全体に対する実質的な援助効果の測定は難しい。学校別の充足率のばらつきの程度を示す変動係数(標準偏差/平均)も第2次計画では0.44であるのに、第4次計画では個々の学校の事情への配慮がないため0.72と大きい。
もし、経済的に恵まれていない地方部で多くの学校を計画対象とし、そのことで教育の地域格差の拡大の緩和に貢献したいのであれば、地方部だけで学校の事情に合わせた建設を行うことも考えられるが、フィリピン側に公平を旨とする政治的な配慮があって、このような建設計画になったのではないかと推察される。
(ロ) 目標達成度
校舎は計画通り建設された。校舎建設は児童・生徒の収容力を高めている。視察した学校ではすべて、校舎建設後も児童・生徒数が急増しており、教室不足を補うため、さらに新たな校舎を増設している学校も多い。
第1次、第2次計画では初等教育に重点を置いて、初等学校70%、中等学校30%の割合で校舎建設を行ったが、第3次計画以降は、中等学校に教室不足が著しい現状から、中等学校の割合を増やしている。表9に示すように、第1次から4次までで普通教室として、初等学校695教室、中等学校526教室が建設されたが、学級規模をそれぞれ40、42人と仮定し、2部制を想定すれば、初等学校で55,600人、中等学校で44,184人の収容可能性を高めた計算になる。
| 次期 | 竣工 | 行政区 | 初等学校 | 教室 | 中等学校 | 教室 | 実験室 | 階数 | |
| 1 | 1994年11月 | 4 | 21 | 104 | 9 | 51 | 9 | 1階+2階 | |
| 2 | 1995年11月 | 5,11,12,ARMM | 80 | 339 | 37 | 172 | 35 | 1階+2階 | |
| 3 | 1996年11月 | 6,7,10 | 39 | 117 | 30 | 90 | 27 | 1階 | |
| 4 | 1 | 1997.11 | 4 | 30 | 90 | 31 | 93 | 23 | 1階 |
| 2 | 1998年11月(予定) | 2,8 | 15 | 45 | 40 | 120 | 19 | 1階 | |
| 計 | 185 | 695 | 147 | 526 | 113 | ||||
(ハ) 効果
基本設計調査報告書によれば、年度によって異なるが、以下の事柄がプロジェクトの効果と期待されている。
- 就学機会の拡大(1~4次)
- 教育環境の改善(4次)
- 教育内容の向上(3次)
- 地域住民の利用と参加/地域住民への貢献(1~4次)
- 地域経済の活性化(1~3次)
- 建築技術の移転(2~3次)
- 衛生状態の改善(3次)
(a) 就学機会の拡大
基本設計調査報告書によれば、第1次計画として第4行政区が選ばれたのはフィリピンで最も教室数が不足(1991年当時13,211教室が不足)しているためである。教室不足以外で、学校を選択する基準は以下の通りである。
- (1) 校舎を建てるスペースがある
- (2) 人口が集中している地域にある
- (3) 他の援助機関などから校舎建設の援助を受けていない
- (4) 資材の搬入が可能な道路に面している
校舎建設が教室数に定員を掛けた分だけ収容可能性を高め、過密学級の状態を緩和したことは事実である。しかし、それがどの程度児童・生徒数の純増、学習機会拡大に効果があったかはデータがなく不明である。一般的には学校施設の改善が直接児童・生徒数の純増に結びつくことはないと言われている(World Bank,1996)。
(b) 教育環境の改善/教育内容の改善
供与された備品に対しては、教師は収納棚、教師用机・椅子、掲示板などに満足が高く、児童・生徒は黒板、児童・生徒用机、児童・生徒用物入れなどに満足が高いなど、概ね評判がよい。全体としての満足度も、調査対象の校長の83%、教師の57%、児童・生徒の54%は「大変満足している」と答えており、これに「満足している」と答えた者を足し合わせれば、それぞれ94%、80%、76%となり、高い評価を得ている(DECS,1997b)。
しかし、定員以上の児童・生徒が教室にいるのが現実であり、定員数だけ供与した机、椅子では足りない。そのため、仕様の違う机、椅子を持ち込んでいるところもある。
一般論としては、快適な学習環境は学習効果を高めると考えられている(World Bank,1996)。教師も児童・生徒も日本の供与による校舎での学習は同じキャンパスの他の校舎での学習と比較して涼しく、快適であると答えている。理科実験室の設置や便所の建設もより快適な学習環境の改善という視点からは評価できる。しかし、施設改善が学校教育全体の質を高めたり、退学率を減少させたりするなど、内部効率を高めたかどうか、学力向上などに具体的にどの程度の効果があったかはデータがない。
(c) 教室利用の仕方
校舎建設により、過密学級が解消され、教育環境が改善されることが期待されているが、校舎建設後、学級サイズがどのように変化したかについてデータはない。視察した学校の中には当初予想されていない使われ方をしている例が見受けられた。例えば、セブ州では「未来の学校:School of Future」プロジェクトの一環として、フィリピン側の教育方針により少数の選抜された児童・生徒の実験教育の場となっていたり、コンピュータ教室など特別教室として利用されていた例があった。
視察したある小学校では日本の供与による教室には当該学校の方針により、PTAの資金で扇風機、蛍光灯による照明、電動スクリーン、カーテンなどの設備をつけ、1学級30人の選抜された児童の教育を行っている一方で、周りの古く、照明が暗い教室では60人の児童が、一部分朝昼の2部制で授業を行っている例もある。さらに児童数が増えれば、2部制を拡大して対応すると校長は言う。日本の供与で出来た新しい教室の快適な学習環境を多くの児童に分け与える考えはなかった。
(d) 衛生状態の改善
一般的にはトイレの設置が女子の就学率を高めたり、衛生状態の改善につながることが期待される。しかし、具体的な指標に基づいて、改善の程度を指摘するにはデータが不足している。
(e) 地域住民の利用と参加/地域住民への貢献
校舎は耐台風設計であり、台風時の避難施設としての可能性を備えており、1996年のロシン台風では避難場所として使われた。
パーティションの設計は、授業方法の柔軟性を高めたり、地域住民の集会の場を提供する可能性を持っている。校長の78%は校舎が地区住民の集会、識字教室、その他の社会教育活動に利用されていると答えている。しかし、視察した学校の中には、住民の集会に使うと汚れるという理由で、集会は既存の古い校舎を使って行っていたものもあった。
(f) 地元経済の活性化/建築技術の移転
本計画はほとんどの資材を現地調達し、また、在来工法であるところがら、建設に多くの熟練、未熟練労働力を必要としている。第1次計画では、援助資金の84.8%がフィリピン国内で使用されている。援助金額に対する労務費の割合も11%程度と推定され、校舎建設が地元の経済に寄与したところは大きかったと考えられる。さらに、必要な現場労働者の数も多く、援助金額あたりの労働者数も「学校校舎建設」計画と比較して4倍以上であり、技術移転の効果も大きく改善されている。工程管理、品質管理、屋根葺き工事等に関して、実地訓練を施したり、講習会を開いたりしているのも、フィリピン国の建築技術者、労働者に対する技術移転に役立っている。
日本の供与による校舎建設は高価であるものの、仕様や設計には多くの工夫が凝らされている。これらの技術はDECSが建設している校舎建設プロジェクトにも応用可能と考えられる。
(ニ) 効率性
(a) 建設単価
資材のほとんどが現地調達されるため、「学校校舎建設計画」のプレファブ校舎と比較して、格段に改善されたのは事実であるが、それでも他のプロジェクトで建てられる校舎と比較して、まだ高価である。
台風や地震災害など最悪の条件を見込んで、頑丈な校舎を建てれば安全であると同時に費用がかかる。万が一の効用と現実の費用をどうバランスさせるかは簡単な問題ではない。実際台風ロシンによって本計画による校舎は無傷だったのに対し、同じ校庭に建つDECS仕様による校舎は半壊した例もある。地域住民の避難場所として重要であれば、費用がかかっても強固でなければならない。
無償だから少々高くてもいつまでも残る、良い物を建てるという考えもあるが、被援助国の現実のニーズに合わない場合もある。校舎を供与された校長は、一様に日本に感謝しながらも、こんな立派な物でなくていいから、沢山の教室が欲しいと言う。供与施設の適切さを校長に尋ねた質問では、24%の校長が適切ではないと答えているが、その理由は児童・生徒数に比して供与された教室数が少なすぎるというものである。教室の絶望的な不足の現状を考えれば、安価で大量の教室を作って欲しいとの希望は、各所で強調されている(例えばDECS,1995)。DECSの建築担当者も「教育施設拡充計画」校舎は地元の建築と比較して仕様が高く、仕様の質を落とせば、その分数を多く建てられると指摘していた。
無償資金協力にあっても、頑丈でなくても、数多くの現地仕様と同等の校舎建築を行うことも一考すべきである。無償案件として適切な仕様を保持しつつ、相手国のニーズや地域の状況をきめ細かく把握して、適正な費用でその地にあった校舎を建設する努力を今後とも続ける必要がある。
(b) 土地の有効利用
既存の学校校庭に校舎を建てているが、都市部では土地は限られており、1階建ての校舎を建てれば、場所によっては今後の土地の有効利用を制限してしまう場合も想定される。視察したある都市部の中等学校では日本の供与により3教室からなる平屋の校舎を供与した後、生徒の増加に対応するため、狭い敷地に3階建て、4階建ての校舎建設を次々と行っている。古い平屋校舎は撤去されるため、やがて平屋の校舎は日本の供与による校舎のみとなる。基本設計調査報告書によれば、「既存施設の配置状況を考慮して、新設校舎が学校の全体計画と一体になる配置計画とする」ことになっているが、日本の供与による校舎が50年間も持つのであれば、将来計画も十分考慮して配置計画を考えなければならない。
今後5年間程度の中等学校生徒数は近所の初等学校児童数から比較的容易に将来推計できるはずであり、上記の学校は地域の事情に合わせてせめて2階建てにすべきであったと思われる。3教室の平屋校舎しか建設しないという方針を堅持するのであれば、校地が限られている都市部の学校は建設候補地から外し、その分教育事情の悪い地方の学校に援助した方が土地の有効利用になったと考えられる。
(c) 校舎の規模
第3次基本設計調査報告書によれば、少しでも多くの学校を建設するために、費用のかかる2階建て校舎の建設を行わないとある。第2次計画では25億6千万円の無償援助で117校、511教室が建設されている。第3次計画では14億3千万円の無償援助で69校、207教室が建設されている。建物の形状が違い、物価調整もしていないので厳密な比較はできないが、1教室当たり援助金額は、それぞれ500万円、691万円、延べ床面積1平方メートル当たり6.7万円、7.4万円と第3次計画の方がかなり高くなっている。環境が異なるので一概に言えないが、小規模校合を作るためスケールメリットが無くなっている事情もあると思われる。援助資金の効率的利用から言えば、一般的には1校舎当たりの規模が大きい方が教室当たりや単位面積当たりの建設費は安くなる。
建設費は様々な条件によって決まるので一概には言えないが、どのような状況の学校にも一律3教室しか作らないと言うのは、形式的平等性は保てても全体の効率性,が損なわれる。日本側に一律3教室に変更しなければならない事情は見あたらないため、フィリピン側の事情ではないかと推測されるが、DECSの実務担当者からは、教室数の決め方に柔軟性をもってほしいという声が多くあった
(ホ) 自立発展性
(a) メインテナンス
「教育施設拡充計画」による校舎の品質管理は申し分ない。基礎的な構造や資材はしっかりしており、大きなメインテナンスなしに、長年にわたって使用できる。しかし、木製のドアやジャロジー窓などは必要に応じて手入れをしたり、破損の修理をする必要がある。このような建物のメインテナンスはDECSが必要な予算支出を行い、実際の仕事は公共事業道路省の地方事務所が行う事になっている。修理が必要な場合は、校長がDECSの地方事務所に要求するのだが、予算不足のため、実際にはなかなか修理が行われないことも多い。第4次計画に係わる校舎1棟あたり年間運営維持管理費は11,526ぺソと推定されているが、その60%は電気・水道代である.
政府の予算があてにならないため、日常の施設のメインテナンスは財源確保も含め、校長の指導力によるところが大きい,校長に対するアンケート調査(DECS、1997b)の結果では、校長は建物を長く使えるようにするため、机や椅子などが壊れたらすぐ修理したり、毎日掃除したり、教師や児童・生徒に施設や設備の適切な利用法を説いたりといった、定期的な努力を行っているまた、校舎を建てた後、施設の利用について講習会をひらいていることは、長期的なメインテナンスに効果的である.、不具合があったときすぐに対応できれば、破損部分が大きくなって修理が大変になることがないからである、
ほとんどの校長は日本の供与による校舎は品質が良く、耐久性に優れていると答えており、97%が地震や台風に耐えられると考えているその理由として挙げられているのは仕様の水準や労働の質の高さである。建築中にいくらか見られた床の亀裂、壁のペンキのはがれ、ドアノブの故障等は直ちに修理された.現左でも屋根の雨漏り、ドアノブの故障、壁のペンキのはがれ、シロアリの被害などの不具合がいくらか報告されているが、供与した校舎や設備が長い間効果を発現するためには、十分な維持管理が重要である。維持管理がうまくいっている例の紹介やマニュアルの作成・配布などの努力も必要であろう。
(b) 水の供給
水の供給は「学校校舎建設計画」と比較して改善された。第1次計画では地上4メートルに設置された高架水槽に代えて、第2次計画からは地上2メートルの水槽による低圧給水方式を採用し、手動でも水の供給が出来るようにしたり、雨水も利用できるようにするなど[たされた。しかし、乾期には井戸水の水位が下がって、使用に困難をきたす場合もあることが報告されるなど、水の供給には問題が残っている。1~3次計画で作られた学校へのアンケート調査によれば教師の17%、生徒の23%は便所が使用できないと答えている。水の供給施設はフィリピン側の分担であるが、水の供給が十分でないことが、便所や理科実験室の機能を減少させている場合もある。
(3) 中等学校教育機材整備計画(SEIEP:1990~93)
ここでは「教育施設拡充計画」(1993~98)で行われた教材の供与についても、併せて評価する。
(イ) 妥当性
供与された教材以外の教材を持たない学校も多く、中等教育開発計画の方針に従って中等教育の質の向上に寄与する教材を提供する計画自体の妥当性は認められる。
パッケージに含まれる教材の量は、表10に示すように、第1期・第2期共に1クラス4グループを原則とし、実験・実習を行うのに必要な数量を算定したとしている。
1990~91に機材を要請した中等学校(ただし教室数不明および教室数1という特殊なケースの10校を除く)の生徒数および教室数をみると、1教室あたりの生徒数の平均は73.2人で、最少は15.3人/教室、最大は368.5人/教室であった。この数値は単純な平均値であり、一部の学校は午前・午後の2部制をとっていると考えられるために、1教室あたりの生徒数は60~70人前後が最も多いと推測される。1クラス4グループとした場合、15~18人/グループとなる。これだけの数の生徒がグループとなって実験や実習を行うとすると、供与された教材を利用する効果には疑問が残る。
| 教材 | クラスあたり個数 | |
|
第 1 期 |
個人的に観察あるいは操作を行うほうが教育効果が上がると考えられる機材 | 4 |
| 教師による機材の説明や操作のみでも教育目的を達成できると考えられる機材 | 1 | |
| 上記2項の基準では生徒の観察や理解が不十分になると考えられる機材 | 8または2 | |
| ガラス器具(原則) | 4 | |
| ガラス器具(壊れやすい物) | 6 | |
|
第 2 期 |
破損しやすいガラス器具や小グループでの実験が効果的な機材 | 6~8 |
| 主として教師が演示のために使用する機材、使用頻度の低い機材および比較的高度な機材 | 1~2 | |
| 上記2項の基準では生徒の観察や理解が不十分になると考えられる機材 | 8または2 | |
| 試験管 | 12~24 |
提供されたパッケージに含まれる品目は、各教科の全国カリキュラムにそったものであり、その点での妥当性に問題はないが、視察した学校の中に一部の教材を全く使用した形跡がない学校があることから、それぞれの学校のニーズを充分に満たしたものとはなっていないと考えられる。特に数量の算定基準を4グループ/クラスとしたことに、標準定員で決めるのではなく、もう少し現実の人数に対する配慮が必要であったのではなかろうか。
他機関による類似案件では、PASMEP(Philippines-Australia Science and Mathematics Education Project)において「小グループでの実験が効果的な機材」とされた教材は、16~48個が各学校に配布されている。これだけの数の教材があれば、4~5人を1グループとすることができ効果的な学習が期待できる。
教育文化スポーツ省が定めた標準機材を供与しているとはいうものの、PHメータなど授業の内容とてらして過剰仕様だと思われる教材も含まれている。視察した学校の教員から「高精度で性能も良いが、その分デリケートな操作が要求され、授業で利用するのは困難」だという指摘もあった。精度や性能が低くても、もう少し気軽に授業で活用できる教材の選定が望まれる。また、理科の各領域では、カリキュラムの内容から網羅的に教材を供与しているが、基礎的な教材や消耗品のみを充分な数だけ提供するという方策も考慮されて良い。
(ロ) 目標達成度
表11に「中等学校教育機材整備計画」の実績を示した。教材の提供はほぼ予定通り行われている。各対象学校への教材パッケージの配布は、第1期に関しては各行政区に設置したキーステーションまでの運搬を日本側が担当し、キーステーションから各対象学校までの運搬をフィリピン側で担当した。第2期は、各対象校までの運搬も日本側が担当した。
| 期 | I | 小計 | II | 小計 | 合計 | ||||
| 行政区 | V | VIII | II | IV | VI | V | |||
| 学校数 | 105 | 105 | 210 | 8 | 107 | 96 | 20 | 241 | 451 |
| 日本側予算(百万ペソ) | 113.4 | 129.1 | 242.5 | ||||||
|
フィリピン側予算 (百万ペソ) |
21.0 | 22.3 | 43.3 | ||||||
今回の調査では第2期の対象校のみを視察したが、視察した学校の内2校ではパッケージの教材内容が当初から3割程度の品目について完全ではなかったという主張があった。第2期に関しては各対象学校までの運搬は日本の担当であったが、輸送時の管理や輸送完了時の輸送側、受け取り側の相互確認が重要である。
(無償課コメント:最終受領時の確認は行っており、完全でないのは引き渡し後の何らかの問題によるものと考えられる。)
今回視察した学校の多くは、この計画による機材の提供を受けるまで、ほとんど教材を持っていなかったため、教材の提供は非常に好意的に受け入れられている。また、学校によっては、基礎的な実験機材(ビーカー・試験管等)を周囲の小学校や中等学校と共有している例もあった。
(ハ) 効果
(a) 教材の使用方法
第1期では、教材の提供と同時に受領校の担当教員に対して研修を行う計画となっており、各地域ごとに受領校の教員を集めて配布した教材の使用方法や授業への活用の方策について研修を行ったが、第2期は教員に対する研修は計画から除かれた。ただし、第2期の基本設計調査報告書(システム科学コンサルタンツ、1992)には、事業負担区分として「教育文化スポーツ省地方事務所に対する機材使用法の指導」を日本側が担当することとなっている。その後、実施機関の責任で地方事務所から現場の教師へ研修することになっている。同報告書のフィリピン国政府への提言には、「整備される機材の用途や授業での利用方法について、教師が十分な理解と知識・技術を持つ様、教師の再教育を実施すること」とある。フィリピン国政府による評価報告書(DECS、1995)によると、第2期には日本政府による地方事務所への研修は行われたが、教育文化スポーツ省による地方事務所から現場教師への研修は行われていない。視察した学校の聞き取り調査においても、第2期の事業に伴う研修を受講した教員はいなかった。
(b) 授業上の効果
今回視察した学校の中に1校、PASMEPから教材の提供を受けた学校があった。PASMEPでは教材の提供と同時に各学校ごとに講師を派遣し、提供した教材についての講習を行っている。この方法は、教材の配布と同時に講師の派遣が必要となるという意味で費用効率は低いといえるかもしれないが、輸送の確実性を高め、教材の利用を促進するという意味では、効果が高いと思われる。
教育文化スポーツ省と協議した上で、標準機材を供与しているが、視察した学校の中には、提供された理科機材がほとんど未使用のまま保管されていたものもあった。また、使用した形跡のある教材も、教師が試しに使ってみただけで、授業には利用していないという学校もあった。教材が未使用、あるいは授業で利用していない理由として挙げられたのは、教材の数が十分でない、破損時の補充が困難、授業で利用するには高度過ぎる、等であった。教材は提供されたが、授業に活用していない例や効果的に教材を活用するための教師教育の不足等により、実際に生徒の学習や成績の向上に寄与していない場合もあると思われる。
標準数を配付しているとはいえ、教室に定員以上の生徒を収容していることから、提供された技術家庭科機材の数も現実の生徒数に比べると十分とはいえない。しかし、技術家庭科の教材は、理科教材に比べて活用されている度合いが高いように見受けられた。それは、理科教材よりも技術家庭科の教材の方が、生徒の就職などに有利になる技能の習得や職能訓練に有効だからであろう。このような観点から、さらに数を増やしてもらいたいという要望が多くあった。
(二) 効率性
(a) スケジュール
他機関による同様の計画に若干の遅れが見られたのに対して、SEIEPは、第1期・第2期共に、計画の実行は当初の予定通り完了しており、この点に関してフィリピン政府は高く評価している。
(b) 高価な教材
パッケージに含まれる教材は製品の質が高く、その点は高く評価されているが、高価で高度な教材であるがゆえに破損時の補充が困難であったり、故障時の部品の確保が困難であるとの指摘があった。今回視察した学校の内3校で、提供された教材であるPHメータが破損して授業で利用することができなくなっていた。教師が授業の前に試用した時点で破損してしまった学校もあり、全く授業に活用されなかったケースもある。このPHメータはフィリピンで作られていないため日本製で高価である。日本語のマニュアルと共にそれを英語に翻訳したものも付属していたとされていたが、今回視察した学校では管理上の問題からか、英語のマニュアルがない学校が多かった。PHメータ以外にも、スイッチ等の表示が日本語のままの教材が一部にあり、実際に授業で活用するには不便な場合もあると推測されるものも多い。
提供する教材は同じ性能であるなら高価な外国製品よりも比較的安価な国内製品を確保し、より多くの学校に教材を提供できるようにする配慮は今後とも必要である。特に壊れやすいもの、消耗品は国内で容易に入手が可能なものを活用し、故障時の修理や消耗時の補充に今後とも留意しなければならない。
(c) パッケージ
視察した学校の多くで、提供された機材の中でも特に理科教材が使われていないのに対して、技術家庭科教材は活用されている。SEDPの主な目的に理数科の向上がうたわれているのは確かだが、生徒自身の将来や日常の生活に直結した技術や技能の習得を可能とする技術家庭科教材を数多く提供することが、フィリピンの現状からすればより効果的であったとも考えられる。実際に学校現場からは、「結局使用することのない/できない理科の実験器具より、技術家庭科で使用する教材を多く欲しい」という意見も聞かれた。
今回の機材供与は、学校を「理科実験室の有無」と「技術家庭科室の有無」によって4つのグループに分け、それぞれのグループに応じた教材パッケージを提供している。しかしパッケージの内容やそれぞれの教材の数量は、各グループで一律なためにそれぞれの学校で必要な教材や数量が提供されているとは言い難い。もちろん学校間の格差をできるだけ無くし、均質な教材を提供することや、教材をパッケージ化することによる各学校までの教材の輸送をより容易にするというメリットは否定できないが、教材を平等に提供する事よりも、提供した教材が実際に利用されることの方が重要である。
(d) 各学校で必要な教材の提供
これらの問題の多くは、定員分だけ標準教材を供与するところにあるよう思われる。現実の生徒数は定員をはるかに越え、先方実施機関と協議の上標準機材を供与している(無償課コメント)ものの実際の授業では標準教材を使用していない。中央の教員研修が末端まで届いていない。定員や標準教材が教育現場の実状にあっておらず、研修も受けないのでは、供与された教材の効果は限られる。
提供した教材が充分に活用されるためには、まず各学校のニーズを満たす教材を提供する必要がある。そのためには教材をパッケージとして提供する際の構成を均質化よりも柔軟性を主眼にする必要がある。保管や輸送の面で困難が予想されるが、配布可能な教材のリストを作成し、一定額の予算範囲の中で各学校に自由に教材を選択してもらう方法なども、今後検討されてよい。
(e) 援助国間の協調
同様の援助計画が複数の国/機関によって実行される場合、その実行において被援助国も含めて充分にコミュニケーションを行い、無駄のない援助をする必要がある。その点今回の案件では、同時期に複数機関が同様の機材供与を行っているにもかかわらず、学校にほぼ重複なく機材を提供できたことは評価できる。今後同様の状況下で計画を実施する際にも、相手国政府・担当機関や他援助機関とのコミュニケーションを密にし、効果的な活動を行わなければならない。
(f) 総合的な援助
教材の作成やカリキュラムの内容に従った教材開発について援助をしてほしい旨の希望は多い。教材を提供して完了する援助ではなく、その効果的利用方法に関する研修を行ったり、被援助国の実状に応じた自作教材の開発等、教材に付帯した総合的な援助が行われることが望ましい。第2期では先方実施期間による研修が行われなかったために、教材の活用が困難になっている例が多くみられた。
PASMEPのように、教材の到着と同時に各学校に講師を派遣し、それぞれに研修を行うことが理想的ではあるが、専門家等人員の確保に困難が予想される。しかしなんらかの形で受領校の担当教員に研修の機会が与えられるよう配慮することは必要である。
JICAは理数科教員を再教育し、教育内容の改善・向上することを目標として、「フィリピン理数科教師訓練センター(UP-ISMED)」へのプロジェクト方式技術協力、JOCVチーム派遣、研修生の受け入れからなる「フィリピン初中等理数科教育開発パッケージ協力」を1994年から開始し、ソフト面への協力を強化している。しかし、パッケージ協力の中核をなすUP-ISMEDでの訓練は行われているものの、地方研修、学校研修の実施は十分でなく、また、中央研修から教育現場に届くまで時間がかかり、研修内容が正確に伝わらない、研修を受けた教員がその内容を実際に授業で必ずしも応用しない、などの問題があって、他ドナーばかりではなく、DECS自身からも研修の効果発現に疑問の声が聞かれた。JOCVにしても、日本が機材を供与した学校を巡回指導しているわけではなく、援助スキーム間の連携に改善の余地が大きい。
日本は、教室建設、機材供与、カリキュラム・教材開発、教員訓練など、様々な援助協力を行っているのだが、それらの連携が弱かったところに問題がある。学校や地域ベースでこれらのプロジェクトを集中的、総合的に行うことができれば、援助の相乗効果が期待でき、学力向上など効果の証明も比較的容易いと考えられる。これまでのようなトップダウン型の援助ではなく、ボトムアップ型の援助も考えられて良い。
(ホ) 自立発展性
(a) メインテナンス予算
ガラス製品などの壊れやすいもの、薬品等の消耗品の継続的な補充に関する配慮が必要である。第1期・2期ともに基本設計調査報告書では、当計画実施に伴う中等学校1校あたりの年間維持管理費は、薬品・消耗品購入費、ガラス器具補填費(器具費の10%と仮定)、技術家庭科の実習材料購入費、光熱費の増分などで、1校あたりの年間平均維持管理費の10%程度増加すると考えられているが(基本設計調査報告書、第2期)、視察した学校において予算の増加措置が実施されているところはなかった。
このように教材の破損、消耗時の補充にかかる予算の目処がつかないこと、教材を故意に破損した場合の補充は、それを破損した生徒あるいは監督していた教師によって弁償される(DECS,1995)など、教材を破損した際に最終的に教師自身に負担がかかる場合があることが、教材が使われていない理由と考えられる。継続的な維持管理予算の手当てはDECSの担当で、これ自体は日本側の責任ではないが、維持管理予算の増加を可能な限り少なくするための措置が考えられても良い。
(b) 教員研修
教師が教材の使用方法に習熟していないことも、教材の活用を疎外する大きな要因である。教材の効果的な活用には、教員研修/教師教育が不可欠である。提供された教材にそった活用のためのガイドブックが開発され提供され始めている。基本設計調査報告書の中で「比較的高度な機材」とされた教材は、ほとんどが日本製であった。これらの教材は比較的高度であるがゆえに、使用には訓練が必要と考えられる。しかし、第2期から使用法の研修が外され、ますます教材の利用が困難になったと考えられる。また、先にも述べたようにそれら機材のスイッチ等の表示が日本語のままのものもあり、教師が授業で機材を使用する際の障害となっている場合もあることが推測される。
5. 提言
(1) セクターレベルの提言
3つの無償案件の評価を通じて得られた知見に基づき、今後の援助に関する提言を以下のように行う。
(イ) 問題の解決と事業の効率・効果に係わる提言
(a) セクター分析
被援助国の教育・人材養成セクターの重要な課題が何であり、その解決策として何が必要かをまず分析しなければならない。セクター全体の中での案件の位置づけが重要である。
学校が無いところに新しい校舎をつくれば教育機会の拡大につながる。校舎新設の効果は就学者の増大という指標で測定できる。既存の学校に校舎を新設した場合には快適な学習環境を与えて、教育の質的改善に寄与するところが大きい。中退率の減少、学力の増加などの指標で測定できる。しかし、教授方法、カリキュラム、学校運営、教育機器利用、宿題の有無、父母の協力なども教育の質的改善に関連する重要な要因である。セクター内の重要な要因の現状と要因間の関連の把握がなければ、案件の効果は実証できない。
(b) ニーズの把握・現実と基準
今後とも援助が独りよがりにならないようにしなければならない。被援助国や学校現場のニーズをよく調査し、画一的でない、きめ細かい、役に立つ、無駄のない援助が望まれる。例えば、現在のフィリピンが抱えている学校教育のニーズは、生徒の収容力の増強である。こうした場合、教室・校舎の供給を大幅に増大させることが教育援助に期待されている。
机、椅子や教育機材などの供与の基準を定員や標準教材にした場合、現実の生徒数が定員をはるかに越えたり、実際の授業では標準教材を使用していない場合には、援助効果は限られたものになる。援助は現実の状態や現場ニーズに基づいて行うことが何よりも重要であり、規則や原則だけに基づいて援助しても、期待した効果は得られない。基準にあっていない現状が悪いのだという訳にはいかない。
(c) 長期的視点
校舎を建設する学校を選ぶ際、現状の分析だけではなく、今後とも将来の動向も十分見極めた上で学校選択をしなければならない。地域住民の年齢構成、地域の社会経済状況、動向などにより、将来の学校規模を予測することは可能であり、校舎が50年間持つならば、その間期待される役割が果たせなければならない。
(d) 援助効果を重視した立案
どれだけ投入したか以上に、その投入によって何がどれだけ向上したかが、より重要である。援助の直接効果、波及効果を重視した案件形成を行なわなければならない。学校を作っても、設備を供与しても、教育の機会が増え、施設・設備が適切に使用されて、学力が増進してはじめて意味がある。学校を作ることや設備を供与することは教育改善のための手段でしかない。ODAも限られた財源を利用する国家事業として、納税者に対しアカウンタビリティを求められる時代となった。適切な評価活動によって、当初の援助目的が達成されたかどうかを調べ、相手国政府と日本の納税者に知らせなくてはならない。評価を意識したデータ収集が不可欠である。
そのためには、結果が測定できるような仕掛けをプロジェクトの中に仕組むことが重要である。プロジェクトに先立って、必要な指標を集め、プロジェクト終了後にそれらがどのように変化したかを、プロジェクトの対象校・対象地域、非対象校・非対象地域について比較しなければならない。被援助国が必要な既存のデータを持っていなければ、援助国側が主体的にデータを収集する必要がある。
まず基本設計調査の中に評価の視点を入れなければならない。今回評価対象となった案件でも、基本設計調査の中で効果として書かれていることは、達成すべき目標ではなく、単なる希望や期待であり、具体的に測定されないし、測定が可能なように援助の条件を整えてもいない。同じ内容の案件でありながら、年度によって違う効果が期待されているのも、後で効果を証明しなければならないことを理解していないからである。
(e) 日本と先方政府との分担
被援助国がオーナーシップを持ち、自立発展を促すためにも、援助プロジェクトは日本の丸抱えではなく、日本側と被援助国側で仕事を分担して実施する場合が多い。しかし、被援助国側の分担部分の完了がプロジェクト全体の成否に決定的な影響を持つ場合、日本側の分担分は計画通り完了したのに、被援助国側の分担分の遂行が不十分で、その結果として、プロジェクト全体の効果が上がらないことが起こりうる。
しかし、この場合でも日本側は責任を果たしたのだから、プロジェクトは目標を達成したと言うことにはならない。理科実験室や便所を作っても、水の供給がなければ利用できず、教員の中央研修を行っても地方研修以下が思うようにいかなければ、現場の授業内容は良くならない。
供与した施設、設備はメインテナンスがなければ、いずれ使用不能となる。先方にメインテナンスの費用負担を約束させるだけではなく、住民参加体制を作るなど、メインテナンス費用が担保出来るような具体的仕組みを施設・設備の供与と同時に作る必要がある。
被援助国に一層の努力を求めると同時に、仕事の分担に問題はないかの吟味も重要である。「教育施設拡充計画」のように、雨水を利用する設計などの工夫も大事である。また、援助案件実施に当たっては、先方政府の義務の遂行が技術的等の理由によって困難であれば、コンサルタントの張り付けによるモニタリングと効果測定のシステムまでも案件のコンポーネントに入れておく事が重要になる。
(ロ) 将来の案件に係わる提言
(a) ハードだけでなく、ソフトも
施設・設備といったハードだけを供給しても、それを上手に利用するソフトがなければ効果は発現しない。日本のこれまでの援助はハードに偏重しており、ソフトに対する援助が少なかった。ソフトがある場合も、ハードと連携しておらず、効果が出にくい場合がある。今後はハードとソフトを組み合わせるような援助をもっと考えていかなければならない。
無償資金協力はこれまで施設や教材などのハードの供給を目的としてきたが、今後はただ単に教室を作ったり、教材や機材を供与するのではなく、それらに関する研修・講習を実施するなど、供与したハードが効果的に利用されるような工夫が必要である。加えて、プロジェクト管理体制の強化をはかり、効率化を図る必要がある。
この意味で、平成10年度よりソフトコンポーネントを一般プロジェクト無償に組み込むことが出来るようになったことは、高く評価でき、今後の無償案件の効果がますます高まることが期待される。
(b) 案件間の関連
援助の効果を高めようとする場合、案件と案件とを有効に結びつけることも大事である。援助は限られた財源に基づいて行われている。その際関係者同志のネットワーキングが非常に重要になってくる。一つ一つのプロジェクトを無関係のものとして実施するよりも、さらに大きな効果が期待できる。
例えば、無償資金で建てた学校を中心に協力隊員が入って理数科教育の巡回指導を行ったり、これらの学校の教員を研修に出したりして、地域の理数科教育の核にするなどの連携が進めば、ハードとソフトを組み合わせた効果の高い援助ができる。
(c) フォローアップの重視
教育援助案件は校舎建設などハードな案件が先行しやすい。これらの被援助校に対して、質的向上、内部効率向上のためのプロジェクトをフォローアップの援助として行えば、全体として総合的なプロジェクトにすることができる。
(d) 地元社会の参加を求めて
今回評価の対象となったフィリピンにおいては、伝統的共同体において農業労働や家屋建設などにおいて助け合い、協力し合うことが慣行となっている。また、各学校においてもHAが活発であり、施設の維持管理からドラッグ防止運動、衛生運動など、実に活動が多岐にわたっている。今後の援助は、こうした地域住民が主体的に関わり、彼ら自身のものとして案件が地域に定着していくことが必要である。さらに言えば、たとえ機材や施設などのハードの案件であっても、地元の人々の意識に働きかけながら、彼らのオーナーシップを高める案件づくりが必要である。
(ハ) 評価方法の改善に係わる提言
今次評価においては国家経済開発庁(NEDA)、教育文化スポーツ省(DECS)等開発・教育関連の中央・地方機関、各学校の校長・教師・PTA等の代表などフィリピン側関係者より幅広い意見を聴取することができ、大変有効であった。また、NEDAやDECSへの現地調査終了報告の際、これら関係者が一同に会し自由闊達な意見交換を交わした。これは評価・分析の上で大変参考となった。しかし、2週間程度の短期間の視察、資料収集は限界が大きい。現地コンサルタントを活用して、調査票を配布、回収するなど、判断材料を増やす必要がある。また、立場によって言うことが違うため、一方からの情報からだけでは判断が偏る。多方面からの情報収集に努めなければならない。
援助の有効的な活用を促進するとの観点から、最近NEDAに援助評価・モニターを実施する部署(PMS:0ffice of the Public Monitoring Staff)が設置されており、今次評価においても積極的な協力を得た。被援助国側におけるかかる動向を積極的に支援する立場からも、今後、我が国のフィリピン向け援助の評価活動においては、PMSと積極的に協力していくことが望まれる。
ADBは1988年から1995年にかけて、フィリピン全土で675校舎の建設を行ったほか、教育設備の充実、カリキュラム開発、教員研修も行った。その修了報告書では、費用の分析だけではなく、就学者の増加など教育の量的改善、成績・中退率・残留率など教育の質的改善について、具体的な数値目標と到達度に言及している(1996)。
これに対し、わが国の援助案件では、教育の量的、質的効果に対しては期待を表明するだけで何らの指標も示さなかった。効果は言葉で希望を述べるのではなく、数字を挙げて、達成度を示してこそ説得力を増す。作った校舎や供与した設備が実際にどのように使われ、効果を上げたかを評価するまでを援助案件の一貫と考え、評価活動を始めから案件に組み込むことが、効果を実証し、納税者の理解を得る手段となる。ADBにおいても、このような指標値による評価は最近のことであり、日本の援助においても、今後はこのような手法をとりいれていくことが適当である。
(2) 政策レベルの提言
(イ) 将来の日本の教育援助に係わる提言
(a) 他援助機関との比較を意識
国際機関や他の援助機関との援助協調が言われている。多くの機関が似たようなプロジェクトを行えば、相互に費用と効果の比較が行われるのはやむを得ない。初等・中等学校校舎建設には高層ビル建設のような特殊な技術を要しない。企画はほぼ類似しており、異なった援助機関間の比較も容易である。今後ますます援助案件のアカウンタビリティが問われ、他援助機関の類似の案件との比較がなされる。援助案件の策定においても、効果比較を念頭に置いた計画が立てられなければならない。
援助案件の評価基準もグローバルになる。効果測定に慣れていない日本国内の特殊事情はあるにしても、今後は効率や効果の視点が重要とならざるを得ない。
(b) 柔軟な援助
援助の姿勢の問題として、計画の実施が硬直的であることが指摘できる。基本設計調査団が来て被援助国と話し合う機会が毎年あり、多くの改善要望を聞いたにも関わらず、それらの意見が基本設計報告書に予算等の問題から十分反映されない場合がある。身障者トイレの設置、教室設計の変更など小さな手直しはしても、構造全体の見直しなど、大幅な変更は計画年度が完了するまでしない。大幅な変更をすれば会計検査上の問題がでたり、見通しの甘さを指摘されることを恐れるあまり、当初計画にこだわりすぎるという事情もあろう。しかし、援助の効果を高めることを第一に考え、当初計画にこだわらず、計画の早期打ち切りも含め、大幅な仕様の改善など、改めるべき所は早急に計画変更する柔軟性が必要である。
(c) 社会開発の視点
これまでの援助はハード中心だったこともあり、社会開発の視点が不足している。校舎建設は強固な建物を建てることだけが念頭にあり、その限りでは達成されたが、社会開発の点から見れば物足りない。特に基本設計調査の段階では、社会開発に関わる様々な専門背景をもつメンバーからなる調査団を組織し、お互いが補完しあいながらプロジェクトを総合的に立案していく必要がある。
(ロ) 将来の日英協調に係わる提言
今次合同評価は英側との初めての合同評価であったが、英側が近年特に重視してきている社会開発面等の視点が加味されることにより、我が国案件評価がより充実したものとなった。このような多国間の評価協力は、評価視点の多様化、客観性及び公正さの確保の面で意義が大きい。お互いに学ぶところ大であった。将来的にはこの関係をより成熟させていくことが望ましい。具体的にあげるならば、
- (1) 終了後評価だけでなく一連の評価調査のプロセスを共同で実施してみること、
- (2) 書式を共有化する作業を続け、手法や教訓、改革案などの要点をまとめる、
- (3) 同一国において、英国も日本も実施しているセクターの案件を比較してみる、
- (4) 英国と日本とが補完的に利点をもてる援助協調の方策を探る、などが考えられる。
(ハ) 他の援助機関との協調に係わる提言
日本はこれまでハード面などの教育インフラ整備を中心に援助を行ってきたが、それらのインフラが十分活用されているとは言えない。上手な利用を通して、教育改善を図るべきであるが、すべてにわたって援助を行うことは不可能である。他の援助機関と協力して、ハードとソフトを織り交ぜた援助ができるのではないだろうか。しかし、その場合も、日本の役割がいつもハードばかりであるのは困る。場合場合に応じて、ハードを担当したり、ソフトを担当したりできることが理想である。
また、他の援助機関もたくさんある中で、援助地域の分担を明確にしていくことも考えられる。本件のような全国全地域に対する広範囲だが一面的な援助では、学力向上などの効果測定を行うことは技術的に極めて難しい。また、管理費用がかかり、プロジェクトの単価を押し上げる要因となる。それに対し、地域を限って多面的な援助を行えば、他地域との比較の形で、援助効果の測定が行いやすい。効果を高めて実証するという立場から、これまでとは異なった形の援助も考えられていい。
文献
ADB, 1996, Project Completion Report on the Secondary Education Development Sector Project in the Philippines
DECS, 1989, A Cost Benefit Study of the JICA-Assisted Typhoon-Resistant School Building Project
DECS, 1994, Project Completion Report TRSBP Phase I
DECS, Project Developmentand Evaluation Division, Office of Planning Service, 1995, A Study of the Effects of the Secondaly Education Development Program in Fifteen Case Schools
DECS, 1996, Master Plan for Basic Education (1996-2005)
DECS, 1997a, Facts Figures on Philippines Education
DECS, 1997b, Report on the Evaluation of the Educational Facilities Improvement Program (EFIP) Phases I to III
国際協力事業団、1990「フィリピン共和国中等学校教育機材整備計画基本設計調査報告書」
国際協力事業団、毛利建築設計事務所、1996「フィリピン共和国教育施設拡充計画(第4次)基本設計調査報告書」
毛利建築設計事務所、1993「学校校舎建設計画基本設計調査報告書(第5期)」
システム科学コンサルタンツ、1992「フィリピン共和国中等学校教育機材整備計画(第2期)基本設計調査報告書」
The World Bank, 1996, Staff Appraisal Report of the Philippines Third Elementary Education Project

