6.日本の教育・人材開発への取り組み
日本はすでに述べたように件数は多くないもののインドネシアに対し、初等・中等教育、高等教育、職業訓練等の各分野で援助を実施している。更めて1980年代以降の主な案件を示すと以下の通りである。
今回の評価調査対象案件は、「貿易研修センタープロジェクト」と「バンドン工科大学整備事業」であるが、インドネシアに対する教育・人材開発援助のあり方を広い視点から考えるため、視察範囲を広げ、初等中等教育分野から中学校校舎整備事業、高等教育分野から高等教育開発計画、スラバや電子ポリテクニックを視察した。以下それら3件のプロジェクトの概略を記す。
| 分野 | プロジェクト名 | 年度 | 援助形式 |
|
初等・中等 |
中学校校舎整備事業 | 95 | 有償 |
|
高等教育 |
|||
| 農産加工計画 | 77~84 |
無償+ プロ技 |
|
| 教育研究資機材拡充事業 | 77,85 | 有償 | |
| 熱帯雨林研究計画 | 84~89 |
無償+ プロ技 |
|
| スラバヤ電子工学ポリテクニック学院 | 87~94 |
無償+ プロ技 |
|
| 科学技術振興プログラム | 88 | 有償 | |
| ボゴール農科大学大学院計画 | 88~93 | プロ技 | |
| ボゴール農科大学拡充事業 | 89,94 | 有償 | |
| 高等人材開発事業 | 90,95 | 有償 | |
| 高等教育開発計画 | 90~99 |
無償+ プロ技 |
|
| 高等教育機材整備計画 | 90,91 | 無償 | |
| 環境研究センター拡充事業 | 91 | 有償 | |
| バンドンエ科大学整備事業 | 92,94 | 有償 | |
| シャクワラ大学整備拡充事業 | 93 | 有償 | |
| ムラワルマン大学整備拡充事業 | 95 | 有償 | |
| パティムラ大学整備事業 | 96 | 有償 | |
| 職業訓練 | 職業訓練指導員・小規模工業普及訓練センター | 83~91 |
無償+ プロ技 |
| 貿易研修センター | 87~95 |
無償+ プロ技 |
|
| CEVEST職業訓練向上計画 | 92~97 | プロ技 | |
| 南南協力研修機材整備計画 | 93 | 無償 | |
| 職業訓練センター機材整備計画 | 93 | 無償 | |
| 海員学校整備事業 | 95 | 有償 |
6-1 スラバヤ電子工学ポリテクニック(EEPIS:Electronic Engineering Polytechnic lnstitute of Surabaya)
6-1-1 プロジェクトの概要
(1) 背景
インドネシア政府は1969年第1次国家開発5カ年計画を策定し、以降数次にわたり5カ年計画を策定し、経済社会開発に努力してきた。常に掲げられた基本目標は、生活水準、教育、福祉の向上とその公平な分配であった。教育においては、教育文化省は1975年に高等教育の基本開発政策を定め、1975年から1985年に至る10カ年実施計画を作成、既存の高等教育の諸条件の改善と国家開発の基本理念に結びついた高等教育システムの開発をめざしている。教育文化省による高等教育の重要政策事項は以下である。
- (1)高等教育機関の整備・充実
- (2)大学院教育および研究活動の推進
- (3)既存の高等教育機関の有効利用
- (4)ポリテクニックの増設による専門的技術をもった人材(中堅技術者)養成の拡充・強化(特にエレクトロニクス、経営、農業、海洋科学)
- (5)大学とその他の政府機関との連携強化(国家開発をサポートするための研究活動のため)
上記事項が重要政策として取り上げられた背景としては下記状況があげられる。
- (1)高い中退率・落第率(低い卒業率)、在学年数の長期化
- (2)高等教育に対する需要の拡大・多様化に対して高等教育機関の収容能力・教育形態が十分でないこと
- (3)教育予算の不足(施設・設備一般、特に図書・実験設備の不足)
- (4)高等教育機関の地域的配置のアンバランス
- (5)S1課程(学士号取得課程)以外の特に専門・職業教育課程の不足・未整備
- (6)教員の数・質の不足(教員給与・研究費などの低水準)
- (7)社会的ニーズに対しての教育機関・形態の拡充不足教育文化省がポリテクニックの増設による中堅技術者の養成を重点政策としていることが、本プロジェクトの要請となった。
(2) 経緯
1984年4月に日本の対インドネシア経済協力総合ミッションがインドネシアを訪問した際、同国政府は日本政府に対し、工芸分野のポリテクニックの新設への協力を要請した。しかし、日本側は1984年7月の年次協議において同分野への協力は、専門家の確保等の面で困難であると説明した。このためこれに変わる分野として、教育文化省と国家開発計画庁(BAPPNAS)は「電子工学」分野を候補にあげ、既存のスラバや工科大学キャンパス内に新たなポリテクニック校の建設と、それにかかわる技術協力を要請した。
国際協力事業団は、1985年1月にコンタクト・ミッションを派遣、同調査に基づき日本は技術協力分野を「電子工学」に特定し、国内支援体制は東京工業大学を拠点とし、専門家派遣、研修員の受け入れについては国立高等専門学校に協力を仰ぐこととした。1985年7月に事前調査団を派遣し、87年3月の実施協議調査団によりR/Dをインドネシア側と署名、本プロジェクトが開始された(プロジェクト方式技術協力1987年4月1日~1992年3月31日)。
インドネシアにおいてはポリテクニックは職業教育制度の範田書にあり、これに従い、EEPISは電子工学、通信工学分野におけるHigher Technicianを養成し、社会に供給するための教育機関との方向付けがなされた。Higher Technicianとは「企業内で大学卒のエンジニアの補佐能力、企業の自営能力、開発プロジェクトの企画・進行・実施能力、技術教育、職業訓練機関の教員としての能力を持つ技術者あるいは技能者」を意味している。
協力の実施過程は以下の通りである。建物建設等無償資金協力18.95億円。
- 1986年 建物、実験機材の設計開始
- 1987年 設計を完了
- 1987年 1月建設着工
- 1988年 3月建設完成
- 1988年 夏供与資材搬入完了
1987年から以下の点について技術協力が実施された。
- (1) 日本側の専門家派遣とカリキュラム開発、学校運営援助
- (2) インドネシア側教員の日本での研修
- (3) プロジェクトの当初に設計、供与された実験機材を補完する形の機材供与
6-1-2 プロジェクト視察
(1) プロジェクトの効果
EEPISプロジェクトは、インドネシアにおける電子・通信工学分野の中堅技術者を養成し、インドネシアの産業界に供給することを目的としている。非石油・ガス製品の輸出振興を図っているインドネシアにおいては製造業部門の将来の技術部門、開発部門を担う技術者の育成を必要としていた。
上記目的を果たすため、EEPISの暫定カリキュラムでは基本的な電子・通信工学に関する内容に加え、EEPISの卒業生の雇用機会拡大を配慮して「工業管理」、「企業内訓練」、「電気・機械工学に関する基礎」、「雇用の多様化に備えた幅広い技術の習得のためのコンピュータ教育」等が付加された。カリキュラムにおける理論と実験・演習の比率は約4対6とされ、実務訓練に重きを置くものであった。また、電子工学科、通信工学科ともに共通科目を多くし、卒業生が幅広く電子・通信系の技術に対応できるような設定も行われた。
EEPISのカリキュラムは実施段階において、電子・通信工業の急速な発展段階を勘案し、日本の高専レベルを志向するものとなった。実施段階で変更された主な点は下記である。
- 1)基礎理論の重視
- 2)理論:実験・演習の時間利率を6:4に変更
- 3)一つの科目は理論と実験のペアで構成されていたが、理論(講義)と実験を分離。
主な変更の理由は下記である。
- 1)理論と実践を兼ね備えた実践的技術者を育成する必要がある。
- 2)主体的に行動できる技術者を養成する必要がある。
- 3)電子・通信工学分野では基礎理論の理解が十分でないと、技術の基礎となる動作を十分理解できない。また、技術進歩の早さから考え、将来の新しい技術に対応するためには基礎理論の深い理解は不可欠である。
こうしたカリキュラムは電子・通信工業という技術革新の大きな分野であるから定期的に検討することが必要と思われるが、インドネシア経済の要請を満たすものであったということができる。
こうしたプロジェクトヘの協力は、建物の建設(無償資金協力18.95億円)、プロジェクト方式技術協力による専門家の派遣、研修員の受入等が実施された。日本への研修員派遣は30名にのぼり、その後日本の大学院で学位(修士号取得3名、うち博士号取得1名、現在取得中1名)を取得したものもいるが、大半は工業高等専門学校で研修を受け帰国した。日本からの専門家派遣は、1992年3月のプロジェクト終了までに長期専門家は第1次から第4次まで32名、短期専門家は21名が派遣された。
EEPISは1988年に電子工学科に最初の入学生63名(合格者に対する受験者倍率9.1倍)、通信工学科に68名(同14.3倍)、合計131名(平均倍率11.8倍)を受け入れ、D3コースの教育を開始した。高い受験倍率はその後も続き、1992年度からは電気科を新設、1995年度からは夜間部も発足させ、順調に教育活動を行っている。
EEPISの入学生数、卒業生数は表6-1に示す通りである。教育期間は3年間であり、1991年9月に第1回卒業生を出した。第1回卒業生は企業の入社試験で優秀な成績を示し、90%の学生が卒業前に就職が内定するほどの教育成果を上げた。例年入学者の1割強の退職者がいるが、この大半は次のようなインドネシアの教育制度によるものである。S1(大学)の入試に失敗したものが第2志望のD1(ポリテクニック)へ入学するものの、翌年S1を再受験し、大学(S1)へ移る。
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 合計 | ||
| 入学者数 | 普通 | 131 | 141 | 139 | 137 | 165 | 180 | 180 | 168 | 171 | 171 |
1,583 |
| 夜間 | 102 | 93 | 102 | 297 | ||||||||
| 退学者数 | 普通 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 21 | 18 | 7 | 8 | 1 | 139 |
| 夜間 | 18 | 3 | 21 | |||||||||
| 卒業者数 | 普通 | 114 | 124 | 121 | 123 | 147 | 154 | 150 | 933 | |||
| 夜間 | 0 | |||||||||||
EEPISの就職率が非常によいのは日本の高等専門学校にみられる就職活動を学校活動の一つにしたということが背景にある。この数年卒業生は、NEC、SONY、ナショナルといった日系合弁企業やインドネシアの大手企業にも多く就職している(図6-1)。
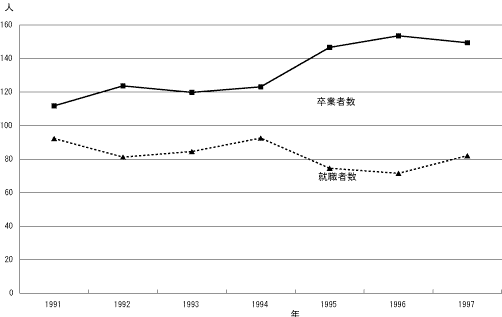
協力期間中に以下のような組織形成が行われたことが効果を生んだといえる。
- 1)継続して卒業生を輩出する組織・財政基盤
- 2)中堅技術者に必要な技術を習得させるカリキュラム・シラバスの設定
- 3)上記カリキュラム・シラバスを教授する能力を持つ教員の養成
- 4)中堅技術者足りうる能力をもつ入学生の選抜
- 5)企業とのコミュニケーションを円滑化し、企業のニーズとカリキュラムとの整合性の確保、就職活動と卒業生の就職状況を把握するためのチャネル
他のポリテクニックに較べ就職面で良い成果を上げているEEPISであるが、不満を持つ卒業生がいないわけではない。ただこれはEEPISの問題というよりインドネシア経済の産業の裾野の狭さによるものである。
面接をしたEEPISの2人の卒業生は、EEPISで通信工学を専攻したが、現在、スラバヤの企業に就職し機械部門の職に就いている。企業数が限られ、就職先が限られているインドネシア経済の現状では、70名の学生の中から選ばれ入社した2人であっても専攻分野の職に就くことは容易ではないのが実状である。
就職指導面で成果を上げているが、卒業生から日常のコース中で企業情報、企業訪問の機会を提供してくれば、希望に添った就職の機会が広がるとの希望が出された。3年間を通じ、企業、工場訪問は2、3回にすぎなかったとのことであり、より実践的技術者の育成を目的とする観点からは企業、工場訪問研修をもっとコースへ組み込むことが効果が上がるように思われる。
日本で研修を受けた教員は26名で、日本での研修先は日本から次年度専門家として派遣される予定の高等専門学校教員の研究室である。このため高等専門学校教員が専門家としてインドネシアに派遣される期間と合わせて、同一専門家から2年間弱の指導が受けられる効率的なシステムとなっている。日本では約2ヵ月東京国際研修センター(TIC)で研修の後、約9ヵ月各地の高等専門学校で指導を受ける。ただ、1年という研修期間をかけるならば、学位取得を目的としないにせよ単位認定制度などを設け、教員が高位の学位を取得する際の助けになるようなシステムを構築すればさらに意欲が高まると思われる。残念ながら学位や資格修得のない1年間の研修は待遇改善(昇級等)の助けとはなっていない。
日本で研修を受けた者の中には、家族持ちにとって1年という期間は長いとの意見もあった。日本語研修をインドネシアで行い、日本でテクニカルな部分の研修を行うようにすれば期間を短縮できるのではとの考えが教員から示された。
日本の高等専門学校の受け入れ態勢であるが、教官とのコミュニケーションに多くの派遣された教員が悩みを感じていた。しかし、派遣された教員は学ぶ側はアグレッシブな態度が必要と積極的な意識を持ち問題に望んでいた。ただ、こうした意欲を示したにもかかわらず高等専門学校の教官が忙しく十分な指導が得られなかったため自分で勉強しなければならなかったケースもあったようである。多くの教員は、高等専門学校の教官と最近でもE-MAIL等で連絡を保ち、情報を得る、指導を得る等の関係を維持しており、協力終了後も望ましい協力関係ができている。
(2) プロジェクトの自立発展性
EEPISは、当初想定された以上の良質な中堅技術者となる卒業生を代表的な企業群に常に提供し、また産業界との協力も良好な教育機関になりうると期待される。表6-1に示すように、1995年から夜間部を開設したのは、施設・設備の有効利用と、授業料収入増加のためである。自立発展への努力の一環と考えられる。
EEPISは良質な教員確保と自己研鐙を促進するための努力を行っており、その結果、教員の学位などについても他のポリテクニックに格段に優れたスタッフがそろっている。そしてさらに改善の努力を続けている。教員の確保とレベルアップは長期間の持続が必要であり、今後も研修などの努力が継続されることが重要である。具体的には次のような継続的な指導が重要である。
- (1)教材を全体的な視点から見直し、自己研鐙を積ませる
- (2)実験計画・技術に関する経験を積ませ、機器運用・保守の能力を高めさせる
- (3)研究課題をもたせ、意欲的に取り組ませるための指導を継続する
産業界が求めるEEPIS卒業生への技術は技術革新に伴い変化していくであろう。したがってEEPISは産業界との対話を密接にし、教科内容を対応させることが必要である。EEPISでは産業界に対し教育を開放している。これはEEPISの意欲の高さ、自立発展性を示すものである。産業界に対する開放は、オムロンの合弁会社やガルーダ・インドネシア航空の社員に対するリカレソト教育として活用されている。ガルーダ・インドネシア航空の場合、毎年30人の技術者を2年、3年に編入させ訓練を行っている。この事業は1992年から1995年まで実施され、合計90名の職員が研修を受けた。オムロンのケースでは製品が高度化し従業員の訓練が要請されたためSのコースとして受け入れているものである。EEPISはオムロンと研修を短期間、日中に行うという合意書を取り交わしており、訓練に必要な1.5億ルピアの機材をオムロンが寄付をするとのことである。今後もこうした事業が定着すれば多くの企業に貢献でき、EEPISの評価を高めることになる。これは、ポリテクニックに集積された技術知識を地場産業に還元するものであり、スラバや地域経済へも貢献しうるものである。
EEPISは良質の教育を提供しており、産業界からの信頼は厚い。しかし、インドネシア社会でポリテクニック卒と大学卒という社会的評価の差に残念ながら直面する場合もある。数年前、ある日系合弁企業では、大学卒の資格を得るためEEPIS卒業生が集団退職し、大学へ進学するという問題が起きた。インドネシア企業は中堅技能者を必要としているが、待遇面では大学卒業者と差があることもこうした問題の原因となっている。
先に述べたEEPIS退学者も大学と高等専門学校の社会的評価の差に関連している。インドネシアでは例年5月に国立大学の入試があり、6月に結果の発表がある。その不合格者がその後行われるポリテクニックを受験し入学するわけだが、第2志望に入学したわけであり多くは翌年大学を再受験し、大学を選ぶ傾向にある。これは大卒者にくらべ、ポリテクニック卒業生に対しては、彼らの有する知識や技能にみあった社会的評価がなされていないためである。ポリテクニックの社会的評価がインドネシア社会において高まるような働きかけや仕組みがない限り、残念ながら援助に対する効果は大きな制約を受けてしまう。
インドネシアの高等教育機関には学問的教育機関と職業専門教育機関がある。ポリテクニックは後者に属する。スラバや電子工学ポリテクニック卒業者が得られる資格はD3であり、大学卒(学士)はS1という資格が与えられる。S1とD3との間の最低就学年数の違いは1年であるが、両者には非常に大きな人事評価ギャップが存在している。
たとえば、公務員のキャリアにおいて大きな差が出る。D3コースは3年課程、S1コースは4~4.5年課程である。D3コース終了者は公務員としてのキャリアはIIB+から始まるが、S1修了者はIIIAから始まる。IIB+とIIIAとの間にはIIC、IIDというランクが存在している。IIB+からIICまでが2年、IICからIIDまでが4年、IIDからIIIAまでが4年かかる。すなわちD3とS1では、就学年数に1年の差があるにすぎないのに職階には10年の差が生じる。民間企業でもほぼ同様の人事評価システムが取られている。したがってD3コースであるポリテクニックに入学してもS1(大学)へ入り直したり、D3保持者は2年間の職務経験があればS1課程の編入試験が受けられるため、先の日系企業のように集団退職のような例が発生する。
こうした問題に対処するためにはEEPISのコースレベルを上げることが必要である。ポリテクニックはD4コースを置くことができる。D4はポリテクニックの教員養成を目的とするプログラムであり、S1と同じ社会的評価が得られる。EEPISはD4コースの設置を準備中で、わが国に対して協力要請を行っている。D4コースが設置されれば、インドネシアの電子工学分野では最初のD4コースとなる。これはただ卒業生の資格の問題に留まらず、インドネシアのポリテクニック政策とも係わる。教育文化省高等教育総局は現在26校あるポリテクニックを今後3年間で19校増やし、2020年までには155校にするという量的拡大計画を持っている。それに見合う教員の養成も課題であり、EEPISがD4コースを持ち電子工学系統のポリテクニック教員供給のセンターとして機能することはインドネシアの教育政策と合致するものである。わが国としても、こうしたEEPISの新しい方向に対して、これまでの援助効果をさらに発展させるための協力が望まれる。
EEPISは今後機材の更新、教員の知識、経験の向上を自らの努力ではからねばならない。EEPISの財政面の強化が重要であるが、生徒数の増加、夜間講座の開設、企業からの訓練生の受入等により自立への努力がなされているといえる。
6-2 インドネシア高等教育開発計画(HEDS: Higer Education Development support)
6-2-1 プロジェクトの背景と経緯
インドネシアは第2次国家25カ年計画(1994/95年~2018/19年)において、教育重点政策として「教員の質の向上」と「工学教育の質の充実」を取り組むべき課題として掲げている。教員に高位学位を取得させ、また大学においては研究を振興することが目指されている。
本プロジェクトは日米共同プロジェクトとしてUSAIDから1988年2月に提案された。目的は、インドネシアの地方開発政策の一環として、スマトラおよびカリマンタン地域における高等教育水準の向上である。同地域から複数の対象大学を選出し、現職教員に高位の学位取得、さらに最新の教授法の技術移転のための機会を提供しようとするものである。
USAIDから参画を要請された日本は、1988年7月実施のプロジェクトデザイン調査に参加、同年11月にプロジェクト形成調査団を派遣し、日本側協力計画案をUSAIDおよびインドネシアに提案した。さらに1989年4月のプロジェクト形成調査団において「日本は工学系分野に対して、またUSAIDは基礎科学と経営学系分野に対しての協力を担当」という枠組みを固めた。こうして両地域で20校が対象大学として選ばれた。この内、14校はスマトラ地域、6校はカリマンタン地域から、また、13校は国立から7校は私立から選ばれた。USAIDはこの20校すべてについて援助を行い、JICAは11校についてだけ協力することとなった。1989年6月にインドネシア政府は日本へ正式要請を行い、日本は1989年8月に事前調査、1990年4月に実施協議調査団を派遣、R/D署名を行い、同年4月12日から5年間の期間でプロジェクト方式技術協力が開始された。JICAが援助対象としている大学は表6-2の通りである。
その後、計画打ち合わせ調査をはじめ1991年から1993年の間に派遣された4回の調査団により、プロジェクトの活動進捗状況と協力計画の確認・検討が行われた。さらに1994年8月の終了時評価調査の結果、本プロジェクトの協力期間はUSAID側の協力終了日にあわせ1996年7月31日まで延長された。また、このプロジェクトを支援するために、無償資金協力による、高等教育機材整備計画が別途実施され、11大学における工学実験機材の拡充が行われた。
| 大学名 | 略称 | 所在都市名 | 備考 |
| スマトラ島 | |||
| シア・クアラ大学 | UNSYIAH | バンダー・アチュ | 国立 |
| 北スマトラ大学 | USU | メダン | 国立 |
| 北スマトラ・イスラミック大学 | UISU | メダン | 私立 |
| メダン・エリア大学 | UMA | メダン | 私立 |
| ノメンセン大学 | UHN | メダン | 私立 |
| ダルマ・アグン大学 | UDA | メダン | 国立 |
| アンダラス大学 | UNAND | パダン | 国立 |
| スリウィジャヤ大学 | UNSRI | パレンバン | 国立 |
| ランプン大学 | UNILA | バンダー・ランプン | 国立 |
| カリマンタン島 | |||
| タンジュンプラ大学 | UNLAM | ボンティアナック | 国立 |
| ランプン・マンクラット大学 | UNLAM | バンジヤルマシン | 国立 |
また、協力延長後の1996年1月、日・米・イ合同評価調査の結果、インドネシア側の自立体制の確立が不十分であるため、協力継続が必要とされ、1996年8月1日から更に3年間、協力期間を延長した。USAID側は主として資金難のため、計画の延長を行わなかった。
6-2-2 プロジェクトの効果
JICAがスマトラ島及びカリマンタン島の11大学の教員の資格、資質向上を図るため実施した活動は次のように要約できる。また、現在のHEDSプロジェクト実施体制は図6-2の通りである。
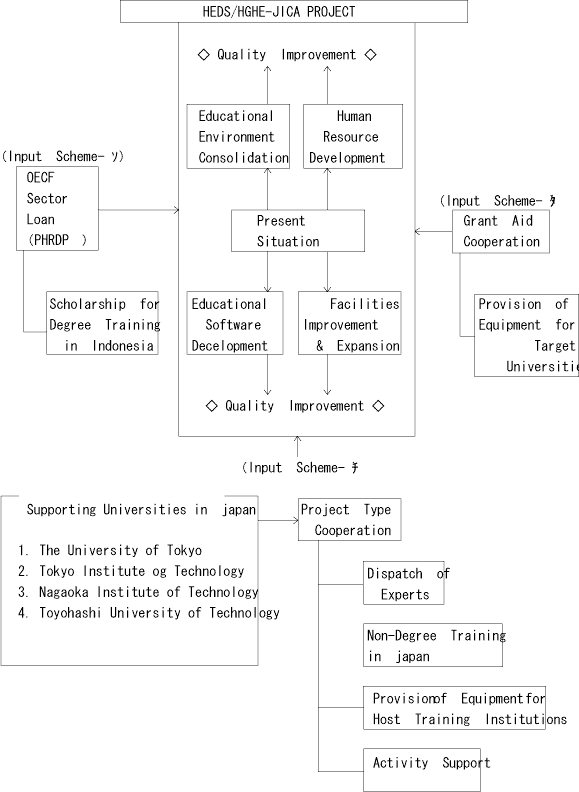
- (1)Degree Program(学位取得プログラム):対象大学の教員で修士号、博士号を保持しない者を、インドネシア国内留学により学位取得させる。
- (2)セミナー、ワークショップ開催:短期の国内研修を対象大学等で行う。
- (3)日本における研修:国内留学で学位を取得した者や、大学の管理運営担当者などに、日本の工学教育の現状を研修する機会を与える。
- (4)教育環境の強化:実験機材や文献など工学教育環境を充実させる。
- (5)活動促進プログラム:上記の活動を効果的に行うため、大学管理システムのコンピュータ化、SDPF(研究開発への資金援助)、コア・ラボラトリ、教科書開発など、各大学が行う活動を支援する。
(1) Degree Program
Degree Programは11大学の教員を対象にバンドン工科大学(ITB)等で国内留学奨学金を支給し、学位取得を奨励するものである。国内奨学金はOECFの「インドネシア高等人材開発事業」の一部資金が充てられている。
当初の計画では1990年から1992年までに各年60名、合計180名が本プログラムの対象とする予定であったが、対象大学の強い要請により実施段階で年間80名、合計240名に増員された。1997年度入学生の大半はITBにて研修を受けることになっているが、ガジャマダ大学工学部、スラバや工科大学においても新たに学位取得プログラムが実施される予定である。ITBにとって国内留学生の面倒をみる負担は大きく、受け入れ基盤の拡大は、特定大学の負担軽減という観点から考えても有益である。ITB担当者にはHEDSプロジェクトで受け入れる大学教員の一部はITBの学生と比較しても学力が低く、また学究生活を送る上での心構えから教えなくてはならないと、厳しい見方をする人もあったが、副学長の一人は今後も全ての修士号取得希望者をITBで引き受けたいとしていた。1校に集中せず、ガジャマダ大学等に受入先が広がることは、負担を軽減する点、競争原理によりプログラムの質が高められる点からも好ましい。
表6-3に示すように、学位取得プログラムにより、ITBにおいて高位学位を取得した教員は1997年10月末現在において修士号が201名(このうち104名は準備課程を経由し、また1名は対象11大学以外)、博士号が1名になる。1990年度入学の第1期から第8期まで修士・博士課程には306名が入学しているが、うち31名が未登録または学位を取らずに退学し、73名が在学している。このうち博士課程には13名が入学し、うち1名が学位を取得し、3名が未登録と中退、現在9名が在学中である。
最初の3期での取得者がかなり多く4期以降で減少(入学者から推定して5期以降も各20名以下)しているのは、入学を希望し資格を有するものの多くがすでに入学済みであるためと思われる。1997年6月現在対象11大学でなお711名(全教員の63%)の教員がS1のみの保有者であり、そのうち約100名は学部卒業直後の若手教員のため学位取得プログラムの潜在希望者は多いと思われる。
S2以上の高位学位保持者の割合はHEDSプロジェクトが開始した1990年には17%であったが、1997年6月には37%となっている。このうち18%はHEDSの学位取得プログラムによる学位取得者である。現在修士・博士課程在学中の教員数から判断して2002年にはS2以上の保持者が43%となり、そのうちHEDSプロジェクトによる取得者の割合は24%となると思われる。本プロジェクトの貢献は大きいといえる。
| 年度 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 計 |
| 大学 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1 | 1995 | 1996 | 1997 | |
|
Batch S3 S2 S2予科 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| 24 | 24 | 33 | 27 | 0 | 21 | 11 | 18 | 158 | |
| 46 | 38 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 在学中 | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 12 | 19 | 73 | |
| UNSYIAH | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 | |||
| USU | 8 | 7 | 4 | 1 | 20 | ||||
| UDA | 6 | 6 | 3 | 15 | |||||
| UHN | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||
| UISU | 1 | 5 | 12 | 2 | 20 | ||||
| UMA | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
| UNSRI | 8 | 5 | 7 | 20 | |||||
| UNAND | 5 | 2 | 10 | 3 | 20 | ||||
| UNILA | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||
| UNLAM | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 | ||||
| UNTAN | 4 | 2 | 7 | 14 | 27 | ||||
| 対象外 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 64 | 49 | 62 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 |
USAIDは対象大学教員を直接アメリカに送って教育したが、JICAは言葉の障壁と費用を主な理由として国内留学により学位を取得させ、修了者の一部を短期研修プログラムにより日本で研修させる方式をとった。結果として、アメリカの援助は費用がかかった割に落伍者が多かったのに対し、日本の援助は費用が安く、歩止まりも良かった。JICAスキームの制約上、国内留学の直接経費はインドネシア政府の負担であるが、取得支援のための間接経費、たとえばパーソナル・コンピュータあるいは教育・研究機材がホスト大学であるITBに供与されている。これはコースを受けている教員の教育・研究の支援だけではなく、ホストであるITBの活動を促進する点からみても有益である。
(2) 日本における研修
インドネシア国内留学によりITBで修士号を取得した対象大学教員に4ヵ月程度の日本での研修機会を提供している。大学運営、特定分野の学位保有者、特定分野の上級教員、特定分野の実験施設職員、共同研究員(SDPF)の5分野である。
表6-4は日本での研修について見たものである。1995年、1996年は若干計画数を下回るものの、原案策定時に想定していた以上の人数の参加が、長期間見られる。各年度の研修員受け入れ合計数は20~30名である。応募数が減少傾向にあるが、日本での研修に対する関心が低下したわけではなく、日本の研修先(大学院など)で相応の英語力が必要とされるのに対し、この制度で高位学位を日本で取得できないことがモティベーションを減少させていると思われる。
開始当初は大学運営部門のプログラムが主であったが、1993年からは学位プログラム卒業生の参加が主になっている。
運営管理プログラムは、学部運営管理を改善するために管理者の意識改革を目的に、1990年から1992年までに工学部長を中心に39名に対し日本で研修を行ったものである。この結果、毎年2回、HEDS学部長会議が実施され、HEDSの実施計画を検討し、かつ大学運営に関する情報が交換されるようになり効果をあげている。
日本で研修した教員は、日本の大学での研究、教育の状況、大学教員の日常の行動を学ぶと同時に、研究への刺激を受けたとしている。研修終了後、国費留学生制度の援助を得て、日本の大学の博士課程に入学したものは12名おり、うち2名はすでに博士号を取得している。
HEDSプロジェクト対象大学における博士号保持者は1997年6月現在でまだ51名のみであり全体の4.6%にすぎない。それもUNSRIに19名、USUに23名と集中している。現在、ITBまたは日本の大学の博士課程に在学中である教員は20数名おり、高学位取得に貢献しているといえる。
| 年度 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 合計 |
| 原案 | 21 | 13 | 14 | 58 | 74 | 180 | ||||||
| (改定案) | 21 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 5 | 244 |
| 達成数 | ||||||||||||
| 大学運営 | 21 | 13 | 5 | 1 | ||||||||
| 特定教科部門 | ||||||||||||
| (学位プログラム) | 9 | 23 | 28 | 21 | 11 | 3 | ||||||
| (上級教員) | 10 | 5 | 7 | |||||||||
| (コア・ラボ教員) | 11 | 2 | 2 | |||||||||
| SDPF関連 | 7 | |||||||||||
| 合計 | 21 | 23 | 30 | 30 | 30 | 23 | 18 | 4 | 179 |
(3) SDPF(Self Development Project Funding)
SDPF(Self Development Project Funding)は従来の援助にないユニークな援助である。すなわちSDPFとはHEDS対象大学の教員の研究活動を強化する目的で、1991年度から実施されたわが国の科学研究費のような競争原理に基づくグラント・プログラムである。SDPFは、若手の教員が応募しやすいように1995年度に選考カテゴリーを以下のとおり3分野に分け、現在も継続している。
- (1)カテゴリーA
研究費:10,000,000ルピア研究期間:2~3年
機材費:100,000,000ルピア使用言語:英語 - (2)カテゴリーB
研究費:6,000,000ルピア研究期間:1~2年
機材費:50,000,000ルピア使用言語:英語 - (3)カテゴリーC
研究費:3,500,000ルピア研究期間:1年
機材費:無し使用言語:インドネシア語または英語
SDPFのカテゴリーAおよびBでは日本側教員がアドバイザーとしてつくことが条件となっている。アドバイザーは短期専門家としてSDPFを与えられた研究者を訪れ研究指導を行い、逆にSDPFを与えられた研究者は日本研修によりアドバイザーを訪問して現状の国際的な研究レベルを理解し、かつアドバイザーからSDPFの研究について指導を受ける。このように、SDPF、短期専門家派遣、日本研修の三つの要素が有機的に結ばれたものであり1996年には7件実施されている。
SDPFの応募件数の推移は図6-3に示した通りである。対象大学の教員数が1,119名であることから、約4~5人に1人の割合で応募していることになる。採用件数はほぼ計画通りだが、応募件数はその2倍から3倍となっており、競争は激しい。
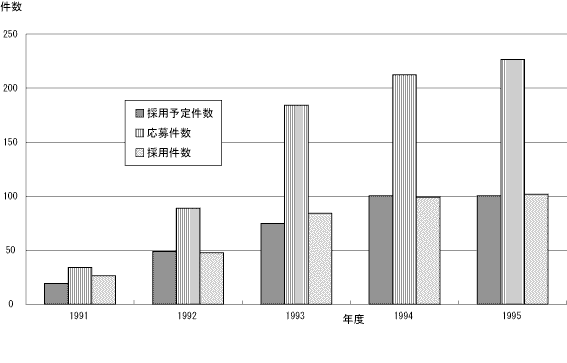
1992年度からSDPFの研究成果を発表する場としてSDPFセミナーが開催され、日本短期研修の成果を含めて表6-5に示す件数の発表が行われた。SDPFには学位取得プログラム修了者の内61名がすでに採用されている。過去10年間の情報学術誌への研究成果の発表状況は表6-6に示す通りである。対象大学の全教員から回答を得ているわけではないが、HEDSプロジェクトが開始された1990年から着実にその数を伸ばしている。
| SDPFセミナー | SDPF論文数 | 日本トレーニング報告 |
| 1992年 | 27(91年度SDPF報告) | 0 |
| 1993年 | 29(92年度SDPF報告) | 0 |
| 1994年 | 49(93年度SDPF報告) | 0 |
| 1995年 | 98(94年度SDPF報告) | 15 |
| 1996年 | 66(95年度SDPF報告) | 19 |
| 年 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| 論文数 | 6 | 5 | 3 | 27 | 16 | 27 | 55 | 70 | 78 | 112 |
(4) コア・ラボラトリ及びセミナー開催
インドネシアの大学工学部の実験施設、特に対象大学における実験施設の立ち後れは著しい。プロジェクトでは全対象大学に無償資金協力により機材を供与し、実験施設の整備を行った。また、1992年から3年間にわたって「コア・ラボラトリ」を全対象大学に設置した。コア・ラボラトリとは、対象大学における教員の研究に資するものでコア・ラボラトリを利用することで教員に従来よりも高度な実験を可能にした。内容としては、デジタル・コントロール、生産工学、鋳造工学などがあり、各対象大学の環境と状況に応じて設置された。
SDPFプロジェクトで採用された研究でもコア・ラボラトリが利用され、実験設備の有用性が示されている。機材の設置が研究を刺激し「研究のトレーニング」となった。また、コア・ラボラトリを利用して地域の中小企業の試験測定を受託していることもあり、産学協同への将来的な発展にも期待がもたれている。
インドネシア国内でセミナー、ワークショップも開催している。期間は数日から2,3週間程度のものまで、年に30前後各種の研修が催された。1990年度から1997年10月末現在で計237(うち187のプログラムはHEDS対象大学で開催)の研修プログラムが実施された。参加者の合計は4,160名に及ぶ。各回の平均参加者人数は17.6名である。こうしたセミナーは大学間相互の研究の向上に貢献している。
6-2-3 プロジェクトの自立発展性
インドネシア側の自発的な大学運営への取り組みとしてTQM(Total Quality Management:管理運営能力向上)セミナーがあげられる。このセミナーはPMU(Project Management Unit)事務局長や学長経験者、教育文化省高等教育総局(DGHE)の関係者によってほぼ毎月行われている。このセミナーでは、DGHEの2005年までの高等教育基本指針に基づき、大学運営管理の指導が行われ、特に各大学でのボトムアップ方式の予算申請の方式を確立しようと指導している。また、HEDS対象外の大学からも、効率的運営などについてのノウハウの移転を求める声が出ている。
産業界や地方政府の要請による1989年度から1995年度までの研究実績は表6-7の通りである。周辺の民間企業や地方政府からの研究委託は増加傾向にある。SDPF支援やコア・ラボラトリなどを通じて、対象大'学の教員たちは研究活動に対する意欲や認識を深めつつあり、今後の研究体制の基盤は着実に整備されつつあるといって良い。今後、民間企業や地方政府からの研究委託の件数を増加させるよう努力すべきである。コア・ラボラトリを中心に研究活動を継続・充実することで周辺企業・地方政府に貢献することは重要である。これによって得られた資金をコア・ラボラトリの維持や拡充にあてることは自立発展性を高めることにつながるからである。
| 年度 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 合計 |
| 研究件数 | 1 | 5 | 6 | 13 | 12 | 37 |
本プロジェクト終了後、成果をいかに維持していくかは重要な課題である。成果が霧散してしまうことは避けたいものである。過去10年間の関係者の努力により、対象大学による地域経済への貢献を可能とする基盤がようやく整ってきた段階にあり、プロジェクトの効果、およびマクロな目標に対する成果はこれから少しずつ見えてくることであろう。他国との共同プロジェクトという難事業でありながら、多くの成果を挙げたプロジェクトとして、国際的な評価も極めて高い。教育分野の協力には限りがなく、どこをもって協力終了と判断することは困難なところである。期限がくれば一旦終了するとしても、小規模な技術協力を必要に応じ行い、成果の推移・継承をしばらく見ていくべきと思われる。
6-3 中学校校舎整備事業
6-3-1 プロジェクトの概要
インドネシアは1994年度から中学校教育も義務教育とし義務教育期間を6年から9年に延長、2003年度までに完全実施を目指している。1993年度の中学純就学率は約40%にすぎず、義務教育が完全実施されると約600万人の生徒が増加し、中学校施設の不足が予想される。
中学校校舎整備事業は、1996年度から1998年度までの3年間で全国27州のうち12州で606の中学校を新設(校舎・必要な施設の新設、教育用機材の整備)をモデル事業として行い、今後の中学校施設の向上に協力するものである。選定された地域は、西ジャワ、中部ジャワ、東ジャワ、リアウ、南スマトラ、ランポン、西カリマンタン、南カリマンタン、中部スラウェシ、南スラウェシ、西ヌサテンガラ、東ヌサテンガラの12州である(図6-4)。OECF約款額は208.8億円である(L/A調印は1995年12月)。

6-3-2プロジェクトの現状
インドネシアは初等教育の普遍化をおおむね達成し、中学校教育に教育政策の力点を移行している。高度な教育を持った豊富な人材を育成するためには中学校教育の普遍化はさけて通ることのできない重要な課題である。かつ、そのような人材育成はジャカルタのみならず周辺地域でも、またジャワ島以外の諸島でも行われるべきである。AFTAよる2003年の貿易自由化達成により国際競争が激しくなると予想され、こうした競争の中で発展していくためには人材開発の必要性はますます高まりつつある。インドネシアの各学校段階における教育投資の社会的収益率を比較した研究では、中学校教育投資の社会収益率がもっとも高いとされている。本事業は未だ実施段階にあり、現時点での評価ではその社会収益性を含めた事業効果を測ることは困難であるが、こうした中学校教育分野へOECFが借款を供与することは妥当であり、効果が期待されると言える。
図6-5は第6次国家開発5カ年計画期間中に新設される予定の学級数に対するOECFの寄与を示している。中学校校舎整備事業による新設学級は1996年度からであるが、それ以前にもOECFのSPL(セクター・プログラム・ローン)の見返り資金が校舎新築、教室増築に活用されている。その割合は、1994年度から1988年度にかけて、それぞれ11.3%,26.6%,17.7%,17.4%,12.8%となる。
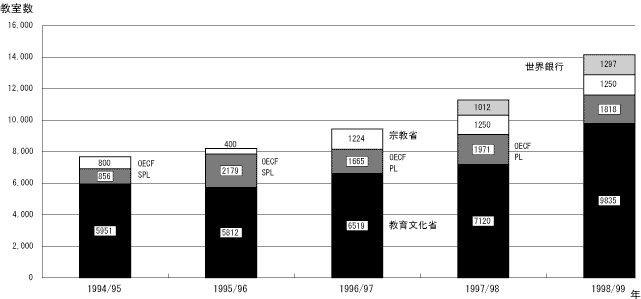
広域に606校の校舎を3年間で建設するという中学校整備事業の意義は大きい。しかし意義が大きいだけに事前調査やコンサルティングに十分な予算配分を行い、十分な体制を整える必要がある。606校の校舎を3年間という短期間で建築しなければならず、プロジェクト管理の困難さが予想される。初年度に185校、2年度に219校、3年度に202校の校舎の建築が予定され、それが12州という広範な地域に及ぶ。校舎新設は、新たに適切な土地選定を行わなくてはならず、用地の確保はインドネシア側の責任においてなされるべきことであり、1995年度にSPLで136校の建設実績があるとはいえ、計画遂行には強力な管理運営体制が要求される。そのため、本事業では、実施機関を補佐すべく事業管理のためのコンサルタントが雇用されている。
予定される中学校は1学年3学級程度の中学校であり、就学率向上の期待される地域をターゲットとしている。校舎を新しく建設するというのは意義ある援助ではあるが、用地の選定や業者決定に時間がかかり、3年間に効率的に建設を行うのは必ずしも容易ではない。仮に用地買収上の困難が今後発生するような場合には、既存の学校の校舎増築を行うといった柔軟な手段も考えられよう。建物の構成はおおよそ教室棟、教職員棟、実験室・作業室棟、礼拝棟、夜警用宿舎等であり、瓦葺きの屋根、白漆喰塗外壁にタイルを施した床が付置されている。数校の事例だけだが建物の建築水準は地域によって、また学校毎に随分と異なる。インドネシアの状況や地域の工業技術水準に合わせた工事設計であり、建築にあたった業者の力量の違いもあり、地域差が出てくるのは仕方がないといえよう。業者選定と調整のため作業の遅延もあるようである。 借款額208億8千万円のうち約165億円が校舎建設に、備品調達に18億円、教育機材に17億円が当てられている。学校校舎建設は1985年以前は教育文化省、以後は公共事業省の担当で実施されてきたが、行政簡素化のため、担当省が工事を行うという大統領の方針に基づき、1996年から再び教育文化省主導で工事を行うようになった。工事の仕上がりのチェックは公共事業省が行う事になっているが、両省の協力関係がかならずしもうまく行かない地方もあり、調整に手間取るケースもあったようである。視察した範囲では、本プロジェクトによる校舎は、公共事業省が建てた一般の中学校やSPLで建てられた校舎よりも全体に出来が良かった。工事を計画通りに行い、各地域で一定の建築水準を確保するためには関係省庁とのより緊密な協力、コンサルティング体制の整備が必要である。これは本事業を成功させ、後のインドネシア側による自立発展的な学校運営を導くためにも必要である。
建設が終了した一部の学校では、政府への学校登録が完了する前に生徒を収容し、授業を開始しているところがある。さらに、学校ができるということで、近所の学校に仮登録した生徒が転入してくるため、開校初年度からすでに2年生まで教室が埋まっている場合がある。そのような学校は人気があり、義務教育でありながら、定員の関係で選抜をして入学を許可しているという。このような学校の存在が日本の援助により増えることで地域社会の教育への関心を高めることができるならば、非常によい効果を生んでいると言える。606校すべてが、このように、入学希望者であふれるような状況になるかどうかは、プロジェクトが終了しないとわからないが、全体としては収容力の向上に大いに寄与すると思われる。
6-3-3 基礎教育への協力の取り組み
中学校校舎整備事業はインドネシアの基礎教育に対してわが国が大規模に行った初めての援助であるが、本格的な評価は、事業が完成しその効果が現れるまでは下しえない。今日世界的にみても基礎教育分野への国際援助・協力のニーズは高く、今後ますます量的にも質的にもさらなる拡充が望まれているところである。こうした潮流をふまえ、効果的な教育援助・協力を行うために、以下では一般的に基礎教育への協力の取り組みについて、いくつかの留意点を述べる。インドネシアにおいても、今後の取り組みにおいては、完全義務(普遍)教育化の推進のための中学校整備という援助効果を持続させるため、以下に述べるように建設後の学校施設の維持管理面での工夫や教育のソフト面でのインプットについて検討していくことも推奨されより。
まず第1はどの場所にどのような学校を建てれば良いかの十分な検討である。スクールマッピング等の手法を利用して、学校を維持するのに十分な数の児童生徒が確保できる場所に、適正な学校を建てなければならない。農村や山間の地に不釣り合いな立派すぎる校舎でも困る。用地選定や業者決定に時間がかかったり、用地選定ができても、用地買収予算や用地買収期間が限定されているため、スクールマッピングの成果を十分に生かせず、条件が悪いが安い土地を購入するほかないような事態も避けなければならない。教育機会の拡大が目的なら、校舎新築だけではなく、用地買収が困難な地域では既存の学校の校舎増築を行うなどといった柔軟な手段も考えられよう。
第2は地域における教育への関心を向上させ、地域住民が積極的に教育活動に参加したくなるような情勢を作ることである。インドネシアに限らず、広く途上国では地域間格差や民族・言語問題が大きな問題となっていることが多い。貧困に悩む地域の住民にとって、子どもを労働させずに学校へ送ることは、大きな決断であろう。まして、教授言語が地域言語と異なる場合には、学習が一層困難になるため子どもの就学をためらうケースも予想しうる。しかしこうした忌避感は国家が経済的・社会的に発展していく際の大きな障害となってしまう。地域において教育への関心を高めることがこのような問題の解決に対する糸口となるであろう。そのためにはこうした地域の親たちに教育とは子どもの幸福を実現するための重要な道具であるという認識が広まることが大切である。地域住民の参加は校舎の適性度、工事にも目配りを与えてくれる。
第3は建設した施設、設備の維持管理についてである。元気のよい生徒が大勢いる中学校となれば、何かにつけ窓ガラスが割れたり、内壁などに穴やヒビが入るなどということが起こりうる。これらを放置せずに、学習者、教職員、ときには父母が適時、適切に対処・補修することが、新設校舎の質を落とさず、学習者にとって魅力的な環境を維持することにつながる。そのためには生徒、父母、教職員に「自分たちの学校なのだから、自分たちで維持管理する」という意識がどうしても必要である。こうした意識醸成のためには、住民参加を生み出すような建設方法なども柔軟に検討されても良かろう。
メンテナンスには技術水準の問題もある。学校は長期的に使用するものであるため、メンテナンスを考慮して建設しなければならない。メンテナンスを容易にするには、地元で調達可能な材料や技術で建設するという、構造や材料の問題だけではなく、費用や労力の負担を含めた、メンテナンスをたやすくする仕組みをはじめから作っておかなければならない。地域住民の計画段階からのプロジェクトヘの参加を促すことは、完成後の学校への就学・保全の意識を持たせる点からも重要である。
第4はハード・ソフトの両方から総合的に援助案件効果を高める努力である。学校を建てることは教育機会を高めたり、教育の質を向上させる手段ではあっても、それ自身が最終目標にはならない。学校を建てただけで、児童・生徒が大勢集まってくるわけでも、立派な教育が行われる訳でもない。施設・設備といったハードだけではなく、教育の質の改善といったソフトの部分も含めた、総合的な援助を目指さなければ、援助の効果は高まらない。今日まで、青年海外協力隊、個別派遣専門家などを中心として、理数科教育や教員養成などにおいて教育効果を高める協力が多数なされてきた。また、国際協力としては新しい分野であるが、日本国内において地域における教育力を充実させることに従事してきた専門家もいる。校舎建設や設備・施設増強などの案件にそのような人々に参加してもらうことで、ハード・ソフトの両方から案件効果を高めることが可能であろう。
第5は効率的な援助を行えるように、プロジェクトの管理体制を充実させることである。特にプロジェクトサイトが点在する場合には、現地政府プロジェクトチームの組織作り、能力向上など、プロジェクトの規模に見合った管理のシステムを構築、さらに整備していくことが必要である。その為に費用がかかったとしても、全体としては効率的な援助が可能となろう。日本の援助はよりソフトな部分、よりキメの細かい対応が求められる部分へ移行しつつある。しかし、より細かい対応が求められながら、マンパワーは不足しているのが現実である。海外、現地を問わずコンサルタントの効率的活用が不可欠であろう。

