4. 貿易研修センター(IETC: Indonesia Export Trading Centre)プロジェクト
4-1 プロジェクトの概要
4-1-1 背景と経緯
インドネシアは輸出に占める石油・ガス製品の割合が非常に高かったため、近年の石油価格下落により財政逼迫を招いた。打開策として非石油・ガス製品の輸出促進が優先課題とされ、そうした政策の結果、1987年に初めて非石油・ガス製品が輸出の50%を超えた。
部門別GDPのシェアの推移を見ると、農林水産部門・鉱業部門が低下し、逆に製造業部門・商業部門が上昇している。1989年から1993年においては農林水産部門が20.4%から17.5%へと減少したのに対し、製造部門は18.5%から21.0%へと増加した。同国政府が石油・ガス依存の経済構造からの脱皮を目指して続けてきた努力が実り、製造業が経済の中心となりつつある。
こうした中で政府貿易関係部門および民間輸出企業における貿易実務の促進に必要な知識・経験を有する人材の不足ならびに輸出産品の検査技術・品質検査能力の低さなどから広く輸出促進に寄与する人材を育成することの必要性が認識された。
こうした状況を背景として、インドネシア政府は、輸出貿易実務に関する計画的研修による人材の育成、輸出産品の検査技術および品質検査技術の向上、さらに産品展示手法の向上等を図るため「貿易研修センター」設立を計画、1985年6月、日本に協力を要請した。日本政府は1987年1月に事前調査団を派遣し、これを踏まえ1988年8月に実施協議調査団を派遣、R/Dに署名した。1988年9月2日から5年間(1993年9月1日まで)の予定で貿易研修センター協力事業がプロジェクト方式技術協力によって実施された。また、無償資金協力で研修センターが建設された(供与額20.24億円、1989年5月インドネシア側へ引き渡し)。
1993年の国際協力事業団による終了時評価において、さらなる技術移転が必要と判断された貿易研修、展示研修、商業日本語研修の3分野に関しては、1994年から1995年までフォローアップ協力が行われた。
また、1997年3月から当センターを拠点として国際協力事業団により「貿易セクター人材育成計画」が実施されている。
4-1-2 組織
IETCが掲げている目標は以下の4つである。
- (1)インドネシアにおける輸出貿易に係わる知識と技術、能力の向上を図る。
- (2)中小企業家を量的に増やし、輸出企業へと成長させる。
- (3)輸出業者の製品デザインと品質検査の能力を向上させ、国際市場で競争しうる力をつける。
- (4)受動的な輸出業者をより能動的な輸出業者へと成長させる。
IETCの組織は図4-1のように事務部(Administrative Division)、事業部(Operational Division)、教務部(Instructors)の3部局に分かれ、それぞれ必要な職員が配置されている。なお、1997年段階では組織改革により、訓練振興・協力部が新設されている。
IETCの研修プログラムは図4-1の組織図が示すように、貿易研修、展示研修、輸出・品質管理研修、商業日本語研修の4分野にわたり実施されている。
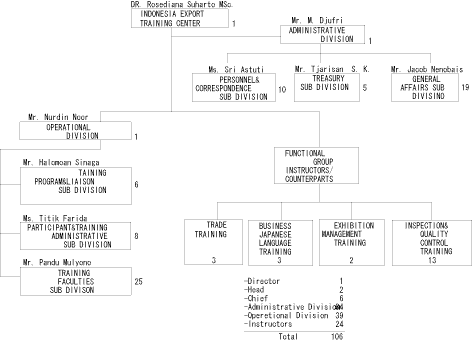
4-2 評価
4-2-1 妥当性
IETCは非石油・ガス製品の輸出増大を担う人材の養成を目標とし、貿易研修、展示研修、輸出・品質管理研修、商業日本語研修の4分野の研修コースを設置した。これは工業製品輸出の拡大を図るインドネシアの開発目標にかなうものであった。貿易実務、インドネシアの主要輸出品である繊維製品、木材・ラタン家具等の品質確保のため、品質検査コースを持ったことは適切であったし、これら製品の国際競争力向上に貢献した。しかし、国際ビジネス環境は日々変化しており、今後とも国際競争力向上をはかるためにはビジネス環境の変化を見て対応を図っていく必要がある。
4-2-2 達成度
協力事業における達成度とIETCのコース運営状況に関する達成度について見ることにする。まず協力事業についてであるが、優秀な専門家の確保は、IETCプロジェクトに限らず難しいが、協力期間においては計画に基づき長期16名、短期専門家延べ22名の派遣専門家の計38名が派遣された。IETC側はカウンターパートヘの継続的指導という点からは長期専門家が望ましいと考えているが、長期間専門家を確保するには日本側の人材確保のむずかしさもある。本プロジェクトでは短期専門家で対応しうる部分へは、短期専門家を派遣し、現実的な協力体制がとられたといえる。どの専門家も現地カウンターパート(以下C/P)とのコミュニケーションは良好で、技術移転が図られた。
商業日本語については、最後の専門家が派遣されるまではIETCオリジナルのテキストは無かった。この最後の専門家は教材開発を意欲的に行い、現地C/Pから高い評価を受けている。C/PであるIETCの講師は日本滞在期間が短かったり、あるいは日本からの専門家派遣が困難であったりという状況にも関わらず、よく努力している。日本語コースを修了した日系企業現地社員と面接したが、「指導は厳しかったが、コース参加以前は全く日本語が理解できなかったにもかかわらず、現在は多くの人々の前で日本語でスピーチできるほどになった」と研修の成果を評価していた。コース修了時、参加者たちは日本語で作文集を作成するが、きれいな文字で漢字も混ぜ、短期間の研修とは思えないほどの作文集となっていた。
C/Pのコース運営状況は次の通りである。表4-1は最近時点までの各年のコース別参加者の推移を表わしている(本プログラムの協力期間は1988年9月2日~1993年9月1日であるが、1994年1月31日~1995年9月30日までフォローアップとして協力期間が延長された。現在は新たに「貿易セクター人材育成計画」が1997年3月1日~2001年2月28日までの予定で実施されている)。1990年以降、参加者は順調に増大している。特に1992年以降は安定して各年1,000人を超える研修員が常に参加している。貿易研修の人気が特に高く、セミナーと貿易研修の合計で安定して700人を確保している。それにつづく人気の高いコースが品質検査コースである。最近では安定して300人前後が参加している。
| コース | 88/89 | 89/90 | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 合計 |
| 貿易 | - | - | 415 | 410 | 753 | 703 | 717 | 741 | 539 | 592 | 4,870 |
| 品質 | - | - | 223 | 157 | 295 | 403 | 373 | 528 | 355 | 170 | 2,504 |
| 展示 | - | - | 141 | 167 | 212 | 231 | 185 | 120 | 113 | 50 | 1,219 |
| 日語 | - | - | 61 | 47 | 27 | 27 | 101 | 79 | 56 | 54 | 452 |
| 中語 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| セミナー | - | - | 169 | 97 | 128 | 20 | - | - | 240 | - | 654 |
| 合計 | - | - | 1,009 | 878 | 1,415 | 1,384 | 1,376 | 1,468 | 1,303 | 884 | 9,717 |
(貿易研修センター協力事業:1988年9月2日~1993年9月1日、フォローアップ:1994年1月31日~1995年9月30日)
(貿易セクター人材育成計画:1997年3月1日~2001年2月28日)
IETCにおけるトレーニングの、開始時から1997年10月までの州別の参加者数は表4-2の通りである。地域別に見ると、貿易研修が一番人気であるのはどの地域でも変わりない。参加者はジャワ島からが圧倒的に多い。セミナーの開催回数もジャワが圧倒的に多く、スマトラ、スラウェシではそれぞれわずかに1回と3回である。地方でのセミナー開催はIETCの直接の目的ではないが、地方での啓蒙活動も「輸出貿易を振興できる層の拡大」との目標のもと、将来重要になると思われる。
| 州 | セミナー 貿易 品質 展示 外語 計 | % |
| スマトラ | 1 745 328 204 15 1,293 | 13.3 |
| ジャワ | 650 3,125 1,743 810 455 6,783 | 69.8 |
| カリマンタン | 3 266 120 109 0 498 | 5.1 |
| スラウェシ | 0 318 159 86 0 563 | 5.8 |
|
バリ、 その他 |
0 390 114 76 0 580 | 6.0 |
中小企業からのIETC受講者の中には、インドネシアの財団から受講料に対し助成を受けている人もいる。IETCは公的な機関であり、受講料は民間団体が開催する同種のセミナーより安く設定されてはいるが、インドネシアの経済水準から考えれば決して安いものではない。どの程度の中小企業が受講料を実際に自己負担しているかの資料はないが、中小企業に対してより一層の門戸開放のための努力が求められていることは示唆できる。
なお、貿易研修センター協力事業の終了時評価調査団(1993年6月)は、貿易研修、展示研修、商業日本語研修については技術移転に不足が認められること、国際環境の動向、ニーズを反映したセンター運営や体制づくりの面で、まだ日本側が経験・アドバイスを与える余地があることからフォローアップ協力の必要性を指摘、1994年1月31日から1995年9月30日までフォローアップ協力が実施された。
フォローアップの後、例えば展示研修部門ではビデオ制作コンテストに入賞するC/Pが出るなど着実な人材養成がなされたことをうかがわせる成果が出ている。
4-2-3 効率性
IETC側は日本人専門家の貢献を高く評価している。特に輸出検査部門に関しては、技術移転が順調に進み、C/Pが専門家の指導や日本での研修を通じ、現在は自らがトレーナーとして能力を発揮している。ただ、貿易研修部門などにおいては、実用的な技術移転をめぐり、どのような内容項目から指導を開始するかで、専門家とC/Pとの間で意見が若干相違する場合もある。
C/Pは本来商業省貿易担当職員であり貿易実務の知識・経験は十分とは言い難い。したがって企業の経営者や管理者が参加する経営コースで自信を持って講義したり、具体的な質問に的確に答えることはまだ難しい。このような認識のもと日本人専門家は、当初貿易実務全般の知識をC/Pに移転することからはじめ、研修コース参加者のニーズに応えるべく、特定産品のマーケティング手法、国際貿易の潮流といった、専門的な知識の移転に重点を移した。
しかし、C/Pが人事異動などで入れ替わることもあってか、派遣された専門家はその都度基礎的な指導から開始した。そのため継続して働いているC/Pに対しては基礎的・理論的な面での指導が重複するという事態もあった。そのため、そうしたC/Pは自分はすでに基礎的な学習・研修は終え、中級レベル以上の域に達しているのだからさらに高度な学習をしたいと希望したケースもあった。
このことは、技術移転を行う際、指導を受ける側にも実力や知識に違いがあることを前提としなくてはならない場合があることを示している。特に協力期間中あるいは継続期間中に新たな専門家が赴任するとき注意を払う必要がある。
日本への研修員の派遣(1989年から1995年まで)は、貿易研修8名、品質検査17名(木製家具4名、繊維6名、ゴム製品3名、冷凍・缶詰製品4名)、展示研修5名、商業日本語3名、マネジメント3名、視聴覚1名、集中日本語1名の計39名となっている(1993年9月までは31名)。日本での研修は目標を達成したが、ただ、配置されたC/Pの約半数がその後人事異動、転職等で入れ替わり、計画的・系統的技術指導の効率性の障害となった。
供与機材は良好に管理・運用されている。ただ、スペア部品の入手が困難で、半年以上入手できなかったケースがあった。
4-2-4 効果
貿易研修センターがもたらす産業界へのインパクトは今後とも高まっていくと思われる。フォローアップまでが終了した1994年度段階で、6,062人が、さらに1997年10月までに累計で9,717人が同センターのコースを受講またはセミナーに参加している。うち民間企業からの参加が協力期間終了時(1993年)までに3,722名(全体の61.4%)、さらに1997年10月までに累計で6,266名(全体の64.5%)にのぼっている。地域別に見ると約70%がジャワ島からの参加であるが、13%がスマトラ等、カリマンタン、スラウェシ等からも約5%ずつ参加が見られる。IETCは日本人専門家の協力を得てジョクジャカルタ、メダン、ウジュバンダンなど地方都市での巡回指導、セミナーを計画・実施してきており、地方展開にも取り組んでいる。
また、IETCのコースは着実に受講者およびその派遣元企業の評価を得ているとみられ、幾つかの企業がその従業員をセミナーなどに数回にわたり派遣している。繰り返し利用するのは、その活動を評価しているからである。また、IETCが行ったトレーニング終了後の満足度調査では、80%以上の修了者がコースについて満足であると回答している。
複数回従業員をコースに派遣してきた政府機関・企業の例として、地方投資調整委員会、商工業省下の公営企業、農業省下の公営企業、鉱物・エネルギー省下の公営企業、アストラ財団、三菱自動車、グレート・リバー・インダストリーズ、アラス・コモド・繊維会社、などがあげられる。
4-2-5 自立発展性
本プロジェクトは全体として目的を達しつつある。特に輸出・品質管理研修における技術移転はほぼ順調に進み、C/Pは自力で各研修コースの講義を運営することができるまでに成長している。一方、激変する国際経済環境を理解しつつ企業のニーズに合ったセミナーをタイミング良く企画立案・実施することは難しく、この点での技術移転が難しいことは理解できる。
センター運営にかかる予算状況については、各研修コースが軌道に乗りつつあることを反映して、非課税収入は順調に増額しつつあり、5年間で1.5倍となった(表4-3参照)。通常予算も順調に伸び、IETCの財政基盤は固まりつつある。とはいえ、機材の維持管理費等政府の予算なしにはやっていけるほどの力はまだない。今後は市場の動向を敏感に先取りしてコースを充実させ、自己収入の拡大をさらに努力することが必要である。
| 年 | 通常予算 | 開発予算 | 非課税収入 | 合計 |
| 1992/93 | - | 900,000 | 473,900 | 1,373,900 |
| 1993/94 | 436,168 | 950,000 | 339,179 | 1,725,347 |
| 1994/95 | 680,727 | 992,722 | 450,000 | 2,123,443 |
| 1995/96 | 814,520 | 989,100 | 500,000 | 2,303,620 |
| 1996/97 | 959,362 | 1,072,236 | 550,000 | 2,581,598 |
| 1997/98 | 1,023,859 | 1,777,761 | 600,000 | 3,401,620 |
政府は1980年代以降石油・ガス依存体質から脱却をはかり構造調整につとめてきた。特に80年代後半からは繊維などを中心とする労働集約型産業へのシフトを行ってきた結果、繊維の輸出は拡大した。工業製品輸出が拡大してはいるが、インドネシアの産業構造は、生産性の高い比較的大規模な事業所と、数の上では圧倒的大多数をしめる零細な家内工業とに2分している。1996年の時点で100人以上の大規模企業および20人から99人までの中規模企業は約17,000社、5人から19人の小規模企業は約125,000社、家内工業(4人以下)は約2,350,000社といわれるように圧倒的に家内工業的小規模企業が多い(『インドネシア貿易セクター人材育成計画協力事業実施協議調査団報告書』JICA 1996年)。そして、大企業を支えるサポーティングインダストリーといったような構造が出来ておらず、裾野産業は未発達である。総生産額の約90%を大規模・中規模企業が占めている。中小企業が、インドネシア輸出総額460億米ドルに占める割合はわずか8.3%にすぎない。
一方ではASEAN自由貿易地域(AFTA)が、2003年までに電子などの15業種の製品のASEAN域内関税を5%以下にし、数量制限、非関税障壁を撤廃すべく動き出している。AFTA後は企業は自由競争にさらされ、それぞれの企業は生き残りを賭け生産性の向上に努めなければならない。中小企業にとってはますます厳しい時代となる。現在実施されている第6次国家開発5カ年計画(1994/95年~1998/99)でも、中小企業の資質と役割の向上を開発項目としてあげている。
したがって中小企業の貿易分野における人材育成は重要な課題となる。こうした状況をのもとでインドネシア政府が新たに協力を要請したのが、「貿易セクター人材育成計画」であり、「貿易研修センター」の新たな発展となるものである。
日本政府は1995年9月に事前調査団、1996年8月に長期調査員を派遣し、要請の内容、先方の実施体制、技術移転内容などについて調査を実施した。それらを踏まえ、1997年3月から2001年2月28日までの4年間を期間として「貿易セクター人材育成計画」への協力が実施に移された。協力の目標は「IETCが、インドネシアの中規模クラスを中心とする企業に対し、貿易に必要な知識・経験・ノウハウを提供する研修コースを策定することができるようにする」ことである。
1993年のIETC終了時評価では、貿易研修等でC/P自身がコースを組み立てていくには技術移転が不十分と判断された。そのためフォローアップ協力による技術移転にて援助を継続したが、変化する経済環境の中で必要な貿易実務をC/Pが受講者に教えられるようになるには援助される側の継続的努力と援助する側の継続的指導が必要である。研修というソフトな部分を持った協力においては知識の継続的供給(協力)は不可欠と思われる。自立発展性という観点からは、すべてをインドネシア側で出来るようになることが好ましいが、センターの運営はインドネシア側が自主的に行えねばならないにしても、日々変化する経済の中での「貿易」に関するソフトな知識、実務は継続的に協力していくことが協力の成果を実りあるものにすると思われる。こうした点で、IETCへ新たに「貿易セクター人材育成計画」協力が付加されたことは好ましいことである。
内外のニーズに即応できる研修能力をつけセンターの拡充が図らねばならない。品質管理のセクションでは、当初のコースは木工・ラタン製品、繊維・衣料品、ゴム・ゴム製品、冷凍・缶詰製品だけであったが、現在では玩具のコースが新設されている。インドネシアの輸出傾向に併せた動きということができる。
また、当初、商業日本語としてスタートしたコースは、1997年から商業中国語が始まり(1997年10月まで18人が受講)、英語コースも開講するなど、ビジネス外国語コースとして発展させようとしていることがうかがえる。
商業日本語は、C/Pの意欲の高さや外国語習得ブームなどから考え、適切なフォローをすることによって発展する余地は大きい。ただ、商業日本語のC/Pは業務終了後日本語のネイティブ・スピーカーとの接触が無く、日本語能力自体を維持することに困難を感じている。IETC側がC/Pを留学させるなど何らかの手段を講ずることが求められる。日本側としても短期専門家の派遣や短期研修などのフォローアップが必要である。
IETCは1998年に開催予定である大規模なマネジメント・セミナーの準備を進めている。そこでは地方からも多数の参加が期待されている。また、遠隔地にいる研修員のための遠隔学習システムの一環として、貿易業務に関するCD-ROMも開発している。今後開発を進めるためには民間団体、経済団体など民間セクターとの協力により市場のニーズに合わせていくことが必要であると認識している。そのような共同作業の中からニーズを発掘し、他の分野にも事業を広げていきたいという意向を持っている。さらに、修学年限1年のD1プログラムを開設する計画もあり、より総合的な貿易研修の機関として、IETCは自立的に発展する意向を持っている。
商工業省はIETCの使命は重大であり、その提供サービスについては目下のところ良好と判断している。さらに同省は東部インドネシアの産業開発に寄与することを目標として、IETCと似た教育訓練機関を東部1(ウジュンパンダン)に設立することを計画しているが、このことはIETCの活動を高く評価している証拠と言えよう。

