2. インドネシアにおける教育・人材開発の現状と改革の動向
2-1 学校制度
インドネシアの教育制度は、日本と同じ6-3-3制で、教育文化省が所管する小学校(SD:Sekolar Dasar)6年、中学校(SLTP:Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)3年、高校(SM:Sekolah Menengah)3年の制度が基本である(図2-1)。小学校と中学校の9年間が基礎教育の期間と考えられている。日本と違っているのは、教育文化省以外にもそれぞれ関連の学校を所管している省庁があることである。その中で最大なのは教育文化省所管の学校体系と平行して初等段階から高等段階まである宗教省所管のイスラム系学校である。
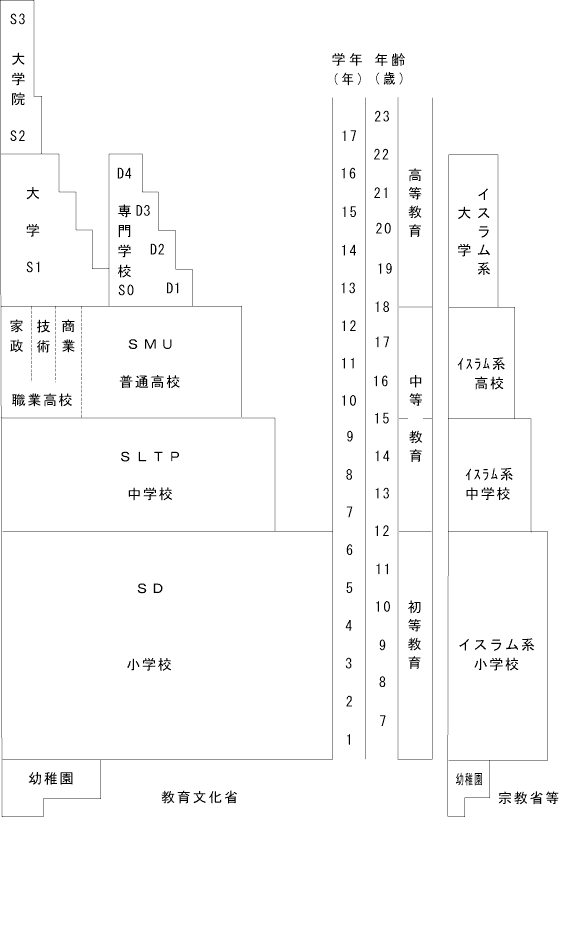
教育文化省所管学校と宗教省等所管学校を合計した児童・生徒数に占める教育文化省所管学校の児童・生徒数の割合は、1994年度で、それぞれ小学校段階86.7%、中学校段階81.8%、高校段階88.4%となっている。以下、学校数、在籍者数共に多い教育文化省所管の学校を中心に説明する。
2-1-1 初等教育
初等教育は幼稚園教育と小学校教育からなる。幼稚園教育の普及は急速に進んでいるというものの、まだ十分ではない。1995年度の教育文化省所管幼稚園幼児数を同年度の小学校1年生で割った値は34.3%にしかならない。幼児の99.5%は私立幼稚園に在籍している。
小学校は6年間の義務教育を提供する。標準的な就学年齢は7歳とされ、入学の優先順位は高いが、6歳からの就学も法律的に可能である。計算上の学齢は7~12歳とされ、純就学率(7~12歳の学齢期人口のうち、小学校に就学している児童の割合)は、宗教省所管のイスラム系小学校、学校外教育プログラム在籍の児童も含め、1993年度で93.5%を達成し、1998年度には94.0%になることが第6次国家開発5カ年計画で(1994/95年~1998/99年)計画されている。
純就学率があまり増加しないと考えられているのは、教育状況が改善されないからではない。主として、6歳で小学校に入学する者の割合が増加している事が就学率の計算に影響することによる。例えば、1995年度の教育文化省所管の公私立小学校入学者の48.1%は6歳児で、41.9%の7歳児よりも多い。全児童の内、7~12歳の者の割合は83.5%に過ぎない。小学校児童には6歳児や留年などによる13歳以上の過学齢児童も数多くいるところがら、全児童数を学齢人口で割った粗就学率は1993年度で109.9%になる。公私の比較では、教育文化省所管小学校児童の内、92.7%は公立小学校に在籍していることが示すように、主として政府の力で就学率の向上が図られている。
人口統計や学校統計には不備も多く、本当の就学率がいくらであるかを推定するのは容易ではない。1995年に行われた中間国勢調査には年齢別の就学状況が記されている。それによれば、7~12歳の就学率は94.6%であるが、この中には中学校在籍者も含まれていることから、上記の小学校純就学率の推定値はほぼ正確であると考えて良い。また、一度も学校へ行ったことがない者の割合は10~14歳の年齢区分で1.1%と最も低い。すなわち、全く学校に行ったことがない者は極少数で、留年や退学が防止できれば、ほぼ完全な就学を達成できることを示している。
小学校のカリキュラム作成や教員養成は教育文化省が担当しているが、小学校の建設や運営は地域住民に最小限必要な基本的サービスを提供する趣旨から、内務省下の地方政府が担当している。児童数が減少している地区では、すでに小学校を廃校にし、同じ内務省が所管している保健所などに転用している所も出ている。
2-1-2 中等教育
中等教育は前期中等教育(中学校)3年間、後期中等教育(高校)3年間に分けられる。前期中等教育は基礎教育に含められ、1994年度から義務教育化された(2003年度までに完全実施を目指している)。ただし、ここでいう義務教育化とは法律でそのように定める事であり、子どもを就学させない親や学校を作らない地方自治体に対する罰則規定がある訳ではない。精神論的な努力目標と言う方が当たっている。
(1) 中学校教育
中学校段階には普通中学校(SMP)の他に、職業教育を行う技術学校(ST)や家政中学校(SKKP)などが存在したが、1994年度からの義務教育化に伴い入学を停止し、年次進行で廃止され、中学校は普通教育を行う機関となった。
中学校生徒の学齢は13~15歳で、純就学率は宗教省所管の中学校なども含め、1993年度に40.2%、1996年度に53.0%と推定されている。粗就学率はそれぞれ54.4%、68.7%と推定されている。1994年度の教育文化省所管の小学校6年生の内卒業した者は95.3%、さらに、1995年度に中学校へ進学した者の割合は卒業生の71.3%にすぎない。公私の比較では、教育文化省所管中学校生徒の内、67.4%は公立中学校に在籍していることが示すように、小学校ほどではないが、公立の役割は大きい。義務教育化に伴い、公立学校の新設や学級の増設が計られ、公立の割合は増加している。
就学率は急速に上昇しているとは言うものの、1996年度の純就学率が最高のジャカルタ特別区は78.1%、東ティモール州は31.3%、粗就学率はそれぞれ107.4%、43.9%であるなど、地域間格差は大きい。量的な拡大が質的な充実を伴っているとは言えないことも問題である。卒業時の全国学力試験は標準化されていないため、年度間の比較は困難であるが、同一年度内での学校間比較、地域間比較は有効である。学校単位の平均点が10点満点で4.5~5.5の学校が45.8%、4.5以下の最低ランクの学校が16.9%(1995年度)などとなっており、質的な充実も急務である。しかも、4.5以下の最低ランクの学校の割合がベングクル州では55.4%、東ティモール州では51.0%であるなど、質的な地域間格差は量的な格差以上に大きい。
(2) 高校教育
高校生徒の学齢は16~18歳である。粗就学率は宗教省所管の高校なども含め、1993年度に33.9%、1996年度に38.0%と推定されている。州別には、最高のジャカルタ特別区は90.6%、最低の東ヌサテンガラ州は26.4%であるなど、中学校以上の地域間格差が見られる。1994年度の教育文化省所管の中学校3年生の内卒業した者は94.5%、さらに、1995年度に各種の高校へ進学した者の合計割合は卒業生の91.3%である。普通高校(SMU)の他に商業高校、技術高校、その他の職業高校に分かれている。従来高校レベルに置かれていた小学校教員養成のための師範学校と体育師範学校は、高等教育レベルに移され、1988年度入学者の卒業を待って廃止された。
公私の比較では、教育文化省所管高校生徒の内、54.3%は私立高校に在籍していることが示すように、私立の役割は大きい。インドネシアでは、一部の学校を除いて、一般に私立よりも公立の方が社会的評価が高い。今後高校進学者が増えれば、公立高校を増設する必要が増すが、私立との調和をどのようにはかるかが問題となる。
2-1-3 高等教育
高等教育機関は学術的教育を行い、学位を出せる機関(大学)と、専門的・職業的教育を行い、終了証書のみを出せる機関(専門学校)の2つに区分される。学術的教育を行う大学は最低就学年限が4年(旧制度では5年)で、卒業生はサルジャナ(学士)の学位を得る。さらに大学院へ進学することにより、マギステル(修士)、さらにドクトル(博士)の学位を修得できる(以下、S1、S2、S3と略記)。一方専門的・職業的な教育は就学年限によって、ディプロマ1~4の課程に分かれる(以下、D1、D2、D3、D4と略記。ディプロマ課程全体はSOと略記)。
高等教育機関の種別は、総合大学(Universitas)、専門大学(Institut)、単科大学(Sekolah Tinggi)、ポリテクニック(Politeknik)、アカデミ(Akademi)の5つである。最初の3つまでが学術的教育および専門的・職業的教育を行う機関であり、後の2つが専門的・職業的教育のみを行う機関である。一つの大学の中にS1課程とSO課程が存在する場合が多い。
高等教育機関の数は毎年急増しているため、正確な数はわからない。教育文化省所管の高等教育機関では国立が77校(1994年度)、私立が1,293校(1996年12月)とされている。この他に、宗教省所管の高等教育機関で、国立が14校(1991年度)、私立が309校(1991年度)あるなど、国の経済力に比べてその数は極めて多い。小規模私立校が林立しているためである。1993年度で全学生数は227万人、学齢人口を19~24歳とした時の粗就学率は10.5%と計算されている。学部にもよるが、S1課程は基本的には4年間で終了できるはずであるが、現実には従来が5年課程であったことの影響もあってか、平均して1.5年ほど卒業までに余分に時間がかかる。内部効率が悪いわけであり、工学部など実験設備などに制約がある学部では、留年者の存在が入学者の拡大を圧迫している。
国立高等教育機関の数は長い間50以下に押さえられてきたが、1994年度から国立大学に付置されていたポリテクニックが分離独立する形で急速に数が増えた。しかし、分離独立すればそれまで頼っていた大学の物的、人的なインフラが利用しづらくなることから、最近では分離独立の動きも収まってきた。このように、高等教育機関の増大は主として私学の増大に依存し、1975年度には教育文化省所管の高等教育諸機関全学生の39.7%が私学に在籍していたものが、1994年度には76.3%が在籍しているなど、私学比率が極めて高くなっている。
私立高等教育機関の場合(初等、中等教育も同様である)、各コースごとにその課程認定の程度によって、「登録」、「認定」、「同等」の3カテゴリーに分けられる。カテゴリーの基準は「同等」は国立と同じ水準、「認定」や「登録」は単位認定試験のすべてを独自に行うことはできず、政府のコントロールのもとに行わなければならない、等である。この制度は私学の教育水準のコントロールのためにあるが、逆に、「登録」であれば比較的容易に設立ができ、実績を積んで、「認定」、「同等」と変更していくことになる。
しかし、これでは国立高等教育機関の水準維持が図れないことから、大学課程評価庁が大学評価を行う制度が導入された。1996/97年の評価結果は1997年11月に発表されたが、国立、私立を含めた「同等」レベル、209大学のS1課程1,364コースのうち、不適当と評価されたコースは国立を含めた21大学37プログラムに及んだ。学生数の急速な拡大が教育の質の維持を困難にしている。
1995年5月時点で、国立の大学、ポリテクニック教員4万2,778名の学歴を見れば、S1所持者は68.7%であるのに対し、S2所持者は22.8%、S3所持者は6.7%、SO所持者は1.8%である。全体としての学位が低いことと同時に、S2、S3所持者が分野、大学によって大きく偏っていることが問題である。インドネシアの高等教育が今後自立発展するためには、大学院を充実し、教員の自給を図る事が必要であるが、そのためには、まず現在の教員の質的向上を計ることが必要とされている。
2-2 教育開発計画
教育分野における開発計画は、国家政策大綱(1993年3月)においてその方向性が、第2次25カ年計画(1994/95年~2018/19年)において具体的な目標が示されている。さらに、第6次国家開発5カ年計画(1994/95年~1998/99年)が第2次25カ年計画の第1期として位置づけられ、目標を実現するための具体的な施策が述べられている。
2-2-1 国家政策大綱
1993年3月に発表された国家政策大綱ではパンチャシラ(国家5原則)と1945年憲法の基本理念に基づく国民教育の在り方を述べた上で、次のように今後取り組むべき最優先課題を掲げている。
(1) 9年制義務教育の実施
(2) 教育機会の均等化
(3) 職業機会の充実と質の向上
さらに教育分野の開発は他の分野の開発と調和して発展するべきであり、国家の開発段階に応じて必要とされる人材育成を行うとの視点から、特に産業界との協力関係、国家労働力計画との連携強化にも言及している。
2-2-2 第2次25カ年計画(1994/95年~2018/19年)
国家政策大綱の方向性に基づき第2次25カ年計画では次のような目標を掲げている。
(1) 9年制義務教育の実現
第2次25カ年計画第3期目の第8次国家開発5カ年計画の最終年度(2008/09年)までに15年かけて9年制義務教育の完全実施を目指す(この計画は1996年の大統領令により修正され、目標年度を5年間短縮して、第7次国家開発5カ年計画の最終年度(2003/4年)までに達成することとなった)。さらに後期中等教育、高等教育レベルにおいても就学率を向上させる。
(2) 教員の質の向上
小学校の教員については最低D2の資格、中学校、高等学校の教員については最低S1の資格、高等教育機関についてはS2とS3の資格をもつ者の割合を80%とする。
(3) 非識字問題の根絶
最終年度までに非識字問題を完全になくす。
2-2-3 第6次国家開発5カ年計画(1994/95年~1998/99年)
第2次25カ年計画の目標にそって、第1期目となる第6次国家開発5カ年計画では、公正な教育機会を配分するため、粗就学率を各教育段階において表2-1のように向上させることが目標とされている。これらの数値は、目標年度に小学校への就学がほぼ完全に行われるという予測に基づいている。これはとりもなおさず小学校卒業者が増加するということであり、中学校の受け入れ能力が増強されなければならない、とある。
| 教育段階 | 達成値(1993/94年)(%) | 目標値(1998/99年)(%) |
| 初等教育 | 109.9 | 114.9 |
| 前期中等教育 | 52.7 | 66.2 |
| 後期中等教育 | 33.2 | 40.5 |
| 高等教育 | 10.5 | 12.8 |
注 : 文章中の数字がこの表の数字と異なる場合がある。文章中の数字は教育文化省等の最新の資料から引用している。いずれも推計値である。作成時期から考えて、文章中の数字の方が新しい推計値と考えられるが、表2-1は原表のままとした。
開発計画もこの中等教育(特に前期中等教育)強化への意気込みを、9年制義務教育の確立という視点から前面に打ち出している。同計画ではこの義務教育を「キーコンポーネント」であると位置づけ、政府と人民の能力にあわせて実施させていくことを唱っている。あわせて、授業料を徐々に廃止し、奨学金プログラムを導入して成績優秀で経済的に困難な境遇にある生徒の費用を補助する計画のあることを記している。さらに、この9年制義務教育制度を確かなものにするために、施設・設備の増強を既存校舎のリハビリテーションと同時に計ること、僻地の学校には、学校長及び教員のための宿舎も完備するなど、職員のための配慮の必要性も記されている。
2-2-4 目標の完成をめざして
現在教育分野の中で優先順位の最も高い中等教育の充実拡充については、図2-2に示すように、中学校、高校とも、計画値を上回る勢いでその就学率を上げている。特に中学校の充実は目を見張るものがある。

小学校から大学まで、ストレートに進める者は多くない。学年の途中で留年・退学したり、学校段階を上がるところで進学を断念したり、入試に失敗したりする者は多い。しかし、最も多くの者がつまずくのは、小学校から中学校への進学段階である。中学校義務教育化政策が成功すれば、このつまずきがなくなるが、中学校の義務教育化は急速に高校進学率の増加、高等教育機関への進学率の増加をもたらすことは明らかである。
したがって、中学校教育の普遍化を政策課題とするのであれば、それに引き続き高校、高等教育の拡充にも目配りをしなければならない。外国からの援助にしても、案件形成から実施までには相当な時間が経過することを考え、実施段階において効果的な援助案件の形成を早めに行うことが重要となろう。
1996年に国際協力事業団が出した、技術人材需要予測報告書(The Study of Engineering Manpower Development Planning in the Republic of Indonesia: Final Report)は、インドネシアが今後の経済発展を行う上において、中堅技術者の不足が降路になるかもしれず、中堅技術者の養成が急務であることを指摘した。中等教育に引き続く高等教育の拡大においては、中堅技術者の養成を長期的に拡大することが重要との認識はインドネシアの有識者の間では広く共有されている。経済状況の逼迫もあり、国立大学の数そのものはあまり増やさず、理工系学部の増強だけを行う、さらに、ポリテクニックの大拡充を行い、現在の26校に加え、2020年までに155校を新たに新設するという高等教育総局の計画もある。将来計画として、現在国立大学ではS1課程の学生がディプロマ課程の学生の2倍いるが、2000年には同数、2020年には逆転して、ディプロマ課程の学生をS1課程の学生の2倍にしょうと計画している。
この計画が実現されたとしても、増大する高等教育進学の要求をこれだけで満たすことは不可能で、ますます私学依存度が高くなることは目に見えている。ある段階の教育拡大は、時間をおいて次の段階の教育拡大をもたらすことの典型的例となるのは間違いなかろう。

