3 主要援助国・国際機関の動向
フィリピンに対する援助の重要性につき、認識を同じくする諸国の参加の下、国際的支援体制を確立することが求められている。そこで、フィリピンが持続的な成長を達成できるよう、国際社会として強力な支援を与えると共にフィリピンの援助実施・吸収能力を高めるために制度改善、構造改革を促すべく、対フィリ ピン多国間援助構想(MAI:Multilateral Aid Initiative)が国際的支援の枠組みとして存在している。
表3-1 1994,95年度ODAセクター別援助額
| セクター | 1994 | 1995 |
| 経済基盤(インフラ) | 744.3 | 600.4 |
| 社会サービス | 268.5 | 305.6 |
| 農村開発 | 195.8 | 253.1 |
| 産業、貿易 | 134.7 | 153.0 |
| 自然資源 | 12.2 | 21.2 |
| 経済開発管理 | 69.2 | 154.0 |
| 総額 | 1,424.8 | 1,487.4 |
UNITED NATI0NS DEVELOPMENT PROGRAMME
1996年の東京援助国会合では総計29億ドルの援助がプレッジされ、日本が16億ドル、世界銀行5億ドル、アジア開発銀行3~4億ドルを占めている。そして他のドナー国、米国、オーストラリア、ドイツ、カナダ、EUが援助額の5分の1を占めている。表3-2でも示されるように、二国間援助では、日本以外の各国の貢献金額は、日本の10%にも満たない状況である。
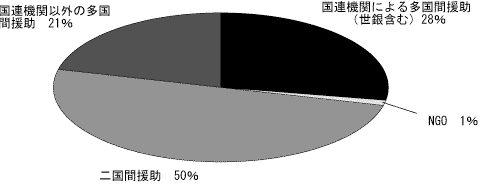
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 総計 | |
| 国際機関 | |||||||||||
| 国際連合 | 8 | 9 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 126 |
| 世銀グループ | 151 | 342 | 507 | 810 | 107 | 648 | 654 | 428 | 448 | 168 | 5,174 |
| アジア開発銀行 | 319 | 45 | 437 | 554 | 317 | 617 | 358 | 377 | 5 | 713 | 3,742 |
| ヨーロツパ連盟 | 19 | 19 | 23 | 72 | 19 | 79 | 231 | ||||
| 小計 | 479 | 396 | 974 | 1,402 | 1,363 | 1,273 | 1,036 | 578 | 478 | 990 | 9,272 |
| 二国間 | |||||||||||
| 日本 | 326 | 43 | 10,521 | 666 | 905 | 1,199 | 297 | 651 | 1,272 | 10,363 | 7,457 |
| アメリカ合衆国 | 56 | 129 | 19 | 56 | 216 | 175 | 174 | 125 | 66 | 6 | 1,152 |
| オーストラリア | 4 | 1 | 0 | 51 | 36 | 18 | 15 | 40 | 166 | ||
| カナダ | 31 | 28 | 18 | 87 | 0 | 1 | 3 | 30 | 202 | ||
| フランス | 53 | 69 | 41 | 48 | 53 | 33 | 48 | 34 | 378 | ||
| ドイツ | 4 | 18 | 45 | 59 | 42 | 12 | 9 | 28 | 13 | 56 | 285 |
| イタリア | 22 | 0 | 75 | 9 | 6 | 5 | 117 | ||||
| オランダ | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 4 | 64 | ||||
| ベルギー | 2 | 6 | 5 | 13 | |||||||
| デンマーク | 72 | 3 | 5 | 4 | 1 | 24 | |||||
| ニュージーランド | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| シンガポール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 韓国 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| スペイン | 11 | 6 | 4 | 46 | 0 | 67 | |||||
| スウェーデン | 1 | 1 | |||||||||
| スイス | 0 | 27 | 7 | 34 | |||||||
| イギリス | 69 | 4 | 12 | 85 | |||||||
| プルネイ | 100 | 100 | |||||||||
| 33 | |||||||||||
| 小計 | 430 | 232 | 1,338 | 1,211 | 1,341 | 1,452 | 540 | 940 | 1,450 | 1,258 | 10,160 |
| 合計 | 904 | 628 | 2,312 | 2,613 | 2,710 | 2,725 | 1,577 | 1,818 | 1,927 | 2,247 | 19,432 |
3.1 国際機関の動向
3.1.1 アジア開発銀行(ADB)
民間部門の参加と持続的な発展を通じた経済成長に主眼を置き、雇用機会の拡大やより開かれた市場経済の導入を目指している。中期的にはインフラの改善に取り組んでおり、また農業生産の拡大、天然資源の開発、環境保護、保健・教育分野の改善に重点を置いている。1995年には農業、エネルギー、金融、社会インフラの各分野に計6件、572百万ドルの借款を行った他、17件、計6.1百万ドルの技術援助を承認している(数値はADB資料、1996)。
対フィリピンに対するODA純額は1990年127.5百万ドル、91年100.5百万ドル、92年83.1百万ドル、93年100.2百万ドル、94年55.0百万ドルと推移し、94年は国際機関中第1位であった(数値はOECD資料、1996)。1995年末の貸付承認額とその分野別配分は表3-1の通りである。
表3-3:ADBの対フィリピン累積貸付承認額(1995年12月31日現在)
| 部門 | 融資数 |
貸付額 (百万ドル) |
構成比 (%) |
|
エネルギー 農業・アグロインダストリー 社会インダストリー 運輸・通信 金融 マルチセクター 工業・非石油鉱業 |
24 52 24 22 14 6 4 |
1,760.9 1,422.9 904.8 760.8 595. 283.7 42.8 |
30.5 24.7 15.7 13.1 10.3 4.9 0.8 |
| 合計 | 146 | 5,770.9 | 100. |
3.1.2 世銀グループ(IDA)
1997年6月末現在、世銀はフィリピンに対して累計90億ドルの融資を実施した。ほとんどどのセクターにも融資を供与しているが、特に農業、インフラ、エネルギー、工業案件が多い。1988~1996年のセクター別融資はエネルギー24%、都市開発、水、インフラ15%、農業14%、ノンプロ融資13%、教育・保健10%、工業7%、交通6%である。
フィリピンに対する世銀の方針は健全なマクロ政策の持続的な発展、貧困緩和の促進、政府部門の強化と民間部門によるインフラヘの投資の促進である。更に農民の生産性を向上させるための農村インフラヘの投資を支援し、コミュニティ開発にも努める。
1997年にフィリピンに対して2億8,140万ドルの融資を供与した。それらは第3初等教育プロジェクト(1,134億ドル)、水資源開発プロジェクト(5,800万ドル)、農地開発コミュニティプロジェクト(5,000万ドル)、第2スービック・ベイプロジェクト(6,000万ドル)の4案件である。
3.1.3国連開発計画(UNDP)
1994年12月31日現在行われているプロジェクト数は40件であり、プロジェクトコストの合計は約36百万ドルである。援助重点分野は農林水産業である(表34参照)。
ODA純額は8.8百万ドル、1991年8.3百万ドル、92年5.0百万ドル、93年4.7百万ドル、94年4.0百万ドルと減少傾向で推移した(数値はOECD資料1996)。
| 分野 | UNDP援助額 |
コスト シェアリング※ |
政府の支出額 |
プロジェクト コスト |
|
農林水産業 雇用 エネルギー 一般開発問題 住居 人道的援助災害管理 工業 天然資源 政務 科学・技術 社会開発 貿易・開発 運輸 |
8,164,115 2,329,264 742,270 4,353,138 2,562,862 1,456,450 3,535,672 830,196 242,370 719,926 435,100 2,169,965 44,000 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,187 0 |
3,956,016 904,192 99,084 645,974 375,934 0 693,572 0 21,251 206,630 174,197 1,203,180 0 |
12,120,131 3,233,456 841,354 4,999,112 2,938,796 1,456,450 44,229,244 830,196 263,621 926,556 609,297 3,504,332 44,000 |
|
合計 (40プロジェクト) |
27,585,328 | 131,187 | 8,280,030 | 35,996,545 |
出所:Compendium of Ongoing Projects as of 31 December 1994.1995 UNDP
3.2 主要援助国の動向
3.2.1 オーストラリア
1997年の対比援助供与額は5,670万ドルで、これはパプアニューギニア、インドネシア、ベトナムに続いてオーストラリアの援助供与国の第4位にあたる。オーストラリアの援助はブルネイ、インドネシア、マレーシアとともに東アセアン成長地域(East ASEAN Growth Area/EAGA)に属するフィリピン南部に焦点をあてつつある。1997年のセクター別援助額は教育21.1%、保健14%、環境7.8%、グローバル・地域(民間セクターのリンケージプログラム、小規模活動スキーム等)5.5%、農業3.9%、社会インフラ3.4%、その他 1%である。
AUSAIDの予算は大幅削減ではなく、現状維持の傾向にある。しかし他のドナーの予算が削減されたので 現在日本に次ぐドナーとなっている。
以前年間1億米ドルの予算があった有償資金協力(ソフトローン)は1996年に中止した。理由はインフラ建設のためのソフトローンは市場をゆがめるという豪政府現政権の見解から中止せざるを得なくなったからである。またNEDAも完全に国際競争させるのではなく、オーストラリアとニュージーランドの企業しか参入できないAUSAIDのやり方を評価しなかったということである。
重点地域としてはミンダナオで、重点分野は教育、保健衛生、農薬、NGO、生計向上、行政能力強化などである。行政に関しては特に地方政府の徴税能力やデータベース作成能力強化に重点を置いている。農業への協力は現在、ミンダナオの農業技術大学への協力しかない。以前カガヤンデオロで2,000万米ドルの農業プロジェクトを実施した。今後はミンダナオ北部で農業開発プロジェクトを実施する予定である。
援助の実施体制については、評価の結果をふまえて現在プロジェクト形式からプログラム形式へと変更しつつある。これは限られた予算でプロジェクト形成のために18ヵ月のF/Sなどを実施すると時間がかかりすぎて、効果が上がらないと判断されたためで、徐々に6ヵ月、3ヵ月でプロジェクト形成できるようなプログラムに移行するとのことである。またAUSAIDのスタッフも全部で26名(内オーストラリア人4名)と限られており、プログラムアプローチが現実的だと考えられている。現在のところ全体の何割をプログラムが占めるかは移行期間なので述べられないが、評価によって効果が確認されれば、一層プログラム化は進むであろう。
実施上の問題点としては特に保健衛生セクターについて一番問題が大きい。フィリピンでは保健省に医者が多く占めており、オーストラリア政府のシステムと極めて異なる。省内に医者が多くを占め、実際のマネジメントがうまくなされないのが最大の悩みである。また、専門家をオーストラリアから派遣するのも困難である。なぜなら熱帯地域の専門家が少なく、またそういう人はアフリカに行きたがる傾向にあり、人選に苦労している。豪政府のボランティアはあるが、AUSAIDと関係していない。HIV/AIDS等については他のドナーと協力している。
NGOとの連携に関しては比のローカルNGOが発展しているので特にオーストラリアのNGOとは協力を強化していない。
現状の問題点は比の予算が25%削減され、カウンターパートが、プロジェクトの予算を出したがらない傾向にあることである。そこで研修のための旅行資金がでない、診療所の開設が延期されるなど様々な問題が生じているが、プロジェクト資金を豪側で丸抱えすることは容認できない。
また比政府が国際入札制を無償にも導入したがっているが、これは豪議会で承認されないであろう。最近のフィリピン外務省の政策には注意が必要であるとのことである。他のドナーとの協力に関しては、技術協力をUNDPと一緒に計画したことがあったが、行政手続きの煩雑さで困難が伴った。児童関係のプロジェクトなどはUNICEFと協力する傾向にある。
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 有償資金協力(Net) | -※ | - | - | - |
| 贈与 | 37.5 | 36.1 | 28.5 | 33.7 |
| ODA(Net) | 37.5 | 36.1 | 28.5 | 33.7 |
出所:Geographical Distribution of Financial Flows to Aid Recipient 1996 OECD
参考文献:AUSAIDホームページ
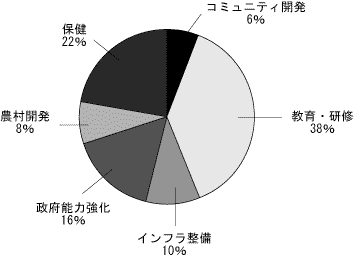
3.2.2 米国
米国にとってフィリピンは以前最大の援助供与国の一つであり、援助供与額は1990年に4億ドルを超えるレベルであった。しかし現在は約5,500万ドルレベルに減少している。ODA純額は1991年から1993年までは増加傾向であったが1994年は減少に転じた。1996年の実績は国際機関を含めた全ての援助機関の中で5位、二国間援助の供与国としては3位である。
米国はフィリピンに対し、人権、民主主義、自由貿易下での相互の経済発展を支援し、また環境破壊、人口増加、エイズの蔓延への共通の懸念を共に克服することを援助の方針としている。
フィリピンは人口、保健、HIV/AIDSの分野で日本と米国間のコモン・アジェンダの中での重要国である。
USAID(米国援助開発省)の目標は広範な経済成長を支援すること、世界的な人口増加を安定させ、人権を保護することと、環境保全、民主化、人道支援の5項目である。1998年は5,056万ドルの援助を実施する方針である。
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 有償資金協力(Net) | -11.0 | -12.0 | -※ | -7.0 |
| 贈与 | 235.0 | 241.0 | 262.0 | 123.0 |
| ODA(Net) | 224.0 | 229.0 | 262.0 | 116.0 |
(注)※(-)は0またはN.A.。
出所:Geographical Distribution of Financial Flows to Aid Recipient 1996 OECD
参考文献:USAIDホームページ
Congressional Presentation Fiscal Year 1995 1994 U.S. Agency for International Development
3.2.3 カナダ
カナダ国際開発庁(CIDA)の二国間援助プログラムは外国政策の声明書で6つの最優先項目を明らかにしている。すなわち、1.ベーシック・ヒューマン・ニーズ、2.女性と開発、3.経済基盤サービス、4.行政能力の強化(人権、民主主義)、5.民間セクターの開発、6環境である。この6項日中、4.5.の2項目がフィリピンでは、強調されている。これはフィリピンの中期開発計画の2つの目標である国際競争力の強化と国民のエンパワーメントに即したものである。
CIDAの最優先2項目である政府能力強化と民営セクター開発を強調するのに加え、横断的な重点項目としてプロジェクトや他のイニシアチブにおいてとりあげられるのはベーシック・ヒューマン・ニーズ、女性と開発、環境、経済基盤サービスの4項目である。
重点地域としては今後もフィリピン国内の最貧地域である西ビサヤとミンダナオの2地域に焦点をおく。
行政強化のプロジェクトのひとつ、Policy, Training and Technical Assistance Facility(PTTAF)はカナダ人コンサルタント1名がアドバイザーとしてNEDAを中心に政府機関の強化のために、カナダ人や他のアジアからの専門家(官・民)を短期で派遣するものである。6年のプロジェクトが1998年で終了するが、比政府から継続を要請されている。地方政府の支援も実施しており(Local Govemment Support Program)はフィリピンのローカルコンサルタントがカナダのコンサルタントを通じて、専門家、研修機材などを送付するものである。
実施状況を把握するために評価をプロジェクトの中期と終了時に実施している。一般的にはカナダ人コンサルタント2名とローカルコンサルタント2名がチームになって、スキーム、計画、リソース等の問題点を評価している。評価活動の結果を踏まえて、最近コンサルタントの雇用形態をStanding Offer Arrangementに変更した。すなわち、長期の契約をやめ、ローカルコンサルタントを登録制にしてプロジェクトに合った 人材を、プロジェクト期間のみ雇用することによって仕事の効率と経費削減に努めている。例えば新聞に地方政府プロジェクトのファンドマネージャーを募集し、270のCVを入手するなどして活用している。もちろん他のドナーからもプロジェクトに合った人材を紹介してもらうなどしている。ローカルコンサルタントはあくまでも個人ベースで会社で判断しないことが重要である。
他のドナーとの共同プロジェクトは積極的に取り組んでいる。JICAとは協力協定を結んでおりもっと共同プロジェクトを増加したいと考えている。ベルギー、EU、AUSAIDとの共同プロジェクトはあるが、現在WB、ADBとの共同プロジェクトはない。

