第4章 分野別経済協力の特徴と評価
1 本調査団の「国別評価」に関する基本的視点
今日、経済協力に関しては、様々な「評価」が行われている。例えば7種類の異なる評価調査が外務省によって実施されており、そのなかで本調査団に課せられた評価は「国別評価」である。「国別評価」とは、基本的には主要被援助国を対象に、我が国援助が当該国の経済開発および民生向上にいかなる効果を挙げているかを巨視的視点から調査・分析することとされている。「国別評価」は従って、個々のプロジェクトについての詳細な評価ではなく、マクロ的視点からの総合的評価であることに留意する必要がある。
しかしながら、マクロ的視点からの総合的評価と言う場合に、評価の基本的視点や狙いおよび評価基準を明らかにしないと評価の焦点が十分に定まらず、評価の本来の目的が達成されない恐れもある。
このような観点から、本調査団の「国別評価」を行うに当たっての基本的視点について、始めにまとめておくこととしたい。
今日、政府開発援助に関する評価については、国際的に統一された定義はないが、これに近いものとして、 我々が評価に当たって参考にしたのは、OECDのDACの次のような評価に対する定義である。
「評価とは、実施中または実施済みの開発援助プロジェクト、プログラムおよび政策、またはプロジェクトの計画策定、実施、成果に対して、可能な限り体系的かつ客観的に行われるアセスメントであり、それぞれについて計画の妥当性、目的達成度、開発の効率性、効果、並びに持続性を評定することを目的とする。 なお、評価結果から引き出される教訓および提言は、被援助国並びにドナー双方の開発援助に関わる意思決定プロセスに反映され、その質の向上が期待されることから、評価によって提供される情報は、信頼性の高い有益なものでなければならない」(1991年のDAC上級会合において採択された評価原則)
次に、ここに述べられているような目的の達成度や妥当性などについては、援助対象国に対してどのような援助成策や方針によって我が国の援助が行われてきたかを明らかにし、その視点から選定されたプロジェクトが適切であったかどうか、目的が達成されたかどうかを評価する必要がある。従って、我が国の援助に関する一般的方針、すなわちODA大綱などによって明示されている基本方針に基づき、具体的に対象国においてその経済的、政治的、社会的特徴を十分に考慮した上で、被援助国に対するどのような国別援助方針が立てられているか、そして、その方針と比較して、実際にどのような援助が行われてきたかをマクロ的視点から総合的に評価する必要があると言えよう。本調査の報告書においては、このような観点からのパラグアイの経済的、政治的、社会的特徴に関する検討を第2章で行っている。以上に述べたことを念頭に、先ず第一に指摘しておきたいのは、本「国別評価」は、上に述べたような基本的考え方に基づいて行われたということである。
このことと共に、評価に当たって重視したのは以下の点である。第一は、対象国であるパラグアイの開発 計画や経済発展のビジョンとの整合性を検討しつつ評価を行うことである。「国別評価」の目的は正に対象国の開発計画や発展のビジョンに我が国の援助成策や方針が合致しているかどうかを見ることにある。従って、本調査においてもパラグアイにおいて、経済の発展のビジョンが、これまでどのようなものであり、また、どのような開発計画が策定されてきたかについて留意した上で評価を行うこととした。
第二に、我が国と他のドナーの援助との関係についても検討を行った。対象国であるパラグアイの経済発 展は、我が国のみならず他のドナーから受けている援助全体の総合的結果であり、我が国援助の貢献度を評価するためには、他のドナーの行ってきた援助を無視することは出来ない。また他のドナーの援助を含む援助全体のなかでの我が国の役割について検討する必要がある。すなわち、パラグアイにおいては我が国が事実上かなりの長期間にわたってトップ・ドナーであったという役割を念頭に置き、その上で、我が国援助と他のドナーとの関連や補完性などの点からも評価する必要があると考えたのである。このことはまた、今後他のドナーとの協調を図りながら援助を行っていくことが必要であることから、引き続き重視しなければならない、点であると考えられる。
先にも述べたように、国別評価は特定の個別プロジェクトについての詳細に亘った評価を行うことを目的とするものではない。しかしながら、上に述べたような視点から出来る限り的確な評価を行うために、本調査では農業、インフラ、人的資源および保健・医療の4つの分野に焦点を当てつつ、夫々の分野に関して評価を行った上で、総合的なマクロ的な視点から評価を行うアプローチをとることとした。
さらにこれらの分野別の検討においても、またそれらを含み、かつそれ以外の分野をも視野に入れた総合的検討の何れにおいても、既述のDAC上級会合において採択された評価原則については十分念頭におくこととした。それらは、目的達成度、選定の妥当性、波及効果、効率性および自立発展性の5点である。
もとよりこれら評価の5項目は、本来は個別プロジェクトに対する評価基準として考えられたものであり、国別評価において、政府開発援助事業全体に亘って、この評価を個別プロジェクトと同様に採用することは困難である。例えば、目的達成度や妥当性、効率性については、プロジェクトによってかなり異なることが考えられるからである。しかしながら、マクロ的視点からの評価に当たっても、総合的に見て重点が置かれてきた援助対象分野が適切に選定されたものであったかどうか、さらに多くのプロジェクトから判断して、総合的に見て実施の効率性や目的達成度についても共通の傾向が見られないか等については検討する必要があり、「国別評価」に含めなければならないと思われる。
波及効果については、分野、地域、国全体における我が国政府開発援助の貢献度を評価するに当たって、最も重要な評価項目であると考えられる。一方、自立発展性も個別プロジェクトによって異なるものの、対象国の多くのプロジェクトで共通の傾向や問題のあることも指摘されよう。また、一般的に自立発展性の阻 害要因として、国際紛争や国際経済環境などの対象国にとっての外部の条件の急変、政策・クーデター等による対象国内部の急変、同様に事後的な国内政策の変更等が挙げられよう。従って、対象国の財政政策、援助受入れ体制、技術レベルや我が国の援助政策、計画策定、プロジェクト実施体制等を総合的に評価するに際して、対象国全体の自立発展性である援助吸収能力を評価することが必要であると考えられる。パラグアイの場合においても、国際経済環境はMERCOSURへの参加等で大きく変わりつつある。また、長期間に亘って続いた独裁政権からの民主制への移行は、パラグアイの政治、経済、社会および国内政策に重要な変化を引き起こしている。
2 援助全般についての総合的評価
全般的に見て、パラグアイにおける我が国の経済協力は、パラグアイ側からも他の援助機関からも非常に高い評価を受けている。多くのプロジェクトはその目標を十分に達成しており、プロジェクトの選定も概ね妥当であったと考えられる。波及効果についても一般的に非常に高かったと考えられる。効率性に関しては、一部に改善の余地があったとの指摘もあるが、一般的には高い効率が達成されていると思われる。自立発展性については、プロジェクト毎の性格によって相違が見られる。
より具体的には、まず、プロジェクトの選定に関しては、農業分野における技術協力や無償資金協力、インフラ分野における有償資金協力や技術協力、医療・保健分野における無償資金協力や技術協力が中心に行われてきており、最近は人材養成の分野のプロジェクトも行われるようになってきている。
パラグアイにおいては、農業は国内総生産、就業人口のいずれから見ても非常に高い割合を占めているばかりでなく、輸出額の大部分は、農産物によって占められており、農業は優先性の非常に高い分野であったと考えられる。従って、これまで農牧畜業にかなり高い比重をおいてプロジェクトを実施してきたことは一般的に適切であったと考えられる。この分野における個々のプロジェクトの妥当性については、特に大豆や野菜、牧畜を中心とした協力が行われてきているが、大豆はパラグアイにとっての二大輸出作物の一つであり、また、野菜はその重要性が高まっている分野である。
農牧業への協力に関する目的達成度は、例えば、我が国の技術協力によって開発・普及の行われた大豆と小麦の不耕起栽培に代表されるように、その目的を十分に達成し、高く評価されているプロジェクトや、野菜、果物関連のプロジェクトのように栽培技術から品質管理、流通の近代化に至るまでの総合的協力により、パラグアイの野菜果物農業の改善と普及に重要な貢献をしたものなど顕著な達成度が見られるプロジェクトが少なくない。しかし、一部には所期の目的の達成には、さらなる工夫や努力を必要としていると考えられる分野も見られる。
一方、パラグアイにおいては、インフラストラクチャーの整備が著しく遅れており、それが経済開発の重要なボトルネックとなっている。そうした中で我が国は、幹線道路網の建設、イタイプ県地方道路網の建設、送電線の建設等のインフラストラクチャー分野における協力を行ってきており、道路や電力関連のプロジェクトの妥当性はきわめて高く、しかも、いずれもきわめて時機を得たものであり、完了したプロジェクトは、所期の目的を十分に達成していると考えられる。一方、エステ市の空港においては、プロジェクト策定時から今日に至るパラグアイをめぐる国際経済環境の大きな変化や、完成後の利用の体制に見られる問題等の面で、所期の目的を達成するために取り組むべきいくつかの課題が残されている。特にMERCOSURへの加盟、 グローバリゼーションの進展のもとでのエステ市の役割、周辺地域における産業発展を視野に入れた有効な活用の方法も考えていく必要があろう。
一方、人的資源開発分野においては、職業訓練を中心に協力が行われてきたが、各プロジェクトは、それぞれの機関において中核的な研修施設と位置づけられており、プロジェクト選定の妥当性、目的の達成度のいずれも総じて高いと考えられる。医療分野での協力は、実施された各プロジェクトの妥当性は高く、特に地方保健強化プロジェクトは、パラグアイにおいてプライオリティのきわめて高いプロジェクトである。また、熱帯病を中心とした検査、研究を行う中央研究所をはじめ、目的の達成度も高いと考えられる。
このような観点から、総合的に見て重点がこれまでおかれてきた援助対象分野は、概ね適切に選定されてきたものであり、その目的の達成度も高かったと考えられる。
また、多くのプロジェクトに関して、高い波及効果が得られたことも確認されている。但し、一部の分野では波及効果をさらに高めるため普及活動等を強化していく必要も指摘されている。
一方、効率性に関しては、専門家の数や資材の調達コスト等に関して、より効率的に行う余地があったのではないかとの指摘も一部のプロジェクトに関してはあるが、プロジェクト実施時の事情等を勘案すると、与えられた条件の範囲内では高い効率性を実現したと一般に考えられる。自立発展性に関しては、プロジェクトの行われた地域の特性や、そのプロジェクトの分野(例えば農業、医療・保健等)によってかなり異なっている。このことは次項以下において分野別に指摘することとしたい。
3 分野別評価
3-1 農牧業分野
(1) 農業分野に対する援助・協力の評価と課題
1) 援助・協力の評価、目標達成度
1992年の国政調査によるとパラグアイの経済活動人口のうち、農牧業は35%を占め、農村人口は全人口420万の50%を占める。その結果GDPに占める農牧業生産の比率は依然高い。今日まで自給自足的側面の強いパラグアイ農牧業の担い手は、ほとんどが中小農民であり、彼らは肥沃な土地を耕作して農牧業を営んできた歴史がある。
日本人の移住は1937年にはじまるが、今日移住者とその子孫からなる日系人は、自給用作物はもとより、都市市場向けの疏菜や果実の生産をはじめ、近年ではヨーロッパやアメリカ合衆国向け輸出用穀類(大豆と小麦)、近隣諸国向け疏菜、鶏卵、果実などの生産・輸出も開始し、パラグアイの農牧業の発展に大きく寄与している。
パラグアイ最大の輸出農産物である大豆の生産には、日本の経済・技術協力・援助が大いに役立った。この点については我が国の技術協力により開発・導入された大豆と小麦の不耕起栽培技術によって、人口数ではわずかな日本人移住者がパラグアイの大豆生産の一割近くを占めるにいたったという事実からも裏付けられる。
農牧業分野に対する我が国の経済・技術協力・援助は、パ国内外の政治・経済状況の影響を受けて、変化せざるを得ない時期にさしかかっているといえよう。とはいえ、今日までの協力・援助は概して言えば適切且つ効果的であったと評価できる。我が国より供与された農牧業部門経済・技術協力案件は当初の計画どおり実施され、運営されており、供与された器機材も適切であったと思慮される。
2) 案件の効果
我が国の対パラグアイ農業分野の援助・協力受け入れ窓口は、主に農牧省である。我が国の協力・援助を取り付けることによって、農牧省はもとより、パラグアイ農業の国際的地位が向上したといえる。さらに、農業分野に一定の近代化をもたらしたことにより、国内的にはパラグアイ農牧省の政治的地位も向上した。
さらには、近代農業に対するパラグアイの行政担当者をはじめ、国民全体の意識を変化させるのにも貢献し、農業生産の計画化・効率化や農産品の品質管理向上などにも貢献したといえる。近代農業の良い例としては、CETAPARにみられる科学的な研究をもとにした農業を挙げることができよう。
有償資金協力案件によっては、農業部門の強化が進んだほか、国立勧業銀行に対する我が国のツーステップローンの供与などによって農業分野に対する低利子の融資が行われた。
無償資金協力案件によっては、食糧増産援助、いわゆる2KRの供与後、順調に積み立てられた見返り資金にアクセスできるようになっている。
無償の「草の根無償」協力は、小回りのきく農村の教育施設や関連施設の建設に役立っており、農村部住民によって活用されている。
技術協力面においては、派遣専門家が現場農村部における農業生産の技術的指導にとどまらず、農牧省と生産地を結ぶ農業行政の指導や助言をも行っている。
カウンターパートも日本で訓練を受けたりすることによって養成された。また、農業に従事する我が国J0CV(青年海外協力隊員)の活躍に対する評価も高い。
移住事業案件も継続的に実施され、移住者に恩恵をもたらしている。
3) 持続的発展可能性
我が国の対パラグアイ経済・技術協力・援助は、パラグアイ農牧業の持続発展を促す目的で実施されている。概ねのプロジェクトについて、当初計画の目標は達成できたが、パラグアイが南米共同市場に加盟したことにより加盟国の農産物の競争にさらされるようになったため、持続的発展を可能にするためにはこうした国際環境の変化を考慮に入れた新たなスキームによる協力が不可欠である。
例えばラ・コルメナ地区の場合は、立地条件が厳しいため移住地内における農地拡大が困難で、人口規模が小さく後継者が不足しているので独力では南米共同市場加盟の他の諸国から流入する農産物と競争しながら持続発展することは望めないのが現状である。
4) 持続発展阻害要因
(i) パラグアイ側の事情
パラグアイは縦割り行政になっており、省庁間調整が著しく困難である。このため経済企画庁作成の社会・経済開発計画の農業分野における多省庁間にわたる総合的且つ効率的なプロジェクトを実施するのは困難を極める事業である。さらに、農業行政機関の非効率性が加わり、農業分野における援助・協力効果が充分に発揮されているとはいえないのが現状である。
待遇条件が厳しいため農牧省職員をはじめとした普及・営農指導員のモーティベーションが低く、現地カウンターパートの離脱率も高いことが、大きな問題点の一つであるから、彼らの待遇条件を改善し、動労意欲の向上を図る必要がある。 また、国際環境の変化に伴い、パラグアイの農業は南米共同市場諸国との競争にさらされ、厳しい状況におかれている。
(ii) 日本側の事情
農業分野の協力に限ったものではないが、派遣専門家の多くは異文化経験が充分でなく、現地の生活・労働習慣への適応にも困難が伴い、スペイン語能力が不十分なことともあいまって、現地の人々との意志疎通が円滑に進まない場合が多々ある。
また、供与される器機材部品が高価である場合があることに加え、調達時の手続きが複雑であるため、納入がかなり後れ、迅速なプロジェクトの進行あるいは機材の修理や運転再開に支障をきたす場合がある。諸手続きの簡素化と迅速化が求められる。
5) 当初計画の妥当性
パラグアイ農牧業分野に対する日本の援助・協力は、パラグアイ政府も高く評価していることにみられるように、同国の農業開発に大きく貢献している。
供与された資機材や設備は極めて良好に管理され、有効に利用されており、10年前に供与されたものも効率的に使用されている。
機動性に富む「草の根無償」援助によって建設された、体育館、学校の教室、多目的施設は、住民によって有効に使用されている。パラグアイ農村における基礎教育施設がそもそも大幅に不足しているだけでなく、教室数増設が就学者数の増加に後れをとっている。このため「草の根無償」援助による施設の建設は農村部における就学率の向上をもたらし、ひいては教育水準の高揚にも貢献できるものと思われる。
日本の経済・技術協力は、パラグアイ全体の大豆、小麦、野菜の品質改良と生産増に貢献した。この協力の恩恵にあずかった日本人移住者の生産物は、人口100万人を抱えるパラグアイ最大の消費地アスンシオン首都圏市場において、南米共同市場加盟諸国の農産物と競争できる技術と質を持っているパラグアイ国の数 少ない商品である。こうしたことから今日に至る日本の援助・協力が妥当であったといえる。
(2) 視察プロジェクト
1) アスンシオン市中央食品卸売市場内の青果物流通改善計画
- アスンシオン市には、1944年に9つの小売公設市場が設置されていた。その後アスンシオンの都市化に伴う人口集中によって中央卸売市場が必要となり、1979年に世界銀行の経済協力と日本の技術協力によって、今日のアスンシオン市中央食品卸売市場が建設された。その後数回にわたる我が国の技術協力案件の実施によって中央卸売市場の近代化が図られ、今日の近代的な市場へと変貌した。
アスンシオン中央食品卸売市場の青果物流通改善計画は1991年3月から1996年3月までに実施された。同計画はモデル的に、アスンシオン向け農産物・青果物の二大産地、ラ・コルメナ地区とコロネル・オビエド地区の農業協同組合の出荷する農産物・青果物の品質管理と流通の改善にあたるというものである。 - 青果物流通改善計画は、アスンシオン中央卸売市場に対する我が国による一連の協力計画の継続である。
- 当初計画である青果物、果実の品質規格基準に基づく集荷、選別、荷姿の統一、出荷を行うための流通機構の編成整備、農産物の品質管理の向上といった目標はおおむね達成されている。
- 同プロジェクトがモデル・ケースとなり、ラ・コルメナ地区農協とコロネル・オビエド農協にとどまらず、他の地域へも一定程度の広がりをみせた。
- アスンシオン市中央食品卸売市場内の生産者・卸売・小売商にも一定程度の影響を与えるに至った点については評価できるが、普及はまだ充分とはいえないのが現状である。また、集荷・出荷モデルとなったラ・コルメナ農協やコロネル・オビエド農協方式の広がりはまだ不十分であり、今後その普及に対する一層の援助が求められる。
- 先見のビジョンをもつこの計画は、現在においては南米共同市場加盟諸国の農産物と競争できるような体制づくりに直結するものであり、妥当なものと高く評価できる。
- 極めてタイムリーなプロジェクトであり、第二次計画が期待される。
2) アスンシオン大学獣医学部に対する「家畜繁殖改善計画」
- 無償資金協力およびプロジェクト方式技術協力によるアスンシオン大学獣医学部に対する「家畜繁殖改善計画」は1982年12月から87年12月まで実施され、同年12月から89年12月まで延長された。さらに、93年4月から95年4月まで再度実施された(アフターケア協力)。これは家畜繁殖技術の改善をはかるために、人工 受精、家畜衛生、家畜栄養の技術協力からなり、畜産技術者の育成、新技術の導入・研究、生産性および生産物の質の向上等、パラグアイにおける技術援助成果の定着を図るものである。
- 畜産技術者の養成と家畜の生産性および生産物の質の向上に向けてのプロジェクトの目標は達成されており、また人工受精師の養成、凍結精液の製造技術および繁殖生涯診断技術の定着なども良好である。
- ペレット方式からストロー方式への切り替えによる凍結精液の製造と利用は、品種改良のみならず、人工受精師の養成を通じた民間獣医師の技術レベルの向上、衛生改善に伴う受胎率の向上、受精卵移植等の新技術の導入等への効果を生み出した。
- プロジェクトサイトが既存の施設を活用しており、人材も豊富で、カウンターパートもかなり残っていることから、当面継続可能なプロジェクトといえる。1985年頃のパラグアイの液体窒素製造量は国内の需要を満たすものではなかった。1980年代末になってパラグアイで複数の企業が液体窒素を生産するようになり、同商品の生産と供給量が増し、市場の需要に応えるようになった。このため、1985年頃に導入された大型機械(液体窒素製造機等)は運転を中断しているが、これは安価になった同商品を外部の民間企業から調達するようになったからである。
人工受精技術は改善され普及した。一方、1980年代まで上昇傾向にあった肉牛の価格が1990年代になって落ち込んだ結果、現在高価な受精卵移植はほとんど用いられていない。この技術はパラグアイの肉牛の価格が低下した現在では経済的に有利でなく、今後の農家への普及にあたっては慎重に検討する必要があると考えられる。とはいえ、農牧畜立国のパラグアイの肉牛の品種改善は引き続き重要であり、人工受精、飼料の開発・試験などは今後とも研究を続けるのが望ましい。 - 計画立案当時の輸入を抑制するための国内生産体制の強化、品種改良と家畜衛生の改善による生産性の向上は、パラグアイ国のニーズに合致したものであり、そのために立案された生産技術者の養成と肉牛等の生産性および質の改善、飼料の改良は妥当なものであったといえる。さらに、人工受精用精子冷却器をはじめとする器機材の導入も適切かつ妥当なものであったと推察される。
3) ラ・コルメナ農村総合整備計画(ラ・コルメナ日本人移住地区)
- ラ・コルメナは1937年に日本人移住者によって建設された入植地である。その後60年の間に入植地中心部にはパラグアイ人も定住して、ある程度都市化が進んだ。
この地区は山岳地帯の麓にあるため、地形は丘陵地である。水が少なく、灌漑設備を備えなければ農業活動の難しいところである。こうした自然環境条件であるため、農地拡大は困難をきわめる。
「ラ・コルメナ農村総合整備計画」は「国家経済社会計画」(1985~1989年)の精神に照らし、農業・農村振興計画のモデル事業としてラ・コルメナ地区が優先候補となったことにより開始された。このため、当該プロジェクトを無償資金協力として、日本政府に要請するパラグアイ側の合意形成が十分にあった。農業開発および地域向上を目的とした同プロジェクトは農牧省が実施した。
「ラ・コルメナ農村総合整備計画」の実施地はパラグアリ県ラ・コルメナ地区であり、実施期間は1989年8月から1992年2月で、供与額は11億4千7百万円であった。 - この案件は、無償資金協力によって整備された生産基盤(灌漑、道路、橋梁)、生活改善設備(飲料・雑用水の確保のため)および維持管理用施設とその関連器材が当初設定したプロジェクトの目的にそって概ね適切に活用され、また施設整備にともなう効果発現の度合いも高く、これが日本人移住者とパラグアイの農業開発に貢献している。
- 農業生産基盤施設、農村生活改善施設および維持管理用施設と関連機材は、事業計画にそって全て整備され、当初のプロジェクトの基本的な目的は達成されている。また、プロジェクトの目標である「営農の近代化」と儂村生活改善」は、かなりの程度達成されたといえる。当初の予想を大幅に上回る飲料・雑用水施設利用農家の増加を通じて、当初予測された必要規模を上回る需要によって灌漑施設の目標も達成された。
- 農業労働の軽減につながり、高年齢者の多いラ・コルメナ地区における営農の安定化に貢献したといえる。 また、飲料・雑用水施設の整備によって衛生面での改善がみられ、同時に水汲み労働が解消された結果、婦女子の労働負担が軽減された。
また、農道の整備によって首都圏にアクセスが容易となったことは、営農上も大きなプラス効果をもたら している。 - 「用水・道路管理委員会」の設立によって、住民による維持管理体制の確立がはかられ、現在は充分にその機能を果たしている。
灌漑農業の普及に関しては、技術的な支援体制が未だ確立されておらず、灌漑用水の有効利用の観点から、これまでの計画には策定されていないが、今後は灌漑農技術の確立・普及が必要とされる。
ラ・コルメナ地区出身の若年層は都市部に流出し、地区内は高齢化が進み、農地の拡大は困難である点からも、少ない水の有効利用の必要性を強調できる。 - 当初プロジェクトの事業計画策定時における国家農業政策では「小農対策」および「都市と農村の生活格差の是正」が基本方針として掲げられている。本プロジェクトの事業計画はこのような国家政策の基本方針に合致しており、案件としては妥当なものであると考えられる。灌漑施設の整備水準は、現地の農業事情に即して、無動力灌漑システムや飲料・雑用水確保のための施設が採用されるなど、維持管理が容易な設計となっており、施設計画内容も妥当であると推察される。
当初はラ・コルメナ地区にイタリア系資本によるジュース・缶詰工場の建設が予定されており、果実選別機、疏菜・果実運搬保冷車の導入もその時点では妥当なものであったといえる。 - イタリア系資本による果実加工工場建設が暗礁にのりあげた現在、選別機、疏菜保冷庫、保冷車の必要性がなくなった。したがって、これらの機材の有効利用を受益者を交えて模索する必要がある。
農業用水が少なく、現状の土地面積で、しかも高齢者に可能な栽培作物を必要としている現状においては、新品種の導入が不可欠である。栽培果実は日本から直接導入しているが、今後は、CETAPAR等国内の研究所・実験所で実験された土地の特質に合致した果実や疏菜を導入できるようにすることが求められる。
農家数が少ないため、市場向けに、安定的に一定量と一定質の果実生産を確保するのは困難である。
農道が整備され、アスンシオン市場へのアクセスが容易になった現在、今後は、隣国の農産物との競争にさらされるため、出荷対象地のアスンシオンの「中央食品卸売市場」内にラ・コルメナ産農産物受け入れ施設の改善が重要となろう。
また、今日においては飲料・雑用水の量に限界があり、もはや節水をする状況になっている。これを改善する意味においても飲料・雑用水の有効利用は不可欠である。 - 当初、環境保全に関する配慮が不足していたため、灌漑施設によって土砂の水源への流人による水質汚濁が問題となっている。また、灌漑施設を設置する際に改修された作業用道路で、現在維持用道路として使用されている道路の存在により、周囲の森林の乱伐が容易になり、環境破壊に利用される結果を招いている。さらに、その道路沿いに貧困層農民が定住し、環境破壊に一層拍車をかけるかたちとなった。
以上のように、パラグアイ政府の環境保全に関するチェック機能は、いまだ不十分である点、憂慮される。
4)パラグアイ農業総合試験場(CETAPAR)
- CETAPARは、イグアス地域の日系移住者の営農の安定と振興を図るために、1962年にイグアス指導農場として発足したJICA直営の農業試験場である。その後1988年にこれまでの農業試験研究業務に普及業務を加えて、名称をCETAPARに変更し、「長期総合研究計画」に基づいてパラグアイ全体の農業発展を視野にいれた農業研究活動を展開している。
CETAPARの研究活動は過去30年におよぶ研究成果に基づいて作成された「長期総合研究計画」に沿って進められている。研究計画は、大豆と小麦に関する特定作物の不耕起栽培技術の確立・普及を核にして進められている。 - 大豆と小麦の不耕起栽培技術は確立し、イグアス移住地をはじめとして日系人農地の間で普及して、パラグアイの農業発展に貢献している。
具体的には、テラロッシャ土壌の特性の研究が順調に進んでいるほか、大豆生産に被害を及ぼす害虫、バクテリアやカビの特性とその駆除の研究と被害対策の普及も一定程度進んでいる。また、パラグアイの伝統的な野菜の代替になりうると同時に、農産物の多角化につながり、農家の単一作物依存の回避と経済的安定をもたらすメロン、ナツメグに代表される作物の研究と実験も順調に進んでいる。 - パラグアイ農業の技術的進歩に多面的に貢献している。
日本人移住者、日系人はもとより、地域社会全体にも貢献している。例えば、近隣の農家から依頼される作物の病害虫の診断も請け負うにいたっている。
さらに、農牧省との連携で開発された技術や知識が報告書、あるいはパネルワークショップ形式で移転、伝授され、一定程度の普及効果がみられる。 - 「長期総合研究計画」で示された研究課題は、大豆を中心とする輸出商品作物の拡大政策を基本とした国家農業政策とも適合するほか、国内農業が抱える広域的な課題にも適用可能な汎用性があるものと考えられる。例えば、不耕起栽培技術は確立され、大豆は南米共同市場においても競争できるようになった。
CETAPARで開発されたメロンはブラジル製品と競争可能となり、パラグアイ国内市場はもとよりブラジル市場でも販売できるようになった。
土壌、病害虫対策の研究は汎用性が認められるほか、大豆などの栽培の安定化をはかるのに貢献したといえる。 - 農畜産加工分野および統合された南米市場調査分野を中心とした新規の研究課題設定が求められる。
研究開発された技術や知識が一定程度普及したとはいえ、農業生産者全般に十分普及、浸透しているとはいえない。CETAPARとパラグアイ政府、および政府と農業生産者との連携が円滑に行われているとはいえず、そのため普及効果が十分に上がっていないのが現状である。今後は、生産者に対する普及計画とその実施が求められる。
大豆や小麦のように大規模経営用商品作物生産は、パラグアイの経済発展にとっては重要であろうが、パラグアイ農業の将来を南米共同市場(MERCOSUR)内で位置づけて考えると、アルゼンチンやブラジル産農産品が国内市場に入り込んできていることから、これらと競争できる果実、疏菜の研究も必要であると考えられる。
パラグアイ東部地域はブラジルのパラナ州地域に自然条件が類似していることから、この地域で既に開発された品種の栽培実験を行うのが適切であろう。農業先進地域パラナで開発された農作物の導入をはかって栽培実験を行いパラグアイに適応させることが、もっとも効率的な方法である。現に、大豆の不耕起栽培技術はブラジルの大豆生産の専門家宮坂博士の技術とカンピーナ農業試験所の開発技術をヒントに開発されたものである。また、輸出作物でも大規模生産によるものばかりでなく、中小規模でも生産可能な作物の開発が重要である。
外部の農業生産者からアクセス容易な広報センターによる情報の開示を進めるため、一層の広報活動の必要性がある。
全体としては、病害虫対策の研究はかなり進んでいるのに比べ、商業ベースにのるような新品種の導入が若干送れている。さらに、開発された技術の普及も十分進んでいるとはいえず、これらの点を改善していく必要がある。
5) イグアス移住地
- イグアス移住地は立地条件に恵まれている。大きな市場をかかえるブラジル国境から45キロ地点に位置し、アスンシオンとブラジルを結びパラグアイで最も重要な経済・貿易道の国道7号線が移住地を貫く。このためブラジルからの刺激も受けやすく、同時に同国産の農産物の競争にもさらされる。さらに、CETAPARに隣接していることから最新の農業技術をいち早く活用できる。
- 「草の根無償」援助によってイグアス移住地内に建設された体育館は、日本人移住者、日系人子弟の教育目的と各種行事に有効に活用されている。
また、同様な「草の根無償」援助によってアドベンティスタ系の初等教育施設内に建設された幼稚園も、それまで存在していた小・中学校に加え、地域の教育事情改善のため極めて重要なプロジェクトとなっている。
このような機動力に富む「草の根無償」方式による援助は今後ますます重要となるだろう。
また、食糧増産援助、いわゆる2KRの積み立て見返り資金の融資による製粉工場の建設は、収穫した大豆を長期間保存可能にし、ひいては農業収入の安定と経営の安定に貢献している。 - 今後は、ブラジル市場を対象にした新品種の支援と見返り資金によるさらなる製粉工場の建設の支援によって、持続的発展を堅固なものにすることが重要であろう。
6) 地域農業研究センター(CRIA)
1979年技術協力協定の締結とともに始まった日本の農牧業分野での協力のうち、初期の本格的なプロジェクトの1つである。イタプア地域の日系人移住者支援と農業支援という目的に基づき、農業機械化、大豆等畑作試験場、林業の3つの分野に協力を絞った「南部農林業開発プロジェクト」が同年から開始された。農業部門として地域農業研究センター(CRIA)と農業機械化センター(CEMA)を、また林業部門として林業開発センター(CEDEFO)をスタートさせ、いずれも無償資金協力による各センターの設立、プロ技協 を通じた包括的協力を実施してきたところである。延長、フォローアップ、個別専門家派遣等を通じて、88年まで10年間に亘る長期の協力が続けられ終了した。
CRIAについては、大豆、小麦に関する遺伝資源、育種、種子生産と管理、土壌管理技術の研究開発、訓練を目的としたプロ技協が、「主要穀物生産強化計画」として、新たに1990年より開始され、95年に97年まで延長された。これに続き、パラグアイ国の輸出の太宗となった大豆の研究開発能力を向上させるため、97年より新たに「パラグアイ大豆生産技術研究計画」を立ち上げ、2002年までの予定でプロ技協を行っている。
CRIAは、当時増産計画の途にあったイタプア地域の小麦、大豆生産を安定拡大するための研究機関として発足し、開発された種子や土壌管理技術が日系移住者を含む生産者に普及するなど、地域のニーズに促しながらプロジェクトに改善を重ね、大豆生産の急激な拡大に貢献してきた。その点からして、CRIA関連のプロジェクトの果たした農業分野への貢献は高いものがあったと評価される。5年間に1つの割合で新品種が導入されている。
CRIAでは、3つのプロ技協をつなげ、15年以上にわたる極めて長期の協力関係が維持されている。日本の技術協力の成果を継続的に発展させるという趣旨は理解できるとしても、異例の長期であり、特に自立発展性という観点から見ると、問題無きにしもあらずである。安定した予算確保が不十分など、プロジェクトを支える農牧省の支援態勢は十分とは言えず、目標とされた事業展開が制約を受けている現状がある。CRIAは、そもそも既存の研究機関から出発した機関だが、予算を中央政府が集中管理しているため、独自の経済性を追求することも困難となっている。
これまでに供与された機械等設備は良く管理されているものの、総じて老朽化が目立っており、一部には、前プロジェクトで建設された施設に時間の経過の割には早い劣化もみられた。予算の制約上、自力で老朽化した設備を更新をするといった姿勢も薄いように受けとめられた。また、農牧省の職員としての賃金水準の低さもあり(アスンシオンと比べて副業も少ない)、中間レベルの技術者(カウンターパート)の定着率が極めて低く、協力の成果の継続性や蓄積に影響を与えている点は否めない。また、予算の90%が人件費に充てられて事業費が著しく抑えられ、そのために研究成果・研究技術の普及体制も十分ではなく、ブラジルから入った技術が生産者に利用される傾向も高くなっている。研究の成果は高いものがあるだけに、 CETAPARのよに、地域の農業生産者との関係を強化して地域にその効果を波及させると同時にCRIAに対する信頼度を高めるため、体制の整備などの一層の努力が求められる。
CEMAは、畑作の機械化や農業機械整備技術の向上に貢献した。CEDEFOについては、林業技術者の養成と育苗、造林及び木材加工技術に関する技術移転は実施されたが、大豆畑の転用を目的に造林伐採が急速に促されるという林業環境自体が一変したため、1990年半ばには造林育苗等の技術者の訓練自体を廃止するなど 協力の成果は継続されておらず、農牧省も失敗案件と見なしている。
その後、農牧省は、CEDEFOをイタプア林業センターとして改編し、苗木供給、木材加工、環境保全等の地域林業振興のための地区センターとして位置づけた。現在は、技術協力として実施されている東部造林普及計画の地域普及活動の拠点として管理・運営されている。
7) イタプア県地方道整備計画
大豆等農産物の輸送を円滑にするためのラパス移住区を中心とした地方道整備を目的として、道路整備関連機材の調達ならびに橋梁の建設が、1993、94年度の2次にわたる無償資金協力により実施されている。
総延長125キロメートルを月間1.2キロのペースで舗装作業が進められており、立派な舗装道路が大豆畑を突っ切って建設されているが、完成すれば、農産物の輸送にとどまらず、地域の物流を活発にすることで、地域経済全体への貢献が極めて大きいものとなることが考えられる。
事業の円滑な実施は、ラパス市議会議長であるラパス農協のタオカ氏(パラグアイに帰化)が、中央政府に精力的に働き掛け、ローカル・コストの捻出に成功しているという、個人の努力に支えられている点を指摘しなくてはならない。こうした地域のインフラ整備が、日系の協同組合のみならず、地域全体の発展に稗益することは明らかだが、今後、周辺の道路補修等に、プロジェクト終了後、供与機材を有効に活用していくことが重要である。既に、エンカルナシオン市の洪水で流された橋の修復に供与重機が活用され評価を受けている。
8) 東部地域給水整備計画
東部農村地域の上水道施設計画であり、井戸掘削用機材など機材供与と4ヵ所の給水施設の建設が1995、96年度の無償資金協力で実施され、第2期工事が進行中である。
ラパス、サンロレンソ、チャイペ、バリオクエにわたるイタプア県の広範な地域を包括する上水道施設計画であり、高低差のある異なった地層を持つ地域での技術移転を含むプロジェクトである。日系移住地のみならず、その周辺を含む広域を対象にしており、広く住民の生活改善に寄与することが期待される。
9) ラ・パス農業協同組合及びウニーダス農業協同組合
- ラ・パス農業協同組合は、国際協力事業団の3つの直轄移住地に入植した移住者によって作られた組合である。
移住者による長期にわたる努力が実り、ようやく15年程前から大豆と小麦の大型機械化農業が導入され、安定した農業経営が行われるようになった。また、入植地においては、一農家当たりの所有地は当初多くても60ヘクタール程度であったが、移住者が借入などによって土地を購入し、耕作地を拡大した結果、今日ラ・パス農協の組合委員の平均所有面積は140ヘクタール程度に達しており、また、平均耕作面積も100ヘクタール程度に達しているとされる。
国際協力事業団による各種の事業〔特に道路、子女の学校教育、医療、次三男対策のための貸付(土地購入などに用いられている)等〕が行われており、この地域における移住者の安定した農業経営と生活条件の改善に多大な効果があったと考えられる。 - 今後の重要な課題として、とりわけ次の2点が指摘される。その一つは、この地域における今後の農業のさらなる発展をどのように行うかという点である。イグアス移住地とは地理的条件が異なり、この地域では大豆と小麦の農業が中心になっている。従来、いくつかの商品作物の導入や養蚕などが試みられてきたが、現在のパラグアイの置かれた条件やこの地域の地理的な特性などから、不耕起栽培による大豆と小麦の生産を中心とせざるを得ない状況にある。
しかしながら、この方式による農業の発展は、土地耕作面積をさらに拡大し、農業経営を大規模化する必要がある。経営規模の拡大は、この地域周辺で土地を購入することに限界があることから容易ではない。したがって、農業経営の多角化が重要な課題となる。
この点で参考になるのがラ・パス農業協同組合に比較的近い地域で活動を行っているコロニアス・ウニーダス農業協同組合である。この組合は、3,500人の組合員を有するパラグアイでも有数の組合の一つであり、また、大豆の他、植物油、小麦、牛乳、マテ茶、配合飼料等様々な農牧業に取り組み成果を挙げ、注目されている。また、22にも上る異なる国籍の農家が組合員となっていることも特徴の一つである。
さらに、重要なことは、教育や研究に力を入れていることであり、組合員の子女や組合がその施設で雇用している人々に対して奨学金を与え、人材養成に貢献し、また、それがこの協同組合の経営や技術的な改善にもつながることが期待されている。ドイツのGTZからの協力が1972年から82年の10年間行われた経緯がある。 - この地域の第二の重要な課題は小農対策である。ラ・パス農業協同組合の周辺にも多数の零細小規模経営の農民がおり、日本人移住者との経済的格差は非常に大きいのが実状である。これらの農民は、土地を所有出来ないか、所有出来ても土地が狭いために、非常に所得が低い状況にある。ラ・パス日本人会は、この地域の250キロメートルの道路の管理及びそこに位置する橋の管理を行っており、これはこの地域の農業や生活に大きく貢献している。
小農対策については、コロニアス・ウニーダス農業協同組合も強い関心を有しており、小農の問題についての調査等も行っている。この調査によれば、小農の所得は最低賃金にも達していない状況にあり、問題を解決するためには、小農自身が農業の改善のために投資を行えるようにする必要があると見ている。また、労働集約的農業である果物の栽培や小動物の牧畜等が適当ではないかとしている。さらに、それら生産物の販売のための市場を確保する必要があることを指摘している。 - こうした状況のなかで、今後さらに日本からの草の根無償などは重要な役割を果たし得ると考えられる。また、これに関連してJICAのシニア・ボランティアによる給食制度の改善が高く評価されていることを紹介しておきたい。このケースは、栄養学の専門家がこの地域で生産される大豆から豆乳を生産し、これを飲みやすく加工して学校給食で子供に飲ませる方式が成功したものであり、この豆乳の普及センターの施設を小規模無償で建設することが検討され、実施される可能性が高い。
3-2 インフラ整備分野
(1) パラグアイにおけるインフラの現状
パラグアイは、南米諸国の中でもインフラストラクチャーの整備が最も遅れている国の一つである。MERCOSUR域内では、アルゼンチンとウルグアイが最も進んでおり、これにブラジルが続いているが、パラグアイはこれらの諸国と比較して、インフラストラクチャー整備の遅れが目立ち、特に電話や下水の普及は著しく遅れている。以下、主要な分野についてインフラ整備の現状を念頭に置きつつ、我が国がこれまで行ってきた経済協力の役割について検討することとしたい。
まず、輸送分野に関しては、パラグアイでは道路交通、河川交通が重要であり、航空および鉄道がこれに次いでいる。パラグアイは内陸国であるため、輸出入の貨物輸送については、河川輸送の割合が高い。輸出の39%、輸入の73%がパラグアイ川およびパラナ川を利用するとされており、その大部分は、ブエノスアイレス、モンテビデオで外洋船に積み替えが行われている。
国内の旅客、貨物輸送の中心は道路であり、その総延長は1993年に30,457キロメートルに達しているとされる。このうち約25,000キロメートルが公共事業通信省の管轄下にあり、約3,500キロメートルが舗装道路となっている。一方、鉄道については、アスンシオン、エンカルナシオン間の376キロメートルおよび64キロメートルの支線があるが、旅客・貨物輸送に果たしている役割は非常に小さい。
国際空港はアスンシオン市およびエステ市にあり、国際線が発着している他、国内線は小型機が主としてアスンシオンーエステ間の旅客輸送および国内の主要都市間の貨物輸送を行っている。
パラグアイは内陸国であることから、特に輸出の競争力を強化するためには、輸送インフラの整備が不可欠である。それにもかかわらずに、パラグアイにおけるインフラの整備は一般に著しく遅れているが、それを解決するために必要な資金は、政府財政が厳しい状況のなかで、きわめて限られている。また、後に述べるように民活方式によるインフラ整備も今後進められていくと考えられるが、最近着手されたに過ぎない。
こうしたなかで、二国間援助でインフラ整備への規模の大きい経済協力を行っているのは日本のみであり、パラグアイ政府はもとより、この分野への援助を行っている米州開発銀行(IDB)等からも日本の協力は高く評価されている。
(2) 道路の現状と我国の経済協力
アスンシオン-エンカルナシオン間の鉄道は、1854年にイギリス資本によって建設された南米最古の鉄道であるが、老朽化が甚だしく、旅客・貨物輸送に果たす役割は非常に小さいため、国内の輸送においては、道路の重要性がきわめて高い。しかしながら、パラグアイの場合、舗装されているかどうかで道路の利用の効率は大きく異なるものとなる。その理由は、パラグアイにおいては、多くの地域で舗装されていない道路の場合、降雨時は車両の通行が事実上不可能となるからである。
これはパラグアイの主要農業生産地域における土壌の性質と降雨の量によるものである。舗装されていない道路の多くは、砕石を敷いた簡易舗装か盛り土工事だけのものが大部分であるが、雨が降った状態で通行すると、道路に深い穴ができ、単にその時点で通行が困難になるだけでなく、改修工事も困難となる。このため盛り土工事だけのような道路の場合には、降雨時には車を動かすことができなくなるのである。こうした状況は、幹線以外の道路の状況等においても同様であり、降雨後道路に深いわだちができ、これを改修するのには非常に時間を要する。
こうした道路事情の改善は、特に農畜産物の出荷コストを引き下げるためには不可欠であり、道路の末整備の状況が、パラグアイの経済発展を大きく妨げてきたということができる。すなわち、上に述べたような特徴を有するパラグアイの道路事情にも関わらず、パラグアイの道路の舗装の進捗状況は、従来非常に遅々としたものであった。
世界銀行の資料(世界開発報告1994年版)によれば、1960年のパラグアイにおける舗装道路の総延長は、僅か254キロに過ぎなかったのである。すなわち、この時期においては、パラグアイの幹線で唯一舗装されていたのは、アスンシオン、エステ市間だけであったといってよく、日本人の移住者の多いエンカルナシオンヘの幹線道路は舗装されておらず、エンカルナシオン、アスンシオン間の旅客・貨物輸送は困難をきわめ、時に陸の孤島となったことがあったと言っても決して過言ではない。
1970年には、舗装道路の総延長が816キロメートルとなり、80年には1,518キロメートル、93年には2,811キロメートル、97年には3,500キロメートルヘと次第に拡大が見られてきているが、それでもまた、パラグアイの道路網全体に占める舗装道路の割合は低く、今後も道路への多額の投資が必要となっている。
道路を整備することによって、農畜産物の出荷が容易となり、またコストの低下を実現できることにより、特に地方農業の発展が可能となることは、後術のようにイタプア県における地方道路整備の効果がきわめて顕著であることからも明らかである。
この他パラグアイにおける道路輸送に関しては、パラグアイ政府の財政難もあって道路の保守・管理が不十分であることや、道路に関連する排水システムが不十分なことなどが指摘されている。例えば1997年にはエルニーニョ現象の影響でエンカルナシオン周辺には、8時間に280ミリという豪雨が襲ったが、このことにより、河川が氾濫し、道路に多大な被害を与えた。この結果、アスンシオンからエンカルナシオンに至る道路の一部が通行不能となる状況も生じた。
これは重要な幹線道路に支障が生ずる事態であり、道路の保守・管理が不十分であることを示す一例であると考えられる。現在パラグアイの舗装道路の人ロー人当たり総延長の長さは、MERCOSUR諸国のなかで最も整備されているウルグアイを100とするとパラグアイは32にとどまっており、アルゼンチンの82、ブラジルの50よりもかなり低い水準にある。
こうした状況のなかで、道路整備の分野における日本の経済協力のはたしてきた役割は大きい。1977年に18億5,000万円のアカアイーラ・コルメナ間の道路を通すための融資が行われ、その後、1989年に、幹線舗装道路の改良および一般道路維持機能の強化のための96億9,600万円の有償資金協力が供与された。後者の場合358キロメートルにおよぶ国道、幹線道路の改良が行われており、これは1993年のパラグアイの舗装道路総延長の12%強に当たる距離であり、重要な経済効果をもたらしたと考えられる。また、この借款によって、一般道路維持管理用機械の購入(612台)と維持管理事務所の機能強化が行われている。
一方、1995年移以降、イタプア県地方道路整備計画が無償資金協力によって実施されている。この整備計画は総延長125キロメートルにおよぶものであり、第一期は9億9,700万円の建設機械調達、第二期は6億4,400万円の橋梁建設(7つの橋)および一部資材供与からなり、総額16億4,100万円の協力が行われた。このプロジェクトのもとで1ヵ月に約1.2キロメートルのスピードで整備が行われてきており、1997年10月末現在で既に35.9キロメートルの舗装が終了している。また橋の建設も既に行われている。
この道路整備は、単に道路の周辺農家のみならず、より広くイタプア県の農産物の出荷等に大きく寄与すると考えられる。また、修理工場がエンカルナシオンに設けられており、かつ無償資金協力で供与された機械はイタプア県に残るので、将来道路の補修や管理も可能となると考えられる。
カウンターパートである公共事業通信省がアスファルト、燃料、ダイナマイト等を提供し、120人の建設労働者によって道路の建設を行ってきているが、財政難の理由からアスファルトやダイナマイト等の資材の供給が遅れ、雇用している労働者が余剰となる状況が生じるなどの問題点が指摘されている。しかしながら、この点については、地元の人々の中央への働きかけなどにより改善が見られており、一般的にはイタプア県地方道路整備計画は順調に進んでいると考えられる。また、以下の理由により、このプロジェクトの完成時には、多大な経済効果が期待される。
パラグアイ東部に位置するイアプア県は、大豆、小麦等の農業生産が多く、パラグアイの農業生産の重要地域と位置づけられている。しかしながら、同県の地方道路は未舗装であり、降雨により不通となり、農産物の輸送に多大な支障をきたしていた。このため道路の未整備の状況はイタプア県の農業開発・経済発展の阻害要因となり、地方道の整備は、この地域の緊急課題となっていた。また道路整備に必要な機材も非常に不足していた。
道路整備の分野における今後の課題としては、地方農村道路の建設の重要性や都市内の道路の建設の必要性が指摘されている。特に雨季においては、道路交通が途絶えてしまう多くの農村地域が存在しており、農村からの生産物の出荷等のためにも地方農村道路の建設は重要性が高い。また、道路の維持管理が非常に不十分であることも指摘されており、さらに、道路の建設や整備に関する管理・運営および企画能力が弱いことも指摘されている。一部の道路へのコンセッション方式による民活の導入も検討されており、その法案が準備されている。その新しい方式の導人により、商業ベースで採算のとれる輸送インフラについては、民活方式に委ねることも今後の課題の一つとなっている。
(3) 電力関連のインフラと我国の経済協力
水力発電による電力エネルギーは、パラグアイが有する重要な資源であり、既にブラジルとの共同プロジェクトによって世界最大のイタイプ発電所(総出力1,200万キロワット)およびアルゼンチンとのプロジェクトによるヤシレタ発電所(総出力300万キロワット)がある。この他、これらの大規模発電所が実現する前に建設されたアカライ発電所(総出力19万キロワット)がある。
パラグアイの電気事業は、電力公社(ANDE)とイタイプ公社とによって運営されている。イタイプ発電所には18の発電タービンがあり、その半分がパラグアイ側に帰属するが、パラグアイの電力需要は1基で間に合うので、余剰電力は全てブラジルに輸出されている。これらのイタイプ、ヤシレタ両水力発電所のパラグアイにとっての経済効果、特に外貨獲得効果はきわめて大きい。1992年から95年の期間両発電所は、年間平均4億2,500万ドル(GDPの4.7%に当たる)を獲得してきた。これらは、発電所のロイヤリティー、補償金および建設や操業のサービスに対する支払いからなっている。
パラグアイは、このようにブラジル、アルゼンチンとの共同事業によって、発電能力に関しては十分な余剰を有している。しかし送配電網は不十分であり、特に電力の主要消費地であるアスンシオン等への送電網を整備することが重要な課題となっていた。先にも述べたように、40年前にアカライ発電所が建設され、そこから第一次、第二次および第三次にわたる送電線の建設が行われてきたが、さらに新たな需要に対応するため、第四次送電計画が作られ、これに対して日本の有償資金協力が行われた。この協力はパラグアイの送電網整備にきわめて重要な役割を果たしたと考えられる。この第四次送変電計画は、220キロボルトの電圧での総延長322キロメートルの送電線と、同じく220キロボトルの電圧での28キロメートルの送電線を建設することおよび5カ所の変電所の新設および既設変電所の増設からなるものであった。この他、各変電所にPLCシステムを新設するとともに、UHFラジオシステムの設置が行われている。
この第四次計画は、1990年に完了したが、送電網の必要性から見て、非常に適切なプロジェクトであり、また、イタイプ発電所完成の時期にもあたり、きわめてタイムリーなプロジェクトであったと考えられ、パラグアイ側から高く評価されている。なお、1991年に20日間におよぶ大停電が起こったが、これは第四次の送変電網以外の送電施設が暴雨風のために倒れたことによって起こったものである。従って、我国の経済協力による第四次計画による送電網がなかったならば、復旧により多くの日時を要し、社会・経済により深刻な影響を与えたであろうと考えられる。
第四次の送変電計画は、土木基礎工事や据えつけ工事も含めて円借款で行われているが、この時の基礎工事が非常に適切に行われていたことから、他の送電施設が暴雨風のために倒れたにも関わらず、我が国の円借款で行われた送電施設には大きな被害がなく、従って、その施設を用いて電力の供給を継続することができたことによるものであるとされる。なお、このプロジェクトはイタイプ発電所からのアスシンオン首都圏への送電の他、パラナ川西岸(チャコ地方の一部)の電化の促進にも貢献している。
現在、第六次送電網の整備が行われているが、電力公社の資金不足などからその進捗は遅れている。今後の課題として送配電網の整備の他、農村等の電化をさらに進める必要があると考えられる。MERCOSUR域内で最も電化率の高いアルゼンチンを100とするとパラグアイは69であり、ウルグアイの93、ブラジルの91と比較して、かなり低い水準にある。
(4) 上・下水道の現状
この他、インフラ整備の分野では、上水道や下水道の整備も重要である。上下水道の整備に関しては、パラグアイはMERCOSUR諸国の中で最も遅れており、安全な水を利用することのできる人口は約60%にとどまっており、また下水道を利用することのできる人口は30%にとどまっている。農村では水道を利用できる人口は20%に過ぎない。
都市人口の90%に上水道を整備し、また80%に下水道を整備するためには、今後15年間にわたって年間3,500万ドル程度の投資を行う必要があるとされている。アスンシオンおよび4,000人以上の都市地域の下水道はCORPOSANA(下水道公社)の管轄となっているが、下水道整備は非常に遅れている。その要因として、管理が不十分であることや、投資が十分に行われていないことが挙げられている。また、水道料金が低く、必要な費用を賄うことができないこと、漏水が大きいこと、水道料金の徴収が不十分であることなども指摘されている。
(5) 空港
公共事業通信省が円借款により建設したストロエスネル空港は、1996年1月よりディナック空港公団に運営委託ざれているが、現状の貨物を主とする発着便からの収益で当面の経常経費を賄っている。現在の航空機の発着便数は、当初計画をはるかに下回るものであり、その点では十分に利用されているとは言い難いが、 空港で使用する一部の機材を有効に利用して地域住民への社会的サービスも行っている。
他方、施設については、建設コストが大幅に増加したために空港規模が30%縮小されており、公団に引き渡された時点で施設・機材に技術的欠陥が見られた等の問題がある他、公団による施設運営においても、建設工事発注の際の契約仕様書が公団側に渡されていないために施設・機材の修復の際に問題が生じており、 また、建設工事を担当した公共事業通信省と公団との連絡・責任体制も確立されていない。このような事情から、空港は現在も未だに完全に機能を備えるに至っていない状況であり、安全面、財政面で効果、効率が十分に発揮されていないなどの問題を残している。しかしながら、空港公団側が述べるように、現在空港近くで計画されている台湾の工業団地の進捗、シウダ・デル・エステを中心とする貿易貨物の増加如何によっては、経常経費以上の収入が期待され、そのような条件が整えば財政面での効率の向上は期待できるとも思われる。さらに、国際空港がアスンシオンと当空港のみであることを考えると、当空港が近隣国の国際空港へのアクセスという戦略的意味合いを持つという空港公団の説明も理解すべきであろう。
(注1:1999年3月、パラグアイ側作成の「事業完成報告書」により、貨物便については十分に活用されていることが確認された。)
3-3.人的資源開発分野
(1) 現状
メルコスールの進展と市場のグローバル化にともない、パラグアイ産業も厳しい国際競争にさらされようとしている。質の高い労働力の形成とともに、メルコスールによって引き起こされる労働市場の調整が重要な課題となっている。メルコスール加盟諸国の中で、パラグアイの教育の遅れは、独裁体制下での教育分野の軽視という要因もあり、質・量ともに深刻だといわざるをえない。地域統合や知識情報社会への参入の準備において、その基盤は著しく脆弱というべきだろう。
都市と農村の格差や貧困の改善、社会的統合の強化、民主化への寄与という点においても、教育など人的資源分野のはたすべき役割は大きく、企画庁、文部省など政府関係者も認識しているところである。また社会的統合を考えるに際してパラグアイ特有の問題である、公用語としてのグアラニー語と二重言語政策を、経済統合による同質化との関係でどのように位置づけるかについても、重要な岐路に立たされているともいえる。
初等・中等教育の合計就学率(1992~94)は78%で、アルゼンチンの93%、ウルグアイの95%、ブラジルの96%と比べ、メルコスール諸国のなかでパラグアイは大きく水をあけられている(UNDP,Human Development Report 1997)。
小学校への入学率は95%と高いが、初等・中等教育ともに、ドロップアウトの割合が著しく高いのが特徴で、卒業生の割合は約半数にすぎない。初等・中等教育の平均就学年数は都市で6.2年、農村で3.5年である。初等教育への入学者で、中等教育を終了する卒業生の比率は17%と、5人のうち1人にも満たないのが現状である。経済活動人口のうち中等学校卒業者は21%、何らかの高等教育を受けた者の割合は9%に満たず、きわめて低い割合となっている(1992年センサス)。
教育関連の基本的インフラも貧弱である。電気を備えた学校は55%と半数以上に達しているが、水道は25%、トイレは31%、電話にいたっては15%の学校に備わっているにすぎない(Mapa Educativo Nacional 1995)。教材、教育機器や設備等も絶対的に不足している。とくに農村部でのインフラは劣悪である。
ソフトな教育インフラも基本的に未整備である。教育の社会的地位も低く、無資格教員の割合が30%に上り、農村でその比率は倍増する。カリキュラムも限定的で、授業方法も教師が教科書内容を板書し、それを清書することで終わるなど、児童生徒を受動的な立場にとどめた伝統的な形態がつづいており、労働市場に参入しうるところまでスペイン語能力や基礎学力を習得するには不十分であることが関係者から指摘されている。
また人口の39.2%が、グアラニー語の支配的地域に居住しており(1992年センサス)、小学校約5,000校のうち、2,000校がそうした地域に位置する。グアラニー語が公用語として認定され、二重言語教育が必要となっているが、グアラニー語のみを話す児童に第二外国語としてスペイン語を教える方法やカリキュラムも確立しておらず(その逆もしかりである)、またそれを担う能力をもつ教員の数は絶対的に不足している。それを改善するためには、大量の教員の再教育が必要であるが、教員を養成する大学教育も不足しているのが現状である(Gynan, Shaw N, "El bilinguismo paraguayo y la problematica de identidad nacionale integracion en el Mercosur, Mercosur: Integracione Identidad, Apep, 1997")。こうした状況を改善するため、1990年文部省に教育改革審議会が設置された。1994年から米州開発銀行(IDB)と世界銀行の協力を受けて、カリキュ ラム、教育書、教育方法、学校施設、教員の再教育、教育行政等を含む、義務教育9年間の全面的な教育改革が具体的にスタートしている。
さらに、地域統合とグローバル化の時代において義務教育の普及による基礎教育の目標を達成するため、米ハーバード大学国際開発研究所HIIDの協力を得て、1996年に、教育改革の戦略的プラン(「パラグアイ2020」)を策定している。
(2) 日本の協力
人的資源形成の分野に対する日本の協力は、職業訓練にほぼ特化する形で進められてきたのが特徴であり、教育分野では青年海外協力隊の派遣にとどまっている。これは、パラグアイ政府の人的資源開発にかかわる長年の政策と符合するものであり、またわが国としても人的資源開発分野においては、職業教育が協力を行ないやすい分野であったためであろう。
1) 実績
日本の人的資源開発の協力案件は、文部省所管の「職業訓練センター」、司法労働省の職業訓練局(SNPP)に対する協力、電気通信公社(ANTELCO)の「電気通信訓練センター」、アスンシオン市所管の「パラグアイ・日本人造りセンター」の4件に集約される。
文部省所管の「職業訓練センター」は、1977年に無償資金協力によって施設が建設され、83年までプロ技協力が実施されるなど、早い時期から協力が積み重ねられた。電気、電子、自動車整備、機械、冷凍、配管、建築、木工、デザインに関わる職業訓練を初等教育修了者に対して行う職業中学の位置づけである。
司法労働省の職業訓練局(SNPP)に対しても20年来の協力が行われてきたが、1987年に無償資金協力により機材供与を行って、サンロレンソ校に電気・電子コースを設置し、その後、同コースに対し個別専門家の派遣を継続的に行った。97年からは、SNPP側が自ら施設の増改築を行い、日本パラグアイ職業能力促進センター」として発展的に拡大を図ることとなった。そのため協力内容を拡大し、従来の電気・電子・統御の各技術移転に加え、冷蔵・空調技術の訓練指導員の再訓練を目指した協力関係が、プロ技協でスタートしたところである。
電気通信公社(ANTELCO)の「電気通信訓練センター」は、1991、92年に無償資金協力による建物の建設と機材供与が行われ、92年から97年までプロ技協が行われ、99年3月末までフォローアップ協力を実施中である。
アスンシオン市所管の「パラグアイ・日本人造りセンター」は、一般プロジェクト無償と文化無償の組合わせで実現したが、文化無償で供与されたコンピューターはSNPPに委任され、コンピューター技術の研修に活用されてきた。
2) 評価
これらの職業訓練は、初級および中堅技術者育成という点で、産業・雇用等の波及効果も高いと評価される。とくに在職者の能力開発のために行われてきた高等職業訓練のプロジェクトは、メルコスールの進展によって産業の再転換が要請される中でも十分に対応できる協力と判断される。
各プロジェクトは、それぞれの機関において、中核的な教育施設、研修機関と位置づけられており、関係者の評価も総じて高いものがある。とくに「電気通信訓練センター」は、アスンシオン大学の工学部、電気通信管理行政訓練センターとともに電気通信分野の三大高等教育機関として位置づけられ、相互の協力関係が行われている。
これまで職業訓練の分野においては、スペイン、ドイツなど各ドナーが協力を行っているが、日本のもつ多様な協力スキームの組み合わせと十分な活用によって、長期にわたって協力が体系的発展的に実施されてきたことは、他のドナーによる協力形態と比べても、大いに評価されるべきである。
職業訓練局(SNPP)の電気・電子コースの修了者数は、1990年以降95年までの6年間に8,597人に達し、またコンピューター・コースは89年以降32,705人に達している(Ministerio de Justicia y Trabajo, 25 anos 1971-1996: Servisio Nacional de Promocion Profesional, Asuncion)。
「人造りセンター」は、数少ない充実した多目的な文化施設として、活発な事業が行なわれており、施設利用度も高く、各種イベントヘの参加者の数は年間7万人(1995年)に達している。国立シンフォニーや日本以外の外交団によっても活用され、現地の社会文化発展に貢献するところは極めて大きい。
各プロジェクトの認知度も高く(とくに「職業訓練センター」)、供与機材や建物の維持管理もしっかりなされている。
自立発展性も、案件によって若干違いが見られるが、総じて高い。
「電気通信訓練センター」は、カウンターパートの待遇改善、研修員の受講に当たってのインセンティブの付与、送迎バスの用意等、自助努力を積極的に行い、センターの発展的な活用が図られている。南米地域の優れた通信技術教育センターとして地域機関から認定され、域内諸外国から研修生が訪れていることは、 関係者の誇りとなっている。これは、「電気通信訓練センター」の設備内容にみられる質の高さや案件に関わった関係者の力量にも原因があるだろうが、電気通信公社の管轄にあるためローカルコストを自主的に負担しやすいという条件とも関係があろう。
司法労働省の職業訓練への協力が日本パラグアイ職業能力促進センター」に発展することになったが、このプロジェクトは、パラグアイ政府側のコスト負担が前提となった性格のものであり、自立的発展の形態の一例として評価できる。それは地域統合への動きの中で、人的資源開発の重要性と、4半世紀にわたりそれを管轄しノウハウを蓄積してきたSNPPの重要性が、政府内でも認識された結果と考えられる。近年、SNPPの予算規模は順調に伸び、予算執行率も1995年は97%となっている。だが「日本パラグアイ職業能力促進センター」が計画通り進展するためには、政府予算が執行されてセンター施設の増改築が予定通り行われること、設備機材の近代化、またカウンターパートの安定的な確保・定着が前提となっている。とくにカウンターパートの安定的な確保という点においては、プロ技開始時点での日本側専門家の苦慮するところとなっている。
「人造りセンター」に見られるように、財政運営の厳しさのために、自立的な事業展開や発展が困難となる可能性をもつところがある。「人造りセンター」の収支のうち、管轄の市役所からの交付金は収入の40%をまかなうにすぎず、残りは施設の使用料等によってまかなわれている。支出の80~90%が人件費に充てられており、機材や施設の維持のみならず、更新に充当される予算はきわめて限られているのが実状である。
3) 検討課題
協力を行なってから、20年から10年以上を経過している案件があり、施設・機材の老朽化が進んでいる。それに対する対応の時期がせまっている。自助努力を促すことは当然ながら、不可能な場合には、追加支援の協力のあり方を考えていくべきであろう。
一般無償資金協力が1999年度をもって終了することに鑑み、従来のような施設の建設・機材供与を無償で行い、プロ技協につなげていくという協力形態が見直しを迫られているが、パラグアイ側に一層のオーナーシップを求めていくことが必要となっている中で、有償資金協力を人的資源開発分野にも導入することが検討されるべきである。
この点で施設増改築や設備の更新をパラグアイ側が負担する「日パ職業能力促進センター」にみられるような自立発展度の高いとみられる案件を積極的に支援していくことが肝要であろう。なお「人造りセンター」で行われていたコンピューター研修は、コンピューター機器の老朽化と、センターが徴収するコミッションが高いことを理由に、SNPPが事業から撤退したため1996年末で停止しているが、センター側の意向では、民間会社との契約で設備を更新し、研修事業を再開したいとのことであった。
パラグアイを取り巻く大きな環境変化の中で、職業訓練の産業への波及効果を高めていくには、政府の産業政策や産業界との有機的連携や協力関係が必要である。メルコスールにおいて、パラグアイが競争力をもつ分野の特定とその振興策に沿った形で、低廉かつ能力のある労働力の育成を考えていく、そのための職業訓練のあり方と分野、方向性を検討していくことが重要な段階となっている。その点からすれば、案件によってはすでに20年近い年月が経過したプロジェクトについては、パラグアイ側との間で、既存の協力内容の見直しや方向性の再検討を行うことが必要であろう。
またIDBは、人的資源開発制度全般の近代化を促すため、1995年に専門的職業開発制度の導入に対する協力をパラグアイ政府と間で行っており、その中でSNPPの位置づけも再検討されてきている。政府及び関連機関、国際機関との密接な連携関係が必要上たっている、
3-4 保健医療分野
(1) 我が国の保健分野への援助
我が国がこれまで行ってきたパラグアイの保健医療分野への主な援助は下記の通りである。
- 無償資金協力:厚生省中央研究所/熱帯病病院建設計画(1981年度、14億円)、アマンバイ地域医療センター建設計画(1984年度、7.06億円、85年度、7億円)
- プロジェクト方式技術協力:らい対策(1970年12月~81年3月)、厚生省中央研究所(1980年8月~87年8月),文部省アスンシオン大学保健科学研究所(1988年3月~93年3月)、地域保健強化プロジェクト(1994年12月~99年11月)
- 個別専門家派遣:35名、派遣総数234名の15%(1986年~96年)
- 青年海外協力隊派遣:77名、派遣総数595名の13%(1978年~97年)
- 研修:208名、研修員総数1,422名の15%(1952年~96年)
- シニア海外ボランティア:4名、派遣総数25名の16%(1992年~97年)
(2) パラグアイの保健状況
パラグアイの保健指標を周辺国と比較すると表4-1の通りである。
| パラグアイ | アルゼンチン | ボリビア | ブラジル | ウルグアイ | |
| 総人口(1,000) | 4,957 | 35,219 | 7,593 | 161,087 | 3,204 |
| 5歳未満児死亡率(1/1,000) | 34 | 25 | 102 | 52 | 22 |
| 1歳未満乳幼児死亡率(1/1,000) | 28 | 22 | 71 | 44 | 20 |
| 粗死亡率(1/1,000) | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 粗出生率(1/1,000) | 32 | 20 | 34 | 20 | 17 |
| 平均余命(歳) | 69 | 73 | 61 | 67 | 73 |
| 妊産婦死亡率(1/100,000) | 160 | 100 | 650 | 220 | 85 |
| 保健員の付添う出産率 | 66 | 97 | 47 | 88 | 96 |
| 適切な衛生施設を持つ人の比率 | 41 | 68 | 55 | 44 | 91 |
| 保健サービスを受けられる人の比率(全国) | 63 | 71 | 67 | - | 82 |
| ポリオ予防接種率 | 79 | 70 | 86 | 83 | 86 |
パラグアイの保健状況は、上記の指標に見られるように、粗死亡率も低下し、平均余命も他の国と同位のレベルにある。パラグアイの公衆衛生は、1970年代から80年代にかけて予防接種などが大幅に改善され、乳幼児死亡率も低下した。従来の重大疾患であった下痢症、呼吸器疾患による死亡率も近年大幅に減少している。しかしながら、妊産婦の死亡率は周辺国のなかでも依然として高く、その原因は、妊産婦の約40%が伝統的産婆による出産をしていること、妊娠時の検診率が30%以下と低いこと、出産後のケアが不適切であることなどがあげられる。また、最近では未熟児の出産も増加傾向にあり、寄生虫、ガン、循環器疾患、精神病などの疾患も増加しつつあることから、予防や生活習慣についての保健教育が重要となってきている。シャーガス病などの熱帯病も見られるが、発生率は地方によって異なる。
都市部と農村部とを比較してみると、1995年時点で、総人口に占める保健サービスを受けられる人の比率は、都市部で90%、農村部で38%、全国レベルで63%となっている。この様に、都市と農村の間の保健医療サービスヘのアクセスには格差が見られるが、その原因はインフラの整備状況が良くないことと、医療従事者が都市部へ集中して地方の医療施設に十分配置されないことにある。パラグアイでは全ての一般労働者は社会保険院への加入が義務づけられているが、その加入率は全労働者の19%と低い。
(3) パラグアイの保健政策
現在の厚生省の政策は、パラグアイの保健状況に沿ってプライマリ・ヘルス・ケア(PHC)に焦点を当てた妥当なものであると言えると同時に、地方分権を進めるなかで住民参加を促進するプログラムの実施は、今後の自立発展を強化する方向として十分評価できる。
同国企画庁が1995年3月に発表した「国家開発計画(1995-1998)-バランスのとれた持続的開発」によると、保健分野では下記の国家政策が掲げられている。
- 社会的弱者および貧困者を対象とする予防・医療活動の充実
- PHCの優先と保健教育・予防医療の強化
- 総合的なシステムの展開による合理的、効果的、バランスのとれた活動
- 保健システムの修復・改善と医療技術の向上
- 地域住民と組織の参加促進
- 国民の参加による保健活動の統合
- 公的保健システムの開発と充実
- 地方分権の強化
このような国家開発のなかで、厚生省は「2000年には全ての国民が健康に」をスローガンとして、妊産婦および新生児の死亡率低減を目指したPHCを導入した政策を展開している。PHCを展開するに当たっては、地方分権化の方向で行政改革を図っており、全国を18の保健行政区に区分し、地域には厚生省の管理する保健委員会を設置して、地方の協力を得ながら国民の健康改善・維持に努めている。最近の政府予算を見ると、現政府がいかに保健分野を重視しているかが窺える。表4-2は1996年の政府予算配分を示すが、厚生省の予算は農牧省、国防省の予算規模にほぼ匹敵する。
| 債務返済 | 1,016,000 | 24.3% |
| 文部宗務省 | 735,300 | 17.6% |
| 公共事業通信省 | 553,200 | 13.2% |
| 農牧省 | 306,600 | 7.3% |
| 厚生省 | 298,900 | 7.1% |
| 国防省 | 293,100 | 7.0% |
| 大蔵省 | 278,000 | 6.6% |
| 内務省 | 267,100 | 6.4% |
| その他 | 438,800 | 10.5% |
| 合計 | 4,186,900 |
(資料:JICA「国別協力情報ファイル」)
PHCを促進する保健政策は地方に向けて展開されているが、パラグアイの都市の人口比率が53%と低く、地方人口が比較的多いことを考えると、地方の社会的弱者や貧困層に的を当てたこの政策は現在の人口分布と経済格差を的確に捉えたものといえる。この地域保健のモデル・プロジェクトと言われているものが、我が国のプロジェクト方式技術協力を得て進めている、第6保健行政区(カアサパ県)の地域保健強化プロジェクトである。厚生大臣は、このプロジェクトの成果を高く評価し、厚生省中央研究所へ我が国の協力と並んで同プロジェクトに対する協力に深い感謝の意を表した。
厚生大臣の説明によると、カアサパのプロジェクトには地方住民が積極的に参加しており、その資金については中央政府と県、地方自治体、地域住民がそれぞれの立場で負担している。人材育成センターも建設され、助産婦を含む医療従事者がそこで育成されている。また、保健所に所属する保健促進員により保健と出産に関する妊産婦への啓蒙・教育が行われ、妊産婦の死亡率の低下を目指している。このようにカアサパのプロジェクトが成功を収めつつあることから、同大臣は、コンセプシオンを次の候補地として同様のプロジェクトを展開したいとしており、その後も各農村地でその地域にあった形の地域保健改善プログラムを進めたいという意向である。
中央政府と県、地方自治体および地域住民の参加のあり方は、地域の経済状態や社会状態により異なるのが当然であり、その地域にあったプログラムを地域別に策定する必要があろう。
上述のような地域保健医療の改善には、日本を中心とする二国間援助機関や国際機関の協力が不可欠となっており、カアサパのプロジェクトでも、我が国の援助資金とパラグアイ側負担との割合は100対25である。このパラグアイ側の資金については、中央政府、県、地方自治体が共同で担っている。日本のほかには、USAID、世銀、GTZ等も保健医療分野への協力に興味を示している。そのなかで、我が国の技術・資金協力は今後とも期待されているところである。
(4) 現地調査プロジェクトの評価
1) 厚生省中央研究所/熱帯病病院
(1981年度無償、プロ技;1980年8月~1987年8月)
本プロジェクトでは、1981年、首都アスンシオンに病院と研究所の施設および機材を無償資金協力で整備し、その後1987年8月まで中央研究所に対する技術協力が行われた。病院は合計50床の規模であり、他方、研究所はスタッフ50名を抱えて各種検査・研究業務を行っている。中央研究所に対しては、臨床検査分野の 技術移転、熱帯感染症の研究、検体輸送システムの向上、効果的な検査・研究のための組織管理システムに関する協力が行われた。
その後、我が国の技術協力による専門家帰国後の1993年頃から研究所業務の質が低下し、2年後にはその問題が新聞等マスコミに取り上げられるまでに至った。問題を憂慮した研究所職員は、同研究所を病院から分離・独立させることを厚生省に要請、その結果、1996年3月に中央研究所が病院から分離された。研究所業務の質の低下の原因は、病院に対して研究所の規模が大きいにも拘らず、病院と研究所の両機能を医者が一元的に管理・運営して病院業務に偏ってしまったことである。
分離独立した中央研究所は、立ち上がるためのフォロー・アップ協力を我が国に要請し、約3万2000ドルの試薬の購入、20項目に亘る機材、専門家の派遣が実施された。現地調査時には、JICA専門家1名が派遣されていたが、研究所は組織改革を行い、現在では全ての職員が所定の業務について無駄のない作業を行っている。現在の中央研究所の業務は以下の通りである。
- 各種検査業務
熱帯病病院の検査依頼が全体の20%。24時間体制で検査を行っており、機材も近代化して一部自動化されている。検査機器の維持管理体制も整っている。 - 国立・民間研究所の支援・技術評価
- 医療従事者の教育訓練(短期訓練コース)
- 病理研究(シャーガス病、デング熱、インフルエンザ等)
これらの業務については、その質も改善され、業務量も増加している。また、隣接する病院に対する検査業務の支援もこれまで同様行っているが、研究所を訪れる患者は毎日平均3,000人、多い時には4,000人という(図4-1参照)。
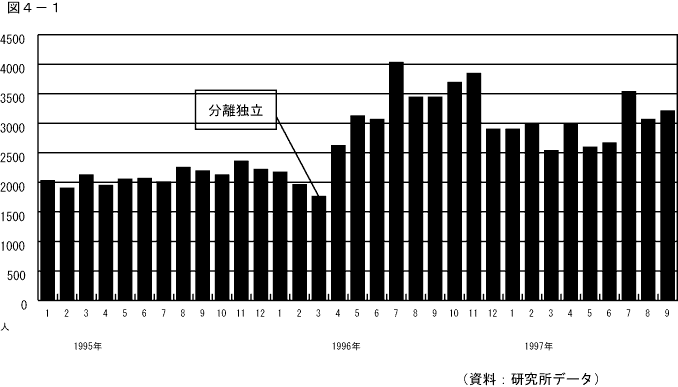
このように現在では我が国の協力の成果が発揮され、研究所長以下スタッフ全員が我が国の援助に深く感謝している。プロジェクトの内容については、機材の選定においてアフターサービスも含めて適切な医療機材が供与され、一部の老朽化した機材を除いては、現在でも十分利用されていることから妥当な内容であると言えよう。研究所は、今後、サービスの地域的拡大を計画しており、他の研究所や病院へのサービス提供も考えている。研究所は、ここに至ってようやく、自立発展の緒についたと言えよう。
プロジェクトの成功した要因について推察すると、(1)我が国の無償援助、プロジェクト方式技術協力、研修員受入れの組み合わせによるパッケージでの協力を行ったこと、(2)プロジェクト方式技術協力を一貫して順天堂大学が受けたこと、(3)スタッフ50名のうち30名が日本で研修していること、(4)上述の通り、スタッフのオーナーシップの意識が高く、質の低下を改善するために研究所の分離独立を自ら進めたほどの意欲、などがあげられるが、特に(4)で述べた研究所スタッフの自立意欲の強さは、今後の本プロジェクトの発展に大きく寄与するものと考える。
今後の問題点としては、研究所が他の地域ヘサービスを拡大していく際に、いかに地方自治体と厚生省との協力関係が構築できるかという点と無償で供与された医療機材の部品をいかにスムーズに調達できるかの点であろう。
2) 地域保健強化プロジェクト(プロ技;1994年12月~1999年11月)
本プロジェクトにおける我が国の協力は、カアサパ市(アスンシオンから南東に150キロメートル)を中心とする第6保健行政区(カアサパ県)におけるPHCサービスのシステム構築の支援である。第6保健行政区は東西に140キロメートル、南北に約100キロメートルの面積で、人口が約14万人。行政区のほかには、地域病院のほかに6個所の診療所、36個所の保健所がある。
このような地域における本プロジェクトの目的は、日常的な公衆衛生知識の啓蒙、身近な診療施設における発病段階での適切な医療サービスの提供、妊産婦および乳幼児の健康確保などであり、第1段階(調査、1.5年)、第2段階(活動、3年)、第3段階(評価、0.5年)に分けて実施されている。現在では既に後半の実施段階に入っており、専門家派遣、医療機材、IEC関連機材、無線、車両などの機材供与、カウンターパート受入れなどが行われている。
このプロジェクトの特徴は、住民の参加により、地域の住民が行う保健強化を日本の専門家が手助けをするというもので、地域住民の組織の活性化から始められている。
我が国の協力に対する現地関係者の評価は高い。なかでも、専門家による集団移動検診、寄生虫の予防、中堅技術者の指導・育成などへの技術協力と、各医療施設間で使用する無線設備、自動二輪などの供与が、地域保健サービスを住民にとって身近なものにしている。カアサパ県は特に開発の遅れていた地域(1992年まではグアイラ保健行政九に属していた)であるだけに、住民の健康維持に関する意識も低く医療サービスヘのアクセスも良くなかった。
また、健康維持に関する意識の向上を示すものとしては、この地域の住民代表者から構成される保健組合が保健所の支援グループとして活躍しているが、保健婦などのボランティアを出しているほか、資金を出し合ってそれにより保健所維持のための補修、塗装アクセス道路の改善などを行っている。これは地域住民が共通の利益のために、自分たちの資金で、自ら健康を維持しようとする意識の表れであり、強いオーナーシップあるいは自立意識の結果と言える。
県と地方自治体の努力により、カアサパ県の保健所ではサービスを無料化する方向で対応している。パラグアイでは県単位で保健医療サービスの料金が決定されるが、カアサパ県では既に、5歳以下の児童、妊産婦、呼吸器疾患などの特定重大疾病患者、貧困者に対しては無料サービスを行っている。
今回の現地調査においては、各医療施設の管理者が当方調査団に対する説明、案内を自ら行い、十分な説明と日本の協力に対する感謝の気持ちを伝えた。このことは、各施設の管理者が状況を十分把握しているということと、強い自立意識の表れであり、今後の発展・拡充に大きな期待が持てるものと推される。
(5) 全体評価
パラグアイの保健医療分野に対する協力は、現政権の政策が妥当なものであり、我が国がその政策に沿って実行したものである。
協力の内容は概ね妥当であり、その社会目的も達しつつ、関連施設・地域への波及効果も見られる。効率の側面については詳細な検討なくしてコメントすべきではないが、他の援助機関との比較から見ると、我が国援助は効率の面からも妥当なものといえよう。特に、USAIDは保健医療分野を重点セクターと捉えたうえで、我が国援助を高く評価している。
我が国の保健医療分野への協力は、過去、プロジェクトとして見る限り6件と数は多くなく、その歴史も長くはないが、全体としては十分評価できると考える。

