第七章 援助実施体制評価
インドネシア
(現地調査期間1996年1月10日~1月19日)
<評価調査団の構成>
門田 英郎 財団法人国際開発センター理事・顧問
佐佐木健雄 国際協力事業団企画部評価監理課
田中 秀和 社団法人海外コンサルティング企業協会
島津 英世 社団法人海外コンサルティング企業協会
下村 暢子 社団法人海外コンサルティング企業協会、他
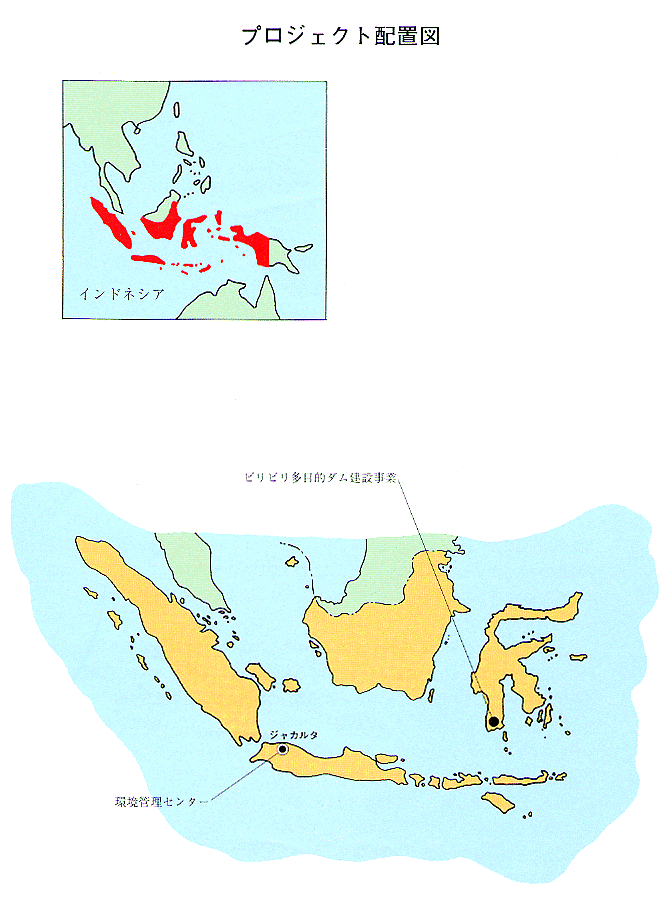
I. はじめに
日本の政府開発援助(ODA)が真に被援助国の発展に役立つためには、近年の国際社会の変化や被援助国の発展に応じ、また相手国援助ニーズの変化に対応して、日本のODAもその実施体制を変えていく必要がある。外務省ではODAの各段階における教訓を学ぶ従来の評価を越え、我が国援助実施体制をふり返るため、平成7年度に援助実施体制評価制度を導入した。その最初のケースとして、日本ODA供与累積第一位であり、かつ近年経済発展の著しいインドネシアを対象に、より望ましい援助実施体制を検討することとなった。
インドネシアヘは、平成6年2月に「対インドネシア経済協力総合調査団」(松永ミッション)が派遣されており、日本からの援助の重点分野として、1)公平性の確保、2)人造り・教育分野、3)環境保全、4)産業構造の再編成、5)産業基盤整備、の5分野を取り上げることが両国政府によって確認されている。今回の調査では、これからの対インドネシア援助の新しいテーマである1)貧困撲滅、2)環境保全、3)人造り・教育、及び4)草の根レベルの協力促進を念頭に置きつつ、インドネシア政府、在外公館、援助実施機関、国際機関、NGOの関係者と意見を交換し、プロジェクト・サイトの現状を詳細に視察する機会を持ち、いくつかの提言をまとめた。これらの提言はインドネシアにおける調査の結果得られたものであるが、他の開発途上国に対する援助を実施する上で参考となる部分が多いと思われる。
II. 新しい援助テーマヘの日本の援助の対応
日本の対インドネシア援助はこれまで同国の開発ニーズに沿って、経済インフラの整備(有償)、農業、保健・医療(無償)、多分野の人造り(技術協力)を中心に行われてきたが、近年のインドネシアの開発ニーズの変化を受けて新しいテーマヘと移行しつつある。1994年2月に派遣された「対インドネシア経済協力総合調査団」(松永ミッション)では公平性の確保、人造り・教育、環境保全などの五つの重点分野について両国間で合意され、きめの細かい経済協力の観点から、各分野への協力に際しては、大型プロジェクトのみならず、小規模であっても住民に直接被益する草の根レベルの案件でも積極的に協力を進めることとなった。環境、社会開発といったこれらの開発における重点分野は国際的な開発の潮流に沿ったものでもあった。現在実施中のインドネシアヘの経済・技術協力案件はこのような指針に沿って選択され、実施されるように工夫がなされているといえよう。
例えば、「農村インフラ整備事業」では、インドネシア側の貧困村支援であるIDT(大統領特別基金)事業に対応し、貧困村のインフラ整備(道路、橋、さん橋、水供給)など既存の枠組みでは対象にしにくい小規模・多数の建設事業を一括し、ローカル・コストだけで実施するというスキームを既存の有償資金協力制度のなかで実現した。また、外貨支援を伴うセクター・プログラム・ローンでは、居住環境整備、保健、社会福祉など貧困層、へき地地域へ被益する案件が中心であり、現地で高く評価されている。技術協力では、南スラウェシ州バル県において1995年より青年海外協力隊をチームで派遣し、村に滞在させながら農村における開発の試みを行っている。さらに、スラウェシ貧困対策プロジェクトとしてプロジェクト・タイプ技術協力をスタートすべく、長期派遣専門家を内務省へ派遣し、住民参加型開発プログラムなどの開発手法を整理しながら準備中である。
このように、在外公館や援助実施機関は既存の援助スキームの枠のなかで創意工夫しながら、シフトしつつあるインドネシアの援助ニーズに対応している。今回の調査を通じて、これら新しいテーマにより効果的・効率的に取り組むためにはさらに改善・工夫すべき点もあると思われたので、本調査の主なテーマである貧困、環境、人材、草の根などの援助テーマを中心に以下の提言をとりまとめた。
III. 提言1 効果的な案件の発掘・形成のために
日本のODAでは、被援助国の当該開発案件に取り組む意志と自助努力の意志の確認を行った上で援助を実施している。相手側実施機関において、援助後の自立性を確保する体制がとられなければ、援助案件の効果は期待しにくい一方、案件の発掘・形成に対して受け身のままでは優良案件への協力の機会が少なくなる。このため、技術協力あるいは無償、有償資金協力の一環として、日本側のイニシアティブで対象となる優良案件を発掘し形成する努力が行われており、年々拡充されている。
本調査の対象テーマである貧困撲滅、環境保全、人材育成あるいは草の根レベルの協力は、いずれもソフト面が鍵をにぎるテーマである。またその内容は、人々の生活や慣習などの社会的側面に強く影響されるもので、地域的バリエーションがあるために定型化できないなど、案件形成がより難しい側面を持っており、以下のような工夫が必要である。
1. 長期派遣者の活用による案件発掘・形成
JICAの長期派遣専門家や青年海外協力隊員などは、現地に長期滞在し、現地の社会、風土、慣習、法制度、地方の開発の現状などを熟知しており、彼らの協力を得ることによって案件の発掘・形成がより効果的なものとなると言えるだろう。既にインドネシアでは、環境分野において環境管理庁に派遣されている専門家が環境管理センターの形成段階で活躍し、またスラウェシ島バル県に青年海外協力隊が派遣され、貧困農村開発の案件形成が行なわれていることは効果的な試みといえよう。
2. 案件発掘調査段階におけるNGO等の活用
貧困対策などのテーマを扱う場合、NGOが持っているノウ・ハウを利用する方法もある。NGOの活動そのものを支援する活動はこれまでも行われているが、NGOの持っている経験を開発調査や専門家派遣に活用しつつODA事業に取り組んでいくことも有用であろう。
3. 有償資金協力促進調査(SAF)の適用
OECFの借款案件形成のためのSAFでは、日本側のイニシアティブである程度の規模の調査を可能にしている。インドネシアではSAF資金により、貧困村に対するインフラ開発借款案件の形成段階で外国人2名、ローカル4名からなるコンサルタントが1ヵ月近くにわたって全国貧困村の調査を行った。この調査と分析の結果、各貧困村落における道路などのインフラ建設単価を積み上げ総事業規模を算出することにより、借款要請の基礎資料を提供することができた。
このような調査では、現地の事情に極めて精通し、長期にわたり現地事情を把握している専門家やローカル・コンサルタントによって案件の発掘形成が機動的になされる必要がある。有償資金協力案件においても、社会開発型案件が増加する傾向にある中、SAF予算を大幅に拡充し、被援助国の案件形成を支援する必要があろう。
4. 開発調査の活用
技術協力の一環として実施される開発調査では、「マスタープラン調査」などにより、広域的なテーマあるいはセクター振興という幅の広いテーマも援助対象として取り上げられている。環境保全については、既に大気、水などを対象とした調査が行われているが、貧困撲滅、人材育成などのテーマも開発調査の対象となり得よう。
IV. 提言2地方レベルの開発援助と面的展開にむけて
インドネシア政府は、第6次国家開発5カ年計画において「公平性の確保」を国家開発の中心目標に掲げ、地方の貧困層への対策を含めた国全体の均衡ある開発に取り組んでいる。インドネシア政府の貧困対策支援の要望に応えるべく、在インドネシア日本大使館の統轄の下、JICA及びOECF現地事務所は国家開発計画局(BAPPENAS)を始め内閣官房庁(SEKKAB)や内務省などの省庁と貧困対策支援プロジェクトの形成のための協議を重ね、既存の援助手法を組み合わせた、全国レベルのプログラム的な援助を展開している。
インドネシアにおけるアンブレラ協力や貧困対策支援事業での経験は、既存の援助手法を組み合わせることで、全国的規模の地域開発ニーズにある程度応えることが可能になることを示している。これは全国展開を視野に入れた地域開発を促進していく際に、無償・技術協力による個別プロジェクトを中心とした「点」的な援助を、種々の援助スキームを有機的に結び付けて「面プログラム」的援助へ拡大していく際のヒントになってこよう。以下、インドネシアの地域開発における日本の援助手法の新たな試みをまとめ、地域開発を促進していく上での今後の改善点を指摘したい。
1. 地方開発に携わる主要中央官庁での政策支援(専門家派遣)
効果的な地域開発を行なうには、被援助国の国家開発計画における地方開発のプライオリティーを把握し、他の援助機関との調整を図りながら、援助事業の計画・立案を進めていくことが不可欠である。インドネシアでは内務省にJICAから派遣された個別専門家が、南スラウェシで実施される農村村落開発プロジェクトの計画・立案を支援しているが、このように、地方開発に携わる主要中央官庁の政策担当部局に長期専門家が派遣されていることで、インドネシア政府の地域開発政策への日本側の理解が深まると同時に、インドネシア中央官庁側においても日本の援助についての理解が進んでいる。被援助国政府の中には、政策担当部局に外国人専門家を受け入れることに難色を示す政府もあろうが、日本側としては中央官庁における政策支援の重要性について被援助国政府の理解を得ていく必要がある。
2. 現地事務所のローカル・スタッフの質的向上
地方開発を効率よく実施するには、主要援助機関との調整、地方における援助ネットワークの確立、政府/研究機関/国際機関のワークショップヘの参加など、長期的視野に立った幅広い情報収集能力の向上が求められる。2、3年で移動する日本人スタッフだけでは継続的な情報収集活動は難しく、現地の状況に精通したレベルの高いローカル・スタッフを揃える必要がある。
3. 大規模経済インフラ案件から小規模社会インフラ案件へ(円借款)
OECFはインドネシア政府の貧困対策事業に応えるべく、農村地域での小規模社会インフラ事業「地方基盤整備事業」を展開している。インドネシア政府は本案件を地方開発の新たなニーズに的確に対応するものとして、非常に高く評価している。住民組織による貧困対策事業の促進を目的とするインドネシア政府の地域開発政策に応えていくには、このように、事業において地域住民もプロジェクト事業に参加できるような手法が必要になってこよう。
4. 地方行政組織における計画・立案・実施能力の向上(技術協力)
地方開発、特に、貧困対策を促進していくにあたっては、中央官庁のみをカウンターパートとした技術協力には限界がある。現在、南スラウェシ州で実施が検討されているJICAの「東部インドネシア開発政策・実施支援」では、地域と日常的な接触を持つ地方自治体の組織強化を図る技術協力プロジェクトの形成が進められている。
地方自治体の組織強化をめざすプロジェクトにおいては、地方自治体側とプロジェクト実施側との相互の信頼関係確立が重要である。プロジェクト開始前に、自治体に長期専門家や長期調査員を派遣するなどして、先方に日本のプロジェクトの理念や特徴を理解してもらうことが、円滑なプロジェクト実施につながると考えられる。
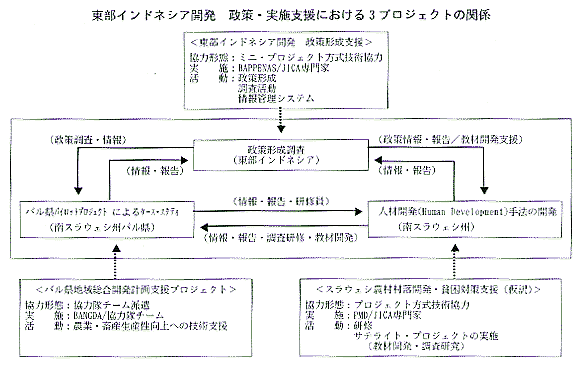
5. プログラム的援助計画の促進(有機的援助の促進)
個別プロジェクトを分野別に計画し、実施するだけでは、横断的なアプローチを必要とする貧困対策や人造り、環境保全などの新しい援助テーマに対応することが難しくなってきている。例えば、地方の貧困層の生活水準を引き上げつつ全国的に均衡のとれた開発を実現するような全国的規模の開発に取り組むためには、広範かつ複雑な現地の実情にきめ細かく対応していくため、既存の技術協力や資金協力等各種の協力形態を組み合わせつつ援助計画を作っていくことが重要である。
アンブレラ方式協力は、技術協力(プロ技・専門家派遣・開発調査等)及び資金協力(無償資金協力、有償資金協力)を組み合わせることにより、開発目標をより効果的・効率的に達成することを指向する対インドネシア農業分野における特有の協力方式である。
1981年度から1985年度までは「米増産協力計画」を、1986年度から1990年度までは「主要食用作物増産計画協力」を実施し、インドネシアの米自給体制の確立及び大豆等主要作物の増産に大きく貢献した。
1995年からは、「農民の生活水準の向上」を最上位目標とした第3次アンブレラ計画が、5カ年間の予定で実施されている。第3次アンブレラ協力では、この最上位目標を達成するために、八つの課題を協力の柱として、中央と地方の各々のレベルにおいて種々の具体的プロジェクトが実施されている。
なお、地方レベルにおいては、南カリマンタン州、西ジャワ州、西ヌサティンガラ州及び南スラウェシ州のモデル地域を対象に、各々のニーズに合わせた具体的な事業が行われることとなっている。
現在、このアンブレラ協力の他に、高等教育(HEDS)や南スラウェシの「東部インドネシア開発政策・実施支援」など各種スキームを兼ね合わせたプログラム的援助計画が進展中であるが、開発目標を効率的に達成するためには技術協力と資金協力のより有機的な結合が不可欠であり、プログラム全体における各協力スキームの役割分担・相互補完性を一段と明確にしつつ、その組み合わせに工夫がなされる必要がある。
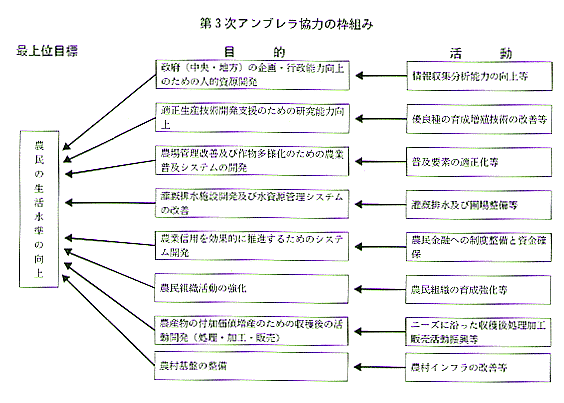
6. 全国的な規模を持つ現地のNGOやその他の組織を活用したネットワーク型援助
保健や教育、農業などの分野で研修、情報普及、技術普及を展開していく効果的な方法のひとつに、全国的なネットワークを持つ現地のNGOやその他の組織との協力を促進していくことがある。例えば、モスレム寺院の全国組織や家族福祉運動(Family Welfare Movement)は、特定地域や住民に活動が限定されがちなNGOに比べ、宗教や家族福祉といった社会的規範を共有している全国的なネットワークを有している。これらの組織ネットワークを活用すれば、住民レベルに至る普及活動が容易になる。全国規模の現地の組織との協力関係を進めていくには、政府カウンターパートのみを対象とする現行の研修システムに加え、現地組織のリーダーの研修、民間組織の運営指導など地域密着型で組織強化を図る指導を促進していくことも考えられる。また、地域を対象とした情報普及・広報活動を展開していく必要もあろう。現地組織との協力を促進するには、組織の指導者達との信頼関係を築くことが前提になる。そのためには、まず共同でセミナーやワークショップを開催したり、現場視察を行なうなどの定期的な交流から始めるのが妥当と思われる。
V. 提言3 プロジェクトの自立発展に向けて
開発プロジェクトの協力期間終了後、被援助国側政府の予算不足・人員不足などのため、プロジェクトの持続性が弱まるケースがある。この点を考慮し、協力期間終了後の自立発展までを念頭においた計画・実施がなされているのが「インドネシア高等教育開発計画プロジェクト(Higher Education Development Support Project:HEDS)」である。ここでは、HEDSを例にとり、開発プロジェクトの自立発展性について考察したい。
HEDS(インドネシア高等教育開発計画プロジェクト)の概要
インドネシア政府のめざす工業化推進に必要とされる高等教育を受けた人材は質・量共に不足しており、大学における工業教育の質の向上やスマトラ島・カリマンタン島、ジャワ島の高等教育レベルの格差是正が大きな課題となってきている。JICAは米国USAIDとの均等負担で、この解決を図るHEDSプロジェクトを形成の上、1990年4月から1996年7月までの間、協力を実施した。
HEDSプロジェクトは、スマトラ島・カリマンタン島にある20大学の理学・工学・経済学分野の高等教育の質的向上、特に教官の育成を目的としている。日本側が工学部の強化を受け持ち・米側は理学部・経済学部の組織強化、就職斡旋センター設立などの支援を行った。HEDSの特徴としては次の5点があげられる。
1) 日米共同プロジェクトであるため、米国のソフト面の援助の経験や手法を活かすことができた。
2) 無償・有償・プロ技を有機的に組み合わせることで、より高い効果をあげている(無償・プロ技のみならず、有償までをも含めたケースは他に例を見ない)。
3) 西部インドネシアの主要な大学多数を対象としており、援助効果の波及の範囲が広く、プロジェクトの対象となっている大学間同士の競争意欲の高まりも期待できる。
4) 「最終仕上げ段階」として日本での研修を組み込む等、研修制度を効果的に活用している。また、一般のプロジェクトと比べ、多数(5年間に180名)の研修員を受け入れている。
5) JICAのPCM(PROJECT CYCLE MAGEMENT)をプロジェクトの実施段階から導入した。また、PDM(PROJECT DESIGN MATRIX)を作成の上、中間・終了時評価等プロジェクト評価の円滑な実施に役立てた。
1. プロジェクトの自立発展を高めるための予算配慮を
プロジェクト期間終了後の持続性を維持するためには、現地への技術移転後の自立計画をプロジェクト実施前におり込むよう相手側と協議し、実施していくことが求められる。プロジェクト実施中の相手側政府の負担については、ある程度具体的な数字で示されることが多いが、完了後の負担と運営についてもコミットメントを引き出しておく必要がある。また、一般財源によるローカル・コスト負担の軽減をはかっていくためには、HEDSで行なわれているように円借款によるローカル・コストの負担、あるいはプロジェクトにより創出されるサービスを有料化し、運営コストをカバーするなど、予算処理についても工夫していくべきである。
2. 技術を組織に残すような方法の確立
日本の技術協力プロジェクトにおいては、技術移転相手のカウンターパートの定着率が問題視されている。移転した技術が人ではなく組織に残るような方法を確立していく必要がある。そのための方策としては:
(1) 技術そのものの移転だけでなく、技術の適性や活用方法を工夫できるようカウンターパートを指導すること、
(2) 派遣された専門家が現地ですぐに力を発揮できるように、標準的な教材、カリキュラムなどの作成をあらかじめ用意しておくこと、
(3) カウンターパートとなる政府機関の職員に対する技術移転のみでは移転できる人数が極めて限定されるので、業界団体・第3セクター・私立大学などまでカウンターパートの対象を広げること、
(4) カウンターパートが移動しても、組織内に知識・技術・ノウハウが残るようマニュアルの整備を一層進めること、などが考えられる。
HEDSの例に見られるように、プロジェクトをセクター化することでカウンターパートの対象を広げれば、移転された技術や知識が特定少数の個人に集中することを避けることができる。人材育成プロジェクトの最終的な成果は国全体の教育・研究の質の向上であり、その点においてもHEDSの手法は評価できよう。
3. プロジェクトの終了計画を当初より盛り込むべき
プロジェクト終了時に専門家派遣や資機材の供与などが急に終わるというやり方では、終了直後の活動維持に必要な負担が被援助国側にとって大きくなりがちである。従って、実際にはプロジェクトの延長、フォローアップなどで徐々に被援助国側の負担を増やしていく例も多く見られる。協力終了後のプロジェクトの発展を確保するには、次のような具体的処置が必要であろう。
(1) プロジェクト計画時から終了時のソフト・ランディングを考えて、案件終了前後の段階的撤退方法(事業運営費を段階的に削減することを前提に供与し、被援助国自身による事業運営を導き出す等)を計画に盛り込む努力をする必要がある。
(2) プロジェクト終了後も持続的に発展するためには、プロジェクト活動自体を自立できる事業にしておく。プロジェクト活動を通じて何らかの組織による収入の捻出の道を作っておくことで、終了後の機材の更新、スペア・パーツの購入などが可能になるとともに、カウンターパートの定着率も高まる。
(3) プロジェクト実施中もローカル・コストがなかなか出ないような途上国では、HEDSのように円借款や世界銀行、アジア開発銀行などのローンでローカル・コストを補うことが有効な場合もある。
VI. 提言4 効果的な広報をめざして
日本のODAは、その規模の大きさと日本の民間セクターのプレゼンス故に、「経済優先」のイメージが先行し、日本国内及び援助供与国内でマスコミの批判にさらされることがしばしばある。環境保全、農村開発、貧困対策などの地味な活動より、住民移転が生じる大規模なインフラ開発が主に取り上げられ、地元の団体、マスコミが日本政府を批判するという状態を回避するためには、効果的な広報活動が必要である。情報公開、広報の促進に資するために以下の提言を行いたい。
1. 情報公開の留意点
日本はODAにおける情報公開を進めているものの、プロジェクト実施予定地の地価高騰などの混乱を防ぐため、情報の早期公開には特定の利益を生む恐れがないことが前提になる。これを客観的に判断することは非常に難しいので、住民移転の問題はガイドラインに沿って住民から移転合意をとりつけ、補償に住民の要望を反映させる等を相手国政府に求め、確認することが中心になる。
インドネシアの有償資金協力の案件、コタパンジャンダム水力発電計画においては住民移転対象者が約2万人であったが、移転地の選択に住民の意思が反映されて近隣の土地に村を単位として移転した。また、政府移住事業に参加するか、現金補償を受け自ら移転地を探すというインドネシアの開発プロジェクトにおいて従来とられていた二者択一の方法から、代替地の現物補償と失われる資産に対する現金補償の二重補償の形に改善された。さらに、インドネシア政府側が住民との対話を重視したことが現地の住宅、村の生活インフラ改善に繋がった。こういつた改善努力と、コタパンジャンダム完成による電化率の向上や電力供給を通じた地域振興の利益を、現地のマスコミ、NGOに対して地道に知らせる活動が重要である。
2. 地元の関心の高いテーマでセミナーを
インドネシアでもODAの役割を具体的に紹介するようなセミナーを実施しているが、ODAだけをテーマにセミナーを開催しても現地の人々を多くひきつけるのは困難であるので、環境、公衆衛生、教育など、一般に関心の高い分野のセミナーを官民一体で開催することが、ODAの効果的な広報に繋がっていくのではないかと思われる。例えば、教育、医療関係者、経済界、オピニオン・リーダーを取り込んでセミナーを開くことにより日本のODA広報が可能になる。日本の理解の幅を広げるこのようなセミナーを積極的に実施することが望ましい。
3. プロジェクトそのものが広告塔になるような案件づくりを
日本の援助は経済インフラ建設や農業開発等大規模開発を重要な柱として実施されてきたが、インドネシアで日本側の貢献をどのように広報すれば適切なのかは非常に難しい問題である。一方、草の根無償資金協力のような社会開発型の援助は、援助金額の規模に比べて広報効果が高いので、積極的に進めていくべきだろう。また、南南協力に関して日本はアジア・アフリカ・フォーラムをインドネシアで開催する際に資金協力をしている。アジアの経験をアフリカの開発に活用するという観点で協力を推進しているという日本側の姿勢が、開発実務担当者のみならずインドネシア側にも広く伝わり、広報効果は高かった。また東カリマンタンでの森林開発に伴うオランウータン保護に対する協力は、マスコミ等でもとりあげられるなど、環境保全に取り組む日本の姿勢を伝えることができた。このような広報効果の高いプログラム、プロジェクトに注目し、日本のODAに積極的に組み入れていくことも有効である。
VII. 個別分野に対する提言
1. 草の根無償資金協力の実施体制について
1989年に導入された開発途上国のNGO、地方自治体に対する草の根無償資金協力は、広報効果も大きく、現在までインドネシアにおいての評価も高い。しかしながら、草の根無償資金協力の事業予算が増大する傾向にある中、NGO支援を効果的に実施するには現状の実施体制のうちいくつかの点について改善する工夫が必要であろう。
(1) 支援対象団体の選考基準を明確に
草の根無償資金協力制度の成立により、1)一般の無償資金協力では拾いきれない小規模の案件要請に応える、2)在外公館のイニシアティブによって援助国日本の広報効果をねらうことが可能になった。しかし、現在支援対象団体の選考基準は必ずしも明確化されておらず、日本大使館に太いパイプをもたなければ援助は受けられないとのイメージも一部にある。そこで「草の根」の意味を再認識し、支援対象団体の選考については以下を考慮する必要がある。
(イ) 都市部に本拠地をおく全国レベルのNGOについては、貧困層など社会的弱者や特定地域のニーズを十分把握できているかどうかを確認する。特に政策提言(アドボカシー)を活動の中心においているNGOの場合、実際に草の根プロジェクトの運営を実施しているとは限らないので注意を要する。国際NGOについても、先進国の視点で活動している場合、必ずしも草の根レベルでの効果が発揮されるとは限らない。
(ロ) 地方自治体も支援の対象となるが、中央政府の意思が過度に強く反映される場合は、草の根無償資金協力の主旨にそぐわなくなることもある。住民のイニシアティブを奨励し、住民の意見反映の仕組みのある参加型の事業に対象を絞るべきであろう。
(ハ) NGOや住民組織が公的資金援助に過度に依存するのを防止するため、支援対象団体は年間予算の一定割合以上を自己資金でまかなっていること、または草の根無償資金協力の供与額がその団体の年間予算規模の一定割合を超えないことなど、組織規模と援助額に関する基準を設ける必要があろう。
(ニ) 日本のNGOを直接支援対象とすることにも一定の基準が必要である。日本側の意思が強く出すぎると地元のイニシアティブが軽視されることもあり得るからである。但し、日本のNGOが地元のNGOを支援する形で実施しているプロジェクトは、後々のモニタリング実施が容易であることなどを考慮すると、高い効果が期待できる場合もある。
(2) 資金供与の運用について
小規模なNGOは実際のプロジェクトを支えるための事務経費予算も不足しており、事業の持続性のため、ハードに対する予算だけでは不十分なこともある。NGO育成も重要であることに鑑み、一般管理費を一定額供与することを考慮してもよいのではないか。ハード購入の予算を含めて、一括的な資金援助をする一方、結果はしっかりモニターすることにより、小さな団体も利用しやすい仕組みを作ることも重要であろう。
(3) NGO活動支援を担当するマンパワー、予算の補充の必要性
NGO、NPO、地方自治体の発掘やモニタリングは、規模の大小にかかわらず、かなりの作業を必要とする。一つのNGOを援助要請からモニタリングまで、フォローしつつ支援することは、一つの一般無償資金協力案件を担当するのと同様の労力がかかる。今後予算額が増大し、案件も増加することになれば、スクリーニングにおいても大使館の現体制では充分な対応が困難になってくると思われる。大使館のローカルスタッフを含んだマンパワーの補充、地方出張のための出張予算措置は、今後の草の根無償資金協力の量と拡大と質の向上に不可欠である(米国の場合、在インドネシアのUSAIDでは、6人のローカルスタッフが現地で定期的なモニタリングを行い、専任の財務管理の専門コンサルタントも雇用している)。
(4) 地元のNGOネットワークとの連携
近年現地のNGOのネットワークづくり、リストづくりも進んでおり、情報を集積している地元の規模の大きいNGOと連携し、小規模で支援に値するNGOとの関係づくりに助言してもらうことも有効である。現地のNGOのネットワーク活動への支援、特にセミナー、会議の支援は広報効果も期待できる。また、日本のNGOの持つ情報も有効に利用すべきである。
一方、地方で活動する青年海外協力隊員やJICA専門家も貴重な情報源となりうる。これらの複数の情報源を利用し、その国、地方独自の草の根の援助ニーズを把握し、支援対象分野、団体の種類などの優先順位を明確にして、選考基準を作ることが重要である。その際、現地の情報に詳しい大使館の裁量により柔軟に対応されるべき点にっき留意すべきであろう。
2. 環境保全
インドネシアの環境保全に関して、現状での最大の課題は、法制度の確立や環境政策の指針策定から、実際に企業が公害防止機器を設置し規制・基準を遵守するようにすること、環境影響評価やモニタリングを行える人材を養成すること、地方自治レベルの環境行政・地方ラボを強化しネットワーク化することなどのテーマに移行していると考えられる。これまでも、JICA、世銀、USAID、CIDA、GTZ等がインドネシアの環境政策策定、基準設定などに貢献してきたが、現在ではモニタリング技術の移転、環境専門家の育成、地方ラボの強化とネットワーク化などの面で、JICAの環境管理センター(EMC、環境管理庁)及び産業公害防止計画(BBIK、工業省)が大きな役割を果たしている。また、公害防止機器の設置については、OECFのツー・ステップ・ローンによる公害防止機器導入プログラム(PAE)が高く評価されている。このプログラムは、1993年に基金約2,714億ルピア(約126億円)でスタートしたが、1995年9月末日現在での応募総数が78件、総額は約5,193億ルピアと基金の約2倍に達しており、事前審査を通過した案件43件だけで既に基金の86.3%を消化している。環境管理センター(EMC)の特徴は、単独では大きな成果を出せないため、たくさんのドナーと協力していることである。インドネシアにおける環境技術協力の経験から、環境保全における日本の援助のあり方に関して、次のような具体的提言ができる。
(1) 政策アドバイザー派遣による戦略策定への参加
開発途上国が環境保全行政を開始する場合には、環境担当官庁の設立と人材育成、環境保全戦略の確立、法制度、規制・基準の整備など、まず上流部分での協力が必要となる。そこで、環境行政を熟知した個別派遣専門家が政策アドバイザーとして環境担当官庁の企画/政策部局に入り、環境保全戦略確立の手助けをして行くことの重要性がいっそう高い。
(2) 他のドナーとの有機的協力の必要性
環境管理庁に対する技術協力は、世銀、アジア開発銀行、JICA、OECFをはじめ、カナダ、オーストラリア、ドイツの技術協力機関が20近くのプロジェクト・プログラムを通じて実施している。環境問題という複雑な問題に対しては、このように複数のドナーが有機的に協力することによって初めて大きな効果を上げることができる。また、環境保全行政に携わる官庁は環境省(環境管理庁)だけではなく、工業省、林業省など複数にまたがるのが一般的であるので、環境というセクター全体を見渡した上で、技術協力の中期計画のようなものをドナー側が共通に持つことも必要になってくる。
3. 人材育成
インドネシアの第2次25カ年計画では、(1)9年制義務教育の実現、(2)教員の質の向上、(3)文盲の撲滅、またその第1期となる第6次国家開発5カ年計画では、(1)9年制義務教育の完全実施をめざした就学率の向上、(2)高等教育における就学率の向上、(3)教員の質の向上を目標としている。このうち職業教育の分野における具体的な施策については、「産業界のニーズに応えるためにも工場等への現場見習い訓練制度をより発展させ、専門的な技能の修得に努めなければならない」と特記されている。その背景として、インドネシアでは他のASEAN諸国と同様、中間レベルの技術者の不足に直面していることがあげられる。これには、過度の学歴偏重により、大卒の就労者が最初からマネージャーになってしまい工場の面倒を見ないこと、技術者の工場内での昇進が少ないこと、また企業内研修を受けるチャンスが少ないことなどの要因が考えられる。これらの問題を解消するためには、中間レベルの技術者を養成する職業訓練学校・教育機関などの強化、企業内研修の強化、地元サポーティング企業の人材育成などが必要と考えられている。
一方、これまでの日本の援助による職業訓練、人材育成は、対象となるカウンターパートが政府関係機関の所属者に限定され、その訓練方法も民間部門での応用を想定することが少なかったため、プロジェクト終了後の民間部門への波及効果が必ずしも十分でなかった。今後は、技術を修得した訓練者の民間への流入を想定しつつ、民間部門でもすぐに活用できる技術・知識の移転を考えていく必要があろう。
今後、ますます多様化していくインドネシアの人材育成ニーズに対応していくために、日本の援助は下記のような点を考慮していくことが望まれる。
・日本人専門家が赴任後すぐに活動できるよう、職業訓練学校・教育機関で使用される標準的なカリキュラム、教材をあらかじめ準備しておくこと。
・職業訓練や教育機関外(例えば業界団体等)の組織・人も訓練の対象とすること。
・日本から派遣された専門家だけでなく、地元の事情に詳しい現地日系企業等の技術者の協力を得ること。
・民間の活力を吸収するため、現地日系企業など民間を含めた技術指導推進の可能性を探ること。

