12. トンガ、フィジーにおける経済協力評価
東京大学名誉教授中根千枝
(現地調査期間:1996年3月25日~4月6日)
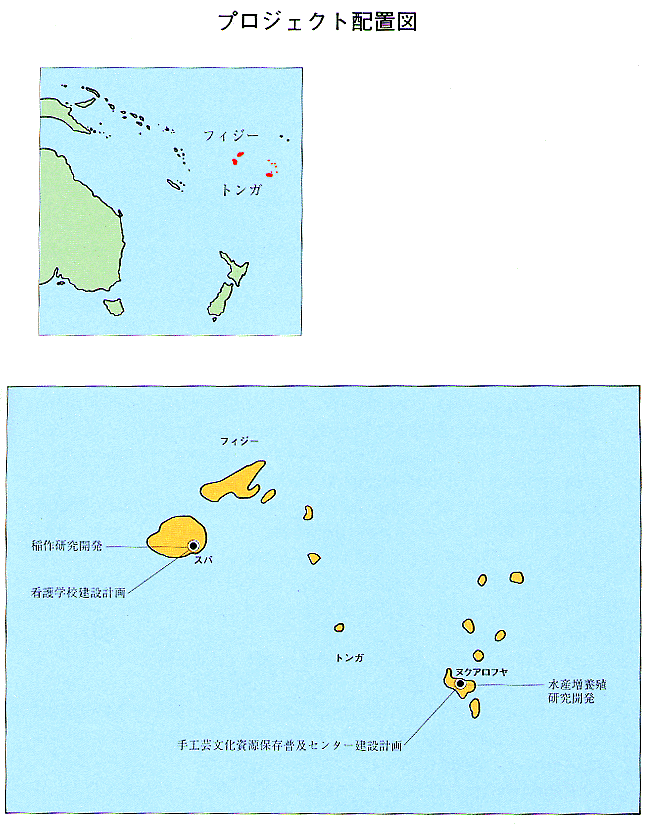
評価対象プロジェクトの概要
| 案件名 | 協力形態 | 協力期間、金額 | 案件概要 |
|
水産増養殖研究開発 (トンガ) |
プロジェクト方式技術協力 |
1991年10月~ 1996年9月 |
国民の重要な動物性蛋白の供給源となっている珊瑚礁内漁業資源の資源管理及び維持増大を図るための、魚介類の増養殖技術の開発及び水産資源管理の基礎技術に関する技術協力。 |
|
手工芸文化資源保存普及センター建設計画 (トンガ) |
無償資金協力 |
1986年度、 5.16億円 |
急速な近代化に伴う文化遺産の国外離散や伝統的手工芸技術の消滅等の事態を防ぐために、伝統的手工芸技術の向上、伝統文化の宣伝・普及を目的とした、施設の建設及び広報用機材の供与。 |
|
稲作研究開発 (フィジー) |
プロジェクト方式技術協力 |
1985年4月~ 1993年8月 |
米増産を目的とした、灌漑二期作を進めるための実用技術の開発、技術普及員の指導等に関する技術協力。 |
|
看護学校建設計画 (フィジー) |
無償資金協力 |
1984年度、 11.45億円 1985年度、 8.13億円 |
看護学校施設の収容能力拡大と機能増大を目的とした、講義棟、宿舎棟等の教育施設の建設。 |
|
青年海外協力隊活動 (トンガ、フィジー) |
青年海外協力隊 |
トンガ 1972年度~ フィジー 1983年度~ |
原則として20歳から39歳までの青年男女を開発途上国に派遣し、現地の住民とともに生活しながら自らの技術を移転する、草の根レベルの援助。 |
南太平洋島嶼国への援助のあり方を考える
―フィジーとトンガの評価視察をとおして―
今回、評価対象案件としてフィジー、トンガあわせて四つのプロジェクトを現地視察したが、いずれも他の地域と異なった南太平洋島興国の特異性が反映されており、この地域全体に対する我が国の援助のあり方について深く考えさせられたので、その視点から報告したいと思う。
南太平洋島嶼国のほとんどは資源をもたない小規模国家で、次のような決定的弱点をもち、援助なしには開発、近代化は不可能である。1)生産は小規模農業、近海漁業といった第一次産業で、天候や国際価格の変動に左右されやすい脆弱性をもっている。2)国内市場の規模が小さい。3)国際市場から遠く離れ、運輸・通信手段が不備である。4)恒常的な人材不足・人口流出、新卒者の雇用機会の確保が困難である、などである。
今回の評価視察はフィジーとトンガが対象であったが、この両国は南太平洋島興国の中で、それぞれ代表的位置付けをもっている。すなわち、フィジーはこの地域の中心的役割をもっており、一方、トンガは小規模島興国の限界を端的に代表しうるものである。そこで、まず、両国の位置付けを簡単に紹介し、主題の背景として論を進めたいと思う。
フィジーは、パプア・ニューギニアを除いて、この地域全体の中心であり、人口も島嶼国中最大で、人材にも恵まれ、近代化推進基地とも言うべきものである。人口は約80万人で、ソロモンの35万人がそれにつぎ、その他の島嶼国は10数万人から数万人、中には1万人に満たない国もある。この中にあってフィジーは群を抜いている。そして、英国植民地時代のインド人移民の子孫が人口の半数近くを占めている。このインド系移民とメラネシア系先住民であるフィジー人との関係は、独立後の政変にもみられるように、種々問題はあるものの、国全体としては力量があり、島嶼国中リーディングロールをもっている。1970年10月10日に独立・同13日に国連に加盟している。マラ大統領のThe Pacific Way構想はよく知られているところであり、1971年には地域の12カ国からなるSPF(南太平洋フォーラム)を発足させた。首都Suvaには12カ国加盟の南太平洋大学が1968年に開設されており、現在小学校の就学率は100%に近いと言われ、中学からすべて英語が使用されている。他の殆どの島興国では人材不足に悩んでいるが、フィジーでは村落レベルにおける青年層の失業が増加している。
トンガ:フィジーの原住民とインド系住民といった複雑な人口構成に対して、トンガは殆どがポリネシア系のトンガ人より構成されており、1845年に全島を統一したトゥポウ一世以来、王国として安定した社会としてまとまりをみせている(1900年英国保護領となり、1970年独立した)。
南太平洋の小規模島嶼国としてトンガは典型的要素をもっている。現在住民人口は10万人であるが、ニュージーランドやオーストラリアに5万人のトンガ人が在住している。生業はヤム・タロイモを主とする農業、近海漁業で、ストックがないばかりか、近代的な生活形態に移行しつつある今日の住民の需要を満たすための資源ならびに方途は殆どない。また、近代化を進める上に必要な人材も大変不足している。高等教育は殆ど外国(ニュー・ジーランドが圧倒的に多い)で受けるが、帰国しても母国に受容能力がなく、結果として人口流出は避けられない状態である。このような状況はトンガばかりでなく、この地域の殆どの小規模島嶼国に共通してみられるものである。
以上の背景をふまえて、以下、視察した個別案件について考察し、特筆すべき問題を指摘し、これからの援助のあり方に関する提言を記したいと思う。
個別案件の評価
1) 水産増養殖研究開発(トンガ)
本プロジェクトの期間は1991年10月2日から1996年10月1日で、訪問時には未だ終了していないが、専門家が実際に働いている現場で意見を聞くことができた。
本プロジェクトはトンガ政府の要請によるもので、その背景には、近年リーフ(珊瑚礁)内における乱獲により、国民の重要な動物蛋白源たる真ボラ、ロブスター、貝類が減少しているという事実をふまえ、資源減少傾向をくい止め、リーフ内漁業資源を管理し、維持、増大を図りたいというトンガ政府の意向があった。同意向にそって、トンガ水産省に対し、水産資源の増養殖、水産統計の維持管理等について技術移転を行うべく、無償資金協力で建設された水産研究センターを拠点としたプロジェクト方式技術協力である。
計画の妥当性という点からいえば、本プロジェクトは漁業資源の枯渇を防ぐという観点のみならず、現在トンガで国王が先頭にたって行われているダイエット運動の目標達成のためにも適当であるといえる(なお、国王は200キロ近くあった体重を半分程度に減らしている由)。ちなみに現在のトンガ人の太りすぎ傾向(村落生活改善のために派遣されている青年海外協力隊員によると、ほとんどのトンガ人は体重が100キロ以上で、日本の体重計が2つ必要とのこと)は漁業省次官によれば、ニュージーランドからの安い脂肪分の多いマトンを食べるようになったことが大きな原因であり、健康のためにもマトンから魚に食生活を切り替える必要があるとのこと。
プロジェクトの目標の達成状況については、ボラ、シャコ貝の種苗技術は移転されたが、夜行貝については養殖の世界でも2番目という難しいものであるとのこと、現在、近くの島において養殖を実施中。ボラの養殖は技術的にそれほど難しくなく、当国の漁民にも受け入れやすいように思えたが、問題は現在養殖しているボラの種類がトンガ人が好む真ボラではなく、小ボラである点である。小ボラを選択した理由は、真ボラの乱獲により、種苗が不足していることにあるとのことであったが、小ボラで十分な需要があるのか、経済性という観点からは疑問があるとの意見が多く聞こえた。
注:本評価調査後の1996年6月にJICAでは小ボラ養殖の経済性に関する調査を行い、無給餌の養殖の場合、1.5ヘクタール以上の養殖池の規模であれば採算性があり、また、家族労働のみの場合は、1ヘクタールの規模でも採算が合うと報告されている。現在仕事に当たっている専門家4人は大変優秀で、トンガでの仕事は2度目の者、また、海外における技術協力の経験が十分あり、専門の仕事だけでなく語学も自由で、トンガの水産関係の役員、職員たちともきわめて良好な関係にあり、日本の援助専門家として貴重な存在であるという印象を受けた。こうした専門家はこのプロジェクトが終わっても、他の島興国で同じように仕事をしてもらうのが日本の援助に大いに役立っだろうし、また本人たちもぞうしたことを望んでいた。ただ彼らにとって、最大の問題はカウンターパート(C/P)の不足で、10名のC/Pのうち、訪問時には中心的な3名がオーストラリアで研修中で、貝類の養殖については一時的にC/Pがいない状態であった。
水産統計資料、水産法規、資源管理政策についてはかなり整えられてきている他、資源保護啓蒙活動も実施され、その関連でポスター、Tシャツなども作成されている。なお、本プロジェクトの拠点となっている我が国の援助で建てられた水産研究センターには、1989年のサイクロンで施設の大部分が破壊されたことに及び、水産省が農業省から独立したときから入居している。
2) 手工芸文化資源保存普及センター(トンガ)
急速な近代化の波により、ともすれば失いやすいトンガ王国の貴重な文化遺産、伝統的手工芸技術を保存、継承する必要性、さらにその伝統的技術の向上を図り、あわせて職業訓練を通じて、トンガの伝統文化を青少年および広く世界に宣伝・普及させることを目的として本計画が策定され、その要請にもとづいて、我が国から1986年9月、5.16億円の無償資金協力のE/Nが締結され、施設建設と機材の供与がなされたものである。
現在、同センターでは、タパといわれる木の皮で作った布、木彫りの訓練コースが開講され、トンガダンスの訓練が行われている。また、観光客向けにカバの儀式、トンガダンスの実演が行われるなど島では数少ない観光名所になっていることから、かなりの程度目的は達成しているものとみられた。
自立発展性については、91/92年度からディナーショーや民芸品の販売を始める等により、年々事業収入は増大しており(88/89年度1万2千ドル→94/95年度15万8千ドルヘと10倍以上の伸びに比し、支出は10万ドル→20万1千ドルと約2倍の伸びにとどまっている)、自立の可能性が高くなってきていると見受けられた。同センターの所長は政府の規制が厳しく自由な活動ができない点を指摘、可能ならば民営化したいとの希望を表明していた。
問題点としては、予算の制約から運営は5名のスタッフと5名の臨時雇用で賄っており、かなりの職員の不足があること、展示品が少ないこと及び野外劇場が海辺からの風雨をまともに受ける位置にたてられており、傷みがひどくあまり使用されていない点が上げられよう。屋内の劇場はよく使われている模様である。
3)看護学校建設計画(フィジー)
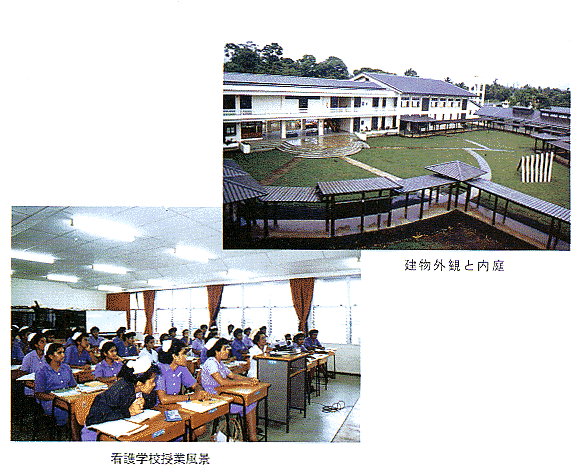
本プロジェクトは、地域の中心となる病院の中堅看護婦と、プライマリーヘルスケアの最前線を守る看護婦の不足解消を緊急の目標とし、適切な専門知識と能力をもった看護婦を養成するため、看護学校施設の拡大と機能の増大を計るものとして、要請にもとづき、我が国の無償資金協力によって1987年に完成した施設(管理棟、講義棟、共同棟、宿舎棟等)で、フィジーを代表するプロジェクトである。現在、フィジーの看護婦の大部分は同学校を出ており(フィジーの看護学校は本校のみ)、また、周辺国の看護学生も受け入れ、看護教育施設を持たない太平洋諸国の看護教育にも裨益している。
学校長ならびに幹部職員から聞くところによると、次のような問題点があった。それは建築設計上の問題である。現在事務所として使われている建設物は湾の正面に向かっており、見晴しは大変よいものの、湾からの風雨をまともに受けるために窓等が壊れやすい。実際、我々が訪問した時も壊れていた。また、講堂の建物は天井が異常に高く、そこに大きな扇風機がっけられているが、その風は下には届かず、また一方の壁には窓が無く、換気が悪く暑い、等の問題がある。保健省側の説明によれば、フィジーにおいては政府の建築物についてはPWD(Public Works Department)がメインテナンスを含め全責任をもっており、本学校を建設するに当たって、PWDが建設設計の過程に入っていなかったことが、建物の設計が不行届きであったり、その後のメインテナンスの費用負担で問題を生じる原因となった、との指摘があった。その後の建設プロジェクトにおいてはPWDを常に参加させるようになった、とのことであった。
注:JICAの報告書によれば、PWDは設計、工事の段階から参加しており、メインテナンスについては看護学校の管理部門がPWDの協力を受けて担当することになっていた。このようなフィジー側関係者との情報の食い違いは、本件協力後に発生したクーデターにより、設計工事にかかわった保健省及びPWDの担当者が替わったことも一因と思われる。
もう一つ訴えられた問題は、施設完成当時供与された看護学校(郊外の小高い山の上にある)と市内の病院との連絡用の2台のバスとジープ1台はみな耐用年数を過ぎている模様で、ジープは動かず、・バスは使用されてはいるが、床がはがれ始めているようなひどい状態で、新規の供与を要請されたことである。フィジー政府の財政状況を考えるとやむを得ない部分もあり、本プロジェクトが我が国のフィジー援助の代表案件であること、また本学校が大変成果をあげてよく運営されていることなどを考えれば、是非その対応も考えて欲しいと思う。実際、バスは毎日看護学校から病院に看護婦たちが往復するための必需品なのである。
4) 稲作研究開発(フィジー)
本計画はこの種の国に対する技術協力というものがいかに難しいものであるかを語るよい例であるので、少し詳しく述べる。このプロジェクトは8年の長きにわたり、多くの専門家を投入し、研修員を受け入れ、多額の機材供与を行ったにもかかわらず、結果的には期待はずれに終ったものである。
もともと、本プロジェクトはフィジーの米の消費量の半分に当たる約2万トンを貴重な外貨を使って輸入(オーストラリア、タイから)していたので、自給率を増大させることを目的として増産計画(第8次国家開発計画)にもとづき、フィジー政府より1983年6月に技術協力の要請があり、1984年3月(10日~28日)事前調査団、1985年4月実施協議調査団の派遣をへて、1985年4月から5カ年計画(1990年4月終了)で実施された。さらに1989年3月に期間延長の要請が出され、同年9月25日~10月8日に調査団が派遣され、3年間(1990~1993年)の延長が決定され実施されたものである。
このプロジェクトは増産計画に基づいて、(1)圃場レベルでの稲作栽培技術システムの開発・改善のための応用研究、(2)主要稲作地帯における試験研究・展示、(3)普及活動、(4)研究並びに普及員の養成、を目的とするものであった。このために我が国から長期専門家9人、短期専門家17人を派遣、約2.79億円分の機材供与、研修員の受入れ11名(1名は第三国研修)、プロジェクト運営のためのローカルコスト負担、約1.166億円等が供与されたものである。
プロジェクト延長要請にともなって1989年9~10月に派遣された調査団の評価によると「両国関係者による合同委員会の設置等のプロジェクト管理体制がとられており、適切なプロジェクト運営によって一定の成果を収め、相手国政府から高い評価を受けている」とあり、JICA専門家の指導のもと、フィジー側も熱意をもって計画推進に当たったと思われるが、1996年3月28日に私たちが訪れたときの現地の評価は、あまりにも悲観的であり、こうした地域の技術移転の難しさを今更のように知り、援助のあり方に反省をうながすものであった。私たちは本プロジェクトの行われたコロニヴィア試験場とナウソリ・パイロットファーム、ナヴゥア・パイロットファームをみてまわり、プロジェクト担当官から今日にいたる推移について、またそれぞれのファームの責任者、さらに農民からも現状を前にして意見を聞くことができた。それは以下のような問題を含むものであった。
もともとフィジーでは、タロ芋、ヤム芋などの根茎類の栽培が主で、稲作は砂糖きび栽培のために移民してきたインド系住民(100年余の歴史をもつ)によって行われてきたものである。1985年の全栽培面積11,653ヘクタールの約90%が天水田と陸稲田で、生産性は低いが栽培の容易な在来品種を使い、肥培管理を殆ど行わない畜力、人力のみに依存する栽培が行われ、年1期作にとどまっていた。灌漑率はわずか20%で、それも灌漑田稲作は10年そこそこの経験しかない。これら稲作に従事する農家は殆どインド人で、その70%は零細農家、全農家の20%近くは自給だけの農家、自給と販売がほぼ半分ずつの農家が約40%、残りが販売を主とした農家である。
日本の専門家たちによって導入された増産の方法は、言うまでもなく高度な水田稲作である。育苗をして田植えをするといった彼らにとっては全く新しい農法で、圃場整備、水管理技術を必須とするものである。このため彼らにとって労働の負担が大きすぎること、管理・運営の維持が難しいという問題があった。また改良品種は今までなかった病虫害、雑草などの防除問題を発生させた。さらに土壌肥料の改良のための燐酸及び窒素肥料、石灰などの使用、農業機械の導入などと投資があまりにも大きく、低廉な米の価格を考えると一般農民にとっては、とても受け入れられないものであった。たしかに新しい技術を導入しての研究はすすめられたものの、他方、技術移転、普及活動についてはC/Pの問題が大きく立ちはだかった。フィジー側の記録によると、このプロジェクトには合計18名のC/Pが投入されたというが、1989年の調査団の報告には、現地職員の不足、長期職場離脱、C/Pの配置のおくれ、不適切な人材の配置、しばしば起こる交代や不在(栽培に関しては7ヵ月配置されたのみで、1年9ヵ月も空白期間が続いた)、などが記され、「我が国専門家のC/Pとなり得る資質のある者が十分いない部門に対しては、我が国の技術協力も実を結ぶことは難しい」と結んでいる。
さきに11人の研修員を日本に受け入れたことを記したが、そのうち5名は1989年現在、外国へ移住、または国内で転職することによって公務員を辞めてしまっている。コロニヴィア農業試験場では研究補助者に位置付けされているC/Pは将来スタッフやラインに決して登用されない状況であるため、民間への転職者が多い。また、研究者の殆どはインド人であったが、1990年以来のフィジー人を主とした政治勢力の影響により、インド系の技術や学歴のある者の中からも海外に去る者が次第に多くなり、試験場自体も現在は大変さびれている。
以上のような状況で、日本側の大変な努力と援助にも拘らず、稲作研究開発プロジェクトの進展は容易ではなかったが、不幸なことに、それに追いうちをかけるような大きな2つの事態が発生し、このプロジェクトを直撃したのである。その第1は1993年の大型サイクロン・キナの襲来で、それにともなう洪水でとくにナウソリ・パイロットファーム(フィジー人地区)の稲が全滅した。農家もすべてのものを失い、再び立ち直ることは不可能に近いと言われ、現在、全く米の生産は実施されていない。第2は、1994年に規制緩和が実施され、米の輸入自由化によって安い米が入るようになったことである。これによってプロジェクト当初の政府の基本政策であった米の輸入量の減少と自給率の増加という目標は捨て去られた。オーストラリア、タイ等から安い米が入るため、生産コストの高くつく米を作るインセンティブは全くなくなったのである。インド系農民の地区であるナヴゥアのパイロットファームでは、圃場整備など日本の技術指導の名残をとどめているが、現在ではもともとの品種を栽培しており、輸入米より高いが、人々はこの米を好むのでやっていけるという。稲栽培の伝統のなかったフィジー系農民地区のナウソリでは、日本の技術協力によってつくられた整然とした圃場に青々とした大きなヤム芋の葉が所せましと成育していた。
以上のような現状をみて、このプロジェクトは反省すべき点が多く、技術協力といったものを考える上で貴重な教訓となろう。まず第1に、技術ギャップの大きさ、被援助国農民の経済能力と伝統的労働リズムといったものを十分考慮することなく行われたことがあげられよう。自然災害や政府の規制緩和の施行といった予期せぬ事態はともかく、対象社会の実態を十分把握することなく、労働集約的な高度な日本の灌漑稲作技術(化学肥料、農業機械などをともなう)を導入したことは、増産の目的にはそうとしても、却って大変なコスト高と、農民に経験したことのない大きな労働負荷を伴うものであった。さらに機械の修理、メインテナンス、灌漑設備の管理などは殆んど実行不可能に近いものである。従来、稲作をしていたインド系農民にとってさえ負荷が大きいものであったが、いわんや単純な根茎栽培からはじめて稲作というものをとり入れるフィジー農民にとっては困難なものであったであろう。
また、その試験研究、普及においてもC/Pを得ることが大変困難な国であるという事情も十分考慮せずに始められたことなども合わせて、技術移転には何よりも対象社会の実状を把握することが必要であると思う。プロジェクトの調査団は稲作事業を中心とした技術者たちによって構成されているために、技術移転をする際の現地社会の可能性の限界、農民の伝統の如何、現地の人々にとっての経済効果まで考慮することは難しいものと思うが、こうした面を合わせて研究できる調査団を派遣することが望ましい。事前調査におけるこうした技術一辺倒のための欠陥は、他の国々に対する援助にもしばしば見られるものであるが、本プロジェクトにおいて端的にあらわれたものということができる。
注:本評価報告を受け、JICAでは1997年3月に調査団を派遣し、プロジェクトの現状確認を行った。その調査結果を踏まえた今後の対応ぶりについては、273頁を参照。
自助努力の限界
以上の案件を通して特に指摘できるのは、C/P確保の難しさとリカレソトコストの不足である。その原因は言うまでもなく、人材不足あるいは人的流動性の高さ、さらに脆弱な国家財政によるものであり、援助の効果が必ずしも期待したようにはあがらないのである。日本の援助は一貫して自助努力ということを強調しているが、このような国々では自助努力には大きな限界がある。そのことを前提として、これらの国々に対する援助のあるべき方法を考える必要がある。
これらの国々にとって、近代国家として体をなしていくためには、インフラから食糧生産にいたるまで、あらゆる分野に援助が必要とされる。実際、外国からの援助はあらゆる面に及んでおり、とくに、オーストラリア、ニュージーランドの援助は大きな部分を占めており、それに次いで近年日本の援助が大きく伸びている。フィジー、トンガともに二国間援助の93年度支出純額ベースでは我が国は最大の供与国となっている。
世界銀行の93年の報告書に、この地域を「太平洋のパラドックス」として、1人当たり援助額が世界最高水準にあるにも拘らず、過去10年間の経済成長は0.1%と最も低い水準にあることを指摘しているが、それはパラドックスではなく、当然の結果といえよう。生産性の低いきわめて小規模の領土と人口といった限定要因があまりにも大きい国では、援助の種を育てる十分な土壌がないのである。
オーストラリア援助庁フィジー所長によると、オーストラリアは島嶼国への援助のトップドナーであり、年間3億ドル前後、全ODAの50%を供与しているが、その効果については悲観的であり、国内からは、これ程までの効果のない大きな援助をするのであれば、むしろ島嶼国の人々をオーストラリアに移住させて世話をした方が無駄な費用を使わなくてよいのではないか、といった極端な批判さえ出ているという。
小規模援助の効果
このような状況にあっても、島民は必ずしも悲観的ではなく、生活水準を向上させ、近代化の恩恵に浴することに期待をもち、まじめにそれぞれの立場でベストを尽くしている。実際、さまざまな援助を通して、自立に導き得る経済的効果はともかく、人々は近代的な活動に対応できる技能、心構えをもつようになってきているのであり、グローバルな発展からとり残されることなく、世界の一員として機能できるようになってきているのである。社会が小規模であるということは、同一社会内に大きな貧富の差による亀裂を生むことなく、今日の大きな変化をのりこえていくことができる。
こうした社会では、人々の生活にとって卑近な援助は小さいものでも大変感謝される。青年海外協力隊員による技術援助、草の根無償資金協力などは大変効果がある。トンガではたまたま東京電力から在職参加の協力隊員の仕事の現場をみせてもらったが、トンガ全島の送電線の殆どがメインテナンスの欠如からひどい状態になっており、それらを一つ一つ助手を伴ってチェックして修理を行っていた。こうした協力隊員の貢献は大きく高く評価されるものである。因みに彼によると、トンガ全島の電力の能力は、日本の新島と八丈島の間に位置するとのことである。また、滞在中にたまたま日本の草の根無償資金協力によるヴァイオラ病院診断施設完成の式典があり、来賓として参加したが、そこにも医療機器専門の女性協力隊員が2人働いており、病院にとっては貴重な存在であった。さきに記したように技術移転をすべきC/Pを得ることは困難であるが、当面こうした協力隊員による貢献は大きく、貴重な存在として感謝されている。
ここで付記しておきたいのは、トンガにおいて協力隊の活動は高く評価され、また協力隊員にとってもトンガは生き甲斐のある仕事場であるが、フィジーにおいては必ずしもそうではない。首都スヴァにおいて12名の隊員から感想を聞くことができたが、いろいろな意味で不満、不本意な面があるようであった。これはフィジーの社会が前述したようにトンガよりずっと複雑な政治経済構造をもち、英語圏であるため、相当高度な英語能力を要求され、より近代化されているために、その組織の中にうまく入りこめなく、不本意な仕事をさせられる、などといった要因によるものと思われる。こうしてみると、全体として協力隊員が要請の60%にしか満たない我が国の現状を考えると、フィジーのような所を少なくし、トンガのような国に投入するのがよいと思われる。
ちょうど、私たちのトンガ滞在中に、トンガタプ島道路改良計画(首都の中心部、空港及び港湾を相互に連結する主要幹線道路のアスファルト舗装の実施)の第1期、約13㎞が完成し、その式典が国をあげて盛大に行われた。トンガの人たちの喜びは私たちの想像以上のものがある。もし、援助というものがドナーにとって被援助国政府やその国の一般の人々からも感謝されるということが、大きなリターンを意味するのであれば(これは外交的な意味で大いに国益に資するわけであり)、これ程援助が効果的な対象国(地域)はないと思う。
これらの小規模島興国に対する援助は、当然無償資金協力と技術協力となるが、それには維持、管理が比較的容易な、道路、建築物、機材などを選ぶべきであり、そして草の根無償資金協力、青年海外協力隊による技術協力などに大きなウエイトをおくべきである。プロジェクト方式技術協力とか大規模な無償資金協力の場合は、次に述べるように、国単位というよりは、広く隣接国を含む地域全体に波及効果のある有効な援助の方法をとるべきである。
外国の援助機関との連携、ならびに地域を対象とする援助の必要性
南太平洋地域はオーストラリア、ニュージーランドにとっては、自分の庭のようなものであり、人的交流も多いし、この地域に関する専門家も多い。当然のことながら援助国としての位置付けは群を抜いている。我が国の援助は近年大きくなり、親日の国々が増えたとはいえ、新参者である。したがって、援助においては、これらの国々との協力、補完関係をもつことが望ましい。
オーストラリアの援助は相当きめ細かい所にまで行われている。上下水道、地方の電話網、医療、学校、奨学金、女性、家族計画、法制の立案、高等裁判所への補佐、警察の訓練、などである。ニュージーランドについてはよく調査できなかったが、とくに教育分野、奨学金援助などが大きいとの印象を持った。現在、フィジー日豪協調案件としてヘルス・プロモーション・プロジェクト(1996年1月から正式スタートし、期間は98年12月までの3年)が進められているが、このようなドナー国間の協力は大いに役立つものと考えられる。それぞれのドナー国が得意とする分野を担当して全体として協力の成果を上げることが期待される。
他方、日本の援助としては、特定国を対象とするだけでなく、近隣諸国をはじめ、地域全体に裨益するプロジェクト方式技術協力のあり方を考えるべきである。島嶼国はみな似たような条件を備えており、単位が小さいのであるから、国別という枠から出て、地域全体として援助計画を進めていく必要がある。この意味で日本側の援助システムを弾力的に機能できるようにすることが必須である。因みに1984年に開設されたJICA事務所(在フィジー)は6カ国(フィジー、トンガ、キリバス、ヴァヌアツ、トゥヴァル、ナウル)を管轄しているが、少なくともこの管轄圏内を単位とする共通な援助スキームを考えることも有効であろう。現在の援助システムが政府対政府のとりきめに基づいているので、どうしても国単位の考え方に固執してしまうが、南太平洋といった特殊な地域では、広く地域を対象としたスキームを何とか運用によって考えられないものかと思う。
この方向は、フィジーの首都スヴァにオフィスを置いている地域国際機関への日本側の積極的な協力をも可能にする道である。現地JICA事務所長もこの点を強く要望していたが、南太平洋のように個々の島国では自立が不可能な地域においては、「南太平洋フォーラム」、「南太平洋大学」、「南太平洋応用地球科学委員会」などといった地域機関への援助の意義は大きいものと思われる。たんに地域機関への拠出金というのではなく、地域機関の中に我が国のプロジェクトを造り、イヤーマークして拠出するというやり方などを積極的に考える必要があると思う。
最後に付記したいのは、この地域を全体としてとらえるということは、我が国の援助の要員の配置にも有効な方法であろうし、また、供与した機材のアフターケアのために、専門家を巡回させるなど、地域の要請に応えることができよう。さきにふれたヴァイオラ総合病院では医療機器の殆どにJICAのマークが入っており、その多さに驚いたが、そこで仕事をしている協力隊員によると故障が一番困ることで、その修理にはオーストラリアに依存せざるを得ない状況とのこと。医療機器ばかりでなく、日本からこの地域に供与された機材は大変多いが、それらの修理はどの国でもできないのが常で、地域全体を対象とした特別のアフターケアのシステムをつくるべきである。そうしてこそ、初めて援助の実があがるものと言えよう。
フィジー「稲作研究開発計画」参考資料
1) 1987年に起こったクーデターを契機に、フィジー政府は、米自給率の向上等を唱った従来の開発計画を変更し、1989年に規制緩和や政府財政支出の抑制等を柱とする新経済政策を決定した。以降、フィジー系優遇政策ともあいまって、稲作に対し大きな影響を及ぼす以下のような施策が展開された。
・米輸入関税の引き下げ(1989年:50%→1994年:20%)
・政府補助の廃止(耕転作業、種子、肥料、農薬等に対する政府補助を1994年に廃止)
2) 本プロジェクトにより4地区でパイロットファームが整備されたが、1997年3月に行った調査結果によれば、全ての地区における現況は以下のとおり。
| 項目/地区 |
Vusuya(Nausori) パイロットファーム |
Calia(Navua) パイロットファーム |
Korokabi パイロットファーム |
Tabia パイロットファーム |
||||
|
設立年月 灌漑方法 |
1989年12月 ポンプ |
1989年12月 重力 |
1991年2月 重力 |
1991年2月 ポンプ |
||||
| 農家構成 |
フィジー系 11 インド系 0 |
フィジー系 0 インド系 10 |
フィジー系 0 インド系 5 |
フィジー系 14 インド系 5 |
||||
| 位置 |
南島VitiLevu 都市近郊 |
南島VitiLevu 都市近郊 |
北島VanuaLevu | 北島VanuaLevu | ||||
| 現状 |
極めて低調。 稲作農家は一名のみ。 |
田面均平等の技術が活用されている。 ファーム周辺の反収 (198丁年:2.7トン/ヘクタール →1995年:2.9トン/ヘクタール) |
植栽密度の改良等の 技術が活かされている。 ファーム周辺の反収 (198丁年:2.1トン/ヘクタール →1995年:2.4トン/ヘクタール) |
低調。 稲作農家はインド系のみ。 |
||||
| 重力灌漑(ヘクタール) | 0 |
12.3 |
9.0 |
0 |
||||
| 無灌漑(ヘクタール) | 14.3 |
0 |
0 |
|||||
| 現在の作付け状況 | MainS. | OffS. | MainS. | OffS. | MainS. | OffS. | MainS. | OffS. |
| 従来種(ヘクタール) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.0 |
3.4 |
3.0 |
0 |
| 改良種(ヘクタール) |
0.5 |
0 |
11.0 |
10.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3) 調査結果を受け、プロジェクトで導入され現在も活用されている技術の更なる改良・定着を図るためのフォローアップの可能性にっき検討したが、現在、フィジー政府は稲作について特段の振興策を講じておらず、また、稲作を主体的に行っているのがインド系農民であり、フィジー系優遇政策を掲げる政府にフォローアップに対する積極的な取り組みは期待し難い状況にあることから、当面はこれを見送り、今後のフィジー政府の農業施策の動向等を見守ることとした。
4) 技術協力が十分にその効果を発揮するためには、対象地域における社会経済情勢を十分に分析し、協力内容を確認していくことが重要であるとの認識のもと、近年のプロジェクトに係る各種調査においては、技術系の団員に加え、社会経済分析或いは農村社会といった分野の団員を参加させるよう努めている(例えば、1995年に実施したホンジュラス森林保全プロジェクトに係る事前調査の団員として経済学者が参加等)が、本件評価の結果を踏まえ、技術協力の効果を高めるためにどのような工夫が望ましいのか検討していく必要がある。

