11. メキシコにおける経済協力評価
NORAD(ノルウェー開発協力庁)コンサルタント クヌート・サムセット
(現地調査期間:1996年2月26日~3月8日)
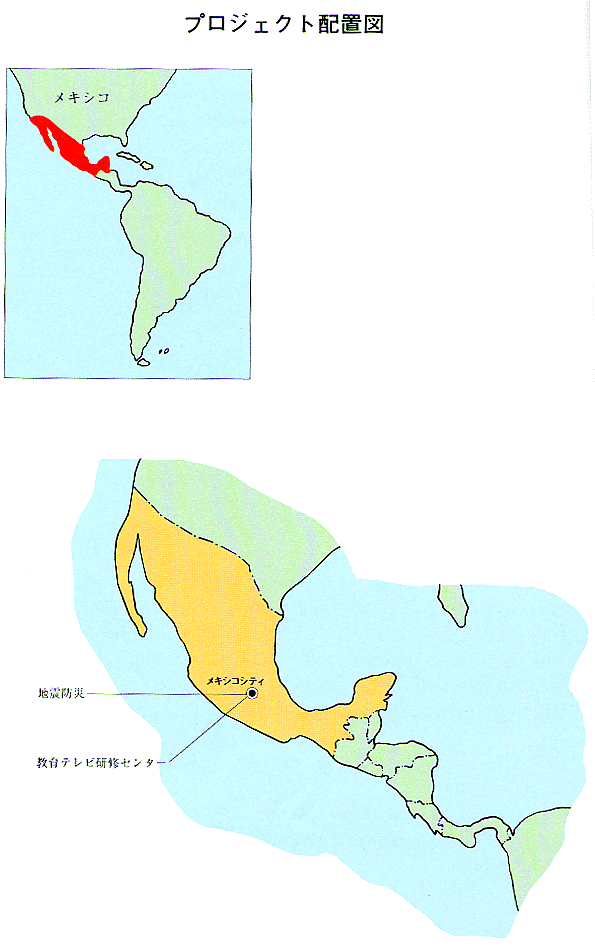
評価対象プロジェクトの概要
| 案件名 | 協力形態 | 協力期間 | 案件概要 |
| 地震防災 | プロジェクト方式技術協力 |
(当初) 1990年4月~1995年3月 (延長) 1995年4月~1997年3月 |
85年9月に大地震災害を受けたメキシコに対し、強震観測、耐震構造等地震防災技術に関する研究、研究成果を生かした研修事業の開発・実施、地震防災技術に関する普及事業の実施に関する技術協力。 延長期間は、研修・普及活動についての協力を重点的に実施。 |
| 教育テレビ研修センター | プロジェクト方式技術協力 | 1991年4月~1996年3月 | メキシコにおける教育テレビ番組製作・放映技術の向上に資するため、教育番組製作関係者に対する理論面での指導と実践面での技術訓練を実施。 |
本評価の目的の一つは、プロジェクト・サイクル・マネージメント(PCM)における評価手法を適用することであった。PCMの評価手法の基本的な評価基準は、効率性、目的達成度、インパクト、妥当性、自立発展性の5つであるが、本評価は調査プロジェクト期間の終了時に行われたため、目的達成度、インパクト、妥当性、自立発展性について断定するのは時宜尚早である。
本評価から導きだされる結論の一つは、総じて、いずれのプロジェクトも相当に良好な成果をもたらしているということである。両機関とも、日本からの充実した時宜に適つた機材供与と技術援助、メキシコ当局の確固とした意思、大規模な資金投入、メキシコ人スタッフの優れた能力と熱意により適切に設立された。評価時点では、両機関とも完全に稼働段階に入っており、期待されたサービスを顧客機関と対象グループに提供していた。但し、自立発展性については、財政基盤の確保、他の関連機関との関係などいくつかの課題を指摘し得る。
地震防災プロジェクト
背景
地震防災プロジェクトの背景には、1985年メキシコ・シティーなどに壊滅的な被害を与えた地震があった。メキシコ政府は、地震防災システムを確立する努力の中で、日本政府に対し援助を要請した。
1989~90年のプロジェクト第一段階では、国立防災センター(CENAPRED)の建物の建設及び主要機材の設置が行われた。資金は、無償資金協力として総額12億4,600万円が供与された。
1990~95年の期間には、合計約30人・年の技術協力と、1億8,700万円相当の専門技術機材が投入された。プロジェクトは、さらに1995~97年の二年間延長され、7人・年の技術協力と約3,000万円の機材供与のための追加予算が投入された。
地震防災はCENAPREDの重要な活動部門の一つであり、地震波の影響に関する研究と、地震の影響を軽減するための建築物構造実験と改良を行っている。センターでは、地震計測網を運用して太平洋岸からメキシコ・シティーまでの地域における地震波の伝搬と、地震波がメキシコ・シティーの都市建造物に与える影響について研究を行っている。
現在、CENAPREDは、国家市民保護システムにおける中心的助言機関としての特別な役割も担っている。この役割における重要な活動の中には、国民保護組織スタッフ及び関連分野の専門家・技術者のトレーニング、防災情報の普及が含まれる。また、センターは、地理学、水文気象学、化学災害、保健衛生、社会的組織という5つの主要防災分野における全国的諮問委員会間の調整も行っている。
評価時点では、センターのスタッフは125名、その60%が専門職、40%が補助スタッフである。センターは、研究、トレーニング、情報普及の分野で数多くの活動を行い、これらの分野での地位を確立してきた。
プロジェクト設計
プロジェクトのマスタープランによれば、プロジェクトの目的は、(1)地震防災のための技術の開発・向上と、(2)メキシコ及び中米・カリブ地域における適切な防災対策への貢献という二つである。プロジェクト設計は、プロジェクトが1994年11月に評価された際に(JICA終了時評価)、プロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)にまとめられた。このPDMでは、プロジェクトの成果をセンターでの調査、研修、情報普及のレベルが向上すること、プロジェクトの目的をセンターがこれらの活動をセンター自身で実施できるようになることとしていて、成果とプロジェクトの目的が実質的には同じであり、プロジェクトの目的は組織レベルにとどまっている。また、PDMの要素はいずれも数量化されていない。PDMの要素、特にプロジェクトの要約と指標はできる限り数量化すべきであり、このことにより、プロジェクト・デザインから評価まで首尾一貫した基礎が与えられることになる。
効率性
期待される成果は、「CENAPREDによる調査、研修、普及のレベルが向上すること」であった。
プロジェクトの第一部(1990~95年)では、技術援助は地震計測機器設置・利用、地質学的リスクの研究、建造物の耐震テストに重点が置かれた。
第一の分野(地震観測)では、プロジェクトは太平洋岸とメキシコ・シティーの間の5カ所、メキシコ市内の10カ所の観測所からなる地震観測網を設置し、これを稼働させた。データは地震発生後直ちに発表され、研究成果は毎年公表されている。さらに、データは全国レベルの地震データベースに組み込まれている。また、プロジェクトはデータの記録・収集システムの改善と、プロジェクトにより供与された9個の携帯用地震記録計の作動作業に取り組んだ。
第二の分野(地質学的リスク)では、プロジェクトは震源メカニズムの研究と地震波の伝搬研究を行った。プロジェクトでは過去の地震損害情報を分析し、データベース及びマイクロゾーン観測網内の地震反応・損害予測地図を表示する地理情報システムを開発した。また、建物内の地震反応を分析する研究も行われた。
第三の分野(耐震テスト)では、プロジェクトは、建物構造の力学テストを行うための大型テスト・ラボの設置と運転を支援した。プロジェクトでは、さまざまな種類の壁面システムの分析を行った。特に煉瓦を固めた壁に関する分析が最も多く、これは、メキシコで建築材料として最も多く使用されているのが煉瓦だからである。また、力学的影響に関する研究や、地盤に関する研究が行われた。
第四の技術援助分野には、研修と情報普及が含まれる。延長前のプロジェクト期間中にセンターで開かれた76のシンポジウム、会議、作業部会などのうち、17がJICAおよび/または日本人プロジェクト・スタッフと共同で開催された。センターの発行する雑誌20冊に加え、刊行物6冊が日本人専門家との共同で編集された。多くのトレーニング・コースが実施され、いくつかの国際機関との連絡もできた。
プロジェクトの第二部(1995~96年)の技術協力は、研修と情報普及分野に重点を置いて実施された。
評価時点で、地震防災プロジェクトには、累計で約100人の専門家が派遣されていた。そのほとんどが短期専門家(80%)で、合計した貢献度は3人・年以下、あるいは全体の10%以下であった。各短期専門家の滞在は平均2週間程度であったが、短期専門家の経歴が、特定の解決すべき問題や防災というセンターの課題に適確に対応していたことから、メキシコ人スタッフは、そのインパクトは重要だと考えている。プロジェクトに派遣された22人の長期専門家は、日本の15に上る諸機関から派遣された。必ずしも全員が、地震防災関連分野での専門的な経験をもっていたわけではない。一般的な経験から述べれば、日本での一つまたは少数の類似した機関から派遣するように調整が図られたならば、プロジェクトに適した専門的な経験を有す長期専門家を確保し、技術援助のインパクトを強化することができただろうと思われる。
プロジェクトの供与機材のほとんどが、センターのニーズに適っていたとのことである。しかし、地震用計器の中にはすでに時代遅れになったものもあり、センターではメインテナンス・コストを削減するとともにメキシコ国内の他の地震ネットワークとの互換性を確保するため、そのような計器をより簡単なアメリカ製計器に順次交換しているところである。
結論として、プロジェクトは、センター設立を支援し、研究を促進し、また、ある程度まで研修と研究結果の普及を促進するということにおいて効果的であった。センターは急速に発展しており、評価者は成果の質を評価できるだけの専門知識を有していないが、少なくとも量的に見る限り大きな成果をあげている。
プロジェクトの目的達成度
プロジェクトの目的は、「CENAPREDが地震防災技術の調査、研修、普及事業を行う組織として機能すること」である。
上述の諸点から、この目的がすでに達成されたことは明らかである。1995~1996年の延長期間も強震観測での活動は継続され、限られた数の機材と短期専門家が投入され、いっそうの発展を示した。この分野では、センターは他の国内の機関に比べ、高い水準を達成したとのことである。地震研究・テスト分野では、独自に新たな活動が開始された。入手した情報によれば、研修・普及活動もプロジェクトが1995年に延長された後、大幅に拡大された。
プロジェクトのインパクト
合意されたPDMによると、上位目標は、「メキシコの一般建築技術に耐震構造技術が生かされる」ことである。
プロジェクトのインパクトを評価するため、工事責任者協会、全国建設業連盟、メキシコ自治大学工学部の代表者と協議を行った。
建築関連法規は、メキシコの各州で異なる。メキシコ・シティーの現行法規は1980年代末に策定されたものである。新建築法が1996年中には制定される予定であり、CENAPREDは、その制定過程で助言を与える役割をもっことになると予測される。
センターの活動が建設技術一般に与える影響を言判面するのはおそらく時期尚早であろう。メキシコ・シティーの多くの工事責任者がセンターによる研修を受け、さらに1995年3月にはセンターと全国建設業連盟との間で協力協定が調印されたとのことである。同連盟は、1995年には18万の受講者に対し1万3,000の研修コースを実施し、独自の技術工学研究所も所有している。連盟によれば、CENAPREDは、連盟内で実施される研修を支援しており、また、CENAPREDがメキシコ国内では建築構造の大規模な力学テストを実施できる唯一のラボを運営していることから、CENAPREDと共同研究プロジェクトを実施することにしているとのことである。
センターは、地域内の他の類似の機関への技術移転戦略を開始した。そのような機関との間には従来より研究協力と情報交換によるある程度の交流は行われてきたが、これまでのところ、あまり大きな成果は認められない。その主因は、メキシコ通貨切り下げにより国際的プロジェクトの実施が困難になったことであるとのことである。
上述のように、CENAPREDは、日本の技術協力プロジェクトの協力領域を越えた防災一般を管轄しており、日本の技術協力は、水文気象学上の災害や化学災害等の分野でのCENAPREDの成果に非常に重要な間接的インパクトを与えている。このような分野の一つには、メキシコ・シティー付近の活火山に関する火山活動の監視がある。センターの出版物および研修の概ね50%が地震防災以外の分野に関するものである。
プロジェクトの妥当性
プロジェクトの妥当性は、主として、CENAPREDの活動が社会にとり有用であるかどうかという問題と、センターの役割がどの程度まで他の諸機関の役割と重複しているかという問題である。
評価者側には、州、全国または国際的な文脈の中でのセンターの現在の役割と潜在的な役割を評価する時間と手段がなかった。地震研究は、主として、その地質構造のために特に地震に対し脆弱なメキシコ盆地に限定されている。このような研究が妥当であることは、地域的な視点からみれば明らかである。全国的な視野に立つと、この研究には、必要な専門的知見を研究所で保持するという妥当性がある。他の地域のデータは他の諸機関から提供されており、全国的なデータベースを通じて利用できるようになっている。
運営管理者によれば、現在センターとしては、全国的規模で助言を与えるという役割を有す情報供給センターの方向に一層移行していく方針である。この場合、研究は、センターの主要な機能ではなく、専門分野における十分な信頼性を確保できるようにするための基本的活動ということになる。これは、メキシコには地震研究や耐震実験、地震工学に従事する機関が他にも数多くあることを考えると、賢明な方針であるかもしれない。センターはこれら多くの機関と協力協定を結んでおり、また、五つの主要防災分野についての全国的諮問委員会の調整機能を担っている。このような活動は、全国的な情報供給センターとしての役割を強化することになろう。
プロジェクトの自立発展性
1995年にプロジェクトを2年延長することが合意された。その理由は、将来のCENAPREDの運営を保証するためには専門知識が十分ではなく、カウンターパートをさらに指導する必要があるということであった。
センターは、比較的専門スタッフの比率が高い(60%)。このうち50%以上が修士または博士の称号を取得しており、また、センターには大学院課程の学生が数多く所属している。
スタッフの入れ替えは、1990~1996年の期間全体で5~10%とのことであり、これは非常に低く、ここでも、スタッフが熱意と充足感を持っているという全般的印象を確認することができるように思われる。
予算は、過去3年間、名目価値では同水準であったが、実質価値ではインフレと平価切り下げにより著しく低下した(50%以上)。しかし、センターの業務には重大な影響を与えていないという。それは一つには、機材とメインテナンス費用の一部がまだプロジェクトにより賄われているからであり、またメキシコ政府も必要に応じ追加資金を供与してきたからである。
研究活動からのわずかな収入を除き、センターの資金は全面的に政府が拠出しており、将来、他の資金源からの収入増大計画はない。センターは、助言・コンサルタント・サービスに力点を置きつつ、サービス業務と学術的研究の間の適切なバランスを図っていく方針であり、一般的経験から言えば、利用者に対し提供するサービスの代金を請求することにより財政状態が改善されるばかりでなく、サービスの質の向上が促されることにもなるであろう。
教育テレビ・プロジェクト
教育テレビ研修センター(CETE)の目的は、教育テレビの技術・編集スタッフを養成することである。このセンターは文部省教育テレビ局(UTE)の一部門として機能している。UTEは、遠隔地にある約1万2,000の地域の中学校を含む受信網による「テレビ中等教育システム」(Telesecundaria)で使用する番組の制作を目的として30年前に設立され、教育テレビ番組を計画、制作し、ローカルテレビ網や最近では通信衛星も使用して放送を行っている。この放送網は、3万4,000人の教師の助力を受けて約70万人の学生に教育を行っている。
メキシコ当局は、現在、米州開発銀行の資金支援による大幅な通信教育システムの拡張を計画しており、CETEにはこの新システム用教材制作に必要な人材養成において最も重要な役割を担うことが求められている。
プロジェクト設計
プロジェクトのマスター・プランでは、プロジェクトの目的は、(1)「UTE及びその他のメキシコの番組作成機関の技術及び制作のスタッフに対する理論的かつ実践的な訓練を提供し」、(2)「同国の教育番組の制作及び放送の発展に資すること」とされている。これは後に、プロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)で以下のように要約されている。
上位目標:メキシコの公共教育において教育テレビの効果が増大する
目的:CETEにおいて教育番組制作者及び技術者が訓練される
成果:カウンターパートとCETE職員が研修を実施できるようになる
地震防災プロジェクトの場合と同様に、このプロジェクトの目的も、組織レベルであり、目指すレベルはプロジェクトの所期の成果と大差ないため、目的は方向性をほとんど示していない。また、デザイン・マトリックスは設計要素または指標を数量化していないので、プロジェクト管理においても評価においてもその利用には限界がある。なお、このデザイン・マトリックスは、1995年末のプロジェクトの終了時評価時に作成されたものであり、プロジェクト実施期間中には、日墨双方のスタッフともこれを使用していない。
効率性
センターの建物はメキシコ当局により建設され、1991年にオープンした。PDMによると、プロジェクトの所期の成果は、センターのスタッフが(1)訓練コースの実施、(2)訓練コースの運営管理、(3)施設、設備の利用と保守、(4)訓練コースの実施に必要なサービスの提供に関して、プロジェクト終了時にその任務を遂行する能力をもつようになるということである。
プロジェクトは総額6億5,500万円(約600万ドル)をかけて、センターにスタジオ、ビデオ、オーディオ、編集機材を設置した。施設は技術スタッフや番組制作スタッフの訓練だけでなく、本格的なテレビ番組の制作にも十分であると考えられる。
センターでは、合計19名(管理職レベル9名、実務レベル10名の19名。うち女性は5名)が日本での研修を受け、この中には日本人専門家のカウンターパートでありセンターでの中心的トレーナーに任命された9名が含まれている。日本での研修期間は平均して1ヵ月以上であり、そのほとんどが日本放送協会(NHK)で実施された。実施された研修のうち約60%が技術分野、約40%が番組制作と管理分野である。研修生の間で研修は有益であったと認識されているが、研修生の3分の1(6名)がCETEを離職しており、これがプロジェクトの能率に与える影響も懸念する者もある。
カウンターパートのうち6名が技術分野の専門家、3名が番組制作分野の専門家である。全員が採用時点で優れた能力をもち、適切な学士の称号をもっている。また、プロジェクトには2~4年参加してきた。1995年11月のJICAの評価報告では、カウンターパートの技能はプロジェクト期間の終了までに期待される技能レベルに到達できるとされており、今回の調査における聴取においても、日本人専門家によれば、カウンターパートは1996年3月のプロジェクト終了時には、外部からの援助を受けずに活動を継続しているだけの必要な専門技能を習得しているであろうとのことであった。
長期専門家は、チームリーダー1名、調整員1名、技術専門家2名、番組制作専門家1名であり、この5名からなるチームが45年または合計23人・年の期間にわたって派遣された。この間に、10名の長期専門家がプロジェクトに派遣され、現在、滞在している専門家は1996年3月末までに離墨する。
短期日本人専門家は累計で39名派遣され、その合計は4人・年であった。このうち半数の専門家が機材設置(2人・年)、残り半分は機材設置後の技術・番組に関係する様々な問題について助言を与えた。
プロジェクト経費については、日本、メキシコ双方の投入金額から推定されるセンターのスタッフ1人当たりの投入額は比較的大きく(約30万ドル)、この投入額が妥当であるためには、番組制作及び訓練活動におけるセンターの成果が相当に大きくなければならない。
プロジェクトの目的達成度
上述のように、プロジェクトの目的は、組織レベルの目的、すなわち、「教育番組の技術・制作要員をCETEで訓練すること」に限定されている。対象グループ、訓練コースの数、受講者の数、訓練の種類、訓練のレベルは特定されていない。
成果は相当に良好である。
訓練の開始は1993年で、この年に約300名の専門スタッフを抱える母体組織(UTE)から訓練に参加した人数は250名であった。1994年からは、他機関の関係者にも訓練が開放され、以後2年間、参加者の数は年ごとに倍増した。1995年9月までにセンターの訓練コースに参加した人数は約1,600名とのことである。約40%が母体組織から、約30%が他の政府機関、約20%が民間機関からの参加者であった。実施された訓練の約3分の2が技術要員向け、3分の1が編集者向けであった。プロジェクト実施期間中に、訓練用テキスト11冊と訓練用ビデオ8本が制作された。
センターは数多くの訓練コースを提供している。評価時点で、100を超える訓練コースが開発されていた。カリキュラムを一層多様化し、コースの数と受講者の数を増やす計画が提出されている。評価時点での訓練施設の利用率は、40%~50%と思われる。
プロジェクトのインパクト
プロジェクト・デザイン・マトリックスに明記された上位目標は、「メキシコの公共教育において教育テレビの効果が増大すること」である。
本プロジェクトの効果を評価するには時期尚早である。現時点でプロジェクトのインパクトを例証できるものはほとんどないが、母体組織であるUTEの報告には、制作する教育テレビ番組の質を評価する指標が、トレーニング活動開始以降、約20%改善されたことが示されている。
他方、メキシコのテレビ業界の規模とテレビ要員訓練に利用しうるセンターの施設規模を考えると、センターが実務スタッフ訓練よりもむしろ業界のトレーナーと潜在的人材の訓練に重点を置けば、インパクトはもっと大きくなるとも考えられる。
プロジェクトの妥当性
一般に、教育部門の番組制作に必要な専門的技能は、他部門のテレビ番組制作に必要な技能と大差ないであろうから、センターでの訓練はあらゆる種類の番組制作能力を向上させることになり、センターで訓練を受けたスタッフが、確実に教育番組の制作だけに自分の技能を使い続けるようにすることは困難であろう。また、センターでの訓練が一般的な機関やテレビ業界自身による訓練より教育番組の制作に適していると考える理由もほとんどない。
したがって、センターの存在を正当化する主な理由は、衛星放送による通信教育システムを大幅に拡充しようとしている政府には、教育番組制作のための人材育成というニーズがあるから、ということになるであろう。この場合、センターの妥当性は、政府の与える優先度、拡充計画の実施程度、この部門の現在および将来の人材需要により決定されることになる。
現在、UTEは300名の専門スタッフを有し、テレビ中等教育システム(Telesecundaria)向けの最大の番組制作者である。評価者が入手した情報によれば、CETEは、約35名の専門スタッフを有し、年間7,000~8,000人の受講者に短期訓練コース(1~2週間)を実施する能力を備えているのであるが、この訓練実施能力は現在の需要と一致していないように思われる。施設の有効利用のためには、センターは教育部門のみならずテレビ全体の実務スタッフに短期訓練コースを実施すること、あるいは教育テレビ番組制作のトレーナー、またはテレビ番組制作全般のトレーナーを対象に長期訓練を提供することが必要なのではないだろうか。
プロジェクトの自立発展性
事業予算は、過去3年間で実質価値では50%以上目減りしているが、訓練の多くは無料で提供されており、1995年に訓練費用を払ったのは受講者の約10%にすぎない。
また、センターでは訓練カリキュラムの多様化と訓練活動の拡大を計画しているが、センターには実質的な現行費用の引き上げが許されず、独自の活動を通して生み出した収益の使用権限ももたないことから、この計画実施には政府からの相当な追加資金が必要となる。
さらに、現在の事業予算とプロジェクトを通じて提供された技術機材への投資額を比べると、機材の耐用年数が短いことを考えると、総事業予算は、投下資本(機材)の減価償却額より小さい。これでは、メインテナンス、更新、新規投資のための政府からの莫大な追加資金が必要となるであろう。
これらのジレンマに対しては、二つの異なる解決策が考えられている。一つは、(1)母体組織の番組制作のためにこの施設を利用させることとし、これら番組制作関連の職場内研修に訓練活動を限定することである。これにより、運営コストを引き下げ、設備の生産的利用を引き上げることになるが、プロジェクトの目的には反することになろう。もう一つは(2)独自の収益をあげ、かっ、その収益を使用できる権限を与えられた分権的機関としての独立した地位を求めることである。当局によれば、1996年に、後者の方式を求める要求書が政府に提出される予定である。この方式により、財政状況が改善されれば、スタッフの離職を抑制するためのインセンティブとなるかもしれない。
結論
プロジェクトは当初の計画で予定された研修センターを成功裡に設立し、センターは意図した対象グループヘのサービスを提供している。上述の問題は、センターの将来の役割と自立発展性に関するものである。いずれも解決されなければならない問題であり、いずれも、センターの制度的枠組みと関連している。このような制度的な枠組みをプロジェクト立案時点に系統的に研究していれば、これらの問題を回避することができたのかもしれない。

