10. ドミニカ共和国、ホンジュラスにおける経済協力評価
日本経済研究センター研究顧問 鮫島 敬治
東京農業大学国際農業開発学科助教授 板垣 啓四郎
(現地調査期間:1996年1月9日~1月20日)
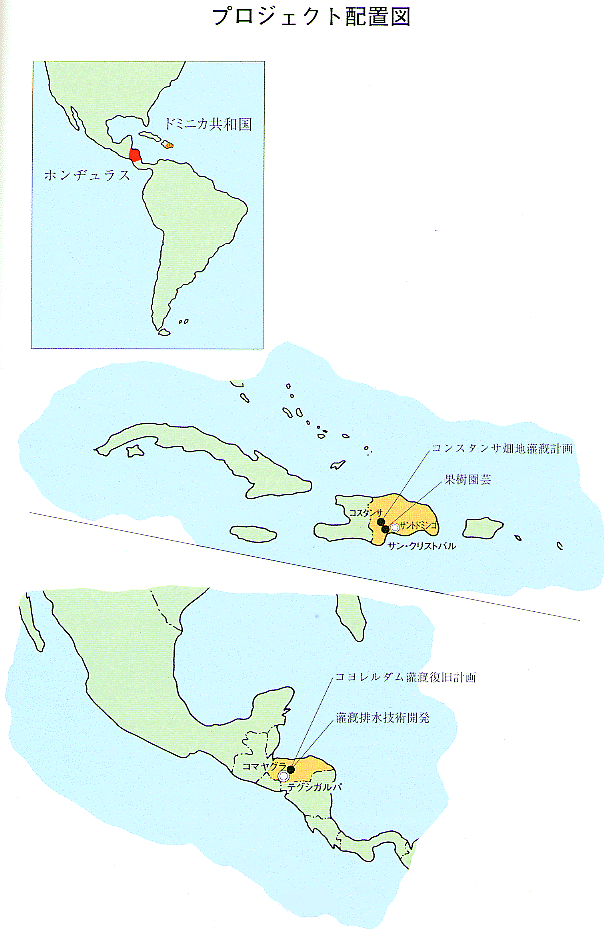
評価対象プロジェクトの概要
| 案件名 | 協力形態 | 協力期間、金額 | 案件概要 |
|
果樹園芸 (ドミニカ共和国) |
専門家チーム派遣協力 | 1993年4月~1996年3月 | マンゴー等の在来果樹を対象として、優良品種の選抜、選定、増殖に関する技術指導を行う。 |
|
コンスタンサ畑地灌厩計画 (ドミニカ共和国) |
無償資金協力 |
1993年度、 5.46億円 1994年度、 0.32億円 1995年度、 9.46億円 |
コンスタンサ地域の農業生産の拡大を図るために、取水施設、導水施設、用水路等を建設する。 |
|
コヨレルダム灌漑復旧計画 (ホンジュラス) |
開発調査 |
1989年12月~ 1990年3月 |
コヨレルダム復旧計画及びフローレス 灌漑地区改修計画の策定。 |
|
灌漑排水開発計画 (ホンジュラス) |
プロジェクト方式技術協力 |
1994年10月~ 1999年9月 |
「ホ」国の自然的、社会的条件に適合した、灌漑排水事業全体に関する基準策定に関し、技術指導及び助言を行う。 |
|
青年海外協力隊活動 (ドミニカ共和国、ホンジュラス) |
青年海外協力隊 |
ドミニカ共和国 1985年度~ ホンジュラス 1975年度~ |
原則として20歳から39歳までの青年男女を開発途上国に派遣し、現地の住民とともに生活しながら自らの技術を移転する、草の根レベルの援助。 |
はじめに
中米、カリブ地域には農業を中心とした経済構造を持った国が多く、同地域への我が国援助も農業分野への協力が重点分野の一つとなっている。
今回の評価調査は、中米、カリブ地域のそれぞれ代表的な我が国の援助供与国を選定し、当該国において我が国援助案件を視察し、先方政府関係者や我が方援助関係者と意見交換することにより、我が国援助がどのような点で同地域の農業分野の発展に寄与しているか、また、今後どのようなことに留意して援助を実施していく必要があるかといったことについて検証し、提言することを目的として実施されたものである。
今回選定したドミニカ共和国、ホンジュラスはいずれも農業を中心とした経済構造を持ち(ドミニカ共和国のGDPの13%強が農業、労働人口の約半分が農業従事者、輸出の45%が農産品。ホンジュラスのGDPの1/4が農業、労働人口の半分以上が農業従事者、輸出の75%が農産品)、地理的にもアメリカの経済・政治等と強い繋がりを持っている点で共通項がある。今回の調査では、これら2カ国における我が国農業開発協力事業を評価するため、大型案件から草の根の協力まで幅広く視察した。
1. 総論
我々は、調査の結果を踏まえ、我が国の援助、及び援助政策、農業分野の特性等を考慮した上で、次に示す三つの視点を基本的認識として分析を行った。
(1) ODAプロジェクト、特に農業分野の援助案件は、相手国政府、裨益住民といった要素に加え、自然条件、国際貿易の動向等様々な周辺要因に左右されることから、全て当初の目論見通りに成就するのが当然であるとのスタンスをとることは楽観的すぎよう。むしろ挫折や失敗、曲折等の試練が通常であり、それを認め、要は経験から教訓をどう引き出していくかが重要である。
(2) ODAプロジェクトにおいては「継続性・一貫性・発展1生」の視点が重要である。これはっまり、いわゆるセンター案件と周辺の関連案件の位置づけを明確にする必要があるということであり、例えば地域発展の中核を担うセンター案件にまず着手し、次第に周辺に関連案件を配置し、これらをうまく結合させて複合的案件へと発展するような長期・総合・大型案件への戦略的な視点を持つことが重要である。その際には地域住民の生活形態、文化等にどのような影響を与え、また関わっていくのかといった視点も交えて検討していくことが肝要である。
(3) 援助の究極の目標は、援助を必要としない状況を作り出すことである。このためには被援助国側の制度、秩序、構造の変革は不可欠である。しかし、それを我が国が押しつけるのが好ましい訳はなく、当然変革の主体がその国ないし地域の人々である必要がある。これはっまり、当該地域経済社会の人々、及び行政部内の管理者とそのスタッフが開発推進の主体であるということであり、そのことを自覚した人々の存在が「主因」で外からの援助は「条件」であるという状態である。換言すれば、受精卵(主因)を暖める(条件)ことが援助であるとの認識に立って、受精卵掘り起こしに努めることが我が国として重要な取り組みである。
次に、これら3点の基本的認識を踏まえ、我が国の中米2カ国における農業分野の協力を視察案件をベースに分析すると、大きく分けて次の二つのタイプに分けることが出来よう。
(1) 被援助国の制度・秩序の変革がなくても、長期的・継続的に取り組んで行くべき協力:即ち、被援助国側の経済社会制度に対し、中立的な対応が可能な形態であり、技術移転を専門的範囲で奥深く推進しうる場合や拠点型・パイロット型プロジェクトとして貢献が期待できるような案件である。
(2) 被援助国側の制度・秩序の変革、ないし構造調整と並行して微調整を加えつつ取り組んでいくべき協力
:即ち、農村開発に直結した案件や、農業分野の政策金融への支援等、被援助国の農地所有、価格形成、流通経路、輸送形態等との密接な関係の中で、実施されるような案件であり、状況の進展や停滞等によって協力のあり方にも見直しが迫られるケースが想定される案件である。
このような基準に従って今回の評価調査の視察案件について概観すれば、まず、ドミニカ共和国のコンスタンサ畑作灌漑計画(無償)、果樹園芸(チーム派遣)、ホンジュラスの農業開発研究センター(プロ技)等は当初の実施期間にかかわりなく何らかの形で継続されるべき案件と言えよう。こういつた案件は当該国の開発の拠点となり得るものであり、むしろ本案件を拠点とし、関連案件と連携して複合長期大型案件として発展していくべき可能性を有した案件である。
この半面、協力隊、個別専門家並びに政府金融機関への資金援助等については、相手国の制度的側面と密接な関連があることから、その都度冷静かっ総合的視点から必要性を分析し、新規実施・継続・拡大すべきか、縮小すべきかを検討する必要がある。これは、例えば、相手国において、大土地所有制の下での多数の極貧層の農民の生産意欲を高めるような政策が取られなかった場合、協力隊員による肥培管理面等での善意の努力も、実際にこれら「圧倒的多数の土地を持たぬ層」を底上げする結果にはならない可能性があるということである。我が国援助当局としても、そういった献身的努力の成果を無にせず、なるべく最大化させるように環境を整え、バックアップしていくことが肝要である。
今回視察したホンジュラスは、青年海外協力隊発足時から多数の人員派遣を積み重ねてきており、人口規模や国土面積から考えれば、突出した実績を持つといっても過言ではない。これは、ニカラグア、エルサルヴァドルなど近隣諸国が政情不安定であったのに引き替え、ホンジュラスが比較的温厚な国民性もあって政情が安定しており、日本からの協力隊を受け入れ易い状況にあったことにもよる。しかし、こういつた国については上述の通り、前例踏襲型で多くの協力を続けるのではなく、厳しい視点で必要性の有無ないしその多寡を検討するべきである。
少なくとも、既存の枠組みの中で従来通りの対応を行うだけでは、協力隊の活動を効果的にしていくことはできないし、彼らを無力感に陥らせることにもなりかねない。
また、ホンジュラス、ドミニカ共和国政府は自作農創設に取り組んでいるものの、政策の一貫性ないし継続性に欠けて逆行している場合もある。政策金融についても、例えばホンジュラスにおいては、地主や大規模自作農に対しては国立農業銀行からの融資を行えるが、IMFによるコンデショナリティの制約のもとで、大部分の零細農はこの政策金融の対象外となってしまっている。ホンジュラス政府関係者は、その分を外からの支援(特に日本のODA)に頼ろうとしているようである。しかし、ホンジュラスの現行の農政の枠組みのままでこのような政策金融を行っても効果は少ないことが懸念され、例え我が国に新たな金融援助要請があったとしても一義的には否定的な態度で当たらざるを得ないであろう。その結果、中小零細・貧農が土地を手放すことを余儀なくされて、再び振り出しに戻る可能性もなしとしないからである。
協力隊の活動については、相手国の制度的な制約の中で、肥培管理や品種改良面での生産技術面にとどまらず、政府機関の現地管轄のカウンターパートとの連携を深めつつ、農村集落単位での作付け計画や、出荷計画から始まって、買い付け商人への安値売り渡しに変革の風穴を求めて生産物の市場開拓を手がけている隊員もおり、我々はこういつた試みを高く評価したい。この隊員の場合は、そうした試みの結果、いくつかの農村で都市近郊スーパーマーケットヘの直接の作物販売ルートを確立し、現金収入増を通じて農民の生活改善に着実な一歩を踏み出している。そういった協力隊員の努力は地域住民からも感謝されている。
一つの教訓としては、途上国の農村開発の観点からは、今後も農業技術移転のみに専念する協力隊員を送り込むよりも、むしろ生産計画、時期別作付け、出荷とそのスケジュール、販売ルート、農民口座への振り込み指導、協同化経理事務等、ひところの日本農村での農業改良普及員と農業協同事業組織管理者の知識と経験を持つような人材を送り込むことが必要であろう。
その他、調査を通じて気付いた点としては、ドミニカ共和国においては、コンスタンサ畑作灌漑計画が日系移住者への側面的支援となっている点も見逃せない。
また、CEDA(ホンジュラスの農業開発センター)における機材のメンテナンス面での自己努力は評価すべきところも多く、今後も使用状況をよく把握しつつ、部品等の供与と併せて機材更新を進めることを考えても良かろう。
中米、カリブ地域は、政権の頻繁な交替に伴う政策一貫性の欠如、各国の規模が小さいことからくる非効率性、そして近隣にアメリカという超経済大国が存在すること等、経済発展上の課題は少なくない。そういった中で我が国援助を活用し同地域の開発に効果的に貢献するためには、前述した「継続性」「一貫性」「発展性」を達成するという視点を念頭においた協力が重要となろう。しかし、我が国だけの努力では効率的・公正な援助は行い得ず、相手国の努力も求められる。その際には相手国の農業開発を取り巻く環境の中でも、特に「道路」「生産者価格」「農地改革」はそれぞれ極めて重要な要素であると考えられ、それらの改善が図られることが我が国援助の効果を高めることとなろう。第二次世界大戦後の日本の農政が、農地改革を基盤に農民意識の変革と生産力の向上によって大きく進展したことを明示しつつ、ODA実施への条件整備を強く提起していくことが急務である。
また、そういった協力の精度を高める努力を行いつつ、我が国援助に関する広報の充実、透明性の確保にもより力を入れるべきである。その際には、ODAが「日本の国民から被援助国の国民への友好の証としての協力事業である」ことを強調し、よりビジュアルな形での広報を心がけていくこと、タックスペイヤーの理解と共鳴と支持を得ることが必要である。
2. 評価対象プロジェクトの概要とその評価
(1) ドミニカ共和国
1) コンスタンサ畑地灌漑計画
本プロジェクトは、首都をはじめとする主要各都市への重要な野菜供給地であるコンスタンサ地域の農産物生産の拡大を図ることを目的として実施された。
コンスタンサは農業潜在力が高い先進的開発地域であるだけに、その開発効果は大きいものと考えられるが、かかる効果はまた、周辺地域や比較的条件の似通った地域に対して波及していくであろうと期待される。
工事は1994年から開始され、無償資金協カシステムの仕組みから1期(94~95年)とII期(95~96年)に分けて行われており、96年度中にはすべての工事が完成の予定である(工事実施期間は18ヵ月程度)。この工事の実施により、取水施設(渓流取水工と沈砂池の新設、揚水機場の設置、既設頭取工の補修)、導水施設(暗渠工の新設と既設導水路の補修)、用水施設(パイプラインの新設と既設幹線用水路及び支線用水路の改修・補修)、付帯施設(分水工、道路横断工、水路橋、水路横断車道橋、ファームポンド)がすでに完成あるいは近々完成の予定である。
工事の完成に伴って、当初期待された成果が徐々に表われつつある。灌漑用水が以前よりも潤沢に供給されるに及んで、農地の利用度が格段に高まり、多様な野菜の周年栽培(根菜類、葉菜類、豆類等)が可能となったのをはじめ、施設園芸では花卉栽培(キク、バラ、カーネーション等)が、果樹では、リンゴ、ブドウ、柿などの栽培が盛んに行われている。また、こうした集約的な園芸作物の栽培を通じ、多くの季節農業労働者が雇用されている。
その一方で、連作や肥料・農薬等の多用で土壌が急速に劣化しつつあり、加えて病虫害の発生も頻発してきているということであった。また良質で均一な種苗の供給が遅滞することもしばしば起こるという。従って、今後、土壌保全、種苗の供給体制と作付体系の改善、病虫害防除など、営農面における専門家の派遣と研修員の受入れが望ましい。
灌厩施設が整備されつつあるとしても、それを受益する農業者が主体的に、適切な水の管理と利用調整並びに施設の維持管理、水利費の徴収などに取り組まなければ、その効果はきわめて限られたものになる。実際、その管理主体となるべき「コンスタンサ農業振興組合」が十分機能を果たすまでには至らず、組合組織の強化と利用する農業者の意識改革及び啓蒙活動が大きな課題となっている。
2)果樹園芸
本プロジェクトは、近年国際価格の低迷が著しいサトウキビの代替作物としてドミニカ共和国に在来する有望な果樹の振興を図ってほしいという「ド」国政府からの要請を受けて、着手されたものである。
果樹という作物の性格上成木に達するまで数年を要することから、短い協力期間中に優良品種の選定とその品種の増殖という成果品を生み出すことは不可能であるため、協力の方法は、品種の特性調査のやり方、比較試験の実証、比較試験や苗増殖技術のマニュアル作成等といったノウハウをカウンターパート(C/P)や農業技術指導員へ定着・普及させるという手法が採用された。
プロジェクト活動は、当初予定されていたC/Pの変更、本プロジェクトに対するローカルコストの縮減や政策の見直し、現地の果樹栽培の現状や栽培技術に関する情報の不足、本プロジェクトに割り当てられた実験室施設や試験圃場の不備など、いくつかの困難な事態に直面したにも拘わらず、協力活動は順調に実施され期待された成果が得られているようである。
オオミアカテツやトゲバンレイシ及びマンゴーについて、果実の生態や形質、栽培の特性に関する調査、優良系統の品種選抜並びにその穂木収集と苗木の育成、台木の収集・特定と無病化並びに育苗用土の改善、育苗期間の短縮と接ぎ木活着率の向上による優良苗増殖技術の改善等が進められている。
また、研究の成果がC/Pにより国内外で開催されたセミナーや会議において発表されるとともに、優良な果樹農家や技術普及員へ伝えられている。
(2) ホンジュラス共和国
1) コヨラルダム灌漑復旧計画
コヨラルダムは、1965年に外国資本によりサンホセ川上流に建設された発電・農業用水、生活用水等に利用される多目的ダムである。しかしながら、最近、ダムの老朽化によりその安定性を確保する意味から、修復補強する必要が生じてきた。またダムの補強により計画貯水量が増大することに伴い、その貯水量に見合った放水路を改善していくことも重要となってきた。
こうした状況を背景として、ホンジュラス政府の要請に従い、我が国はそのための開発調査の実施を引き受け、実際の工事とコンサルタント業務はイタリアが請け負うことになった。またこの工事にかかる経費は、クウェートが負担することになった。
工事は順調に進んでいるが、いくつかの問題点もある。例えば、コンクリート打設に必要な生コンが不足しがちであるということ、貯水池の貯水量が年度によってかなり不定であり安定的な用水の供給が困難であること(このために貯水池周辺の植林が必要とされること)、そしてダムに土砂が堆積し、将来除去する場合は多くの労力と資金を要するということである。
とはいえ、ダムの補強工事により放水量が増大すれば、ダム下流域の灌漑用水受益地域であるフローレスも、安定的な作物栽培が可能となる。事実フローレス地域は、国内でも有数の野菜・果樹の園芸地帯であり、首都のテグシガルパに近いことから、近郊の園芸農産物供給基地である。ここには、コヨラルダムから放流される灌漑用水を一時的に貯水する頭首工やそこからの導水路があるが、施設が貧弱であったり、かなり老朽化が進んでいることから、その修復工事の必要が迫られていた。ダムの補強と並行して、それら施設の改善に今から着手しようとしているところである。
2) 灌漑排水技術開発計画
本計画の目的は、ホンジュラスにおける灌漑農業を発展させるため、同国の自然的、社会的条件に適合した灌漑排水全体に関する技術を研究・設定しようとするものである。このために、既存の農業開発研修センター(CEDA)内の組織充実を図り、灌漑排水全般に関わる基準の策定を目的とした調査研究部門を新設する。ホンジュラス政府は、本計画の目的を達成するために、我が国に対して灌漑排水事業の基準を設定できる技術者養成のための技術協力と本計画に関わる経済的支援を求めてきた。
本計画を推進する以前に、ホンジュラス政府は、灌漑を始めとする農業開発分野の技術者を養成する訓練センターの設立が急務であるとし、「農業開発研修センター」の設立を計画した。この計画実現のために、ホンジュラス政府は我が国政府に対してセンター施設整備(建物・圃場・排水導水路など)のための無償資金協力と技術者養成のためのプロジェクト方式技術協力を要請してきた。
「灌漑排水技術開発計画」は、この「農業開発研修センター計画」の成果を引き継ぐ形で行われる、いわゆる継続プロジェクトである。
本プロジェクト協力の上位目標は、同国の自然的・社会経済的な実態に適合した灌漑排水に関わる計画・設計の基準(地域係数)を策定し、その基準に基づいて既存の灌漑排水施設の修復・更新や維持管理を行い、施設の効率的・経済的な運用管理を図ろうとするものである。もちろん、新規の施設を設置する場合にもこの基準が適用される。そして、この地域係数を作成することのできる技術者の養成が協力の直接的な目標となる。従って、協力目標を実現するために着手すべき技術協力の範囲は、地域の実態に適合させつつ灌漑排水施設を計画・設計するために必要な各種「地域係数」を決定する手法を、C/Pへ技術移転することにある。
「地域係数」を用いた灌漑排水施設に対する設計基準の開発は、国内のそれぞれにおかれている自然的・社会経済的諸条件に適合した効率的な施設の設置や既存施設の修復に役立つものと期待されている。また、ある特定の地域で作付されている作物の種類やその成育段階、気象の状況によって、必要な灌漑と排水の水量の基準は異なっているわけであるから、効率的な作付体系に基づいて生産性の水準を引き上げるためには、施設の設計基準や水管理の在り方も当然地域ごとにきめ細かくなっていかざるを得ない。設計基準の開発も、そうした観点から大いに期待される。しかしながら、「地域係数」は、土壌の浸透性やその保水力などの土壌条件、作付される作物の生理的性質、必要な用水の質と量及び供給可能量など多様な要因によって地域ごとに異なるし、また時間の経過とともに変化する。従って、地域係数の算出、つまり施設を計画・設計する基準の策定手法技術をいかに効果的にC/Pへ移転していくべきか、この点が残された協力期間における課題となっている。
3. 調査対象案件に対する評価といくつかの提言
1) 協力案件をどのように評価するか
我が国が両国で協力している農業開発プロジェクトの基本的手法は、農地単位当たり生産性の水準を高めるための生産基盤の整備に加え、これら農業開発の分野に携わる指導的立場にある人材に対して、近代的で効果的な技術のノウハウを移転し、また技術移転に関わって必要な体系的知識を教示することにあるといってよい。その意味では、我が国の協力の姿勢は、あくまで指導する立場にある人材を育成することに重点が置かれており、農業生産者を直接的に支援するというスタンスにはない。現地政府が、マクロ的な視点にたって直面する政策課題、つまり需要の動向に見合った食糧供給の増大とか外資獲得能力のある有望な輸出産品の開発・育成といったような課題を解決するために、我が国をはじめとする先進援助国に対して技術と資金の協力を要請するというものである。
今回のケースも、まさしくそうした政府主導型のトップダウン方式により、開発プロジェクトの政策決定がなされ、事業実施のすべての過程を政府が掌握するという形態であった。その限りにおいては、農業生産者並びに事業が展開されている地域の住民は受動的な立場に置かれることになる。このため制度的な枠組み(農地制度とか金融システムなど)いかんによっては、開発プロジェクトの振興に伴う恩恵が特定の社会階層に固定化される恐れがある。その結果として、プロジェクト実施地域の内部における階層間の格差が助長されて、貧困層はいっこうに改善されずますます困難な局面に追い込まれることにもなりかねない。
もちろん、今回調査した協力プロジェクトは、協力事業の内容自体としては十分に意義深いものであるが、そのプロジェクトの展開に伴う開発の恩恵が、一体誰にどういう形で帰属するのか、事前の計画段階において必ずしも特定化されていたわけではない。加えて、プロジェクトが展開する過程で、地域の内部ではどのような農家の階層分化が起こり、それによって階層間の経済格差がどの程度生じ、また世帯内におけるジェンダー(男女間の社会的役割)の変容がどのような形で生起するものと事前に予想されていたのかについても、明らかではない。もし、プロジェクトの展開によって引き起こされるであろうこうした事柄のシナリオが、前もって想定されていたならば、最低限不利な状況を招かないだけの手立てが用意できていたかもしれない。
例えば、ドミニカ共和国有数の農業生産地帯であるコンスタンサで、我が国の無償資金協力で実施している畑地灌漑計画は、既存の灌漑施設を改修するとともに、新規に施設を設置することによって、当地域の水利条件を改善することに大きな主眼が置かれた。この事業によって、当地域の野菜栽培を主体とする農業の生産性が飛躍的に向上し、また農地の有効利用が図られることになったのは、紛れもない事実である。コンスタンサの農村風景は、一見して我が国の情景と見間違うほどまでに整然としていて美しく、この地に灌漑用水が網の目のように行き届くことによって、緑豊かな大地が約束されたのは、想像に難くない。農道の路上では、野菜を満載したトラックが所狭しと行き交っている。しかしながら、その一方で外観からだけでは決して理解し得ない構造的課題を地域の内部に内包していることも事実であろう。コンスタンサにおける農家の経営規模をみると、農家戸数全体の60%が1.Oヘクタール未満の零細農家であり、経営規模5~1Oヘクタール以上の農家となると、全体のわずか10%でしかない。域内には土地無しの貧困世帯がかなりの戸数にのぼっている。彼らは、専業農家のもとで野菜の苗の定植や収穫・運搬などの作業に従事する季節的な農業労働者であったり、その地域内での種々雑多な就業の機会をとらえて日々の生活の糧を得て、いわば生存ぎりぎりの生活を強いられている。これに対して、規模の大きい富裕な農家階層では、以前から灌漑用水や自分で築造したファーム・ポンドを有効に活用して、優良な種苗や肥料・農薬などを投入し、優れた営農技術を駆使しながら高い生産性の水準と所得を確保していた。今回の灌漑施設の改修・新設により、さらに効率的な農地の利用と営農活動が期待できる。彼らが、いわば地域のリーダー的存在であり、任意組合や水利組合を結成して、投入財の共同購入、生産物の共同出荷、灌漑用水の各圃場への配水、水利費の徴収などに取り組んでいる。
ともかくも、現行の条件のもとでは、灌漑施設の改修・新設が富裕な農家階層に対して有利に作用するばかりか、これら階層によって主導される任意の協同組合や水利組合の運用の仕方も、富裕層のもつ政治的な権力の行使いかんで、自らの利益拡大のために誘導される恐れもなしとしない。農地所有制度とか信用供与サービスといった制度的システム、技術の農家レベルヘの移転普及という公的サービス、農業者人材養成のためのシステム、さらには農産物の価格決定やその市場流通、生産者組織の形成の在り方が、より貧困な階層の社会経済的地位と所得水準の向上を目指して制度的に改善かっ政策的に支援されなければ、善意の無償資金協力が、域内の貧富の格差拡大を助長することにもなりかねない。
このことは、コンスタンサ畑地灌漑計画だけでなく園芸開発計画や、ホンジュラスにおけるCEDAでの灌漑・排水開発計画、その他の協力案件についても同様にいえることなのである。
このように、協力案件のプロジェクトがその性質上たとえ中立的なものであったにせよ、実際に協力活動が展開され、その効果が地域へ浸透していく過程で制度や政策というプリズムが歪んでおれば、協力の成果は当然のことながら偏重し屈折してしまうことになる。従って、プロジェクトを立案/計画する段階で、プロジェクトの上位目標が何で、誰を協力対象とするのか、社会的な公正を達成するためにどのような制度改革と政策的支援が必要なのか、またプロジェクトの実施による成果を持続させ、より発展的なものとするためには、次の段階でどのような協力パッケージを用意し、現行のプロジェクトに連動させたらよいのか、などをかなり明確なものにしておかなければならない。こうしたきめの細かい配慮を怠るならば、その実施の過程でプロジェクトの自立性・持続性は大きく損なわれ、むしろネガティブな効果が生み出されるかもしれないのである。
確かに相手国の制度改革や政策的支援は協力の範疇を大きく逸脱し、このことは、むしろ相手側政府の姿勢や国民の意思決定に委ねるべき問題であるかもしれない。しかしながら、それらの問題をいつまでも不問にしてプロジェクト推進のために協力を続けることが、決して望ましい姿といえないことも事実であろう。そのためには、次の項でも述べるように相手側政府に制度の改革なり政策の改善を強く働きかけ、粘り強い政策対話を続けていくことが必要なのである。少なくとも、相手側政府の機能の中に格差の問題を軽減し地域社会の参加を促進するような仕組みが内在しているのか、もしくはそのための努力を払っているのか、を確認する作業が必要となろう。
指摘するまでもなく、開発の主体はあくまでも相手側政府であり、またプロジェクト・サイトに居住する地域住民である。しかしながら、協力する側もプロジェクト自体が果たして地域住民を開発の様々な局面に参加させ、開発の恩恵を広く住民に均霧させるような、いわゆる「参加型開発」を指向しているものであるのかどうか注視し、モニタリングするだけの自覚と責任を負わなければならないであろう。参加主体である地域住民の間に意識化・組織化が図られ、社会的能力が高まっていること、その能力をいかんなく発揮できるインスティテューションの舞台が整っていることが、「参加型開発」の前提条件であることを、もう一度想起しなければならない。
2) いくつかの提言~より効果的な協力アプローチの構築を目指して
「参加型開発」を進展させる方向で協力を実施するにあたり、極めて重要なことは、開発協力の効果が参加主体の経済的・社会的能力の育成・向上に対して如何に貢献し得るのかといった視点を明確に位置付けることである。そのためにどのような点を考慮に入れるべきなのか、以下いくつかの提言を整理して述べることにしよう。
まず第一に、想定される最終的な受益者の経済的、社会的なニーズを的確に把握するために、プロジェクト・サイトの地域構造に関する綿密な事前調査活動を実施し、その結果を協力の計画に反映させることである。また、より多くの地域住民がプロジェクトの局面に主体的に参加して協力の成果を享受できるように、地域社会の組織づくり(住民の組織化)と制度づくり(インスティテューションの構築)に対する支援の在り方を検討し、地域住民とともにその実施の手順を探っていくことが重要となる。支援の在り方なり実施の手順は地域住民との間だけで検討し協議するのではなく、相手側政府とも検討を重ね、公的なレベルでの支援策を得る努力も必要になってくる。
第二に、開発プロジェクトの発掘とその案件形成一計画立案一実施、そしてその評価に至る、いわゆるプロジェクト・サイクルの諸段階で、途上国自らが「参加型開発」の要素を取り入れて開発プロジェクトのマネージメントを行うことができるように仕向けることである。そのためには、相手国側の自主性を尊重した上で、既存の政府組織とシステムの改善、新しい制度づくりについて突っ込んだ協議を行い、緊密な対話と支援活動を通じて、相手国側の理解促進及び能力向上を図る必要がでてこよう。
第三に、協力の実施にあたっては、現地の事情に精通したNGOと密接な連携をとりながら、彼らが過去に蓄積してきた人材の訓練・研修のためのノウハウを生かすことが不可欠な条件であるということである。現地NGOは、これまで地域住民の自主的な組織づくりを強化するための彼らの意識向上を目的とした啓発訓練や生産力向上のための技術支援に努めてきた貴重な経験を有しており、プロジェクト実施の過程においてNGOが参加する機会を増大させるだけでなく、計画の策定/立案の段階からNGOの参画を得ることが必要であろう。また、一口に現地に駐在しているNGOといっても、活動形態やその専門的機能において多様であることから、NGOの活動範囲に関する詳細なリストを作成すると同時に、それを基礎にしていかなる協力分野及び協力段階において、どのようなNGOとどのような側面で連携を図っていくかの指針、運用上のマニュアルを作成しておく必要がある。
第四に、「参加型開発」に関わる我が国の協力人材を育成すべきという点である。そうした人材とは、コミュニティ・レベルの社会構造や政治構造並びにその社会に存在する相互扶助組織やそのシステムなどについて社会分析等を通じ十分に理解した上で、住民が開発の過程に参加できるようにするための条件整備や住民参加を促進するための手法を、よく熟知している専門家である。我が国では、まだこうした組織づくりのノウハウを有する協力人材が育っているとはいえない。ただし、農村開発の分野においては、農業改良普及員とか生活改善普及員などといったような営農と農家生活の改善に関する技術の指導普及に長年携わってきたスタッフとか、農協など生産者団体の組織運営に関わってきた人材が豊富に存在する。かかる人材は、組織づくりや組織の意識啓発、地域住民の社会的能力の育成向上に対して、貴重な経験と有益なノウハウを有していると考えられるので、それを協力の現場にどのように生かすべきか、今後十分考慮するに値しよう。
以上、四つの点に整理して「参加型開発」を促進するための協力アプローチの在り方を指摘した。これまでにも再三述べてきたように、「参加型開発」に即した地域住民の自助努力を支援するために、我が国が留意すべきことは、地域住民の開発ニーズと受容能力を見極めつつ、住民がプロジェクトへ主体的に参加できるような環境を整えてあげることであろう。そして彼らの意向が十分プロジェクトの計画・実施に反映されるように努め、その過程で住民によって形成された組織の社会的能力(資源維持管理能力、自治管理能力並びに対外交渉能力など)を向上させるために援助の手を差しのべるべきである。そして何よりも、まずもって「参加型開発」プロジェクト案件形成のための事前調査マニュアルを作成することが、もっとも差し迫った課題であると考えられる。

