7. ネパールにおける経済協力評価
国際基督教大学国際関係学科教授 中内 恒夫
(現地調査期間:1996年2月10日~2月18日)
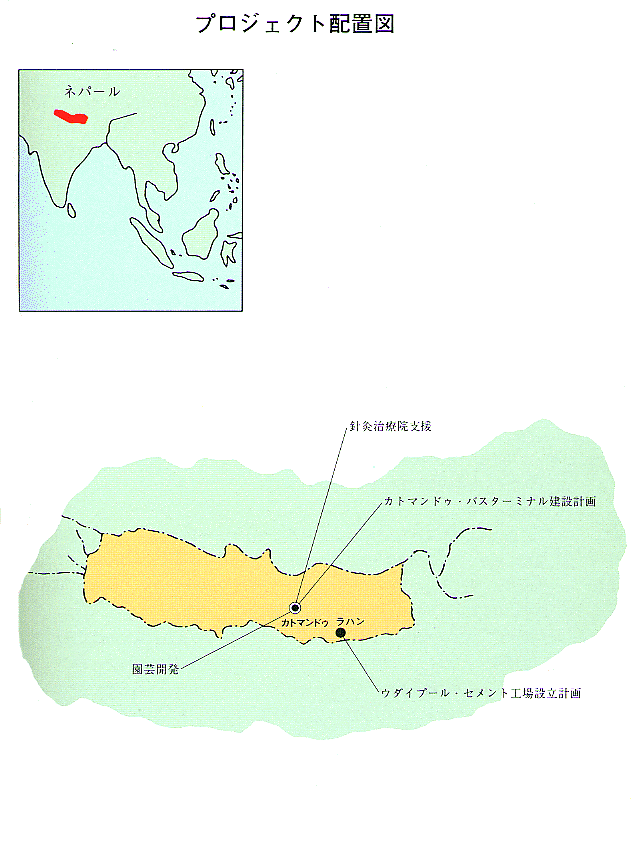
評価対象プロジェクトの概要
| 案件名 | 協力形態 | 協力期間、金額 | 案件概要 |
| 園芸開発計画 |
無償資金協力 プロジェクト方式技術協力 |
1985年度、 8.47億円 フェーズI 1985年10月~ 1990年10月 フェーズII 1992年11月~ 1997年11月 |
園芸の強化により食糧事情を改善し、かつ輸出振興を目的として、新換金作物を導入するための計画策定、適正作物の選定、普及員の養成等に関する技術協力を行う。 |
| ウダイプール・セメント工場設立計画 | 有償資金協力 |
1987年度、 187.70億円 |
セメントの需要拡大に伴い、国内資源を活用し、国内の工業の強化を図るため、セメントエ場を建設。 |
| カトマンドゥ・バスターミナル建設計画 | 無償資金協力 |
1991年度、 7.86億円 |
未整備なバス輸送システムを改善することにより、カトマンズ市内の交通機能の向上を図るため、バス・ターミナルビルの施設を建設し、機材を供与した。 |
| 針灸治療院支援 | 草の根無償資金協力 | 1992年度、 | 訓練活動の普及を通じて雇用機会を拡大する。 |
この評価調査は、「有識者評価マニュアル」作成調査の一環である事例研究として、行われたものです。
第1章 個別案件の評価
1. 園芸開発計画
(1) 評価結果概要
技術移転の達成度及び期間延長(フェーズII実施)への経緯に注目して、本案件を評価した。
1) 目標達成度及びインパクト
現在、35名の技術普及員が六つの地域に設けられたサブ・センターに常駐しており、本プロジェクトによる研修、新品種導入等の成果を広く普及している。また、日本から持ち込まれた柑橘類や梨等の果実が順調に生育されており、これからの市場化に期待が持たれる。
2) 効率性
別に無償資金協力で建設されたセンターと有機的に結びついたプロジェクトである。また、土着の種類と日本式接ぎ木をしたものを隣接して展示するなどの工夫を施し、周辺農民の啓発・研修のためのデモンストレーション・ファームとしての機能にも十分な配慮が施されている。
3) 妥当性
政府の当該分野における政策に合致している上に、現地レベルに対応した技術導入及びきめ細かいトレーニング・メニューの整備など、現地に受け入れられやすく、また定着しやすい方式がとられている。ただし、当該分野の研究を集中して行うことを目的として先般新設された政府機関と、本センターでの研究活動とが、必ずしも効果的に連携していない。
4) 自立発展性
現地日本側関係者からのクレームにもあったが、ネパール側カウンターパートの頻繁な交替は事実のようである。これに対して、フェーズ[開始時からはカウンターパート毎にアシスタント・カウンターパートと呼ばれる補助員をつけ、継続的な技術協力ができるよう配慮してはいるものの、カウンターパートを本センターに定着させるための根本的な対策は特に実施されていない。
(2) 教訓と提言
在来品種よりも良質の作物の生産が軌道に乗りつつある現在、案件による開発技術の普及にあたって流通網整備・市場開拓は不可欠である。現状の限られた量であればホテル等の売り先で十分であるが、今後こうした技術を発展させていくためには市場確保は非常に重要な条件であると言える。
従って、フェーズ皿が必要かどうかについては、さまざまな要素を併せで慎重に検討しなければならないが、現在までのプロジェクトの達成状況ならびにプロジェクトの存在意義そのものに鑑みるに、自立発展性確保のために、市場調査実施等を含めた運営・管理及びマーケティング能力向上のための技術移転の必要性が認められる。
2. ウダイプール・セメント工場設立計画
(1) 評価結果概要
本案件については、セメントの国内需給における当該工場の貢献度及び事業経営の適切性を重点項目として評価に臨んだ。
1) 目標達成度及びインパクト
セメント需要に関しては、当初計画の予測通り、国内需要が年平均10%(1984-1994年)で著しく増加しており、本工場は国内3工場のうち最大のもの(日産800トン)として大きくネパール経済の発展に貢献しているとの評価を得ている。
2) 効率性
事業経営の現状については、財務諸表等の資料が整備されておらず、詳細な分析は不可能な状況である。ただし、現時点では債務の返済は開始されておらず、円高による負荷増大を併せて鑑みるに、この返済計画のあり方が本プロジェクトの正否の鍵となることが予想される。
3) 妥当性
ネパールの開発においてインフラ整備に高いプライオリティが与えられていることに加え、セメント生産は大幅な需要超過の状態にあった。その意味で、このセメント生産プロジェクトは目的の設定において妥当であったといえる。
4) 自立発展性
良質な原料を利用しているため、生産されたセメントも質が良いことで知られており、その市場は安定的に発展するものと予測される。しかし、稼働率が60%前後と低く、その原因究明のための調査が必ずしも実施されていないことから、その市場の成長性に対する多少過度な自信がうかがわれる。
(現在、OECFにて実施機関の立場から評価を実施中のところ、稼動率の問題についても確認の上、必要な対応を行う。)
(2) 教訓と提言
プロジェクト自体は、国内需要の増大に対応すべく計画され、適切に実施されているが、同国における質量バランスの現状を考慮すると、質を多少低めても量産を可能にする技術的方策も検討に値する。また、稼働率を下げている理由として挙げられている「不適正な部品調達」及び「技術労働者の質的・量的不足」は普遍的な問題であるが、今後の事業の発展を考えた場合、深刻な課題であり、運営・管理能力改善のための技術移転、職業訓練制度の強化等、いくつかのバリエーションを持った対策が早急に用意されるべきであろう。
3. 力トマンドゥ・バスターミナル建設計画
(1) 評価結果概要
本案件では、効率的な中・長距離バス運営及びカトマンドゥ市内の交通渋滞緩和に対するインパクトをポイントに評価を行った。
1) 目標達成度及びインパクト
ターミナル整備以後は中・長距離バスが市内中心に集結しなくなったため、交通渋滞の発生要因の一つが取り除かれた。さらに、ターミナル周辺には店舗・住宅等が広がりつつあり、プロジェクトによる開発の波及効果も認められる。
2) 効率性
チケット売場の運営をバス会社組合に委託するなど、合理的な運営が行われており、車輌の発着等もスムーズに管理されているように見受けられる。ただし、一日100台程度の見込みのところ、現在タクシー等も含めて約400台の車輌が出入りしており、すでに許容量限界の感がある。
3) 妥当性
カトマンドゥ市の中心から30~40分程度離れているため利用しにくいとの苦情が多く聞かれるが、中心部の渋滞状況に鑑みれば、多少郊外に設置することになったのはやむを得なかったといえよう。ただし、その中心部とターミナルを結ぶアクセス整備は不十分なままである。
4) 自立発展性
すでにバス会社組合による運営は軌道に乗っているといえ、その発展には大いに期待できるところである。本ターミナルのスペース不足を受けて、その拡張あるいは新たなターミナル整備の構想案があり、現在よりもさらに民間活力を取り込んだ方式を目指している。
(2) 教訓と提言
本案件は不特定多数の住民が便益を得られるという性質により、かなり知名度が高く、日本によるODAの宣伝効果も大きい。ただし、市中心部からかなり遠いためターミナルまで市内バスを利用しなければならず、その市内バスによるアクセスは決して十分とはいえない。未だに解決してはいない市内の交通渋滞を考慮すると、現在のロケーションは妥当といえるだろうが、アクセス道路の整備など、中心部からのアプローチを改善することにより、施設整備による波及効果をより一層拡大することが必要であろう。
4. 針灸治療院支援
(1) 評価結果概要
本件では、援助資金の利用法を中心に、通常案件と比較して圧倒的に少額のインプットによる援助効果の現れ方に注目した。
1) 目標達成度及びインパクト
他に例がないという珍しさも手伝ってか、非常に盛況であり、客並びに生徒に好評である。その規模から、国民経済に与える影響の数量的把握は困難だが、小さくとも現地住民の生活に対する具体的なインパクトは目に見えやすい。
2) 効率性
援助額は少額ではあっても、援助先が現地NGOという性質上、必然的に資機材等は現地調達となり、かなり充実した整備が可能である。
3) 妥当性
既存施設・設備の拡張・改善のための協力であり、ある程度被援助団体及びプロジェクトの実績内容について、十分にスクリーニングが行われた後での実施であった。
4) 自立発展性
現地の人々を顧客の対象としたサービスを技術の実地訓練とし、主に観光客を相手にしたサービスを利益獲得にあてるなど、教育・訓練と事業運営を両立している。ここで訓練を受けた生徒たちの働く場の確保が、これからの事業存続のための課題である。
(2) 教訓と提言
民間NGOに供与する場合が多いこのスキームでは、特に被援助組織の運営能力が重要であると考える。その意味で、運営システム及び人材スタッフの審査が重要であり、“良質案件"ならぬ“良質NGO"の発掘が鍵であろう。また、将来的には、他スキーム(技術協力等)との組合せを促進することが、援助事業の幅を広げることになるのではないだろうか。
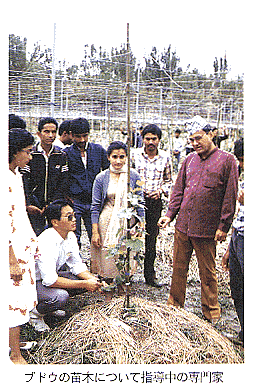

第2章 横断的提言
1 セクター・レベルの提言
従来、我が国の対ネパール援助は、同国が農業を中心産業とするLDCであるという経済的特徴に対応して、社会基盤(基礎インフラ)、農業、保健・医療を重点セクターとしてきた。同国の発展レベル等に鑑みて、この傾向は特に大きく転換することはないものと考えられる。また、今回の現地政府当局者との協議においても、この重点設定は基本的に支持されている。ただし、これから徐々に流通関連整備や職業訓練協力等の産業支援型プロジェクトもより推進されていく必要があろう。
2 政策レベルの提言
開発援助事業においては、経済開発及び人道的支援といった面はもちろんであるが、プロジェクト及び援助国について現地住民に広く知られるための配慮も必要である。この意味で、今回対象としたバスターミナルは住民の間で大変評判が高く、好例であった。こうした不特定多数の便益享受者を対象とする案件も引き続き実施する必要があろう。
また、ネパールは地形によって、大きく地域の特徴を異にしており、地域による経済格差も大きい。“地域別援助戦略"といったものを検討し、同種の特徴を持つ諸国への援助における一つの事例を示すことが可能であるかもしれない。
ただし、隣国のインドなどとは異なり、ネパール政府には援助に対するかなり強い依存体質がうかがえる。さらに、政府の体力から判断して、効果的かっ自立発展性のあるプロジェクト形成のためには住民参加を重視していくことが適切であると考えられ、技術協力や草の根無償資金協力等の比較的小規模なプロジェクトの推進が当面適当であろうと考えられる。

