6 中国、モンゴルにおける経済協力評価
財団法人 新日本ITU (国際電気通信連合)協会
専務 理事 岩噌 弘三
(現地調査期間:1995年8月20日~9月3日)
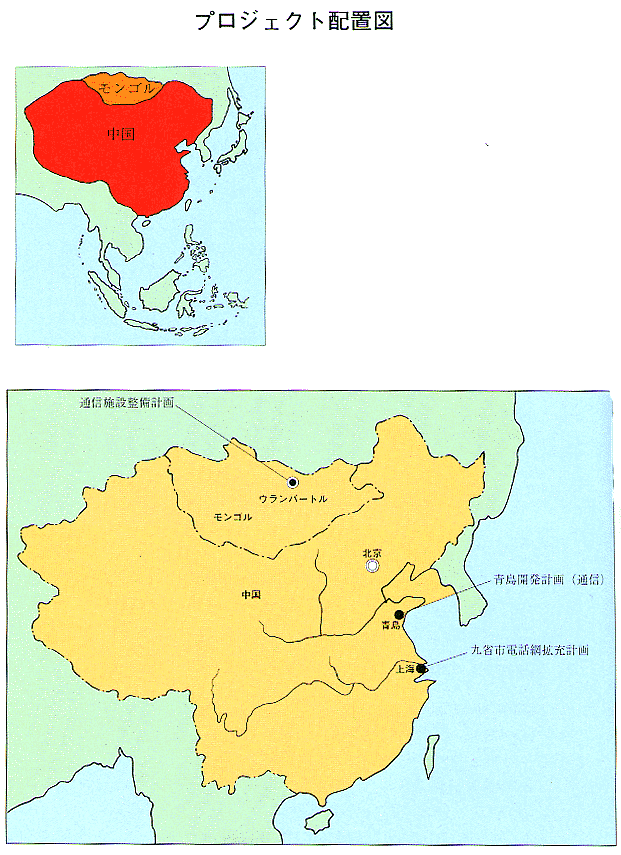
評価対象プロジェクトの概要
| プロジェクト名 | 協力形態 | 供与金額、協力期間 | プロジェクトの概要 |
|
通信施設整備計画 (モンゴル) |
無償資金協力 |
1991年度、 9.48億円 1992年度、 5.62億円 |
国際通信の改善のため、首都ウランバートルに衛星通信地上局関連設備(第1期)及び国際・市外併合交換機(第2期)を設置し、衛星地上局との間をマイクロ波回線で結ぶ。 |
|
青島開発計画(通信) (中国) |
有償資金協力 |
1990年度、 40.34億円 |
青島市に電話交換機、保守・運用センター、局間伝送装置、加入者ケーブル等を新設する。 |
|
9省市電話網拡充計画(I)(II)(III) (中国) |
有償資金協力 |
1990年度、 178.00億円 1991年度、 115.76億円 1992年度、 143.58億円 |
天津市、上海市、広東省など9省市に、各種電話交換機などを設置する。 |
はじめに
今回の評価は、モンゴル、中国における我が国の通信分野の経済協力案件3件を調査し、個々の案件の評価を行うとともに、今後の我が国の通信分野における経済協力のあり方を探ったものである。
1.通信施設整備計画(モンゴル)
(1)調査実施の概要
日本大使館において各種説明を受けたほか、電気通信担当として現地で活躍中のJICA専門家2名から、資料提供と現地説明の協力を得た。
モンゴル側では、外務省、通産省及びインフラ開発省との面談の後、モンゴル通信会社(MTC)とも会合を持った。
さらに、前記JICA専門家とMTC幹部の案内で、ウランバートル市郊外にある衛星通信地上局設備と市の中心部にある郵電局の電話交換機設備の実態調査を実施した。
(2) 調査結果
(イ) すべての機関において、本件は非常に成功したプロジェクトであるとの高い評価を得た。
このプロジェクトの下での設備が導入される前は、国際回線としては、ロシアとの間に、インタースプートニク衛星経由が4回線、地上マイクロ波経由が4回線、ケーブル経由が9回線に加えて、北京との間に裸線線路が3回線存在したのみであった。
日本などの外国との通信はこれらの回線によって行われていたため、国際接続の待ち合わせ時間も長く、接続が行われても劣悪な通話品質であった。新設備完成後は、世界の多くの対地と即時接続で通話できるようになり、また音声の通話に比べてより良好な回線品質を要求されるFAX通信も問題なく伝送されている。現在もインタースプートニク衛星によっているロシアヘはFAXがうまく伝送されないことが多いとのことであった。
(口) モンゴルからの国際通信料金は非常に高く設定されている。例えば加入者ダイヤルによるモンゴルから日本向けの料金は1分間5米ドルであるのに対し、日本からのKDD料金は最初の1分間は360円であり、その後は220円となる。モンゴルとしても料金を国際水準に下げ、企業にも個人にも、もっと利用させるべきであると考える。
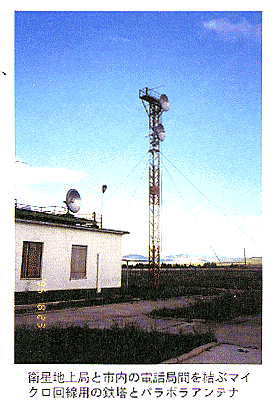
この点に対しては、モンゴル側は国際通信の利益で国内通信の赤字を補填していると主張している。しかしながら、都市国家や島嶼国など一部の例外を除いて、一般に国内通信の方が国際通信よりはるかに規模が大きく、国際通信の黒字で国内通信の赤字を埋めるという考え方には無理がある。日本では売上規模で見た場合、国内通信は国際通信の約28倍の規模であり、モンゴルも国内通信の発展のためには、国内通信の例えば住宅用電話の基本料1ヵ月1ドルのような低料金を改め、独立採算にできるようにするべきではないかと考える。モンゴル側もMTC社長などは、国際通信料金と国内通信料金の見直しの必要性をアジア開発銀行から言われており、その必要性を理解しているようであった。
国際電気通信連合(ITU)では、古くから一国の電話普及率と国民人当たりの国内総生産(GDP)との間には密接な関係があることを明らかにしているが、モンゴルでは、旧社会主義国の特異な政策のせいか、世界的な平均からすると、国民一人当たりのGDPの割に多くの電話を設置している。このため、ユーザーはこうした多くの電話を負担する能力が低く、コストに見合った料金が設定できない状況と考えられる。国内通信の赤字経営は、将来、国内通信設備の拡大計画の実行に当たって制約となる可能性がある。
(ハ) 衛星地上局との会談では、すべての設備は良好に機能しているが、強いて言えば電力に関して問題がある、との話であった。商用電力は信頼性を高めるため2系統を地上局へ引き込んでおり、両方停電した時には、45分間のみは蓄電池で電気を確保できる。ただしこれでは時として十分でなく、大型の非常用発電機を上層部へ要求しているが、まだ認められない、とのことであった。国際通信は大きな利益を上げているのだから、それくらい自力で購入するようにすればよいのではないかと提案したが、旧社会主義時代の体制のせいか、収入と支出は全く別のチャンネルになっているようであった。世界的に見て、電気通信は利益を上げることのできる事業であるが、収益を国家に吸収される構造では、自己資金による電気通信設備の拡充ができなくなる。事業運営的な考え方の導入が必要と考える。
(二) 本プロジェクトで日本政府からモンゴルへ供与した電話交換機は、国際と市外との併合交換機である。しかし現実には国際交換機としてのみ使用され、市外回線564回線の規模で国内の各地と結ぶ予定であった市外交換機としては使用されていない。その代わりとして、同じウランバートル市内に設置されたアルカテル社のE10B交換機に、市外交換機としての機能を果たさせている。
(ホ) 公衆通信用の電話網は、国際交換機を頂点に市外交換機を経て、底辺の市内交換機へと一般的にピラミッド状に広がっている。最上位の国際交換機とそれに伴う衛星通信施設を日本から無償供与したのであるから、それを一種の目玉商品として、後に続くさらに大規模な市外および市内交換機の分野での日本製品の進出につながることが望ましかった。しかし、アジア開発銀行の資金により、アルカテル社がいち早く首都の大部分の地域をカバーする市内交換機を供給した。最近、シーメンス社が首都の残りの地域向けの市内交換機を供給することになったとの情報もある。各国が電気通信マーケットヘの進出に激しい競争を行っている状況では、我が国の電気通信分野での途上国協力は広い視野での戦略が必要であろう。

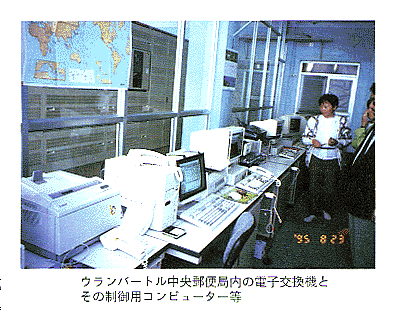
(へ) モンゴルの関係各省を訪問中に、モンゴル通信会社(MTC)がKorea Telecomにかなり大規模に株式を売却し合弁事業を行う予定であるとの話がでたが、明確な説明は得られなかった。しかし最後の8月23日にMTC社長と会談した際になって、次のような意外な話が突如として出てきた。
「この8月1日から、通信会社は次の二つの会社に分割された。
MCAC:国営の会社で、資産を所有し、政策などを担当し、約30人のスタッフで構成される。
MTC:MCACから通信設備を借り受けて、ユーザーへのサービス提供を担当する。1,000万米ドルの資本金で構成される株式会社であり、40%を外国の投資家向けにテンダーにかけた結果、Korea Telecomに決定した。後は契約調印のみが残っていて、多分8月31日に行われるであろう。従業員は、現在約5,000人で、Korea Telecomからは多分数人の技術者とマネージメントやマーケテング関係に2~3人派遣されるであろう。」
このような大きな改革も一般には報道されておらず、MTCに毎日勤務しているJICAの専門家にも、初耳だったようである。国の体制の違いを痛感するハプニングであった。今後日本の協力を進めるに当たっても、新体制を前提に検討する必要がある。
2 青島開発計画(通信)(中国)
(1) 調査実施の概要
青島市郵電局において、収益状況、今後の投資計画、問題点などの説明があった。その後、電話局を訪問し、円借款で設置された電子交換機、保守・運用センター、手動交換台、電源装置などの実地調査を行った。
(2) 調査結果
(イ) 円借款により加入者8万回線のためのデジタル電話交換機とそれに付随する伝送設備、加入者ケーブル、光ケーブル、空調設備などが購入された。このうち5.5万回線は新設の電話局7局(旧方式の交換機をこの機会に撤去して、電子交換機に変えた局を含む)に割り振られ、残りの2.5万回線は、すでに稼働している電話局で設備の増設に使用された。機種を統一する都合上、既存の交換機納入の会社から随意契約で購入された。
(口) 総投資額は2.3億元に対し、電話を新設するとき、ユーザーから3,000~5,000元(郵電局の話では、北京は一律に5,000元で、これより安いとのこと)徴収しているとの話があった。現在すでに6万加入がこの設備に接続されている。郵電局からは、元に対し円が強くなってきており、返済条件が実質厳しくなっていることに不満を表明した。しかし、6万加入の開通時にすでに元ベースでの総投資額をほぼ回収しており、円高になる前に実質円借款を返済できたバランスになっていて、それ以降はすべて返済を終わった設備で収入を上げて行っているという非常に健全な経営と考える。
明治時代に電話を財産とみなして電話加入権と言う概念を導入した日本を例外として、先進国では、電話事業は電気や都市ガス事業と同じく、接続時に特別に高額な一時金を徴収することなく工事料程度の徴収に止め、長期の使用料で投下資本を回収するという考え方を採用している。これに対し、青島では電話は家電製品などと同じ概念で販売・新設されている。急速に発展している中国では、人々は一刻も早く電話を欲しがっているため、電話が高額であることについてはあまり不満がないようである。この点を考えると、中国のこうしたやり方も投下した資本をすぐに回収し、それを再投資に回すことによって、雪だるま的に規模を拡大できるので、非常に賢明な方策であると考える。
(ハ) 郊外を含め電話交換機容量はすでに60万端子に達している。ただし、申し込んでいるが開通していないものが3万あるので、本年8万端子の増設計画を自己資金と銀行からの借入金を使って実施している。初期の円借款は電話網拡大のためのスタート役として、非常に重要な役割を果たしたと判断される。しかし、その後は、巧妙な政策によって、資金的にはあまり苦労せずに順調に拡大路線を歩んでいるものと考えられる。
(二) 電気通信網では、それを構成する機種は出来る限り少ないことが望ましい。円借款で購入された電話交換機は、日本のNEC社製のNEAX-61型と、アルカテル社系の上海ベル社の1240型の2機種である。最新の交換機間の信号方式であるNo7信号方式は同一メーカー間は良好に機能しているが、異機種間は問題が残っている。この2機種の信号方式についてはいまだにメーカーの技術者が調査・調整中であった。また、交換機の運転状況や障害を集中監視・制御する保守・運用センターにも2機種用の設備と要員を配置せざるを得ない状況であった。日本などと異なり競争入札をせざるを得ない条件下ではこうした不便も止むを得ないことと考えられる。
しかし、最近新たにAT&T社のNo5交換機を8万回線設置することにしたとのことであった。No5は最も進んだ交換機であり、各種の新サービスができることが理由とのことであるが、他の交換機に接続された加入者は新サービスが受けられないため不公平な状況となる。電子交換機の特徴は、ソフトウエアを入れ替えて新技術・新サービスに対応できるところにあり、度々新しいソフトウエアに入れ替えて、全加入者に同一の新サービスを提供するのが、一般的な考え方であると考える。
No5交換機の設置場所は今後発展が予想される郊外とのことで、一応設置エリアを分けようとしているようである。別の情報によれば、AT&Tが青島に約100億円規模の交換機製造工場を建設したとのことである。政治的な判断を迫られ、上記の素人向けの導入理由説明を行っている可能性も否定できない。
(ホ) 新技術の自力による運営には、十分な訓練を受けた良質な技術者の確保が重要である。青島郵電局では、ボーナスが普通の給与と同額支給されており、実質的に毎月の給与が2倍になっている。青島では郵電局は最優良企業の一つとして、市民から羨ましがられており、従って優秀な人材の確保も容易であるとの説明があった。
3.9 省市電話網拡充計画(中国)
(1) 調査実施の概要
このプロジェクトは、中国の天津市、上海市、広東省、広州市(広東省ではあるが別扱い)、黒竜江省、福建省、陝西省、吉林省、浙江省及び江蘇省における国際電話交換機1,400回線、市外電話交換機30,320回線及び市内電話交換機76.5万回線を新増設するもので、!990年度から円借款437.34億円を供与している。まず、北京の郵電部で全体的な調査を行い、詳細な調査及び現地の施設調査については、本計画のカバーする範囲が極めて広いため、国際、市外及び市内電話交換機が含まれていた上海のみを調査対象に選んだ。
北京で中国郵電部と、上海で上海市郵電管理局及び上海市人民政府対外経済貿易委員会と会談を行い、その後、電話局施設の実地調査を行った。
(2) 調査結果
(イ) 中国及び9省市全体
(1) 本計画で設置された諸設備のうち最も規模の大きい市内電話交換機では、富士通(F-150)、NEC(NEAX-61)、上海ベル(S1240)、AT&T(Nα5)及びアルカテル(E10B)のものが採用されている。
(2) 郵電部の資料によれば、中国全土での電話交換機容量を今世紀中に1億4,000万端子にする計画である。1994年末時点の電話交換機容量は、6,162万回線に達しており、1993年末に比べて1,956万回線の増加となっている(参考:日本での過去最大の年間加入者増加数は340万)。最近の中国の急速な発展の下で電気通信の拡充に桁違いの投資が行われている。
(3) 電話普及率についても、1995年末で、全国平均が4.2%、都市部の平均は17%に達する見込みである。電話の新規開通の平均所要期間も3ヵ月未満、最長でも6ヵ月未満となっており、申し込みの95%以上が3ヵ月以内に開通するという、開発途上国では格段に良好な水準に達している。
(4) 電子交換機の特徴を生かして、3者会議通話、多数参加会議通話、留守番電話サービス、目覚ましサービス、ホットライン接続サービス、着信課金の800番サービスといった新サービスが提供されている。
(5) 9省市全体で1995年1月までに167の契約調印が行われており、その合計額406.035億円は、円借款総額437.34億円の92.84%、支払額372.7411億円は、67.36%となっており、順調に進捗中である。
(口) 上海
(1) 当初の円借款調印時の計画では、国際交換機1,400回線、市外交換機2,500回線及び市内交換機12万回線を設置するという内容であった。ところが、1991年、直轄市及び省都で使用する市外交換機、国際交換機は、すべて上海ベル製を採用するとの決定が中央でなされたため、円借款は国際競争入札とするとの原則に反するという理由で、本件円借款は伝送装置の設備に使用することとした。戦略的に考えると、電気通信網を立体的に押さえることは極めて重要である。電気通信網は必ず拡大するものであり、拡大するときには交換機の特性上、原則として既設の機種で行われるため、3つのレベルの機種が円借款で購入されていたならば、将来もこれらを設置したメーカーへの追加発注が期待できた。
(2) 工事関係で未完成のものとしては、NECへ発注した追加伝送装置、新郵電管理局ビルに設置工事中の保守センターがあるが、それぞれ完成は前者が1995年10月末、後者は1995年9月末の予定である。
(3) 新規加入者に対する接続料の徴収は1993年から開始されており、現在は1回線当たり4,000元となっている。今までに11万回線加入しており、計3.3億元の収入となっている。
(4) 電気通信部門では、前に設置した装置の増設の場合が度々あり、同一の製品でなければ困るために随意契約にならざるを得ない。円借款の条件として、1件5億円以上の契約は、国際競争入札にかけなければならないことになっているため、その場合、OECFの承認が必要となっているが、これには時間がかかるとの指摘があった。
(5) 電気通信施設の現地調査を行うと、交換機のみでも、前の第2次円借款によるもの、調査対象の第3次円借款によるもの及び自己資金でその後追加購入したものなどがあり、巨大な設備に成長していることがわかる。料金処理用の電子計算機は、円借款で購入のものは容量不足になりつつあるので、近く別機種の電子計算機に置き換える予定とのことであった。また上海地区の電話加入者は、今年末までに250万となる予定で、数年前に東京が実施し、近く大阪で実施を検討中の市内電話8数字化が1995年11月25日に実施される予定とのことであった。

終わりに
今回の調査結果を一言で言えば、モンゴル及び中国への電気通信分野の円借款は、些細な点を除けば、全般的に成功し、受け入れ側からも感謝されているプロジェクトであったと評価できる。

