5 中国における経済協力評価
財団法人 ダム水資源地環境整備センター調査第三部長 田中 耕一
三菱総合研究所アジア市場研究部アジア研究室長 小林 守
(現地調査期間:1995年11月13日~11月28日)
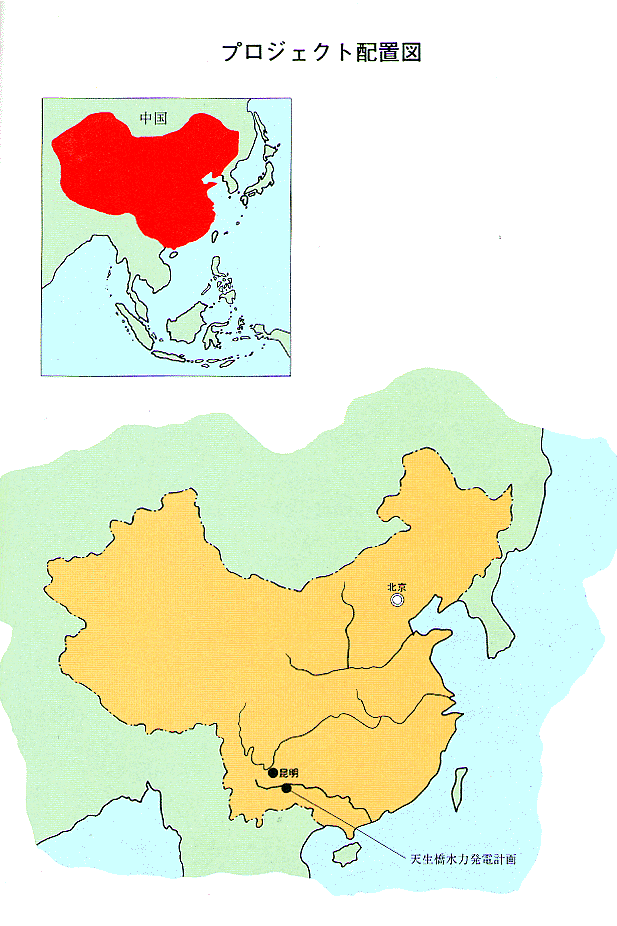
評価対象プロジェクトの概要
| 案件 | 協力形態 | 協力期間、金額 | 案件概要 |
| 天生橋水力発電計画 | 有償資金協力 |
1984年度 124.00億円 1985年度 123.53億円 1986年度 180.15億円 1987年度 113.72億円 1988年度 40.00億円 1989年度 192.35億円 |
ダム水路式発電所(ダム:コンクリ十重力式、総貯水量26×10(の6乗)立法メートル、発電所:最大出力220メガワット×4)及び貴陽・広州に送電するための送変電設備(送電線総亘長1,440キロメートル、変電所5カ所)を建設する。 |
1 天生橋水力発電事業の現況と対象地域の電力事情
(1) 天生橋水力発電事業の現況
1) 事業の背景と目的
第6次5カ年計画(1981~1985)における開発方針に基づき、水利電力部(現電力工業部)は南部の豊富な水力資源の積極的開発及び水力発電施設の拡充を図るための一環として、『紅水河総合利用計画』を策定し1981年に国務院の承認を受けた。
当計画は、本事業を含めて10水力発電所を建設し、将来電力不足が予測される広東省を中心に電力供給を図ろうとするものである。
本事業の目的は、(1)経済特区を中心とした経済発展が予測される広東省への電力供給及び広西省・貴州省における電力供給力の増強、(2)広東・広西・貴州の各省の電力系統の連係による電力融通及び供給信頼性の向上、(3)石炭火力から水力ヘエネルギー転換することにより、石炭輸送で逼迫している鉄道輸送状況の改善を図ることである。
2) 事業内容
本事業の内容は、(1)紅水河上流の南盤江天生橋に総出力1,320メガワット(220メガワット×6)の天生橋第2発電所のうち第1フェーズとして880メガワット(220メガワット×4)の発電所の建設、(2)貴陽・広州に送電するための送変電設備(送電線亘長1,440キロメートル、変電所5カ所)の建設である。
当初の事業計画に対して86年と88年に計画の変更があった。
86年の変更点は貴陽のアルミ工場建設計画に伴う貴陽変電所の追加である。
88年は、広州市への電力供給の安定性及び信頼性向上のため(1)広州西北部~西南部間送電線(亘長72キロメートル、500キロボルト1回線)の追加、天生橋水力発電所及び岩灘発電所を含めた天生橋~広州間電力系統の安定性及び信頼性向上のため(2)岩灘発電所~平果変電所間送電線(亘長102キロメートル、500キロボルト1回線)、平果変電所変圧器増設(500メガボルトアンペア×1)、1・2号導水路トンネル掘削促進のため(3)作業トンネルの追加掘削(最終的には3号導水路トンネルとなる)などである。
本事業に対して、第2次円借款により下記に示す様に1984~89年で約774億円が供与されている。
| 年度 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 総額 |
| 金額 | 12,400 | 12,353 | 18,015 | 11,372 | 4,000 | 19,235 | 77,375 |
現在、本事業の直上流において中国南方電力聯営公司が1991年より総出力1,200メガワットの天生橋第1発電所(300メガワット×4)を建設しており、その竣工に併せて第2フェーズ(5・6号機)が実施され、計画では天生橋2級発電所は99年に全て完成予定である。
なお、天生橋第1水力発電所建設計画は第3次円借款により91年から供与開始している。
3) 事業の現況
本事業は1982年より準備工事、83年より本体工事に着工した。
当初予定では、89年に1・2号機、90年には3・4号機が運開の予定であったが、地質不良のため導水路トンネルの掘削作業が難行し、1号機の運開が92年12月、2号機が93年9月と遅れた。
95年11月現在、1~3号導水路トンネルのうち既に完成している1号導水路を通して1・2号発電機は発電しているが、2号導水路(後の調圧水槽、水圧管路は施工済み)の下流端付近で1号導水路と連絡させ3・4号機にも水を送れるようにし、変則的であるが95年11月に3・4号機の運転を開始している。
現在、2号及び3号導水路トンネルを鋭意施工中であり、96年末には3・4号機も正式に運開となる予定である。
送電線については、貴陽(貴州省)、平果(広西省)、広州(広東省)への500キロボルトの送電線の他、岩灘水力発電所~平果変電所間の500キロボルトの送電線、魯布格(雲南省)、興義(貴州省)、隆林県(広西省)への220キロボルト送電線がすでに完成している。
天生橋2級発電所の電気は93年より500キロボルト送電線を通して貴州・広西・広東に送電され、電力不足の解消に大いに役立っている。また、220キロボルトで送電される電力は、周辺地域の農・工業発展に貢献している。
| 発電量 | 送貴州 | 送広西 | 送広東 | |
| 93年 | 14.43 | 4.10 | 5.56 | 4.38 |
| 94年 | 27.42 | 1.44 | 6.62 | 17.94 |
| 95年(10月まで) | 23.38 | 0.11 | 3.48 | 18.53 |
天生橋2級水力発電所の運開以降の発電量と送電状況は次の通りである。(中国南方電力聯営公司からの受領資料より)天生橋2級水力発電所と送電線の運営管理及び天生橋1級水力発電所の建設管理は中国南方電力聯営公司によって実施されている。
中国南方電力聯営公司は1991年8月3日に国(中国国家開発銀行)と広東・広西・貴州・雲南省の出資により設立され、国策の中国西南部の電力資源の開発『西電東送』を目標としている。
(2) 対象地域の電力事情
対象地域の94年の発電設備容量と年間発生電力量は次表の通りである。
| 発電設備容量(Mw) | 年間発生電力量(億kwh) | 備考 | ||||
| 水力 | 水力 | 原子力 | 計 | |||
| 広東省 | 4,540 | 13,470 | 1,800 | 19,810 | 770 | 人口 6,582万 |
| 広西省 | 2,627 | 1,610 | 0 | 4,237 | 171 | 人口 4,438万 |
| 貴州省 | 1,340 | 1,860 | 0 | 3,200 | 154 | 人口3,408万 |
| 雲南省 | 4,000 | 1,500 | 0 | 5,500 | 201 | 人口3,885万 |
| 全国 | 200,000 | 9,281 | 人口121,228万 | |||
各省の独立していた電力グリッドは天生橋水力発電事業の高圧500キロボルト送電線建設により、1993年1月広東省・広西省・貴州省の電力網は連係され、更に93年8月天生橋2級発電所と雲南省の魯布格発電所が220キロボルトの送電線で連係され、4省は一つの大きなネットワークとなった。
各省の送電網のうち500キロボルト送電線の亘長は次の通りである。
(Electric Power INDUSTRY IN CHINA 1994より)
| 広東省 | 745キロメートル |
| 広西省 | 859キロメートル |
| 広東および広西省 | 187キロメートル |
| 貴州省 | 275キロメートル |
| 雲南省 | 226キロメートル |
| 全国 | 10,231キロメートル |
なお、紅水河総合利用計画の10発電所のうち広西省の岩灘、大化の2水力発電所はすでに完成しており、それぞれ平果、来賓変電所で本事業の500キロボルト送電線と連係されている。
南方聯営4省の融通電力量は93年から95年10月までは次の通りである。(中国南方電力聯営公司からの受領資料より)
| 93年 | 94年 | 95年(10月まで) | |
| 貴州から広東への融通 | 0.835 | 2.123 | 1.458 |
| 雲南から広東 " | 5.400 | 9.006 | 6.554 |
| 広西から広東 " | 5.394 | 0.687 | 0.396 |
| 貴州から広西 " | 0.621 | 2.332 | 5.286 |
| 広西から広東 " | 0.616 | 0.000 | 0.000 |
| 広西内聯営送電網送電量 | 11.018 | 30.329 | 27.627 |
| 合計 | 23.885 | 44.476 | 41.321 |
さらに、天生橋1級の運開に合わせ天生橋1級から広州まで500キロボルトの直流送電線1回線を97年までに投入する予定である。
2 環境保護に対する行政の取組と天生橋水力発電事業における環境への影響
(1) 環境に対する行政の取組
中国では国務院の下に国家環境保護局があり、環境保全に関する法律と行政について全国的に統一管理している。
国家環境保護局は、具体的には環境保護に対する政策・法律等の制定、国家経済・社会中長期計画その他の開発計画策定への参加、環境保護国家標準の制定と発布、全国大の環境モニタリングシステムの監督管理等を行っている。
また、各省においては省の環境保護局があり、国の『中華人民共和国環境保護法』に基づき独自に条例を制定し環境保全を図っている。
大気・水質等の環境基準については国の基準に比べ、各省の基準はより厳しいものとなっている。
法律、条例の遵守状況については、国家レベルのプロジェクトほど遵守しているが、地方においては状況に応じて行っているようである。
法律によると、国家環境保護局は環境報告書の評価の他、建設については一定期間の後、設計・施工・運転での環境配慮について検査をすることになっており、場合によっては、プロジェクトの停止、罰金などを命ずることができるとしている。
中国では社会主義市場経済による集約型の社会経済発展を目指しており、その中では充分に環境を考慮していくとしており、第8次5カ年計画(91~95年)では環境対策費としてGNPの0.7~0.8%を投資したが、第9次(96~2000年)ではGNPの1%、4,000億元の投資予定である。
エネルギー関連では、95年8月に大気汚染防治法が制定され、酸性雨対策として今後、新規の火力発電所建設には脱硫装置を設置すること、また、既設の火力発電所についても設置していくこととなっている。
国や市では基準に基づいて観測ステーションを決めモニタリングを実施している。また、各企業や発電所においてもモニタリング室の設置が義務付けられている。国では200カ所の観測点の管理監督をしており、国際的観測にも参加している。
天生橋プロジェクトは水利電力部(現在は電力工業部)の主管であるが、500万米ドル以上のプロジェクトであるため国家環境評価報告書が必要となり、国家環境保護局の審査を受けている。
この報告書制度は70年より開始され、80年代から全面的に実施している。
天生橋発電事業の環境影響評価報告書は貴陽勘測設計院(省環境研究所、大学環境系と共に)で作成され、貴州省の環境保護局及び国の環境保護局の審査を経て、電力工業部からの初歩設計報告書と共に国家計画委員会で承認を受けている。
承認フローは次図の通りである。
〈環境影響評価報告書の承認フロー〉
設計院工程庭『初歩設計報告書』→→→→→→水利電力部
貴陽勘測設計院 ↑ (現電力工業部)
(省)環境研究所 『環境報告書』→→→貴州省環境保護局 ↓
大学環境系 ↓ ↓ ↓
3省(貴州・広西・広東)→国家環境保護局→国家計画委員会
環境報告書は、現状の環境(社会経済状況、自然生態環境等)と貯水池完成後の環境予測(水質変化、植生の変化、誘発地震の問題等)について述べている。
天生橋1級発電所環境影響評価報告書については電力工業部昆明勘測設計研究院で作成され、同様に承認されている。
(2) 天生橋水力発電事業における環境への影響
1) 天生橋2級建設事業における環境への影響
a 周辺地域への社会・経済的影響
天生橋2級建設に伴う移転は100戸1,000人余であるが、そのうち水没による移転は3村21戸115人である。
移転した住民は稲作から果樹栽培に変わったり、工場労働に従事することによって生活は安定し豊かになり、移転住民の生活レベルは鎮の人々と同レベルまで向上した。建設現場周辺地域の人口は少なくしかも貧しかったが、建設に伴う人口増により村は鎮となり、建設に伴う道路、電気、通信等のインフラが整備され郵便局、病院、学校、銀行、警察、人民政府、商店等の新たな建設、路線バスの停車場の設置により便利になり生活は改善され衛生環境も向上した。
国は、地元に設置された第3セクターに対して『電力工業部水電建設ダム区域補修費用に係わる規定』に基づき、ダム周辺の環境保全のため整備資金として毎年発電量に応じて百数十万元支払っており、これも地元の活性化・発展に大きな役割を果たしている。
b 自然環境等への影響貯水池規模(貯水容量2,600万平方メートル)が比較的小さいため周辺生態系及び局地気象(降雨・気温・湿度など)に及ぼす影響は少ない。
・水質・水温について
水質悪化の原因は上流の町にあり、水質は定期的に2カ所で検査している。天生橋の流域面積は5万平方キロメートルあり、貯水池に到達するまでに自然浄化されると考えている。
流入水温は平均20.4℃で、貯水池の水温変化はほとんどなく、水性生物に対する影響はないと思われる。
・捨土について
建設に伴い生ずる大量の残土の処理が問題となるが、この地域は石灰岩地帯のためあまり生物がいないことから、捨て土による環境問題は生じていない。土捨場は捨て土後客土して緑化を図っている。また、工事区域は峡谷で平地が少ないため、一部住民の要望により凹地を埋め立てグランドを造成した。
c 減水区間の問題
天生橋2級発電所はダム水路式で、ダムと発電所放水口間の14.6キロメートルは減水区間となり、河川は1年のうち60%は水なしの状態である。この河川の減水区間には魚はほとんどおらず漁業を生業としている人はいない。また、住民は地下水を飲料水としているため、周辺生活環境への減水の影響はない。
d 貯水池の堆砂の問題
貯水池に入ってくる土砂量は年間約1,500万m3であり、そのうち掃流砂は70万m2であるが、排砂ゲートが河床と同レベルになっており、堆積させることなく排除でき堆砂の問題は生じない。
e その他の影響
・遺跡・文化遺産について
建設の影響範囲には遺跡・文化遺産はない。
・貯水池誘発地震について
ダム貯水池の規模が小さいことからほとんど影響はない。
・天生橋2級発電所プロジェクトで得られた将来有効な建設技術について
貴陽勘測設計研究院からの聞き取りによると、技術面で今後生かされると考えられる主なものは次の2点である。
(1)トンネルの掘削技術、(2)地滑りに対する対策工導水路トンネルは直径9メートル、延長約9.5キロメートル、3条で、掘削に当っては米国製のTBM(Tunnel Boring Machine)を採用した。TBMによるトンネル掘削が、石灰岩の溶洞の存在など地質上の理由により大幅に遅れたため、一部在来工法に変更し、トンネル施工の進捗を上げるため作業トンネルを設けるなどして、数カ所での同時施工を可能とした。
今回の地質上のトラブルにより石灰岩の溶洞の処理、事前探査技術および導水路トンネルの合理的設計法などトンネルの設計・施工に関する技術を修得した。
また、天生橋2級の工事中にダム、調圧水槽、発電所の3カ所で大規模なすべりが発生した。
ダム地点では、右岸側で200メートルの高さで幅1キロメートルに渡ってすべりが生じたため、その防止対策としてコンクリート枠を施工し安定化を図った。
調圧水槽部分のすべりに対してはコンクリート吹付を実施し法面の安定を図った。
発電所は位置変更をしたが、背面の岩にすべりが発生した。対策としてPSテンドンで地山を補強し、下部に1,100メートルの排水トンネルを施工し安定を図った。
これらの建設技術はコンサルタントの技術指導を得て修得されたもので、今後の建設に大いに生かされるものと考えられる。
2) 天生橋1級発電所建設事業における環境への影響について
a 周辺地域への社会・経済的影響
天生橋1級のダムは178メートルと高く、貯水容量は102億立方メートル、湛水面積は173.7平方キロメートル、湛水池の長さは140キロメートルに達し、貯水池の影響は6つの県市に及ぶ。
水没のうち耕地は4,539ヘクタール、森林は3,697ヘクタールを占め、移転住民44,000人のうち42,000人は農業に従事している純農業地区である。
移転後の生活安定計画については、省の関係部門で決めて国の承認後実施している。
移転先での仕事については、移転先の環境容量の調査を行い、大農業を主として農
・林・畜・魚・付(副業)の順で従事することになる。85%が農林を占め、15%は郷鎮企業、建設資材、農加工、交通運送業、サービス業、貯水池での漁業、船運業などである。
工場に対しては金銭補償がなされ、特に条件もなくどこに移転してもよく、現地の砂糖工場が補償金で興義市の近くに澱粉工場を建てたケースもある。
すでに、5,031人が移転しており、その収入は移転前の500元/年に対して移転後は600~700元/年に増えた。また、食料消費量も以前の150キログラムから180キログラム/年/人に増加しており、移転後の生活水準はかなり上がったと考えられる。
建設に伴う道路などのインフラ整備と共に、将来はダムによって生ずる巨大な貯水池を利用した観光開発、物資輸送、交通・観光のための船運及び漁業等により、新たな雇用機会も増え地域の活性化が進む。
天生橋1級発電所の発生電力(52.26億キロワットアワー)は西電東送の重要電源として広東省に送られるだけでなく、周辺地域の鉱業・農業の発達にも大きく寄与することになる。
また、天生橋1級の大貯水池の調整機能により、天生橋1級発電所の運転開始に伴って紅水河下流の既設の3水力発電所(天生橋2級、岩灘、大化)の保証出力及び発電量はそれぞれ、883.9メガワット、40.77億キロワットアワー増加する。
b 自然環境等への影響
・水質・水温について
流域の人口は700万人で耕地は890万ムーであり、上流域には化学工場、製鉄所など工場が多くあり、また周辺の興義、隆林からも生活廃水、工場廃水が入ることになるが、上流部の支川での水質調査によると、現状では1~2級(1~5級まであり、1級は飲料可、2級は農業用、3級以下は処理が必要)である。上流の工場廃水などからの重金属は、天生橋1級の貯水池が大きく、重金属が沈降するため、水質は良くなると考えている。また、下流域においては、貯水池による調整効果により流量が平準化され、豊水期の河岸侵蝕防止や渇水期の水質等河川環境にとって良い結果をもたらすとしている。
水温については、湖泊率(湖水面積/流域面積)が0.4%と小さいため、環境に対するインパクトは小さいと判断している。貯水池周辺では貯水池の存在により日間、月間の温度差が小さくなるため農作物の生育に良い影響を与える。
・生態系について
貯水池周辺には貴重な陸上動物、水性生物はおらず一般的なものしかいないため、それに対する影響はほとんどない。また、植物については周辺で655種が観察され、うち貴重種が8~9種あり、その中には保存の必要のあるもの、経済効果のあるものもある。
C その他の影響
・文化遺跡の保護
隆林県那来洞は古代人の遺跡で地区級の遺跡であり、パンダ等動物の化石、古代人の歯が発見されており、歴史・文化研究のため移動させる。
安龍県の布依族の小さな村で、古代人の建物、製紙場の遺跡が発見されており、それは興義に移す予定である。
・誘発地震について
この地域の地震烈度は6度(最大は10度)であり破壊力はない。地震が生じても6度以下と考えられ問題ない。なお、ダム完成後は地震観測を行うことになっている。
天生橋1級の建設に当たっては周辺環境維持・保全のため(1)水土維持、緑化保護、
(2)地元政府による衛生環境の改善、(3)地元民の生産・生活の安定を図る、(4)貯水池の監視を強め継続監視していくことなどの対策を講じている。
(3) 環境問題と水力開発について
人口が増大するなかで経済発展していくためには膨大なエネルギー消費が必要となり、このエネルギー消費が環境の破壊をもたらすと言われている。
特に、化石燃料による火力発電は酸性雨、地球温暖化などの地球規模の環境問題を生じている。大規模ダムを伴う水力発電開発においても、移転の問題、生態系の変化などの環境問題はあるが、水力発電所建設による社会経済的効果は多方面に渡っており、特に水力発電は再生可能なクリーンエネルギーとして評価されている。
中国は2000年までに、現在の2億キロワットの発電設備を3億キロワットまでに開発しなければならないとしている。
中国は今後、火力75%、水力25%の割合で開発する方針であるが、中国は膨大な包蔵水力を有しており、地球規模の環境保護のためにも水力開発を積極的に進めていく必要があるのではないかと考える。なお、大規模水力開発には移転・生態環境問題のほか、種々の技術的問題や莫大な資金問題を伴うため、環境保全技術などを含めた技術協力、資金協力など、日本国の大いなる協力・援助が期待される。
3 円借款やODAへの期待
内陸各省の水源開発には量的に多くの資金が必要であるが、建設期間が長いこと、需要地である沿海部への送電線建設が必要であることから事業の収益性においては不透明な点が多く、民間主体のBOT方式や商業借款は期待できない。また、コストの高い外資系(BOT方式による石炭火力発電所など)発電所から省が買電するのは経済的に疑問ありという意識が中国側(南方電力)に存在している。中国側にはむしろ国有企業である南方電力主体の電源開発を支援して、そこから電力を購入するのが筋であるとの意見もある。
一方、中国内の行政改革や民営化に伴い、公的機関といえども、市場競争原理から逃れられない現状である。この意味で電力工業部系の南方電力は公的資金への希望が強く、円借款には大きな期待を持っている。
今回調査の対象地域のうち最大の電力消費地域、広東省は改革開放政策発動以降の中国経済を牽引してきた地域であり、それゆえ経済発展の度合いが高く、民間資金による電源開発も可能になっている中国でも希有の地域である。従って平均的な地方を考えれば、電源開発の資金源については依然として円借款など公的資金での対応が自然であると思われる。
また、本レポートでも述べたように、環境基準の厳格化と中国政府の経済政策の変化によってBOT方式なども必ずしも収益性を見込めないとする投資家も増えている。この意味でも中国の電源開発、電力セクター整備に円借款の果たす役割は引き続き大きいといえる。
但し、各地方政府レベルでは環境基準自体は厳格であっても、外国直接投資を呼び込まんとするあまり、その運用を緩和している可能性も懸念される。従って、水力発電など周辺の自然環境を大きく改変する可能性のある事業に対しては、日本政府としてもOECFの環境配慮ガイドラインなど各種の日本側ガイドラインを基準に、積極的に中国側にアドバイスしていく必要がある。また、こうしたアドバイス作業は円借款など融資の可否を判断するための審査段階に止まらず、事業が実施されている最中、完成時、評価時にも意見交換の形で繰り返し続けていくことが中国側にとっても有益であろう。


