4 タイにおける経済協力評価
長崎大学経済学部教授 式部 透
長崎大学経済学部教授 菅家 正瑞
長崎大学経済学部助教授 ウマリ・セリア
(現地調査期間:1995年9月3日~9月10日)
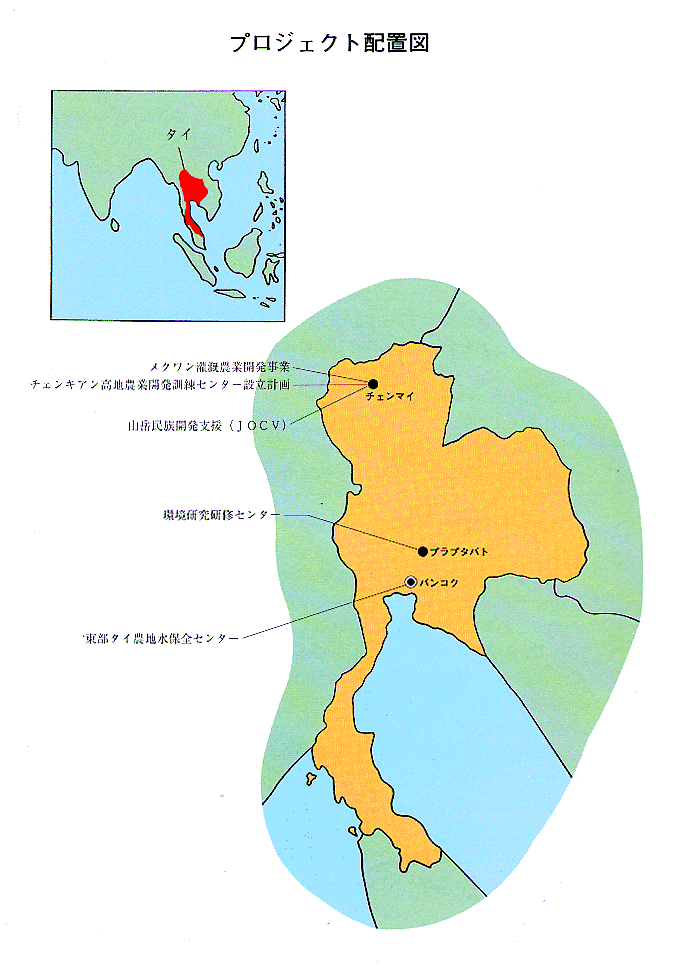
評価対象プロジェクトの概要
| 案件 | 協力形態 | 協力期間、金額 | 案件概要 |
| メクワン灌漑農業開発事業 | 有償資金協力 |
1984年度、 23.00億円 1985年度、 91.97億円 1987年度、 28.05億円 |
農業灌漑を主目的とした洪水制御、水力発電等の多目的ダム及び関連施設を建設する。 |
| 環境研究研修センター | 無償資金協力プロジェクト方式技術協力 |
1989年度、 15.94億円 1990年度、 8.62億円 1990年4月~1997年3月 |
近年のタイの著しい都市化・工業化が引き起こす環境問題に対応するため、環境研究研修センターを設立し、同センターの運営、水質汚濁、大気汚染等に関する研究・研修・モニタリング等の技術の向上を図る。 |
| 東部タイ農地水保全センター | プロジェクト方式技術協力 | 1993年6月~1998年6月 | 東部タイ地域における広範な土壌流亡を防止し、接続的な農業生産システムを確立するための農地・水保全に関する技術指導 |
| チェンキアン高地農業開発訓練センター設立計画 | 無償資金協力 |
1992年度、 5.96億円 |
高地民族の民生の安定のため、ケシ栽培に替わる換金作物栽培を目的とした技術指導者の訓練・育成用施設を建設し、機材を供与する。 |
| 山岳民族自立支援 | 青年海外協力隊 |
1995年12月~ (事前調査) |
山岳民族村落の社会的、経済的発展を目指し、村落共同体の活性化、自立性の促進に寄与する。 |
1.プロジェクトの評価
(1)タイ環境研究研修センター
(EnvironmentaI Research and Training Center)
近年におけるタイ国のめざましい経済発展は、その反面において無秩序な工場建設、バンコクをはじめとする首都圏地域への急速かつ大量の人口集中、交通渋滞問題などをもたらした。その結果、さまざまな環境問題を引き起こし深刻の度を加えている。例えば、バンコクおよび周辺地域の交通渋滞による自動車排気ガス汚染は、年々深刻化している。さらに、地方にも広がる工場や発電所からのばい煙による大気汚染、ほとんど処理されない工場排水・生活排水による河川や運河・海洋地域の水質汚濁、農薬散布・有害物投棄による土壌汚染などの環境問題が深刻化してきており、住民の生活にも悪影響を及ぼしつつある。
タイ国は、このような深刻な環境問題に対応するため、1975年に国家環境保全法を制定するとともに、同法に基づき環境庁(1992年より科学技術環境省)が設立し本格的な取り組みを開始した。しかし、近年の著しい都市化・工業化が引き起こす環境問題は、タイ国環境庁の人的・物的体制では的確に対応できない状況にあったため、環境技術対策にかかわる技術者・研究者の技術向上および絶対数の不足しているこれら技術者・研究者の養成を目的として、1983年に「タイ環境研究研修センター」(BRTC)設立計画を策定し、同計画に対する無償資金協力およびプロジェクト方式技術協力を日本に要請してきた。これを受け、2名の環境分野専門家が派遣され、タイにおける環境研究研修のあり方について調査を実施し、1987年に「タイ国環境研究研修センター基本計画」をとりまとめた。同報告を踏まえて日本側の無償及びプロ技のスキームによる協力が開始されることとなり、1991年、同プロジェクトがタイの第7次開発五カ年計画に組み込まれて以降、センターは完全操業している。
ERTCには現在二棟のビルがあり、そこに管理運営棟、及び滞在施設、カフェテリアその他が設置されている。また、近く、多目的ホール及び庭園建造の予定がある。そうしたセンターの設備により、ERTCの研究者は環境分析に関する最新の技術を利用可能である。
ERTCの主要業務は、汚染、天然資源と環境管理、汚染制御、及び環境サンプルの標準解析手法の開発等に関する研究、及び技術移転を行うことにある。今日に至るまで、同センターでは、中央・地方政府、民間部門、及びNGOから派遣された、2,000人に及ぶ中級・高級要員の訓練を行ってきている。センターでは、求められる訓練内容を確定すべく、多くの政府機関等のスタッフに質問状を送付している。これは、重要、適切かっ必要とされる訓練コースを提供することへのセンターのコミットメントを表わすものであり、活動姿勢として高く評価できる。
日本政府はJICAを通じ、日本人専門家の派遣、機械・装置の提供等を行い、センターを技術的に支援している。毎年、JICA専門家10人がERTCスタッフヘの環境関連技術移転のために同センターを訪れる他、ERTC現地スタッフも訓練のために日本に出かけている。
経済が高成長をしている国では、多くの環境問題の発生が予想されるものであり、年率8%以上の経済成長を伴うタイもその例外ではない。つまり、タイにおいては、環境や国内天然資源、及びその管理に関し懸念が生じ得る多くの要因が存在している。従って、1983年に遡るERTCの創設は、将来の環境問題を予見しその緩和策を準備しておくという意味で、先見性のある政策決定であった。その存在目的と指導原理は現時点においても極めて適切かつ重要である。
研究及び訓練プログラムは、汚染管理から固形廃棄物管理、水質管理、森林管理、さらに情報普及までをカバーする。その訓練コースは、中・高級職員のみならず、一般への周知活動や教育コースを通じ、広く一般大衆を対象としている。持続可能な開発のためには、普通の人々が環境を守り、また環境と調和した生き方を学ぶことが必要であり、その実現の唯一の方策が教育や情報普及であることを鑑みれば、このことは極めて重要である。
このことを背景に、センターでは現在、地方政府職員に対し、環境及び人的資源開発に関する意思決定能力改善の訓練を行っている。総合基本計画(Master Plan)策定の分散化に伴い、特に地方レベルでの政策決定を支援するという観点で地方政府職員に対する訓練が極めて重要になってきている。近年、研究諸機関により、計画やプログラムを地方レベルで策定することが多くの国々の環境保全や資源管理の領域において少なからず有用であることが提唱されている。この議論の主たる根拠は、地方レベルでの人々や政府職員こそが、自らの抱える問題や必要を最も深く理解し、また知識を有していることにある。従って、近年センターが行っている地方政府職員訓練の強調は、中央政府の非集権政策と整合的かっ適切なものと考えられる。
訓練センターについては、そこで学んだことが訓練生の実際の職務において役に立っているかどうかを見るため、卒業生のフォロー・アップ調査を行うことが望まれる。興味深いことに、ERTCでは、訓練後の業績報告を行わせるべく、過去の訓練生を年次セミナーに呼んでいる。こうしたセミナーに基づき、訓練生の経験と将来の訓練要請を考慮に入れて、訓練コースは修正、改善されていくことが期待される。
適切な建物、施設、技術的アドバイス等がなければ、センターは以上の業務を適切に、かっ自信をもって処理することはできなかったであろう。それに必要とされた基本的諸条件は日本のODAによって供与されたものであることはいうまでもない。
プロジェクトのパフォーマンス評価を行う際の一つの指針として、その事業の継続可能性を挙げることができる。プロジェクト期間の後半においてそれが自律的継続性を持ちうるのか。プロジェクト期間が終了した場合、誰がその資金調達を行うのか。プロジェクト支援が終了した後は、誰が継続する経費を持つのか等々を検討しておく必要があろう。
1983年にそのプロジェクト提案が行われた後、1991年、最終的にERTCの活動が開始されるまでにはかなりの時間を要した。タイ政府と日本政府の間の合意が最終的な完了をみたのは、ERTCのプロジェクトがタイの第7次開発五カ年計画に組み込まれた後のことである。これにより、タイ政府はセンターの労働力と運営費用を賄うコミットメントを与えた形となり、センター業務の滞りない遂行が可能となった。
プロジェクトの自律的永続性を評価する際のもう一の重要な側面は、センターが現地の専門技術だけで研究・訓練機能を果たしていけるか否かにある。この点に関してはJICAの専門家が重要な役割を果たしている。彼らは、最新設備の活用のみならず分析手法について、熱心にタイの研究者を訓練し、またアドバイスを与えている。しかしながら、現時点ではまだ、地元の研究者が訓練をする側に回る準備ができているとは言い難い。
(注)本プロジェクトの終了時評価調査団(1996年10月16日~26日派遣)の調査結果報告によれば、「研修事業は、既存のコース(30コース・956人/年)に地域の教育大学と連携した研修(4コース・233人/年)及び環境管理の行動計画展開のための研修(15コース・667人/年)が新たに開設され国の重要な研修機関の一つになりつつある。これらのコースは全てタイ側独自で運営が可能となってきた。」との評価を得ている。
地元のスタッフが十分に技術を習得し、プロジェクトが終了した時にも研究や訓練の業務を自らこなせるようになるまでは、JICAの専門家派遣の継続が重要である。ERTCが、近い将来、アジアにとっての地域的研究訓練センターとなるためには、このような地方の人材開発が最も重要である。アジアの多くの国々がタイと同様の環境問題に苦しんでおり、それらがERTCのような研究機関から学ぶべきことは多い。
(2) 高地農業社会開発センター(山岳民族自立支援(JOCV))
(Highland Agricultural and Social Development Center)
チェンキアン高地農業開発訓練センター設立計画
(Highland Agricultural Research Training Center)
高地農業社会開発センター(HASD)の基本的目的は、タイ北部の少数民族である高地部族(Hilltribe)の人々の生活条件、生活水準を改善することにある。彼らの大半は環境に非常に有害な破壊的農業に従事している。高地部落民は、食料不足、劣悪な健康・衛生状況、教育機会の不足、森林破壊、土壌汚染、アヘンの氾濫等の問題に直面している。また、高地農業研究訓練センター(HARTC)の主目的は高地農業に関する研究と訓練を行うこと、特に、森林破壊を防止し、山間地におけるアヘン生産の他産品生産へのシフトを促進することにある。
HARTCとHASDの究極の目的は共通しており、農業開発を通じて環境保全と高地部族の生活改善を達成することにある。
こうした問題認識に立ち、HASDでは、高地部族農民に適切かつ持続可能な農業方式を習得させるべく教化に努めている。そこで勧められているのは、地形に応じた、米、とうもろこし、コーヒー、茶、果樹等の栽培である。HASDの計画プロセスではボトム・アップ型の計画概念が重視されており、そこでは村民自身が草の根的に問題や必要の所在の特定及び適切な解決策の展開に参加している。HASDは村民の支援や援助に対するこうした要請に基づきプロジェクトを実行する。
HASDが高地部族のための農業開発に採っているアプローチは持続可能性や適正技術の概念を支えるものである。始めに、小区画で、全投入をプロジェクトが提供する形で、新しい農業生産技術が実演される。次いで各農家は、農地管理以外の全投入についてプロジェクトからの援助を受けつつ、自らの農地の小区画でその技術を試してみる。その技術を採用することを決めた農家は、次いで、その試行をより広い区画に拡張する。この際にも全ての投入はプロジェクトにより提供されるが、農家には村の回転資金(Village revolving fund)を通じたその返済が求められる。農家がその新しい農業手法を採用した後は、次第に独立性を増して、投入を自ら供与したり回転資金からの信用貸しを受ける形が生じる。この場合、農家は、新たな技術を実際に採用する以前の段階でそれが機能するかどうかを確かめることができ、そのプロジェクト支援に依存するか否かを裁量的に決められる。
日本政府はJICAを通じてHASDに専門家を派遣し、農業社会開発の分野で技術援助を行っている。JICAの技術スタッフ(青年海外協力隊員)の佐藤女史によれば、技術スタッフは村落で働き、高地部族の人々との交流もあるとのことである。
高地部族の人々が発展していくことは極めて重要である。そうした少数部族は極めて豊かな文化と伝統を保有しており、また強い独自性を持っている。彼らがHASDのプログラムから得るところも大きい。しかしながら、彼らの発展とそのタイ社会主流への統合過程において、彼らの豊かな文化と伝統が維持・保護されることも望まれる。
HASDが以上の目的を達成できているか否かについて、その進展や成功の程度を評価するためには、そのプログラムによって環境面に生じた変化を計測することが必要であると思われる。また、チェンキアン高地農業開発訓練センター(HARTC)の方の今日における中心業務は訓練にある。センターが訓練コースを始めたのはようやく最近のことなので、プロジェクトの開始によって高地部族の環境が改善したかどうかを知ろうとすることは時期尚早かもしれない。しかし、プロジェクトがもう少し進行した後には、こうした影響の計測が行われてしかるべきだろう。
(3) メクワン灌漑農業開発事業
(Mae Kuang lrrigated Agricultural Development Project)
タイ国においては、1980年代に入って工業化が著しく進み発展してきたが、依然として全人口の約6割に相当する約3,500万人が農業に従事して生計を立てている。農業セクター(第一次産業)のGDP産業別構成は、1993年には11.9%、1994年には11.3%という僅かな比率であるが、多くの労働力を吸収する雇用源でもあり、タイ国においての農業は経済や社会基盤を支えている重要な産業でもある。
このような状況に対して、タイ国政府は、第5次国家経済社会開発5カ年計画(1982年~1986年)により、天水農業地域や高地農業地域などの生産性の低い地域に灌漑農業を導入し、生産性の向上による所得の増加と地域間格差の是正を図ることを重要開発目的とした農業政策を行った。
本事業対象地域となったチェンマイ地方の東側メクワン地域においては、既存のメクワン堰による灌漑農業地域と主に天水農業を行っているその他の地域との間には約40%の農業所得格差が生じていた。
このような状況を踏まえ、灌漑農業開発計画を策定して実施することによる作付け面積の増加、生産性の向上を図るため「メクワン灌漑農業開発事業」計画が策定された。
プロジェクトの主目的はメクワン川の水資源を開発し、ダムや運河の建設を通じ灌漑を行い、事業対象地域に現代的農業を導入することにある。メクワン灌漑農業開発事業は、1981年から82年のJICA実施調査を受け、!981年、OECF供与のソフト・ローンを活用する形で始められた。プロジェクトは1992年、総費用30~90億バーツで完了した。
1981年に行われた事業のフィージビリティ・スタディによれば、この農業開発プロジェクトは37,270ヘクタールに及び、期待される灌漑領域はネットでも20,000ヘクタールに達する。当局によれば、事業は現時点で26,923ヘクタール(175,000rai)に恩恵を与えており、28,000ヘクタールが灌漑運河の便宜を得ている。
貯水池の容積は263立法メートルある。プロジェクト・スタッフによれば、現在ダムの水位には2メートル分の余裕しかなく、このままではモンスーンの雨が降れば洪水の危険がある。この点につき、当局は、適切な水位管理を行っていくと共に万が一水害の危険がある場合には周辺地域住民に警告が出せるよう気候の変化には注意が必要であると述べていた。
(多雨年には余水が生じるが、余水吐がフェーズIIで完成しており、対応できる体制となっている。)
灌漑により、農家では一年で二毛作、あるいは三毛作までの米の栽培が可能になると思われる。しかし、当局によれば、灌漑が不十分であるため、まだ年一回の栽培に止まっている。ただし、年一回以上の収穫は農家に経済的利益をもたらすかもしれないが、一方で農家経営の観点での注意喚起も求められる(具体的には、収穫過剰になると、価格下落等の販売上の問題が生じる他、土壌劣化が生じる危険もある)。
一般的に灌漑事業については、以下に例示するような多くの疑問が上がってくる。つまり、一旦プロジェクトが動き出した後、誰が維持コストを負担するのか。その維持のために料金徴収を行うべきか。それによってどれだけの所得が生み出されているか。プロジェクトの収益とは何か。これらの問題は、特にプロジェクト・ローンの返済を考える際に、重要な問題となってくるのではないか。
メクワン・ダムの維持・運営はもっぱらタイ政府の経費で賄われている。農家は運河さらいに協力はしているものの、受益農家が灌漑費用の負担を求められることは一切ないということのようである。
今回は時間的制約から十分な検討ができなかったが、本プロジェクトを含む灌漑事業については以下三つの点での一層の検討が必要ではないかと思われた。
1)成果―プロジェクトにより産み出された物理的産物(例えば、ダムの容量、灌潮水の量、建設運河の長さ、灌漑地のヘクタール数、等々)
2)効果―プロジェクトの直接的な帰結(例えば、年当たりの収穫増、ヘクタール当たりの収穫増、収穫システムの改善、年当たり洪水の減少、等々)
3)影響―プロジェクトによる農家の生活水準の変化(個人や家族のレベルでは、例えば、所得、住宅事情、栄養、健康状態の変化等であり、コミュニティーのレベルでは、ヘルス・ケア等社会的サービスの構造変化や生産、社会的基礎資本等経済構造の変化、あるいは社会構造等の変化である)。
(4) 東部タイ農地水保全センター事業
(Land and Water Conservation Center Project)
タイ東部には明瞭な二つの季節がある。第一は東岸における熱帯サバンナ(乾季)であり、他方は西岸の熱帯モンスーン(雨季)である。また、ここの土壌は砂地で崩れやすい構造なので、モンスーン期には極めて頻繁に土壌流出が起こる。その結果土地は酸性で痩せており、生産性も低い。
タイ東部はこのような問題を抱えていたため、その農家を救済することは緊急の課題であった。こうした認識に立ち、1988年、この地域の開発研究プロジェクトを創設するための調査団を派遣する要請が日本政府に対し提出された。援助の開始は1991年で、選出された16のパイロット・プロジェクトに対し約3億2千万円相当の機械・設備が使用に供された。1993年には土地・水資源保全センター(LWCC)事業の第三段階が開始され、日本とタイの間の技術協力も始まった。プロジェクトの主目的は、土地及び水資源保全に関する適切な技術を開発し、それを地域の専門家や農家に移転することである。
1993年から1998年を期間とする事業の第三段階では、JICA専門家のプロジェクト任務への派遣、タイ専門家の日本での訓練、施設・設備・機械等の供与、東部地域に適した技術の開発、及び、その技術の移転等が行われる。プロジェクトの最終段階には、16パイロット・プロジェクトの構造及びその誌面についての本の出版も予定されている。プロジェクト・リーダー達は、彼らの経験が引き継がれ、プロジェクトが終了する1998年以降にも再利用可能なように、それを文書で残すことが重要だと考えている。
前述したように、土壌流出の頻発は雨、土の質、地形、植生及び土壌構造等によるものである。これらのうち地形・植生を除けば、それらの要因を変えることは不可能、あるいは極めてコスト高となる。そこでLWCCパイロット・プロジェクトの一つであるチョンブリ(Chonburi)の実験所では、土壌流出を防止する最善の方法を開発し、テストする試みを行っている。実験所には雨量計測器が装備されている。また、一定の地形・土地傾斜の下でさまざまな耕作パターンがもたらす侵食(土壌流出)効果についての実験も行っている。
こうした問題が地域固有の避け難い性質のものであることを考えれば、LWCCプロジェクトは極めて適切なものであるといえる。問題が立地特殊的性質を抱えるものであるがゆえに、技術移転の前段階で行う各パイロット・プロジェクトでの適正土地・水資源保全技術の開発及びテストはプロジェクトの極めて重要な構成部分となっている。
プロジェクト技術者たちがJICAスタッフの専門技術から学ぶところは多く、こうして取得されたノウハウは援助主体が引き上げた後も有効に活用されるであろう。 プロジェクトの成果は、開発された最善の土地・水資源保全手法といった研究成果、この研究成果の農家への普及率等によって評価される。具体的には、プロジェクトの直接的効果は、その新技術を受け入れた農家の数、誤った土地利用の減少、収穫への効果、洪水や土壌流出の発生頻度等によっても確認できる。最終的には、プロジェクトによる農家の生活水準の変化も検証可能であろう。より長期的には、この地域の環境の変化によって、このプロジェクトがその当初の目的を達成したか否かが評価されよう。
2 全体的評価
その急速な経済成長にもかかわらず、タイに代表されるアジアの多くの国では、当該国政府のみならず国際的機関の関与をも必要とする危急の環境、社会、農業問題が発生している。また、そうした国々の内部にあって、経済成長が集中する中核的都市域から大きく遅れていく地域も存在している。こうした事実に目を瞑れば、そうした地域の貧困は進み、一層の環境破壊が進行しよう。
こうした問題を緩和するための援助国・援助機関の役割は極めて重要である。援助が供与できる資源は危急かつ大事なものだが、量的に限られている。従って、援助対象(通常は社会的に恵まれない人々のグループ)に巧く恩恵が及ぶよう、適切に配分され、最適な活用が図られることが肝要と思われる。
なお、今回、短期間のうちに多くの案件を視察したが、それぞれのプロジェクトにおいて、関係者のご努力、ご労苦には真に頭が下がる思いであった。一般のマスコミにこのような我が国援助関係者の真摯な活動が紹介されることが少ないことこそ、もっとも改善されるべき点であるとの感を一同強く持った。

