3 カンボジア、マレーシア、ミャンマーにおける経済協力評価
産経新聞社論説委員 安村 廉
(現地調査期間:1995年7月16日~7月29日)
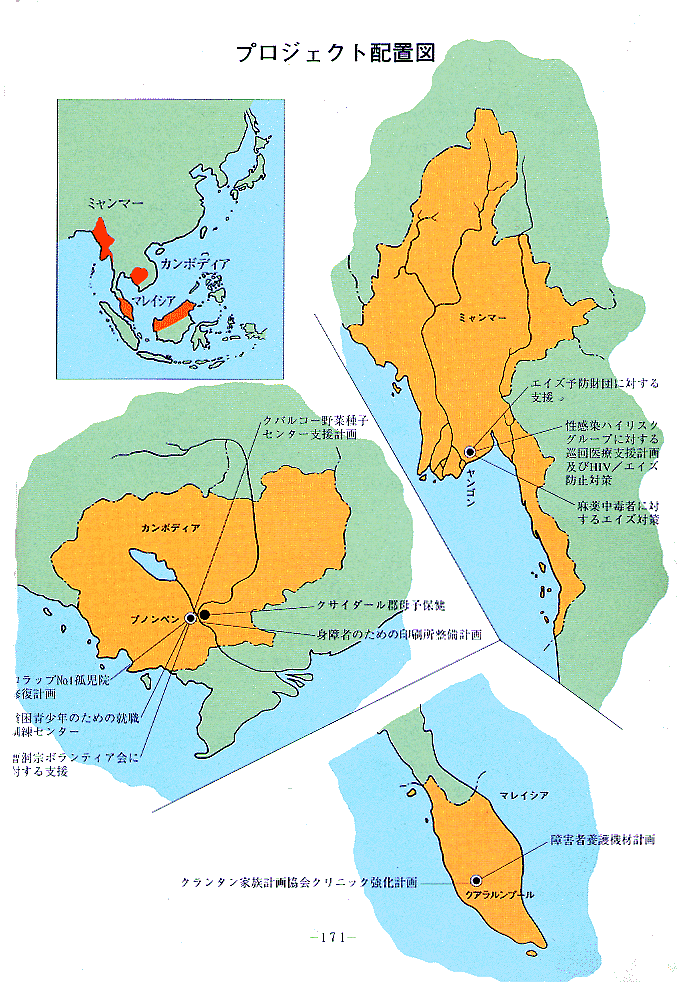
評価対象プロジェクトの概要
| 案件 | 協力形態 | 協力期間、金額 | 案件概要 |
| 曹洞宗ボランティア会に対する支援(カンボジア) | NGO事業補助金 |
1,000万円 (93年度) |
印刷・出版事情が十分でないカンボジアにおいて、オフセット印刷から製本までの技術全般の指導を行う。 |
| クバルコー野菜種子センター支援計画(カンボジア) | 草の根無償資金協力 |
386万円 (93年度) |
農民へ野菜の栽培と採種技術を普及・促進するため、試験圃場灌漑施設の修復・拡張、機材の整備を支援する。 |
| 貧困青少年のための職業訓練センター(カンボジア) | 草の根無償資金協力 |
224万円 (94年度) |
青少年を対象としてミシン、コンピュータの職業訓練を行うセンターに対し、大型ジェネレーターを供与。 |
| コラッブNo1孤児院修復計画(カンボジア) | 草の根無償資金協力 |
207万円 (94年度) |
孤児院の一部である寄宿舎の復旧・修復を行い、在籍孤児の生活、教育水準の向上を図る。 |
| クサイカンダール郡母子保健(カンボジア) | 草の根無償資金協力 |
563万円 (93年度) |
カンボジアの僻地農村であるクサイダール地域の深刻な課題である母子の保健・健康状態の向上を図るために、郡病院に産婦人科病棟を増築し、地域保健活動訓練室を併設。 |
| 身障者のための印刷所整備計画(カンボジア) | 草の根無償資金協力 |
171万円 (94年度) |
身障者、傷疾軍人に対し識字教育、職業訓練を行っているキエンクリエン障害者センターに対し、印刷所設置を支援することにより、教科書等の印刷を可能にし、身障者、傷疾軍人の教育指導の向上を図る。 |
| 障害者養護機材計画(マイシア) | 草の根無償資金協力 |
249万円 (89年度) |
養護施設運営、身障者家庭巡回訪問等を行っているマレーシアン・ケアに対し福祉用機材を供与し、障害者に対する機能開発訓練、介護者の指導に資する。 |
| クランタン家族計画協会クリニック強化計画(マレーシア) | 草の根無償資金協力 |
442万円 (94年度) |
超音波診断器等の医療機材及び移動診療所としての車輌を導入し、クランタン家族計画協会の医療活動の向上を図る。 |
| エイズ予防財団に対する支援(ミャンマー) | NGO事業補助金 |
600万円 |
HIVテストキット及びコンドームをミャンマー政府に供与し、エイズ予防対策について技術指導を行う。 |
| 性感染ハイリスクグループに対する巡回医療支援計画及びHIV/エイズ防止対策(ミャンマー) | 草の根無償資金協力 |
876万円 (94年度) |
エイズに関する啓蒙・教育、移動診療サービスを実施し、性的接触によるエイズ感染防止を図ることを目的として、医療品、巡回診療用車輌等を供与。 |
| 麻薬中毒者に対するエイズ対策(ミャンマー) | 草の根無償資金協力 |
441万円 (94年度) |
静注薬物濫用によるエイズ感染の防止を目的として、エイズ教育を実施するための教育機材を供与。 |
本調査は、草の根無償の持つ制度的なメリット、ODA事業におけるNGO活動の効果等について、具体的案件の視察、関係者との意見交換等を通じて検証し、今後の我が国の取り組み方について、政策提言することを目的に実施された。
I 評価結果
これら11案件に対する支援は、総じて有益かつ評価すべきものと考えられた。もちろん、ミクロ的に見れば、問題点がなかったわけではない。
例えば、カンボジアの「クバルコー野菜種子センター支援計画」のケースでは、二度にわたり灌漑用ポンプを供与しているが、たまたま調査した時期は雨期であり、降雨量が多いため一基は使用されておらず、種子選別機、種子洗浄機は、ともに専用の作業棟が未完成であるため、まだ使われていなかった。
同じくカンボジアの「コラップNo.1孤児院の修復計画」については、老朽・破損が著しい孤児院の建物の一部を新築したが、別の入居者がその老朽建物に引き続き居住しなければならぬ現状は変わっていない。新たに居住環境の格差を生み出した面がある。
マレーシアの「障害者養護機材計画」の場合、身障者用の玩具開発という発想面では、旧宗主国・英国が「先進国」であること、事実上キリスト教会の付属施設となっていることもあって、利用者はクリスチャンにほぼ限られており、日本の「顔」はきわめて見えにくくなっている。
ただし、これらは支援規模が小さいことや事業内容の多様性から見ても、試行錯誤として許容してよいものであり、適切なアフターケアさえ絶やさなければ、地道な日本の貢献活動となり得るものである。
半面、ミャンマーにおける一連のエイズ対策支援は、ただちに効果が表われにくいという基本的な制約条件を抱えながらも、政府と現地NGO及び日本の有機的なつながりが確保されている点を評価したい。
後述するが、当該国政府のとっている政策と、NGO特に外国NGOの活動が、政治的な摩擦を起こすケースもあるようだ。しかし、ミャンマーのエイズ対策については、今のところ、保健省、WHO、現地医師会、外国NGO、それに日本の支援がかみ合っており、日本公館の担当官が一種のコーディネーターの役割を果たしているとさえ感じられた。
カンボジアでは、「シェア」「難民を助ける会」それに「曹洞宗ボランティア会」の挙げている成果を率直に評価したい。当地は今やNGOのメッカであり、日本における対外NGOの原点は、カンボジア難民救援だったという事情もあって、真のボランティア精神に触れることができた。
「シェア」の派遣医師は、新式医療機材の供与などは不要で、現地の病院が最低限の医療水準を満たすだけのインフラ整備や、現地医療スタッフの自助努力に主眼を置いていた。
「難民を助ける会」の女性スタッフは職業訓練の過程で生まれた皮革製品などで収益を上げつつある。「曹洞宗ボランティア会」も当地では一流の技術を持つ“印刷工場"として、さまざまな需要に応じている。
そうした背景には、開発から民生、医療、教育に至るまで、行政の手がまったく届かないカンボジアの特殊事情がある。したがって草の根協力のニーズは無限にあり、現地公館のみならず外務本省は、「官主導」の印象を極力避けつつ、NGOに対する情報提供や、ボランティア精神の発露を待つ広報活動に取り組むべきである。もちろんカンボジアに限ったことではない。
マレーシアの「クランタン家族計画協会」に対する支援は、ある程度の発展段階に到達してはいるが、中央とはまだ格差のある地方の医師団体に、超音波診断器や巡回診療車両を供与したもので、カンボジアのケースとはまったく違う。同国に対する草の根協力は、現地NGOの要請がベースになると思うが、これまた有意義なことである。
II 国内で留意すべき点
(1) 日本のNGOの特性
どの先進国にも多少共通することだろうが、とりわけ日本のNGOには、反政府的と言わないまでも、アンチ・ガバメントの姿勢が強く感じられる。
そうした事情もあってか、開発途上国の草の根のニーズに応じ、自らメニューを提示し得るという未来志向型のNGOの基盤はまだまだ脆弱であるとみられる。
それを裏付けるように、タイ国境のカンボジア難民キャンプで給食活動をした実績を持つあるNGOは、カンボジア和平のあと何をしてよいのかわからないという意味のことをある左傾誌に告白している。「シェア」や「難民を助ける会」の存在を知らないかのようである。
(2) 活力あるNGOの育成
したがって、草の根無償協力に対する積極的な広報活動を通じて、健全なNGOが自発的に生まれるように、外務省は側面的な援助をすべきである。
政治的指向性が強すぎては困るが、これにも幅はあって当然であり、色々な考え方を持ったNGOが現地で活動することは、日本自身の価値観の多様さを、その国に示すメリットもあろう。
しかし、「官主導」でNGOを育成・誘導しようとしても、ボランティアが本来、個人の精神的自立で生まれることを考えれば不可能である。役所の窓口をできるかぎりオープンにし、NGOとの意思疎通を図るため、随時に自由な雰囲気の集まりを呼びかけるなどの努力が求められる。
(3) 水平・垂直分業体制
膨大な途上国のニーズに少しでも効率よく対応するためには、さまざまな特性・特技を持つNGO間の役割分担がなされれば最適である。しかし、NGOが基本的に独立心が旺盛であることを考えれば、そう簡単ではない。複数のNGOに聞いても、この点には残らず否定的であった。しかし、外務省がNGO補助事業選定の過程で、これを調整していくことは可能ではないか。
(注)補助対象事業の経費の半分以上がNGOの自己負担であること、NGO事業補助金は政策誘導型のものではなく助成型補助金である(奨励補助金ではない)ことを勘案すると、NGO間で否定的である役割分担を補助金事業で調整することは容易ではないと思われる。
(4) 精算払いの改善
NGO事業補助金は、事業費の半分までを精算時に支払う仕組みであるため、立ち上がりの時点で資金調達に苦しむNGOも多い。そうした声を現地でも帰国後も聞いた。事業計画がしっかりしたものであれば、最初から補助金を支出することも検討してよい。
(注)補助金の前払いとは、供託金を取らずに国費の前渡しを行うということであるが、「精算払」であればこそ、事故を未然に防ぐことが可能となり、納税者に対する国費の責任をもった取り扱いという点から、補助金の前払いについては慎重に検討する必要がある。
III 在外公館が留意すべき点
(1) 当該国政府との相互補完関係
NGOが敬遠しがちな面だが、草の根協力といえども、現地政府の無用の警戒心を呼び起こすものであっては、効果が減殺される。例えばミャンマーにおけるエイズ啓蒙対策は、現地医師会が、運転免許更新時の講習にとどまらず、政府が公式にはタッチできない売春婦に対する教育なども行い、現段階ではNGOとの協力関係は良好に保たれている。こうした枠組みは絶対的条件ではないにしても、できるだけ活動を円滑に進めるための調整作業、つまり現地政府とNGOを仲介することも現地公館に求められよう。
(2) コンサルタント制度の導入
今後、草の根協力が増えると思われるが、現在の公館の限られた人員では、NGOが提示する案件の可能性調査をはじめ、供与機材の選定・決裁などの事務量増大に対応することは難しいと考えられる。これは草の根協力の特徴の一つである機動力を損なうことにもなる。
カンボジアのように治安が回復すれば、多数のNGOが地方展開するとみられる公館では、担当官の下に情報を一元化するネットワークづくりが必要である。「官主導ないし介入」にNGOの抵抗が強いというのであれば、青年海外協力隊調整員のような立場の「NGO調整員」を制度化することも、検討すべきだろう。多国間ネットワークができ、これに参画できることになれば理想的である。
(3) 継続性と試行錯誤
11にのぼる案件を見て痛感したのは、継続的援助の必要性である。いずれも単年度限りの措置で解決する問題ではなく、むしろ息の長い取り組みが必要なものが多かった。アフターケアをしっかりやるのは当然である。同時に、試行錯誤を恐れるべきではない。草の根協力は異文化を前提とした住民密着型だけに難しい面もあり、効果がすぐ目に見えるとは限らない。厳正な査定は当然とはいえ、一件平均500万円に満たないという少額の援助である。NGOと共に学びながら、キメ細かな協力の方途を探っていく余裕も必要だと考える。

