2 インドネシア、タイ、中国、フィリピン、マレーシアにおける経済協力評価
笹川平和財団参与 高橋一生
(現在国際開発高等教育機構国際開発研究センター所長)
(現地調査期間:インドネシア、タイ、フィリピン1995年6月21日~7月1日
中国、マレーシア1995年12月12日~12月21日)
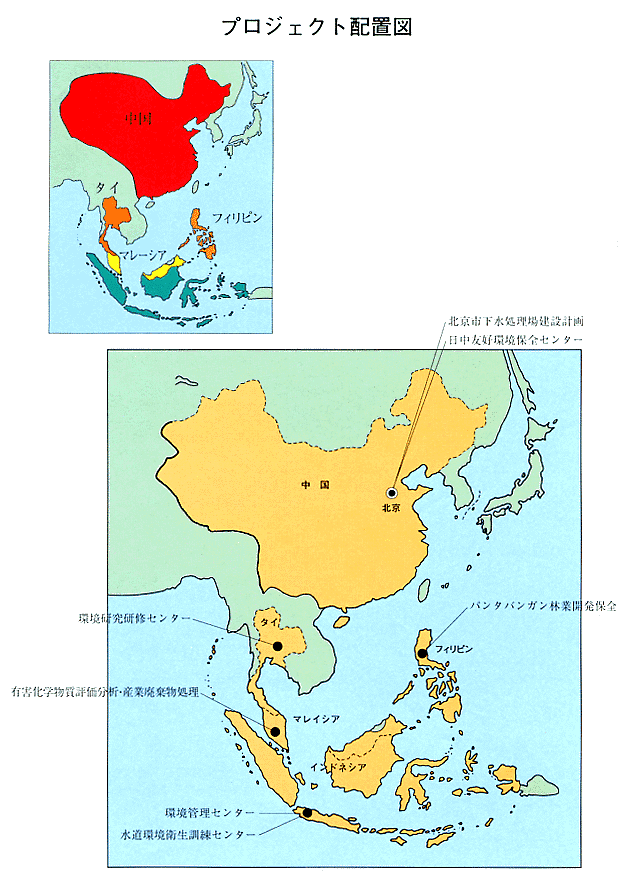
評価対象プロジェクトの概要
|
案件 |
協力形態 |
協力期間、金額 |
案件概要 |
| 水道環境衛生訓練センター(インドネシア) |
無償資金協力 |
1988年度、11.14億円 1991年4月~1997年9月 |
生活環境関連施設の整備・運営に関する技術者の育成を目的とした、訓練施設の建設、道管理及び環境衛生に関する技術協力。 |
| 環境管理センター(インドネシア) |
無償資金協力 |
1991年度、8.88億円 1992年度、17.99億円 1993年1月~1997年12月 |
各種汚染影響及び自然資源の破壊の危機並びに一般環境衛生問題の解決のため、環境管理センターを設立し、環境研究・研修分野における官民の技術者の技能・技術の向上を図る。 |
| 環境研究研修センター(タイ) |
無償資金協力 |
1989年度、15.94億円 1990年度、8.62億円 1990年4月~1997年3月 |
近年のタイの著しい都市化・工業化が引き起こす環境問題に対応するため、環境研究研修センターを設立し、同センターの運営、水質汚濁、大気汚染等に関する研究・研修・モニタリング等の技術の向上を図る。 |
| 北京市下水処理場建設計画(中国) | 無償資金協力 | 1988年度、26.40億円 | 北京市に下水処理場(50万㎡/日)を建設し、同市の環境状況の改善を図る。 |
| 日中友好環境保全センター(中国) |
無償資金協力 |
1990年度、2.43億円 1991年度、3.02億円 1992年度、19.14億円 1993年度、42.21億円 1994年度、38.19億円 フェーズ1 1992年9月~1995年8月 |
中国では、急激な経済成長に伴い環境問題が深刻になりつつあるため、研究開発の中核をなす環境保全センターを設立し、環境管理手法、環境監測技術を指導し、環境保全の推進に資する。 |
| パンタバンガン林業開発(フィリピン) |
無償資金協力 |
1978年度、10.50億円 フェーズ1 1976年6月~1987年7月 フェーズII 1987年7月~1992年7月 |
森林保全技術の教育訓練、技術指導を行うための研修センターを設立し、移動農耕、過放牧等による森林資源の量的・質的低下防止のために、森林造成技術、森林保全技術の移転を行うもの。 |
| 有害化学物質評価分析・産業廃棄物処理(マレーシア) |
プロジェクト方式技術協力 |
1993年9月~1997年9月 | 有害化学物質の評価・分析技術並びに産業廃棄物の微生物処理手法の向上を通じ、有害化学物質及び廃棄物の安全体制の整備、合理化を図る。 |
I 概論
1 播斉ダイナミズムと環境保全
先行き不透明な世界経済の中で、東アジア経済は唯一、光輝いている地域である。その経済ダイナミズムを背景にして、東アジア全体が世界政治の表舞台におどり出してきた。世界の注目を集めれば集めるだけ、この地域の個々の国、個々の社会の内容が国際社会の関心事項にならざるを得ない。高度経済成長をもたらす政府の役割、輸出志向、高い教育投資等をめぐって、東アジア・モデル論争が繰り広げられつつある。
光と同時に影もある。高度経済成長のもたらす環境破壊は、その最もも顕著な問題である。一方で高度成長続行の押せ押せムードがあると同時に、他方で、環境破壊に対する懸念も強まり始めている。この両者をいかに両立させるかが、東アジア諸国全体の課題になりつつある。タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、中国、5ヵ国ともそれぞれ異なる政策ミックスでこの課題に取り組みつつある。
持続可能な開発という概念の充分な具体化は、世界中どこでも未だ出来ていないが、このコンセプトの各論化の最先端で現実に取り組んでいるのがこれら諸国であろう。日本のこれらパートナー諸国との環境協力も、一歩一歩この概念の各論化への作業という色彩を強く持たざるをえない。すなわち、すでに解答があり、それを適用する、ということではなく、パートナー諸国と解答麹地球社会全体への明日のリーダーシップを目指すという姿勢が重要であろう。
その大前提は、東アジア諸国の経済ダイナミズムに対して環境保全対策がブレーキになってはならない、ということであろう。中国、タイ、マレーシアの8%台、インドネシアの6%台、フィリピンの5%台以上の成長の持続が前提になる。その実現のための投資、人材配分等が政治的安定性とともに重要な課題であり続けるものと認識すべきであろう。その上で、効果的な環境保全対策を実施する、という位置づけが保持されなければならない。
対象5ヵ国とも、幸いにして、政策面で環境保全認識が強くなりつつある。法規及び制度上、環境保全に対する考慮がすでにかなりなされている。これらの基盤のもとに、実効ある環境保全対策を執行する体制を、いかにして強化するか、ということが国際的パートナーの役割である。中国、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンの政策の基本的な方向は、自国の国内からの圧力、1992年のリオにおける環境サミットに向けたプロセス及びドナー・コミュニティーの環境保全に対する強い関口・により、打ち出されてきた。従って、数年前までの、構造調整政策及び環境保全に関しての基本的な開発政策の方向をめぐっての政策対話の時代は過ぎ、現在は、その両者の各論及び政策ミックスの有効性の検証の時期に入りつつある。このコンテキストで経済ダイナミズムと環境保全の両立のための日本の役割が考えられてゆかねばならない。
2 技術移転と環境保全強化
その各論化の有力な出発虚が技術移転である。人口増加と同様、一人あたり国民所得の増加と環境破壊との相関関係がある。一人あたりの国民所得がある一定の高さに達すると、人口増加が減少しはじめ、さらに高くなると増加そのものが停止する。同様に、一人あたり国民所得がある一定点よりも高くなると、経済成長のもたらす環境破壊度も減少しはじめる。ところが、その一定点に達する直前の段階の経済成長のもたらす環境破壊度は極めて高い。この一定点はOECD諸国ではおよそ一人当り国民所得が10,000ドル程度であった。日本は1970年代にこの段階に入った。1972年のストックホルムにおける国連人間環境会議は、1960年代後半にOECD諸国が、この一定点に達する前後の猛烈な環境破壊が、世界的課題になったことにより、一連の合意に達せざるをえなかった。
ところが、一部の国では、この一定点が10,000ドルよりもずっと下にさがりつつある。たとえば韓国ではその半分以下の4,000ドル前後にこのターニングポイントが下がった。この低下に貢献した一番大きな要素が環境保全技術の移転である。たとえばNOXについては、日本は1968年に下がりはじめ、当時の一人あたりGNPは11,000ドルであったが、韓国は1987年にさがりはじめ、その時点では4,100ドルであった。この技術移転を成り立たせるためには教育、国民意識等が密接に結び付き、これらの点に関してはいまだ解明すべき問題も残るが、この傾向を促進することが、日本の国際環境協力の中心課題であろう。この目的を明確にし、政府、自治体、企業さらにはNGOが一体となり、東アジアの経済的にダイナミックなパートナー諸国が、なるべく早くターニングポイントに達するよう努力することが、日本が環境保全分野における世界的リーダーシップをとるための一里塚であろう。
この目標達成のためには、企業間の技術移転の促進、人材育成、研究協力、政策効果測定のための技術協力等が連携したかたちで行われる必要がある。さらに、パートナー国の政策の有効性、関連技術の特定地域における有効性、また人材の配分等にっき、パートナー国と常に協議し、相互に改善努力をする必要がある。また、このターニングポイントの下方移動努力の世界的な適用可能性についても、東アジアの地球社会全体に対する貢献として、検証し、フォーミュラ化する必要がある。
3 環境保全の新しいうねり
タイ、インドネシア、フィリピン及びマレーシアにおける環境保全の重要な担い手としてNGOが登場して10年近くなる。特に、1992年のリオにおける環境サミットをきっかけとして、これらの国における環境NGOは社会のメインストリームになりつつある。政府とNGOとの関係は、これら諸国では、対立よりも、むしろ相互補完的色彩が強くなりつつある。
これら諸国のNGOと比して、日本のNGOは残念ながら、あまりにも弱体であり、環境問題に対して、日本が有効な国際協力を行う場合、この点が、ボトル・ネックになる。欧米のNGOとの協力を含め、工夫が必要である。
中国においては、現在環境分野における独立のNGOは、ただ一つであり、他は多かれ少なかれ政府に関係のある団体のようである。しかし、この分野におけるNGOの形成及び活動は、今後かなり大きな可能性があるように見受けられた。
さらに、政策立案プロセスにおいても、立法府の環境保全に対する前向きな態度は中国以外の4ヵ国で共通している。最近の選挙においては、この4ヵ国とも、環境保全は政治イシューとはならず、ほとんどの主要政党の網領の重点項目として扱い、政治的には高いプライオリテイー事項としてコンセンサスが形成されつつある。
また、インドネシアの54木堂における環境センターもしくは学科をはじめ、中国、マレーシア、タイ、フィリピンにおいても大学における環境関連学科もしくはコースの拡大は顕著な流れである。環境学として一つの学問分野として確立していないことを考えると、この傾向は、今後大学社会に、さまざまなインパクトをもたらすであろう。一つはっきりしていることは、今後のより高度な環境分野における人材育成のための重要な基盤が形成されつつある、ということである。
しかし、行政府をみると、後発分野として、環境行政はまだまだ弱体である。関連分野が多くの省にまたがっていることとともに、環境行政担当者の未熟さが、この分野の行政府内における弱さの大きな要因である。環境保全分野における前向きの大きなうねりの中で、制度的な強化が徐々に行われてはいるが、行政府内の環境行政の立ち遅れが、今後の大きな課題になろう。特に、自治体レベルにおける環境保全行政の立ち遅れは、さらに顕著なように見受けられた。
4 東アジアの環境保全と国際社会における新たなリーダーシップ
経済ダイナミズムの維持と環境保全の両立は地球社会全体にとっての主要課題である。この課題への具体的な取り組みが、中国、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンとの日本の環境協力の主目的であろう。この目的を追求するためには、これら諸国の中・長期的開発政策と日本の開発協力のパートナーシップの中で、環境保全の位置付けを明確にし、そのうえで、それぞれの持つものを出しあうことが重要である。
これら5ヵ国の中には、開発戦略が必ずしもはっきりしていない国もある。しかし、中・長期的にみて工業セクターの拡大、さらには近代的第三次産業と工業セクターとの連携の拡大という、開発プロセスの大筋は共通である。その流れの中で、環境技術の移転と共同研究は、中核的な役割を果たし、ターニング・ポイントの下方移動に大きな貢献をするはずである。
他方、これら諸国の活発な経済活動は、森林、湖沼、河川、さらには海洋の自然生態系へますます大きなインパクトをもたらすであろう。それらすべてに対して国際協力をすることは不可能でもあるし、また、ローカル・コストを考えると、不適切でさえある場合もある。この分野でもプライオリティーを明確にした戦略的アプローチが必要になる。一つのオプションとしては、生物的多様性が豊かでありながら危機に瀕している場所に集中的に協力を行うホット・スポットアプローチがある。すなわち、危機に瀕していつつも、その豊かな資源を有効利用しつつ、自然環境を保全するアプローチである。世界で18ヵ所特定されているが、そのうち14カ所が熱帯雨林であり、インドネシア、マレーシア、フィリピンの一部地域もそこに含まれる。保護地域アプローチ、種の銀行等、その他いくつかのアプローチがあるが、今のところこのアプローチが一番有効のようである。
また、東アジア諸国の海洋性と日本のエネルギー源としての石油運搬路とを考えると、いわゆるブルー・イシューに対する取組も重要である。珊瑚礁、マングローブ等の生態系保護と、石油に関する災害予防とを兼ね併せた形でブルー・イシュー戦略を考えることも一案であろう。
さらに、東アジア諸国の経済ダイナミズムは、新たな農村の貧困を生み出し、貧しさゆえの環境破壊に拍車をかけている。いわゆるレッド・イシューである。主として炊事用エネルギーと農地関係の問題を中心としている。この分野では効率の高いカマドの普及等、やはり目玉を考えることも一案であろう。
これらの、いわゆるブラウン(公害)、グリーン(森林)、ブルー(湖沼・海洋)、レッド(貧困)の諸問題を総合的に扱い、かっ、ブラウン・イシュー、その中核として環境保全センター・アプローチを中心に位置付けることが、ジャパン・イニシアティブの内容になってもよいものと思える。
II 各論
1 タイ
社会的には、いわゆる中間所得者層の増加と、都市化が顕著な方向である。古典的知識層の僧侶と、新たな中間所得者層の二つが中心のNGO運動等を通じて環境問題を社会の中心課題として位置付けつつある。彼らの動きを活発なジャーナリズムが支援して、大きな政治的影響力を彼らに与えている。環境研究・研修センター(ERTC)
このプロジェクトは水質汚濁、大気汚染、騒音・振動、廃棄物及び有害物質についてのモニタリング手法、分析技術の向上のための技術移転及び技術者の養成を目的としている。
これまで、本プロジェクトにっき、いくつかの問題点が指摘された。JICA派遣専門家の一部とERTCのリーダーシップのコミュニケーション・ギャップ、ERTCスタッフの外部(特にビジネス・センター)への流出、さらにはトレーニング対象を近隣諸国に広げることなどである。
これらのプロジェクト実施上の問題点のより大きな背景としては、タイの高度経済成長を支える人材配分の問題がある。特に、工学分野に対する需要が今後ますます大きくなるが、年間工学部卒業生は約3,000名のみである。ERTCのスタッフの流出は最近はほとんどないようであるが、民間の給料が3~5倍であることを考えると、ERTCの位置付けを余程しっかりしないと、流出の再現はありうる。また、考え方によっては、むしろ民間への人材供給を一つの目的としてもよいのかもしれない。どっちにしろ、ERTCのスタッフの意味を明確にする必要がある。
他方、ERTCは、JICA専門家からの技術移転がかなり進みつつある。また、研修事業も拡大しつつある。1993年10月より1994年9月までに487名、1994年10月より1995年9月までに520名(予定)と着実に伸びている。予算も年約40%ずつ増加し、近い将来、ERTCはインスティテユートとして、行政上一つ上のランクが与えられることになっている。
ERTCの機能のニーズとしては、今後、まず、タイ環境行政の地方分権化にともない、地方の環境行政担当官の研修がある。本プロジェクトでは、彼らの測定技術の向上に的が絞られているが、今後はプロジェクト形成能力の強化も課題になるであろう。1994年から5年間で5,000名の研修が必要であるとみなされている。そのための寮の拡充が期待されている。
また、ERTCでは、インドシナ諸国の専門家の研修、さらにはASEAN諸国へのモニタリングに関する影響の増大が重要であると認識している。上記により総合的に判断すると、ERTCはほぼ初期の目的を達しつつあるものと思われる。今後については次の三つのオプションが考えられる。
1 タイ国内の地方分権化にともない、研修の主な対象は地方の行政担当官とする。技術 移転については、当初よりの5分野における測定法に的を絞り込む。
2 タイ社会の行政のみならず、ビジネス及びNGOの研修センターとして位置付ける。しかし、技術移転は5分野の測定方法に限る。
3 今後5年をめどにし、インドシナ、ミャンマーをも含めた地域のセンター・オブ・エクセレンスを目指す。そのために、JICA専門家も、この地域での研究活動も重視し、日本の第三国研修の一つの拠点として位置付ける。さらに、ASEMにおける役割も、今後ERTCの展開において重要な意味を持つであろう。
この三つのオプションのうち、タイ政府の外交姿勢、ERTCの可能性、日本の環境協力の新展開等を考慮すると、第三のオプションが最適と思える。しかし、その具体化には次の三つの作業が必要である。一つは日・タイ間に作業グループを形成し、センター・オブ・エクセレンス構想を煮詰めること。二つめはタイ政府のより積極的な肩入れ、特に、ERTCに有能な企画官及び総合調整官が必要である。三つ目には、インドシナ諸国及びミャンマーの政治的反応及び具体的ニーズをさぐることである。
2 インドネシア
環境保全分野においては森林及びバイオダイバーシティーに焦点が当てられてきた。最近になって公害及び海洋・河川・湖沼等の、いわゆるブルー問題に対しても関心が高くなりつつある。また、大学卒の優秀な人材が、かなり環境NGOに行きつつある。
環境行政の機構は三段階を経て発達してきた。第一段階は1978年の開発・環境省の設立であり、第二段階は1983年の人口・環境省への機構変えであった。1993年に環境省が独立の組織となり、政策立案、環境関連法制度の整備及び関係省庁との調整を行っている。1990年に設立された環境管理庁は政策の推進官庁として位置付けられ、現在は環境省の決定した事項の推進をその主な機能としている。
(1) 環境管理センター
上記の環境行政機構のかかえる一番の弱点は、環境の実態を把握し、政策、法規との関係を判断することである。この弱点を補強するために、行政担当官の研修を行うことを目的として環境管理センターを設立し、大気、水質、有害物質について測定の技術移転を行った。
当該センターはまず、環境モニタリングを行うためのリファレンス・ラボ及び研修に焦点があてられている。リファレンス・ラボとしての機能は、すでに発揮しはじめている。インドネシア政府はまず、全国の400ほどの工場を(今後は1,000に増やす)環境的側面からみて5段階にランク付けし、それを公表するという政策を1994年以来採用している。この世界的にみても極めてユニークな政策が可能なのは、当該センターのリファレンス・ラボとしての機能があるからである。
研修は、まずセンターのスタッフをトレーナーとして育てることから始めている。まだ新卒をとって3年ほどなので、今後も2~3年は彼らを教育するヒとに重点を置く必要があろう。インドネシアではタイと異なり工学系大卒が不足するということはなく、また、国内の54の大学で環境分野のコースを持っているので、今後も若手の採用に困難を来すことはなさそうである。しかし、彼らをトレーナーとして訓練するためには時間が必要であろう。
インドネシアも徐々に地方分権化の方向にあり、地方の環境行政担当官の研修が今後の大きな課題になる。地方に小規模のセンターが一つか二つあるが、全国的には当該センターのみであり、今後はそれぞれの地方の環境特質を考慮しつつ、インドネシア全国の専門家の研修に重要な役割を担うことが期待されている。このようなことから、当初、環境管理庁の一プロジェクトとして三名の副長官の一人の下についていたが、その後、長官(環境大臣サルワーノ=モクタール前外相の弟=が兼任)直属で、かつ行政機構の一部になった。インドネシア政府としても、今後かなり肩入れをすることが期待される。
当該センターのリーダーシップのJICA専門家に対する信頼は厚いようにみうけられた。しかし、専門家が必ずしも外部の者に対するトレーニングコースの担当者として適してはいない点は残念な様子であった。プロジェクトの目的は外部の人達の研究を行うのではなく、トレーナーの育成のはずであるので、この点は相互の承解を常にしておく必要があろう。
JICA専門家からは、いくらインドネシアのシステムの一部だとはいえ、研究員がアルバイトに精を出しすぎる、という点が指摘された。JICAチームの中では、調整員が専門家と現地スタッフのギャップを埋める役割を果たし、その活躍が特に光っていた。インドネシア語力、インドネシアにおける長期の生活が強みである。
上記をもとに総合的に考えると、環境管理センターは、所期の目的を達しつつあると思える。地方の専門家の研修、さらに、行政機構への格上げという新しい状況を踏まえ、日本一インドネシア間で、当該センターの今後の在り方につき、この段階でよく協議しておく必要があろう。その際、今後の方向の選択肢としては、次のものが考慮の土台になるであろう。
i) インドネシア内部の研究・研修センターとして、インドネシア社会全体に対象を広げることが考えられる。優秀な人材が行きつつあるNGOに高度な研修機会を与えることがまず考えられる。さらに、ビジネスセクターの研修ニーズも今後増大するであろう。
ii) インドネシアは外交的にASEANを足場とする段階から、非同盟議長国、APEC議長国をこなし、グローバル・アクターになりつつある。特に南南協力には力を入れている。その一環として、当該センターも南南協力の一つの場とすることも近いうちに日程にのぼるであろう。
この二つは、おそらく今後の第一フェーズ(地方専門家の研修、1995年9月より)、第二フェーズ(総合的研修)、第三フェーズ(南々協力)ということなのかもしれない。そのような可能性を考慮に入れつつ、今後の当該センターの発展の方向につき、日本一インドネシア間でよく協議をしておくことが重要である。
2 水道環境衛生訓練センター
当該センターは水道管理と環境衛生の二分野にっき包括的な研修を行う。一般コースと上級コースに分けて行われ、協力も上級コースに対して行われている。最近は上級コースの受講者が増加しつつある。
上級コースの研修能力は年間約800名であるが、現実には1994年は443名強が研修を受けたのみである。これは、主として予算不足のためである。インドネシア各地の技術者7,000人ほどを出来るだけ早く研修を受けさせねばならないが、予算不足のために、パイプ業者などのビジネス・セクターから費用をとって研修を行っているのが現実である。
また、水は地方で異なり、その管理も変えねばならない。この点に対する配慮が十分行えていない、という自己分析があった。
スラバヤに世銀の協力で同様のセンターができた。しかし、当該センターより規模が小さく、また環境衛生は含まれない。
新たな展開として、下水道、個型廃棄物、生活廃水処理を扱う方向に向かいつつある。将来的には居住環境を対象とするように質的転換が考慮されている。
これはタイのERTCやインドネシアの環境管理センターが、同じ機能を拡大・強化することとは大きく異なる。この質的転換がどの程度必然的なものなのかをはっきりと判断する必要がある。
3 フィリピン
社会的には1986年のいわゆるピープル革命以来、NGOの力が強く、各分野で活発に活動を行っている。環境保全分野でのNGOの活動は特に目を見張るものがある。これらNGOが選挙の際に大きな役割を果している。フィリピンの環境NGOの活動は森林関連活動からはじまり、環境行政も、この分野から手がっけられはじめた。公害及び海洋分野は、これからはじまる、というところである。
パンタバンガン林業開発
1979~1981年に建物が建てられ、1982年に研修事業が始まった。治山、造林の技術移転が目的であった。
その後当該センターは、フィリピン全体にいくつかある研修センターのモデル・センターの役割を担うようになり、1993年には環境省に編入された。現在、年間600名ほどの研修を行っている。対象は地方行政環境担当官、NGO、教会関係者等である。
その間、JICA専門家は当該プロジェクトを通じて熱帯林の再生技術開発に精を出した。報告書も100本以上書かれ、その後の日本の熱帯林の再生、植林協力プロジェクトに大きな貢献をした。なお、植林後30年ほどは追跡調査をする必要があるので、その観点から、このサイトは今後もフィリピンの専門家にとっても、また日本の専門家にとっても重要であるとのことである。
このプロジェクトは、協力目的を達成するために現地の実情に応じ、順次活動内容が変化してきたが、プロジェクトの目的そのものはある程度達成している。しかし、手法として住民の啓蒙は取り入れているが、住民の十分な参加は図られていなかった。
一方、専門家にとっての技術開発対象としての価値は、今後もしばらくあり続ける。技術開発の継続可能な手を打っておくことが必要であろう。
(より有用な樹種の活用、研修内容の充実等を目的として、97年7月から2年間のアフターケア協力を予定。)
4 マレーシア
1992年のリオにおける環境サミットにいたる一連のプロセスを通じて、マレーシアは国際社会のイシューとしての環境問題という補え方に、一貫して反対していた。現在もこの原則に変わりはない。基本的には自国の開発に対して、先進国から、環境を含め、いかなる条件を付けられることも反対する、ということである。多かれ少なかれ途上国にある要素であるが、マレーシアの場合にはこの色彩が最も明確である。しかし、マレーシア政府自身の判断としては、環境問題に対する取組に徐々に真剣になりつつある。
有害化学物質評価分析・産業廃棄物処理
本件は、開発途上国における環境保全に対する貢献を積極的に図るという観点から、我が方から環境保全の重要性を配慮したプロジェクト形成の支援を行い、従来の案件より迅速に対応する方式(積極型環境保全協力)で実施された第一号である。
積極型として、当該案件をすみやかに実施にこぎつけることが最優先され、人材もより多く投入し、通常のJICA案件よりは短時間で実施段階に入った。
8項目の技術移転実施分野のうち、五つが有害化学物質の評価分析技術、三つが産業廃棄物関連である。前者は5名の長期専門家、後者は短期専門家で対応している。評価分析技術については、専門家1名に対して、マレーシア側2名ないし3名がつき、技術移転もかなり進んでいる。目標は、試験責任者を育てることであるが、2年程の間には目標達成が可能なようである。
機材は大半がマレーシア国内で調達されたものであり、パーツの問題も今後かなりの程度処理できるであろう。
現状は、とりあえず当初の予定に近い形で実行されているようである。これは、専門家チームがよくまとまっているという点も無視できないが、何よりも研究所の所長の力に負っているように見受けられた。積極型案件の場合,相手方に高い実施能力があることが必須条件である。
1996年3月を目標に、標準工業研究所は国有会社に移行する。政府の持株会社の形態をとり、研究所のいくつかの部門がそれぞれ会社となるという構想のようである。政府の補助が研修等については継続されるとのことであるが、当該案件はその対象にはなりにくいのかもしれない。中・長期的に、当該案件は、ニーズとコストの両面からしてもマーケット・ベースで機能するとは考えられず、1997年9月のプロジェクト終了後、どのようになるのかを明確にしていくということが今後の中心課題である。
注:第6次マレーシア計画(91~95年)では、環境の章において、有害廃棄物等の問題の解決とともに産業部門の積極的な環境配慮、政府機関の役割強化等の必要性を指摘していたが、第7次マレーシア計画(96~2000年)では、より明確に有害物質・有害廃棄物の節が設けられた。また、現在、科学技術環境省環境局においてIndustrial Chemical Actの法案が作成中である等、産業界及び政府内部双方で技術的基盤の確立が求められている。標準工業研究所は1996年9月に公社化されたが、マレーシア首相府経済計画部、科学技術環境省環境局とも、公社化後も同研究所を政府内での重要な技術的機関と見なしており、また、本プロジェクトの技術分野はマレーシアの政府関係機関の中で唯一のものであるため、関係省庁からの継続的支援が期待される。さらに、研究所における運営経費の50%、開発経費全額が政府から支給されていることもあり、財政的面でのプロジェクトの自立発展性については、基本的には心配はない。
さらに、当該案件は研修を含まず、数名の専門家が育ったらそれで終わり、ということである。マレーシアの経済発展の状況からして、今後5年、10年、15年に当該分野のニーズはかなり拡大するであろう。その要素は、1995年12月にプロジェクト・デザイン・マトリックスの中に取り込まれた。
注:カウンターパートヘの技術移転の結果、標準工業研究所の有割ヒ学物質の評価・分析、廃棄物処理の技術能力が向上し、産業界への指導や分析サービスができるようになり、96~97年には13件の受託研究・分析を実施できるまでになった。
マレーシアの2020年先進国入り目標はかなり真剣に取り組まれているが、環境基準の問題は今後ますます重要なテーマになるはずである。
積極型第一号案件として、当該プロジェクトは示唆に富んでいる。まず第一には、積極型はともすれば押し付け型と捕えられがちであろうが、かっ、その面からして環境分野では反北側のスタンスをとっているマレーシアでも、本研究所の所長のように、相手方に人を得ればとにかくきっちりと実行できる、ということを意味している。特に、マレーシア政府自身の判断で環境保全に力を入れつつある状況で、ヒトを得たことの意味は大きい。第二には、積極型の場合でも、しっかりとした事前及びモニタリングの一環としての調査が必要である、ということである。この点は、プロジェクトの政策環境として、マレーシアにおける急速な市場経済化の意味と、プロジェクトの中味の、中・長期的ニーズという二点の明確な把握が、極めて重要であるということである。
このように、プラスの面と明確に把握すべき面が、本プロジェクトにはよく出ている。今後の課題として、一つには、マレーシア側からも出されている環境センター構想があろう。
日本は北京、バンコク、ジャカルタにすでに環境センターを設立しているが、それぞれ異なった分野で技術移転と人材育成を行っており、マレイシァのものも、更に異なる分野に特化するように話をしていくことができるのではないかと思われる。そこに、本プロジェクトをやがて吸収させることを想定してよいであろう。日本からみて、バンコク、ジャカルタ、クアラルンプールの三つの環境センターが、それぞれ異なる分野で東南アジアのセンター・オブ・エクセレンスに育っていくように、全体構想を持ってもよいのではなかろうか。中国の環境センターも含め、日本がアジアにおける環境技術の移転と人材育成について、全体構想をこれら諸国と協力しつつ描く時期に来ているように思われる。そのような枠組みの中で、当該プロジェクトで育ちつつある人材を新しいセンターに吸収するように考えてゆくことが、一つの解決策であるように思える。
5 中国
環境問題に対して、この2、3年、政府の態度が前向きになりつつある。党のレベルにおける関心の変化の兆しは見られないが、国務院レベルでは環境問題に対する取組がかなり変わりつつあるようである。一つには、現実に都市環境の悪化をはじめ、問題そのものがあまりにも深刻になりはじめているからであろうし、またもう一つには、日本をはじめ、ドナー・コミュニティーの環境保全に対する高いプライオリティーを無視できなくなってきているからのようである。現在は国務院の環境局と科学技術委員会が中心となって環境問題に取り組んでいるが、近い将来、多くの部局が環境保全プログラムを持ち、かなり行政的に混乱する、ということが大いにあり得る。それに加うるに、中央と地方のデマケの曖昧さを考えると、中国の環境保全政策の全体像の把握がかなり難しくなることを念頭に置く必要があるように思える。
中国の環境問題は「北は大気・南は水」と表現される。環境保全局は、2010年までのグリーン・プロジェクトというコンセプトで立法、行政、プロジェクト・マネージメント能力、人材育成などの面に力点を置いている。それに対して、科学技術委員会は、1992年のリオ環境サミットで合意されたアジェンダ21の中国版を作り、総合的アプローチをとっている。その二者間の政策調整はあまり出てきていないように見受られけた。
問題の関心は、いわゆるブラウン・イシュー(公害)が中心であり、グリーン・イシュー(生物多様性、森林等)に対する関心は、あるにはあるが、極めて限られているようである。ブルー・イシュー(湖沼・海洋)は、湖と河川に関してはかなり関心が高まりつつあるが、沿岸については未だ関心が低いようである。レッド・イシュー(貧困と環境のリンケージ)は非常に大きな問題であるはずであるが、政策当局の関心は極めて低いようである。
日中友好環境保全センター
初期のスタッフは約240名で、将来的には400名体制を予定している。部門として次の六つを持つ。
―公害防止技術部
―環境技術交流及び公共教育部
―環境戦略政策研究部
―環境情報部
―環境観測技術部
―開放型実験室
このうちで政策研究についてのみ、今後予定されているプロ技の第二フェーズの具体化ができていない。この部門は、今まであった環境戦略センターが統合され、36名で始め、55名体制にもってゆく予定である。実質上環境保全局の頭脳機能が想定されているので、この部局の共同作業の具体化が準備出来ていないのは極めて残念である。他の五つの分野は第一フェーズを通して人材も徐々に育ちつつあるようである。
環境保全局の熱の入れようからして、本センターは今後、中国の環境保全政策の中で重要な役割を担ってゆくであろう。国際環境協力の重要な柱として育っていく可能性が大いにある。しかし、そのためには主として次の二点が今後の課題である。一つは本センターの運営についての日中協議メカニズムをしっかりしたものにすることであり、他の1つは政策研究についての協力を工夫することである。
協議メカニズムは本センターの価値を左右する最も重要な要素であろう。環境センターの運営は、他の分野に比べて柔軟さが要求される。環境問題そのものと政策対応が、他の分野より早く変化する傾向があるためである。日・中双方とも本センターの在り方にっき広い視野のもとに協議し、相互によく了解しあうことが極めて重要である。そこには、できるだけ近い将来に世銀の地方測定用コンピューターと接続するための協議も含める必要がある。一方で、中国の本センターに対する当事者意識をさらに高め、他方で、日本も常に状況をよく把握し、必要に応じてさらに適切な協力を行う、という体制作りが急務である。
政策研究については、世界的な環境政策の状況、中国の政策課題、日本の経験の三つの側面を扱うのがよいであろう。そのそれぞれについてのプロジェクト化を、日・中2~3名ずつのタスク・フォースでつめるメカニズムを作るのが現実的な手順であろう。日本の開発協力のソフト化の試金石として位置付けるべきであろう。北京市下水道処理場
1993年末に開場されたこの施設は、中国で一番規模の大きいものである。この施設により、北泉市の汚水処理は10%から20%に高まった(東京の場合90%)。処理済みの水は農業用水、発電用水及び川へ流す三つの目的に使う。現在、汚水は52%が生活排水、48%が工業排水であるが、将来的には生活排水の比率がさらに高まるものと予測されている。本処理場は人材育成機能も備えている。操作要員の育成は本処理場そのもので行う。しかし中・高級人材の育成には、できるだけ海外視察を含めるようにしている。東京都がカウンターパートとして重要な役割を果たしている模様である。
本処理場は、とりあえず大きな問題もなく機能しているようである。一応は近隣の貧困コミュニティーの一部に対する雇用機会も提供している。しかし、ダム建設等の場合のように、このように広大な敷地を必要とするプロジェクトの場合、他の場所へ移らざるを得なくなった人達が反感を持ち出すのは、対価を使い果たした後、すなわち、だいたい10年ほど経ってからである。そのことを念頭に置いた運営をすべきことを、日本側は何らかの形で通知しておいた方が良いであろう。
III.総合評価
1 以上の状況を今後の国際環境協力政策との関係で考えてみると、いくつかの特徴が明確になってくる。まず第一は、環境行政の内容および手法が変化し、さらに、政治全体の中での環境問題の位置付けが高まるにつれて、環境管理センターの機能も変化しっっあることが挙げられる。
第二に、環境技術の移転は途上国の経済成長の環境に与える負荷との関係で重要な機能を果たす。日本は、主として今のところ測定技術という側面に関してであるが、技術移転に前向きに取り組んでいる。かつ、その実績はかなり評価し得るものである。他のドナーと比較して、この点の日本の貢献は顕著である。今後は、この努力を民間企業も含めて、産業における環境技術の移転ということが大きな課題である。民間を通じて、これら諸国における環境産業の育成ということも視野に入ってくることが望まれる。
第三は、途上国の環境は先進諸国と異なる点が多々あり、その異なる環境を共同して研究することが部分的に行われているが、この点を強化することが今後の課題である。公害分野、森林関連、また海洋・河川・湖沼すべての分野について言えることである。これは、やがてエコ・プロスペクティング(生物多様性の経済的利用)への道をつけることにもなり得るであろう。
第四は、日本が重点を置いてきている人材育成は、環境保全分野でも、日本特有の貢献をしてきていることが分かったことである。今後は、人材育成に大学レベル、初級実務者、中級実務者、上級レベルを大系的に考える必要があるであろう。
これらの四要素、すなわち変化する目的に対する柔軟な対応、技術移転、研究協力、及び人材育成を総合的に組み立ててゆくことが、日本特有の環境協力アプローチ確立への途であると思われる。
2 その一つの具体的な型はネットワーク型環境管理センターである。すなわち、今あるタイ、インドネシア、中国(さらに可能性としてマレーシア)の環境管理センターを核として、技術移転機能を拡大し、研究協力を強化し、人材育成を大系化し、なおかっ、これらのセンター間の協力、第三国研修機関化を図ることである。パートナー諸国と緊密に協議しつつ、まず東アジアにこのネットワークを構築することが、この地域の経済のダイナミズムを考えると、地球社会全体に大きな貢献をすることになるであろう。
3 日本型国際環境協力の構築、それを通じての世界における日本のリーダーシップの発揮には、戦略的アプローチが必要になる。特に、この分野では臨機応変な対応が必要であるだけに、軸足をきっちりと定めておくことが重要である。まず、公害に対しては、東アジアの環境管理センターのネットワークを基盤として、そのグローバル展開を図ることである。東アジア・ネットワークを強化しつつ、南アジア、中近東、アフリカ、ラ米に一カ所ずつ環境管理センターを設立し、それらを東アジア・ネットワークに結びつけることである。そのための中期計画が必要になるであろう。
IV アジア環境保全協力に関する政策提言
1992年にアジェンダ21がリオ・サミットで採択された後、各国、各機関のアジェンダ21が作られつつある。自治体レベルでのアジェンダ21も増えつつある。しかし、ドナーとしてのアジェンダ21は、バイにしろ、マルチにしろできていない。個々のプロジェクトが進行しつつある状況である。
日本は1989年のアルシュ・サミット及び1992年のリオ・サミットにおいて、それぞれ3年及び5年の援助ターゲットを公表した。今年度いっぱいでその8年間も終了する。また、さらに1992年に策定されたODA大綱では、途上国における環境と開発の両立が一つの主要な原則として採用された。翌1993年に成立した環境基本法では、三つの理念の一つに国際的協調による地球環境保全の積極的推進をあげている。
このような背景のもとに今後のアジア環境保全協力が推進されていくことになる。まず第一には、1998年以後は金額のみのターゲットということでは説得力に欠ける、ということである。第二には、地球全体を視野に入れたプログラムを考える以外にはない、ということであり、第三には、しかし、実質上アジアを中心とした内容になることが自然であろう、ということである。このような前提のもとに、1998年以後の環境協力プログラム作製を、タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、中国の現場を念頭に入れつつ考えると、プロセス及び内容にっき、次のような案も考えられる。
1 プロセス
1) まず、日本の環境協力全体のレビューを行う必要がある。環境プロジェクトのみならず、環境配慮の面をも含め、少なくとも1980年代の中頃から10年程は、対象にするべきであろう。この作業では日本の得手・不得手、さらには目玉になり得る分野を特定することを目指す。また、この作業を通じて、日本の環境専門家のディレクトリー作りの手掛かりも得ることができるであろう。
2) バイ及びマルチの、やはり10年程の実績を調査する必要がある。ここには主要な国際環境NGOを含める必要があろう。またCSDのレビューを行なうことも意味がある。時間的制約からして、かなり荒い作業でも仕方ないものと思われる。しかし、主要ドナーの得手・不得手及び環境協力分野全体で極端に努力不足の分野・地域があるかどうか等をはっきりさせる必要がある。
3) 上記1)及び2)を踏まえ、日本の環境協力中期計画にとりかかる。一方で、通常の日本人有識者(NGO及び財団も含め)からなる委員会を作ると同時に、その委員会が主催する形で、途上国の有識者(政府代表ではない)10数名を招待し、日本プログラムに意見を言ってもらうワークショップを2~3回開く。そこにWRI、IIED、World Watch Instituteのような環境シンクタンク、WWF、CI、地球評議会のようなNGO、世銀、UNDP、アジア開銀、CSD事務局、UNEP等の国際機関を適宜入れるのも一案であろう。日本の役割はできるだけ聞き役に徹することである。
4) この3)の作業では、日本プログラムそのものは、当然日本自身が決めることをはっきりさせておく。最終的なプログラムは次の四つの要素を盛り込むつもりであることをはっきりさせることが必要である。
―明確なミッション(もしくはコンセプト)
―主要な目玉
―しかし、ある程度柔軟な幅をもったものにする
―今後も途上国、国際機関、NGOの意見を聞く機会をつくる
5) 中期環境協力は、当然のことながら、まず日本のODAプログラムの一つのガイドラインとしての機能を果たす。その上に、次のような国際的役割を考えてよいであろう。
―1997年6月のリオ・サミット5周年国連特別総会にジャパン・イニシアティブとして、ドナー・アジェンダ21のモデルとして提出する。
同時に、他のバイのドナー国にもドナー・アジェンダ21作製を呼びかけるために、DACで1997~1998年の中心的なセクター作業として環境分野を取り上げさせる。そのためには1996年9月頃から根回しを始める必要があろう。
―1997年のG7サミットは環境保全に焦点が当てられる可能性が高いので、そこでジャパン・イニシアティブをさらにプレイ・アップするのもよいであろう。
2 内容
全体として、途上国を中心とした外部の有識者の意見を聞きつつ内容を詰める、という作業になる。しかし、その作業を進めるためにも、一応の案は持っておく方がよいであろう。その案のうち、どこをどの程度最初の段階で提出するかは、準備プロセスで判断すればよい。
1) ミッションもしくは中心的コンセプトとしては、地球的規模での循環型社会の追及、ということも一案であろう。日本のODAの役割はそのための触媒として位置付ける。
2) 地理的にはアジアに重点を置き、分野としてはブラウン・イシューを中心に据える、という位置付けが考えられる。
3) ブラウン・イシューの中心を環境センター・アプローチとする。
4) グリーン及びブルー・イシューについても重視し、前者はホット・スポット・アプローチ、後者は珊瑚礁、マングローブ、石油運搬関連を中心とする。
5) 貧困と環境破壊とのリンケージ、いわゆるレッド・イシューに関しては、農村のエネルギー対策(カマド等)を中心にすることも一案であろう。1997年のUNDPの「人間開発報告書」のテーマは貧困になる。それと環境とのリンケージは1997年の一つの重要課題になるであろう。
これらの内容については、日本及び世界の環境協力のレビュー及びワークショップで多くの案が出てくるものと思われる。それをスクリーニングし、全体的な構想に組み立てる上で、日本委員会が中心的な役割を果たすことが期待される。その際、フロン、気候変動、生物多様性をはじめ、日本が国際条約上負っている諸義務を念頭に置くのみならず、継続中のプログラムに対する配慮をすることは当然である。さらに、できれば5カ年計画なら、その5カ年に達成すべき目標(ものによっては数字を含め)を明確にすることが重要である。


