第四章 有識者による評価
1. インドネシアにおける経済協力評価
上智大学文学部社会学科教授目黒依子
(現地調査期間:1995年8月24日~31日)
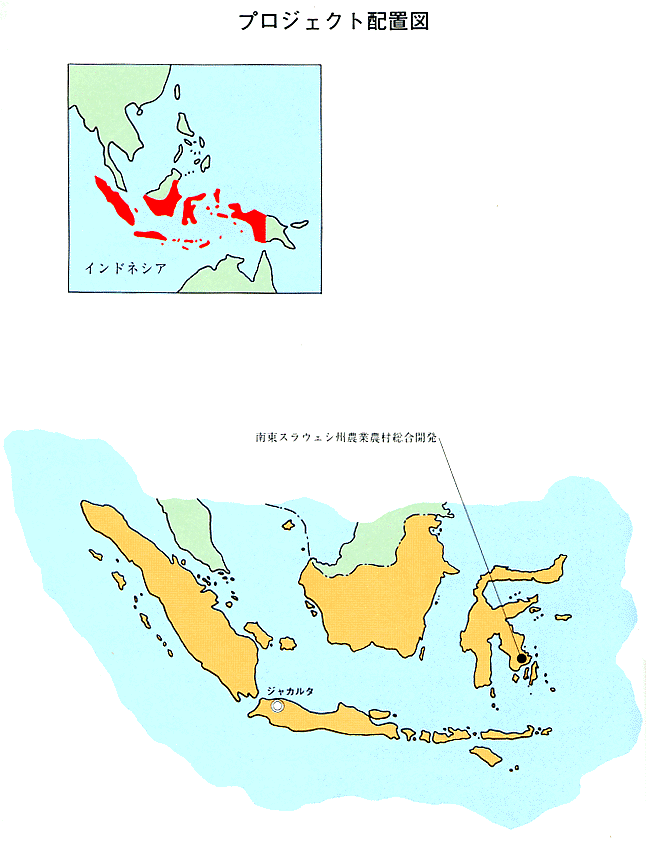
評価対象プロジェクトの概要
| 案件名 | 協力形態 | 協力期間 | 案件概要 |
|
南東スラウェシ州農業農村総合開発計画 |
プロジェクト方式技術協力 | 1991年3月~1997年2月 | 農業生産、社会的条件等の異なる数ヵ村を対象に、農民参加の下、それぞれの農村に適した農業計画策定から農業・農村基盤整備、農業機械導入、栽培・営農技術の演示・訓練に至る総合的農業・農村開発事業を実施。 |
1 調査の目的と方法
本調査の目的は、開発援助におけるその重要性が強調されつつある参加型総合地域開発のアプローチに基づくプロジェクトをWIDの観点から評価することにある。1991年2月、我が国初のWIDに関する分野別援助研究会による「開発と女性へのアプローチが提言されたが(注)、本調査の対象案件の形成はそれに先行しており、参加型の総合地域開発を目指すにもかかわらずWIDの視点は統合されていなかった。プロジェグトの本来の目的がWIDでないにもかかわらず本案件を評価対象とする理由は、1)それが地域総合開発を目的とし、2)住民参加型アプローチによるといういわば住民のエンパワーメントを前提とする方式をとるプロジェクトであることから、最大の成果をあげるためにはWIDの視点が欠かせないと思われるからである。従って、評価に当たっては、案件形成時の目的に含まれていない成果の達成度の議論ではなく、地域生活における男女の関係やプロジェクトによる影響などを検討することを通して住民=男性ではなく住民=男女であるということ、現行の地域開発の方向が将来どのような社会構造をもたらし、それが女性及び男性のエンパワーメントに繋がるものか、を考察し、今後の縦断的開発アプローチによるプロジェクト計画に資するような材料を提供することにある。
(注)研究会報告書では、地域社会ごとの女性の特性に配慮したアプローチ、地域総合開発の視点に立つ横断的アプローチ、WIDの視点を開発の全てのプロセスに反映させる縦断的アプローチがWIDアプローチとして提言されている。
本調査は、プロジェクト関連機関の責任者やJICA専門家及び8カ村中4カ村の住民女性たちのヒアリングを中心として行われた。また、住民女性の自宅を訪問し、生活環境や日常の労働・活動内容について確認した。
2 プロジェクト実施地域の生活構造
インドネシア25年開発計画における東部開発のための住民参加型プロジェクトとして、8ヵ村がプロジェクトサイトとして選ばれた。その選択基準として、アランアラン(雑草)の撲滅が必要、波及効果に繋がる展示効果がある、良いリーダーが存在する、貧困である、平地である、他の公共事業の対象となっていない、政策移民の村でないなどの条件があり、それに該当する村々なのである。まず、調査対象4カ村の人口構造は、以下のようになっている(JICA専門家提供のデータを再構成;平均世帯員数及び母親一人当たりの平均子供数は筆者算出)。
| 村名 | 人口 | 平均世帯員数 | 平均子供数 | 主民族 | ムスリム(%) |
| ラノメト | 1,856 | 5.35 | 3.65 | トラキ、ジャヴァ | 97 |
| パランガ | 1,683 | 4.91 | 1.83 | トラキ、ブギ | 99 |
| キアエア | 1,283 | 4.55 | 3.03 | ブギ、トラキ | 100 |
| サブラコア | 4,048 | 4.96 | - | トラキ、ジャヴァ、パリー | - |
人口の性比はサブラコアを除いてはいずれも男性の方が女性を上回る。しかし親の性比はパランガでは同数であるが、ラノメト、キアエアでは女性の数が上回っている。世帯内の母親数が父親数より多い世帯が前者で17戸、後者で20戸ある。またパランガとキアエアでは「その他」の世帯員がそれぞれ390人と20人同居している。
トラキ族は地付きの焼き畑農民であるのに対し、他は水田耕作を主とする民族である。各村の民族構成はラノメト、パランガ、キアエアではトラキとその他の割合が約半々であるのに対し、サブラコアではトラキが4分の3を占めている。本プロジェクトのねらいの中心が雑草荒地・焼き畑を改良し稲作湿田の開発にあるならば、農法と村落構造が密接に関連していることから、農業開発と農村開発を統合的に進めるに当たっては、技術移転の方法についてはもちろん営農観や生活観などの価値観を含む村落構造変革への取り組みが必要となる。
村の権力構造は、行政村としてのトップは村長であり、男性を中心とする世帯主たちとの「合意」によって村単位での決定が行われているようである。村長には、選挙により選出される者と知事の任命による者がおり、後者に関しては住民の意向を知事にアピールすることも可能である。ちなみにキアエア村の村長は女性である。中央政府を頂点とする官僚制度が徹底しており、住民の合意を得るといっても、地域・村レベルの有力者が中心となった住民参加になる可能性が強いように見受けられる。本プロジェクトの導入に関しても、住民側の代表は男性世帯主であり、女性たちは実施の段階で初めて知る、という経験をしている。後述するように、調査対象となった村々の地域特性に差異がみられ、女性たちの積極性が男性中心の仕組みの運用を柔軟にする可能性はあるかもしれない。
3 参加型農業・農村総合開発の方法
(本プロジェクトはWID配慮プロジェクトとしてスタートしたものではないので、住民組織強化及びWIDの観点から重要とみられる側面を中心に)
JICA専門家とそのカウンターパートは、各サイトの住民側に計画案を説明し、意見交換を行って、住民の3分の2の同意を得てスタートした。道路整備については、個人所有地の提供における不平等が生じるが、その調整は住民にまかせた。整地調査にも住民が参加し、小川を利用した農業用水路作りは、専門家の指導の下に住民たちが直接参加するという方式をとった。住民による普請にはスワダヤという受益者だけが行うもの(水管理や土管設置など)とゴトンロヨンという村人全員参加のものがあるが、用水路作りでは作業完了後に参加者に賃金が支払われ、しかも、賃金の25%から35%をストック・ファンドとしてプールするという方式がとられた。各村5カ所の井戸作りについても、専門家指導一住民実施の方法をとったが、その場所の選定については男性中心の住民側にまかされ、実際に水仕事や水くみを役割として担う女性の意見が聞かれなかった村もあった。また、精米センターの設置に関しては、精米機の導入を機に専任のオペレーターが一括して精米作業を行うことになり、女性たちは長時間のマニュアル精米作業から解放されるという成果をあげた。しかし、その設置場所の選定が住民サイドにまかされたとはいえ、精米センターに米を運ぶ役割を担う住民の意見が聞かれることなく決定されたということで、ここにも、住民参加、住民のニーズを重視という際のその「住民」が誰であるかという問題が見られ、既存の村落組織を強化することの問題が例示されているといえる。
指導の方法は、普及員が各村に2名配置され、プロジェクト側の提供機材の利用・運営についての調整等、彼らが援助提供側と住民とのリエゾンの役割を果たしている。例えば、各村に供与されたハンドトラクターの利用について、村民によるその利用代金をプールし新しいトラクターを購入するとか、専属オペレーターを雇い、機械の操作と故障などの管理をするといった、村民で共同管理するという彼らにとっての新しい体験を普及員が調整をしながら定着させている。また、新しい精米センターの建設により従来の手打ち精米労働から解放された(これは女性の役割)が、この精米機のオペレーターの雇用を含む共同管理も、農機具の共同管理と同様に、管理組合規定作りや、費用分担、管理することのメリットの理解、現金の管理などの側面が含まれており、彼らにとって初体験で、普及員のサポートが欠かせない。
本プロジェクトでは、持続性という観点から社会開発・村落開発を進めることが重要であるという考えに基づき、住民の意識や能力を啓発するための住民組織の強化が一つの柱となっている。上記の共同管理の定着もその一環であるが、その他に、主として青年グループと女性グループを対象とするミニ・プロジェクトが実施されてきた。女性グループ対象には家庭菜園やカシュー・ナッツ皮割りなどがあるが、青年グループ対象に行われた養鶏プロジェクトに女性たちが関心を示しているという。それは、鶏卵の孵化をすることで値段が玉子の2倍(250ルピーが500ルピーに)になり、収入創出の道が開けるからだとのことである。このような展開は、住民のニーズを引き出す方法が固定的であってはならないことを物語っており、対象者の性別や世代を超えて柔軟にアプローチすることの必要性を示唆していよう。
本プロジェクトの展開をプロセスとしてみると、例えば精米センターの完成後、その利用状況をフォローし、利用上の利点と共に問題点についても、専門家やカウンターパートと住民女性たちとのインフォーマルな意見交換があり、住民の生活向上への意識の持続性が窺える。
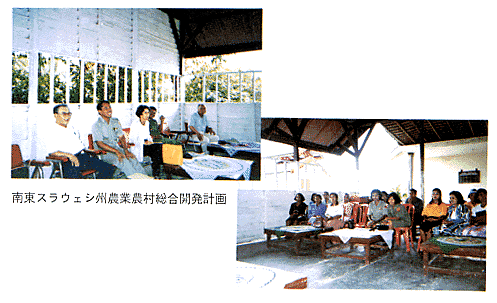
4 女性の生活とプロジェクトのインパクト
今回の現地調査では、WIDの観点からの評価ということでもあり、現地住民女性たちの生の声を聞く必要があると考えた。調査地域の地理的広がりと日程土の制約もあり、訪問する村の女性たちにグループ・インタビューをする形となった。集会所には普及員の他に村長やカウンター・パートの担当官、JICA専門家が同席し、どこまで女性たちの本音が出てくるか明らかではなかった。しかし、結果をみると、サイト間の差異がかなり明白であるところがら、少なくとも彼女たちの置かれた社会状況・生活状況の違いによる意識や態度の差が鮮明になった。インタビューはフォーマットにしたがって以下のようにまとめた。
1)ラノメト(Ranometo):都市近郊総合農業開発
クンダリ市近郊のいわゆる都市近郊農村で、JICAのプロジェクトとして最初に着手した地区で、既に事業は完了。
*生活時間:通常朝4時30分~5時頃起床し、10時00分頃就寝。夫より早く起き、遅く寝ている。一般の家事や育児等の他に農作業においても男性より働く。
*家計:家計は夫と相談もするが主として妻の責任。収入が増えたら、子供の衣服、子供の教育、食物、本人のものなどに支出。
*日常生活の楽しみ:農作物(とくにプロジェクトの家庭菜園)の成長・収穫。子供の成長一中には、大学に行き就職して欲しい(例えば公務員)というケースもある。
*現在直面する問題・困難:現金不足一例えば子供の通学に必要な交通費は、家庭菜園からの収入で賄っている;夫は現金を入れない。
*プロジェクトの効用:家庭菜園の活用による増収;精米センターでの精米による労働軽減(精米は女性の仕事で、従来は手打ち式のもので時間がかかった);井戸の増設による飲料水の確保と労働軽減(水汲み、洗濯・炊事などは女性の仕事);水田の拡張・灌漑システムの改善
*今欲しいもの:きれいな飲料水;粉ひき機;カシューナッツ・カッター(皮取り機)―カシューナッツの皮を剥いたものは高く売れるので現金収入に繋がる;ブレンダー;クレープ焼き器など。ほとんどが収入創出・増加に関連するモノで、プロジェクト関連の集会であったことによる状況効果かもしれない。
*習いたい技術:家計に加える現金収入に繋がる手工芸や菜園に関する技術・技能
*クレジット:ローンヘのアクセスがない。もしあっても、今の利息は高すぎる。もしできるなら、ローンで肥料を買い、増産を図りたい。
2) パランガ(PaIanga)及びキアエア(Kiaea):水稲稲作・エステート作物の複合開発純農村。
純農村。 プロジェクトはほぼ完了。
*生活時間:朝5時頃起床し、9時から10時頃就寝。
例: 5時起床、コーヒーの準備; 8時~12時 農作業; 12時~3時 昼食;3時~5時
農作業;10時 就寝
活動内容は、農作業の他に料理、子供の世話、KI0SKで売るケーキを作る、掃除、鶏やアヒルの世話、精米、自家消費及び販売のための家庭菜園など。この村の女性たちは時間の観念を明確にもっている。時計はどの家にもあると言う。以前に家族計画の指導が入り、時間の観念が定着した模様。
*家計:妻が管理。子供の教育のために郵便貯金をする者もいる。週、月、季節単位で個人単位のものや建築・農機具購入のための家単位のアリサンという互助会があり、重要な機能を果たしている様子。
*プロジェクトの効用:集団活動を通してアイデアを共有するようになった;農道の整備や作業の機械化により耕作地を拡大した;機械化により労働の削減をみた;ダムの建設により二期作が可能になった;以前の焼き畑式農法の時代に比べ増産・増収となった;労働量は機械化や二期作により増えたが増収に繋がるので良い;精米センターの建設により自家精米に比べ労力や時間が軽減され、その分農作業を増やせる。
*きつい労働:水汲み;野菜の水やり;穀物の乾燥
*今欲しいもの:菜園技術の訓練;クレープ作成器;ハンド・トラクター;野豚から野菜を守る棚;製粉器;電気。
*人生で大切なもの:カシュー・ナッツ・プロセサー;プロジェクトから得られる指導。集会の性格を考慮してもあまりにも即物的な発想。
3) サブラコア(Sabulakoa):農業基盤改良による水田開発
この村は最貧地の一つ。隣のバリ島からの計画移民たちに押されて、生活状況がむしろ貧困化しているという。雨期が長引いたため、ダムの建設が予定より遅れており、プロジェクトはまだこれからの段階であるが、成果が期待されている。女性を対象とした家庭菜園の研修は終了。
*生活時間:他の村と類似。活動内容は、田植え、裁縫、田の草取り、農作物の販売(市場で)など。
*互助会:他の村と同様にアリサンがあるが、そこから回ってきた金の用途はほとんどが冠婚葬祭のためという。
*今欲しいもの:ケーキ作りや裁縫の技術指導;豆腐製造器(この村では大豆の栽培をしている);精米機;ココナツ・クラッシャー;井戸;電気。井戸がないものは約1時間かかる川で水汲みや沐浴をしている。
*人生で大切なもの:食費や教育費を得るための技術;収入。この村の女性たちは他の村の女性たちに比べて無表情で精気がない。人生のイメージが具体的な「生きる」ことであり、長期的な人生設計を考える発想はみられない。他の村の女性たちがプロジェクト導入前にこのような状態であったかどうか不明であるが、この村でのプロジェクトが終了する頃に彼女たちの状態がどのように変化しているかを確認することは、プロジェクトの成果を評価する上で重要な指標となろう。
5 プロジェクト・サイクルと女性の参加
本プロジェクトは、農業・農村地域の開発を住民参加型のアプローチで実施することをその特徴とするものである。ここでは、その「住民」の範疇に女性がいかに含まれているかという観点から、プロジェクトの展開と成果を検討しよう。
1) 計画段階
本プロジェクトが「WID配慮案件」として計画されたものでなかったところがら、計画の段階で住民の意見を聞き、それを計画に反映させる際に、女性はその「住民」の中に組み込まれていなかったことは既に述べた。インドネシア政府の担当部局及びJICAとの交流会に出席した住民代表の中に女性がほとんど含まれていなかったのみならず、この度のインタビューで、夫たちからもプロジェクトについて説明されていない女性が多くいた。地域社会の総合開発では、経済のみならず社会的・文化的側面を含む統合的なアプローチが求められる。それが農業を中心とする計画であっても、女性も重要な農業の担い手であるという実状を認識し、計画段階から女性の意見が全体の方針決定にはいるべきである。当該地域は、焼き畑式農業が主で、その場合、男性よりも女性の果たす役割は数・量共に大きい。プロジェクトの結果として水田稲作農業に転換することで生産性を高め、住民生活の向上に繋がりつつあるが、計画段階から女性も住民として参画したならば、彼女たちが担う農業に対し、より積極的・創造的に取り組む動機付けとなったのではないだろうか。この地域の原住民はあまり労働意欲が高くないといわれる。しかし女性たちは、現状を改善する可能性を認識した時、それまで以上の労働を厭わず、積極的・意欲的になってきている。農業様式の違いによる性別役割分業の違いに留意することは、当地のイスラム的慣習への配慮以上に重要であったと思われる。
2) 実施段階
ミニ・プロジェクトや女性グループ対象の研修という形で、生活向上に役立っ活動の成果をあげている。特に収入創出事業として実際に家計に貢献している。家庭菜園や手工芸の生産の領域ではかなりの手応えがあるようであるが、販売網の確立がいずれ重要な決め手になると思われるので、地域の全体的な流通の仕組みについても、研修プログラムに組み入れていくと良いのではないだろうか。
既存の組織を強化することを主眼とする方針は、住民の内発的発展に資すると言える半面、従来の性別役割規範に基づく男性中心の社会構造を温存することにも繋がる。既に多くの重要な役割を担っている女性たちの正当な評価がされるような仕組みを作っていくような組織作りがさらに望ましい。
インフラ整備を通して、農作業の多くを担う女性たちは、水汲み、耕作、精米などにおける労働の削減や、生産性向上による増収という利益を得た。農道、水路、井戸、精米センターなどの位置(設置場所)の決定は住民側に委ねたといっても、女性たちはその決定に参加していないが、利用者は主として女性たちである。それは彼女たちが水汲みや精米などの作業の担い手となっているからである。また、水管理や農機具の共同管理、現金の管理など、プロジェクト実施地域の住民にとっての新しい経験となる指導・研修は、農業・農村社会の中心となっている女性たちにとっても必要であり、新しいノウハウの修得は、女性のエンパワーメントに資することにもなろう。
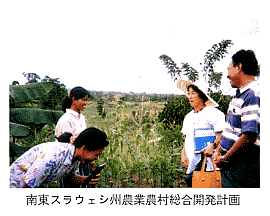
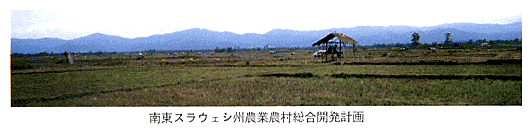
3) 成果
本プロジェクトの成果は、家庭菜園(栄養向上、家計の向上、集団菜園の場合は共同管理のノウハウ)、精米センター(労働軽減、労働時間短縮)、井戸(水の確保、労働軽減、労働時間短縮)、農業の機械化(収穫労働の軽減、労働時間短縮、その結果の生産活動増加)、カシューナッツ・カッター(ナッツの付加価値の増加による増収)など、広範囲にわたってみられる。いずれも女性の労働軽減や家計の増収に繋がる成果である。しかし、それらが与えられた計画から得られた成果であるせいか、次々と与えられることを期待する発想が強いことも、彼女たちとのインタビューから得た印象である。家庭菜園に関しては、本人のアテンドする部分が多いので、栽培の技術を身につけたいという願望が出てきている。この点では、技術移転と自助努力のマッチングがあるといえよう。
6 WID/GADの視点から見た課題
一般に農業様式と農業の担い手との関連が強いことは、多く指摘されてきたところである。主としてアフリカを中心とする焼き畑様式の場合、男性が果たす役割は限定的で、多種の農作業を女性が担っている。一方、アジアに見られる定住型の水田耕作の場合、農業は男性中心で、特に耕作機械の操作は男性の役割とされることが多い。近年では、地域を問わず、人口増加が前者から後者への変化を促進してきたとされる。アジアの焼き畑地域でも、人口増加に伴って、あるいは貧困対策として、水田耕作への変化がみられる。その際の最大の問題は、ジェンダー関係の変化である。これまでに見られた一般的な動向は、女性の生産活動における主権が奪われるというものであった。
本プロジェクトでは適正な規模・レベルのインフラ整備と営農指導が中心課題で、圃場整備・開発とそれに適応する営農指導を中心とする農業開発であるから、上の図式では男性が農業の主導権を握ることになる。課題の内容適正化と持続性確保のために主体的住民参加が不可欠だとする住民参加型開発ではあるが、男性が決定権を持つような村落構造においては、女性たちは主要な決定に参加しない重要な労働力であることは既にみた通りである。女性たちの農業における自律性は、家庭菜園という領域では顕著に認められた。このような開発が進んだ時、女性たちは家庭菜園の担い手に留められ、生産の中心=男性という枠組みが確立してしまうのだろうか。インドネシアの人口増加率そのものは低下しているが、南東スラウェシ地域にとって貧困からの脱出は最大の課題であることに変わりはない。生産量の増加に繋がる水田稲作に転換した時に、水や機械の操作や管理に女性も男性と共に携わっていくような仕組みを作ることが、ジェンダー関係の平等を視野においた貧困軽減のための地域総合開発を可能にする鍵となろう。本プロジェクトにおける技術移転の多くは、地域の男性たちにとっても新しい経験となるタイプのものであるから、既にそれまでの農業及び農村生活の重要な担い手であった女性たちが共に新しい技術を修得することは、彼らの抵抗を招くことなく新しい地域生活基盤の確立に男女住民が主体的に関わる重要な一歩となるのではなかろうか。
上記5「プロジェクト・サイクルと女性の参加」3)でまとめた女性たちにとっての成果は、主として栄養や労働の領域での女性の状況改善であるといえる。このような成果が得られたことは十分に評価されるべきである。また、このような結果のみならず、プロジェクト実施側の活動のプロセスに、対象住民への動機付けを常に考慮する方法が柔軟性をもって講じられるような姿勢が感じられる。このことが、本来WID配慮案件ではなかったにもかかわらず、一部の村々での女性たちを「元気」にしている理由ではないかと思われる。

